仢挷嵏丒曬崘
壠寁徚旓偺僐僂儂乕僩暘愅
亅暷丄媿擏丄慛嫑偍傛傃堸梡媿擕偵偮偄偰亅
愱廋戝妛柤梍嫵庼丂怷丂岹
1丂擭楊偲徚旓
丂1990擭摉帪偺傾儊儕僇恖偺僐乕僸乕徚旓偼拞崅擭憌偑懡偔乮侾恖侾擔俆侽侽倗
慜屻乯丄庒擭憌偼彮側偄乮20戙偼170倗埲壓乯丅懠曽丄僐乕儔椶偺徚旓偼庒擭憌
偑懡偔乮20戙370倗乯丄拞崅擭憌偑彮側偄乮偦傟偧傟50戙120倗丄60戙偼偝傜偵彮
側偔70倗乯乮徻偟偔偼擾柋徣偵傛傞挷嵏寢壥偺昞1嶲徠乯丅
昞侾丂傾儊儕僇恖偺擭楊奒媺暿僐乕僸乕偍傛傃僐乕儔偺徚旓検
乮抝惈侾恖侾擔摉偨傝丄1989乣91擭乯
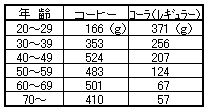 丂弌強丗USDA Continuing Survey of Food Intakes by Individuals, 1989-91
丂暷崙偱傕恖岥偺崅楊壔偑恑峴偟偰偄傞丅傕偟摨偠恖偱傕拞崅擭偵側傞偲僐乕儔
偺徚旓偑棊偪僐乕僸乕偵堏傞偲偡傟偽丄2010擭崰偵偼傾儊儕僇慡懱偲偟偰僐乕僸
乕偺徚旓偼憹偊丄懠曽僐乕儔椶偼尭彮偡傞偲梊憐偝傟傞丅
丂偩偑暿偺桳椡側尒曽傕偁傞丅American Demographics偺1994擭12寧崋偵乽偁偲
俀擭偱僋儕儞僩儞乮戝摑椞乯偼50戙傪寎偊傞偑丄斵偼憡曄傢傜偢儅僋僪僫儖僪搣
偱偁傠偆乿偲偺尒弌偟偑嵹偭偰偄傞丅庒偄崰偵僴儞僶乕僈乕偵姷傟恊偟傓偲拞崅
擭偵側偭偰傕偦偺廗暼偼帩偪墇偝傟丄僴儞僶乕僈乕揦偵捠偆偩傠偆偲偄偆偺偱偁
傞丅偙偺尒曽傪愭偺僐乕僸乕偲僐乕儔偺働乕僗偵摉偰偼傔傞偲丄1990擭摉帪20乣
30戙偺恖払偑丄2010擭崰拞崅擭偵払偟偰傕丄僐乕儔堸梡偺暼偼敳偗偢丄偐偮偰偺
拞崅擭幰偲摨偠傛偆偵傕偭傁傜僐乕僸乕傪偨偟側傓偲偄偆偙偲偼側偄偩傠偆丅偩
偲偡傞偲丄慡懱偲偟偰僐乕儔偺徚旓偼憹偊丄僐乕僸乕偺徚旓偼尭傞偩傠偆偲偄偆
寢榑偵側傞丅
丂慜幰偺尒曽偼1990擭摉帪偵娤嶡偝傟偨擭楊暿徚旓偺宆偑丄偙傟偐傜偟偽傜偔偼
曄傢傜側偄偲偡傞棫応偱偁傝丄屻幰偺尒曽偼恖惗偺偁傞帪婜乮嫲傜偔僥傿乕儞僄
僀僕儍乕偺崰乯偵宍惉偝傟偨悽戙摿桳偺堸怘偺廗姷偼丄偦偺屻偺壛楊偵偐偐傢傜
偢帩偪墇偝傟偰偄偔偲偡傞棫応偱偁傞丅
丂偟偐偟忋婰偺扨擭搙尷傝偺摑寁偐傜偼丄擭楊岠壥偑嫮偄偲傒傞傋偒偐丄悽戙岠
壥偑桪惃偱偁傞偲傒傞傋偒偐偼寛傔傜傟側偄丅
丂傢傟傢傟偼偡偱偵擔杮恖偺怘擏丒嫑夘椶偺徚旓傪擭楊暿偵悇寁偟丄摿偵嫑偺徚
旓偼拞崅擭憌偱崅偔丄巕嫙傪娷傓庒擭憌偱挊偟偔掅偄偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅乮拲
1乯夁嫀10悢擭偺婜娫偵偮偄偰擭楊暿偺徚旓偺摦偒傪挱傔傞偲丄嫑偺徚旓偼妋偐
偵壛楊偲偲傕偵憹偊傞偑丄巕嫙丒庒偄崰偵嫑傪偁傑傝怘傋側偐偭偨怴偟偄悽戙偼丄
擭傪庢偭偰拞擭憌偵嬤偯偄偰傕埲慜偺拞崅擭憌掱偼怘傋側偄傛偆偱偁偭偨丅偡側
傢偪偐側傝偺掱搙悽戙岠壥傪堷偒偢偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偺報徾傪帩偭偨丅
丂栤戣傪偝傜偵擄偟偔偡傞偺偼丄偙偺10悢擭偺婜娫偵丄慡懱揑側孹岦偲偟偰嫑偺
徚旓偑尭彮偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偙偲偱偁傞丅偡側傢偪梫場偲偟偰擭楊偲悽戙偵
壛偊偰帪戙偺塭嬁偑壛傢偭偰偄傞丅捈姶揑偵3偮偺岠壥傪幆暿丄暘棧偡傞偺偼晄
壜擻偵嬤偄丅
拲侾丗怷岹懠乮1997乯乽奺庬怘擏徚旓偲擭楊乿亀暯惉8擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏
丂丂尋媶帠嬈亁擾抺嶻帠嬈抍丄Lewis, M. A., Mori. H. and Gorman. Wm. D.,
丂乽Estimating Japanese At-Home Consumption of Meats and Seafoods by Age
丂丂Groups乿丄乽愱廋宱嵪妛榑廤乿32姫2崋側偳
丂弌強丗USDA Continuing Survey of Food Intakes by Individuals, 1989-91
丂暷崙偱傕恖岥偺崅楊壔偑恑峴偟偰偄傞丅傕偟摨偠恖偱傕拞崅擭偵側傞偲僐乕儔
偺徚旓偑棊偪僐乕僸乕偵堏傞偲偡傟偽丄2010擭崰偵偼傾儊儕僇慡懱偲偟偰僐乕僸
乕偺徚旓偼憹偊丄懠曽僐乕儔椶偼尭彮偡傞偲梊憐偝傟傞丅
丂偩偑暿偺桳椡側尒曽傕偁傞丅American Demographics偺1994擭12寧崋偵乽偁偲
俀擭偱僋儕儞僩儞乮戝摑椞乯偼50戙傪寎偊傞偑丄斵偼憡曄傢傜偢儅僋僪僫儖僪搣
偱偁傠偆乿偲偺尒弌偟偑嵹偭偰偄傞丅庒偄崰偵僴儞僶乕僈乕偵姷傟恊偟傓偲拞崅
擭偵側偭偰傕偦偺廗暼偼帩偪墇偝傟丄僴儞僶乕僈乕揦偵捠偆偩傠偆偲偄偆偺偱偁
傞丅偙偺尒曽傪愭偺僐乕僸乕偲僐乕儔偺働乕僗偵摉偰偼傔傞偲丄1990擭摉帪20乣
30戙偺恖払偑丄2010擭崰拞崅擭偵払偟偰傕丄僐乕儔堸梡偺暼偼敳偗偢丄偐偮偰偺
拞崅擭幰偲摨偠傛偆偵傕偭傁傜僐乕僸乕傪偨偟側傓偲偄偆偙偲偼側偄偩傠偆丅偩
偲偡傞偲丄慡懱偲偟偰僐乕儔偺徚旓偼憹偊丄僐乕僸乕偺徚旓偼尭傞偩傠偆偲偄偆
寢榑偵側傞丅
丂慜幰偺尒曽偼1990擭摉帪偵娤嶡偝傟偨擭楊暿徚旓偺宆偑丄偙傟偐傜偟偽傜偔偼
曄傢傜側偄偲偡傞棫応偱偁傝丄屻幰偺尒曽偼恖惗偺偁傞帪婜乮嫲傜偔僥傿乕儞僄
僀僕儍乕偺崰乯偵宍惉偝傟偨悽戙摿桳偺堸怘偺廗姷偼丄偦偺屻偺壛楊偵偐偐傢傜
偢帩偪墇偝傟偰偄偔偲偡傞棫応偱偁傞丅
丂偟偐偟忋婰偺扨擭搙尷傝偺摑寁偐傜偼丄擭楊岠壥偑嫮偄偲傒傞傋偒偐丄悽戙岠
壥偑桪惃偱偁傞偲傒傞傋偒偐偼寛傔傜傟側偄丅
丂傢傟傢傟偼偡偱偵擔杮恖偺怘擏丒嫑夘椶偺徚旓傪擭楊暿偵悇寁偟丄摿偵嫑偺徚
旓偼拞崅擭憌偱崅偔丄巕嫙傪娷傓庒擭憌偱挊偟偔掅偄偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅乮拲
1乯夁嫀10悢擭偺婜娫偵偮偄偰擭楊暿偺徚旓偺摦偒傪挱傔傞偲丄嫑偺徚旓偼妋偐
偵壛楊偲偲傕偵憹偊傞偑丄巕嫙丒庒偄崰偵嫑傪偁傑傝怘傋側偐偭偨怴偟偄悽戙偼丄
擭傪庢偭偰拞擭憌偵嬤偯偄偰傕埲慜偺拞崅擭憌掱偼怘傋側偄傛偆偱偁偭偨丅偡側
傢偪偐側傝偺掱搙悽戙岠壥傪堷偒偢偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偺報徾傪帩偭偨丅
丂栤戣傪偝傜偵擄偟偔偡傞偺偼丄偙偺10悢擭偺婜娫偵丄慡懱揑側孹岦偲偟偰嫑偺
徚旓偑尭彮偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偙偲偱偁傞丅偡側傢偪梫場偲偟偰擭楊偲悽戙偵
壛偊偰帪戙偺塭嬁偑壛傢偭偰偄傞丅捈姶揑偵3偮偺岠壥傪幆暿丄暘棧偡傞偺偼晄
壜擻偵嬤偄丅
拲侾丗怷岹懠乮1997乯乽奺庬怘擏徚旓偲擭楊乿亀暯惉8擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏
丂丂尋媶帠嬈亁擾抺嶻帠嬈抍丄Lewis, M. A., Mori. H. and Gorman. Wm. D.,
丂乽Estimating Japanese At-Home Consumption of Meats and Seafoods by Age
丂丂Groups乿丄乽愱廋宱嵪妛榑廤乿32姫2崋側偳
2丂僐僂儂乕僩暘愅偺峫偊曽
丂昞俀偼懳徾傪侾侽嵨偒偞傒偱嬫暘偟丄侾侽擭偛偲偵孞傝曉偟偨偁傞怘昳偺徚旓
挷嵏偺敳悎偱偁傞丅偙偺傛偆偵嶌傜傟偨昞傪乽僐僂儂乕僩昞乿偲屇傫偱偄傞丅尒
曽傪愢柧偟傛偆丅
昞俀丂偁傞怘昳偺擭楊奒媺暿徚旓検
丂1970丄1980偍傛傃1990擭乮壦嬻椺乯
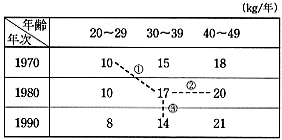 丂傑偢昞拞偺嘆偵偮偄偰丄1970擭偵20戙偺恖払偼10kg丄1980擭偵30戙偵側偭偰17
kg偵側偭偨丅挷嵏偼昁偢偟傕摨堦屄恖傪捛愓偟偰偄傞栿偱偼側偄偑丄斵傜偼1941
擭偐傜1950擭偵弌惗偟丄1950擭偵0乣9嵨婜丄1960擭偵10乣19嵨婜傪夁偟丄偙偺20
悢擭娫偺娫偵嫲傜偔摨偠傛偆側恖惗丄幮夛忋偺宱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偵懏偟偰
偄傞丅17亅10亖7kg偺憹壛偼丄1偮偵偼20戙偐傜30戙偵10嵨憹偊偨壛楊岠壥偲丄擭
戙偑1970擭偐傜1980擭偵10擭宱夁偟偨帪戙岠壥乮偺嵎乯偺2偮偐傜崌惉偝傟偰偄
傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘇偵偮偄偰丄1980擭偵30戙偼17kg丄40戙偼20kg徚旓偟偰偄傞丅偙偺3kg偺嵎偼
30戙偲40戙偺擭楊偵傛傞嵎偩偗偱偼側偄丅1980擭偵40戙偺恖払偼丄1931擭偐傜
1940擭偵弌惗偟丄椺偊偽愴拞丄愴憟捈屻偺婹夓揑惗妶側偳偵偮偄偰丄偦傟埲崀弌
惗偺悽戙偲偼堎側偭偨懱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偱偁傞丅偦偺傛偆側夁嫀偺宱尡偺
堘偄偵傛傞悽戙岠壥偺嵎偑丄弮悎偺擭楊岠壥偺嵎偵壛傢偭偰偄傞偲傒傞傋偒偱偁
傞丅偨偩偟偙偙偱傕椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘊偵偮偄偰丄摨偠30戙偺徚旓傪尒傞偲丄1980擭偐傜1990擭偵偐偗17kg偐傜14kg
偵3kg尭彮偟偰偄傞丅偙傟偼1980擭偐傜1990擭偺10擭娫偵強摼傗壙奿偑曄壔偟偨
側偳偺帪戙偺曄壔偵傛傞傕偺偱偁傞偺偼尵偆傑偱傕側偄偑丄偦傟偩偗偱偼側偄丅
1990擭偵30戙偺恖偨偪偼1951擭偐傜1960擭偵弌惗偟丄僥傿乕儞丒僄僀僕儍乕偺帪
戙偼崅搙惉挿婜偺恀偭捈拞偱丄偦偺慜偺悽戙偲偼壙抣娤側傝廗姷宍惉偵偍偄偰堎
側偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丅廬偭偰3kg偺嵎偼扨偵擭帪偺嵎偩偗偱偼側偔丄偦偆偟
偨悽戙岠壥偺嵎偵傛傞偲偙傠偑彮側偔側偄偲傕峫偊傜傟傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼
暘偐傜側偄丅
丂偝偰昞2偺傛偆側擭楊暿徚旓偺僐僂儂乕僩昞偑丄擭楊嬫暘偱傕墶偵挿偔丄挷嵏
擭師偵娭偟偰傕廲偵傕偭偲挿偔偲傟傟偽丄忋婰偺嘆丄嘇丄嘊偺愢柧偵偍偄偰傕丄
廬棃偺擭楊丄悽戙偍傛傃擭師側偄偟帪戙偺塭嬁傪丄偦傟偧傟検揑偵暘棧偟偲傜偊
傞偙偲偑梕堈偵側傞偲婜懸偝傟傞丅
丂偨偩偟偙偺暘棧偺栤戣偼丄摑寁妛偺悽奅偱偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偍偗傞乽幆暿
栤戣乿偲偟偰媍榑偼巆偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅乮拲2乯偩偑挊幰偨偪偼丄摑寁悢
棟尋媶強偺拞懞棽嫵庼偺奐敪偝傟偨乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖乿偺慜採忦審
傪惀偲偟丄傑偩姰慡偐傜偼墦偄偑堦墳PC梡偵嶌傝忋偘偨僾儘僌儔儉偵傛偭偰丄擭
楊丄悽戙丄帪戙偺3岠壥傪暘棧丄悇寁偟偮偮偁傞丅擾抺嶻嬈怳嫽帠嬈抍偺埾戸偵
傛傝幚巤偟偨暯惉10擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏尋媶帠嬈傪尦偵丄偦偺屻偝傜偵暘愅
傪恑傔偰偄傞丅
丂師愡埲壓偱偄偔偮偐偺抺嶻暔偲擔杮恖偺怘惗妶偺婎杮偱偁傞暷偍傛傃嫑偵偮偄
偰丄暘愅寢壥偺堦晹傪徯夘偟偨偄丅
拲2丗Mason. W. and S. Fienberg, Editars乮1985乯乽Cohort Analysis in Social
丂丂Research : Beyond the Identification Problem乿丄Springer-Verlag丄New York
丂丂側偳嶲徠
丂傑偢昞拞偺嘆偵偮偄偰丄1970擭偵20戙偺恖払偼10kg丄1980擭偵30戙偵側偭偰17
kg偵側偭偨丅挷嵏偼昁偢偟傕摨堦屄恖傪捛愓偟偰偄傞栿偱偼側偄偑丄斵傜偼1941
擭偐傜1950擭偵弌惗偟丄1950擭偵0乣9嵨婜丄1960擭偵10乣19嵨婜傪夁偟丄偙偺20
悢擭娫偺娫偵嫲傜偔摨偠傛偆側恖惗丄幮夛忋偺宱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偵懏偟偰
偄傞丅17亅10亖7kg偺憹壛偼丄1偮偵偼20戙偐傜30戙偵10嵨憹偊偨壛楊岠壥偲丄擭
戙偑1970擭偐傜1980擭偵10擭宱夁偟偨帪戙岠壥乮偺嵎乯偺2偮偐傜崌惉偝傟偰偄
傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘇偵偮偄偰丄1980擭偵30戙偼17kg丄40戙偼20kg徚旓偟偰偄傞丅偙偺3kg偺嵎偼
30戙偲40戙偺擭楊偵傛傞嵎偩偗偱偼側偄丅1980擭偵40戙偺恖払偼丄1931擭偐傜
1940擭偵弌惗偟丄椺偊偽愴拞丄愴憟捈屻偺婹夓揑惗妶側偳偵偮偄偰丄偦傟埲崀弌
惗偺悽戙偲偼堎側偭偨懱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偱偁傞丅偦偺傛偆側夁嫀偺宱尡偺
堘偄偵傛傞悽戙岠壥偺嵎偑丄弮悎偺擭楊岠壥偺嵎偵壛傢偭偰偄傞偲傒傞傋偒偱偁
傞丅偨偩偟偙偙偱傕椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘊偵偮偄偰丄摨偠30戙偺徚旓傪尒傞偲丄1980擭偐傜1990擭偵偐偗17kg偐傜14kg
偵3kg尭彮偟偰偄傞丅偙傟偼1980擭偐傜1990擭偺10擭娫偵強摼傗壙奿偑曄壔偟偨
側偳偺帪戙偺曄壔偵傛傞傕偺偱偁傞偺偼尵偆傑偱傕側偄偑丄偦傟偩偗偱偼側偄丅
1990擭偵30戙偺恖偨偪偼1951擭偐傜1960擭偵弌惗偟丄僥傿乕儞丒僄僀僕儍乕偺帪
戙偼崅搙惉挿婜偺恀偭捈拞偱丄偦偺慜偺悽戙偲偼壙抣娤側傝廗姷宍惉偵偍偄偰堎
側偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丅廬偭偰3kg偺嵎偼扨偵擭帪偺嵎偩偗偱偼側偔丄偦偆偟
偨悽戙岠壥偺嵎偵傛傞偲偙傠偑彮側偔側偄偲傕峫偊傜傟傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼
暘偐傜側偄丅
丂偝偰昞2偺傛偆側擭楊暿徚旓偺僐僂儂乕僩昞偑丄擭楊嬫暘偱傕墶偵挿偔丄挷嵏
擭師偵娭偟偰傕廲偵傕偭偲挿偔偲傟傟偽丄忋婰偺嘆丄嘇丄嘊偺愢柧偵偍偄偰傕丄
廬棃偺擭楊丄悽戙偍傛傃擭師側偄偟帪戙偺塭嬁傪丄偦傟偧傟検揑偵暘棧偟偲傜偊
傞偙偲偑梕堈偵側傞偲婜懸偝傟傞丅
丂偨偩偟偙偺暘棧偺栤戣偼丄摑寁妛偺悽奅偱偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偍偗傞乽幆暿
栤戣乿偲偟偰媍榑偼巆偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅乮拲2乯偩偑挊幰偨偪偼丄摑寁悢
棟尋媶強偺拞懞棽嫵庼偺奐敪偝傟偨乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖乿偺慜採忦審
傪惀偲偟丄傑偩姰慡偐傜偼墦偄偑堦墳PC梡偵嶌傝忋偘偨僾儘僌儔儉偵傛偭偰丄擭
楊丄悽戙丄帪戙偺3岠壥傪暘棧丄悇寁偟偮偮偁傞丅擾抺嶻嬈怳嫽帠嬈抍偺埾戸偵
傛傝幚巤偟偨暯惉10擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏尋媶帠嬈傪尦偵丄偦偺屻偝傜偵暘愅
傪恑傔偰偄傞丅
丂師愡埲壓偱偄偔偮偐偺抺嶻暔偲擔杮恖偺怘惗妶偺婎杮偱偁傞暷偍傛傃嫑偵偮偄
偰丄暘愅寢壥偺堦晹傪徯夘偟偨偄丅
拲2丗Mason. W. and S. Fienberg, Editars乮1985乯乽Cohort Analysis in Social
丂丂Research : Beyond the Identification Problem乿丄Springer-Verlag丄New York
丂丂側偳嶲徠
3丂僐僂儂乕僩暘愅寢壥偺夝庍亅暷偵椺傪偲偭偰
丂昞俁偍傛傃昞俆乣俈偼丄憤柋挕摑寁嬊偑栺8,000屗偺悽懷乮扨恎幰悽懷傪彍偔乯
偵偮偄偰幚巤偟偰偄傞乽壠寁挷嵏乿偺悽懷庡擭楊奒媺暿偺僨乕僞偐傜丄悽懷堳偺
擭楊峔惉偺峴楍傪慻傒擖傟偨楢棫曽掱幃傪夝偄偰悇寁偝傟偨悽懷堳屄乆偺擭楊暿
徚旓偺悇堏傪帵偟偰偄傞丅0乣4嵨帣偍傛傃5乣9嵨帣偵偮偄偰傕悇寁偟偰偄傞偑丄
摑寁揑偵昁偢偟傕埨掕偟偨寢壥偑摼傜傟偰偄側偄偺偱丄昞7偺堸梡媿擕傪彍偄偰
嵹偣偰偄側偄丅
丂暷乮偆傞偪暷乯偺壠寁徚旓偼1979擭偺1恖摉偨傝45.16kg偐傜1997擭偺30.26kg傊
14.9kg丄33.0亾寖尭偟偨丅傢傟傢傟偺悇寁乮昞3乯偵傛傞偲丄1980擭慜屻偵偼10戙
偺枹惉擭憌偲20戙偺庒擭憌偼1恖摉偨傝40kg慜屻丄40戙埲忋偼60kg嫮偱偁偭偨丅
偦偺屻偳偺擭楊奒媺傕徚旓偼尭彮偟偰偄傞偑丄拞崅擭憌偼20亾慜屻偺尭彮偱偁傞
偺偵斾傋丄庒擭憌偱偼敿尭丄10戙偺枹惉擭憌偵偄偨偭偰偼60悢亾傕尭彮偟偰偄傞
偺偑尒偰偲傟傞丅
昞俁丂暷偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
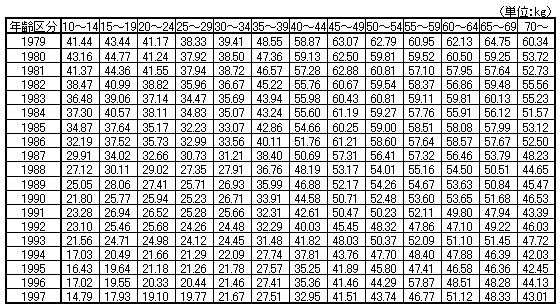 丂偙偺傛偆側曄壔傪擭楊丒悽戙偍傛傃帪戙偺3梫場偵暘偗偰暘愅偡傟偽偳偆側傞
偱偁傠偆偐丅SAS尵岅傪梡偄偨拞懞偺儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖偵傛傞寁應寢
壥偼丄昞4偺傛偆側宍偱嶼弌偝傟傞丅
昞係丂暷偺僐僂儂乕僩暘愅寢壥偺椺
丂偙偺傛偆側曄壔傪擭楊丒悽戙偍傛傃帪戙偺3梫場偵暘偗偰暘愅偡傟偽偳偆側傞
偱偁傠偆偐丅SAS尵岅傪梡偄偨拞懞偺儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖偵傛傞寁應寢
壥偼丄昞4偺傛偆側宍偱嶼弌偝傟傞丅
昞係丂暷偺僐僂儂乕僩暘愅寢壥偺椺
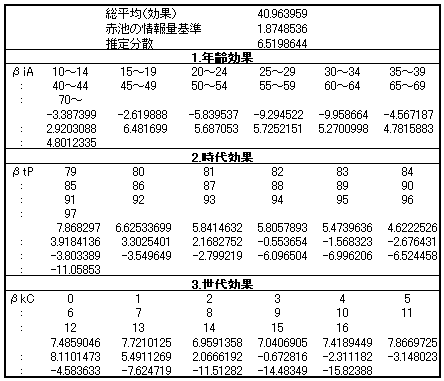 丂偁傞擭師乮 t 擭乯擭偵偍偗傞偁傞擭楊奒媺乮 i 奒媺乯偺徚旓乮兪 i t 乯偼丄19
擭亊13奒媺亖247偺僙儖偵嫟捠偺兝乮憤暯嬒乮岠壥乯乯傪儀乕僗偵丄嫹媊偺擭楊
i 奒媺偵摿桳偺擭楊岠壥丆兝i A 偲丄挷嵏帪 i 擭偵嫟捠偺帪戙岠壥丆兝t P 偑壛傢
傝丄偝傜偵傕偆1崁丄偦傟偧傟偺僙儖乮 t 擭師偵 i 擭楊奒媺偺廤抍乯偑丄偄偮弌
惗偟丄惉恖婜偵払偡傞傑偱偵偦傟偧傟堎側偭偨宱尡傪嫟桳偟攟傢傟偨偱偁傠偆摿
桳偺悽戙岠壥丆兝k C 偑壛傢傞丅偡側傢偪丄
丂兪 i t亖兝亄兝i A 亄兝t P 亄兝k C 亄岆嵎崁乧乮1乯
乮1乯幃偺傛偆偵偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞偲憐掕偡傞丅尰幚偵嬤偯偔偨傔偵偼傕偭
偲暋嶨側儌僨儖傪梡堄偡傋偒偱偁傠偆偑丄寁嶼偼擄偟偔側傝丄岆嵎傕奼戝偡傞嫲
傟偑偁傞丅
丂悽戙傪帵偡斣崋0偐傜16偼曋媂揑側傕偺偱丄0偑挷嵏婜娫偺巒傔偵70嵨埲忋偩偭
偨恖乆丄偡側傢偪1909擭埲慜弌惗偺堦斣屆偄悽戙丄媡偵16偼挷嵏偺嵟嬤擭師偵10
乣14嵨偱偁偭偨恖乆丄偡側傢偪1985乣89擭偵弌惗偟偨悽戙傪帵偟偰偄傞丅昞4偺
悇寁抣傪巊偭偰嬶懱揑側寁嶼傪帋傒偰傒傛偆丅
寁嶼嘆
丂1984擭偵55乣59嵨偩偭偨恖乆偼1925乣29擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋4偵摉偨傞丅偙
偺廤抍偺棟榑忋偺徚旓偼乮1乯幃偐傜丄
丂兝亄兝A55亅59亄兝P'84亄兝C4 亖40.96亄5.73亄4.62亄7.42亖58.73kg偲悇寁偝傟
傞丅偪側傒偵昞3偺奩摉僙儖偺抣偼57.76kg偱偁傞丅
寁嶼嘇
丂1994擭偵25乣29嵨偩偭偨恖乆偼1965乣69擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋12偱偁傞丅摨條
偵乮1乯幃偐傜偙偺廤抍偺棟榑抣偼丄
丂兝亄兝A25亅29亄兝P'94亄兝C12 亖40.96亅9.29亅6.10亅4.58亖20.99kg丅偙傟偵
懳墳偡傞昞3偺抣偼丄21.29kg偱偁傞丅
丂昞係偺暷偵偮偄偰偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥傪娙扨側恾偵偡傞偲恾1偺乮俙乯乣
乮俠乯偺傛偆偵側傞丅乮俙乯偑擭楊岠壥兝i A 丄乮俛乯偑悽戙岠壥兝k C 丄乮俠乯
偑擭師側偄偟帪戙岠壥兝t P 傪偦傟偧傟帵偟偰偄傞丅偄偢傟偺岠壥傕僛儘偺慄傪
拞怱偵嵍塃偵偽傜偮偒丄廤寁偡傞偲嵎偟堷偒僛儘偵側傞傛偆偵側偭偰偄傞丅乮儼
兝i A 亖0丄儼兝k C 亖0丄儼兝t P 亖0乯丅
仦恾侾丗暷偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖40.96kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢憤暯嬒乮岠壥乯偑40.96kg偱偁傞丅
丂乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯偼丄30戙偺屻敿40戙偺慜敿傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘
偐傟傞丅嫹媊偺擭楊岠壥偲偟偰40戙埲忋偼憤暯嬒40.96kg偵亄5.0kg慜屻偑壛傢傞丅
偦傟傛傝庒偄擭楊憌偱偼媡偵仯5.0kg偑壛傢傞丅偡側傢偪慜幰偼46kg慜屻丄屻幰偼
36kg慜屻偵側傝丄拞崅偲庒擭偺椉奒憌娫偱10kg慜屻偺嵎偑奐偔丅摿偵20戙屻敿偲
30戙慜敿偼仯9kg嫮偺擭楊岠壥傪帵偟乮40.96亅9佮32kg乯丄偝傜偵暷傪怘傋側偄擭
楊奒憌偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅偨偩偟偙傟傜偺奒憌偑暷徚旓偺憤検偑偦傟傎偳掅偄
偐偳偆偐偼暘偐傜側偄丅嫲傜偔拞崅擭憌偵斾傋丄摿偵彈惈偺応崌丄奜怘偺婡夛偑
懡偔丄偦偺暘暷偺壠寁徚旓偑彮側偄偲偄偆帠忣偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅乮拲俁乯
傢傟傢傟偺僐僂儂乕僩暘愅偼偦偺拞恎傑偱偼柧傜偐偵偟偰偔傟側偄丅
丂師偵乮俛乯偺悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰丄弌惗偑愴拞乮1940乣44擭乯乣愴憟捈屻
乮1945乣49擭乯傪嫬偵丄屆偄曽偼僾儔僗丄怴偟偄曽偼儅僀僫僗偲柧妋側嵎堎偑帵
偝傟偰偄傞丅摿偵1935乣39擭埲慜偵弌惗偟偨悽戙乮1995擭尰嵼50戙屻敿傛傝忋乯
偼丄乮憤暯嬒40.96kg偵壛偊傞偵乯亄7kg慜屻丄偙傟偵懳偟1955乣59擭弌惗偺悽戙
偼仯2kg丄偝傜偵怴偟偄悽戙偵側傞傎偳晧偺抣偼壛懍搙揑偵戝偒偔側傞丅崅搙惉
挿婜埲崀丄摿偵1975乣79擭弌惗偺悽戙偼仯12kg丄1980乣85擭偺偦傟偼仯15kg庛偲
堦憌戝偒側晧偺岠壥傪帩偭偰偄傞丅懎側尵梩偱昞尰偡傟偽丄怴偟偄悽戙掱乽暷棧
傟乿偺孹岦偑尠挊偱偁傞丅
丂偙傟傜偺悽戙傕傗偑偰擭傪庢傝丄椺偊偽2020擭戙偵偼40嵨埲忋偵側傞丅恾1偺
乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯傪偨偳偭偰仯5kg偐傜亄5kg傊10kg慜屻憹偊傞偱偁傠偆偑丄
偦傕偦傕僗僞乕僩偺悽戙摿桳偺抣偑丄椺偊偽1995擭偵40戙屻敿偩偭偨恖払偵斾傋丄
亄2亅乮亅14乯亖16kg慜屻掅偄"僴儞僨傿"傪堷偒偢偭偰偄偔偙偲偵側傞丅偲偡傞偲丄
2020擭崰偺40戙屻敿偺恖払偺徚旓偼丄崱屻偺帪戙偺摦偒傪柍帇偡傟偽丄1995擭偺
偦偺奒憌偺徚旓検丄42kg慜屻乮昞3乯傛傝16kg掱搙彮側偄25kg慜屻偵側傞偺偱偼側
偄偐偲梊憐偝傟傞丅擭楊丒悽戙岠壥偺恾偼丄埲忋偺傛偆偵彨棃梊應偵傕棙梡偱偒
傞丅
丂1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰暷偺1恖摉偨傝壠寁徚旓偼45.16kg偐傜30.26kg傊尭彮
偟偨偑丄偙偺婜娫偵挷嵏壠寁偺悽懷堳偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偼尠挊偵曄壔偟偰偄
傞丅偪側傒偵悽懷庡偑60嵨埲忋偺悽懷偼1979擭偵8,000屗偺偆偪1,072屗偩偭偨偺
偑丄1997擭偵偼摨偠偔2,442屗偵憹偊偰偄傞丅偡側傢偪恖岥偺崅楊壔偑恑傫偱偄傞丅
摨帪偵1979擭偵60嵨側偄偟70嵨埲忋偩偭偨屆偄悽戙丄偡側傢偪悽戙斣崋0乣2偺懡
偔偼徚偊嫀傞偐挊偟偔妶摦偑撦傝丄1980埲崀弌惗偺悽戙偑怴偟偔壛傢偭偰偒偨丅
偙偺婜娫偵偍偗傞憡懳揑側暷徚旓偺曄壔偵偦偺傛偆側崅楊壔偲悽戙峔惉偺曄壔偑
嶌梡偟偰偄傞偱偁傠偆偙偲偵媈栤偺梋抧偼側偄丅
丂偦偺傛偆側擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偑丄恾1偺乮俠乯偵
帵偝傟偰偄傞丅1979乣81擭崰偼憤暯嬒40.96偵壛偊偰亄7kg慜屻偩偭偨偺偑丄1987
乣89擭偵亇0丄1995乣97擭偵偼仯7kg慜屻偵傎傏堦娧偟偰尭彮偟懕偗丄婜娫傪捠偟
偰寁14kg慜屻尭彮偟偰偄傞丅偙偺抣偼忋弎偺1恖摉偨傝扨弮暯嬒抣偺尭彮偲傎傏
堦抳偡傞偑丄嫲傜偔恖岥偺崅楊壔偺塭嬁偼偐側傝僾儔僗偺曽岦偵摥偄偨偑丄悽戙
岎戙偺塭嬁偼儅僀僫僗曽岦偱丄偨傑偨傑憡嶦偟崌偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傟傜2
偮偺岠壥偺嶌梡偼丄昳栚偵傛偭偰堎側傝丄昁偢偟傕暷偲摨偠偱偼側偄偺偼屻偱尒
傞偲偍傝偱偁傞丅
拲俁丗椺偊偽40戙偍傛傃50戙偼梉怘偺奜怘斾棪偑12.2偍傛傃10.5亾偵懳偟丄20乣
丂24丄25乣29偍傛傃30戙偼偦傟偧傟20.7丄18.4偍傛傃13.6亾偱偁偭偨乮岤惗徣
丂乽崙柉塰梴偺尰忬丒暯惉5擭挷嵏乿傛傝乯丅
丂偁傞擭師乮 t 擭乯擭偵偍偗傞偁傞擭楊奒媺乮 i 奒媺乯偺徚旓乮兪 i t 乯偼丄19
擭亊13奒媺亖247偺僙儖偵嫟捠偺兝乮憤暯嬒乮岠壥乯乯傪儀乕僗偵丄嫹媊偺擭楊
i 奒媺偵摿桳偺擭楊岠壥丆兝i A 偲丄挷嵏帪 i 擭偵嫟捠偺帪戙岠壥丆兝t P 偑壛傢
傝丄偝傜偵傕偆1崁丄偦傟偧傟偺僙儖乮 t 擭師偵 i 擭楊奒媺偺廤抍乯偑丄偄偮弌
惗偟丄惉恖婜偵払偡傞傑偱偵偦傟偧傟堎側偭偨宱尡傪嫟桳偟攟傢傟偨偱偁傠偆摿
桳偺悽戙岠壥丆兝k C 偑壛傢傞丅偡側傢偪丄
丂兪 i t亖兝亄兝i A 亄兝t P 亄兝k C 亄岆嵎崁乧乮1乯
乮1乯幃偺傛偆偵偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞偲憐掕偡傞丅尰幚偵嬤偯偔偨傔偵偼傕偭
偲暋嶨側儌僨儖傪梡堄偡傋偒偱偁傠偆偑丄寁嶼偼擄偟偔側傝丄岆嵎傕奼戝偡傞嫲
傟偑偁傞丅
丂悽戙傪帵偡斣崋0偐傜16偼曋媂揑側傕偺偱丄0偑挷嵏婜娫偺巒傔偵70嵨埲忋偩偭
偨恖乆丄偡側傢偪1909擭埲慜弌惗偺堦斣屆偄悽戙丄媡偵16偼挷嵏偺嵟嬤擭師偵10
乣14嵨偱偁偭偨恖乆丄偡側傢偪1985乣89擭偵弌惗偟偨悽戙傪帵偟偰偄傞丅昞4偺
悇寁抣傪巊偭偰嬶懱揑側寁嶼傪帋傒偰傒傛偆丅
寁嶼嘆
丂1984擭偵55乣59嵨偩偭偨恖乆偼1925乣29擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋4偵摉偨傞丅偙
偺廤抍偺棟榑忋偺徚旓偼乮1乯幃偐傜丄
丂兝亄兝A55亅59亄兝P'84亄兝C4 亖40.96亄5.73亄4.62亄7.42亖58.73kg偲悇寁偝傟
傞丅偪側傒偵昞3偺奩摉僙儖偺抣偼57.76kg偱偁傞丅
寁嶼嘇
丂1994擭偵25乣29嵨偩偭偨恖乆偼1965乣69擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋12偱偁傞丅摨條
偵乮1乯幃偐傜偙偺廤抍偺棟榑抣偼丄
丂兝亄兝A25亅29亄兝P'94亄兝C12 亖40.96亅9.29亅6.10亅4.58亖20.99kg丅偙傟偵
懳墳偡傞昞3偺抣偼丄21.29kg偱偁傞丅
丂昞係偺暷偵偮偄偰偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥傪娙扨側恾偵偡傞偲恾1偺乮俙乯乣
乮俠乯偺傛偆偵側傞丅乮俙乯偑擭楊岠壥兝i A 丄乮俛乯偑悽戙岠壥兝k C 丄乮俠乯
偑擭師側偄偟帪戙岠壥兝t P 傪偦傟偧傟帵偟偰偄傞丅偄偢傟偺岠壥傕僛儘偺慄傪
拞怱偵嵍塃偵偽傜偮偒丄廤寁偡傞偲嵎偟堷偒僛儘偵側傞傛偆偵側偭偰偄傞丅乮儼
兝i A 亖0丄儼兝k C 亖0丄儼兝t P 亖0乯丅
仦恾侾丗暷偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖40.96kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢憤暯嬒乮岠壥乯偑40.96kg偱偁傞丅
丂乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯偼丄30戙偺屻敿40戙偺慜敿傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘
偐傟傞丅嫹媊偺擭楊岠壥偲偟偰40戙埲忋偼憤暯嬒40.96kg偵亄5.0kg慜屻偑壛傢傞丅
偦傟傛傝庒偄擭楊憌偱偼媡偵仯5.0kg偑壛傢傞丅偡側傢偪慜幰偼46kg慜屻丄屻幰偼
36kg慜屻偵側傝丄拞崅偲庒擭偺椉奒憌娫偱10kg慜屻偺嵎偑奐偔丅摿偵20戙屻敿偲
30戙慜敿偼仯9kg嫮偺擭楊岠壥傪帵偟乮40.96亅9佮32kg乯丄偝傜偵暷傪怘傋側偄擭
楊奒憌偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅偨偩偟偙傟傜偺奒憌偑暷徚旓偺憤検偑偦傟傎偳掅偄
偐偳偆偐偼暘偐傜側偄丅嫲傜偔拞崅擭憌偵斾傋丄摿偵彈惈偺応崌丄奜怘偺婡夛偑
懡偔丄偦偺暘暷偺壠寁徚旓偑彮側偄偲偄偆帠忣偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅乮拲俁乯
傢傟傢傟偺僐僂儂乕僩暘愅偼偦偺拞恎傑偱偼柧傜偐偵偟偰偔傟側偄丅
丂師偵乮俛乯偺悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰丄弌惗偑愴拞乮1940乣44擭乯乣愴憟捈屻
乮1945乣49擭乯傪嫬偵丄屆偄曽偼僾儔僗丄怴偟偄曽偼儅僀僫僗偲柧妋側嵎堎偑帵
偝傟偰偄傞丅摿偵1935乣39擭埲慜偵弌惗偟偨悽戙乮1995擭尰嵼50戙屻敿傛傝忋乯
偼丄乮憤暯嬒40.96kg偵壛偊傞偵乯亄7kg慜屻丄偙傟偵懳偟1955乣59擭弌惗偺悽戙
偼仯2kg丄偝傜偵怴偟偄悽戙偵側傞傎偳晧偺抣偼壛懍搙揑偵戝偒偔側傞丅崅搙惉
挿婜埲崀丄摿偵1975乣79擭弌惗偺悽戙偼仯12kg丄1980乣85擭偺偦傟偼仯15kg庛偲
堦憌戝偒側晧偺岠壥傪帩偭偰偄傞丅懎側尵梩偱昞尰偡傟偽丄怴偟偄悽戙掱乽暷棧
傟乿偺孹岦偑尠挊偱偁傞丅
丂偙傟傜偺悽戙傕傗偑偰擭傪庢傝丄椺偊偽2020擭戙偵偼40嵨埲忋偵側傞丅恾1偺
乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯傪偨偳偭偰仯5kg偐傜亄5kg傊10kg慜屻憹偊傞偱偁傠偆偑丄
偦傕偦傕僗僞乕僩偺悽戙摿桳偺抣偑丄椺偊偽1995擭偵40戙屻敿偩偭偨恖払偵斾傋丄
亄2亅乮亅14乯亖16kg慜屻掅偄"僴儞僨傿"傪堷偒偢偭偰偄偔偙偲偵側傞丅偲偡傞偲丄
2020擭崰偺40戙屻敿偺恖払偺徚旓偼丄崱屻偺帪戙偺摦偒傪柍帇偡傟偽丄1995擭偺
偦偺奒憌偺徚旓検丄42kg慜屻乮昞3乯傛傝16kg掱搙彮側偄25kg慜屻偵側傞偺偱偼側
偄偐偲梊憐偝傟傞丅擭楊丒悽戙岠壥偺恾偼丄埲忋偺傛偆偵彨棃梊應偵傕棙梡偱偒
傞丅
丂1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰暷偺1恖摉偨傝壠寁徚旓偼45.16kg偐傜30.26kg傊尭彮
偟偨偑丄偙偺婜娫偵挷嵏壠寁偺悽懷堳偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偼尠挊偵曄壔偟偰偄
傞丅偪側傒偵悽懷庡偑60嵨埲忋偺悽懷偼1979擭偵8,000屗偺偆偪1,072屗偩偭偨偺
偑丄1997擭偵偼摨偠偔2,442屗偵憹偊偰偄傞丅偡側傢偪恖岥偺崅楊壔偑恑傫偱偄傞丅
摨帪偵1979擭偵60嵨側偄偟70嵨埲忋偩偭偨屆偄悽戙丄偡側傢偪悽戙斣崋0乣2偺懡
偔偼徚偊嫀傞偐挊偟偔妶摦偑撦傝丄1980埲崀弌惗偺悽戙偑怴偟偔壛傢偭偰偒偨丅
偙偺婜娫偵偍偗傞憡懳揑側暷徚旓偺曄壔偵偦偺傛偆側崅楊壔偲悽戙峔惉偺曄壔偑
嶌梡偟偰偄傞偱偁傠偆偙偲偵媈栤偺梋抧偼側偄丅
丂偦偺傛偆側擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偑丄恾1偺乮俠乯偵
帵偝傟偰偄傞丅1979乣81擭崰偼憤暯嬒40.96偵壛偊偰亄7kg慜屻偩偭偨偺偑丄1987
乣89擭偵亇0丄1995乣97擭偵偼仯7kg慜屻偵傎傏堦娧偟偰尭彮偟懕偗丄婜娫傪捠偟
偰寁14kg慜屻尭彮偟偰偄傞丅偙偺抣偼忋弎偺1恖摉偨傝扨弮暯嬒抣偺尭彮偲傎傏
堦抳偡傞偑丄嫲傜偔恖岥偺崅楊壔偺塭嬁偼偐側傝僾儔僗偺曽岦偵摥偄偨偑丄悽戙
岎戙偺塭嬁偼儅僀僫僗曽岦偱丄偨傑偨傑憡嶦偟崌偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傟傜2
偮偺岠壥偺嶌梡偼丄昳栚偵傛偭偰堎側傝丄昁偢偟傕暷偲摨偠偱偼側偄偺偼屻偱尒
傞偲偍傝偱偁傞丅
拲俁丗椺偊偽40戙偍傛傃50戙偼梉怘偺奜怘斾棪偑12.2偍傛傃10.5亾偵懳偟丄20乣
丂24丄25乣29偍傛傃30戙偼偦傟偧傟20.7丄18.4偍傛傃13.6亾偱偁偭偨乮岤惗徣
丂乽崙柉塰梴偺尰忬丒暯惉5擭挷嵏乿傛傝乯丅
4丂僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥亅媿擏丄慛嫑偍傛傃堸梡媿擕
乮1乯媿擏
昞俆丂媿擏偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
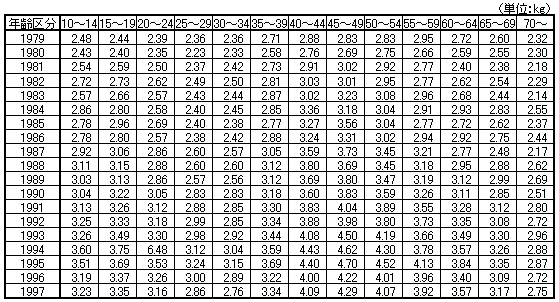 丂昞俆偺1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰偺悽懷堳偺擭楊奒媺暿偺徚旓検乮娫愙悇寁乯
偺僨乕僞傪僐僂儂乕僩偺暘愅偵偐偗傞偲丄恾2偺傛偆偵側傞丅
仦恾俀丗媿擏偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖3.12kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄愭偺暷偺応崌偲摨偠傛偆偵30戙屻敿偲40戙慜敿
傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘偐傟傞丅拞崅擭憌偼憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵壛偊傞
偵亄0.4乣0.5kg丄懠曽10戙偺枹惉擭憌傪娷傒庒擭憌偼仯0.5kg慜屻偱丄暷偺応崌摨
條摿偵20戙屻敿偲30戙慜敿偼晧偺抣偑戝偒偔丄仯0.7kg傪帵偡丅嫲傜偔奜怘婡夛
偲娭學偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂偦傟偵偟偰傕擭楊岠壥偑丄庒擭憌偱憤暯嬒偺15乣20亾偵憡摉偡傞儅僀僫僗偲弌
傞偙偲偵婏堎偺擮傪姶偢傞撉幰偑偍傜傟傞偐傕偟傟側偄丅擾嬈憤崌尋媶強偺愇嫶
婌旤巕巵偑乽壠寁挷嵏乿偺屄昜傪巊偭偰峴偭偨暘愅寢壥偐傜傕丄慡崙揑偵丄庒擭
憌偺媿擏徚旓偑拞崅擭憌偺悈弨偵嬤偯偔偺偼桝擖帺桼壔埲崀偺偙偲偱丄偦傟埲慜
偼庒偄憌偼撠擏偵孹幬偟偰偄偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅乮拲4乯杮峞偵偼嵹
偣偰偄側偄偑昅幰偺僐僂儂乕僩暘愅偱傕丄撠擏偺応崌庒擭憌丄摿偵10戙偺擭楊岠
壥偼僾儔僗偵悇掕偝傟偰偄傞丅
丂悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰偼暷偺応崌偲慡偔懳徠揑偱偁傞丅偡側傢偪丄1935乣39擭
埲慜弌惗偺屆偄悽戙偼丄憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟15乣20亾偺儅僀僫僗丄懠曽
1945乣49擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄憤暯嬒偵懳偟10亾慜屻偺僾儔僗偺岠壥傪帵
偡丅摿偵1970擭埲崀弌惗偺悽戙偼15亾偺僾儔僗偺岠壥傪帩偭偰偄傞偲悇掕偝傟傞丅
丂1995擭崰20丄30戙偩偭偨恖乆偑2020擭戙偵40丄50戙偵側傟偽丄恾2偺乮俙乯偺
擭楊岠壥傪偨偳偭偰徚旓偼1.0kg掱搙憹偊傞偩傠偆丅懠曽1995擭摉帪40丄50戙偩
偭偨悽戙偵斾傋丄悽戙岠壥偵娭偟0.5乣0.6kg懡偄偐傜丄崱屻偺帪戙岠壥傪峫偊側
偔偲傕丄偐傟傜偺徚旓偼尰嵼偺拞崅擭憌傛傝憡摉掱搙懡偔側傞偺偼娫堘偄側偄丅
丂恖岥偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偺曄壔偵傛傞塭嬁傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙乮岠壥乯偑
恾2偺乮俠乯偵帵偝傟偰偄傞丅擭乆偺墯撌偼偁傞偑丄1979乣81擭摉帪偺仯0.4kg偐
傜1989擭偵僛儘丄1995擭偵亄0.55偲憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟偰慡婜娫偱30亾
嫮偺憹壛傪帵偟偰偄傞丅1996擭偵0.25偵棊偪傞偑丄偙傟偼椺偺俷157帠審傗嫸媿
昦憶偓偵傛傞堦帪揑側棊偪崬傒傪偁傜傢偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂悽懷堳1恖摉偨傝偺扨弮暯嬒偼丄1979擭偺2.46kg偐傜1995擭偺3.61kg傊46.7亾憹
壛偟偨丅偦偺婜娫偺恖岥偺榁楊壔偵傛傞塭嬁乮偙傟偼僾儔僗乯偲丄偝傜偵廳梫側
偺偼1980擭摉帪60丄70戙埲忋偩偭偨屆偄悽戙偑師戞偵徚偊丄摉帪梒帣丄10戙偩偭
偨怴偟偄悽戙偑壛傢偭偨偙偲偵傛傞塭嬁偑嶌梡偟偰偄傞丅偙傟傜2偮偺岠壥傪彍
嫀偟偨偺偑忋婰偺弮悎偺擭戙岠壥丄栺30亾憹偱偁傞丅偙偺揰傪峫椂偣偢偵枹壛岺
偺僨乕僞偱帪宯楍偺夞婣暘愅傪偡傞偲丄廀梫抏椡惈偑夁戝偵悇寁偝傟傞嫲傟偑偁
傞丅
拲係丗愇嫶婌旤巕乮1998乯乽桝擖帺桼壔慜屻偵偍偗傞媿擏偺壠寁徚旓峔憿曄壔乿
丂丂擾嬈憤崌尋媶52姫4崋丄曗榑丅傑偨拞懞偺儀僀僘宆儌僨儖偵偮偄偰偼丄拞懞
丂丂棽乮1982乯乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖亅昗弨僐僂儂乕僩昞傊偺揔梡亅乿
丂丂摑寁悢棟尋媶曬29姫2崋丄Nakamura. T.乮1986乯乽Bayesiyan Cohort Models
丂丂for General Cohort Table Analyses乿Ann, Inst. Statist. Math., Vol.38,
丂 Part B, Tokyo 側偳
乮2乯慛嫑
丂擭楊岠壥偲悽戙岠壥偺宍偼丄愭偵徻弎偟偨暷偵傛偔帡偰偄傞丅擭楊岠壥偲偟偰
40戙慜敿傪嫬偵庒偄憌偑儅僀僫僗丄擭攝憌偑僾儔僗偱偁傞丅傑偨悽戙揑偵丄1950
擭崰傛傝埲慜偵弌惗偟偨悽戙偼僾儔僗丄偦傟埲崀弌惗偺怴偟偄悽懷偼丄怴偟偄掱
椵恑揑偵儅僀僫僗偺抣傪帵偟偰偄傞丅庒偄恖偲偄偆傛傝怴偟偄悽戙偺乽嫑棧傟乿
偑媫懍偵恑傫偱偄傞傜偟偄偙偲偑摑寁揑偵棤晅偗傜傟偨偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅
昞俇丂慛嫑偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
丂昞俆偺1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰偺悽懷堳偺擭楊奒媺暿偺徚旓検乮娫愙悇寁乯
偺僨乕僞傪僐僂儂乕僩偺暘愅偵偐偗傞偲丄恾2偺傛偆偵側傞丅
仦恾俀丗媿擏偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖3.12kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄愭偺暷偺応崌偲摨偠傛偆偵30戙屻敿偲40戙慜敿
傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘偐傟傞丅拞崅擭憌偼憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵壛偊傞
偵亄0.4乣0.5kg丄懠曽10戙偺枹惉擭憌傪娷傒庒擭憌偼仯0.5kg慜屻偱丄暷偺応崌摨
條摿偵20戙屻敿偲30戙慜敿偼晧偺抣偑戝偒偔丄仯0.7kg傪帵偡丅嫲傜偔奜怘婡夛
偲娭學偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂偦傟偵偟偰傕擭楊岠壥偑丄庒擭憌偱憤暯嬒偺15乣20亾偵憡摉偡傞儅僀僫僗偲弌
傞偙偲偵婏堎偺擮傪姶偢傞撉幰偑偍傜傟傞偐傕偟傟側偄丅擾嬈憤崌尋媶強偺愇嫶
婌旤巕巵偑乽壠寁挷嵏乿偺屄昜傪巊偭偰峴偭偨暘愅寢壥偐傜傕丄慡崙揑偵丄庒擭
憌偺媿擏徚旓偑拞崅擭憌偺悈弨偵嬤偯偔偺偼桝擖帺桼壔埲崀偺偙偲偱丄偦傟埲慜
偼庒偄憌偼撠擏偵孹幬偟偰偄偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅乮拲4乯杮峞偵偼嵹
偣偰偄側偄偑昅幰偺僐僂儂乕僩暘愅偱傕丄撠擏偺応崌庒擭憌丄摿偵10戙偺擭楊岠
壥偼僾儔僗偵悇掕偝傟偰偄傞丅
丂悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰偼暷偺応崌偲慡偔懳徠揑偱偁傞丅偡側傢偪丄1935乣39擭
埲慜弌惗偺屆偄悽戙偼丄憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟15乣20亾偺儅僀僫僗丄懠曽
1945乣49擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄憤暯嬒偵懳偟10亾慜屻偺僾儔僗偺岠壥傪帵
偡丅摿偵1970擭埲崀弌惗偺悽戙偼15亾偺僾儔僗偺岠壥傪帩偭偰偄傞偲悇掕偝傟傞丅
丂1995擭崰20丄30戙偩偭偨恖乆偑2020擭戙偵40丄50戙偵側傟偽丄恾2偺乮俙乯偺
擭楊岠壥傪偨偳偭偰徚旓偼1.0kg掱搙憹偊傞偩傠偆丅懠曽1995擭摉帪40丄50戙偩
偭偨悽戙偵斾傋丄悽戙岠壥偵娭偟0.5乣0.6kg懡偄偐傜丄崱屻偺帪戙岠壥傪峫偊側
偔偲傕丄偐傟傜偺徚旓偼尰嵼偺拞崅擭憌傛傝憡摉掱搙懡偔側傞偺偼娫堘偄側偄丅
丂恖岥偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偺曄壔偵傛傞塭嬁傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙乮岠壥乯偑
恾2偺乮俠乯偵帵偝傟偰偄傞丅擭乆偺墯撌偼偁傞偑丄1979乣81擭摉帪偺仯0.4kg偐
傜1989擭偵僛儘丄1995擭偵亄0.55偲憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟偰慡婜娫偱30亾
嫮偺憹壛傪帵偟偰偄傞丅1996擭偵0.25偵棊偪傞偑丄偙傟偼椺偺俷157帠審傗嫸媿
昦憶偓偵傛傞堦帪揑側棊偪崬傒傪偁傜傢偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂悽懷堳1恖摉偨傝偺扨弮暯嬒偼丄1979擭偺2.46kg偐傜1995擭偺3.61kg傊46.7亾憹
壛偟偨丅偦偺婜娫偺恖岥偺榁楊壔偵傛傞塭嬁乮偙傟偼僾儔僗乯偲丄偝傜偵廳梫側
偺偼1980擭摉帪60丄70戙埲忋偩偭偨屆偄悽戙偑師戞偵徚偊丄摉帪梒帣丄10戙偩偭
偨怴偟偄悽戙偑壛傢偭偨偙偲偵傛傞塭嬁偑嶌梡偟偰偄傞丅偙傟傜2偮偺岠壥傪彍
嫀偟偨偺偑忋婰偺弮悎偺擭戙岠壥丄栺30亾憹偱偁傞丅偙偺揰傪峫椂偣偢偵枹壛岺
偺僨乕僞偱帪宯楍偺夞婣暘愅傪偡傞偲丄廀梫抏椡惈偑夁戝偵悇寁偝傟傞嫲傟偑偁
傞丅
拲係丗愇嫶婌旤巕乮1998乯乽桝擖帺桼壔慜屻偵偍偗傞媿擏偺壠寁徚旓峔憿曄壔乿
丂丂擾嬈憤崌尋媶52姫4崋丄曗榑丅傑偨拞懞偺儀僀僘宆儌僨儖偵偮偄偰偼丄拞懞
丂丂棽乮1982乯乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖亅昗弨僐僂儂乕僩昞傊偺揔梡亅乿
丂丂摑寁悢棟尋媶曬29姫2崋丄Nakamura. T.乮1986乯乽Bayesiyan Cohort Models
丂丂for General Cohort Table Analyses乿Ann, Inst. Statist. Math., Vol.38,
丂 Part B, Tokyo 側偳
乮2乯慛嫑
丂擭楊岠壥偲悽戙岠壥偺宍偼丄愭偵徻弎偟偨暷偵傛偔帡偰偄傞丅擭楊岠壥偲偟偰
40戙慜敿傪嫬偵庒偄憌偑儅僀僫僗丄擭攝憌偑僾儔僗偱偁傞丅傑偨悽戙揑偵丄1950
擭崰傛傝埲慜偵弌惗偟偨悽戙偼僾儔僗丄偦傟埲崀弌惗偺怴偟偄悽懷偼丄怴偟偄掱
椵恑揑偵儅僀僫僗偺抣傪帵偟偰偄傞丅庒偄恖偲偄偆傛傝怴偟偄悽戙偺乽嫑棧傟乿
偑媫懍偵恑傫偱偄傞傜偟偄偙偲偑摑寁揑偵棤晅偗傜傟偨偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅
昞俇丂慛嫑偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
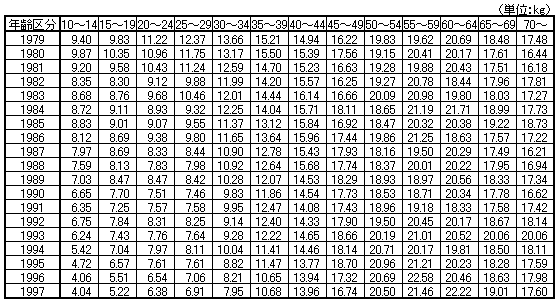 丂悽懷堳1恖摉偨傝偺暯嬒徚旓検偼1979擭偺14.57kg偐傜1997擭偺13.64kg傊丄栺7
亾尭彮偟偰偄傞偑丄擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偼丄恾3偺
乮俠乯偵傒傞傛偆偵僛儘偺慄傪拞怱偵偽傜偮偒丄暷偺傛偆偵堦娧偟偨尭彮孹岦偼
帵偟偰偄側偄丅
仦恾俁丗慛嫑偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖13.79kg乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
乮3乯堸梡媿擕
丂昞7偺擭楊奒媺暿徚旓偺悇堏傪傒傞偲丄1980擭崰偼梒帣偐傜30戙慜敿偔傜偄傑
偱偺憌偑栺30r庛丄偦傟傛傝忋偺憌偼21乣24r偔傜偄偱偁偭偨丅偦偺屻丄梒丄彫帣
偺徚旓偼孹岦揑偵傎偲傫偳曄傢傜偢丄僥傿乕儞僄僀僕儍乕偼旝憹丄20戙偲30戙慜
敿偼傎偲傫偳墶偽偄偱偁偭偨偺偵懳偟丄30戙屻敿埲忋憌偱尠挊偵憹偊偰偄傞丅摿
偵50戙屻敿偐傜偺崅楊憌偵偍偄偰偼丄傎傏攞憹偵嬤偄怢傃傪傒偣偰偄傞丅
昞俈丂堸梡媿擕偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
丂悽懷堳1恖摉偨傝偺暯嬒徚旓検偼1979擭偺14.57kg偐傜1997擭偺13.64kg傊丄栺7
亾尭彮偟偰偄傞偑丄擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偼丄恾3偺
乮俠乯偵傒傞傛偆偵僛儘偺慄傪拞怱偵偽傜偮偒丄暷偺傛偆偵堦娧偟偨尭彮孹岦偼
帵偟偰偄側偄丅
仦恾俁丗慛嫑偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖13.79kg乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
乮3乯堸梡媿擕
丂昞7偺擭楊奒媺暿徚旓偺悇堏傪傒傞偲丄1980擭崰偼梒帣偐傜30戙慜敿偔傜偄傑
偱偺憌偑栺30r庛丄偦傟傛傝忋偺憌偼21乣24r偔傜偄偱偁偭偨丅偦偺屻丄梒丄彫帣
偺徚旓偼孹岦揑偵傎偲傫偳曄傢傜偢丄僥傿乕儞僄僀僕儍乕偼旝憹丄20戙偲30戙慜
敿偼傎偲傫偳墶偽偄偱偁偭偨偺偵懳偟丄30戙屻敿埲忋憌偱尠挊偵憹偊偰偄傞丅摿
偵50戙屻敿偐傜偺崅楊憌偵偍偄偰偼丄傎傏攞憹偵嬤偄怢傃傪傒偣偰偄傞丅
昞俈丂堸梡媿擕偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
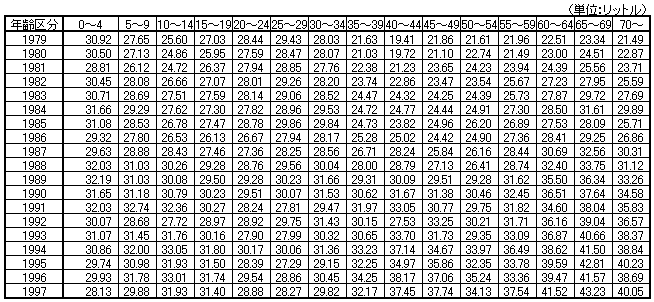 丂偙傟傜偺悢抣傪儀僀僘宆僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞偲丄恾4偺傛偆側岠壥偑嶼弌
偝傟傞丅堸梡媿擕偵偮偄偰丄堦惗偵傢偨傞堸梡姷廗偑宍惉偝傟傞乮佮乽悽戙岠壥乿
偑屌掕偡傞乯帪婜偼丄媿擏傗慛嫑側偳偵斾傋傞偲傛傝擭彮偺帪婜丄梒帣婜偐彫妛
峑偺掅妛擭崰偱偼側偄偐偲偄偆堄尒偑偁傞丅
仦恾係丗堸梡媿擕偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖29.49倢乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
丂傢傟傢傟偼媿擕偵偮偄偰偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞擭楊奒媺偺嵟壓抂傪丄0
乣4嵨丄師偵5乣9嵨乧側偳偲壗捠傝偐帋傒偨丅偄偢傟偺帋傒偐傜傕忢幆偵斀偡傞
傛偆側寢壥偼惗傑傟側偐偭偨偑丄摨帪偵偳偺奒媺偐傜僗僞乕僩偝偣傞偺偑嵟傕椙
偄偺偐傕敾慠偲偟側偐偭偨丅偙偙偱偼愭偺3昳栚偵崌傢偣偰丄10乣14嵨傪嵟壓抂
偲偟偨暘愅寢壥傪徯夘偡傞丅
丂傑偢乮俙乯擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄10戙慜敿偑憤暯嬒24.49r偐傜20亾庛偺僾
儔僗丄10戙屻敿偐傜20戙偲掽尭偟丄20戙偺屻敿偱僛儘丄30戙屻敿偑仯4.59偱掙傪
偮偒丄偦偺屻憹壛偟偰60戙慜敿偱傗傗僾儔僗丄70嵨埲忋憌偱偼亄5r嫮偺抣傪帵偡丅
丂拲栚偵抣偡傞偺偼乮俛乯悽戙乮岠壥乯偱偁傞丅嵟傕屆偄悽戙丄1909擭埲慜弌惗
偺恖乆偼傗傗儅僀僫僗丄1925乣1950擭戙弌惗偺悽戙偼憤暯嬒偵懳偟10乣15亾偺僾
儔僗偺抣傪帵偡偑丄1960擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄擭楊岠壥傪暘棧偟偨悽戙岠
壥偺傒偲偟偰丄憤暯嬒偺10亾埲忋偺儅僀僫僗偺抣傪帩偪丄嵟嬤弌惗偺悽戙掱儅僀
僫僗偺愨懳抣偼掽憹偟偰偄傞丅
丂扨弮偵擭楊偑庒偄偲偄偆偺偱偼側偔丄乽崅搙惉挿乿偑僗僞乕僩偟偨屻偵惗傑傟
偨怴偟偄悽戙偼丄偦傟埲慜弌惗偺悽戙丄愴屻偡偖偵惗傑傟妛峑媼怘偺媿擕乮扙帀
暡擕乯傪偁傝偑偨偔堸傫偩悽戙偵斾傋丄悽戙偺摿惈偲偟偰亄4.5亅乮亅6.5乯亖11
r慜屻傕掅偄抣傪帩偮偲悇掕偝傟傞丅偙傟傜偺悽戙偼1995擭摉帪30嵨埲壓偩偑丄
傗偑偰擭傪庢傝丄懠曽1930擭戙偐傜愴憟捈屻偵惗傑傟偨悽戙偵懼傢偭偰偄偔偵偮
傟丄偦偺尷傝偵偍偄偰乮師偵弎傋傞帪戙岠壥偺愭峴偒傪峫偊側偗傟偽乯媿擕徚旓
偼尭彮偟偰偄偔偐傕偟傟側偄丅
丂媿擕偺壠寁徚旓偼1979乣80擭偐傜1996乣97擭偵偐偗丄1恖摉偨傝扨弮暯嬒偱25.
1r偐傜34.6r傊10r庛憹戝偟偨丅擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨擭戙岠壥偼恾4偺
乮俠乯偵帵偝傟傞捠傝偱丄1979乣80擭偺仯6.6r偐傜孹岦揑偵憹偊丄88乣89擭傪嫬
偵僾儔僗偵揮偠丄1996乣97擭偵偼亄8.0r偲14r嫮偺弮憹傪帵偟偰偄傞丅
丂偨偩偟彨棃偺廀梫憤検傪偙偺慄傪墑挿偟偰梊應偡傞偺偼婋尟偱偁傞丅媿擏偺傛
偆偵丄怴偟偄悽戙偑傗偑偰徚偊峴偔屆偄悽戙偲懳徠揑偵僾儔僗偺悽戙岠壥傪帩偮
働乕僗偲偼媡偵丄媿擕偵偮偄偰偼怴偟偄悽戙偑丄屆偄悽戙偵斾傋偐側傝儅僀僫僗
偺悽戙岠壥傪帩偭偰偄傞傜偟偄偙偲偑暘偐偭偨丅崱夞偺偙偺悇寁岠壥傪丄娭學幰
偼廫暘柫婰偟偰偍偔昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞丅
丂偙傟傜偺悢抣傪儀僀僘宆僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞偲丄恾4偺傛偆側岠壥偑嶼弌
偝傟傞丅堸梡媿擕偵偮偄偰丄堦惗偵傢偨傞堸梡姷廗偑宍惉偝傟傞乮佮乽悽戙岠壥乿
偑屌掕偡傞乯帪婜偼丄媿擏傗慛嫑側偳偵斾傋傞偲傛傝擭彮偺帪婜丄梒帣婜偐彫妛
峑偺掅妛擭崰偱偼側偄偐偲偄偆堄尒偑偁傞丅
仦恾係丗堸梡媿擕偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖29.49倢乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
丂傢傟傢傟偼媿擕偵偮偄偰偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞擭楊奒媺偺嵟壓抂傪丄0
乣4嵨丄師偵5乣9嵨乧側偳偲壗捠傝偐帋傒偨丅偄偢傟偺帋傒偐傜傕忢幆偵斀偡傞
傛偆側寢壥偼惗傑傟側偐偭偨偑丄摨帪偵偳偺奒媺偐傜僗僞乕僩偝偣傞偺偑嵟傕椙
偄偺偐傕敾慠偲偟側偐偭偨丅偙偙偱偼愭偺3昳栚偵崌傢偣偰丄10乣14嵨傪嵟壓抂
偲偟偨暘愅寢壥傪徯夘偡傞丅
丂傑偢乮俙乯擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄10戙慜敿偑憤暯嬒24.49r偐傜20亾庛偺僾
儔僗丄10戙屻敿偐傜20戙偲掽尭偟丄20戙偺屻敿偱僛儘丄30戙屻敿偑仯4.59偱掙傪
偮偒丄偦偺屻憹壛偟偰60戙慜敿偱傗傗僾儔僗丄70嵨埲忋憌偱偼亄5r嫮偺抣傪帵偡丅
丂拲栚偵抣偡傞偺偼乮俛乯悽戙乮岠壥乯偱偁傞丅嵟傕屆偄悽戙丄1909擭埲慜弌惗
偺恖乆偼傗傗儅僀僫僗丄1925乣1950擭戙弌惗偺悽戙偼憤暯嬒偵懳偟10乣15亾偺僾
儔僗偺抣傪帵偡偑丄1960擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄擭楊岠壥傪暘棧偟偨悽戙岠
壥偺傒偲偟偰丄憤暯嬒偺10亾埲忋偺儅僀僫僗偺抣傪帩偪丄嵟嬤弌惗偺悽戙掱儅僀
僫僗偺愨懳抣偼掽憹偟偰偄傞丅
丂扨弮偵擭楊偑庒偄偲偄偆偺偱偼側偔丄乽崅搙惉挿乿偑僗僞乕僩偟偨屻偵惗傑傟
偨怴偟偄悽戙偼丄偦傟埲慜弌惗偺悽戙丄愴屻偡偖偵惗傑傟妛峑媼怘偺媿擕乮扙帀
暡擕乯傪偁傝偑偨偔堸傫偩悽戙偵斾傋丄悽戙偺摿惈偲偟偰亄4.5亅乮亅6.5乯亖11
r慜屻傕掅偄抣傪帩偮偲悇掕偝傟傞丅偙傟傜偺悽戙偼1995擭摉帪30嵨埲壓偩偑丄
傗偑偰擭傪庢傝丄懠曽1930擭戙偐傜愴憟捈屻偵惗傑傟偨悽戙偵懼傢偭偰偄偔偵偮
傟丄偦偺尷傝偵偍偄偰乮師偵弎傋傞帪戙岠壥偺愭峴偒傪峫偊側偗傟偽乯媿擕徚旓
偼尭彮偟偰偄偔偐傕偟傟側偄丅
丂媿擕偺壠寁徚旓偼1979乣80擭偐傜1996乣97擭偵偐偗丄1恖摉偨傝扨弮暯嬒偱25.
1r偐傜34.6r傊10r庛憹戝偟偨丅擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨擭戙岠壥偼恾4偺
乮俠乯偵帵偝傟傞捠傝偱丄1979乣80擭偺仯6.6r偐傜孹岦揑偵憹偊丄88乣89擭傪嫬
偵僾儔僗偵揮偠丄1996乣97擭偵偼亄8.0r偲14r嫮偺弮憹傪帵偟偰偄傞丅
丂偨偩偟彨棃偺廀梫憤検傪偙偺慄傪墑挿偟偰梊應偡傞偺偼婋尟偱偁傞丅媿擏偺傛
偆偵丄怴偟偄悽戙偑傗偑偰徚偊峴偔屆偄悽戙偲懳徠揑偵僾儔僗偺悽戙岠壥傪帩偮
働乕僗偲偼媡偵丄媿擕偵偮偄偰偼怴偟偄悽戙偑丄屆偄悽戙偵斾傋偐側傝儅僀僫僗
偺悽戙岠壥傪帩偭偰偄傞傜偟偄偙偲偑暘偐偭偨丅崱夞偺偙偺悇寁岠壥傪丄娭學幰
偼廫暘柫婰偟偰偍偔昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞丅
尦偺儁乕僕偵栠傞
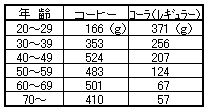 丂弌強丗USDA Continuing Survey of Food Intakes by Individuals, 1989-91
丂暷崙偱傕恖岥偺崅楊壔偑恑峴偟偰偄傞丅傕偟摨偠恖偱傕拞崅擭偵側傞偲僐乕儔
偺徚旓偑棊偪僐乕僸乕偵堏傞偲偡傟偽丄2010擭崰偵偼傾儊儕僇慡懱偲偟偰僐乕僸
乕偺徚旓偼憹偊丄懠曽僐乕儔椶偼尭彮偡傞偲梊憐偝傟傞丅
丂偩偑暿偺桳椡側尒曽傕偁傞丅American Demographics偺1994擭12寧崋偵乽偁偲
俀擭偱僋儕儞僩儞乮戝摑椞乯偼50戙傪寎偊傞偑丄斵偼憡曄傢傜偢儅僋僪僫儖僪搣
偱偁傠偆乿偲偺尒弌偟偑嵹偭偰偄傞丅庒偄崰偵僴儞僶乕僈乕偵姷傟恊偟傓偲拞崅
擭偵側偭偰傕偦偺廗暼偼帩偪墇偝傟丄僴儞僶乕僈乕揦偵捠偆偩傠偆偲偄偆偺偱偁
傞丅偙偺尒曽傪愭偺僐乕僸乕偲僐乕儔偺働乕僗偵摉偰偼傔傞偲丄1990擭摉帪20乣
30戙偺恖払偑丄2010擭崰拞崅擭偵払偟偰傕丄僐乕儔堸梡偺暼偼敳偗偢丄偐偮偰偺
拞崅擭幰偲摨偠傛偆偵傕偭傁傜僐乕僸乕傪偨偟側傓偲偄偆偙偲偼側偄偩傠偆丅偩
偲偡傞偲丄慡懱偲偟偰僐乕儔偺徚旓偼憹偊丄僐乕僸乕偺徚旓偼尭傞偩傠偆偲偄偆
寢榑偵側傞丅
丂慜幰偺尒曽偼1990擭摉帪偵娤嶡偝傟偨擭楊暿徚旓偺宆偑丄偙傟偐傜偟偽傜偔偼
曄傢傜側偄偲偡傞棫応偱偁傝丄屻幰偺尒曽偼恖惗偺偁傞帪婜乮嫲傜偔僥傿乕儞僄
僀僕儍乕偺崰乯偵宍惉偝傟偨悽戙摿桳偺堸怘偺廗姷偼丄偦偺屻偺壛楊偵偐偐傢傜
偢帩偪墇偝傟偰偄偔偲偡傞棫応偱偁傞丅
丂偟偐偟忋婰偺扨擭搙尷傝偺摑寁偐傜偼丄擭楊岠壥偑嫮偄偲傒傞傋偒偐丄悽戙岠
壥偑桪惃偱偁傞偲傒傞傋偒偐偼寛傔傜傟側偄丅
丂傢傟傢傟偼偡偱偵擔杮恖偺怘擏丒嫑夘椶偺徚旓傪擭楊暿偵悇寁偟丄摿偵嫑偺徚
旓偼拞崅擭憌偱崅偔丄巕嫙傪娷傓庒擭憌偱挊偟偔掅偄偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅乮拲
1乯夁嫀10悢擭偺婜娫偵偮偄偰擭楊暿偺徚旓偺摦偒傪挱傔傞偲丄嫑偺徚旓偼妋偐
偵壛楊偲偲傕偵憹偊傞偑丄巕嫙丒庒偄崰偵嫑傪偁傑傝怘傋側偐偭偨怴偟偄悽戙偼丄
擭傪庢偭偰拞擭憌偵嬤偯偄偰傕埲慜偺拞崅擭憌掱偼怘傋側偄傛偆偱偁偭偨丅偡側
傢偪偐側傝偺掱搙悽戙岠壥傪堷偒偢偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偺報徾傪帩偭偨丅
丂栤戣傪偝傜偵擄偟偔偡傞偺偼丄偙偺10悢擭偺婜娫偵丄慡懱揑側孹岦偲偟偰嫑偺
徚旓偑尭彮偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偙偲偱偁傞丅偡側傢偪梫場偲偟偰擭楊偲悽戙偵
壛偊偰帪戙偺塭嬁偑壛傢偭偰偄傞丅捈姶揑偵3偮偺岠壥傪幆暿丄暘棧偡傞偺偼晄
壜擻偵嬤偄丅
拲侾丗怷岹懠乮1997乯乽奺庬怘擏徚旓偲擭楊乿亀暯惉8擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏
丂丂尋媶帠嬈亁擾抺嶻帠嬈抍丄Lewis, M. A., Mori. H. and Gorman. Wm. D.,
丂乽Estimating Japanese At-Home Consumption of Meats and Seafoods by Age
丂丂Groups乿丄乽愱廋宱嵪妛榑廤乿32姫2崋側偳
丂弌強丗USDA Continuing Survey of Food Intakes by Individuals, 1989-91
丂暷崙偱傕恖岥偺崅楊壔偑恑峴偟偰偄傞丅傕偟摨偠恖偱傕拞崅擭偵側傞偲僐乕儔
偺徚旓偑棊偪僐乕僸乕偵堏傞偲偡傟偽丄2010擭崰偵偼傾儊儕僇慡懱偲偟偰僐乕僸
乕偺徚旓偼憹偊丄懠曽僐乕儔椶偼尭彮偡傞偲梊憐偝傟傞丅
丂偩偑暿偺桳椡側尒曽傕偁傞丅American Demographics偺1994擭12寧崋偵乽偁偲
俀擭偱僋儕儞僩儞乮戝摑椞乯偼50戙傪寎偊傞偑丄斵偼憡曄傢傜偢儅僋僪僫儖僪搣
偱偁傠偆乿偲偺尒弌偟偑嵹偭偰偄傞丅庒偄崰偵僴儞僶乕僈乕偵姷傟恊偟傓偲拞崅
擭偵側偭偰傕偦偺廗暼偼帩偪墇偝傟丄僴儞僶乕僈乕揦偵捠偆偩傠偆偲偄偆偺偱偁
傞丅偙偺尒曽傪愭偺僐乕僸乕偲僐乕儔偺働乕僗偵摉偰偼傔傞偲丄1990擭摉帪20乣
30戙偺恖払偑丄2010擭崰拞崅擭偵払偟偰傕丄僐乕儔堸梡偺暼偼敳偗偢丄偐偮偰偺
拞崅擭幰偲摨偠傛偆偵傕偭傁傜僐乕僸乕傪偨偟側傓偲偄偆偙偲偼側偄偩傠偆丅偩
偲偡傞偲丄慡懱偲偟偰僐乕儔偺徚旓偼憹偊丄僐乕僸乕偺徚旓偼尭傞偩傠偆偲偄偆
寢榑偵側傞丅
丂慜幰偺尒曽偼1990擭摉帪偵娤嶡偝傟偨擭楊暿徚旓偺宆偑丄偙傟偐傜偟偽傜偔偼
曄傢傜側偄偲偡傞棫応偱偁傝丄屻幰偺尒曽偼恖惗偺偁傞帪婜乮嫲傜偔僥傿乕儞僄
僀僕儍乕偺崰乯偵宍惉偝傟偨悽戙摿桳偺堸怘偺廗姷偼丄偦偺屻偺壛楊偵偐偐傢傜
偢帩偪墇偝傟偰偄偔偲偡傞棫応偱偁傞丅
丂偟偐偟忋婰偺扨擭搙尷傝偺摑寁偐傜偼丄擭楊岠壥偑嫮偄偲傒傞傋偒偐丄悽戙岠
壥偑桪惃偱偁傞偲傒傞傋偒偐偼寛傔傜傟側偄丅
丂傢傟傢傟偼偡偱偵擔杮恖偺怘擏丒嫑夘椶偺徚旓傪擭楊暿偵悇寁偟丄摿偵嫑偺徚
旓偼拞崅擭憌偱崅偔丄巕嫙傪娷傓庒擭憌偱挊偟偔掅偄偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅乮拲
1乯夁嫀10悢擭偺婜娫偵偮偄偰擭楊暿偺徚旓偺摦偒傪挱傔傞偲丄嫑偺徚旓偼妋偐
偵壛楊偲偲傕偵憹偊傞偑丄巕嫙丒庒偄崰偵嫑傪偁傑傝怘傋側偐偭偨怴偟偄悽戙偼丄
擭傪庢偭偰拞擭憌偵嬤偯偄偰傕埲慜偺拞崅擭憌掱偼怘傋側偄傛偆偱偁偭偨丅偡側
傢偪偐側傝偺掱搙悽戙岠壥傪堷偒偢偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偺報徾傪帩偭偨丅
丂栤戣傪偝傜偵擄偟偔偡傞偺偼丄偙偺10悢擭偺婜娫偵丄慡懱揑側孹岦偲偟偰嫑偺
徚旓偑尭彮偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偙偲偱偁傞丅偡側傢偪梫場偲偟偰擭楊偲悽戙偵
壛偊偰帪戙偺塭嬁偑壛傢偭偰偄傞丅捈姶揑偵3偮偺岠壥傪幆暿丄暘棧偡傞偺偼晄
壜擻偵嬤偄丅
拲侾丗怷岹懠乮1997乯乽奺庬怘擏徚旓偲擭楊乿亀暯惉8擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏
丂丂尋媶帠嬈亁擾抺嶻帠嬈抍丄Lewis, M. A., Mori. H. and Gorman. Wm. D.,
丂乽Estimating Japanese At-Home Consumption of Meats and Seafoods by Age
丂丂Groups乿丄乽愱廋宱嵪妛榑廤乿32姫2崋側偳
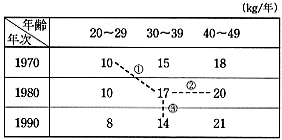 丂傑偢昞拞偺嘆偵偮偄偰丄1970擭偵20戙偺恖払偼10kg丄1980擭偵30戙偵側偭偰17
kg偵側偭偨丅挷嵏偼昁偢偟傕摨堦屄恖傪捛愓偟偰偄傞栿偱偼側偄偑丄斵傜偼1941
擭偐傜1950擭偵弌惗偟丄1950擭偵0乣9嵨婜丄1960擭偵10乣19嵨婜傪夁偟丄偙偺20
悢擭娫偺娫偵嫲傜偔摨偠傛偆側恖惗丄幮夛忋偺宱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偵懏偟偰
偄傞丅17亅10亖7kg偺憹壛偼丄1偮偵偼20戙偐傜30戙偵10嵨憹偊偨壛楊岠壥偲丄擭
戙偑1970擭偐傜1980擭偵10擭宱夁偟偨帪戙岠壥乮偺嵎乯偺2偮偐傜崌惉偝傟偰偄
傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘇偵偮偄偰丄1980擭偵30戙偼17kg丄40戙偼20kg徚旓偟偰偄傞丅偙偺3kg偺嵎偼
30戙偲40戙偺擭楊偵傛傞嵎偩偗偱偼側偄丅1980擭偵40戙偺恖払偼丄1931擭偐傜
1940擭偵弌惗偟丄椺偊偽愴拞丄愴憟捈屻偺婹夓揑惗妶側偳偵偮偄偰丄偦傟埲崀弌
惗偺悽戙偲偼堎側偭偨懱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偱偁傞丅偦偺傛偆側夁嫀偺宱尡偺
堘偄偵傛傞悽戙岠壥偺嵎偑丄弮悎偺擭楊岠壥偺嵎偵壛傢偭偰偄傞偲傒傞傋偒偱偁
傞丅偨偩偟偙偙偱傕椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘊偵偮偄偰丄摨偠30戙偺徚旓傪尒傞偲丄1980擭偐傜1990擭偵偐偗17kg偐傜14kg
偵3kg尭彮偟偰偄傞丅偙傟偼1980擭偐傜1990擭偺10擭娫偵強摼傗壙奿偑曄壔偟偨
側偳偺帪戙偺曄壔偵傛傞傕偺偱偁傞偺偼尵偆傑偱傕側偄偑丄偦傟偩偗偱偼側偄丅
1990擭偵30戙偺恖偨偪偼1951擭偐傜1960擭偵弌惗偟丄僥傿乕儞丒僄僀僕儍乕偺帪
戙偼崅搙惉挿婜偺恀偭捈拞偱丄偦偺慜偺悽戙偲偼壙抣娤側傝廗姷宍惉偵偍偄偰堎
側偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丅廬偭偰3kg偺嵎偼扨偵擭帪偺嵎偩偗偱偼側偔丄偦偆偟
偨悽戙岠壥偺嵎偵傛傞偲偙傠偑彮側偔側偄偲傕峫偊傜傟傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼
暘偐傜側偄丅
丂偝偰昞2偺傛偆側擭楊暿徚旓偺僐僂儂乕僩昞偑丄擭楊嬫暘偱傕墶偵挿偔丄挷嵏
擭師偵娭偟偰傕廲偵傕偭偲挿偔偲傟傟偽丄忋婰偺嘆丄嘇丄嘊偺愢柧偵偍偄偰傕丄
廬棃偺擭楊丄悽戙偍傛傃擭師側偄偟帪戙偺塭嬁傪丄偦傟偧傟検揑偵暘棧偟偲傜偊
傞偙偲偑梕堈偵側傞偲婜懸偝傟傞丅
丂偨偩偟偙偺暘棧偺栤戣偼丄摑寁妛偺悽奅偱偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偍偗傞乽幆暿
栤戣乿偲偟偰媍榑偼巆偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅乮拲2乯偩偑挊幰偨偪偼丄摑寁悢
棟尋媶強偺拞懞棽嫵庼偺奐敪偝傟偨乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖乿偺慜採忦審
傪惀偲偟丄傑偩姰慡偐傜偼墦偄偑堦墳PC梡偵嶌傝忋偘偨僾儘僌儔儉偵傛偭偰丄擭
楊丄悽戙丄帪戙偺3岠壥傪暘棧丄悇寁偟偮偮偁傞丅擾抺嶻嬈怳嫽帠嬈抍偺埾戸偵
傛傝幚巤偟偨暯惉10擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏尋媶帠嬈傪尦偵丄偦偺屻偝傜偵暘愅
傪恑傔偰偄傞丅
丂師愡埲壓偱偄偔偮偐偺抺嶻暔偲擔杮恖偺怘惗妶偺婎杮偱偁傞暷偍傛傃嫑偵偮偄
偰丄暘愅寢壥偺堦晹傪徯夘偟偨偄丅
拲2丗Mason. W. and S. Fienberg, Editars乮1985乯乽Cohort Analysis in Social
丂丂Research : Beyond the Identification Problem乿丄Springer-Verlag丄New York
丂丂側偳嶲徠
丂傑偢昞拞偺嘆偵偮偄偰丄1970擭偵20戙偺恖払偼10kg丄1980擭偵30戙偵側偭偰17
kg偵側偭偨丅挷嵏偼昁偢偟傕摨堦屄恖傪捛愓偟偰偄傞栿偱偼側偄偑丄斵傜偼1941
擭偐傜1950擭偵弌惗偟丄1950擭偵0乣9嵨婜丄1960擭偵10乣19嵨婜傪夁偟丄偙偺20
悢擭娫偺娫偵嫲傜偔摨偠傛偆側恖惗丄幮夛忋偺宱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偵懏偟偰
偄傞丅17亅10亖7kg偺憹壛偼丄1偮偵偼20戙偐傜30戙偵10嵨憹偊偨壛楊岠壥偲丄擭
戙偑1970擭偐傜1980擭偵10擭宱夁偟偨帪戙岠壥乮偺嵎乯偺2偮偐傜崌惉偝傟偰偄
傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘇偵偮偄偰丄1980擭偵30戙偼17kg丄40戙偼20kg徚旓偟偰偄傞丅偙偺3kg偺嵎偼
30戙偲40戙偺擭楊偵傛傞嵎偩偗偱偼側偄丅1980擭偵40戙偺恖払偼丄1931擭偐傜
1940擭偵弌惗偟丄椺偊偽愴拞丄愴憟捈屻偺婹夓揑惗妶側偳偵偮偄偰丄偦傟埲崀弌
惗偺悽戙偲偼堎側偭偨懱尡傪嫟桳偟偰偄傞悽戙偱偁傞丅偦偺傛偆側夁嫀偺宱尡偺
堘偄偵傛傞悽戙岠壥偺嵎偑丄弮悎偺擭楊岠壥偺嵎偵壛傢偭偰偄傞偲傒傞傋偒偱偁
傞丅偨偩偟偙偙偱傕椉幰偺斾廳偼暘偐傜側偄丅
丂嘊偵偮偄偰丄摨偠30戙偺徚旓傪尒傞偲丄1980擭偐傜1990擭偵偐偗17kg偐傜14kg
偵3kg尭彮偟偰偄傞丅偙傟偼1980擭偐傜1990擭偺10擭娫偵強摼傗壙奿偑曄壔偟偨
側偳偺帪戙偺曄壔偵傛傞傕偺偱偁傞偺偼尵偆傑偱傕側偄偑丄偦傟偩偗偱偼側偄丅
1990擭偵30戙偺恖偨偪偼1951擭偐傜1960擭偵弌惗偟丄僥傿乕儞丒僄僀僕儍乕偺帪
戙偼崅搙惉挿婜偺恀偭捈拞偱丄偦偺慜偺悽戙偲偼壙抣娤側傝廗姷宍惉偵偍偄偰堎
側偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丅廬偭偰3kg偺嵎偼扨偵擭帪偺嵎偩偗偱偼側偔丄偦偆偟
偨悽戙岠壥偺嵎偵傛傞偲偙傠偑彮側偔側偄偲傕峫偊傜傟傞丅偨偩偟椉幰偺斾廳偼
暘偐傜側偄丅
丂偝偰昞2偺傛偆側擭楊暿徚旓偺僐僂儂乕僩昞偑丄擭楊嬫暘偱傕墶偵挿偔丄挷嵏
擭師偵娭偟偰傕廲偵傕偭偲挿偔偲傟傟偽丄忋婰偺嘆丄嘇丄嘊偺愢柧偵偍偄偰傕丄
廬棃偺擭楊丄悽戙偍傛傃擭師側偄偟帪戙偺塭嬁傪丄偦傟偧傟検揑偵暘棧偟偲傜偊
傞偙偲偑梕堈偵側傞偲婜懸偝傟傞丅
丂偨偩偟偙偺暘棧偺栤戣偼丄摑寁妛偺悽奅偱偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偍偗傞乽幆暿
栤戣乿偲偟偰媍榑偼巆偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅乮拲2乯偩偑挊幰偨偪偼丄摑寁悢
棟尋媶強偺拞懞棽嫵庼偺奐敪偝傟偨乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖乿偺慜採忦審
傪惀偲偟丄傑偩姰慡偐傜偼墦偄偑堦墳PC梡偵嶌傝忋偘偨僾儘僌儔儉偵傛偭偰丄擭
楊丄悽戙丄帪戙偺3岠壥傪暘棧丄悇寁偟偮偮偁傞丅擾抺嶻嬈怳嫽帠嬈抍偺埾戸偵
傛傝幚巤偟偨暯惉10擭搙抺嶻暔廀梫奐敪挷嵏尋媶帠嬈傪尦偵丄偦偺屻偝傜偵暘愅
傪恑傔偰偄傞丅
丂師愡埲壓偱偄偔偮偐偺抺嶻暔偲擔杮恖偺怘惗妶偺婎杮偱偁傞暷偍傛傃嫑偵偮偄
偰丄暘愅寢壥偺堦晹傪徯夘偟偨偄丅
拲2丗Mason. W. and S. Fienberg, Editars乮1985乯乽Cohort Analysis in Social
丂丂Research : Beyond the Identification Problem乿丄Springer-Verlag丄New York
丂丂側偳嶲徠
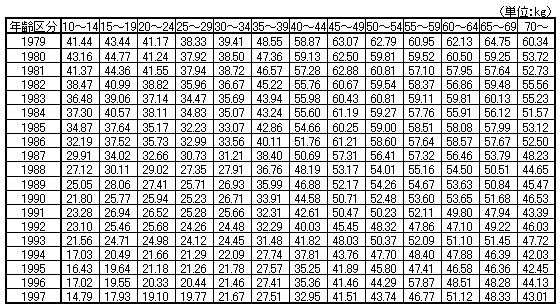 丂偙偺傛偆側曄壔傪擭楊丒悽戙偍傛傃帪戙偺3梫場偵暘偗偰暘愅偡傟偽偳偆側傞
偱偁傠偆偐丅SAS尵岅傪梡偄偨拞懞偺儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖偵傛傞寁應寢
壥偼丄昞4偺傛偆側宍偱嶼弌偝傟傞丅
昞係丂暷偺僐僂儂乕僩暘愅寢壥偺椺
丂偙偺傛偆側曄壔傪擭楊丒悽戙偍傛傃帪戙偺3梫場偵暘偗偰暘愅偡傟偽偳偆側傞
偱偁傠偆偐丅SAS尵岅傪梡偄偨拞懞偺儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖偵傛傞寁應寢
壥偼丄昞4偺傛偆側宍偱嶼弌偝傟傞丅
昞係丂暷偺僐僂儂乕僩暘愅寢壥偺椺
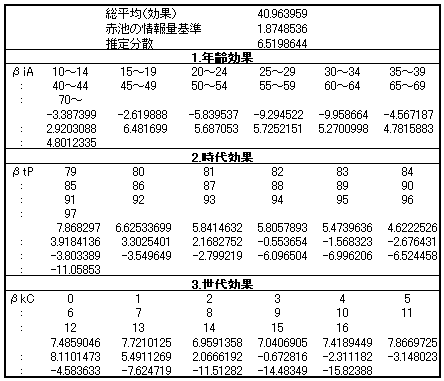 丂偁傞擭師乮 t 擭乯擭偵偍偗傞偁傞擭楊奒媺乮 i 奒媺乯偺徚旓乮兪 i t 乯偼丄19
擭亊13奒媺亖247偺僙儖偵嫟捠偺兝乮憤暯嬒乮岠壥乯乯傪儀乕僗偵丄嫹媊偺擭楊
i 奒媺偵摿桳偺擭楊岠壥丆兝i A 偲丄挷嵏帪 i 擭偵嫟捠偺帪戙岠壥丆兝t P 偑壛傢
傝丄偝傜偵傕偆1崁丄偦傟偧傟偺僙儖乮 t 擭師偵 i 擭楊奒媺偺廤抍乯偑丄偄偮弌
惗偟丄惉恖婜偵払偡傞傑偱偵偦傟偧傟堎側偭偨宱尡傪嫟桳偟攟傢傟偨偱偁傠偆摿
桳偺悽戙岠壥丆兝k C 偑壛傢傞丅偡側傢偪丄
丂兪 i t亖兝亄兝i A 亄兝t P 亄兝k C 亄岆嵎崁乧乮1乯
乮1乯幃偺傛偆偵偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞偲憐掕偡傞丅尰幚偵嬤偯偔偨傔偵偼傕偭
偲暋嶨側儌僨儖傪梡堄偡傋偒偱偁傠偆偑丄寁嶼偼擄偟偔側傝丄岆嵎傕奼戝偡傞嫲
傟偑偁傞丅
丂悽戙傪帵偡斣崋0偐傜16偼曋媂揑側傕偺偱丄0偑挷嵏婜娫偺巒傔偵70嵨埲忋偩偭
偨恖乆丄偡側傢偪1909擭埲慜弌惗偺堦斣屆偄悽戙丄媡偵16偼挷嵏偺嵟嬤擭師偵10
乣14嵨偱偁偭偨恖乆丄偡側傢偪1985乣89擭偵弌惗偟偨悽戙傪帵偟偰偄傞丅昞4偺
悇寁抣傪巊偭偰嬶懱揑側寁嶼傪帋傒偰傒傛偆丅
寁嶼嘆
丂1984擭偵55乣59嵨偩偭偨恖乆偼1925乣29擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋4偵摉偨傞丅偙
偺廤抍偺棟榑忋偺徚旓偼乮1乯幃偐傜丄
丂兝亄兝A55亅59亄兝P'84亄兝C4 亖40.96亄5.73亄4.62亄7.42亖58.73kg偲悇寁偝傟
傞丅偪側傒偵昞3偺奩摉僙儖偺抣偼57.76kg偱偁傞丅
寁嶼嘇
丂1994擭偵25乣29嵨偩偭偨恖乆偼1965乣69擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋12偱偁傞丅摨條
偵乮1乯幃偐傜偙偺廤抍偺棟榑抣偼丄
丂兝亄兝A25亅29亄兝P'94亄兝C12 亖40.96亅9.29亅6.10亅4.58亖20.99kg丅偙傟偵
懳墳偡傞昞3偺抣偼丄21.29kg偱偁傞丅
丂昞係偺暷偵偮偄偰偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥傪娙扨側恾偵偡傞偲恾1偺乮俙乯乣
乮俠乯偺傛偆偵側傞丅乮俙乯偑擭楊岠壥兝i A 丄乮俛乯偑悽戙岠壥兝k C 丄乮俠乯
偑擭師側偄偟帪戙岠壥兝t P 傪偦傟偧傟帵偟偰偄傞丅偄偢傟偺岠壥傕僛儘偺慄傪
拞怱偵嵍塃偵偽傜偮偒丄廤寁偡傞偲嵎偟堷偒僛儘偵側傞傛偆偵側偭偰偄傞丅乮儼
兝i A 亖0丄儼兝k C 亖0丄儼兝t P 亖0乯丅
仦恾侾丗暷偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖40.96kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢憤暯嬒乮岠壥乯偑40.96kg偱偁傞丅
丂乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯偼丄30戙偺屻敿40戙偺慜敿傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘
偐傟傞丅嫹媊偺擭楊岠壥偲偟偰40戙埲忋偼憤暯嬒40.96kg偵亄5.0kg慜屻偑壛傢傞丅
偦傟傛傝庒偄擭楊憌偱偼媡偵仯5.0kg偑壛傢傞丅偡側傢偪慜幰偼46kg慜屻丄屻幰偼
36kg慜屻偵側傝丄拞崅偲庒擭偺椉奒憌娫偱10kg慜屻偺嵎偑奐偔丅摿偵20戙屻敿偲
30戙慜敿偼仯9kg嫮偺擭楊岠壥傪帵偟乮40.96亅9佮32kg乯丄偝傜偵暷傪怘傋側偄擭
楊奒憌偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅偨偩偟偙傟傜偺奒憌偑暷徚旓偺憤検偑偦傟傎偳掅偄
偐偳偆偐偼暘偐傜側偄丅嫲傜偔拞崅擭憌偵斾傋丄摿偵彈惈偺応崌丄奜怘偺婡夛偑
懡偔丄偦偺暘暷偺壠寁徚旓偑彮側偄偲偄偆帠忣偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅乮拲俁乯
傢傟傢傟偺僐僂儂乕僩暘愅偼偦偺拞恎傑偱偼柧傜偐偵偟偰偔傟側偄丅
丂師偵乮俛乯偺悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰丄弌惗偑愴拞乮1940乣44擭乯乣愴憟捈屻
乮1945乣49擭乯傪嫬偵丄屆偄曽偼僾儔僗丄怴偟偄曽偼儅僀僫僗偲柧妋側嵎堎偑帵
偝傟偰偄傞丅摿偵1935乣39擭埲慜偵弌惗偟偨悽戙乮1995擭尰嵼50戙屻敿傛傝忋乯
偼丄乮憤暯嬒40.96kg偵壛偊傞偵乯亄7kg慜屻丄偙傟偵懳偟1955乣59擭弌惗偺悽戙
偼仯2kg丄偝傜偵怴偟偄悽戙偵側傞傎偳晧偺抣偼壛懍搙揑偵戝偒偔側傞丅崅搙惉
挿婜埲崀丄摿偵1975乣79擭弌惗偺悽戙偼仯12kg丄1980乣85擭偺偦傟偼仯15kg庛偲
堦憌戝偒側晧偺岠壥傪帩偭偰偄傞丅懎側尵梩偱昞尰偡傟偽丄怴偟偄悽戙掱乽暷棧
傟乿偺孹岦偑尠挊偱偁傞丅
丂偙傟傜偺悽戙傕傗偑偰擭傪庢傝丄椺偊偽2020擭戙偵偼40嵨埲忋偵側傞丅恾1偺
乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯傪偨偳偭偰仯5kg偐傜亄5kg傊10kg慜屻憹偊傞偱偁傠偆偑丄
偦傕偦傕僗僞乕僩偺悽戙摿桳偺抣偑丄椺偊偽1995擭偵40戙屻敿偩偭偨恖払偵斾傋丄
亄2亅乮亅14乯亖16kg慜屻掅偄"僴儞僨傿"傪堷偒偢偭偰偄偔偙偲偵側傞丅偲偡傞偲丄
2020擭崰偺40戙屻敿偺恖払偺徚旓偼丄崱屻偺帪戙偺摦偒傪柍帇偡傟偽丄1995擭偺
偦偺奒憌偺徚旓検丄42kg慜屻乮昞3乯傛傝16kg掱搙彮側偄25kg慜屻偵側傞偺偱偼側
偄偐偲梊憐偝傟傞丅擭楊丒悽戙岠壥偺恾偼丄埲忋偺傛偆偵彨棃梊應偵傕棙梡偱偒
傞丅
丂1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰暷偺1恖摉偨傝壠寁徚旓偼45.16kg偐傜30.26kg傊尭彮
偟偨偑丄偙偺婜娫偵挷嵏壠寁偺悽懷堳偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偼尠挊偵曄壔偟偰偄
傞丅偪側傒偵悽懷庡偑60嵨埲忋偺悽懷偼1979擭偵8,000屗偺偆偪1,072屗偩偭偨偺
偑丄1997擭偵偼摨偠偔2,442屗偵憹偊偰偄傞丅偡側傢偪恖岥偺崅楊壔偑恑傫偱偄傞丅
摨帪偵1979擭偵60嵨側偄偟70嵨埲忋偩偭偨屆偄悽戙丄偡側傢偪悽戙斣崋0乣2偺懡
偔偼徚偊嫀傞偐挊偟偔妶摦偑撦傝丄1980埲崀弌惗偺悽戙偑怴偟偔壛傢偭偰偒偨丅
偙偺婜娫偵偍偗傞憡懳揑側暷徚旓偺曄壔偵偦偺傛偆側崅楊壔偲悽戙峔惉偺曄壔偑
嶌梡偟偰偄傞偱偁傠偆偙偲偵媈栤偺梋抧偼側偄丅
丂偦偺傛偆側擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偑丄恾1偺乮俠乯偵
帵偝傟偰偄傞丅1979乣81擭崰偼憤暯嬒40.96偵壛偊偰亄7kg慜屻偩偭偨偺偑丄1987
乣89擭偵亇0丄1995乣97擭偵偼仯7kg慜屻偵傎傏堦娧偟偰尭彮偟懕偗丄婜娫傪捠偟
偰寁14kg慜屻尭彮偟偰偄傞丅偙偺抣偼忋弎偺1恖摉偨傝扨弮暯嬒抣偺尭彮偲傎傏
堦抳偡傞偑丄嫲傜偔恖岥偺崅楊壔偺塭嬁偼偐側傝僾儔僗偺曽岦偵摥偄偨偑丄悽戙
岎戙偺塭嬁偼儅僀僫僗曽岦偱丄偨傑偨傑憡嶦偟崌偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傟傜2
偮偺岠壥偺嶌梡偼丄昳栚偵傛偭偰堎側傝丄昁偢偟傕暷偲摨偠偱偼側偄偺偼屻偱尒
傞偲偍傝偱偁傞丅
拲俁丗椺偊偽40戙偍傛傃50戙偼梉怘偺奜怘斾棪偑12.2偍傛傃10.5亾偵懳偟丄20乣
丂24丄25乣29偍傛傃30戙偼偦傟偧傟20.7丄18.4偍傛傃13.6亾偱偁偭偨乮岤惗徣
丂乽崙柉塰梴偺尰忬丒暯惉5擭挷嵏乿傛傝乯丅
丂偁傞擭師乮 t 擭乯擭偵偍偗傞偁傞擭楊奒媺乮 i 奒媺乯偺徚旓乮兪 i t 乯偼丄19
擭亊13奒媺亖247偺僙儖偵嫟捠偺兝乮憤暯嬒乮岠壥乯乯傪儀乕僗偵丄嫹媊偺擭楊
i 奒媺偵摿桳偺擭楊岠壥丆兝i A 偲丄挷嵏帪 i 擭偵嫟捠偺帪戙岠壥丆兝t P 偑壛傢
傝丄偝傜偵傕偆1崁丄偦傟偧傟偺僙儖乮 t 擭師偵 i 擭楊奒媺偺廤抍乯偑丄偄偮弌
惗偟丄惉恖婜偵払偡傞傑偱偵偦傟偧傟堎側偭偨宱尡傪嫟桳偟攟傢傟偨偱偁傠偆摿
桳偺悽戙岠壥丆兝k C 偑壛傢傞丅偡側傢偪丄
丂兪 i t亖兝亄兝i A 亄兝t P 亄兝k C 亄岆嵎崁乧乮1乯
乮1乯幃偺傛偆偵偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞偲憐掕偡傞丅尰幚偵嬤偯偔偨傔偵偼傕偭
偲暋嶨側儌僨儖傪梡堄偡傋偒偱偁傠偆偑丄寁嶼偼擄偟偔側傝丄岆嵎傕奼戝偡傞嫲
傟偑偁傞丅
丂悽戙傪帵偡斣崋0偐傜16偼曋媂揑側傕偺偱丄0偑挷嵏婜娫偺巒傔偵70嵨埲忋偩偭
偨恖乆丄偡側傢偪1909擭埲慜弌惗偺堦斣屆偄悽戙丄媡偵16偼挷嵏偺嵟嬤擭師偵10
乣14嵨偱偁偭偨恖乆丄偡側傢偪1985乣89擭偵弌惗偟偨悽戙傪帵偟偰偄傞丅昞4偺
悇寁抣傪巊偭偰嬶懱揑側寁嶼傪帋傒偰傒傛偆丅
寁嶼嘆
丂1984擭偵55乣59嵨偩偭偨恖乆偼1925乣29擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋4偵摉偨傞丅偙
偺廤抍偺棟榑忋偺徚旓偼乮1乯幃偐傜丄
丂兝亄兝A55亅59亄兝P'84亄兝C4 亖40.96亄5.73亄4.62亄7.42亖58.73kg偲悇寁偝傟
傞丅偪側傒偵昞3偺奩摉僙儖偺抣偼57.76kg偱偁傞丅
寁嶼嘇
丂1994擭偵25乣29嵨偩偭偨恖乆偼1965乣69擭偵弌惗偟丄悽戙斣崋12偱偁傞丅摨條
偵乮1乯幃偐傜偙偺廤抍偺棟榑抣偼丄
丂兝亄兝A25亅29亄兝P'94亄兝C12 亖40.96亅9.29亅6.10亅4.58亖20.99kg丅偙傟偵
懳墳偡傞昞3偺抣偼丄21.29kg偱偁傞丅
丂昞係偺暷偵偮偄偰偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥傪娙扨側恾偵偡傞偲恾1偺乮俙乯乣
乮俠乯偺傛偆偵側傞丅乮俙乯偑擭楊岠壥兝i A 丄乮俛乯偑悽戙岠壥兝k C 丄乮俠乯
偑擭師側偄偟帪戙岠壥兝t P 傪偦傟偧傟帵偟偰偄傞丅偄偢傟偺岠壥傕僛儘偺慄傪
拞怱偵嵍塃偵偽傜偮偒丄廤寁偡傞偲嵎偟堷偒僛儘偵側傞傛偆偵側偭偰偄傞丅乮儼
兝i A 亖0丄儼兝k C 亖0丄儼兝t P 亖0乯丅
仦恾侾丗暷偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖40.96kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢憤暯嬒乮岠壥乯偑40.96kg偱偁傞丅
丂乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯偼丄30戙偺屻敿40戙偺慜敿傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘
偐傟傞丅嫹媊偺擭楊岠壥偲偟偰40戙埲忋偼憤暯嬒40.96kg偵亄5.0kg慜屻偑壛傢傞丅
偦傟傛傝庒偄擭楊憌偱偼媡偵仯5.0kg偑壛傢傞丅偡側傢偪慜幰偼46kg慜屻丄屻幰偼
36kg慜屻偵側傝丄拞崅偲庒擭偺椉奒憌娫偱10kg慜屻偺嵎偑奐偔丅摿偵20戙屻敿偲
30戙慜敿偼仯9kg嫮偺擭楊岠壥傪帵偟乮40.96亅9佮32kg乯丄偝傜偵暷傪怘傋側偄擭
楊奒憌偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅偨偩偟偙傟傜偺奒憌偑暷徚旓偺憤検偑偦傟傎偳掅偄
偐偳偆偐偼暘偐傜側偄丅嫲傜偔拞崅擭憌偵斾傋丄摿偵彈惈偺応崌丄奜怘偺婡夛偑
懡偔丄偦偺暘暷偺壠寁徚旓偑彮側偄偲偄偆帠忣偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅乮拲俁乯
傢傟傢傟偺僐僂儂乕僩暘愅偼偦偺拞恎傑偱偼柧傜偐偵偟偰偔傟側偄丅
丂師偵乮俛乯偺悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰丄弌惗偑愴拞乮1940乣44擭乯乣愴憟捈屻
乮1945乣49擭乯傪嫬偵丄屆偄曽偼僾儔僗丄怴偟偄曽偼儅僀僫僗偲柧妋側嵎堎偑帵
偝傟偰偄傞丅摿偵1935乣39擭埲慜偵弌惗偟偨悽戙乮1995擭尰嵼50戙屻敿傛傝忋乯
偼丄乮憤暯嬒40.96kg偵壛偊傞偵乯亄7kg慜屻丄偙傟偵懳偟1955乣59擭弌惗偺悽戙
偼仯2kg丄偝傜偵怴偟偄悽戙偵側傞傎偳晧偺抣偼壛懍搙揑偵戝偒偔側傞丅崅搙惉
挿婜埲崀丄摿偵1975乣79擭弌惗偺悽戙偼仯12kg丄1980乣85擭偺偦傟偼仯15kg庛偲
堦憌戝偒側晧偺岠壥傪帩偭偰偄傞丅懎側尵梩偱昞尰偡傟偽丄怴偟偄悽戙掱乽暷棧
傟乿偺孹岦偑尠挊偱偁傞丅
丂偙傟傜偺悽戙傕傗偑偰擭傪庢傝丄椺偊偽2020擭戙偵偼40嵨埲忋偵側傞丅恾1偺
乮俙乯偺擭楊乮岠壥乯傪偨偳偭偰仯5kg偐傜亄5kg傊10kg慜屻憹偊傞偱偁傠偆偑丄
偦傕偦傕僗僞乕僩偺悽戙摿桳偺抣偑丄椺偊偽1995擭偵40戙屻敿偩偭偨恖払偵斾傋丄
亄2亅乮亅14乯亖16kg慜屻掅偄"僴儞僨傿"傪堷偒偢偭偰偄偔偙偲偵側傞丅偲偡傞偲丄
2020擭崰偺40戙屻敿偺恖払偺徚旓偼丄崱屻偺帪戙偺摦偒傪柍帇偡傟偽丄1995擭偺
偦偺奒憌偺徚旓検丄42kg慜屻乮昞3乯傛傝16kg掱搙彮側偄25kg慜屻偵側傞偺偱偼側
偄偐偲梊憐偝傟傞丅擭楊丒悽戙岠壥偺恾偼丄埲忋偺傛偆偵彨棃梊應偵傕棙梡偱偒
傞丅
丂1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰暷偺1恖摉偨傝壠寁徚旓偼45.16kg偐傜30.26kg傊尭彮
偟偨偑丄偙偺婜娫偵挷嵏壠寁偺悽懷堳偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偼尠挊偵曄壔偟偰偄
傞丅偪側傒偵悽懷庡偑60嵨埲忋偺悽懷偼1979擭偵8,000屗偺偆偪1,072屗偩偭偨偺
偑丄1997擭偵偼摨偠偔2,442屗偵憹偊偰偄傞丅偡側傢偪恖岥偺崅楊壔偑恑傫偱偄傞丅
摨帪偵1979擭偵60嵨側偄偟70嵨埲忋偩偭偨屆偄悽戙丄偡側傢偪悽戙斣崋0乣2偺懡
偔偼徚偊嫀傞偐挊偟偔妶摦偑撦傝丄1980埲崀弌惗偺悽戙偑怴偟偔壛傢偭偰偒偨丅
偙偺婜娫偵偍偗傞憡懳揑側暷徚旓偺曄壔偵偦偺傛偆側崅楊壔偲悽戙峔惉偺曄壔偑
嶌梡偟偰偄傞偱偁傠偆偙偲偵媈栤偺梋抧偼側偄丅
丂偦偺傛偆側擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偑丄恾1偺乮俠乯偵
帵偝傟偰偄傞丅1979乣81擭崰偼憤暯嬒40.96偵壛偊偰亄7kg慜屻偩偭偨偺偑丄1987
乣89擭偵亇0丄1995乣97擭偵偼仯7kg慜屻偵傎傏堦娧偟偰尭彮偟懕偗丄婜娫傪捠偟
偰寁14kg慜屻尭彮偟偰偄傞丅偙偺抣偼忋弎偺1恖摉偨傝扨弮暯嬒抣偺尭彮偲傎傏
堦抳偡傞偑丄嫲傜偔恖岥偺崅楊壔偺塭嬁偼偐側傝僾儔僗偺曽岦偵摥偄偨偑丄悽戙
岎戙偺塭嬁偼儅僀僫僗曽岦偱丄偨傑偨傑憡嶦偟崌偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傟傜2
偮偺岠壥偺嶌梡偼丄昳栚偵傛偭偰堎側傝丄昁偢偟傕暷偲摨偠偱偼側偄偺偼屻偱尒
傞偲偍傝偱偁傞丅
拲俁丗椺偊偽40戙偍傛傃50戙偼梉怘偺奜怘斾棪偑12.2偍傛傃10.5亾偵懳偟丄20乣
丂24丄25乣29偍傛傃30戙偼偦傟偧傟20.7丄18.4偍傛傃13.6亾偱偁偭偨乮岤惗徣
丂乽崙柉塰梴偺尰忬丒暯惉5擭挷嵏乿傛傝乯丅
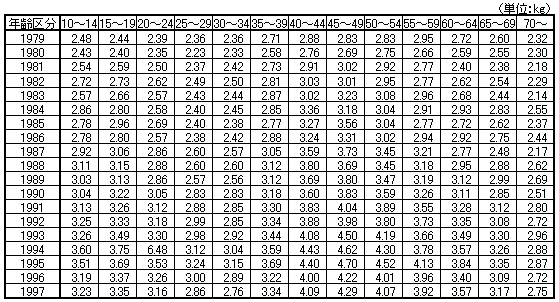 丂昞俆偺1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰偺悽懷堳偺擭楊奒媺暿偺徚旓検乮娫愙悇寁乯
偺僨乕僞傪僐僂儂乕僩偺暘愅偵偐偗傞偲丄恾2偺傛偆偵側傞丅
仦恾俀丗媿擏偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖3.12kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄愭偺暷偺応崌偲摨偠傛偆偵30戙屻敿偲40戙慜敿
傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘偐傟傞丅拞崅擭憌偼憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵壛偊傞
偵亄0.4乣0.5kg丄懠曽10戙偺枹惉擭憌傪娷傒庒擭憌偼仯0.5kg慜屻偱丄暷偺応崌摨
條摿偵20戙屻敿偲30戙慜敿偼晧偺抣偑戝偒偔丄仯0.7kg傪帵偡丅嫲傜偔奜怘婡夛
偲娭學偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂偦傟偵偟偰傕擭楊岠壥偑丄庒擭憌偱憤暯嬒偺15乣20亾偵憡摉偡傞儅僀僫僗偲弌
傞偙偲偵婏堎偺擮傪姶偢傞撉幰偑偍傜傟傞偐傕偟傟側偄丅擾嬈憤崌尋媶強偺愇嫶
婌旤巕巵偑乽壠寁挷嵏乿偺屄昜傪巊偭偰峴偭偨暘愅寢壥偐傜傕丄慡崙揑偵丄庒擭
憌偺媿擏徚旓偑拞崅擭憌偺悈弨偵嬤偯偔偺偼桝擖帺桼壔埲崀偺偙偲偱丄偦傟埲慜
偼庒偄憌偼撠擏偵孹幬偟偰偄偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅乮拲4乯杮峞偵偼嵹
偣偰偄側偄偑昅幰偺僐僂儂乕僩暘愅偱傕丄撠擏偺応崌庒擭憌丄摿偵10戙偺擭楊岠
壥偼僾儔僗偵悇掕偝傟偰偄傞丅
丂悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰偼暷偺応崌偲慡偔懳徠揑偱偁傞丅偡側傢偪丄1935乣39擭
埲慜弌惗偺屆偄悽戙偼丄憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟15乣20亾偺儅僀僫僗丄懠曽
1945乣49擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄憤暯嬒偵懳偟10亾慜屻偺僾儔僗偺岠壥傪帵
偡丅摿偵1970擭埲崀弌惗偺悽戙偼15亾偺僾儔僗偺岠壥傪帩偭偰偄傞偲悇掕偝傟傞丅
丂1995擭崰20丄30戙偩偭偨恖乆偑2020擭戙偵40丄50戙偵側傟偽丄恾2偺乮俙乯偺
擭楊岠壥傪偨偳偭偰徚旓偼1.0kg掱搙憹偊傞偩傠偆丅懠曽1995擭摉帪40丄50戙偩
偭偨悽戙偵斾傋丄悽戙岠壥偵娭偟0.5乣0.6kg懡偄偐傜丄崱屻偺帪戙岠壥傪峫偊側
偔偲傕丄偐傟傜偺徚旓偼尰嵼偺拞崅擭憌傛傝憡摉掱搙懡偔側傞偺偼娫堘偄側偄丅
丂恖岥偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偺曄壔偵傛傞塭嬁傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙乮岠壥乯偑
恾2偺乮俠乯偵帵偝傟偰偄傞丅擭乆偺墯撌偼偁傞偑丄1979乣81擭摉帪偺仯0.4kg偐
傜1989擭偵僛儘丄1995擭偵亄0.55偲憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟偰慡婜娫偱30亾
嫮偺憹壛傪帵偟偰偄傞丅1996擭偵0.25偵棊偪傞偑丄偙傟偼椺偺俷157帠審傗嫸媿
昦憶偓偵傛傞堦帪揑側棊偪崬傒傪偁傜傢偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂悽懷堳1恖摉偨傝偺扨弮暯嬒偼丄1979擭偺2.46kg偐傜1995擭偺3.61kg傊46.7亾憹
壛偟偨丅偦偺婜娫偺恖岥偺榁楊壔偵傛傞塭嬁乮偙傟偼僾儔僗乯偲丄偝傜偵廳梫側
偺偼1980擭摉帪60丄70戙埲忋偩偭偨屆偄悽戙偑師戞偵徚偊丄摉帪梒帣丄10戙偩偭
偨怴偟偄悽戙偑壛傢偭偨偙偲偵傛傞塭嬁偑嶌梡偟偰偄傞丅偙傟傜2偮偺岠壥傪彍
嫀偟偨偺偑忋婰偺弮悎偺擭戙岠壥丄栺30亾憹偱偁傞丅偙偺揰傪峫椂偣偢偵枹壛岺
偺僨乕僞偱帪宯楍偺夞婣暘愅傪偡傞偲丄廀梫抏椡惈偑夁戝偵悇寁偝傟傞嫲傟偑偁
傞丅
拲係丗愇嫶婌旤巕乮1998乯乽桝擖帺桼壔慜屻偵偍偗傞媿擏偺壠寁徚旓峔憿曄壔乿
丂丂擾嬈憤崌尋媶52姫4崋丄曗榑丅傑偨拞懞偺儀僀僘宆儌僨儖偵偮偄偰偼丄拞懞
丂丂棽乮1982乯乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖亅昗弨僐僂儂乕僩昞傊偺揔梡亅乿
丂丂摑寁悢棟尋媶曬29姫2崋丄Nakamura. T.乮1986乯乽Bayesiyan Cohort Models
丂丂for General Cohort Table Analyses乿Ann, Inst. Statist. Math., Vol.38,
丂 Part B, Tokyo 側偳
乮2乯慛嫑
丂擭楊岠壥偲悽戙岠壥偺宍偼丄愭偵徻弎偟偨暷偵傛偔帡偰偄傞丅擭楊岠壥偲偟偰
40戙慜敿傪嫬偵庒偄憌偑儅僀僫僗丄擭攝憌偑僾儔僗偱偁傞丅傑偨悽戙揑偵丄1950
擭崰傛傝埲慜偵弌惗偟偨悽戙偼僾儔僗丄偦傟埲崀弌惗偺怴偟偄悽懷偼丄怴偟偄掱
椵恑揑偵儅僀僫僗偺抣傪帵偟偰偄傞丅庒偄恖偲偄偆傛傝怴偟偄悽戙偺乽嫑棧傟乿
偑媫懍偵恑傫偱偄傞傜偟偄偙偲偑摑寁揑偵棤晅偗傜傟偨偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅
昞俇丂慛嫑偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
丂昞俆偺1979擭偐傜1997擭偵偐偗偰偺悽懷堳偺擭楊奒媺暿偺徚旓検乮娫愙悇寁乯
偺僨乕僞傪僐僂儂乕僩偺暘愅偵偐偗傞偲丄恾2偺傛偆偵側傞丅
仦恾俀丗媿擏偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖3.12kg乯仦
乮A乯擭楊
乮B乯悽戙
乮C乯擭戙
丂傑偢擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄愭偺暷偺応崌偲摨偠傛偆偵30戙屻敿偲40戙慜敿
傪嫬偵僾儔僗偲儅僀僫僗偵暘偐傟傞丅拞崅擭憌偼憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵壛偊傞
偵亄0.4乣0.5kg丄懠曽10戙偺枹惉擭憌傪娷傒庒擭憌偼仯0.5kg慜屻偱丄暷偺応崌摨
條摿偵20戙屻敿偲30戙慜敿偼晧偺抣偑戝偒偔丄仯0.7kg傪帵偡丅嫲傜偔奜怘婡夛
偲娭學偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂偦傟偵偟偰傕擭楊岠壥偑丄庒擭憌偱憤暯嬒偺15乣20亾偵憡摉偡傞儅僀僫僗偲弌
傞偙偲偵婏堎偺擮傪姶偢傞撉幰偑偍傜傟傞偐傕偟傟側偄丅擾嬈憤崌尋媶強偺愇嫶
婌旤巕巵偑乽壠寁挷嵏乿偺屄昜傪巊偭偰峴偭偨暘愅寢壥偐傜傕丄慡崙揑偵丄庒擭
憌偺媿擏徚旓偑拞崅擭憌偺悈弨偵嬤偯偔偺偼桝擖帺桼壔埲崀偺偙偲偱丄偦傟埲慜
偼庒偄憌偼撠擏偵孹幬偟偰偄偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅乮拲4乯杮峞偵偼嵹
偣偰偄側偄偑昅幰偺僐僂儂乕僩暘愅偱傕丄撠擏偺応崌庒擭憌丄摿偵10戙偺擭楊岠
壥偼僾儔僗偵悇掕偝傟偰偄傞丅
丂悽戙乮岠壥乯偵偮偄偰偼暷偺応崌偲慡偔懳徠揑偱偁傞丅偡側傢偪丄1935乣39擭
埲慜弌惗偺屆偄悽戙偼丄憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟15乣20亾偺儅僀僫僗丄懠曽
1945乣49擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄憤暯嬒偵懳偟10亾慜屻偺僾儔僗偺岠壥傪帵
偡丅摿偵1970擭埲崀弌惗偺悽戙偼15亾偺僾儔僗偺岠壥傪帩偭偰偄傞偲悇掕偝傟傞丅
丂1995擭崰20丄30戙偩偭偨恖乆偑2020擭戙偵40丄50戙偵側傟偽丄恾2偺乮俙乯偺
擭楊岠壥傪偨偳偭偰徚旓偼1.0kg掱搙憹偊傞偩傠偆丅懠曽1995擭摉帪40丄50戙偩
偭偨悽戙偵斾傋丄悽戙岠壥偵娭偟0.5乣0.6kg懡偄偐傜丄崱屻偺帪戙岠壥傪峫偊側
偔偲傕丄偐傟傜偺徚旓偼尰嵼偺拞崅擭憌傛傝憡摉掱搙懡偔側傞偺偼娫堘偄側偄丅
丂恖岥偺擭楊偍傛傃悽戙峔惉偺曄壔偵傛傞塭嬁傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙乮岠壥乯偑
恾2偺乮俠乯偵帵偝傟偰偄傞丅擭乆偺墯撌偼偁傞偑丄1979乣81擭摉帪偺仯0.4kg偐
傜1989擭偵僛儘丄1995擭偵亄0.55偲憤暯嬒乮岠壥乯3.12kg偵懳偟偰慡婜娫偱30亾
嫮偺憹壛傪帵偟偰偄傞丅1996擭偵0.25偵棊偪傞偑丄偙傟偼椺偺俷157帠審傗嫸媿
昦憶偓偵傛傞堦帪揑側棊偪崬傒傪偁傜傢偟偰偄傞偺偱偁傠偆丅
丂悽懷堳1恖摉偨傝偺扨弮暯嬒偼丄1979擭偺2.46kg偐傜1995擭偺3.61kg傊46.7亾憹
壛偟偨丅偦偺婜娫偺恖岥偺榁楊壔偵傛傞塭嬁乮偙傟偼僾儔僗乯偲丄偝傜偵廳梫側
偺偼1980擭摉帪60丄70戙埲忋偩偭偨屆偄悽戙偑師戞偵徚偊丄摉帪梒帣丄10戙偩偭
偨怴偟偄悽戙偑壛傢偭偨偙偲偵傛傞塭嬁偑嶌梡偟偰偄傞丅偙傟傜2偮偺岠壥傪彍
嫀偟偨偺偑忋婰偺弮悎偺擭戙岠壥丄栺30亾憹偱偁傞丅偙偺揰傪峫椂偣偢偵枹壛岺
偺僨乕僞偱帪宯楍偺夞婣暘愅傪偡傞偲丄廀梫抏椡惈偑夁戝偵悇寁偝傟傞嫲傟偑偁
傞丅
拲係丗愇嫶婌旤巕乮1998乯乽桝擖帺桼壔慜屻偵偍偗傞媿擏偺壠寁徚旓峔憿曄壔乿
丂丂擾嬈憤崌尋媶52姫4崋丄曗榑丅傑偨拞懞偺儀僀僘宆儌僨儖偵偮偄偰偼丄拞懞
丂丂棽乮1982乯乽儀僀僘宆僐僂儂乕僩丒儌僨儖亅昗弨僐僂儂乕僩昞傊偺揔梡亅乿
丂丂摑寁悢棟尋媶曬29姫2崋丄Nakamura. T.乮1986乯乽Bayesiyan Cohort Models
丂丂for General Cohort Table Analyses乿Ann, Inst. Statist. Math., Vol.38,
丂 Part B, Tokyo 側偳
乮2乯慛嫑
丂擭楊岠壥偲悽戙岠壥偺宍偼丄愭偵徻弎偟偨暷偵傛偔帡偰偄傞丅擭楊岠壥偲偟偰
40戙慜敿傪嫬偵庒偄憌偑儅僀僫僗丄擭攝憌偑僾儔僗偱偁傞丅傑偨悽戙揑偵丄1950
擭崰傛傝埲慜偵弌惗偟偨悽戙偼僾儔僗丄偦傟埲崀弌惗偺怴偟偄悽懷偼丄怴偟偄掱
椵恑揑偵儅僀僫僗偺抣傪帵偟偰偄傞丅庒偄恖偲偄偆傛傝怴偟偄悽戙偺乽嫑棧傟乿
偑媫懍偵恑傫偱偄傞傜偟偄偙偲偑摑寁揑偵棤晅偗傜傟偨偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅
昞俇丂慛嫑偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
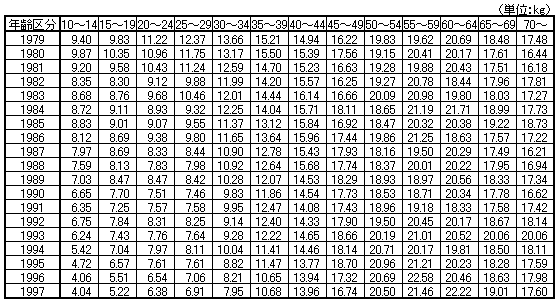 丂悽懷堳1恖摉偨傝偺暯嬒徚旓検偼1979擭偺14.57kg偐傜1997擭偺13.64kg傊丄栺7
亾尭彮偟偰偄傞偑丄擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偼丄恾3偺
乮俠乯偵傒傞傛偆偵僛儘偺慄傪拞怱偵偽傜偮偒丄暷偺傛偆偵堦娧偟偨尭彮孹岦偼
帵偟偰偄側偄丅
仦恾俁丗慛嫑偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖13.79kg乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
乮3乯堸梡媿擕
丂昞7偺擭楊奒媺暿徚旓偺悇堏傪傒傞偲丄1980擭崰偼梒帣偐傜30戙慜敿偔傜偄傑
偱偺憌偑栺30r庛丄偦傟傛傝忋偺憌偼21乣24r偔傜偄偱偁偭偨丅偦偺屻丄梒丄彫帣
偺徚旓偼孹岦揑偵傎偲傫偳曄傢傜偢丄僥傿乕儞僄僀僕儍乕偼旝憹丄20戙偲30戙慜
敿偼傎偲傫偳墶偽偄偱偁偭偨偺偵懳偟丄30戙屻敿埲忋憌偱尠挊偵憹偊偰偄傞丅摿
偵50戙屻敿偐傜偺崅楊憌偵偍偄偰偼丄傎傏攞憹偵嬤偄怢傃傪傒偣偰偄傞丅
昞俈丂堸梡媿擕偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
丂悽懷堳1恖摉偨傝偺暯嬒徚旓検偼1979擭偺14.57kg偐傜1997擭偺13.64kg傊丄栺7
亾尭彮偟偰偄傞偑丄擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨弮悎偺擭戙岠壥偼丄恾3偺
乮俠乯偵傒傞傛偆偵僛儘偺慄傪拞怱偵偽傜偮偒丄暷偺傛偆偵堦娧偟偨尭彮孹岦偼
帵偟偰偄側偄丅
仦恾俁丗慛嫑偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖13.79kg乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
乮3乯堸梡媿擕
丂昞7偺擭楊奒媺暿徚旓偺悇堏傪傒傞偲丄1980擭崰偼梒帣偐傜30戙慜敿偔傜偄傑
偱偺憌偑栺30r庛丄偦傟傛傝忋偺憌偼21乣24r偔傜偄偱偁偭偨丅偦偺屻丄梒丄彫帣
偺徚旓偼孹岦揑偵傎偲傫偳曄傢傜偢丄僥傿乕儞僄僀僕儍乕偼旝憹丄20戙偲30戙慜
敿偼傎偲傫偳墶偽偄偱偁偭偨偺偵懳偟丄30戙屻敿埲忋憌偱尠挊偵憹偊偰偄傞丅摿
偵50戙屻敿偐傜偺崅楊憌偵偍偄偰偼丄傎傏攞憹偵嬤偄怢傃傪傒偣偰偄傞丅
昞俈丂堸梡媿擕偺屄恖擭楊奒媺暿壠寁徚旓検偺悇寁抣乮1979乣1997乯
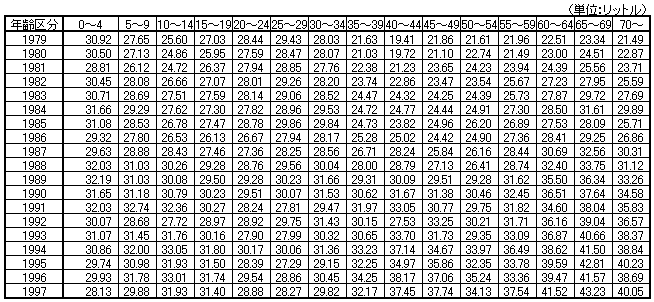 丂偙傟傜偺悢抣傪儀僀僘宆僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞偲丄恾4偺傛偆側岠壥偑嶼弌
偝傟傞丅堸梡媿擕偵偮偄偰丄堦惗偵傢偨傞堸梡姷廗偑宍惉偝傟傞乮佮乽悽戙岠壥乿
偑屌掕偡傞乯帪婜偼丄媿擏傗慛嫑側偳偵斾傋傞偲傛傝擭彮偺帪婜丄梒帣婜偐彫妛
峑偺掅妛擭崰偱偼側偄偐偲偄偆堄尒偑偁傞丅
仦恾係丗堸梡媿擕偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖29.49倢乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
丂傢傟傢傟偼媿擕偵偮偄偰偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞擭楊奒媺偺嵟壓抂傪丄0
乣4嵨丄師偵5乣9嵨乧側偳偲壗捠傝偐帋傒偨丅偄偢傟偺帋傒偐傜傕忢幆偵斀偡傞
傛偆側寢壥偼惗傑傟側偐偭偨偑丄摨帪偵偳偺奒媺偐傜僗僞乕僩偝偣傞偺偑嵟傕椙
偄偺偐傕敾慠偲偟側偐偭偨丅偙偙偱偼愭偺3昳栚偵崌傢偣偰丄10乣14嵨傪嵟壓抂
偲偟偨暘愅寢壥傪徯夘偡傞丅
丂傑偢乮俙乯擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄10戙慜敿偑憤暯嬒24.49r偐傜20亾庛偺僾
儔僗丄10戙屻敿偐傜20戙偲掽尭偟丄20戙偺屻敿偱僛儘丄30戙屻敿偑仯4.59偱掙傪
偮偒丄偦偺屻憹壛偟偰60戙慜敿偱傗傗僾儔僗丄70嵨埲忋憌偱偼亄5r嫮偺抣傪帵偡丅
丂拲栚偵抣偡傞偺偼乮俛乯悽戙乮岠壥乯偱偁傞丅嵟傕屆偄悽戙丄1909擭埲慜弌惗
偺恖乆偼傗傗儅僀僫僗丄1925乣1950擭戙弌惗偺悽戙偼憤暯嬒偵懳偟10乣15亾偺僾
儔僗偺抣傪帵偡偑丄1960擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄擭楊岠壥傪暘棧偟偨悽戙岠
壥偺傒偲偟偰丄憤暯嬒偺10亾埲忋偺儅僀僫僗偺抣傪帩偪丄嵟嬤弌惗偺悽戙掱儅僀
僫僗偺愨懳抣偼掽憹偟偰偄傞丅
丂扨弮偵擭楊偑庒偄偲偄偆偺偱偼側偔丄乽崅搙惉挿乿偑僗僞乕僩偟偨屻偵惗傑傟
偨怴偟偄悽戙偼丄偦傟埲慜弌惗偺悽戙丄愴屻偡偖偵惗傑傟妛峑媼怘偺媿擕乮扙帀
暡擕乯傪偁傝偑偨偔堸傫偩悽戙偵斾傋丄悽戙偺摿惈偲偟偰亄4.5亅乮亅6.5乯亖11
r慜屻傕掅偄抣傪帩偮偲悇掕偝傟傞丅偙傟傜偺悽戙偼1995擭摉帪30嵨埲壓偩偑丄
傗偑偰擭傪庢傝丄懠曽1930擭戙偐傜愴憟捈屻偵惗傑傟偨悽戙偵懼傢偭偰偄偔偵偮
傟丄偦偺尷傝偵偍偄偰乮師偵弎傋傞帪戙岠壥偺愭峴偒傪峫偊側偗傟偽乯媿擕徚旓
偼尭彮偟偰偄偔偐傕偟傟側偄丅
丂媿擕偺壠寁徚旓偼1979乣80擭偐傜1996乣97擭偵偐偗丄1恖摉偨傝扨弮暯嬒偱25.
1r偐傜34.6r傊10r庛憹戝偟偨丅擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨擭戙岠壥偼恾4偺
乮俠乯偵帵偝傟傞捠傝偱丄1979乣80擭偺仯6.6r偐傜孹岦揑偵憹偊丄88乣89擭傪嫬
偵僾儔僗偵揮偠丄1996乣97擭偵偼亄8.0r偲14r嫮偺弮憹傪帵偟偰偄傞丅
丂偨偩偟彨棃偺廀梫憤検傪偙偺慄傪墑挿偟偰梊應偡傞偺偼婋尟偱偁傞丅媿擏偺傛
偆偵丄怴偟偄悽戙偑傗偑偰徚偊峴偔屆偄悽戙偲懳徠揑偵僾儔僗偺悽戙岠壥傪帩偮
働乕僗偲偼媡偵丄媿擕偵偮偄偰偼怴偟偄悽戙偑丄屆偄悽戙偵斾傋偐側傝儅僀僫僗
偺悽戙岠壥傪帩偭偰偄傞傜偟偄偙偲偑暘偐偭偨丅崱夞偺偙偺悇寁岠壥傪丄娭學幰
偼廫暘柫婰偟偰偍偔昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞丅
丂偙傟傜偺悢抣傪儀僀僘宆僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞偲丄恾4偺傛偆側岠壥偑嶼弌
偝傟傞丅堸梡媿擕偵偮偄偰丄堦惗偵傢偨傞堸梡姷廗偑宍惉偝傟傞乮佮乽悽戙岠壥乿
偑屌掕偡傞乯帪婜偼丄媿擏傗慛嫑側偳偵斾傋傞偲傛傝擭彮偺帪婜丄梒帣婜偐彫妛
峑偺掅妛擭崰偱偼側偄偐偲偄偆堄尒偑偁傞丅
仦恾係丗堸梡媿擕偺僐僂儂乕僩暘愅偺寢壥恾乮憤暯嬒亖29.49倢乯仦
乮俙乯擭楊
乮俛乯悽戙
乮俠乯擭戙
丂傢傟傢傟偼媿擕偵偮偄偰偼丄僐僂儂乕僩暘愅偵偐偗傞擭楊奒媺偺嵟壓抂傪丄0
乣4嵨丄師偵5乣9嵨乧側偳偲壗捠傝偐帋傒偨丅偄偢傟偺帋傒偐傜傕忢幆偵斀偡傞
傛偆側寢壥偼惗傑傟側偐偭偨偑丄摨帪偵偳偺奒媺偐傜僗僞乕僩偝偣傞偺偑嵟傕椙
偄偺偐傕敾慠偲偟側偐偭偨丅偙偙偱偼愭偺3昳栚偵崌傢偣偰丄10乣14嵨傪嵟壓抂
偲偟偨暘愅寢壥傪徯夘偡傞丅
丂傑偢乮俙乯擭楊乮岠壥乯偵偮偄偰偼丄10戙慜敿偑憤暯嬒24.49r偐傜20亾庛偺僾
儔僗丄10戙屻敿偐傜20戙偲掽尭偟丄20戙偺屻敿偱僛儘丄30戙屻敿偑仯4.59偱掙傪
偮偒丄偦偺屻憹壛偟偰60戙慜敿偱傗傗僾儔僗丄70嵨埲忋憌偱偼亄5r嫮偺抣傪帵偡丅
丂拲栚偵抣偡傞偺偼乮俛乯悽戙乮岠壥乯偱偁傞丅嵟傕屆偄悽戙丄1909擭埲慜弌惗
偺恖乆偼傗傗儅僀僫僗丄1925乣1950擭戙弌惗偺悽戙偼憤暯嬒偵懳偟10乣15亾偺僾
儔僗偺抣傪帵偡偑丄1960擭埲崀弌惗偺怴偟偄悽戙偼丄擭楊岠壥傪暘棧偟偨悽戙岠
壥偺傒偲偟偰丄憤暯嬒偺10亾埲忋偺儅僀僫僗偺抣傪帩偪丄嵟嬤弌惗偺悽戙掱儅僀
僫僗偺愨懳抣偼掽憹偟偰偄傞丅
丂扨弮偵擭楊偑庒偄偲偄偆偺偱偼側偔丄乽崅搙惉挿乿偑僗僞乕僩偟偨屻偵惗傑傟
偨怴偟偄悽戙偼丄偦傟埲慜弌惗偺悽戙丄愴屻偡偖偵惗傑傟妛峑媼怘偺媿擕乮扙帀
暡擕乯傪偁傝偑偨偔堸傫偩悽戙偵斾傋丄悽戙偺摿惈偲偟偰亄4.5亅乮亅6.5乯亖11
r慜屻傕掅偄抣傪帩偮偲悇掕偝傟傞丅偙傟傜偺悽戙偼1995擭摉帪30嵨埲壓偩偑丄
傗偑偰擭傪庢傝丄懠曽1930擭戙偐傜愴憟捈屻偵惗傑傟偨悽戙偵懼傢偭偰偄偔偵偮
傟丄偦偺尷傝偵偍偄偰乮師偵弎傋傞帪戙岠壥偺愭峴偒傪峫偊側偗傟偽乯媿擕徚旓
偼尭彮偟偰偄偔偐傕偟傟側偄丅
丂媿擕偺壠寁徚旓偼1979乣80擭偐傜1996乣97擭偵偐偗丄1恖摉偨傝扨弮暯嬒偱25.
1r偐傜34.6r傊10r庛憹戝偟偨丅擭楊岠壥偲悽戙岠壥傪彍嫀偟偨擭戙岠壥偼恾4偺
乮俠乯偵帵偝傟傞捠傝偱丄1979乣80擭偺仯6.6r偐傜孹岦揑偵憹偊丄88乣89擭傪嫬
偵僾儔僗偵揮偠丄1996乣97擭偵偼亄8.0r偲14r嫮偺弮憹傪帵偟偰偄傞丅
丂偨偩偟彨棃偺廀梫憤検傪偙偺慄傪墑挿偟偰梊應偡傞偺偼婋尟偱偁傞丅媿擏偺傛
偆偵丄怴偟偄悽戙偑傗偑偰徚偊峴偔屆偄悽戙偲懳徠揑偵僾儔僗偺悽戙岠壥傪帩偮
働乕僗偲偼媡偵丄媿擕偵偮偄偰偼怴偟偄悽戙偑丄屆偄悽戙偵斾傋偐側傝儅僀僫僗
偺悽戙岠壥傪帩偭偰偄傞傜偟偄偙偲偑暘偐偭偨丅崱夞偺偙偺悇寁岠壥傪丄娭學幰
偼廫暘柫婰偟偰偍偔昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞丅