| 1.はじめに
1本1リットル325円(消費税込み)の「田野畑山地酪農牛乳」が健闘している。1996年4月のスタート時点でわずか200本/週だった販売量が、現在では約1,400本/週にまで伸びてきた。この数量自体は都府県酪農でも小規模経営一戸の生産量にすぎないが、後述するように「田野畑山地酪農牛乳」の展開は、わが国酪農の展望を考える上で多くの示唆を与えてくれている。そこで本稿では、「田野畑山地酪農牛乳」の起点である山地酪農の経営特性を再検討するとともに、アグリビジネスモデルの視点から「田野畑山地酪農牛乳」のマーケティング戦略を考察し、今後「日本型酪農」の一形態として山地酪農が普及・定着していくための条件を考えてみたい。
なお、今回取り上げる「田野畑山地酪農牛乳」を生産・販売しているのが、岩手県田野畑村の熊谷牧場(くがねの牧)と吉塚牧場(志ろがねの牧)である。経営者である熊谷隆幸さんと吉塚公雄さんが山地酪農に取り組み始めた経緯やその後の展開過程、および「田野畑山地酪農牛乳」販売当初の様子などについては、すでに本誌『畜産の情報』1998年12月号(増井和夫「日本型放牧を先導する山地酪農岩手県田野畑村の事例」)に紹介されている。その意味で本稿は増井レポートの続編であり、内容の重複もできる限り最小限にとどめることにした。併せてお読みいただければ幸いである。
2.山地酪農の強靱性と低収益性
平地の少ないわが国で稲作とは別に永続的で安定的な農家の創設を夢みて、「牧山に乳牛を放牧し、乳牛に草を処理させ、人間が調整して牛乳、牛体を生産する」ことを提唱し続けた植物生態学者の猶原恭爾博士。1970年代前半にその猶原博士と個々別々に出会い、博士の教えに共感した熊谷さんと吉塚さんは、以来30年余り志を同じくする仲間として誠実に山地酪農を実践してきた。そして今日、二人の追い求める山地酪農の姿は、「田野畑山地酪農牛乳生産者規定」(別表参照)にみることができる。
| (別表) |
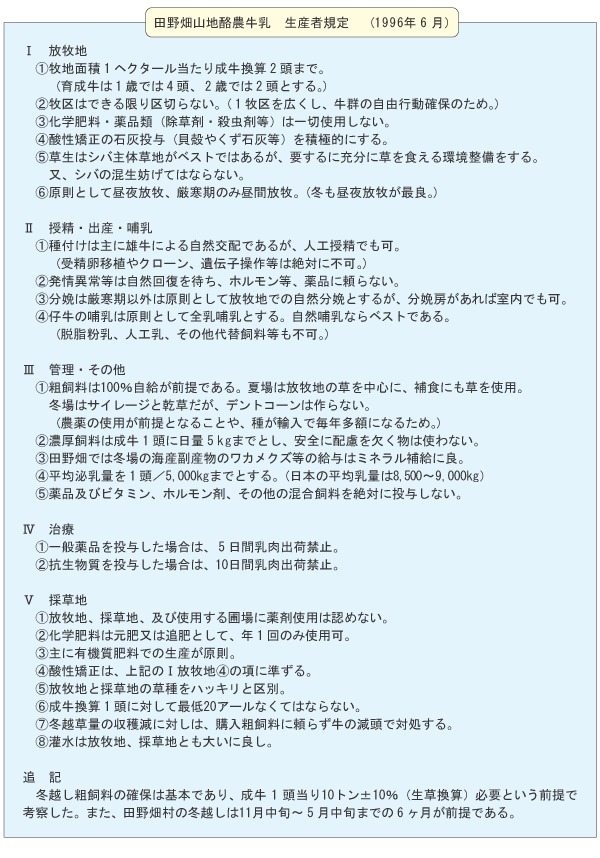 |
そこでは、牧区を区切らず、放牧は1ha当たり成牛換算2頭までとし、年間搾乳量は1頭5,000kgまで、放牧地や採草地での薬剤使用は厳禁、粗飼料は100%自給で、濃厚飼料も輸入トウモロコシなど安全性の担保されない物は給与しない、またデントコーンは種子が輸入で農薬使用が前提のため作付けせず、越冬用の草が不足した場合でも購入に頼らず牛の減頭で対処する、等々の条件が課せられており、いささか厳格すぎると映るかもしれない。
しかし、筆者には、自然の摂理に従い、この生産者規定を遵守して、「土−草−牛」の物質循環を大切にしていることが、田野畑山地酪農の存在意義を確固たるものにしているように思われる。以下では、熊谷牧場の取り組みをもとに、田野畑山地酪農の特性をみていくことにしよう。
熊谷牧場の経営概要を表1に示した。増井レポートから約5年。この間に後継者である宗矩さんは盛岡市出身の美穂子さんを妻に迎え、長男和真くんを授かった。現在の熊谷家は4世代7人が同居する大家族である。この4世代の家計を支える強靱性こそ山地酪農の最大の特性ではないかと思われるが、この点については後述する。このほかに、乳牛飼養頭数が若干増加し、牛舎を増築するとともに事務所を新設している。放牧地や採草地、山林などに変化はみられない。
|
表1 熊谷牧場の経営概要(2003年11月)
|
|
|
| 出所:聞き取り調査より作成。 |
○田野畑山地酪農の技術的特性
改めて述べるまでもなく、熊谷牧場の特色は、シバ草主体の1牧区25haの放牧地と12haの採草地を擁している点にある(図1参照)。熊谷牧場では、よほど冷え込みの厳しい冬の夜間を除き牧山に牛を昼夜放牧しており、牛の排せつ物はシバ草の成長を促す有機質肥料としての役割を果している。現在の牧地面積1ha当たり頭数も成牛換算で約1.7頭と、さきの生産者規定の上限2頭を下回っており、熊谷牧場には家畜ふん尿問題はみられない。これが第1の特性である。
|
図1 熊谷牧場の牛舎・ほ場等の配置(2003年11月)
|
|
|
第2の特性は、飼料自給率が高いことである。熊谷牧場では採草地に、オーチャード、クローバー、イタリアンライグラスを主体とした5種混播牧草を播種しており、その単収は約5t/10aである。これに対して粗飼料(乾草とグラスサイレージ)の給与量は、日量成牛換算で夏場10kg、冬場15kgであり、粗飼料自給率は100%を超えている。また配合飼料も国産のふすまとビートパルプを主体に給与(搾乳牛の場合でも、夏場4kg、冬場2kg)しており、熊谷牧場の国産飼料自給率は極めて高くなっている。
そして第3の特性が、世代を超えて長期低コストで利用可能な生産基盤を確保できることである。図1にみられる放牧地は、いまでこそ見事なシバ草地(=牧山)であるが、「沢」が走っていることから推察できるように、かつてそこは農業に利用することもできず薪炭用に使っていた山林であった。猶原博士と出会った直後、熊谷隆幸さんはそこに牧柵を張り、牛を放ち、ころ合いを見計らって不要な雑木を伐採した後で、丹念にシバを張っていったのである。シバは定着するまでに、繁茂する雑草を刈り取らなければならないなど手間がかかり、条件の良いところでも3年、条件の悪いところでは10年を要するという。このように定着までの初期段階で膨大な時間と労力を必要とはするものの、シバ草地は一度出来上がってしまえば後の管理は難しくない。生命力の強いシバは毎年再生し、管理は放牧されている牛が勝手に行ってくれるからである。人手を要するのはせいぜい酸性土壌を矯正するために、数年に一度石灰を散布する程度のことである。ちなみに熊谷牧場では近々、酸性土壌の矯正と泥濘化防止のために、産業廃棄物であるカキ殻を粒状に粉砕し、牧山に投入するという。他産業との連携を図り、循環型社会の形成に貢献することも、山地酪農の特性と言えるのかもしれない。
第4の特性は、傾斜地などを活用することで、土壌侵食を抑制し、土地利用率を高めていることであり、これは上記で述べた牧山のマクロ的評価である。
第5の特性は、乳牛の供用年数が高いことである。熊谷牧場では2〜3年前に乳房炎が多発し乳牛の更新を早めたが、それでも現在の平均産次数は約5産と全国平均の2.6産(家畜改良事業団牛群検定情報結果)を大きく上回っている。また分娩間隔も約13ヶ月で、1年1産を確実にしている。これは放牧により牛のストレスが軽減し発情発見が容易になっているほか、まき牛による自然交配を通して山地酪農向きの牛(体重約600kgと舎飼いの牛より一回り小さく、足腰が強い)を作り上げてきたことによると思われる。いずれにせよ、乳牛の供用年数が高いことは乳牛資本の償却・更新費用を低下させ、低コスト酪農を可能にする。
第6の特性は、「ゆとりある経営」を実現していることである。一般的に言われているように、放牧の導入は、畜舎での飼養管理労働やふん尿処理作業、夏季の飼料収穫作業を軽減する。データは少々古いが、岩手県畜産会が実施した経営診断結果によれば、熊谷牧場の2000年の1人当り投下労働時間は約2,050時間であり、全国平均(約2,400時間)を15%ほど下回っている。また2世代4人の家族労働力を有していることも、1番草〜3番草の収穫とサイレージ作りの組み作業を容易にしており、「ゆとりある経営」を実現する重要な要因になっている。
そしてなによりも、健康な牛とトレース(追跡)可能な飼料からつくられる畜産物は、「安全で安心できる」食品そのものであり、多くの消費者の要請にかなっている。これが第7の特性である。
以上、田野畑山地酪農の技術的特性をみてきたが、これらはいずれも今日のわが国農畜産業がかかえる数多くの深刻な問題を解決している姿でもある。しかしながら、それでもなお山地酪農は普及していかない。次にその原因を探るため、経営の視点から田野畑山地酪農の特性を検討してみよう。
○田野畑山地酪農の経営的特性
田野畑山地酪農と都府県酪農の経営比較を表2に示した。ここで比較対象である都府県酪農の平均像は、同表から推量できるように、飼養頭数に比べて草地や飼料畑が少なく、飼料の大半を輸入飼料に依存しながら舎飼いで高泌乳牛を飼育している経営である。
比較結果によると、どちらの経営も経産牛飼養頭数はほぼ同じであるが、1頭当たり乳量の格差が大きすぎるため、熊谷牧場の生乳生産量は都府県平均の40%程度に止まっている。乳価は熊谷牧場の方が若干高いものの、それでもなお農業収入は都府県平均の半分でしかない。しかし、これまでみてきたように山地酪農は低コスト酪農である。飼料・肥料費をはじめ、種付け・素畜費、光熱水費、診療医薬費と、熊谷牧場の支出は軒並み都府県平均の約半分ないしは1/3〜1/5という水準である。その結果、わずかではあるが、熊谷牧場の農業所得(=農業収入−農業経営費+家族労働報酬)は都府県平均のそれを上回っている。収入は少ないが経費も低く抑えることができ、結果的に高い所得率を実現できることが山地酪農の第8の特性である。
|
表2 田野畑山地酪農と都府県酪農の経営比較
|
|
|
注1:熊谷牧場の経営概要と経営収支は2002年の実績値、生産技術指標は2000年の実績値である。
2:都府県平均の数値は中央畜産会の2001年度畜産経営安定化指導事業の調査結果から、経産牛飼養頭数規模20〜30頭の22戸と30〜40頭の46戸の集計値を加重平均したものである。 |
ところで、同じ農業所得を生み出すのに熊谷牧場では4人の労働力を投下しているのに対して、都府県平均では2.4人と少ない労働力で済んでいる。この点だけに着目するならば、熊谷牧場は労働生産性の低い経営ということになる。しかし、もし仮に家族労働力の誰かが病気になったり事故で怪我をした場合には、都府県平均の一人当り労働強度は急速に上昇し臨界点を超える可能性が高い。これに対して「ゆとりある経営」を実践している熊谷牧場の場合には、労働調整は比較的容易である。同様のことは、例えば、飼料価格が変動する場合についてもいえる。異常気象や為替レートの変動により飼料価格が高騰した場合には、購入飼料依存度の高い都府県平均の経営収支は急速に悪化する。これに対して飼料自給率の高い熊谷牧場の場合には、影響は微少と考えられる。このようにリスクへの対応力が高いことが山地酪農の第9の特性である。
このことはまた、熊谷隆幸さんのいう「千年家構想」につながっていく。それは、シバ草主体の牧山は出来上がるまでに20年も30年も時間を要するが、一度形が決まれば末代まで不変的に牛乳や牛体を供給できることを指している。家族経営の目的が利潤を最大化することにあるのではなく、家計の再生産に必要な一定の所得を確保することと余暇から得られる効用を最大化することにあるとするならば、山地酪農は、牧山の牧養力に応じて飼養頭数を調整し、世帯構成の変化に弾力的に対応できるのである。家族周期(ファミリーサイクル)に合わせた経営展開を可能とすることが、山地酪農の第10の特性である。
さて、これまで山地酪農の優れた特性をみてきたが、それをもとに考えてみると、山地酪農が普及・定着しない原因は、1)確固たる生産基盤が出来上がるまでに一世代相当の長い時間がかかり、2)農業所得は飼養頭数よりも放牧地や採草地の規模に規定されるため、3)一定規模の生産基盤を確保できなければ家計を維持することができない点にある、と言えよう。事実、1974年に田野畑村に新規参入した吉塚公雄さんの牧場は10haと小規模なため、農業所得も少なく負債償還も滞りがちとなり、1990年代中頃には離農寸前にまで追い込まれた。
そして、その難局を打開するために始めたのが、プライベートブランド「田野畑山地酪農牛乳」の販売である。幸いなことに、地元テレビ局に勤める吉塚さんの友人の手助けもあり、「田野畑山地酪農牛乳」は、たびたびマスコミで取り上げられ、その売上げを順調に伸ばしてきた。
|
|
|
「くがねの牧」の担い手熊谷さん一家
|
|
(左から 隆幸氏、幸子さん、美穂子さん、宗矩さん)
|
3.「田野畑山地酪農牛乳」のマーケティング
「田野畑山地酪農牛乳」の生産・加工・流通経路を整理したのが、図2である。原料乳の供給は熊谷牧場と吉塚牧場の2戸のみで、毎月曜日・水曜日・金曜日の週3回、牛乳缶に詰め替えた生乳を自分たちで田野畑村産業開発公社のミルクプラントに運び込んでいる。現在1回に運び込む量は580kgで、これはミルクプラントにある1つのタンクの限界処理能力でもある。この制約のため、熊谷牧場の生乳の一部は、田野畑村の他の酪農家の原料乳と一緒に「たのはた牛乳」ブランドとして加工され、販売されている。熊谷さんと吉塚さんは殺菌・充填された「田野畑山地酪農牛乳」をすべて買い取り、毎週火曜日には盛岡市の120〜130世帯に520〜530本を、毎週金曜日には地元田野畑村と隣接する岩泉町の約70世帯に約150本を、それぞれ自分たちで配達している。このほかに、毎週約700本がクール宅急便で首都圏などに運ばれている。
|
図2 田野畑山地酪農牛乳の生産・加工・流通経路
|
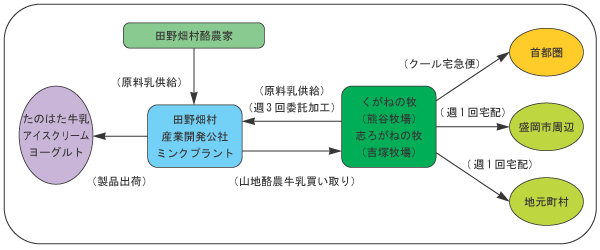 |
| |
|
| |
素朴さと力強さを、想起させるパッケージデザイン「山地酪農牛乳」
|
さて、「田野畑山地酪農牛乳」のマーケティングとはいかなるものか。J.A.マッカーシーの4Pに従って、その特徴を整理してみよう。マッカーシーの4Pとは、製品(Product)、価格(Price)、販売チャネル(Place)、販売促進(Promotion)のことで、これらを上手に組み合せて相乗効果を発揮させること(マーケティング・ミックス)が、売上げの増加につながるという考え方に基づいている。
○製品(Product):「田野畑山地酪農牛乳」の製品特性は、何よりも健康な牛と化学肥料や農薬を一切使用せず、トレース(追跡)可能な飼料からつくられた「安全で安心な」牛乳という点にある。しかし、牛乳は一般的に品質による製品差別化が難しい商品である。「田野畑山地酪農牛乳」の場合も、表2にみられるように、乳脂率および無脂固形分率ともに他の牛乳とそれほど大きな格差はみられない。むしろ「田野畑山地酪農牛乳」は、パッケージデザインで差別化を図っているように思われる。白地のパッケージに毛筆書体で描かれた商品名と簡潔なメッセージは、素朴さと力強さを想起させ、自然の営みから生まれた本物の牛乳であることを消費者に訴求している。盛岡市在住のグラフィックデザイナー山崎文子さんがボランティアで引き受け、制作した作品である。
○販売チャネル(Place):「田野畑山地酪農牛乳」の販売先は単純明瞭で、先に述べたようにほとんどが宅配と通販である。これは生産者規定を満たす原料乳生産が限られており、スーパーや量販店向きでないことにもよるが、それよりも「こだわり商品」を確実にかつ長期継続的に購入してもらうために選択した結果と考えられる。ただし、「顔のみえる取引」の宅配にはリスクも少なくない。例えば、盛岡市へ配達に行く毎週火曜日は、田野畑村を早朝6時前には出発しなければならない。幾つもの峠と山を越え、到着するまでは車で約2時間半の道程である。夏期は別としても、冬期間の凍結した雪道の運転は多大な精神的苦痛を伴う。ましてや配達を担当する吉塚公雄さんと熊谷宗矩さんは、それぞれの牧場の基幹的労働力でもある。最近、吉塚さんの長男が宅配担当に加わり負担は軽減されたとはいうものの、万が一、事故にでも遭遇した場合には、経営の継続が困難になりかねない。それでもなお宅配を外部に委託しないのは、顧客の喜ぶ顔をみることができることと直接会話ができる関係を大事にしたいからであるという。
 |
|
くがね牧場(熊谷牧場)の牛乳処理室と牛乳缶
|
|
○価格(Price):「田野畑山地酪農牛乳」の販売価格は、基本価格が1本1リットル310円+消費税で、盛岡市の宅配価格が350円+消費税、首都圏向けなどの通販価格が基本価格+クール宅急便代金となっている。ミルクプラントからの買取価格が約220円で、紙容器の代金や発送作業の経費などを考えあわせると、基本価格の310円は決して高くはないように思われる。しかし、それでもなお量販店などで売られている牛乳の約1.5倍の価格であり、そこには価格プレミアムが発生している。このプレミアムの全額を消費者の「安全・安心」に対する支払い意思額とみることもできようが、筆者はそれよりも熊谷牧場と吉塚牧場に田野畑山地酪農を継続してもらいたいと願う顧客(賛同者)の態度表明ではないかと考えている。盛岡市在住で田野畑山地酪農牛乳「消費者友の会」会長の花田さんは、田野畑山地酪農牛乳の購入理由を、「少々価格は高いが毎日一所懸命働いている自分へのささやかなプレゼント」であり、「熊谷さんと吉塚さんの取り組みに共感を覚えるから」と答えてくれた。「こだわり牛乳」の価格形成要因としては、「安全・安心」よりも、生産者の生きざま(the
Way of Life)に対する共感が強く作用していると思われる。なお、購入者の中に子育てが一段落し生活に余裕が出来てきた人たちが多いことも、高価格を維持できる要因となっている。
○販売促進(Promotion):「田野畑山地酪農牛乳」の販促活動には、次の3つのタイプがみられる。第1は、マスコミを活用した情報発信である。当初は地元のテレビや新聞、雑誌に取り上げられる程度であったが、ここ数年は田野畑山地酪農それ自体を題材としたテレビ番組が東北エリアのみならず全国ネットでも放映され、「田野畑山地酪農牛乳」の存在が広く知られるようになってきた。首都圏での購入者が多い理由の1つはそのためである。第2は、デパートや催事でのマネキン販売である。対面販売は、商品情報だけでなく生産履歴や牧場の生活など付加的情報を直接その場で伝えることができるため、消費者の購買意欲を刺激して新規需要の獲得につながりやすい。ただし、マネキン販売は生産者が自ら売り子を勤めなければならないので、たびたび実施できるわけではない。そして第3が、販売開始当初から継続している会員通信『まき』の発行(毎月1,000部)と現地交流会の開催(毎年1回9月)である。これらはどちらも会員に、田野畑山地酪農の良き理解者であり支援者、すなわちサポーターになってもらうことを主眼に置いた活動であり、「田野畑山地酪農牛乳」それ自体の販売促進を直接的な目的としているわけではない。しかし、サポーターの拡大は、結果的には「田野畑山地酪農牛乳」の購入継続を勧める上で必要となる追加的費用の低下につながっていく。また彼らの口コミによる新規購入者の獲得は、売上げを増大させるばかりでなく、生産者と消費者双方の探索費用や商品の評価費用など営業費用を大幅に縮減する。既出の「消費者友の会」の花田さんによれば、盛岡市での宅配件数がこの5年間で倍増した最大の理由がこの口コミ効果にあるという。このように、口コミは活動範囲が限定的であるものの、「田野畑山地酪農牛乳」の販売促進にとっては極めて実効性の高い手段である。逆に言えば、そうであるからこそ、サポーターの育成に向けた会員通信作りや現地交流会が重要になってくる。そしてそこでは何よりも、読者や参加者に感動を与え、共感を持ち続けてもらうことが大切である。この点で、吉塚さんと熊谷さんの通信作りは至ってシンプルではあるものの、ある程度成功しているように思われる。例えば、『まき』第80号(平成15年11月6日発行)には、これまでの「田野畑山地酪農牛乳」が歩んできた経緯(シリーズ連載)と、「くがねの牧」「志ろがねの牧」の現況報告が綴られている。そのなかでも特に、放牧の群れからはぐれて行方不明になっていた熊谷牧場の「きらこ号」4歳が、牧山の沢近くの泥濘に足を捕られたまま遺体で発見されるくだりは出色の出来で、筆者も思わず目頭を熱くしてしまった。「きらこ号」を必死で探す熊谷宗矩さんの目線で読み進み、山地酪農の厳しさと生産者の優しさを疑似体感していたのである。このような疑似体感は、一度でも現地を訪れたことのある者にとっては尚更強く感じるに違いない。無意識の内に記憶を探り、その情景を思い起こすからである。現地交流会は何かと手間暇のかかるイベントであるが、それは参加者に直接感動を与えるだけでなく、会員通信と補完し合うことによって、彼らの共感を持続させる効果を併せ持っていることも忘れてはなるまい。
以上をまとめると、「田野畑山地酪農牛乳」は価格が高く数量も限定的で品質による製品差別化が難しいため、その基本的マーケティングは、生産者の生きざまや田野畑山地酪農の取り組みに共感する人たちに需要を絞り込み、生産者が自ら(遠隔地の人には宅急便で)商品を届けるという方法である。そして、会員通信と現地交流会を通してサポーターの拡大を図り、長期安定的な顧客を確保していくとともに、彼らの口コミで新規購入者を獲得していく発展戦略である。
このような「田野畑山地酪農牛乳」のマーケティング戦略は、図3に示される生産者関与型の消費者創造志向と位置付けられよう。図3は、農畜産物に限らず商品全般を対象としたマーケティングの展開方向を整理したものである。田村馨氏(福岡大学商学部)は、「1年間で8〜9割の商品が入れ替わるコンビニの店頭をターゲットとしたビジネスモデルと、アグリビジネスモデルが同じ土俵であるはずがない。どこまでアグリにこだわれるかが、アグリビジネスモデルの構築においてはポイント」で、「アグリビジネスモデルが依拠すべきポジショニングは、(高度経済成長期の)単なるプロダクトアウトでもなければ、(低成長移行後の)消費者ニーズ絶対型のマーケットインでもない。今後は、消費者との対等な関係(図中の点線部分)を構築する仕組みとして設計されるべきである」と述べている。さらに、「アグリビジネスモデルを評価する軸や基準は、効率性や利益率だけでなく、持続性、スロー性、コミュニティとの共存性、ネットワーク性、自然環境保全性、コモンズ性、社会的責任性、多様性などが想定される」と主張する。筆者もまさに同感である。その意味で、「土−草−牛」の物質循環にこだわり、消費者と「顔の見える取引」関係を継続しながら着実にサポーターを増やしていく田野畑山地酪農は、時代の最先端をいくアグリビジネスモデルそのものであると言えよう。
|
図3 今後のアグリビジネスモデルの枠組み
|
|
|
出典:田村馨「アグリビジネスモデルのアーキテクチャー(設計思想)と可能性」『農林統計調査』第53巻第12号,pp4-10,2003年
注:上記出典の原図を一部修正している。 |
4.おわりに
本稿では、田野畑山地酪農経営の取り組みを対象として、山地酪農の優れた技術的特性と経営的特性を再確認するとともに、「田野畑山地酪農牛乳」のマーケティング戦略が、今後目指すべきアグリビジネスモデルに適合していることを明らかにした。ここでは最後に、そのように優れた特性をもつ山地酪農経営が普及・定着していくために必要な3つの政策的支援を述べておきたい。なお、山地酪農の研修制度や展示圃場の設置などについてはすでにある程度整備されており、割愛する。
第1は、放牧地や採草地など生産基盤の整備に関する支援である。とかく山地酪農は、放牧に適した土地をまとめて確保するのが難しいという理由から敬遠されがちであったが、今日の中山間地域に眼を向けてみると、そこにはすでに管理の行き届かなくなった山林や丘陵地が数多く見受けられることから、生産基盤を確保するための土地制約は、かなり緩くなってきていると考えられる。それよりもむしろ深刻なのは、中山間地域で不在地主が増えているとか、誰の土地なのかもわからなくなっているといった土地所有の権利調整問題である。これは個別経営で解決できる問題ではない。また山地酪農の場合には、これまでみてきたように牧山など放牧地の確立に20〜30年を要することから、一世代でみた場合の土地に対する資本投資効率は極めて低くならざるを得ない。これでは誰も山林を切り開き、牧山を造成しようとしないのも当然である。そこでこれらの問題を解決するために、公的機関が土地の権利関係をきちんと整理し、そこに一括利用権設定をした後で、30〜50年の長期土地賃貸借事業を展開していく必要があると思われる。
第2は、農家所得に対する補てんである。仮に一括利用権設定された土地を長期間借り受けることができたとしても、その土地にあった牧草が蹄耕法で定着するまでには、やはり一定の年月がかかることになる。言うまでもなく、その期間中の農業所得は水準も低く、変動も大きい。場合によっては、最低生活水準を下回ることさえあるかもしれない。そのような事態を回避するために、現行の中山間地直接支払い制度を継続し、内容の充実を図ることも考えられようが、そもそも平地地域との生産費格差を補てんする同制度を山地酪農経営の安定化に適用するには無理がある。山地酪農を夢みてその地域に定住しようする人に対しては、生産基盤が確立するまでの一定期間、生計費を補てんする意味で、農家所得に対する直接支払いをしていく必要があるのではなかろうか。
そして第3が、消費者や都市住民、子供達との交流を促進するための支援である。山地酪農を支える根幹に、彼らの感動と共感があることはすでにみてきた通りである。そして現地交流会が、その感動と共感をもっとも強く体感できる場であることも首肯できよう。しかし、現地交流会は意外と機会費用の高いイベントである。酪農家にとっては予想以上に受け入れ準備に手間暇がかかるし、子供達に体感してもらう教育ファーム・プログラムはいまだ個々の酪農経営で手探りの状態にある。一方、参加者にとっても、日帰りの場合には短い滞在時間で感動する間もなく、宿泊を伴う場合には宿泊先の確保など追加費用を負担しなければならない。このような障壁を少しでも低くするために、実効性の高い交流プログラムの開発と宿泊に対する助成措置などを検討していく必要もあると思われる。
|

