1.カルシウム不足の日本人
高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める比率)20%を越えたわが国において、単に寿命を延ばすばかりではなく、いつまでも自分の手足を用いて生活を自立させたいとは誰もが願うことであろう。そのために重要なことの一つが、骨粗しょう症を防ぎ、寝たきりを防止することであると思われる。若年期に骨密度を増加させ、中高年期にその低下を防ぐためには、(1)カルシウム、ビタミンDなど必要な栄養素の充足、(2)重力負荷をかける適度な運動、(3)適度な量の日光浴、などが必要であることが知られている。(2)、(3)の充足度の評価は難しいが、(1)に関しては少なくとも十分とはいえない状況である。表1に示した、平成17年の国民健康・栄養調査の結果をみていただきたい。
表1 日本人のカルシウム摂取量と摂取基準による目標量との比較
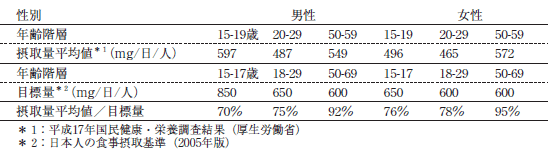
「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の摂取基準によるカルシウムの目標量と比較した場合、2種の資料の年齢区分が異なるので厳密な比較はできないものの、どの年代、どちらの性別でも、カルシウム摂取量が、目標量を満たしていないことがおわかりになるであろう。特に、最大骨密度に到達する10代でのカルシウム摂取量は70%台と低い。ここで、目標量とは、この値に達していれば生活習慣病のリスクが低いとされる量である。
では、カルシウムをより多く摂取したいと思うとき、どのような食品を思い描くだろうか。乳・乳製品、小魚類、青菜などが浮かんでくるが、なかでも牛乳は100グラム当たりカルシウムを110ミリグラムと豊富に含むこと、調理の手間がかからないこと、そして吸収率もほかの食品と比較して高いといわれていることから、理想的なカルシウム補給源と思われる。しかし、ここで問題となるのが、私たち日本人には、乳糖不耐症の人が多いために、成人が牛乳を飲むと、少なくとも一度に大量に飲むと、下痢、腹痛、膨満感などの不快な症状が引き起こされやすいという事実である。本稿では、本学で行った調査や実験結果を交えて、乳糖不耐症への対応についても述べてみたい。
2.乳糖不耐症が「牛乳を飲む、飲まない」を分ける?
私が若年女子(18歳〜22歳)を対象に行った牛乳摂取頻度調査によると(図1)、「ほとんど毎日飲む」(31%)に近い割合の、「ほとんど飲まない」(27%)という者がいる。これをほかの乳製品であるヨーグルト、また、人によって臭いに好き嫌いがあると思われる納豆と比較していただきたい。どちらも「毎日食べる」、「ほとんど食べない」という人の割合よりも、「週2〜5回」、「月1〜5回」の方が多くなっている。通常、食品の摂取頻度調査を行うと、肉、卵、魚などどのような食品の場合でも、平均の頻度を頂点として、両側が低い分布となる。しかし、牛乳はこの点で特殊であり「摂取習慣のある人」と「摂取習慣のない人」の2つのグループに分かれやすい食品であるということができる。
図1 牛乳・ヨーグルト・納豆の摂取頻度調査*3
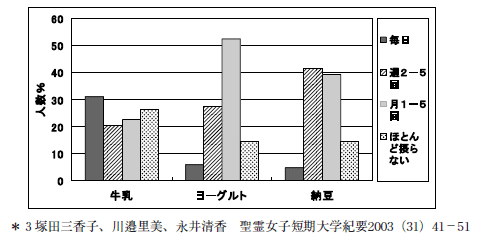
では、今度は表2をご覧いただきたい。「牛乳をほとんど飲まない」と答えた57名にその理由について尋ねたところ、「お腹がごろごろする」という明らかに乳糖不耐症が原因と思われる理由で飲まない者の割合が28.1%を占めたのである。このことから考えられるのは、「牛乳を飲む、飲まない」を分けるのは、乳糖不耐症が原因なのだろうか、ということである。
表2 牛乳をほとんど飲まない理由とその割合*3
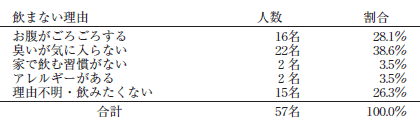
日本人と乳糖不耐症
では日本人の中に乳糖不耐症の性質を持つ人はどのくらいの割合で存在しているのだろうか。乳糖不耐症のもともとの原因は、小腸粘膜にある乳糖分解酵素(ラクターゼ)という、二糖類である乳糖をグルコースとガラクトースに分解する酵素の活性が弱いことにある。牛乳100ミリリットルには乳糖が約5グラム含まれているが、この乳糖がラクターゼによって分解吸収されずにそのまま結腸内に到達すると、浸透圧上昇により水分を大腸内に引き込んで下痢の原因となる。
また、結腸内で細菌の分解を受け、乳酸、炭酸濃度が上昇するとpHの低下による大腸運動の活発化を招き、先の諸症状が引き起こされる。これらの事象を利用して、乳糖不耐症の人とそうでない人を区別する幾通りかの方法が考案されてきた。
最も直接には、(1)「空腸の生検によるラクターゼ活性の測定」により行われるが、この方法は多数の健康人を対象に行うには無理がある。そのため、(2)「乳糖投与後の血糖値の増加」または、(3)「乳糖投与後の呼気中水素濃度上昇」を観察することにより、間接的に測定される。
(2)の方法は、ラクターゼ活性の高い対象者は、乳糖を空腸内で直ちにグルコースとガラクトースに分解吸収できるため、血糖値の低い空腹時に乳糖を与えると血糖値(血中グルコース濃度)の上昇が観察される、という原理に基づく。この方法では、1972年に日本人の乳糖不耐症者の割合を86%と報告した研究と79%と報告した研究がある。2003年に私たちが74名の若年女子集団を対象として行った調査では、82.4%が乳糖不耐症者であると判定された。
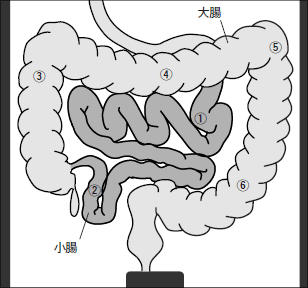
(1)空腸 (2)回腸 (3)上行結腸 (4)横行結腸
(5)下行結腸 (6)S状結腸
(5)下行結腸 (6)S状結腸
一方、(3)の方法は、乳糖が空腸内で分解されず、そのまま結腸内に到達したときに、細菌によって分解されて呼気中に排出された水素ガスをガスクロマトグラフ法により測定し、この水素ガス濃度が上昇すれば乳糖不耐症者であると判定する方法である。この方法によっては、1998年に51.6%と報告した研究と、1992年に94.7%が乳糖不耐症者であると判定した報告がある。なぜこのように乳糖不耐症者の割合にばらつきが見られるかということについては、(2)の方法では血糖上昇には対象者の耐糖能という別な要因が関連してくるため、(3)の方法では結腸内の腸内細菌叢によって影響を受けるため、という理由が考えられる。
3.成長後の乳糖不耐症はほ乳類にとって普通のこと
実は乳糖は人間や牛を含むほ乳類の乳汁中にのみ存在の知られている二糖類である。なぜ乳糖が乳汁中にのみ存在するかについては、ガラクトースは乳児期にさかんである神経系の発達に必要な栄養素であるが、グルコースからガラクトースへの変換が乳児期には十分できないため、外から栄養素として与えられる、という説明が考えられている。このため、離乳期に達して、もう母乳を摂取しない時期になると乳糖を栄養素として摂取することはないため、ラクターゼの役割は終了したということになり、次第に活性が弱くなり、成人期には乳児期の1/10程度に減少してしまうといわれている。これは何も人間に限ったことではない。私たちがマウスを用いて空腸内のラクターゼ活性をマウスの日齢を追って測定した資料が図2である。
図2 マウスの日齢と小腸粘膜の二糖類分解酵素活性*4
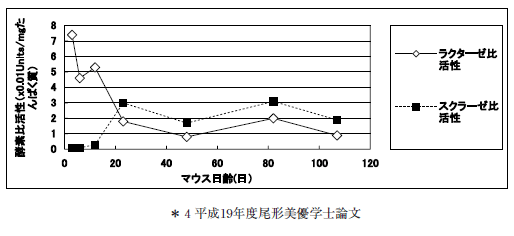
マウスは約3週齢で離乳するが、生後12日までは高いラクターゼ活性が23日では急激に低くなり、1/5の活性となる。その代わりのように、ショ糖(スクロース)をブドウ糖(グルコース)と果糖(フルクトース)に分解するショ糖分解酵素(スクラーゼ)活性が離乳を境に急激に上昇することがおわかりになるであろう。これはマウスを用いた実験であるが、ラットでも同様に確認されており、ほ乳類全般に認められる事象であると思われる。
また、いったん活性の低くなったマウスの空腸にあるラクターゼの働きは、牛乳を与えてももとにはもどらない。図3を見ていただきたい。これは3群のマウスの小腸ラクターゼ活性を比較したものであるが、左から、通常飼料で11週齢まで飼育したマウス、7週齢まで飼料、その後11週齢まで牛乳で飼育したマウス、4週齢から11週齢まで牛乳で飼育したマウスを示している。乳糖を含まない標準飼料を食べ続けても、牛乳を4週間飲み続けても、7週間飲み続けても、ラクターゼの働きに違いは認められない。つまり、これの意味するところは、離乳期を過ぎ、いったんラクターゼ活性の低くなった空腸ラクターゼ活性は決して高くならないということである。
図3 牛乳投与の有無によるマウス小腸粘膜のラクターゼ活性の比較*5
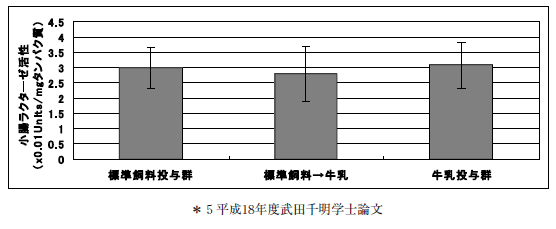
では、成人期に乳糖不耐症でない人種にはどのようなことが起こったのかを考えてみよう。乳糖不耐症者の少ない人種はアングロ・アメリカン(15%)、ザイールのツチ族(10%)などであるが、彼らは長い牧畜生活の中でウシ、ヤギなどの乳を栄養の補給源として頼ってきた、という歴史をもっている。つまり、ほ乳類の中で初めて乳児期以降も乳糖を摂取し続けるという状況が何代も続く中で、やがて乳児期以降もラクターゼ活性の高い状態が継続するように適応した、と考えられる。このような状況はほ乳類の中ではごく特殊な状況であると思われる。日本人にとっては牛乳が食品として現れたのは明治期以降であるため、長い牧畜文明をもち、乳糖消化に適応した民族のように、1日に何リットルもの牛乳を飲む、というようなことは無理なことといえよう。
4.牛乳摂取が腸内細菌叢を変えて乳糖分解を助ける
では、もともと空腸にある自分の酵素であるラクターゼの働きの弱い人たちは、乳糖を含む乳類を飲用することはできないのであろうか。私たちはこれを腸内細菌によるラクトース分解酵素の働きによって助けてもらうことができると考えている。ここでもマウスを用いた実験を紹介しよう。表3は同じ6週齢のマウスについて、乳糖を含まない標準飼料を与え続ける群と牛乳を66日間与え続ける群に分け、糞便中に認められる腸内細菌数を計測したものである。この結果、ラクトバチルス、ビフィズス菌といったラクトース分解酵素活性を持った細菌類の数が、牛乳を摂取した群では標準飼料のみで飼育した群よりも上昇する傾向が認められた(表3)。これらはまだ確認を要する実験ではあるが、牛乳の飲用によって腸内細菌叢が変化し乳糖不耐症を軽減するように働いている可能性があると考えられる。
表3 糞便中の細菌数の比較(log10細菌数/g)*6
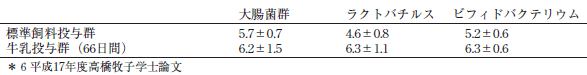
いくつかの論文で、成人性乳糖不耐症の生ずる民族においては、「乳糖不耐症と自覚する集団は、乳類を摂取しないためカルシウム摂取量が低い」ということが確かめられている。このような集団に起こるのは、「牛乳による不快な症状を自覚しやすい人は牛乳など乳製品を取らない、すると乳糖を摂取する機会がないために乳糖分解を助ける腸内細菌叢が形成されない、細菌による乳糖分解の助けもないために牛乳をのむと益々乳糖不耐症の症状が自覚されやすい。」という循環が成り立ってしまうためである。ここで問題になることは、乳糖不耐症を自覚する集団は、乳糖不耐症を自覚しない集団に比較して、カルシウム摂取量が低いため骨密度もまた低い、という疫学調査の結果が得られていることである。
5.十分なカルシウム摂取のために
ここで、最初に立てた仮説である、「牛乳を飲む、飲まない、を分けるのは乳糖不耐症が原因なのだろうか?」という問題にもどりたい。これまで述べてきたように、日本人は他の多くの民族と同じように成人性の乳糖不耐症が生じる民族ではあるが、このような集団でも、牛乳200ミリリットル中に含まれる、乳糖約10グラムの飲用ではほぼ症状の問題は生じない。しかし、症状を強く意識する方たちはあまり意識しない方たちよりも、牛乳を摂取しない、という習慣がつきやすい。そのことによりまた、乳糖分解を助ける腸内細菌が定着しない。逆説的ではあるが、日本人においては、乳糖不耐症が「牛乳を飲む、飲まない。」をわけるのではなく、牛乳摂取習慣が「乳糖不耐による症状が強く出る、出ない。」を分けることになる。
では何が最初に牛乳摂取習慣を形づくるかといえば、私は摂取している集団では、さまざまな食品を日常の食生活に取り入れている傾向が認められた調査結果から、「健康は食生活が基本と意識している集団」には、牛乳摂取習慣が根付くのではないだろうか、と推定している。
確かに、日本人の中に牛乳飲用後の不快症状を経験した者は多く、朝の空腹時などに牛乳をのむことにはためらいがあるかもしれない。これら症状を軽減するためには、少ない量にし、飲用回数をわけること、温めて飲むこと、乳糖分解済みの牛乳、ヨーグルトなど乳糖量の少ない乳製品を利用すること、などがさまざまな専門家により推奨されている。
私たち日本人は古来よりさまざまな食文化を取り入れて、栄養素の不足を補ってきた民族である。カルシウム摂取の重要性を知識として認識し、食生活を構築していただきたいものと思う。