1.はじめに
トウモロコシなど輸入される飼料原料の価格上昇から、国内で生産される飼料原料についての取り組みは全国各地で活発化しており、飼料用米の作付面積についても急拡大している(図1)。
農事組合法人京都養鶏生産組合(代表理事 西田 敏)は、経営の安定、自立を図るため、「ニワトリからエサまで、すべて国産を基本に卵はつくれないものか」との問い掛けから、トウモロコシの代替品として「コメ(飼料用米)」に着目し、平成17年から国産原料割合を高めた飼料による鶏卵づくりに取り組んでいる。
純国産種の採卵鶏を用い、飼料用米を主原料とし、外来魚を魚粉化して使うなど、すべて純国産に「こだわる」取り組みから、年間約18トン(1,000羽相当)の鶏卵が生産されている。国産化に伴い生産費は上昇するため、販売価格は高めとなるが、これについては、鶏卵の付加価値を高め、差別化を図るなどの企業努力が功を奏し、消費者を獲得している。
今回、当生産組合を訪問する機会を得たことから、国産原料割合を高めた飼料による鶏卵生産の取り組みについて紹介する。
|
図1 拡大する飼料用米の作付面積
|
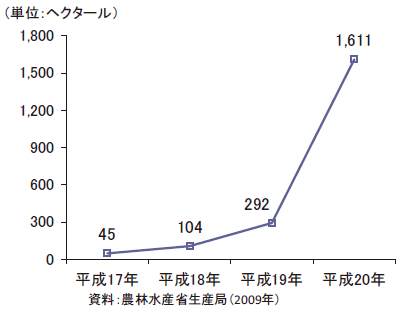 |
2. 養鶏場の概要 − 経営の「強み」は生産から販売までの一貫体制 −
(1)消費地へのアクセスには地の利
農事組合法人京都養鶏生産組合(昭和59年設立)は、宇治茶や世界遺産の平等院で知られる宇治市の隣、城陽市の東端に位置している。城陽市は、京都市と奈良市のほぼ中間で、京都市と奈良市からそれぞれ五里(一里は約3.7キロメートル)離れた距離にあることから「五里五里の里」と呼ばれており、消費地へのアクセスに地の利を得た地域である(図2)。
|
図2 「五里五里の里」と呼ばれる城陽市
|
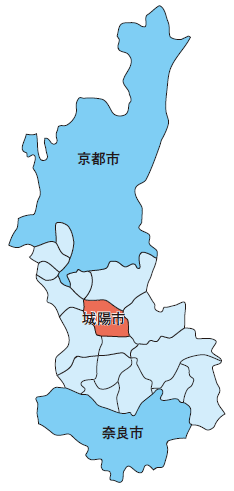 |
(2)採卵鶏は10万羽、19万羽まで拡大可能
同生産組合の従業員数は33名、敷地面積は広大で甲子園球場の約3倍となる約12ヘクタールである。この敷地に採卵鶏約10万羽(純国産鶏のゴトウ交配種さくらNEO(以下「さくら鶏」という。)と純国産鶏のゴトウ赤玉鶏もみじ(以下「もみじ鶏」という。)がそれぞれ年平均5万羽)を飼養し、日産約8万個の鶏卵を生産している。
鶏舎は、15棟で、成鶏、大すう185,000羽が飼養可能な13棟(木造、開放高床式鶏舎と平飼い鶏舎)と中すう、幼すう61,000羽が飼養可能な2棟(鉄筋、セミウインドレス鶏舎)から成る。現在の飼養羽数が約10万羽であることから、経営拡大に向けたポテンシャルは、著しく大きい(写真1)。
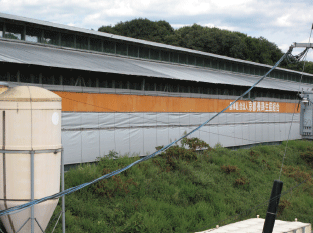 |
|
写真1 鶏舎は傾斜地も利用
|
(3) すべて国産原料により生産される卵は「京たまご・穀産(こくさん)」名で販売
販売する鶏卵の総称ブランド名は「京たまご」である。この総称ブランド名に、さくら鶏から生産される鶏卵は「京たまご・さくら」のブランド名で、また、もみじ鶏から生産される鶏卵は、与える飼料を違えることにより「京たまご・茶乃月(ちゃのつき)」と「京たまご・穀産(こくさん))」のブランド名で販売している。
さくら鶏には、非遺伝子組み換え(NON-GMO)で、収穫後に除虫剤を用いない(PHF)トウモロコシ、大豆かすなどが給与され、「京たまご・さくら」は生産されている。 当生産組合が特にこだわる鶏卵は、もみじ鶏が生産する「京たまご・茶乃月」と「京たまご・穀産」である。
京たまご・茶乃月は、その名が示すように、さくら鶏の自家配合飼料に地元名産である宇治茶の泥粉(どろこ:お茶の製造過程で発生し、ふるいの目に残らないもの)をベースとして、ハーブ、ゴマ、ヨード(海藻)などを加え生産されている。宇治茶などを配合したのは、鶏卵自体の品質を向上させるためであるが、お茶の成分に含まれるカテキンにより、鳥インフルエンザに対する抵抗力を付けさせたいとの意図からとしている。一方、京たまご・穀産は、すべて国産原料による飼料から生産されている。配合飼料中の約6割を構成するトウモロコシ全量をすべてコメ(飼料用米)に、また、残りの飼料原料もすべて国産にこだわるという全国でもまれな試みにより、年鑑約18トン(1,000羽相当)の鶏卵が生産されている。なお、ブランド名の「穀産」は「すべて国産原料」から生産されているという意味をダブらせ名付けたとしている。
鶏卵はそれぞれ、外見上、宇治茶とコメ(飼料用米)の影響を受け、京たまご・茶乃月の卵白色は、通常の卵白よりも無色透明度が高いという特徴が、また、京たまご・穀産の卵黄色は、鮮やかなレモンイエロー色(淡い黄色)という特徴を有している(写真2)。
 |
|
写真2 卵黄が鮮やかなレモンイエロー色の 「京たまご・穀産(こくさん)
|
3.トウモロコシに代わり飼料用米、大豆かすに代わり外来魚の魚粉 − 飼料原料の国産割合を高めたい −
(1)きっかけ
西田代表理事によると、養鶏飼料の原料価格が国際市場での価格変動にさらされ、経営に与える影響が小さくないことから、養鶏経営の安定、自立を図るために何とかしなければとの「危機意識」が、国産原料にこだわる発想のそもそもの出発点になっているとしており、平成16年頃から「飼料原料の国産割合を高めたい」と問い掛け、トウモロコシに代わる国産原料を探していたとしている(写真3)。
 |
|
写真3 西田代表理事の「問い掛け」
|
「コメ」を選ぶことになるきっかけは、飼料の主原料として米国ではトウモロコシが、また、欧州、豪州、カナダでは小麦・大麦が用いられており、各国で飼料原料とするのは、その土地で豊富に収穫され、安定供給される作物が選ばれていることに気付いたことによる。
このことは、「なぜ日本では、トウモロコシ見合いの栄養価を持ち合わせているコメを利用しないのか」という疑問につながり(表1)、また、地元では耕作放棄地や休耕田が見受けられることもあり、飼料用米を試してみることを考え始めたとしている。
|
表1 鶏におけるトウモロコシ、 もみ米の成分、消化率の比較
|
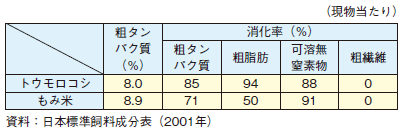 |
(2)卵黄のレモンイエロー色は「売り」
飼料用米の利用については、事前に「生存率」、「好んで食べるかという嗜好性」、「産卵個数、産卵重量などの生産性」、「卵の品質」、「卵の味覚」などを繰り返し調べ、トウモロコシを給与していないことから卵黄の色素成分となるキサントフィルなどが薄まり、卵黄が鮮やかなレモンイエロー色(淡い黄色)となる以外の影響は見られなかったとしている。なお、飼料用米は「もみ米」で給与されている。 西田代表理事によると、当初、卵黄がレモンイエロー色になることから「消費者に受け入れてもらえるか」と心配し、従来の卵黄色を出すためにパプリカ粉末などの色素を添加することも考えたそうである。
しかし、消費者に飼料用米から生産された鶏卵であると「きちんと」説明を繰り返すことで支持を得、今では当初の思いとは逆に、レモンイエロー色であることが国産原料のみ使用していることの「証」となり、また、飼料用米により鶏卵に含まれる脂肪酸組成が変化することから、栄養価の上からもお客の支持を得ることができ、販売価格は高めとなるが差別化が図られ、付加価値を高めた鶏卵としてのステイタス(地位)を得ているとしている。
購入客には、ホワイトロールケーキ、白いだし巻きなどでは、この鶏卵でなければならないとこだわる固定客が付くばかりでなく、健康に関心が高い消費者層にも受け入れられ、お客のすそ野は着実に広がりを見せているとしている。また、京たまご・穀産のブランドイメージにけん引され、他のブランドの売り上げも増加するというシナジー(相乗効果)も見逃せないとしている。
(3) 稲作農家は当初、うまいコメづくりに強い「思い入れ」
「コメ」への取り組みは、国産の食用玄米、古米の利用により行われていたが、価格が高くなることから、生産費の削減、また、安定的な調達に迫られていた。 このため、耕作放棄地や休耕田などを利用した飼料用米の栽培先を探し、どうにか城陽市、JA城陽などの協力を取り付け、平成17年に城陽市内の耕作放棄地や休耕田20アール(2反)での栽培にまでこぎ着けた。
飼料用米栽培の交渉では、購入価格面の折り合いでの労力以上に、稲作農家のマインドの中には、人間が食べるうまいコメをつくりたいとの強い「思い入れ」があり、これを説得することに、労力を費やしたそうである。
その後、岐阜県養老町で耕作放棄地や休耕田などを活用した飼料用米の栽培が始められていることを聞き、そこでは、稲作農家14戸が耕作放棄地や休耕田145ヘクタールに「クサホナミ」、「クサノホシ」、「はまさり」などが栽培され、地元の養鶏農家9戸向けに飼料用米1,000トン程度が生産されていたことから、岐阜県の飼料用米利用促進協議会(岐阜養鶏農業協同組合)にお願いし、安定した入手ルートを確立するに至った。
西田代表理事によると、飼料用米の栽培は、品種は変わるがコメづくりが続けられ水田が維持できること、栽培技術は食用のコメづくりと同じであること、また、新たに農器具を購入するなどの投資を必要としないことなどから、稲作農家にとってのメリットは大きいのではないかとしている。
しかし、その一方で、飼料用米の栽培は、補助事業の支えによる影響が小さくないことから、多収量品種などにより生産効率を高めるなど、生産費の削減に向けた経営努力が、今後の飼料用米の広がりに影響を与えるだろうとしている(写真4)。
 |
|
写真4 岐阜県養老町の飼料用米圃場、 これが養鶏飼料に
|
 |
|
写真5 フレコンバックに詰められ、もみ米ごと給与される飼料用米
|
(4) 大豆かすに代わり琵琶湖の外来魚を魚粉化
大豆かすに代わるたんぱく質源は、琵琶湖では厄介者とのレッテルが貼られている「ブルーギル」、「ブラックバス」などの外来魚(大部分はブルーギル)を魚粉化しており、外来魚は、国産原料の調達に寄与している(表2)。
西田代表理事によると、ほぼ100%の国産魚粉ということなら入手可能であるが、確実に100%の国産魚粉となれば入手は難しく、琵琶湖の外来魚を魚粉化する前は、国産に間違いない魚粉を手に入れるため、北海道、九州から取り寄せていた。このため、大豆かすに代わる身近な国産たんぱく質源を探していたところ、車で30分程度の距離にある琵琶湖で、年間400トン程度の外来魚が水揚げされ魚粉化されていることを聞き、平成18年頃から飼料に使えないものかとの検討を始めたとしている。
外来魚を魚粉化している滋賀県漁業協同組合連合会によると、外来魚から魚粉への重量歩留まりは1/4程度で、毎年100トン程度の魚粉がコンスタントに生産されていること、また、琵琶湖の魚粉は、魚のあらだけではなく魚を丸ごと魚粉化しているため、通常の魚粉よりもたんぱく質の含有率が高い特徴があるとしている。
西田代表理事によると、京たまご・穀産の生産に必要な魚粉は、1カ月当たり1トン程度であるため、数量的には問題なく、この取り組みは、当養鶏組合だけでなく琵琶湖の漁師の双方に大いに喜ばれているとしている。
|
表2 国産原料との代替関係
|
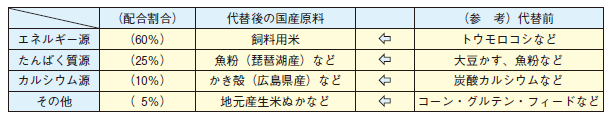 |
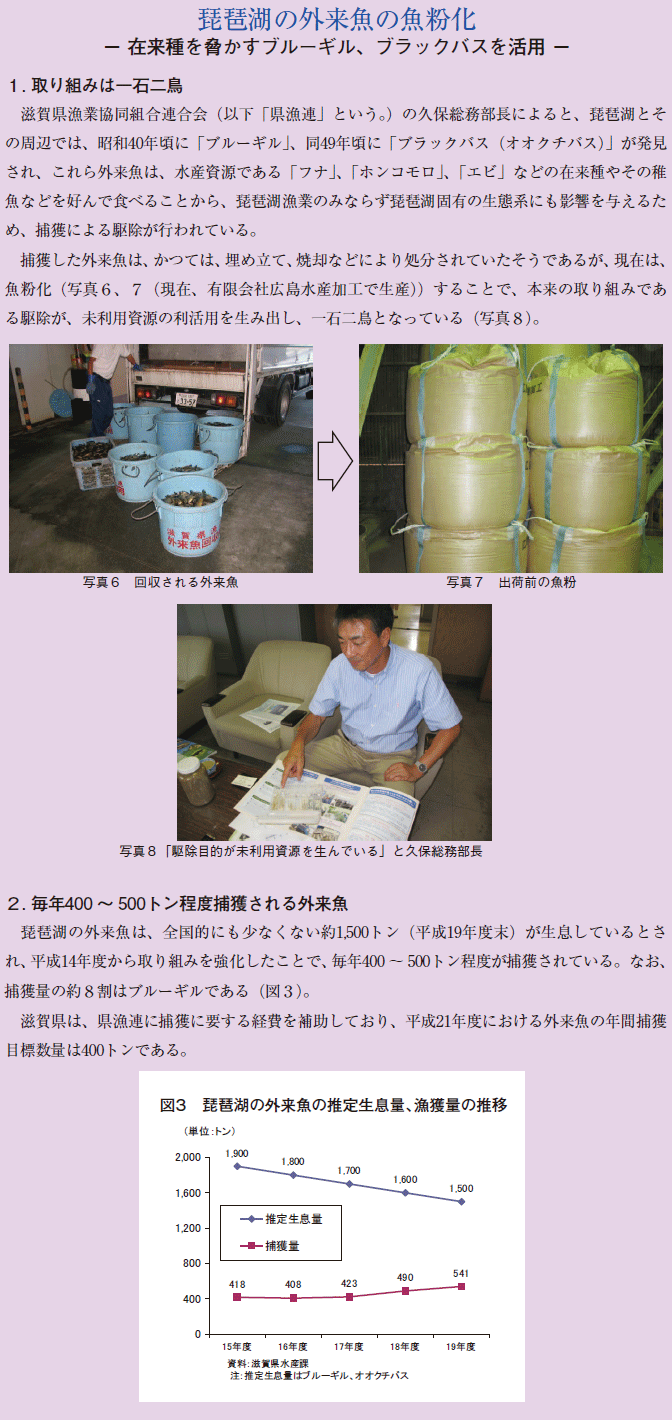 |
(5) 国産のカルシウム源として、広島産のカキ殻を
飼料用米や魚粉のほかにも、カルシウム源には、広島産のかき殻を粉砕し、また、地元の生米ぬかも飼料原料として用いるなど、国産原料にこだわる取り組みが行われている。京たまご・穀産の生産には、日量約100キログラムの自家配合飼料が必要となる。このための飼料調整の作業は毎日行われず、1週間〜10日分の使用量700キロ〜1トン程度がまとめて製造されている(写真9)。
 |
|
写真9 自家配合飼料を製造する撹拌機
|
 |
|
写真10 発酵エコ・フィード施設
|
4.おわりに
トウモロコシを全量「コメ(飼料用米)」に代え、残りの飼料原料も国産にこだわる鶏卵づくりは全国でもまれな試みである。
飼料用米の作付面積は拡大し、今後ますます生産量の増加が見込まれる一方、飼料用米は、生産費の削減が課題となっていること、加えて、国の補助事業により支えられている部分が大きいことから、その導入については、生産する稲作農家側と利用する畜産農家側の双方において、二の足を踏む者が少なくないようである。
しかし、今回訪問した生産組合で話を聞くと、単純に、飼料原料の内外価格差を比べることだけに焦点を絞っていない。飼料用米などによる国産原料の利用拡大は、飼料原料の国際価格の動きが、経営見通しをたてにくくしている中で、販売価格は高めとなるが、経営の安定、自立を図るためには、必然的に、飼料原料の国産割合を高めなければならないとする考え方が、経営の背中を後押ししているからである。
販売に当たっては、付加価値を高め、差別化を図るなどひと工夫凝らさなければならないが、この考え方は、今後、稲作農家、畜産農家の双方において徐々に広がっていくのであろう。