1.はじめに
2005年に策定された「新たな食料・農業・農村基本計画(以下、新基本計画)」では、稲わらや飼料用イネの利用拡大などにより粗飼料自給率を2005年度の75%から100%へ、また、食品残さなどの飼料化により濃厚飼料自給率を2005年の11%から14%へそれぞれ向上させることにより、飼料自給率を2005年度の25%から35%へと大幅に引き上げることが目標として掲げられている。そうした中、1990年以降、減少傾向にあった飼料作物の作付面積は、濃厚飼料の価格高騰に伴う青刈りトウモロコシや飼料用イネの作付面積の増加により、2008年には前年度に比べ4,300ha増加した。このように2008年度に飼料作物の作付面積の減少傾向に歯止めがかかったことは、それ自体大きな意味を持つものの、掲げられた政策目標を達成するには、さらなる飼料作物の作付面積拡大と収量の増加への技術革新が必要であると考えられる。また、自給飼料生産のみならず、これまで廃棄されてきた未利用資源を有効活用していくことで、さらに飼料自給率を向上させていくことが可能になると期待できる。
そこで本研究では、粗飼料自給率が高く、土地利用型畜産の色彩が強い和牛繁殖経営(または繁殖肥育一貫経営)を対象に、繁殖雌牛飼養における飼料給与構成の変遷を概観した上で、国産飼料の給与・利用に創意工夫を凝らしている和牛繁殖経営の事例を取り上げ、今後の国産自給飼料生産の方策について検討することを目的とする。
2. 自給飼料の変遷
1970年代、わが国における肉用牛繁殖経営部門は、小頭数飼養で、稲作などの耕種作物生産に対する副業的な位置づけであった。そうした時代には、和牛飼養のための給与飼料は、野草や牧草などの粗飼料はほとんど国内で自給され、また濃厚飼料である屑米・砕米、大麦や米ぬかなども自給されていたので、これらの飼料のみで必要な栄養のほとんどを賄うことができていた。しかし、その後のわが国の畜産は、飼養頭数の拡大と専業化に伴い、海外からの輸入飼料に依存した加工型畜産へとその性質が大きく変貌していった。
|
表1.全国平均的給与飼料構成の変遷1)2)
|
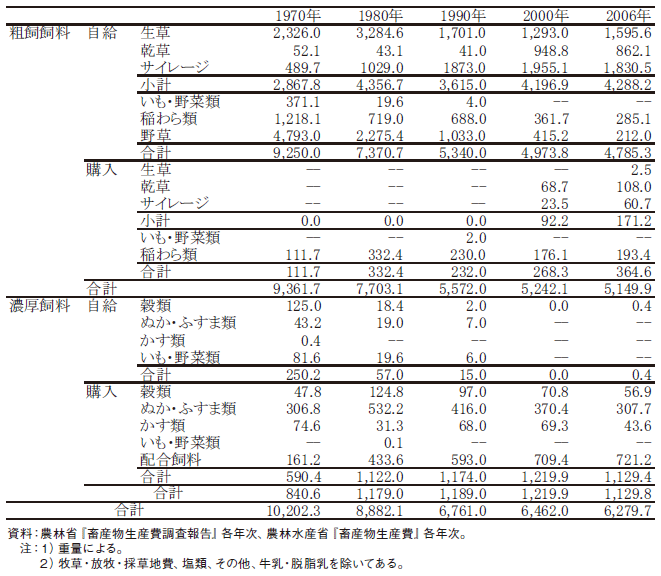 |
表1は、繁殖経営において粗飼料の自給率が100%であった1970年から2006年までの繁殖経営における飼料給与の構成を示したものである。粗飼料については、1970年には給与量のおよそ半分を野草が占めていたが、その後、採草地や放牧地などの減少に伴い、野草の給与量は大きく減少した。また、1970年には、いも・野菜類や稲わらも粗飼料としてかなり給与されていたが、その後、そのような粗飼料の給与量は大きく減少していった。牧草に関しては、1980年代までは、生草での給与が多かったが、飼養者の高齢化に伴う労働力不足、飼料生産技術の向上や専用収穫機の発達に伴い、乾草、サイレージでの給与へとその給与形態が変化していった。他方、濃厚飼料に関しては、1970年代には穀類、ぬか・ふすま類などの農作物の副産物が自給濃厚飼料としてさかんに給与されていたが、1980年代以降はその量が大幅に減少し、1990年代以降はほとんど給与されなくなり、これらに取って代わって農家外から購入された配合飼料の給与量が大きく増加した。
3.自給飼料の給与に創意工夫を凝らしている経営事例
本章では、実際に筆者らが聞き取り調査を行った経営の事例調査の結果を紹介する。事例調査で取り上げた経営の概況は表2に示すとおりである。以下では、和牛繁殖肥育一貫経営(AおよびB)および繁殖経営(C)の計3戸の事例を取り上げ、粗飼料を中心とした飼料生産および飼料確保のあり方についての検討を行った。また、事例調査に際しては、1)農家の概況、2)飼料確保の概況、3)たい肥利用、4)創意工夫点、5)今後の取り組みの5点に着目し調査を行った。
|
表2.調査農家の概要
|
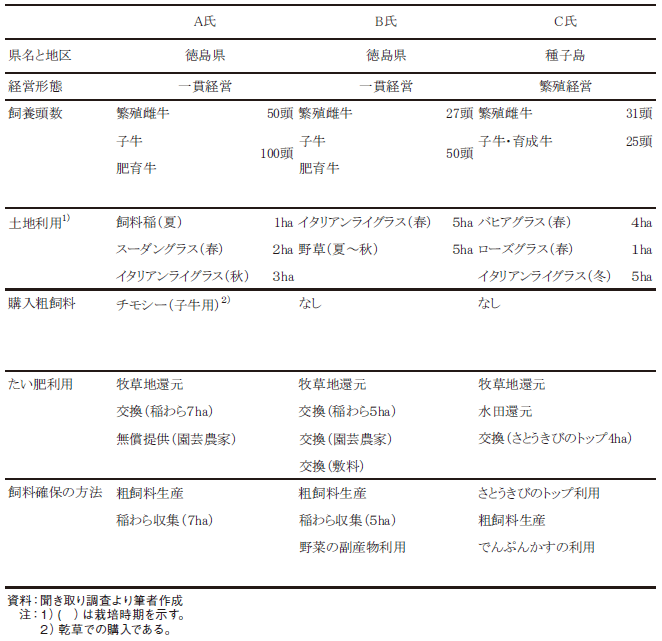 |
(1)A氏:繁殖肥育一貫経営
1)農家の概況
徳島県のA氏の父親は家畜商を営んでおり、10頭前後のホルスタイン乳牛を飼養する酪農経営であった。A氏は父親の影響もあり、高校を卒業した昭和45年より酪農経営を始めた。当時、周辺の酪農家は、妊娠牛を購入することで規模拡大を図っていたが、A氏は北海道から妊娠していない雌牛を購入することで規模拡大を図った。その理由は、妊娠牛は高価で購入には借金することが必要であったが、非妊娠牛ならば妊娠牛1頭の価格で3〜4頭購入できたからであった。
昭和50年代後半より、乳価の下落とともに交雑種を導入し一貫経営を開始した。A氏は、交雑種の増頭を図るとともに乳用種をとう汰していき、品種の転換を図っていった。当時の飼養頭数は、繁殖牛45〜50頭、肥育牛25頭であった。平成に入り乳用種をすべてとう汰し、本格的に交雑種の飼養を開始した。その後、A氏はBSEの発生を契機に、交雑種飼養を中止し、黒毛和種との入れ替えを行い、自家繁殖雌牛の保留と粗飼料生産に力を入れていった。その理由は、子牛市場や輸入飼料の価格変動によるリスクを回避するためであった。 現在、A氏の経営では、黒毛和種の繁殖雌牛50頭、子牛・肥育牛100頭を飼養しており、年間40〜50頭出荷している。出荷する枝肉成績はすべて4・5等級である。また、繁殖雌牛の分娩間隔は12〜13ヵ月であり、ほとんどの繁殖雌牛で1年1産を達成している。
2)飼料確保の概況
酪農経営開始当初、A氏は水田70aの裏作にイタリアンライグラスを作付けし、その他の粗飼料は、北海道からチモシー乾草を購入していた。当時、A氏の経営では、所有地での粗飼料生産による粗飼料確保は困難であったため、稲わら、麦わらなどの粗飼料を近隣農家から収集し、給与していた。さらに、麦ぬか、酒ぬか、おから、ビールかす、みかんや竹の子の皮などの農作物の副産物も積極的に集め給与していた。
昭和50年代に入り、転作の強化が図られるようになり、トウモロコシやソルガムの作付けを行うようになった。また、同時に近隣農家の高齢化が進んだことから、A氏に水田を預けてくれるようになった。その結果、土地の集積が3haまで拡大し、夏にはトウモロコシとソルガム、冬には裏作としてイタリアンライグラスの生産が可能となった。
現在A氏は、春に飼料用イネを1ha、スーダングラスを2ha栽培し、スーダングラスは2回刈りを行い、冬期の粗飼料として利用している。秋にはイタリアンライグラスを3ha栽培し、春先の粗飼料として給与している。また、たい肥との交換により稲作農家から稲わらを7ha分収集している。A氏の経営では、4ヵ月齢までの子牛に対してのみ購入したチモシー乾草を給与している(図1)。
|
図1.A 氏の経営における資源利用の流れ
|
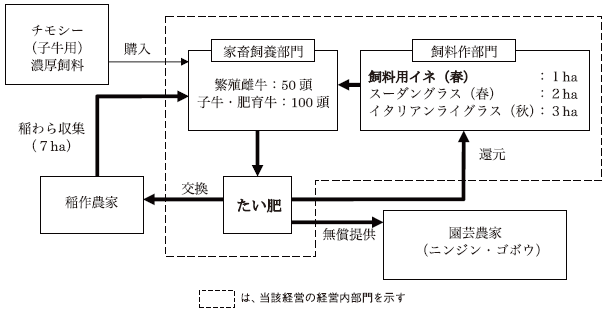 |
3)たい肥利用
たい肥処理に関しては、A氏はたい肥舎を自己所有しており、たい肥生産を行っている。たい肥の熟成期間は季節によって多少の変動はあるが、およそ1ヵ月間である。たい肥の利用として、春先に所有地の水田および牧草地への還元を行っている。5月以降に造られるたい肥は、自身のたい肥舎に堆積させておき、12月に稲作農家の稲わらと交換している。また、余剰たい肥は、ニンジン、ゴボウを栽培している園芸農家に無償で提供している。そのため、たい肥の余剰は発生しておらず、たい肥は経営内および地域内で完全に循環している。
4)創意工夫点
A氏は、稲作農家とたい肥の交換により7ha分の稲わらを収集している。収集した稲わらは、経営内のビニールハウスで乾燥させ、タイトベーラーで梱包し給与している。また、収集した稲わらは、その品質により、乾燥期間を調整しながら給与量を変えている。こうした作業は手間がかかるものの給与ロスが少なく、嗜好性も良好であった。その結果、繁殖雌牛の受胎率も向上し、分娩時の事故・死産などもBSE発生以降、A氏の経営では発生していない。
5)今後の取り組み
近隣農家から水田を借りているため、水路の管理を含めた水田の維持・保全を行っていく必要がある。飼料用イネの生産は、粗飼料確保の点からは重要であるが、育苗や除草など手間のかかる作業が多く、労働強度は高いが、近隣農家との関係などの地域性を考慮した場合、飼料用イネ生産を継続していくことは重要であると考えている。今後は、A氏自身が56歳という年齢の問題もあり、現在の飼養頭数より若干少ない繁殖雌牛40頭、子牛肥育牛80頭規模の経営を行っていきたいとの意向である。
(2)B氏:繁殖肥育一貫経営
1)農家の概況
徳島県のB氏は、両親が酪農家であったこともあり、20歳の時から牛の飼養を開始した。昭和50年代後半から牛乳が余りだし、乳価が低迷したことを契機に、昭和59年、乳用種の肥育経営へと転換した。昭和60年代前半には、大阪の知人を通じて知り合った酪農家から交雑種を購入し、交雑種肥育を開始した。しかし、BSEの発生により交雑種の枝肉価格が低迷したため、黒毛和種の繁殖肥育一貫経営へと転換し、現在は、繁殖雌牛を27頭、子牛・肥育牛を50頭飼養している。
B氏は受精卵移植を積極的に活用し、優良牛の効率的な飼養を行い、枝肉成績の向上に努めている。受精卵移植での受胎率は5割程度で、今後7割を目標としている。種付けは平均2回行っているが、平均以上の受胎率を確保している。また、分娩間隔も短く、ほとんどの繁殖雌牛で1年1産を達成している。B氏は、このことは良質の粗飼料給与のおかげと考えている。
また、肥育牛は28〜30ヵ月齢、出荷体重は700〜750kgで出荷し、枝肉重量は450〜500kg、枝肉の格付けは、すべて4・5等級となっている。
|
図2.B 氏の経営における資源利用の流れ
|
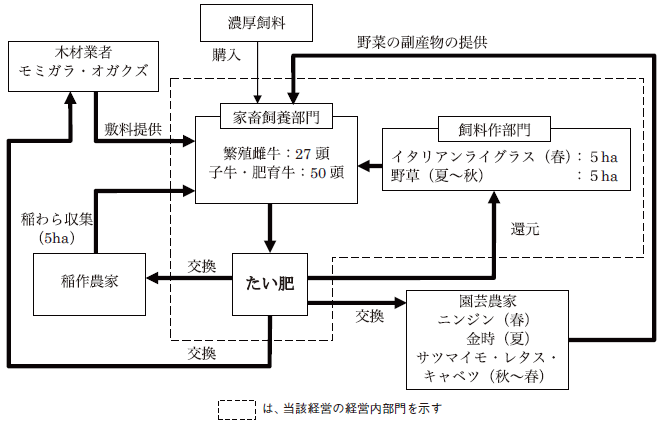 |
2)飼料確保の概況
図2は、B氏の経営における資源利用の流れを示したものである。B氏の経営の特徴は、河川敷の占有許可を得た敷地を利用し、粗飼料生産を行っていることである。
B氏は、河川敷の敷地でイタリアンライグラスを5ha栽培し、春先に1番草、7月に2番草を刈り取っている。イタリアンライグラスの収穫後、野草をまいて、3回刈りを行い、サイレージとして給与している。こうした野草は、さまざまな草種による微量元素のバランスが良く、特に窒素含量が少なく、カロテン含量が高いため、繁殖雌牛の受胎率に大きく貢献しているとB氏は考えている。
またB氏は、3戸の稲作農家とたい肥の交換により稲わらを5ha分収集している。毎年、稲わらの収集にかかる日数は延べ10日程度である。稲わらは、倒伏しておらず刈り取りやすいほ場で行っている。そのため気候条件などが整えば、あと3ha程度の稲わらの収集が可能であると考えているが、肥育牛に給与する稲わらが余り気味であるため、現在は、稲作農家から稲わらを集めることを制限している。収集した稲わらを給与するときは、繁殖雌牛と子牛にはそのまま給与するが、肥育牛には、1年間置き、ビタミンを抜いてから給与するようにしているそうである。
その他の粗飼料の確保に関してB氏は、近隣の園芸農家から、春にはニンジン、夏には金時、秋から春にかけてはサツマイモ、レタス、キャベツなどの余剰品や規格外品(野菜の副産物)を提供してもらっている。その代わりにB氏は園芸農家に対してたい肥を提供している。提供してもらった野菜の副産物の栄養価は濃厚飼料に近い水準であるため、給与過多とならないように注意している。また、繁殖雌牛に対して稲わらを給与すると繁殖成績が低下したが、野菜の副産物を給与することで繁殖成績の改善が見られた。特にレタスの葉を給与すると繁殖成績が向上したため、B氏にとってレタスの葉は、繁殖雌牛の貴重な粗飼料となっている。
3)たい肥利用
B氏はたい肥舎を自己所有しており、たい肥生産を行っている。園芸農家とは、たい肥と野菜の副産物の物々交換をしており、また稲作農家ともたい肥と稲わらの交換を行っている。こうした園芸農家や稲作農家とのたい肥交換の際、B氏は、ショベルカーやダンプカー、マニアスプレッターを無償で貸し出している。園芸農家や稲作農家は、B氏のたい肥舎からたい肥を持ち帰り、各自の所有する農地に散布している。また、木材業者もたい肥をもらいに来ており、その際、モミガラやオガクスなどの敷料をB氏に提供している。
このようにB氏は効率的なたい肥利用を行っているが、余剰が発生したときには、自身の所有する牧草地に還元することにしている。しかし、近年はたい肥に対する需要が高まっているため、たい肥の供給量が追いついていない状態である。
4)創意工夫点
以前、B氏は輸入粗飼料を購入していたが、繁殖雌牛の受胎率が低かったため、輸入粗飼料の購入を止め、自給粗飼料の生産に力を入れるようになった。B氏は、自給粗飼料に見合った頭数規模の経営を心がけている。そのため、河川敷の占有許可を取得し、牧草地での粗飼料生産を行い粗飼料の確保を行っている。さらに、近隣農家とたい肥の交換により稲わらや野菜の副産物を収集するなどの工夫を凝らしている。また、B氏は、粗飼料生産に必要な収穫機などを所有できていることが粗飼料生産の優位性を生んでいると考えている。そのため、機械を10年以上更新しないで済むように機械のメンテナンスに力を注いでいる。
5)今後の取り組み
現在、稲わらが余り気味であること、たい肥の需要に対応しきれていないことなどから、肥育牛を増頭する意向を持っている。また、5割程度である現状の受胎率を7割程度まで引き上げることを課題としている。
(3)C氏:繁殖経営
1)農家の概況
鹿児島県種子島のC氏は現在、繁殖雌牛31頭、育成牛3頭、子牛22頭を飼養する繁殖経営である。子牛の1日当たり増体量は、雄子牛で1.0kg、雌子牛で0.9kgを達成している。子牛の出荷は8ヵ月齢であり、出荷体重は250kg前後となっている。
繁殖雌牛の受精は1回で種がつき、受胎率はほぼ100%に近い数字となっている。分娩間隔は12.5ヵ月とほぼ1年1産の繁殖体系となっている。
また、C氏は、パソコンの利用にも長け、繁殖雌牛の分娩日を入力するだけで、次回発情発生日や分娩日、さらには出荷日時までを逆算することが可能なプログラムを利用している。このようにC氏は、詳細な予定を把握しながら飼養管理を行っているため、発情の見逃しなどの飼養管理ロスが非常に少なくなっている。
2)飼料確保の概況
C氏の経営における資源利用の流れを示したのが図3である。C氏の経営の特徴は、サトウキビとでんぷんかすを利用することで飼料コストを極めて低い水準に抑えている点である。
|
図3.C 氏の経営における資源利用の流れ
|
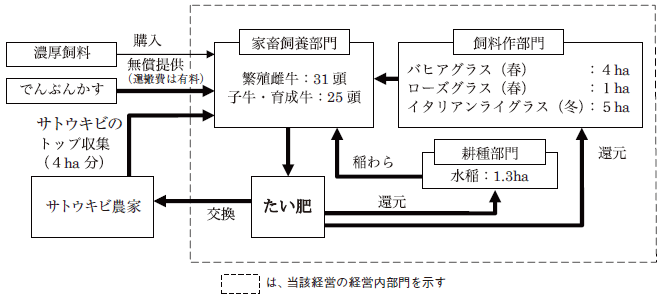 |
C氏は、春にバヒアグラス4haとローズグラス1haを栽培し、秋から冬にかけての粗飼料として利用している。また、冬にはイタリアンライグラスを5ha栽培し、春から夏にかけての飼料として給与している。さらに、トップと呼ばれるサトウキビの梢頭部を近隣のサトウキビ農家から4ha分収集している。サトウキビのトップは、サトウキビ農家が収穫した際にC氏の牛舎へ運んできてもらっている。給与期間は、12月から翌年の4月までである。その他の粗飼料として、所有する水田1.3haからの稲わらを給与している。また、粗飼料が不足している時期は、C氏が所有している1haの放牧地に昼間、放牧し野草を採食させている。
C氏は粗飼料以外にも濃厚飼料の確保も行っており、近隣の工場よりでんぷんかすを無償で提供してもらっている(なお、運搬費は農家が負担)。でんぷんかすは、風味が良く、極めて嗜好性が高い飼料となっている。C氏は、でんぷんかすを利用しているため、繁殖雌牛の繁殖成績が良好な成績となっていると考えている。こうしたでんぷんかすの利用は、以前C氏が養豚経営を行っていたときに給与していた経験に基づくものである。
3)たい肥利用
たい肥処理に関しては、C氏はたい肥舎を自己所有しており、たい肥生産を行っている。たい肥利用の内訳は、自作地への還元とサトウキビトップとの交換である。自作地への還元に関しては、牧草地5haに12月から2月の間に10a当たり4tのたい肥を還元している。また、水田にも10a当たり4tのたい肥を還元している。さらに交換に関しては、サトウキビのトップを供給してくれるサトウキビ農家とのたい肥の交換を行っている。サトウキビ農家とのたい肥の交換量は、1年間で軽トラックおよそ50台分である。
4)創意工夫点
C氏は、たい肥との交換でサトウキビのトップを4ha分確保している。また、でんぷん工場よりでんぷんかすを無償で提供してもらっていることから、飼料コストが極めて少ない経営となっている。さらに、パソコンを駆使し、計画的な飼養管理に努めている。
5)今後の取り組み
C氏の息子が後継者として経営を継ぐことが決定しているが、現在は果樹作に従事している。今後、息子に飼養管理の技術を伝えていくことが重要な課題となっている。また、C氏の経営では、経営内での飼料供給量に見合う飼養頭数で飼養管理を行っていく意向を持っている。そのため、牛舎の増設による規模拡大を目指すのではなく、生産費の削減とともに繁殖雌牛の繁殖成績、子牛成績の向上などの飼養管理技術を磨いていくことが重要であると考えている。
(4)調査のまとめ
本章では3戸の個別経営の事例を取り上げ、それぞれの農家における粗飼料生産および粗飼料確保のあり方についてみてきた。これらの事例調査より各々の経営の特徴をまとめると以下のようになる。
A氏は子牛にのみ購入したチモシー乾草を給与していたが、繁殖雌牛に関しては完全な自給粗飼料による飼養であった。A氏は、飼料生産農地の集積により牧草地を確保し粗飼料生産を行っていたことに加え、たい肥との交換により稲わらを7ha分収集することで粗飼料の確保に努めていた。
次いで、B氏は、河川敷の占有許可を得た敷地5haで粗飼料生産を行っていることに加え、たい肥との交換により5ha分の稲わらを収集していた。さらに、園芸農家から野菜の副産物を収集することによって粗飼料を確保していた。
最後、C氏の経営では、5haの牧草地において粗飼料を生産していることに加え、たい肥の交換によりサトウキビのトップを4ha分収集し、粗飼料を確保していた。さらに、近隣の工場よりでんぷんかすをもらい受け、ウシに給与することで濃厚飼料の確保も行っていた。
以上、事例として取り上げた経営の特徴をまとめたが、その中で、たい肥を有効活用し稲わらなどの粗飼料を確保していること、野菜の副産物利用、サトウキビのトップの利用、野草の利用など、未利用資源を有効活用し粗飼料確保を行っていることは評価されるべき事実であると考えられた。
4.おわりに
本研究では、繁殖雌牛飼養における飼料給与構成の変遷を概観した上で、和牛繁殖経営および和牛肥育繁殖一貫経営を行っている3戸の農家の事例を取り上げ、自給飼料生産の実態把握を行ってきた。繁殖雌牛飼養における飼料給与構成の変遷をみてみると、粗飼料自給率が100%であった1970年では、粗飼料の大半を野草が占めているとともに、いも・野菜類や稲わらも自給粗飼料としてかなり給与されていた。また、濃厚飼料は、穀類、ぬか・ふすま類などが自給濃厚飼料として給与されていた。また、本研究で取り上げた事例では、経営内の飼料生産のみならず、たい肥との交換により稲作農家から稲わらを収集したり、園芸農家から野菜の副産物を収集したりすることで、粗飼料の確保に努めていた。さらには、C氏のように近隣のでんぷん工場よりでんぷんかすを収集することで濃厚飼料の確保を行うなど、各々の経営において創意工夫を凝らした飼料確保を行っていた。
以上、本研究の事例で取り上げた個別経営では、粗飼料を有効活用しながら繁殖成績や枝肉成績が良好な家畜生産を行っていた。このことより、国産自給飼料多給による家畜生産は可能であることが示唆された。先に示した新基本計画の飼料自給率を達成するためには、本研究で取り上げた個別経営の事例のように、1970年代に利用していた飼料を再評価し、利活用していくことは有効な方策であると考える。特に、稲わら、野菜の副産物やかす類などは、日常生活の中から容易に入手できる飼料である。今後は、こうした飼料を再評価するとともに、畜産農家と耕種農家が連携し、地域内で飼料の有効活用が図れる生産システムを構築していくことが重要である。
謝辞
本研究は独立行政法人農畜産業振興機構の「平成20年度畜産物需給関係学術研究情報収集推進事業」によるものである。このような研究機会を与えていただいた同機構に深く感謝の意を表する。また、調査にあたっては、徳島県立農林水産総合技術支援センターおよび西之表市役所農林水産課の関係者の方々に御協力いただいた。重ねて深く感謝の意を表する。