【要約】
「大雪区域畜産基地建設事業」により町内の広大な農地を草地造成・粗飼料基盤整備し、大規模にアンガス牛を導入。コープさっぽろなどとの取引で事業は順調に進んでいたが、牛肉輸入自由化の波にのまれ、2001年にはアンガス牛は上川町から姿を消した。深刻な後継者難・担い手不足に「戸別農家の規模拡大」や「第三者継承」、「新規就農」など、戸別をベースに対応するのではなく、全町対象とした作業請負組織「農業生産法人(有)グリーンサポート」を設立し、一方で労力不足の農家の作業を請け負い、他方で法人格を取得することにより「新たな担い手」候補者を募集、養成することを通じて地域農業の維持・発展を図る上川町の農業生産法人における事例について報告する。
はじめに
同居農業後継者を確保しているのはわずかに1万戸余、20.9%。2005年センサスが伝えた北海道農業の実態である。「後継者難」や「跡継ぎなし高齢農家」問題には以前から様々な対応策がとられてきた。しかし、せっかくの努力もなかなか実を結ばず、事態がますます悪化の方向をたどってきたことを、それら数値は物語っている。親と同居していない後継者や後継者と目される子息がまだ年少のため確定していないところもあり、5軒に4軒の割合で後継者が確保されていないと見ることはできないが、いずれにしろ深刻な後継者難、担い手不足に見舞われていることだけは疑いない。事実、農村を回ってみてもいつも耳にするのは高齢化問題と後継者不足問題であり、「確保しているのは良くて5〜6割」「ここの集落ではほんの数軒だけ」などとの話しを良く耳にするからである。
農業の後継者、担い手をいかに確保していくのか。域内自給率200%余を誇り、「わが国の食料基地」としての北海道農業が抱える現実であり極めて重要な課題である。
今回は、このような課題を町あげての集団的な対応で後継者・担い手確保難に挑み、大きな成果を残してきている北海道上川支庁管内上川町の事例を紹介する。そこでは、畜産(肉用牛)と畑作を複合的に営み、また交換耕作のセンター的な役割を果たしている超大規模法人「農業生産法人(有)グリーンサポート(以下、「グリーンサポート」という。)」が、その主役の座を担っている。
1 上川町とグリーンサポート
上川町は、旭川市から高速道路を車で走ること1時間余。北海道が誇る名峰「大雪山系」黒岳の北方に添うように展開する総面積1,049平方キロメートル、人口4,300人程の町である。町内に柱状節理の岩肌や大滝、「氷瀑祭り」などで名高い層雲峡温泉を抱え、観光地としても有名なところである。周囲を美しい山々に囲まれ、風光明媚この上ないとは言え、気候条件は「内陸性」的で至って厳しく、特に冬期には積雪も多く、気温も−20℃を下回る日も珍しくない。農業、林業、そして温泉・観光業を主力産業としてきたが、林業は一時の勢いを失いつつあり、温泉・観光業が農業と並ぶ地域の基盤産業になっている。
上川町では2,400ヘクタールの農地に68戸の販売農家が展開し、米や野菜、豆類などの耕種作物や肉用牛・生乳などの畜産物を生産している。2,400ヘクタールを68戸で除すと一戸当たり約35ヘクタールとなり、「比較的大規模な農家群が展開している」と思われそうであるが、残念ながらそうはなっていない。10ヘクタール以上層が25戸と37%に止まっているのに対して、自給的農家水準に近いと思われる3ヘクタール未満層は22戸と3分1も占めている。これらの数値は「規模拡大し大規模経営を」という指向が弱かったこと、反対に「規模縮小」的な指向が強かったことを示唆している。事実、「150戸のJA正組合員のうち現役は50戸ほど」、「農地は持っているが今はやっていない人も沢山いる」との担当者の返答である。
こうした規模縮小指向には、各種農業政策や価格低下など、特に後継者難・担い手確保難が強い影響を与えた。それは、北海道農村一般に見られる問題であるが、こと上川町のような大都市圏・消費地から遠隔地に当たる地域には特に強く現れざるを得なかった。前述の150戸のうち100戸ほどは既に「非現役」=脱農者という現実は、そのことを雄弁に物語っている。これを放置すれば、地域農業どころか、地域そのものの崩壊につながりかねない。1990年代後半頃に、上川町農業が直面していた極めて重要で深刻な課題であった。
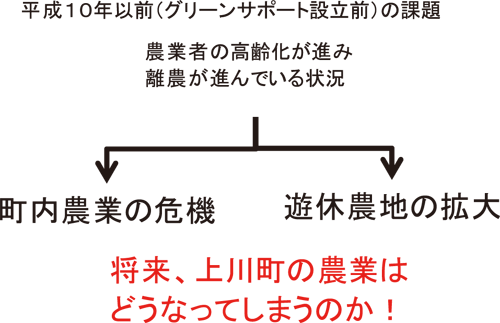 |
後継者難・担い手不足を背景に、下降=規模縮小指向がますます強まる中で、上川町が見出した対応・解決方向は、俗に「上川方式」とも呼ばれ、今では道内でも有名となった後継者難・担い手不足への全地域的・集団的対応策である。それは簡潔に言えば、深刻な後継者難・担い手不足に「戸別農家の規模拡大」や「第三者継承」、「新規就農」など、戸別をベースに対応するのではなく、全町を対象とした作業請負組織「グリーンサポート」を設立し、一方で労力不足の農家作業を請け負い、他方で法人格を取得することにより「新たな担い手」候補者を広く募集、養成することを通じて地域農業の維持・発展を図っていこうとする戦略であった。グリーンサポート設立以降、上川町の農業産出額は反転、上昇傾向を見せており、その戦略は見事に当たったと評しても良いかもしれない。
図1 「上川方式」における各主体の位置づけ |
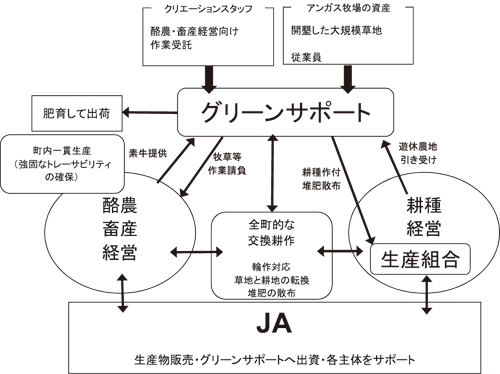 |
資料:グリーンサポート・JAへの聞き取り調査(2010)を元に筆者作成 |
2 グリーンサポート設立への二つの底流−地域農業の危機と共同・協同の伝統
「グリーンサポート」は、JA上川町、上川町、農業改良普及センターの呼びかけに応えて1998年2月に結成・設立された。その出資者は水田農家1戸、畑作農家1戸、酪農の法人2戸・個人1戸、JA上川町、アンガス牛肥育牧場の職員3人の計9人。
しかし、幾ら深刻な後継者難・担い手不足に陥っていたとは言え、それが一朝一夕に、何もないところから急に結成・設立されたわけでは決してない。そこには二つの共同・協同の貴重で長い、また苦さも含んだ経験・歴史が流れていた。
その一つは、酪農部門における協業法人の設立・運営と共同利用施設・組織の設立・運営である。上川町では1992年から1995年にかけて公社営畜産基地建設事業が実施され、その中で大規模な酪農協業法人2戸とこれも大規模な酪農個人経営2戸が誕生した。そして、これらの大規模経営を支える組織として、乳牛育成施設「フロンティ」と粗飼料生産の共同作業組織「クリエーションスタッフ」が結成された。育成部門と粗飼料生産部門を共同・協同化し、大規模経営を労働力面からサポートする。「フロンティ」は現在も稼働しており、また、「クリエーションスタッフ」は、酪農家が牧草などの収穫作業に出役し、共同で作業するというもので、それは今日、グリーンサポートへと受け継がれ「作業受託部門」の基盤になっている。
図2 グリーンサポートの部門構成と役割 |
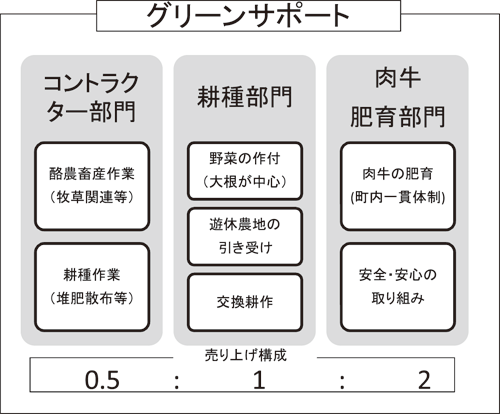 |
資料:グリーンサポートへの聞き取り調査(2010)を元に筆者作成 |
もう一つは鳴り物入りでスタートした「アンガス牛肥育牧場」である。1975年、上川町ではアンガス牛の繁殖・肥育を目的とした「大雪区域畜産基地建設事業」をスタートさせた。町内旭丘地域に600ヘクタールの草地を造成し、粗飼料基盤を整え、大規模にアンガス牛を導入する事業である。アンガス牛の繁殖は13戸の畜産農家・法人が戸別に担当し、肥育は同じ13戸で別途「アンガス牛肥育牧場」を設立し、そこで共同で肥育し、販売する計画であった。造成草地の大方は肥育用の放牧地・粗飼料用地に使われ、また、牛・草地などの管理担当として数名の従業員を雇用した。コープさっぽろなどとの取引もあり、当初は順調に進んでいたアンガス牛事業も1990年頃からの牛肉輸入自由化の波にのまれ、価格低下に見舞われ、次第に立ちいかなくなった。そして、ついに2001年、アンガス牛は上川町から姿を消すのである。
アンガス牛不振が続く中で、広大な放牧・採草地及び「アンガス牛肥育牧場」の後処理、職員の雇用問題が次第に浮上してくることになる。様々な検討の末に出した結論は、「資源を地域農業振興にいかに生産に振り向けていくのか」、また「共同の経験などをいかに次につなげていくのか」という前向きの視点を持って考えていこうということであった。広大な放牧・採草地を耕作放棄地にしてはいけない。また、後継者難・担い手不足を何とかしなければ上川町農業の未来はない。こうした苦悩の中から出てきたのは、「グリーンサポート」の設立につながる多面的機能を持った組織の設立であった。とは言え、皆がその方向に確信を持っていたわけではない。将来性に対する大きな不安もあったことも事実であった。
危機的様相を深める地域農業への熱い思い、共同・協同の経験と伝統などが、グリーンサポート設立につながった。
3 作業受託・耕種経営・肉牛肥育の三部門を持つグリーンサポート
1998年に設立されたグリーンサポートは作業受託部門、耕種経営部門、肉牛肥育部門の三つの部門を持つ。
作業受託部門は、出役制をとっていた粗飼料生産の共同作業組織「クリエーションスタッフ」を引き継ぎ、コントラクター部門として再編したもので、デントコーンや牧草などの飼料作物関係の諸作業を請け負っている。今は出役制はとられておらず、利用に応じて経費を負担するという形になっている。労働力に余力が生じた場合にはグリーンサポートへ出役し、作業労賃を獲得できるという道は残されている。不足する労働力を可能な限り地域内でカバーしつつ、酪農家等の支援も行っていこうとする知恵が働いている。なお、グリーンサポート関係農地は所有・賃貸地で350ヘクタール、作業受託等で1,000ヘクタール、合計1,350ヘクタールほどとされるから、全町の農地面積2,400ヘクタールの過半にグリーンサポートは関与している。
耕種経営部門は、アンガス牛肥育牧場から引き継いだ農地やその後、有償・賃貸などで集積した農地を使い、大豆・ライ麦や大根、ジャガイモ、カボチャ、アスパラなどの野菜類を生産する。町内で遊休農地を出さないように、離農跡地や規模縮小農家の農地を有償譲渡、あるいは長期賃貸借などで引き受けている。
注目すべき点は、この耕種経営部門が全町的な交換耕作のセンター役を果たしていることである。厳しい自然条件下にある上川町では、積算気温(作物の生育に必要な平均気温の積算温度)不足のため豆類の作付けが出来ないなど、充分な輪作体系が組めない地域が存在する。そうした不利を克服し、各農家・法人が充分な輪作体系を組め、地力の維持・増進によって収量と所得の増加とが図れるようにしようと全町的な交換耕作はスタートした。もちろん、グリーンサポートの持つ広大な農地も、重要な交換耕作の一環としてその中に含まれていることは言うまでもない。交換する農地の選定や小作料などの各種経費負担の調整は各農家の輪作状況や家畜たい肥の投入状況などを考慮しながら、農業者(地主)で作る独立の委員会、「農用地利用調整委員会」で行われている。特に家畜たい肥の投入状況が考慮されるのは、条件不利として交換に出された農地のほとんどがグリーンサポートに集まり、その地でグリーンサポートは大根を栽培するのを常としているからである。グリーンサポートがこうした交換耕作のセンター役を担っているのは、先に触れた設立の理念、また関与面積の多さからいえば当然と言えるかも知れない。
 |
肉牛肥育部門の主力、ホルスタイン |
「アンガス牛肥育牧場」を前身に持つ肉牛肥育部門では、ホルスタインとF1が肥育されている。主力はホルスタインであり年間約450頭が出荷され、うち約60%が生協へ出荷されている。子牛の100%が町内の酪農家で生産されるという完全「町内一貫体制」がとられている。子牛の移動距離は短く、環境変化も牛にかかるストレスも極めて少ない。「動物福祉」的であり、環境にも優しい21世紀型の畜産と言えるのかもしれない。もちろん、「安全・安心」がモットーで、トレーサビリティの担保(町内素牛農家→グリーンサポート→生協の流れであれば、これに勝るトレーサビリティ体制はないとさえ言える)、無農薬粗飼料100%自給、遺伝子組み換え飼料の不使用、抗生剤(モネンシン)の不使用などに取り組んでおり、「大雪高原牛」のブランドで出荷されている。また、生協との産直を契機に、消費者との交流も活発に行なわれており、2009年度には「コープさっぽろ農業賞大賞・北海道知事賞」にも選ばれており、上川町農業のPRに大きな役割を果たしている。
 |
町内一貫体制により、消費者へ「安心・安全」を届ける |
三部門の売上げは2009年度で、「コントラクター部門」約5500万円、「耕種部門」約1億3000万円、「肉牛肥育部門」約2億円となっており、それぞれの部門毎に「独立採算制」がとられている。2009年度には耕種部門で価格下落に見舞われ、通常2億円前後から7千万円ほど低下し、利益も1000万円に落ち込んだとされる。利益は出資者への配当には回さず、機械の更新・拡充等へ向けて内部留保している。
 |
消費者との交流の様子 |
4 担い手確保にひとまず成功。しかし新たな課題も
本稿の主題である後継者・担い手確保の地域的・集団的対応について見ていくことにしよう。
グリーンサポートの役員は元畑作農家の藤田輝男社長を先頭に、出資者を中心に6名。大方が50歳台とされ、全員農作業に当たっている。設立が今から十数年程前の1998年であったから、40歳代の「中堅の担い手」時代に彼らは参画したのである。上川町農業の動向からすれば10余年の歳月が流れる中で、もしグリーンサポートが設立されていなかったら、この中からも農業を離れざるを得ない方も出ていたかもしれない。また、地域の農家・法人でも事情は同じである。その意味で、相変わらず離農が続いていたとしても、グリーンサポートの設立によって、そのスピードは大いに穏やかなものになったことだけは間違いない。
この役員を支え共に作業に当たるのは従業員。いずれも30歳台未満の若者で、作業受託部門に2名、耕種部門に2名、肥育部門に2名の計6名が籍を置く。もちろん通年雇用で、3名は町内出身、3名は町外出身。更に農繁期(概ね5〜10月)にのみ雇用する「臨時雇用」が10名程度在籍する。また、直接グリーンサポートの雇用ではなく、酪農の協業法人から作業毎に出向してくる作業員(労賃をグリーンサポートが支給)も若干名、存在している。なお、それでも間に合わず、やむを得ず派遣従業員も雇い入れなければならない場合もあるという(図3)。
図3 グリーンサポートにおける従業員の構成 |
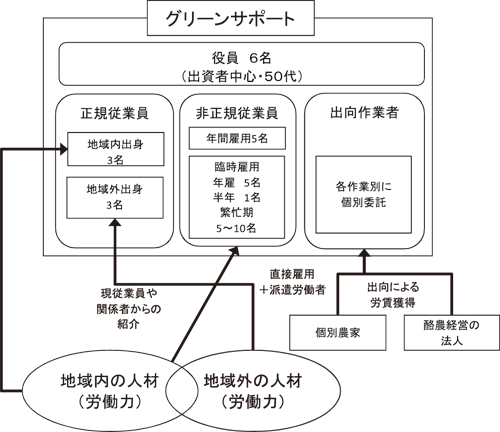 |
資料:グリーンサポートへの聞き取り調査(2010)を元に筆者作成 |
さて、これら従業員などを、グリーンサポートではどのように確保してきたのか。それが簡単でないことは容易に察しがつく。グリーンサポートでは発足当初から、広く町内外に呼びかけ、また、ハローワークや北海道農業会議など活用しながら、従業員の募集に努めてきた。そもそも地域農業の後継者・担い手の確保・育成がグリーンサポートの一つの大きな課題だったからである。しかし、いわゆる「公募」方式では、残念ながら目立った成果はなかなか得られなかった。いろいろ考えた末に思いついたのは、今働いている従業員の人脈を通じて募集するという方式である。確かに、この方式では一度に沢山の従業員を確保することは難しい。「公募」方式に比べて志の高い従業員を確保できる可能性が高いかも知れない。こうした地道な努力が徐々に実り、従業員6名体制は確立してきたのである。私見ではあるが、彼ら従業員の心意気はすこぶる高く、確かにグリーンサポート、地域農業の担い手候補者としてたくましく育ってきていることを、先の「コープさっぽろ農業賞大賞」の審査で現地を訪れた際、強く感じたことを付記しておきたい。確かに、グリーンサポートの活動によって、得難い地域農業の後継者・担い手候補者が「6名も立派に育ってきている」のである。
さらに、次代をにらみ、新規就農希望者の研修の受け入れも積極的に行っており、様々なルートを駆使しながら、非農家・町外出身者を含めた人材、後継者・担い手確保に力を入れているのである。今のところ、従業員の人数はしばらくは現状維持でいく予定と言われる。夏期作業はともあれ、増員に見合う冬期作業の確保が容易でないからである。今後、農産加工の実施など六次産業化の道も検討中である。
とは言え、そうとばかり言っていられない事態に近々、陥るかも知れない。というのは、一大戦力の臨時雇用の確保が次第に困難になってきている。中でも、耕種部門の繁忙期における確保が加速度的に難しくなってきていると言う。それは何も上川町だけのことではない。多くの地域で、臨時雇用の確保難から「派遣労働者」を雇用するケースも増えているとされ、グリーンサポートも例外ではなく、派遣労働者の導入には経済的に大きな困難が伴う。協業法人などからの出向作業員には「時間当たり最低賃金水準の683円(取材当時)」の支払いに対し、派遣導入では時間当たり1,300〜1,400円の支払いとなり、最低賃金水準の倍以上にもなるからである。更に、交通費の支払いもあり、特に、多くの派遣会社が軒を連ねる旭川市からの遠隔地に当たる上川町では不利さは倍加してしまう。
今でこそ、関連法人・農家からの出向やJAからのサポートもあり、社長を先頭に総員「獅子奮迅」の態勢の下、何とかしのいでいるものの、将来、冬季作業を確保しつつ、新たに従業員を増やしていくことが必要とされる。
30歳台未満の従業員出身の役員はいない。しかし、「しっかりした教育を施し、従業員出身の役員が一刻も早く誕生するようにしていきたい」、そして「彼らがグリーンサポートの経営を担い、地域農業を担っていくようになっていってもらいたい」。藤田社長が語る将来の方向性・夢である。思えば藤田社長以下、役員の面々は40歳台前半からグリーンサポートを担い、地域農業を担ってきたのである。
5 培った経験を基に、更なる発展を
1998年に産声を上げた「グリーンサポート」は今年で14年目を迎える。全町的なサポートの下、新たな担い手候補者も生み出し、地域農業のけん引役として、大きな足跡・成果を残してきた。形の上では「一農業生産法人」に過ぎないが、全町的なコントラクター事業の展開といい、交換耕作のセンター的機能といい、また消費者の交流事業といい、ただ単に、一個の農業生産法人というに止まらず、上川町農業の協同・共同組織と言って良い存在なのかも知れない。こうした組織、全町的対応はどこにでも見られるありふれたものでは決してなく、極めて珍しいケースと評せる。
なぜ、上川町ではこうした対応が可能となったのか。その一つとしてあげられるのは地域農業を襲う危機がとりわけ深刻で、このまま放置すれば地域農業どころか、地域社会の消滅すら危惧されるような状況に立ち至ったことがあげられる。藤田社長の「こうするしかなかった」との言が、そのことを雄弁に物語っていよう。ぎりぎりの選択であったが故に、全町的対応が可能となり、全町的な協力態勢も揺るぐことなく10数年にも渡って続いてきたと考えられるのである。
二つ目は地域内での人々の深いつながり、相互信頼・扶助的関係があった。すなわち「町内の皆が相互につながっているので、自分だけ勝手なことをするわけにはいかない」との藤田さんの言が如実に示しているように、地域が孤立化せずに、有機的な諸関係で結ばれていたことである。これがあるからこそ、危機に対しても一丸となって立ち向かっていこうとするエネルギーも生まれてこようというものである。
三つ目は、藤田社長の実直で粘り強い人柄をあげておきたい。「アンガス牛肥育牧場」を襲った危機に対しても、「失敗した」と清算的に総括するのではなく、あくまでも前向きに総括し、展望を導き出した点は特筆に値しよう。それが「一時的に利益が減少しても、簡単にやめない」(藤田社長談)とする気概につながり、失敗をバネに次の一手を考えることにつながっていることは間違いない。農業・農地利用は継続してこそ意味があり、力になるのである。
そして最後に、消費者組織(コープさっぽろなど)の支えがあったことをあげておきたい。1970年代のアンガス牛導入以来、「安全・安心」に留意し、消費者との信頼の輪を築き、固めることに上川町農業は尽力してきた。それは今日、トレーサビリティの担保、遺伝子組み換え飼料・抗生剤モネンシン不使用などをうたった「大雪高原牛」に受け継がれ、コープさっぽろなどとの継続的な取引につながり、消費者との積極的な交流、精神的な支援の輪の広がりにつながっているのである。いにしえに「人はパンのみにて生きるにあらず」という言う如く、農業はただ単に「農産物」という「物体」を届けれていればそれでこと足りるのではなく、消費者を思う気持ち、生産者を思う気持ち、そしてそれらの交差が必要不可欠なのではではないだろうか。まさに「生・消提携」であり、そうした伝統があったこそ、上川町農業は苦境にもめげずに頑張れたのではないかと思えてしようがない。
危機的・限界的対応に対処するために成立した全町的対応組織、グリーンサポートは、それ故、相変わらず厳しい条件下に置かれているだろうことは想像に難くない。しかし、度重なる危機を乗り越えてきた貴重な経験は、間違いなくその中に受け継がれていることは疑いない。従業員を地域内外から確保し、営農技術や経営ノウハウなどを受け継ぎ、時には先進地視察・研修などで研さんを深めつつ、地域農業の灯台・けん引役としてますます発展することを願ってやまない。
 |
グリーンサポートのみなさん |