1.地産地消型の地域特産品の作出
地域活性化を目的として地域ブランドを保護するため、平成19年4月1日から始まった地域団体商標制度には、これまで「近江牛」や「松阪牛」など数多くの農畜産物が登録された。これらのブランドは、いわば全国区として認知され、その特性や品質を維持するための生産体系が確立されている。
その一方で、小規模ながら、地域の消費者からの信頼を得た「地産地消」を地道に実践する地域特産品としてのブランドも数多くある。
本稿で取り上げる福岡県うきは市の吉井町養豚組合は、種豚場を含むわずか5戸の農家ではあるが、地域に根ざした取り組みを行い、地域の消費者の支持を得ている事例である。
うきは市は、福岡県の南東部に位置し、フルーツの里として知られており、福岡市内へは高速道路で約1時間と比較的近い。同市の総世帯数のうち、農家世帯数の割合は3割を占め、農業は主要な産業の一つである。特に果樹は、いちご、桃、なし、ぶどう、柿など年間を通じて栽培が行われ、16年の農業生産額の約4割を占めており、次いで、野菜が2割弱となっている(図1)。一方、畜産業の農業生産額に占める比率は7%程度で、養豚農家は、吉井町養豚組合に所属する5戸にすぎない。
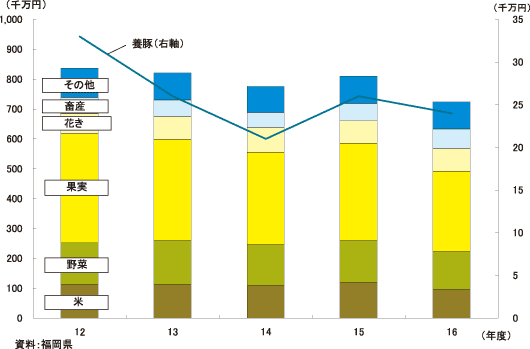
吉井町養豚組合は平成6年、養豚農家8戸で結成され、その後、地域に密着した生産・販売体制を確立するための地産地消を目指した地域ブランドを作出することとなった。
10年に取り組んだ大麦の給与によるブランド豚の試みは、販売ルートが確立できなかったが、純粋デュロック種の雌のみを「耳納(みのう)あかぶた203」として14年に発表、同時に地元で試食会を開催し、同年11月には販売を開始した。しかし、これは年出荷頭数が50頭と少ないため、主に福岡県内のレストランや居酒屋などの業務用向けとして販売されている。
一方、地域住民にブランド豚をアピールするためには、家庭向けや学校給食の食材として、出荷頭数が確保でき、かつ手ごろな価格を設定できるブランド豚の作出が不可欠であった。既に13年に組合が導入していた大ヨークシャー種(W)の系統豚「フクオカヨーク」(福岡県農業総合試験場)とランドレース(L)「ゼンノーL01」の雌にデュロック(D)を掛け合わせたLWD、WLDの三元豚のうち、雌のみを「耳納いっーとん」(読み方:「みのういっとん」)として15年1月に作出した(図2参照)。このとき、新聞紙上において「薩摩が黒なら、吉井は赤」との見出しで赤豚デュロックを掛け合わせた新しい地域ブランド豚が大々的に掲載され、その後テレビ番組にも取り上げられるなど地元における知名度を上げることに成功し、同年8月には吉井町内のAコープ、久留米市内のFコープにて販売が開始された。15年の出荷頭数は24頭にすぎなかったが、現在、LWD(WLD)の雌は、年間6,000頭ほど出荷されており、その中から肉質の良好なものに限定し、約2,300頭を「耳納いっーとん」として出荷するに至っている。季節ごとの生産頭数の増減により不足が生じることがないように余裕を持って出荷頭数が確保されている。
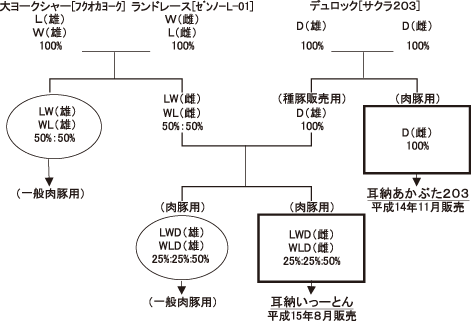
2.「耳納いっーとん」の流通形態
「耳納いっーとん」などのすべてのブランド肉は、生産者がと畜・解体を県内の業者に委託し、部分肉として生産者が自ら販売する形で流通している。
具体的には、生産者は肥育豚を全農への通常出荷分と「耳納いっーとん」として委託加工するものを選別した後、出荷する。「耳納いっーとん」分は、九州協同食肉で委託と畜された後、2つの食肉加工場で7分割(かた、かたロース、うで、ヒレ、ロース、ばら、もも)に委託加工され、これらの部分肉はフルセットでAコープの3店舗などへ配送される仕組みとなっている。

Aコープの豚肉売り場。耳納いっーとんが数多く
並べられている。上方には、
「吉井特産耳納いっーとんは私たちが育てた豚です」
との文字とともに、養豚組合のメンバーの
写真が掲げられている。
ところで、「耳納いっーとん」の定義は以下のとおりである。
(1) 品種など:LWDの三元交配の雌豚のみ
(2) 格付等級:「中」、「上」
(3) 枝肉重量:74キログラムを上限
(4) 給与飼料:配合飼料にハーブを添加し、パンの残さを給与すること
学校給食への食材納入は、これらAコープに納入されたフルセットの中から配送される。これは既存の学校給食の食材仕入れルートを踏襲した結果である。
ただし、後述の庄山氏のように、Aコープがカバーしていない全生徒数20〜30人の小規模小学校などについては、数百グラムを山間地まで届けるためまさにボランティア精神で生産者自らが配送を行っている場合もある。
「耳納いっーとん」は小学校への豚肉販売はもとよりAコープの地元店舗でも販売されているため、地元流通の第一の要となっているのが、Aコープ九州である。
Aコープ九州で「耳納いっーとん」を販売しているのは、よしい店、うきは店、田主丸店の3店舗で、組合員は一店舗ずつ担当が割り振られている。これは問題が起こった時に、生産者が責任を持って対応するためである。部分肉フルセットでAコープに納入された後、うでやももといった部位の一部が学校給食の食材として配送されるが、それ以外はAコープが精肉として販売している。なお、フルセット納入後、契約店舗以外に搬出する場合は、一般の豚肉として販売されるため、「耳納いっーとん」としては、契約店舗においてのみ販売される仕組みとなっている(図3)。
「耳納いっーとん」は、現在、うきは市教育委員会から学校給食の地元食材として指定されている。Aコープは、教育委員会と年間納入価格を交渉し、月に一度、指定された小学校の栄養士からの注文に応じて配送している。
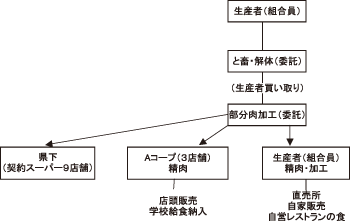
小学校への豚肉納入は15年9月から開始されており、現在はうきは市内の10校すべて、児童数で18年度合計1,944名が「耳納いっーとん」を学校給食で食べている。納入数量は15年度約300キログラム、16年度400キログラム、17年度約1トンと増加し、18年度は全校をほぼ100%カバーする約2トン程度と推計される。「耳納いっーとん」の名前の由来は小学校の学校給食で年間1トンを供給することを目標として「いっーとん」という名前が付いたそうだが、その2倍の量をわずか3年半で達成したことになる。
3.「耳納いっーとん」の支持者を増やす食育活動
わずか8戸で結成された同養豚組合は、現在5戸にまで減少したが、この小さな組合が地域での販売ルートの確保に成功した要因は、店頭での積極的な試食販売を実施したことやマスコミに取り上げられたこともあるが、何よりも地域を重視した点にもある。それは地元の小学校の児童のみならず保護者をも巻き込んだ食育プログラムに積極的に取り組んだ点が挙げられる。同養豚組合の杉正廣組合長によれば、LWDの雌に限定してブランド化した背景には、乳歯が抜けて永久歯に生え替わるまでの間の低学年の児童でも簡単にかみ切れて、おいしく食べてもらうことを念頭に置いていたとのことだそうだ。
食育活動は、「耳納いっーとん」の給食納入が開始された15年から取り組まれている。組合が実施する食育は、小学5年生を対象に5時間のプログラムが組まれており、生産者が講師として小学校に派遣される。児童は、豚について学習した後、とんかつなどを作る調理実習を実施、最後に農場見学を行う(表1)。調理し、おいしく豚肉を食し、さらに生きた子豚に触れ、その体温を感じるという過程において、スーパーの店頭に並ぶ精肉しか見たことのない児童であっても、「自然の恵み」、「命の大切さ」、そして生産者に対する感謝の気持ちを学ぶ。同時に、この過程において保護者を対象とした取り組みも実施される。児童が豚肉の調理実習を行う傍ら、別室にて保護者向けに講義を実施し、児童が作った料理の試食を親子で行っている。親子で食について考え、食への関心を高めることができるのに加え、保護者に対する「地場食材」のPRにもなる。この結果、地元のAコープで販売される「耳納いっーとん」を購入する機会が増えると同時に、その味に慣れ親しんだ子どもたちが将来、地場食材への理解者として地元農業にエールを送る大事な支援者になる。
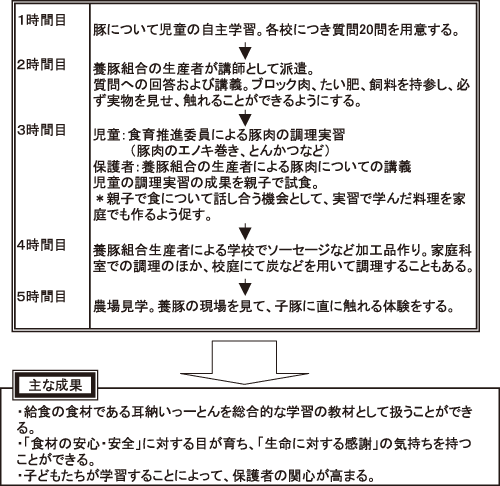
杉組合長は、「少数の養豚農家が、それぞれに利益を追求すれば、個人の力では、家畜環境問題などを克服することは難しかった」と話す。地元の理解を得、そして生産物をアピールするためには、地域コミュニティとのネットワーク作りが必要であった。このようなことから、学校給食、さらには食育活動、地産地消を念頭に置いた地元における販売ルートの開拓、地元の果樹、野菜農家へのたい肥の供給などへと活動を展開することとなった。
なお、うきは市が、17年12月に「うきは市における食育推進協議会」を立ち上げ、学校給食における地産地消がクローズアップされるようになったが、その2年前から吉井町養豚組合は既にこれに取り組んでいたことになる。
4.小学校以外の地元販売先の拡大
−直売所が地域ブランドの展開を支える−
「耳納いっーとん」は、市内Aコープ(3店舗、年間500頭)で、また、組合員の独自ブランド豚肉は、道の駅などの直売所や直営レストランで豚肉または豚肉加工品として販売されている。
「耳納いっーとん」の販売数量や販売価格については、個々の生産農家ではなく、養豚組合がAコープ側と交渉している。取引価格は年間一本で、食肉卸売市場価格などを参考に決定される。
Aコープへの納入価格が年間契約されることと併せて、道の駅などの直売所で販売する場合は、出荷者が価格を提示することができるため、生産者は年間の経営を見通しやすくなる。最近の配合飼料価格の高騰など、生産コストの上昇が懸念されるが、100グラム単位の小売価格で設定すれば、コスト上昇分も比較的転嫁しやすいとのことであった。また、給与するパンくずは、食パン、パンの耳であれば、地元製パン会社から安価で入手が可能ということで、給与量は飼料全体の約2割程度に相当するとしている。吉井町養豚組合は、現段階では更なるコスト削減よりも、多少価格が高くなったとしても売り切ることができる品質を維持し、小売店側に「高くても売り場に置きたい」と考えてもらえるような信頼関係の構築に力点を置いていきたいと話していた。
養豚組合員の庄山氏は、現在黒豚のバークシャー種を取り入れたWBD((大ヨークシャー×バークシャー)×デュロック)であるオリジナルブランド「千年豚」の豚肉や豚肉加工品を道の駅や直売所に出荷し、自営のレストランの食材としても利用している。庄山氏が出荷している直売所の一つであるにじの耳納の里は、地元のJAにじが100%出資し、16年4月にオープンした。JAにじの組合員であれば、誰でも出荷することができ、800人を超える登録者のうち、1日平均200人〜250人が出荷している。現在、人口3万人強の町で、一日のレジ通過客数は平日で平均1,000〜1,200人、休日には福岡市近郊から果実狩りなどで訪れた観光客が全体の3割近くになり、その数は2,000人を超え、平均売上額は200万円以上に上る。にじの耳納の里は、当初、消費者にスーパーとの違いを認識してもらえなかったが、今では消費者の間に「地元産の商品を置くところ」との意識が浸透し、昨年度の売り上げは前年度比1億1千万円増の6億9千万円に達している。

にじの耳納の里店内。
平日の午前中から、地元の人々でにぎわう。
庄山氏のように個人ブランドを展開する場合、直売所は生産者と消費者を繋ぐ重要な役割を果たしている。庄山氏は、にじの耳納の里が開設された当初、加工品のみを出荷していたが、精肉を出荷したところ、思いのほか評判がよく、週末には飲食業者によるまとめ買いが多かったため、販売は好調である。実際、庄山氏のにじの耳納の里での年間売上高は出荷者の中でもトップクラスであり、にじの耳納の里の柳主任によれば、千年豚は脂にクセがなく、甘みがあると評判とのことだ。しかしながら、にじの耳納の里に出荷する場合、精肉のパック詰めは生産者自身が行わなければならず、庄山氏の場合、自営レストラン閉店後、夜半まで作業がかかるため、引き合いがあっても、出荷数量が増やせないとのことであった。

にじの耳納の里における庄山農場の販売コーナー。
竹と竹炭を粉末状にして混ぜ込んだハム・ソーセージが
注目されている。
庄山氏のブランドが良好に展開している要因は、生産規模が小さい点を逆にメリットとして、生産から販売までを自ら管理することによって、精肉・加工品ともに品質のよいものを手ごろな価格で提供し、さらには消費者の顔を見ることができる立ち位置で経営を行っている点にある。これは、消費者の反応を直接得ることができることに加え、自分の経営理念を小売店、消費者に伝えることができる点で、他の競合食材と差別化を図り、競争を勝ち抜くための基礎になり得ると思われる。
5.自営レストランにおける消費者との直接交流がさらに良い豚を生み出す
−庄山氏の取り組み−
地元消費者からの支持を得、消費が拡大している「耳納いっーとん」であるが、需要の伸びに応じて生産者が既存農場で規模拡大することは、環境問題の面から非常に難しくなっている。そのような経営環境において、組合員の庄山氏は独自のブランドを直売所のみならず、自営レストランでも展開している。庄山氏が農場で飼養している母豚頭数は約30頭と規模は小さいが、バークシャー、デュロック、大ヨークシャーやWHの交雑などその種類は多い。集落の中心に農場を構えており、さらに採卵鶏も飼養しているため、環境問題なども考慮し、今以上の規模拡大は考えていないとのことだ。一方、自身で生産した豚肉を委託加工した後、自営のレストランで使用することにより、消費者の反応を直接得ることができることから、「レストランで使いやすく、客の要望に応え得る豚肉」とその加工品の生産に取り組んでいる。現在、加工品はハム、ベーコンが月産10キログラム、ウインナーが同20キログラム程度であるという。
庄山氏は、父が始めた養豚農家を継いだ後、飼養規模拡大の限界から、独学で付加価値の高いハム・ソーセージの加工を学んだ。「趣味程度に始めて、人に食べてもらいながら工夫を重ねた」とのことだが、7年に自宅加工場の一角に直売所を設けて加工品の販売を始めたところ、メディアにも取り上げられ、好評を得たという。そのうち、客の中から「食べて帰りたい」という要望が出るようになり、11年に「庄山レストラン」を出店するに至った。当初は、焼肉・しゃぶしゃぶを出していたが、BSEの発生を契機にレストランにおける牛肉の取扱を休止し、豚肉専門店とした。豚しゃぶは、値段も手頃で、非常に客の反応も良かったという。しかし、庄山氏は常に客の声に耳を傾け、よりおいしい料理を提供するため、黒豚のバークシャー種を取り入れたWBDを生産するようになり、農場が所在する地名をとって「千年豚」と名付けた。バークシャーを掛け合わせているため、分娩頭数も少なく、出荷まで8カ月かかるため生産効率はよくないが、豚肉としての「千年豚」の評判はかなり高い。レストランに通う顧客は、庄山氏自身が生産している豚肉であることも知っており、食材の供給者の顔が見える点において、その味とともに消費者の信頼感を得たものと思われる。

庄山三成氏。庄山レストランの前にて
6.地域密着ブランドのネットワークを
「耳納いっーとん」自体はLWD(WLD)の3元交配の雌であり、飼料にパンくずとハーブを与えるという要件はあるものの、品種や飼養管理の点で特に大きな特徴があるとは言えない。しかしながら、それぞれの養豚組合員は「耳納いっーとん」を統一ブランドとして生産しつつ、組合員それぞれが創意工夫して、新たなブランド豚の作出や加工品の製造、飲食店の経営など様々な可能性を模索している。
この結果、地元ブランドとして、学校給食のみならす、Aコープのある店舗の豚肉のショーケースは今ではすべてが「耳納いっーとん」で占められていたし、旅館や料理店も地元食材として使用されており、おいしい豚肉を地元に安く提供するという姿勢は地元の消費者には受け入れられている。
また、農畜産物の直売所では、「にじの耳納の里に行けば地元産の良いものが買える」といった消費者と、「にじの耳納の里に良いもの出荷すれば売れる」という生産者側の意識の醸成が、その成功に繋がっている。現在、うきは市周辺には3つの直売所が設置されているが、今後さらに2店舗が開店する予定であり、消費者のみならず生産者の品質へのこだわりは確実に増しつつあると思われる。これはとりもなおさず生産者は、自らが生産する農産物を、いかに付加価値を高めて販売するか、という生産意欲の向上をもたらすことになる。
ところで、養豚組合の生産者は、それぞれたい肥を耕種農家に供給している。ただし、たい肥の供給形態は、果樹農家が無償で引き取る場合や、完熟たい肥を販売するなど組合員中でも一様ではない。吉井町養豚組合の組合長杉氏は、たい肥の成分分析を含め、果樹・野菜の品目ごとに効果的な散布時期などをアドバイスすることで、たい肥利用のリピーターは増えると見込んでいる。
耕作放棄地の増加や鳥獣害被害の拡大はうきは市も例外ではないが、果樹や野菜農家が、品質向上を目指してたい肥を積極的に利用する機会を増やすことができるかが、地域のネットワーク化の大きな課題となるものと思われる。

耳納いっーとんのしゃぶしゃぶ肉