1 はじめに
2005年を100とした飼料価格は2008年9月には141.2に跳ね上がった(農林水産省『農業物価統計』)。近年まれに見る高騰であったが、もちろん、その背景にBRICsなどの経済発展やバイオエタノール化の激増などによる穀物需要の増大や穀物市場への「投機マネー」の流入などがあることは言うまでもない。周知のように、畜産経営では飼料費が生産費の30〜60%を占める。飼料費の値上がりは、それに見合った畜産物価格の上昇がない限り、直接、畜産経営を大きく圧迫する。飼料価格をいかに抑制するか。今、畜産経営が抱える第一義的課題と言って良い。
こうした中で注目されているのが地域・国内に“眠っている”未利用資源であり、特に、各種食品残さの飼料化利用である。思えば、古来、“カス酪”“カス畜”と言われてきたように、食品残さの利用は畜産の本流であったとも言える。しかし、「畜産公害」を避けるために畜産業が都市近郊から遠隔地へ移動したことや規模拡大などに伴って、食品残さの利用から遠ざかってしまった。また、畜産物の均質化を求めることなどにより、成分変動の大きい食品残さの利用が敬遠されたという事情もある。こうして、1,500万トンにも及ぶ大量の穀物飼料が輸入される傍ら、大量の食品残さが利用されないまま廃棄物として処理されるという状態が続いてきたのである。こうしたことの反省に立ちつつ、近年、食品残さの飼料利用が全国各地で試みられてきたが、今次の飼料価格の高騰は、そうした方向に大きな注目を集めることになったのである。
食品残さの有効利用は,飼料価格高騰への対策としてだけではなく、今、大いに問題となっている地球規模の環境問題への対応策、すなわち廃棄物の削減による環境負荷の軽減策としても意味を持つ。また、飼料自給率の低さがわが国の食料自給率を押し下げていることを考えれば、それは食料自給率の向上にも意義深いと言える。さらに、利用する食品残さによっては“○○牛”“○○豚”などと畜産物の差別化、あるいは畜産や地域イメージのアップにも有効になるかも知れない。
今回は、食品残さとしてワイン生産の副産物(「ワインオリ」)を使い、ワインの赤にちなんで赤毛(褐毛)の牛にこだわりつつ肉牛生産に励んでいる北海道池田町の取り組みを紹介することにしたい。後論で触れるように、それは地域内の関係諸機関が連携することによって、ワイン工場と畜産経営とが“ウィン・ウィン”の関係を築いている点も興味が尽きない。
 |
放牧されるあか牛
|
2 ワイン醸造廃棄物(オリ)を飼料化
1)ワインの町、池田町池田町は十勝平野の中央部のやや東寄り、帯広市から車で30分ほどのところに位置する。町面積37,200ヘクタール、人口8,000人ほどの町である。池田町を全国的に有名にしているのは何と言っても“十勝ワイン”であり、それにちなんだ“ワイン城”である。
池田町がワイン製造に取り組むことになったのは、今を去る40数年前、1960年代初頭のことである。町内の山野に自生する山ブドウが1963年、ワイン醸造に適したアムレンシス系の品種であることが判明したのである。もちろん、町にワイン作りの伝統もなければ、技術もない。言わばゼロからのスタートで、試行錯誤を重ねながら醸造技術を習得し、「前例がない」と渋る税務署を何とか説き伏せて、試験製造免許を取得した。そして、研究所と工場を持つ町直営の「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」を開設し、1966年から「十勝ワイン」のブランド名で販売を開始した。
1960年代と言えば、ワイン消費が一般的とはとても言えず、消費量は今日に比べて特段に少ない頃である。今にして思えば、無い無いづくしの中で、しかも、大した消費量もない中で、山に醸造向きのブドウが見つかったということでワイン醸造に踏み切った点は“大いなる英断”と言って良いかも知れない。途中、国際的なコンクールで入賞したことも手伝って、「十勝ワイン」は順調に販売量を伸ばしていった。1974年には醸造能力1,800klの本格的な工場を新設した。新工場は十勝平野を見下ろす丘の上にそびえ,その独特の外観からいつしか“ワイン城”と呼ばれるようになった。ワイン城にはワインとステーキ、ビーフシチューを味わえるレストランも併設されており、十勝を代表する観光地の一つとなっている。2004年には開設30周年を記念して、5億円を投じた改修工事が行われ、地下の熟成室の見学が可能になるなどワインづくりをより身近に感じられる施設へと生まれ変わっている.
近年は安価な輸入ワインの圧迫を受けて販売量の減少を余儀なくされており、2007年度の販売量は630kl、売上高は7億3,000万円にとどまっている。しかし、池田町を代表する“名物”、十勝を、北海道を代表するワインであることは間違いない。
2)ワインの赤にちなんで褐毛和種を導入〜あか牛部会発足
池田町の耕地面積は9,640ヘクタールで、うち一般畑が6,120ヘクタール、牧草地が3,110ヘクタールである。ここに、2007年時点で344戸の農家が営農しており、平均一戸当たり耕地面積28ヘクタールと十勝平均の38ヘクタールに較べると小規模と言える。そのため、池田町には畑作を中心としつつも畜産との複合経営が多い。農業産出額は麦・豆・馬鈴薯・てん菜のいわゆる畑作四品を中心に70億円程度であり、うち肉用牛は10億円ほどを占める。
池田町での褐毛和種の振興は1973年、熊本県から160頭導入したのが始まりである。当初、たい肥の確保や山間地の活用を目的にしていたが、なぜ、褐毛かと言えば、(1)性格が温順で飼いやすい、(2)粗飼料の利用性が高い、(3)成長が早く24ヵ月齢ほどで出荷できる、といった特徴に加えて(4)ワインの赤と“あか牛”がマッチするという理由からであった。導入当初、繁殖は農家、肥育は町営肥育センターが担当するという分業態勢の下、ピーク時の1992年には繁殖用雌牛の飼養頭数が1,400頭を数えるまでになった。しかし、その後、牛肉の輸入自由化に伴う子牛価格の低落によって、飼養中止や黒毛和種への転換が急速に進んでいく(図1参照)。褐毛和種にとって危機と言って良い。
危機は、人々に新たな対応を取らせる起爆剤になるらしい。褐毛和種の導入当初は「繁殖は農家、肥育は町営肥育センター」という分業態勢が取られ、その後も繁殖と肥育は概ね別々の農家が担うという態勢が取られていたが、それを農家段階で統合する、すなわち繁殖・肥育一貫経営へ移行しようという動きが出てくるのである。それはJA十勝池田町組合員11戸による1993年1月の「池田町あか牛肥育生産組合」の結成につながっていく。同肥育生産組合は「いけだ牛」のブランド化に向けて、あか牛の本場である熊本県から講師を招いて研修会や現地視察を実施し、肥育技術の向上と平準化を図り、また、優良雌牛・精液を導入して繁殖牛の資質向上に努めてきた。さらに、現在は中断しているが、受精卵移植にも取り組んだ。なお、同肥育生産組合は当初、「JA池田町和牛生産組合あか牛部会」の分会のような位置づけにあったが、繁殖のみの経営が次第に減少し、繁殖・肥育一貫経営がほとんどを占めるようになったために、2007年に両者は統合し、今では「JA池田町和牛生産組合あか牛部会」と名乗っている(以下、便宜上、旧肥育生産組合のことも「あか牛部会」とする)。
2007年12月末時点で、池田町で褐毛和種を飼養している農家は17戸で、繁殖用雌牛は436頭となっている。そのうちJA十勝池田町(池田町には「JA十勝池田町」と「JA十勝高島」の2農協がある)は11戸、302頭である。あか牛部会に所属している11戸のうち一貫経営が8戸、繁殖経営が2戸で、残る1戸は黒毛和種の受精卵移植用に1頭を飼養する農家である。
「いけだ牛」として販売される頭数はここ10年間ほど200〜250頭で安定的に推移している。出荷された牛は池田町食肉加工センターで枝肉にされた後、地元の卸売会社T社を通じて、北海道内のスーパーや小売店に約80%、残り20%ほどが岩手県・長野県・大阪府などに販売されている。枝肉価格は黒毛和種の同一規格のそれの88%という契約になっており、2007年で平均すると一頭当たり70万円ほどであった(図2参照)。
図1 池田町における褐色和種飼養戸数・頭数(繁殖雌牛)の推移 |
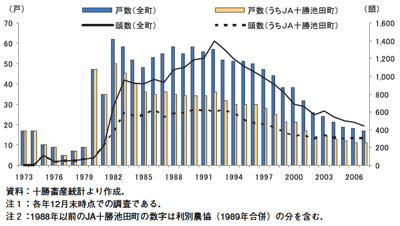 |
3)あか牛部会によるワインオリの飼料化の試み
さて、ワインオリの飼料化への歩みは2002年に、あか牛部会と十勝東部地区農業改良普及センター(以下、「普及センター」)が中心となって実施したワイン副産物の飼料化試験に始まる。図3に見られるように、ワイン製造過程で副産物として圧搾カスとワインオリとコウ(ブドウの房から実を取り除いた残りの部分)が出てくる。その量は、概ねブドウ1キログラムから720mlのワインが生産されるが、圧搾カス(主に皮や種)は200グラムほど、ワインオリ(ワイン熟成中に樽やタンクの底に沈殿するもので、ほとんどが酵母)は50グラムほど、コウは30グラム程度である。これまで、圧搾カスとコウはたい肥化され、農地に還元されていたが、ワインオリはどろどろした液状をなし、若干のアルコール分を含んでいたために、産業廃棄物として業者に処理を委託していた。その処理料は1トン当たり3万円程度であった。
あか牛部会と普及センターなどによる飼料化試験は圧搾カスやコウはもちろん、ワインオリの飼料化をも目指していた。特に、ワインオリは処理費用がかかることもあって、その有効利用は切望されていたと言って良い。試験の結果、圧搾カスとコウは栄養面でメリットが少ないことが判明し、また保存性にも優れないということで、飼料化は見送られたが、ワインオリは粗タンパクを30%も含み(表1参照)、長期保存にも耐えうることから本格的な飼料化試験が開始されることになった。
先に触れたようにワインオリはどろどろした液状をしている。このままでは、ワイン工場から農家までの運搬に大きな支障をきたす。そこで試みられたのは、ビートパルプのペレットと混合し水分調整をした上で、サイレージ化する方法である。出来上がったワインオリ・サイレージを給与したところ、牛の食い込みが良くなるなど、良好な結果が得られたため、2004年に本格的な生産・利用が開始されたのである。現在、排出されたワインオリの全量が飼料化されており、2008年のワインオリ飼料は30トンに達している。
図2 池田町のあか牛生産に関連する諸組織
|
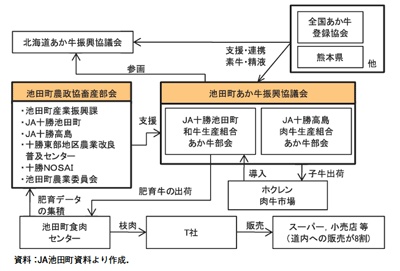 |
図3 ワインの製造工程と副産物
|
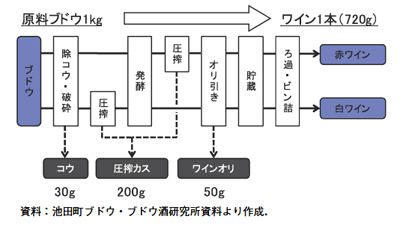 |
表1 ワインオリの成分
|
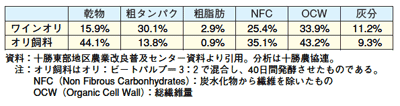 |
3 サイレージにし、育成牛に給与
1)ビートパルプと混合し、サイレージ化ワインは毎年10月に仕込まれ、ワインオリが排出されるのは10月から翌年の3月にかけてである。ワインオリはステンレスバットに貯められ、屋外で保存される。冬の十勝は寒さが厳しく、氷点下20℃に達することも珍しくない。当然ながら冬期間、ワインオリは凍結しているため、融け出す4月上旬頃になって、ビートパルプペレットとの混合作業が実施される。作業は10人余で行い、半日ほどで終了するが、その際ワイン工場の職員のほか、あか牛部会の部会員もボランティアとして参加する。作業は至ってシンプルで、500キログラムのフレコンにビニールの内袋を敷き、その中にビートパルプを入れ、そこにワインオリを注ぎ込む。そして、攪拌し、袋の口を結んで密封し、2カ月ほど発酵させた上で、牛に給与する。
ワインオリとビートパルプの混合割合は3:2が目安とされるが、2008年の飼料価格高騰時にはビートパルプの需給の逼迫によって予定量を確保出来なかったために、混合割合を2:1とワインオリの割合を多めに調整した。ただし、目分量での作業で、しかもワインオリが固い場合には適宜水を加え調整するなどしており、混合割合はそれ程厳密なものではない。また、混合時の攪拌が不十分で発酵ムラが生じ、給与時に問題となることもままあるが、今のところ簡便な製造方法を採用しているのでやむを得ない、とされる。
 |
 |
ワインオリ飼料の調整作業 |
|
 |
完成したワインオリ飼料
|
2)実費相当分のみの取引価格
ワインオリ飼料はブドウ・ブドウ酒研究所が製造し、全量を一括してあか牛部会に販売するという形を取っており、部会ではそれを飼養頭数に応じて、部会員に配分・販売している(図4参照)。研究所では、本格的にワインオリ飼料を製造するに当たって、新たに飼料製造の免許を取得している。ワインオリ飼料の販売価格は、農協から購入したビートパルプやフレコンなどの資材の実費分を積算した価格となっており、ワイン工場職員の飼料製造に関わる人件費は入っていない(ただし、2008年製造分からは若干の手数料が上乗せされることになった)。表2は2008年4月製造のワインオリ飼料のコストと販売価格を示したものであるが、製造量が31,500キログラムで、ビートパルプが34.3万円、フレコンが15.9万円の計50.2万円であるから、飼料単価(フレコンの価格も含む)は約16円/キログラムとなる。この単価と、普及センターが実施した給与試験の結果とに基づいて、ワインオリ飼料の経済性について試算したのが表3である。普及センターの給与試験によれば、ワインオリ飼料3キログラム/日/頭の給与によって、配合チャンス(育成肥育飼料)1キログラムと乾草0.5キログラムが節減でき、飼料費にして34.0円/日/頭が節減できる勘定となる。この試算では製造・運搬に関わる農家の労働費が含まれていないことに留意する必要があるが、それを含んだとしても十分なコスト節減効果を見込むことができると言えよう。
こうしたコスト節減効果に加えて、後述するように牛の嗜好性も極めて良好であることから、町外からも購入要望が寄せられているが、ワインオリに最初に注目し、飼料化の方法を開発したのがあか牛部会であることから、あか牛部会を優先させていると言う。
表2 ワインオリ飼料の製造コストと販売単価
|
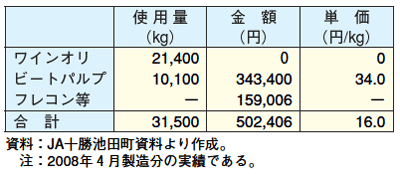 |
図4 ワインオリ飼料化にかかわる主体の関係
|
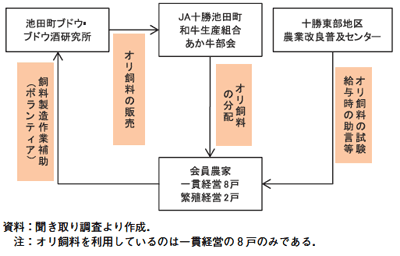 |
3)粗タンパクの高さから育成牛へ給与
あか牛飼養農家でのワインオリ飼料の給与実態とその評価は、どのようなものであろうか。
あか牛肥育生産組合の発足時からの組合長であり、今日、あか牛部会の部会長を務めるN氏によれば、4カ月齢から10カ月齢の育成牛にワインオリ飼料を与えており、嗜好性は極めて良好で「餌の食い込み」が良くなるとされる。ワインオリ飼料には多くの粗タンパクが含まれており、肥育期にはタンパクを減らす必要があるため、肥育期ではなく育成期に給与する。一頭当たりの給与量は、概ねワインオリ飼料2キログラムに配合飼料3.5キログラムであり、乾草の給与量は特に制限せず、いわば「喰いたい放題」となっている。ワインオリの給与は9月に開始し、12月初頭には使い切ってしまうため、以降、コーンサイレージで対応している。
ワインオリ飼料の量が少なく、また給与期間も4カ月程度と短いので、飼料コスト削減効果はそれ程大きなものではないと思われそうだが、決してそうではない。
あか牛は枝肉の格付けでA3を目標に品種改良されてきたが、あか牛部会全体でA3にランクされるのは3割程度で、残りのほとんどはA2である。既に触れたように、枝肉の格付けが同じであれば、黒毛和種に比べて価格は12%低い。しかし、あか牛は肥育期間が黒毛に比べて短く、また耐病性に優れているなどの利点がある。肥育期間が短い分、生産コスト、特に飼料費は安く済み、病気に強い分、薬剤費・獣医療費などが安く済むのである。N氏によれば、概ね一頭当たり「コストは30万円ほど低く生産できる」とされ、ある程度の収益が確保できるとされる。ただし、素牛価格が安いこともあって、育成だけでは採算は取りにくく、肥育までの一貫になって、はじめて採算が取れるとされる。
生産コストの多くを飼料費によって占められていることを考えれば、いくらかでもその節減に結びつくことであれば大歓迎と言ったところであろう。ワインオリ飼料は量こそ少ないとは言え、一日一頭当たり34.0円の飼料費の節減は大きいと言える。9月から11月の3カ月の給与で一頭当たり3千円余の節減となるからである。仮に、ワインオリ飼料の給与牛が10頭であれば3万円、30頭であれば9万円の節減になり、また、不安定性を増す飼料価格の影響を受けることもない。さらに、飼料の「食い込み」も良くなるという効果もあるのであり、ワインオリ飼料の価値は決して少なくないと考えられるのである。
表3 ワインオリ飼料の経済性
|
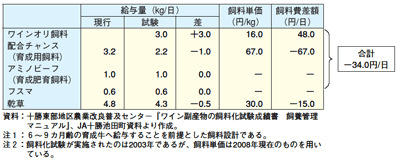 |
4 おわりに
国際的な穀物価格の不安定感が増し、また、大量の食品残さが未利用となっている中で、その有効利用、すなわち飼料化は緊急にして重要な課題と言って良い。事実、飼料化、エコフィードの取り組みは徐々にではあれ、各地に広がりつつあるのである。
本稿で紹介したワインオリの飼料化も、その貴重な一つの取り組みである。しかし、問題がないわけではない。
その一つは、ワインオリの量が少ないという問題である。周知のように、ワインオリはワイン醸造の副産物であり、ワイン醸造量を離れて、勝手に増産するわけにはいかない。そのワイン醸造量は、輸入廉価ワインに押されて、この間減少傾向で推移しており、反転、大きな増産に向かうという見通しを持つことはなかなかできない。それでは他地域のワイン工場から搬入・購入すれば良いのではないかと思われるかも知れないが、液状であるため、輸送には極めて大きな技術的な困難が伴う。また、運賃負担も問題であり、ワインオリがたとえ無料でも莫大な運賃をかけて輸送したのでは、むしろ“高価な”飼料になりかねない。ワイン醸造量をいかに増やしていくかが、オリ飼料の増産に直結するわけで、町あげての十勝ワイン消費拡大運動などの展開が切望されるのである。敷延して、国産ワインの愛用が国内でのオリの増産をもたらし、オリ飼料の増産の可能性を高め、結果として、飼料自給率の向上、そして食料自給率の向上に結びつく可能性のあることを指摘しておきたい。
二つは、ワインオリを給与したあか牛の「製品差別化」を図ることが出来ないかという問題である。今のところ、オリ飼料が肉質にいかなる影響を与えているのかが実証出来ないために、現地には大きなためらいがあるようである。しかし、「北の大地で生産された○○」などの差別化の方向もあるのであり、せっかく池田町内に45ヘクタールのブドウ畑を持ち、また、道内産ブドウも使っているのであるから(「十勝ワイン」の全てがそれによっているわけではない)、「十勝ワインあか牛」などイメージ的な差別化を図るなど、何らかの対処方法はありそうである。
三つは、今のところ飼料化はワインオリだけに止まっているが、圧搾カスなどの飼料化の道も試みられても良い。圧搾カスの飼料化は過去一度、試みられたが、栄養成績が芳しくなく、見送られた経緯があるが、今、再度、飼料化試験を始めたという。嗜好性の高いワインオリ飼料とうまく混合するなど、様々な試みの中から有効利用、飼料化の道が開かれてくることを祈りたい。
ワインオリの飼料化はスタートして5年目。あか牛の生産期間の長さからすれば、始まったばかりと言っても良い。しかし、一度は見送られた圧搾カスの飼料化の試みが再スタートするなど、農家の目が着実に地域内の未利用資源の有効利用に向けられてきていることを、強く感じるのである。こうした地道な試みの積み重ね、そしてその広がりが全体として「エコフィード」利用を増大させ、飼料自給率・食料自給率の向上や環境保全に大きく寄与していくだろうことだけは疑いない。