1.はじめに
飼料用米生産は収益性が低いことなどから敬遠されてきた。しかし、昨今の配合飼料価格高騰への対応、飼料自給率向上への期待、さらには政府が打ち出した水田フル活用の助成策が強化されたことなどから、各地で取り組みがスタートし作付面積は近年急速に拡大してきている。飼料用米の利点は畜産農家にとっては(1)栄養価が高く、家畜の嗜好性も良い、(2)長期保存ができる、(3)増産できれば国産飼料原料として安定した入手が可能、(4)飼料用米を給与した畜産物はヘルシーなものとなり差別化販売が可能であるといった点が挙げられる。また、稲作農家にとっては(1)排水不良田などでも作付け可能で水田のフル活用ができる、(2)栽培技術は食用米とほぼ同じで取り組みやすい、(3)麦・大豆などの連作障害を回避できる、(4)農機具について新たな投資が必要ない−などの利点がある。
しかし、飼料用米の生産コストについて、配合飼料の原料となる輸入トウモロコシ価格と比較すると、流通経費(輸入トウモロコシの場合は、港湾等諸経費)を除いて試算した場合、その差は現状でも5倍以上になるとも言われており、経済的な面からは、飼料用米の生産は、政府の助成なしで成立しがたいことも事実である。
そこで、当機構は、飼料用米の生産部門に着目し、東京農業大学農学部信岡誠治准教授をはじめとする同大農学部畜産マネジメント研究室(以下「畜産マネジメント研究室」)と共同で、平成20年産の飼料用米生産農家へのアンケート調査を実施した。
本稿では、アンケート調査の結果から、飼料用米生産の実態と生産コストや収益性を分析するとともに、コストダウンの可能性について論点を整理する。
2.飼料用米生産の現状
飼料用米の作付面積については、地域水田農業活性化緊急対策等の支援措置(平成19年度補正予算)により平成20年度は前年の5倍以上の1,611ヘクタールに急速に拡大してきている(図1参照)。また、政府は平成21年度からは水田フル活用転換元年として位置づけ、21年4月に新たに制定した「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」(米粉・エサ米法という)に基づき推進方策を明確にするとともに、支援策をさらに強化し飼料用米の本格的な生産・利用拡大に向けた取り組みを推進しているところである。
具体的な支援策としては、21年度当初予算では水田等有効活用促進交付金を創設、飼料用米の拡大面積に応じて10アール当たり55,000円の助成をスタートさせたほか、21年5月に成立した21年度補正予算ではさらに追加として飼料用米の生産面積に応じて10アール当たり25,000円を助成することとしている。合わせると10アール当たり55,000円プラス25,000円で80,000円の助成である。さらに、稲わらを畜産用に利用すると10アール当たり13,000円が助成されることから、最終的には10アール当たり93,000円という助成金が交付されるという状況になっている。
この結果、21年産の飼料用米の作付面積はさらに大幅に拡大することが見込まれている。ただし、この決定が田植え時期にずれ込んだことから、超多収穫品種を利用した飼料用米の作付拡大が間に合わなくて、既存の食用米品種を利用した飼料用米生産の拡大となっているのが実態のようである。
|
図1 飼料用米の作付面積の推移
|
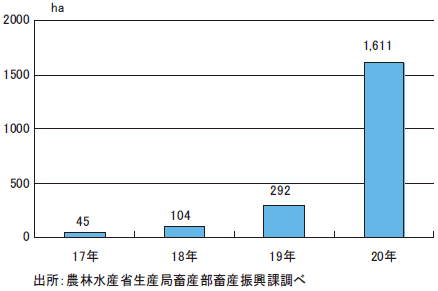 |
3.飼料用米生産の実態
平成20年産の飼料用米生産の現状については前記で述べたように、面積的には急拡大しているが、その内容については今ひとつ明らかでないのが実情である。そこで、平成20年度から当機構の畜産業振興事業である国産飼料資源活用促進総合対策事業(うち飼料用米導入定着化緊急対策)において、飼料用米の利活用に係るモデル実証に取り組んでいる全国49集団に参加し、飼料用米生産を行った稲作農家(98戸)に対して飼料用米栽培に関するアンケート調査を実施した(調査票参照)。また、これらの集団には参加していないが、独自に飼料用米生産に取り組んでいる稲作農家(27戸)に対しても同様のアンケート調査を実施し、全国の稲作農家54戸から回答を得た。そこで、この回答をベースに現在の飼料用米生産の実態を明らかにしてみよう。
1) 飼料用米生産に取り組んでいる農家はほとんどが「専業農家」
飼料用米生産に取り組んだ稲作農家のほとんどは「専業農家」である。54戸中、47戸(87%)が専業農家で、兼業農家は7戸(13%)にすぎない(図2)。稲作に意欲を持っている専業農家が飼料用米生産にも意欲的に取り組んでいるのが実態である。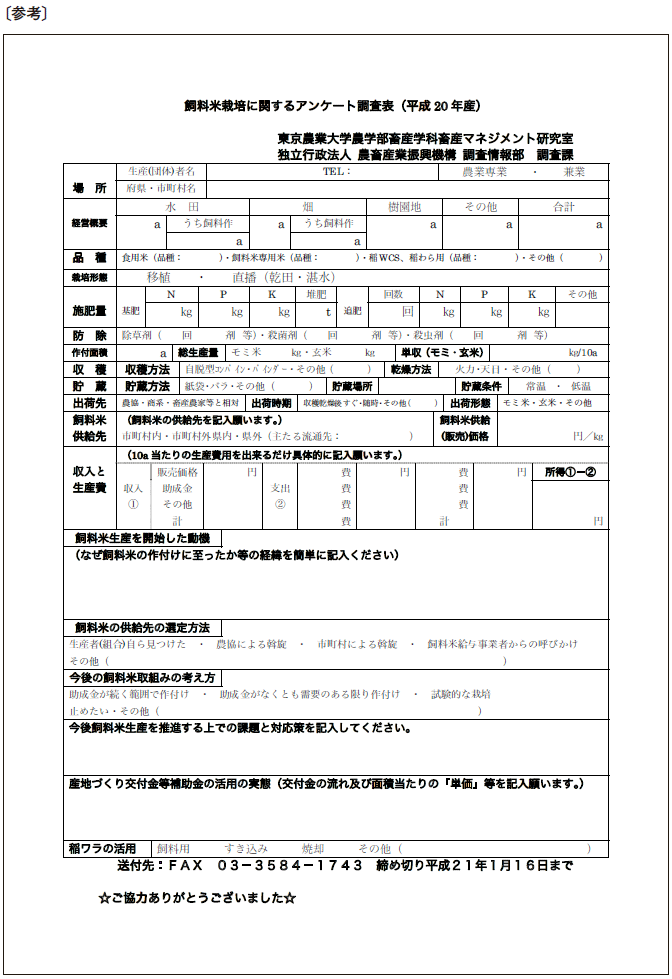 |
|
図2 アンケート回答農家の専業別構成
|
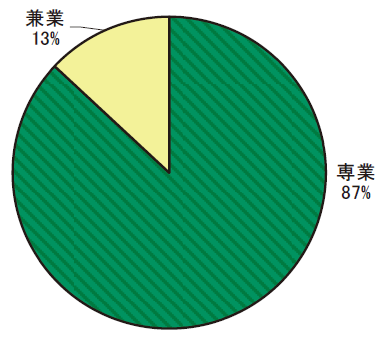 |
2) 飼料用米の作付面積は格差が大きい、一戸当たり平均面積は「249アール」
|
図3 飼料用米栽培農家の栽培面積の分布
|
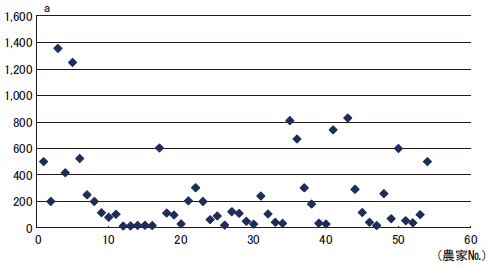 |
3) 玄米換算の平均単収は「559キログラム」、ただし単収の格差は大きい
飼料用米の平均単収(モミ米換算)は「699キログラム」、玄米換算では「559キログラム」である注)。平成20年産の食用米の単収(全国平均)が543キログラムであるので、飼料用米の平均単収は食用米よりも約3%多いが、期待されたほどの多収にはなっていない。特に単収(玄米収量換算)の格差とばらつきが大きいのが目立っており、最低は195キログラム、最高は858キログラムと4倍以上の開きがある(図4)。|
図4 飼料用米の玄米換算平均単収の分布
|
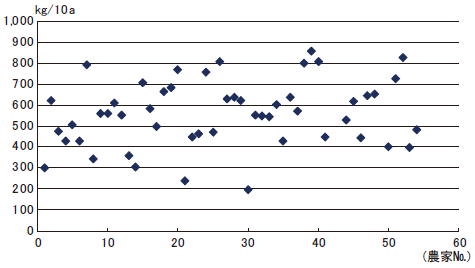 |
4) 品種は食用米や飼料稲品種を利用、超多収米品種の利用はまだ少ない
飼料用米品種については食用米や飼料稲品種を利用しているところが多い。飼料用米としての栽培品種は「ひとめぼれ」「コシヒカリ」「あきたこまち」「あけぼの」「てんたかく」「ヒノヒカリ」「はえぬき」などの食用米品種を利用している農家が30戸、飼料用米あるいは飼料稲品種として開発された「ホシアオバ」「クサノホシ」「クサホナミ」「べこあおば」「ふくひびき」「モミロマン」「タカナリ」などの品種を利用した農家は35戸である。このうち、食用米と飼料用米や飼料稲の両方を利用している農家は11戸である。品種として最も利用が多いのは「ふくひびき」である。これは飼料用米品種として開発されたものではないが飼料用米として利用している農家が20戸ある。他方、超多収の飼料用米品種として普及が期待されている「タカナリ」を利用した農家は7戸、我が国で最も多収品種とされている「モミロマン」を利用した農家は1戸のみであった。5)施肥量は慣行の食用米とほぼ同じ
施肥体系は、複合化成肥料を用いている農家が多い。また、複合化成肥料とともにたい肥を施用した農家は19戸である。施肥体系と収量の関係が明らかな40戸について分析してみると、飼料用米生産農家における10アール当たり平均施肥量は窒素成分量で基肥7キログラム、追肥はN成分量で0.8キログラム、合計7.8キログラムである。これは食用米の慣行施肥量とほぼ同等である。施肥量と単収(玄米換算)との関係を見ると、施肥量が多くなると単収が上がるという相関関係ははっきりと出ていない(図5)。また、たい肥の投入量は平均で10アール当たり1トンであるが収量の増減との関係がこの回答でははっきりと出ていない。むしろ、他の個別の要因によって収量の増減が支配されている。具体的にいうと最も単収が多かった(10アール当たり858キログラム)のは大豆の後作に「ふくひびき」を「施肥なし」で栽培したところである。|
図5 窒素成分投入量と単収の関係
|
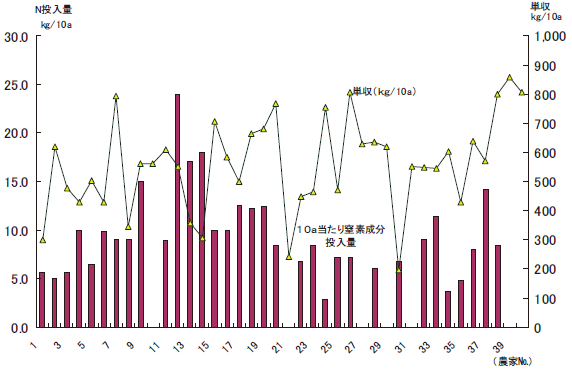 |
6) 栽培形態は「移植」がほとんどを占める
栽培形態は、「移植」のみが48戸でほとんどを占め、「直播」のみの農家は1戸、「移植と合わせて直播」に取り組んだ農家は5戸である。「直播」のみの農家の単収は344キログラムで移植よりも低いのが実態である。7) 除草剤等、農薬の使用は慣行栽培に準じる
「除草剤」は1戸を除き、全て農家が施用している。除草剤の種類は初期の一発剤の利用が多いので1回のみ使用がほとんどを占めている。しかし、一部の農家(3戸)は3〜4回、除草剤を散布している。農薬の使用は「殺菌剤」を使用している農家が31戸で平均の使用回数は1.7回、残りの23戸は殺菌剤を使用していない。「殺虫剤」の使用は28戸で平均の使用回数は1.3回で、残りの26戸は施用していない。病虫害の発生程度に応じて農薬を使用しており、慣行栽培に準じた使用である。8) 収穫は「自脱型コンバイン」、乾燥調整は「火力乾燥」
飼料用米の収穫はすべて「自脱型コンバイン」である。また、収穫後の乾燥調製は「天日乾燥」が2戸のみで残りは「火力乾燥」の農家である。これらの作業内容は食用米と全く同じ作業内容となっている。
4.飼料用米出荷の実態
1) 飼料用米の貯蔵方法は「フレコンバッグ」が多い
収穫した飼料用米の貯蔵方法は3分の1が「紙袋」、残りの3分の2は「フレコンバッグ」でフレコンバッグによる保管が多い。保管場所は、「JA倉庫」がほとんどを占め「自宅倉庫」や「畜産農家の倉庫」は少ない。 |
|
飼料用米はフレコンバッグで貯蔵
|
2) 飼料用米の保管は「常温」が多く、 出荷先はJAが多い
飼料用米の保管は「常温」がほとんどを占めており、「低温倉庫」の利用は6戸のみである(図6)。出荷先は「JA」が5分の3強を占め、残りは「商系」が3戸、「畜産農家」が14戸である。出荷時期は「収穫後すぐに」と「随時」が半々で、「通年」で出荷しているのは3戸のみである。|
図6 飼料用米の保管条件
|
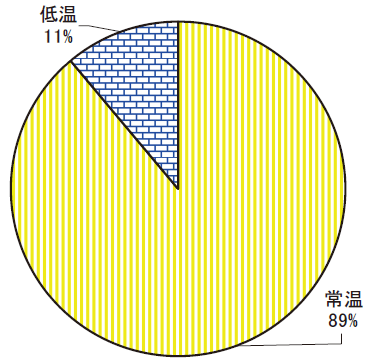 |
3) 飼料用米の出荷形態は玄米とモミ米の2形態が多い
出荷形態は「モミ米」が20戸、「玄米」が26戸、「モミ米と玄米の両方」が2戸、「不明」が6戸でモミ米と玄米での出荷形態が多い(図7)。飼料用米の流通先は一番多いのが「市町村内」の畜産農家であるが、一部で「県外」の畜産農家への流通もある。
|
図7 飼料用米の出荷形態
|
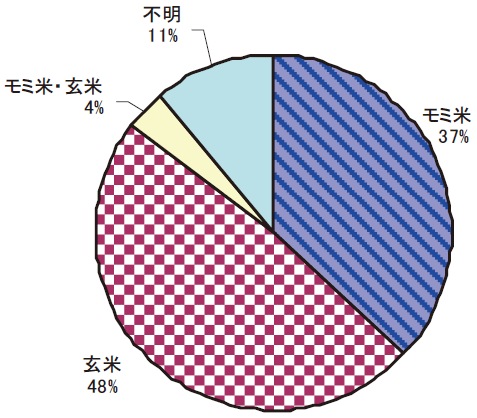 |
4) 飼料用米の農家販売価格はモミ米がキログラム当たり34円、玄米キログラム当たり48円
農家販売価格は平均するとモミ米出荷では1キログラム当たり34円、玄米出荷では同48円である。
5.飼料用米生産の経営収支
1) 飼料用米生産の収入は10アール当たり74,733円
回答農家のうち経営収支の明らかな48戸のデータを分析すると、飼料用米生産から得られる10アール当たりの販売収入は、飼料用米の販売価額が27,430円、助成金が42,734円、その他が4,569円で、合計は「74,733円」である。助成金収入が57%を占めているのが現状である(図8)|
図8 飼料用米生産の収入構成
|
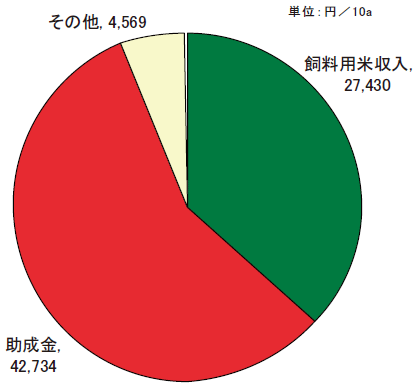 |
2) 飼料用米生産の費用合計は10アール当たり69,911円
次いで、生産コストを費用合計に相当するところでみると、10アール当たり「69,911円」である。内訳は「種苗費」が8,909円、「肥料費」が5,542円、「農業薬剤費」が4,266円、「光熱動力費」が1,096円、「その他の諸材料費」が602円、「土地改良及び水利費」が6,154円、「賃借料及び料金」が9,640円、「建物費」が1,230円、「自動車費」が138円、「農機具費」が10,640円、「労働費」が15,675円、「その他」が6,019円である(乾燥調整は「農機具費」と「賃借料及び料金」に含まれる)。食用米生産の費用合計(平成19年米)である10アール当たり115,721円と比較すると労働費を中心として4割程度縮減されている(図9)。
|
図9 飼料用米生産の費用合計
|
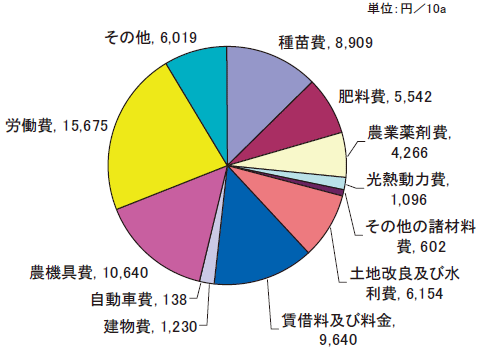 |
3)飼料用米生産の実質的な経営収支は赤字
そこで、以上の販売収入の合計から生産コスト(費用合計に相当)を差し引くと10アール当たり4,822円のプラスとなるが、地代や資本利子がこの費用には含まれていないことから実質的には赤字である。なお、労働費を自己労賃と見なした場合の飼料用米所得を見ると、10アール当たり20,497円である。したがって、20年産の現段階における飼料用米生産の経営収支は助成金を加えても経営的には自分の労働費の一部がなんとか賄える程度である。なお、21年産については、大幅に助成金が増額されたことから経営収支は黒字への改善が期待される。
6.おわりに
本稿では、20年産の飼料用米生産の経営収支を分析したが、現段階ではほとんどが初めての取り組みということもあり、飼料用米生産は、食用米の品種、栽培体系、生産構造を軸に展開しており、助成金なども加えた収入と生産コスト(費用合計)はほぼ同等で経営収支は厳しいことが明らかとなった。これを克服し、経営収支を改善するためには地域に適合した超多収穫品種への転換を含めて生産コストの大幅な削減に結びつくように栽培技術体系の根本的見直しが必要である。現在、畜産マネジメント研究室では、現行の飼料用米生産コストの5分の1以下での生産が実現できるよう、超低コスト栽培技術の確立に向けて、各地の農家と一緒に平成21年産から本格的に取り組んでいる。コストダウンの方策で最も効果的なのは単収の大幅な増大であり、その鍵となるのは(1)超多収品種の導入、(2)たい肥の大量施用(化学肥料の大幅削減)、(3)水管理の合理化、(4)乾燥調製作業の省略、(5)育苗作業の省略、(6)農薬撒布の節減、(7)機械費(償却費)の削減である。投入労力と投入資材をできるだけ縮減しながら単収を上げていく栽培法を確立していけば、将来的には助成金に依存しなくても飼料用米の実用化の可能性は高いと考えられる。
 |
|
東京農業大学畜産マネジメント研究室による飼料用米の収穫作業(厚木農場・棚沢水田)
(20年産の全刈収量はモミ米で10アール当たり1,073キログラム) |
本調査の実施者
東京農業大学農学部 畜産学科 准教授 信岡誠治
東京農業大学農学部 畜産学科 畜産マネジメント研究室
調査情報部調査課(現酪農乳業部乳業課)伴加奈子
参考資料: 社団法人日本草地畜産種子協会「平成20年度飼料用米の利活用に向けた調査報告書
−国産飼料資源活用促進総合対策事業 飼料用米導入定着化緊急対策事業−」
(平成21年3月)