1.はじめに
わが国の自給率向上や未利用資源の積極的利用などの観点から推進されてきたコメの飼料用利用(以下、「飼料用米」という。)の取り組みについては各地で見られるようになった。特に養豚部門での利用は、特徴ある畜産物として差別化を図ることに成功していることなどから認知度が高っている。また、地域水田農業活性化緊急対策など政策的な後押しもあり飼料用米の作付面積は増加傾向で、農林水産省生産局畜産部畜産振興課の調べによると平成20年度は前年度比5.5倍の1,611ヘクタール、平成21年度は同2.6倍の4,129ヘクタール(平成22年2月時点見込み)と2年続けて大幅に増加した。飼料用米が利用される畜種については、豚のほか採卵鶏にも広がり、こだわりの生産方法の一つとして定着しつつある。このよう中、岩手県北部の肉用鶏(ブロイラー)経営において、全国的にも例の少ない飼料用米の全羽給与が開始された。今回、同県軽米町の稲作農家および洋野町でブロイラー経営を行う株式会社ニチレイフレッシュファーム洋野農場(以下、「洋野農場」という。)でのこの取り組みについて聞き取りをする機会を得たので紹介する。
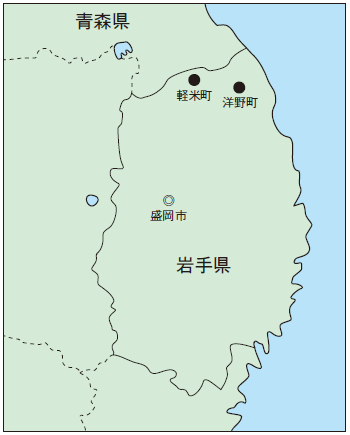 |
|
図1 飼料用米作付面積の推移
|
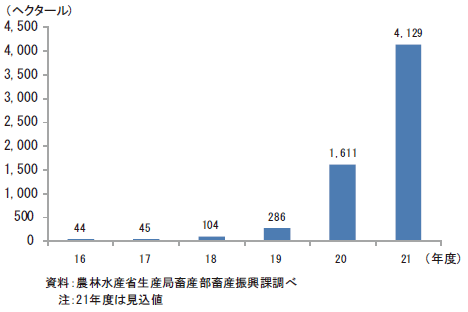 |
2. 軽米町での飼料用米生産の取り組み
(1) 軽米町農業概況軽米町は、岩手県の北端に位置し、主要作物は、水稲、ほうれんそう、葉タバコ、ホップなどとなっている。畜産も盛んで農業産出額ベース(平成19年時点、以下同じ。)では町全体の76%を占め、畜種別ではブロイラーの割合が同41%と高い。総耕地面積は2,430ヘクタールで、このうち水田が919ヘクタールと全体の38%を占めている。しかし、図2のとおり、作付面積は522ヘクタールと全体の56%となっており、残りの4割以上が休耕、または、何らかの理由で耕作されていないことが分かる。
|
図2 軽米町における水田の作付面積(平成19年)
|
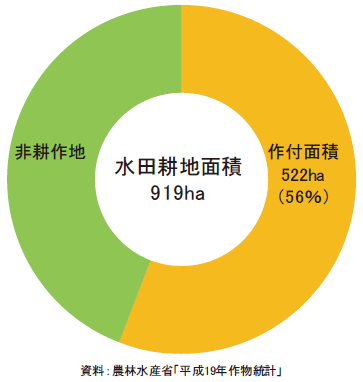 |
軽米町では、平成19年度から養豚用飼料への供給および休耕田の有効利用を目的に飼料用米の生産を開始した。作付面積は、初年度の4ヘクタールから始まり翌20年度には11ヘクタール、21年度については33ヘクタールにまで増加している。同町によれば作付面積増加は、洋野農場への供給開始によるところが大きいとしており、21年度の作付面積のうち25ヘクタールは同農場向けとなっている。品種は、多収量型の岩手85号(つりみのり)を利用しており、21年度の単収は最も高い農家で10アール当たり600キログラム程度となっている。稲作生産者によれば、飼料用米生産を開始後3年ということもあり、食味ではなく収量を増加させるための栽培技術が発展途上にあるという。そのため、技術を習熟すれば将来的には同800キログラム程度まで増加させることも可能とみている。同町では、休耕や高齢化の影響などから作付されない水田も多いものの、新たな作物を見いだせない状況にあったことから飼料用米への期待は高い。生産者の多くは長年米を生産しており、用途が変わっても基本的な栽培方法は従来と同じであることに加え新たな機械の導入が不要であることからも飼料用米生産のメリットは高いとしている。作付面積の増加に伴い生産量が増加した結果、町内の畜産農家も飼料用米の利用に関心を持ち始めているという。
ただし、作付面積の増加については、10ヘクタール当たり8万円の補助金も大きな要因となっている。反収が500キログラムの生産者の場合、販売価格(調査時聞き取り)は1キログラム当たり50円、10ヘクタール当たり2万5千円(乾燥調整など諸経費控除前)程度であることを考慮すると、その効果が大きいことがうかがえる。
 |
|
軽米町で生産された飼料用米(平成21年10月撮影)
|
3.飼料用米を利用したブロイラー生産の事例
(1) 生産概況
洋野農場は、軽米町に隣接する洋野町において平成19年11月からブロイラー生産を開始した。同農場は、鶏舎が32棟で常時約20万羽を飼養しており、年間出荷羽数は約140万羽となっている。成育期間は60日以上と約2カ月に一回の割合で出荷し、農場全体で見ると年間でおおむね4回転していることになる。品種は独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(以下、「センター兵庫牧場」という。)で育種改良された「小雪(こゆき)」と「紅桜(べにざくら)」の交配種である「純国産鶏種たつの」を採用している。ブロイラー生産に採用される品種の原種は主に海外からの輸入が大部分を占めているが、これらに比べ国産鶏種は日本人が好む適度な弾力とうま味の濃さを兼ね備えている点が一つの付加価値となっており、生産された鶏肉は「純和鶏(じゅんわけい)」というブランドで販売されている。同農場では、国産飼料を給与することによって製品の付加価値をさらに高め、また、地域における資源循環サイクルの構築を図ることを目標に、軽米町で収穫された20年産飼料用米の玄米での給与を平成21年1月に開始した。年間の飼料総給与量が約8,000トンに対し飼料用米は約120トン程度に過ぎないが、飼養する全羽に給与する大規模なブロイラー経営の事例は少ない。
 |
|
同一敷地内に32棟の鶏舎を設置
|
飼料用米利用に当たって洋野農場がまず配合飼料メーカーに相談を持ちかけたところ、隣接する軽米町で生産されていることを知り、その後、地元JA、配合飼料メーカーなどとの調整を経て、今年1月からの全羽給与が実現された。飼料用米利用に当たっての最大の課題は、従来から利用している配合飼料の主原料であるトウモロコシに比べ割高であることにある。そのため、配合割合は後期仕上げ飼料用として2%配合することからのスタートとなっている。
飼料用米給与のコスト削減の方法の一つとして、現在行っている玄米での配合から、籾での配合にすることを挙げている。肉用鶏への飼料用米給与に関する試験を行ったセンター兵庫牧場によれば、従来の配合飼料を給与した群と籾米を10%配合した飼料を給与した群とでは、増体などの成育面でも遜色はなく、また、ふんに籾は残らないと報告されており実現性が高いコスト削減の方法とみられる。しかし、同農場は、籾に付着した残留農薬の基準が明確ではないため採用していない。農薬を使用せず、当地で生産が盛んな木炭の副産物である木酢液を農薬の代わりに散布することも検討されたが実現に至ってないとのことであった。稲作農家は、飼料用米の水田に農薬を散布しないことによって近隣の食用を含めた水田に病害虫の被害が広がることを懸念しており賛同を得ることは困難とみられている。社団法人日本草地種子協会が発行する飼料用稲・米に関するガイドブック「飼料用イネ種子のご案内」によれば、鶏へ給与する飼料用米への農薬の使用に当たっては、(1)出穂期以降に農薬の散布を行う場合には、家畜へは籾摺りをして玄米で給与すること、(2)籾のまま、もしくは籾ガラを含めて給与する場合は、出穂期以降の農薬散布は控えることが推奨されている。(2)の対策をとれば籾での給与も可能ではあるが、同農場では科学的に検証されたデータに基づいて籾での給与を検討することとしている。
配合割合の引き上げの可能性については、コスト面での課題を別にすれば、30%程度まで引き上げてもブロイラーの成育面や製品の品質に問題は無いとみている。むしろ配合割合を高めることによって、飼料用米を給与した鶏肉として製品の付加価値を高めることが出来ると期待を寄せている。
(3) 耕畜連携で資源循環モデルを確立 〜鶏ふんを水田に還元〜
同農場は、ブロイラー生産に飼料用米を利用することと併せて鶏ふんを飼料用米の肥料として利用する耕畜連携にも取り組んでいる。1日当たり約12トン発生する鶏ふんの水分含有率は通常40%程度であるが、これを国内でも珍しい鶏糞有機肥料化設備で乾燥することで約3%程度としている。乾燥された鶏ふんは、フレコンバックで肥料原料として出荷されているほか、一部は農家に直接販売され、飼料用米の水田には直接散布されている。鶏ふんの肥料利用については、産業廃棄物として処理した場合のコストを考慮すると、メリットは高いという。
軽米町で生産された飼料用米と同農場で発生する鶏ふんの流通経路を整理すると、(1)地元JAの施設へ集荷され乾燥調整、(2)青森県八戸市の飼料メーカーで飼料へ配合、(3)洋野農場へ配合飼料として搬入、(4)飼料用米を給与した鶏のふんが水田に還元−となっており、飼料用米と鶏ふんを通して地域の資源循環モデルが構築されている。現在、稲作農家は散布後速やかに耕起することで飛散を防止していることから、この取り組みを広めるためには、散布時に飛散しやすい粉末状からペレット状にするなど鶏ふんの形状を工夫し、利用者を増やすことも課題のようである。なお、飼料用米については洋野農場とJAが、飼料用米を混合した配合飼料については洋野農場と配合飼料メーカーが取引を行っている。
 |
|
乾燥プラント内部
|
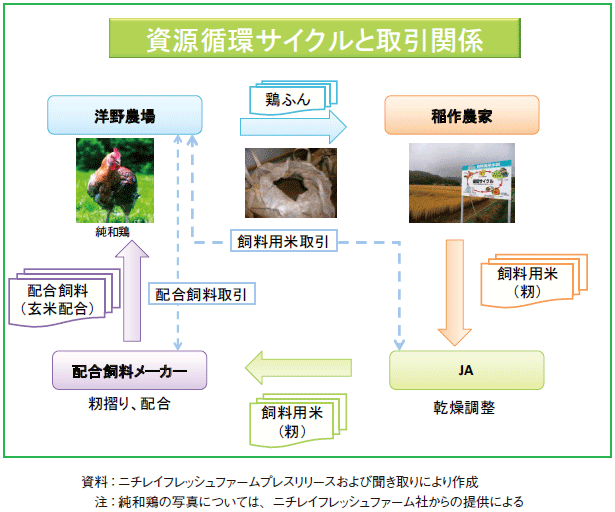 |
4.おわりに
訪問先では、飼料用米の供給者である稲作農家と需要者である畜産経営とが近隣に立地しており、輸送や両者の意見調整といった面からも理想的な協力関係を構築しているように感じられた。洋野農場は、国産鶏種を利用した特徴のあるブロイラーの生産をしているため、一層の付加価値を目指すという点から飼料用米を利用しやすい経営環境にあるとみられるが、一般のブロイラー経営において利用が定着するにはコスト面などから課題もあろう。しかし、ブロイラー経営は、ほかの畜種に比べ規模拡大が進展していることから1経営体当たりの飼料の利用量は大きいと考えられ、これらの経営において飼料用米が利用されれば、配合割合は少なくともまとまった需要が期待でき安定的なユーザーとなりうると考えられる。ただし、飼料用米の利用を推進するためには、生産者である稲作経営の協力はもちろんのこと、利用者である畜産経営側にも何らかのインセンティブが必要である。同農場では飼料用米の利用を商品のこだわりとして付加価値化につなげるといった検討をしているものの、具体的に消費者へどのような方法でアピールしていくかは今後の課題と語っていた。
水田を利用した自給率の向上や潜在的生産能力を確保するため、平成22年度から新たな政策的支援の開始が決定されている。農林水産省によれば、戸別所得補償モデル対策として飼料用米の生産に10アール当たり8万円の助成を行う水田利活用自給力向上事業を開始予定であり、現在、事業現場への周知や、供給者である耕種農家と需要者である畜産農家などのマッチング活動を行っているとしている。また、籾米利用の畜産物に係る農薬残留を評価するための事業も実施することとしており、洋野農場のように給与コスト削減の方策として籾での給与を検討しながらも、残留農薬の問題で採用に踏み切れない経営にとっては、その期待は高いであろう。
洋野農場で飼料用米を給与して生産された鶏肉は、3月から出荷が開始されている。生産段階における品種、飼料へのこだわりをどのように消費者に伝え、取引に活かしていくのか注目したい。また、軽米町では飼料用米生産が増加したことを背景に地域の畜産農家も関心を持ち始めており、ブロイラー経営における飼料用米利用の先進的取り組みの開始によって、全国的にも養鶏の盛んな岩手県北部および青森県南部において今後どのように波及していくのかについても注視していきたい。
おわりに今回の調査に当たり、ご協力いただいた軽米町の稲作関係者およびニチレイフレッシュファーム洋野農場の皆さまにこの場を借りて感謝申し上げたい。
(参考資料) 農林水産省大臣官房統計部「作物統計(平成19年度)」
独立行政 法人家畜改良センター兵庫牧場ホームページ
社団法人日本草地種子協会「飼料用イネ種子のご案内」
ほか