【要約】
わが国の酪農・畜産経営は、飼料用穀物のほとんどを輸入に依存していることから、近年の飼料価格高騰などの影響を受け、生産コストが高止まりするなど、経営をめぐる状況は厳しい。飼料の調達コストをいかにして低減させ、かつ必要量を安定的に確保するのかということが喫緊の課題となっている。本稿では、飼料卸会社である湯浅商事株式会社と、その取引先の1つである有限会社マルミファームの取り組み事例を基に、食品循環資源の活用や配合飼料との関係について紹介するとともに、今後の資源の活用と課題について整理する。
1.はじめに
2006年秋から2008年にかけての価格急騰以降、下落傾向にあった穀物の国際価格は、2010年より再び上昇に転じ、主要な飼料穀物であるとうもろこしや大豆の国際価格は、2012年夏に過去最高を記録した。2013年からは下落に転じてはいるが、2014年2月末現在、2006年秋頃と比較して価格は1.6〜2.6倍となっている(農林水産省大臣官房食料安全保障課「穀物等の国際価格の動向」、2014年3月3日発表)。輸入穀物に強く依存し、飼料費が生産費の中心を占めるわが国の酪農・畜産経営にとって、依然として厳しい状況であることに変わりはないと言えよう。
このような価格変動の背景には、BRICs諸国における飼料穀物および酪農・畜産物需要の拡大に加えて、気候変動や過剰耕作に伴う穀物生産基盤の脆弱化、投機マネーの穀物市場への流入に象徴される金融経済化などの構造的変化がある。すなわち、「飼料需給安定法」「配合飼料承認工場制度」「保税工場制度」および基本法農政下での選択的拡大など、これまで安価な輸入穀物に依存することで酪農・畜産経営における飼養規模拡大と収益率向上が推進されてきたが、その前提条件が大きく崩れたことを意味している。ただし、これは現在に始まったことではない。世界同時不作と米国による大豆禁輸措置、オイルショックによる不況に起因する1970年代の畜産危機がその代表であり、輸入穀物に強く依存するわが国の酪農・畜産経営の脆弱さが露呈されたのである。昨今のわが国の酪農・畜産経営が直面している状況は、畜産危機がさらに先鋭化したものと言っても過言ではない。
1960年の「貿易・為替自由化計画大綱」以降、輸入酪農・畜産物に対する関税・非関税障壁の削減や、近年におけるFTA/EPA締結により、わが国の酪農・畜産経営は世界レベルでの価格競争に包摂されてきた。更にTPP交渉が予断を許さない状況にある一方で、「アベノミクス」により景気がやや回復基調にあると言われてはいるが、食品関連産業および消費者における低価格志向は依然として強く、差別化による脱価格競争にも限界がある状況となっている。
以上のようなわが国の酪農・畜産経営を取り巻く状況を勘案すれば、生産費の中心を占める飼料の調達コストをいかにして低減させ、かつ必要量を安定的に確保するかということは喫緊の課題である。本稿では、中堅飼料卸会社である湯浅商事株式会社(愛知県名古屋市)と、その取引先の1つである有限会社マルミファーム(愛知県額田郡幸田町)を事例として、それぞれにおける食品循環資源と配合飼料との関係に注目して、上記課題への接近を試みたい。
2.飼料会社における食品循環資源と配合飼料との関係
1)湯浅商事株式会社の概要
1947年に設立(創業は1910年)された湯浅商事株式会社(以下「湯浅商事」)は、従業員110名、年商270億円(2012年3月)の中堅飼料卸会社である。1931年に主要配合飼料メーカーの1つである日本農産工業株式会社の代理店となり、現在では日本配合飼料株式会社、協同飼料株式会社、日清丸紅飼料株式会社、中部飼料株式会社、兼松株式会社、くみあい飼料株式会社などの代理店として、配合飼料の販売を行っている(配合飼料部門)。このほか、海外からの乾牧草、ビート、ヘイキューブなどの粗飼料、とうもろこしなどの穀物、国内で発生する食品循環資源などを扱う輸入飼料部門、食品循環資源を原料の1つとするTMRの製造・販売を行う飼料製造部門などがある。2)食品循環資源と配合飼料との関係
2000年代に入り、飼料給与合理化を目的に、酪農経営においてTMRの導入が進められていた。湯浅商事では配合飼料販売以外に、大型家畜用の輸入粗飼料などの販売も行っていたが、2005年頃から、輸入乾牧草(主にスーダングラス)の価格上昇と品質のばらつき(主に太さの違い)が出た。他の粗飼料を探したが、嗜好性や採食性に問題があったことから、それを解消するために発酵TMRの製造に取り組んだ。製造を始めた当初、名古屋近郊に立地する缶詰工場から排出されるパイナップル粕や、ビール工場から排出されるビール粕などを原料として利用していた。当時はこういった物が主流だった。ただし、ビール粕については、飼料としての需要が増大する一方で、ビールと比較して麦芽使用量が少ない発泡酒や、麦芽を使用しない「第3のビール」のシェアが増大したことから、ビール粕供給量が減少しており、現在ではビール粕の安定的調達が困難となっている。名古屋近郊だけでなく、関西地区からも調達をしているが、それでも供給量が少ないことから、代替原料として濃縮ビール廃液も利用している。また、おからとパイナップル粕にとうもろこしを混合した発酵飼料も製造・販売している。
湯浅商事が取り扱う発酵TMRは、長野県と宮崎県にある工場で製造されており、原料は主に地域で調達している。注目すべきは、宮崎の工場では酪農経営の要望に応じて、発酵TMRの混合割合を調整し供給していることである。具体的には、自給飼料や酪農経営が独自に調達する焼酎粕などの食品循環資源の内容と量に応じて、自社ブランド発酵TMRにおける原料の混合割合を調整し供給しているのである。食品循環資源には、排出量の季節変動が大きく、通年での同一資源の利用が難しいという特性があるが、湯浅商事による発酵TMRの混合割合の調整は、食品循環資源の飼料利用において課題となる、排出量の季節変動の克服という意味において重要となってくる。食品循環資源を含む低・未利用資源の飼料利用が政策的にも推進されているが、排出量の季節変動の大きさから、飼料として十分に利用されているとは言いがたい状況にある。それゆえ、こうした取り組みは、酪農経営の近隣に存在する多様な食品循環資源の飼料利用における鍵と評価できるのである。
大型家畜用以外にも、養豚用飼料として、ジャガイモ加工の際に出る皮や残さ(ポテトピール)の販売も行っている。京都に立地する食品加工業者から排出される、液状化されたポテトピールを全量引受の条件で調達しており、取引先である養豚経営に販売されるほか、販売残についてはスポットで消化されている。ポテトピールは、食品加工業者において、ph調整のため蟻酸を添加している。湯浅商事は廃棄物の収集・運搬に関する許可を有していないことから、輸送については廃棄物処理事業者へ業務委託している。また、ポテトピールが調達できない場合の調整も行っている。工場からの排出予測数量を養豚経営者へ示し、経営毎に不足分を独自に調達してもらうか、代替品を手当てすることもある。全量引受には、排出側である食品加工業者にとっては廃棄物処理に関する煩雑性の回避、湯浅商事にとっては安定的かつ安価に調達することが可能となるメリットがあるが、販売残をスポットで消化しなければならないというデメリットもある。それでも湯浅商事が養豚用飼料としてポテトピールを取り扱うことの意味は大きい。湯浅商事の中心的事業は配合飼料販売であるが、わが国の配合飼料市場が停滞・縮小傾向にあり、飼料の差別化が困難かつ値引き競争にも限界があるなかで、安定的な需要者を確保していくことが企業として必要不可欠な状況となっている。食品循環資源の利用が増えれば配合飼料の利用は減るが、安価なポテトピールの量的・価格的安定供給を担保することによって、配合飼料需要者の固定化が図られているのである。こうした湯浅商事の対応は、需要者である養豚経営においてもメリットがある。飼養規模が小さく需要量の制約があって、排出事業者から直接調達することができない経営においても、安価なポテトピールの調達が可能となっているのである。
ポテトピールの販売そのものの利益率は低く、また、これ以上食品循環資源の取り扱いを増やすことは、配合飼料販売との競合を引き起こすことが考えられるため、中心的事業としては位置づけられてはいない。換言すれば、すべての経営が食品循環資源のみによる給与体系となることはないことから、配合飼料の販促ツールとしてコストの低いポテトピールが位置づけられていると理解できる。ここに飼料卸会社としての限界があると言えるが、そのほかの食品循環資源については、養豚経営に対し中間処理事業者を紹介することで対応している。
図1 湯浅商事株式会社によるポテトピールの商流・物流と食品循環資源に関する情報提供 |
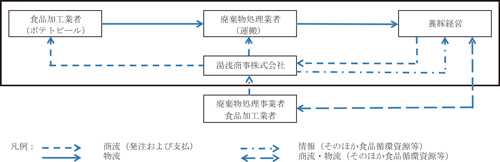 |
資料:湯浅商事株式会社へのヒアリング調査(2013年11月)に基づき作成。 |
3.養豚経営における食品循環資源と配合飼料との関係
1)有限会社マルミファームの概要
有限会社マルミファーム(以下「マルミファーム」)は、日本農産工業株式会社に勤務していた稲吉弘之氏によって1974年に設立された。母豚36頭の繁殖経営としてスタートしたが、弘之氏が会社勤務であったことから、妻の昌子氏が主体的に養豚業に従事していた。弘之氏が同社を退職した1978年に母豚60頭の一貫経営に移行し、以後規模拡大が図られている。2011年に獣医師でもある稲吉克仁氏(2001年マルミファーム入社)が代表取締役として経営を引き継ぎ、母豚400頭(年間出荷頭数9,000頭)の地域最大規模の養豚経営となっている。豚舎の管理業務は克仁氏のほか社員5名とパート1名で行っている。2007年に、食品循環資源の飼料利用によるコスト削減を目的に、リキッドフィーディングシステムを導入し、現在では指定配合飼料のほか、ポテトピール、菓子屑、ウズラ卵など多様な食品循環資源が飼料として活用されている。
 |
豚舎内の様子 |
2)飼料共同購入組織「やまびこ会」設立
「やまびこ会」は、全国養豚経営者会議(現・一般社団法人日本養豚協会)での視察を契機として、マルミファームを中心に1997年に設立された。視察先である九州の養豚経営では、とうもろこしの全粒粉を主原料とする自家配合飼料が給餌されており、同等水準の既成配合飼料と比較して飼料価格が安価で、飼養成績も良好であった。これに刺激を受け、マルミファームほか近隣の養豚経営においても自家配合飼料への転換の機運が高まったのであるが、設備や維持コストの問題から実現には至らず、飼料原料の共同購入・配合委託のための組織として「やまびこ会」が設立された。会員20名、飼料購入量は1カ月当たり2,000トンからスタートし、現在では25名、同3,000トンまで拡大している。会の中では母豚400頭が最大規模で、ほかは200頭前後とそれ以下の養豚経営で構成されており、中小規模養豚経営の組織ではあるが、同会全体で母豚4,000頭の規模となっている。「やまびこ会」の1カ月当たりの配合飼料需要量は、小規模配合飼料工場における月間定時生産能力に相当する量であり、比較的大規模な配合飼料工場(月産定時生産能力1万2000トン〜1万5000トン)が立地する伊勢湾地域においても、価格交渉力を発揮するには十分な量となっている。「やまびこ会」の設立契機が自家配合飼料への転換であったことから、他で見られるような指定配合飼料の共同購入とは異なった活動を行っている(図2)。原料選定は「やまびこ会」が直接行い、商流と物流を湯浅商事、配合を大手配合飼料メーカーへ委託しているのである。委託先のメーカーは2社あり、肉豚用と繁殖豚用で別になっている。1社独占より全体で経費が安くなるため、このような体制となっている。設立以来、年1回枝肉勉強会を開催し、各経営の枝肉を見比べ、生産する肉豚の方向性を確認しあってきた。また、それとは別に、会員同士で飼養成績を比較検討する機会を年2回設けている。これと並行して、四半期毎に飼料配合設計についての検討会も開催され、各養豚経営における肥育成績に基づく配合設計の見直しや、原料動向についての情報共有が行われており、これは現在も継続して実施されている。技術情報については生産者団体との交流のほか、各配合飼料メーカーやコンサルタントなどから提供を受けているが、最終的な決定は「やまびこ会」が行っており、主体性の確保と知識の蓄積が図られている。肥育豚の販売は基本的には個別販売となっているが、4戸共同でスーパーに直販しているものもある。
図2 「やまびこ会」における配合飼料調達および情報交換・蓄積システム |
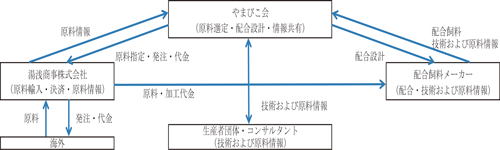 |
資料:有限会社マルミファームへのヒアリング調査(2013.11)に基づき作成。 |
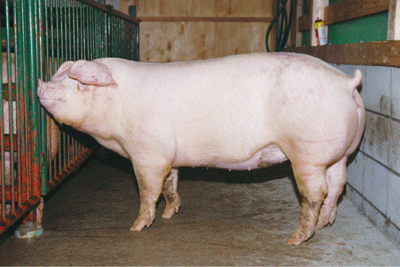 |
夢やまびこ豚 |
3)リキッドフィーディングによる食品循環資源活用の取り組みと生産性
穀物価格高騰による飼料費削減問題に直面した2007年、克仁氏は飼料効率向上を目的に、リキッドフィーディングへの転換を図った。しかしながら、氏が視察した岐阜県高山市の事例(有限会社ロッセ農場(以下「ロッセ農場」)、母豚1,000頭規模)では10パーセント程度の向上が確認されたが、運用面での経験不足から、マルミファームでは期待した水準までは向上しなかった。このため、ロッセ農場の関連会社から技術者の派遣を受けてその克服を図ると同時に、運用および飼料設計に関わる知識の蓄積を図っている。現在、リキッドフィーディングに関する作業は、平日1日当たり2〜3時間、1名の従業員で行っている。リキッド飼料は1日に10〜12回(2時間毎)給与されるが、コンピューター制御となっており、餌槽に飼料が残ると自動的に給餌が止まる(この場合、1回休んで4時間後に餌槽が空になると給与される)。1度システムをセットすると、豚の成長に応じて設定されたフィードカーブに合わせて、自動的に給餌量が増加するようになっている。マルミファームでは4,000頭分のシステムを導入しており、導入費用は資材費約4000万円、工事費込みで約1億円となっている。頭数が増えてもコンピューターは1台で対応できるので、規模が大きい方がコストは安い。豚舎をオールアウトした際に配管および配線などの作業を行いながら、複数の豚舎に導入していった。システムのメンテナンスコストは、部品代などが年間通して必要となる。
飼料要求率は、配合飼料のみでは3.1〜3.0であったが、食品残さを利用して2.7〜2.6に向上していることから、結果的にコストダウンにつながっている。また、オランダから導入した母豚の成績が良いため、9,400〜9,500頭だった出荷頭数が、今は1万頭を超えている。母豚頭数が変わらないのに離乳頭数が1週当たり180頭から200頭以上となったため、現在は母豚頭数を減らしている。
マルミファームでは、食品残さの取り扱いを増やしたいが、調達量が不足気味のため難しく、現状では飼料は変更できないと考えている。これ以上不足が続くようであれば、配合設計を見直す必要があるとのことである。規模拡大した経営の中には、ヘルスコントロールや飼料、母豚の品種の見直しで飼料要求率を改善できる、と判断してリキッドフィーディングを選択しなかった経営もあることから、従業員教育など人件費をかけて取り組むメリットがどこまであるか、精査していく必要があると考えている。今後は、飼料要求率を更に追求し、安定した離乳成績を維持しつつ、豚舎の有効利用など効率化を図って行く、とのことである。
 |
リキッドシステムが導入されている豚舎 |
 |
飼料原料の保管施設(写真左は液体原料用のタンク) |
4)食品循環資源の活用と調達
「やまびこ会」会員の中でリキッドフィーディングシステムを取り入れているのはマルミファームのみであり、2007年から育成・肥育豚向けに取り組んでいる。当時、名古屋市で展開する一般社団法人循環資源再生利用ネットワーク(以下「ネットワーク」)を紹介されたことを契機に、2009年から食品循環資源を飼料原料として調達している。2003年に設立されたネットワークは、食品加工業者、食品流通業者、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬・中間処理業者、耕・畜産経営者、肥飼料メーカー、生協など71法人7個人の会員によって構成され、食品加工・流通業者から排出される230品目以上(ただし恒常的に排出されるのは120品目程度)、量にして年間1万1400トンの食品循環資源を、飼料原料として酪農・畜産経営へ供給している(2013年度実績)。物流と商流については各会員間で直接行われるが、ネットワークでは情報共有に基づく需給接合・調整が図られている。具体的には、需要者である酪農・畜産経営における要望と食品加工業者・流通業者からの供給条件の擦り合わせが行われ、近隣での需給接合・調整が図られている注1。
当初、ネットワークに参加することで、近隣で原料を調達しやすくなると考えたが、県によってその取り扱い基準が異なったため、県内にも原料があったものの調達ができず、車で3時間の距離にある岐阜県内で調達していた。
マルミファームでは、ネットワークからの調達をベースに、多様なルートで食品循環資源の調達を行っている(図3)。前述のポテトピール調達のほか、豆腐類製造業者からおからや廃豆乳を調達している。マルミファームは産業廃棄物を取り扱う各種許可を有していないが、「再生利用業個別指定制度」に定められた再生活用業の指定を受け、おからや廃豆乳を直接調達している注2。これは、豆腐類製造業者が比較的近隣に立地しており、産業廃棄物処理業者を経由して調達した場合に物流費負担が大きくなるためである。「再生利用業個別指導制度」の指定は1年ごと、また産業廃棄物ごとに行われるため、多様な食品循環資源を独自に調達する場合には手続きが煩雑であるが、近隣から特定の食品循環資源を調達する場合には有効な制度として機能している。このほか、近年では、ネットワーク会員以外の産業廃棄物処理業者からの調達も増えつつある。同業者間における情報交換により、新たな販路として認知されたことがその要因であり、一部は固定的な調達先となりつつある。
図3 有限会社マルミファームにおける食品循環資源調達経路概要 |
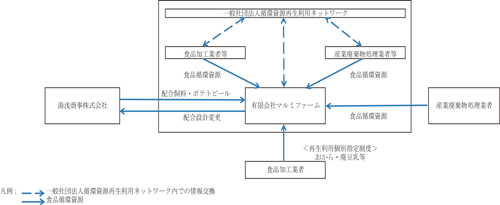 |
資料:有限会社マルミファームへのヒアリング調査(2013.11)に基づき作成。 |
 |
キッチン内部 原料を混ぜるプレミキシングサイロ |
注1 酪農・畜産経営からの要望のうち、代表的なものとして、塩分・油脂分の高い食品循環資源の
混入を避けること、腐敗・変敗などの防止策を行うこと、取引ロットおよび価格の引き下げなどが
ある。一方、食品加工業者をはじめとする供給業者からは、運賃負担の観点から、取引ロットの
引き上げ、再資源化率の低い食品循環資源の飼料利用拡大などが要請されており、これらに
起因する需給のミスマッチ解消がネットワークにおいても課題となっている。
注2 再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を、都道府県知事が
再生利用に関わる産業廃棄物とその利用方法を特定した上で個別に指定し、産業廃棄物処理
業の許可を不要とする制度。再生利用業には、再生利用のために産業廃棄物の収集運搬を行う
「再生輸送業」と、再生利用のために産業廃棄物の処分を行う「再生活用業」がある。
4.おわりに
経営外部の諸要因によって決定され、しかもそれが生産費の中心を占める飼料の調達コストをいかにして低減させ、かつ必要量を安定的に確保するのか。本稿では食品循環資源と配合飼料の関係に注目して、この課題に接近を試みてきた。事例とした湯浅商事は、中堅飼料卸会社として長い歴史を有し、わが国における酪農・畜産の発展とともに事業を拡大してきたが、国内飼料市場の縮小という大きな転換点に直面している。食品循環資源への取り組みは、収益の観点からみれば、新たな事業として企業の屋台骨となることは望めないだろう。しかし、その小さな胎動が大きくなる可能性を秘めていることもまた事実である。酪農経営における自給飼料や独自に調達する食品循環資源などに応じた、自社ブランド発酵TMRにおける混合割合の調整は、酪農経営における食品循環資源の活用という選択の幅を広げる可能性を内包しているのである。
このことは、もう1つの事例であるマルミファームの成果より確認される。マルミファームでは、多様な食品循環資源を飼料原料として活用することにより、年間1800万円もの飼料費の削減を図っている。やや矛盾する言い方になるが、これを可能にしているのが「やまびこ会」の一員として湯浅商事から調達する配合飼料なのである。事例でも確認されるように、配合飼料割合の上昇は飼料費に直接影響を及ぼすことになるが、食品循環資源の調達状況に応じて配合飼料の設計を細かく調整することによって、食品循環資源に不可避な量的変動による栄養価の変動が吸収されている。季節変動などが比較的少なく、量的にも安定している一部の食品循環資源に需要が集中し、それ以外の食品循環資源の飼料への利用が進まない要因の1つに、量的変動による飼料の栄養価の変動を細かく調整する手段を酪農・畜産経営が有していない、換言すれば、主たる飼料となっている配合飼料の配合設計における自由度が、極めて狭い範囲にしかないことを指摘することができよう。マルミファームにおける食品循環資源の位置と配合飼料との関係がそれを雄弁に物語っている。粗飼料、単味飼料、配合飼料、食品循環資源のそれぞれの位置と相互関係の把握から、各酪農・畜産経営における最適な組み合わせを追求していくことが求められるのであり、その根底には、忍耐強い試行錯誤に基づく経験と知識の蓄積が不可欠である。訪問の際に稲吉克仁氏には数多くの資料をご提示いただいた。その記録の緻密さと多岐にわたる検討の積み重ねこそが、これからの酪農・畜産経営の生き残りにおいて不可欠であると、改めて感じさせられた。
現在、ロットの大きな一部の食品循環資源は、北海道で調達された物が関東まで運ばれるなど広域に流通している。大規模な経営であれば使用量も多く、入手しやすいかもしれない。規模がそれほど大きくない経営でも、地域にある小ロットな資源を活用できるようになれば、運搬にかかる経費をかけず、更なる資源の活用が進む可能性があるのではないか。そのためには、飼料設計や給与体系についての情報提供など、できることはあるはずである。今後の取り組みに期待したい。
―謝辞―
本稿執筆にあたって、湯浅商事株式会社輸入飼料部和田英男様ならびに配合部中尾年秀様、有限会社マルミファーム社長稲吉克仁様には貴重なお時間とお話をいただいた。ここに紙面を借りて御礼申し上げる。