【要約】
TPP交渉が大筋合意し、本格的なグローバル競争時代を迎えることが明白になった今や、国内農業は競争力強化策を急がねばならない。
埼玉県川越市の養豚経営・(有)大野農場は、膨大な資本投資で飼養規模を拡大するのではなく、“
1 はじめに−課題と背景−
難航した環太平洋戦略的経済連携協定(以下「TPP」という)だが、ついに大筋合意に達した。合意内容の全容も見えてきた。牛肉と豚肉は重要5品目の一角に位置付けていて、当面の関税維持を目指しての交渉にあたったが、豚肉は次のようになった。
(1) 豚肉は、差額関税制度が維持されるとともに、分岐点価格についても現行の1キログラム当たり524円が維持される。
従価税(現行4.3%)は、発効当初には2.2%となり、10年目以降は撤廃される。
従量税(現行1キログラム当たり482円)は、発効当初は同125円、10年目以降は同50円に引き下げられる。
ただし、輸入が急増した場合は、従量税を1キログラム当たり100〜70円に、従価税を4.0〜2.2%に、それぞれ戻すセーフガードが措置される(11年目まで)。
(2) 豚肉調製品(ソーセージなど差額関税でないもの)は、現行10〜20%の関税を、毎年、同じ割合で削減し6年目に撤廃される。
実質、関税撤廃に近い。10年という猶予期間は、政府が重要品目として位置付けていたことの体面を保ったが、国内生産者には激変緩和の一時しのぎにしか見えない。
豚肉は、牛肉の国産和牛のような差別品を作れないので、安い種類の豚肉の大幅下落が中上級肉の相場も引っ張る。さらに、輸入牛肉による価格低下・消費量増大の代替効果によって豚肉価格は引き下げられる。国産豚肉は大幅な価格低下の洗礼を受けるだろう。多くの中小規模の農家養豚は経営が成り立たなくなり、廃業に追い込まれよう。政府は重要5品目を中心に対応策を検討しているが、単に所得を補塡する政策ではなく、『競争力のある強い養豚経営』へ向けて支援し、そして何と言っても若い世代が夢を持って後継する養豚業に転換していかなければならない。
もちろん、当事者たる養豚生産者は発想を切り替えなければならない。いや応なしにTPP発効後の新しい経済環境を受け入れざるを得ないのであるから、旧態依然とした補助金頼みの考え方は捨てて、果敢に踏み出す経営戦略とそれを実現する具体策を構想し、その実現にこそ、国の政策事業を積極活用するという姿勢を持ってもらいたい。
今後の養豚経営には、このグローバルな時代を生き抜く覚悟を持って一歩を踏み出してもらいたいのであるが、その場合、経営展開の方向性を大所高所から見通すと2つの選択肢がある。
1つ目は生産性を高める“技術イノベーション”である。
2つ目は、経営内の活動に明白にバリュー・チェーンを組み立て、付加価値率を高めることである。こちらは“経営イノベーション”と呼ぼう。
1つ目の生産性向上は、優良品種の導入、技術改善・最新技術の導入、最新建物・施設・機械の導入による。品種改良は試験研究機関の成果を待つしかない。生産性の向上を図る飼養技術の改善は経営者の創意工夫によっても編み出されるが、現代の新技術の多くは畜舎・施設・機械の中に組み込まれてしまっている。従って、多額の資本投資をしなければならないが、資本投資には損益分岐点規模があり、現状以上の規模拡大を要求する。これが規模拡大によって生産性向上を図る技術イノベーションの構図になる。
2つ目の付加価値率の高いバリュー・チェーンの形成は、消費者の選好を把握して、競合する輸入豚肉に対して意識して差別化した商品を作るのが基本である。その場合、輸入豚肉には不可能な地場の地域と消費者を重視したい。消費者の嗜好
しかし、こうして価値が高まった生産物の付加価値を、より直接的に獲得するためには、養豚生産だけにとどまっているわけにはいかない。生産から加工・販売まで一貫した「B to C型」(生産者が消費者へ直販)の経済活動をするのである。行き着く経営形態は「生産・加工・販売の垂直複合経営」である。顧客に満足してもらえる「商品づくり」を生産から加工、販売工程に一貫させる。先の技術イノベーションの資本投資による飼養規模拡大には走らず、その代わり、加工・販売部門を創設することになる。そして、最後に販売によって実現するその経済成果−より高い付加価値−の全てを自らのものにする。
技術イノベーション(規模拡大⇒コストダウン)は旧来から主張されてきているが、あえてここに言う経営イノベーションにも注目したい根拠がある。農林水産省の肥育豚飼養規模別生産費を参照すると、確かに、規模拡大と共に費用低減しているが、大きな費用低減が労働費である。しかし、労働費は家族経営には大きな所得の源泉であり、その減少を意味していることを理解しておくべきである。一方、飼養規模別の主産物価額、すなわち出荷豚の販売単価を参照すると、300〜500頭規模で最大になっている。ここでその背景を考察する余裕はないが、この規模階層は販売頭数は多くないものの、相対的に高品質な肥育豚に仕上げ、有利な販売方法によって高付加価値販売ができているのである。つまり、ここに経営イノベーションが示唆されているのである。
イノベーションに次いで挙げておきたいのは、養豚経営に限らないが、長期的・持続的な経営発展の視点での次世代への円滑な経営移譲である。やっと発展軌道に乗った経営を永続的にその軌道上に維持する視点である。後継者のいない経営者1代の経験年数に対応させた経営体のライフ・サイクルは「参入期⇒成長期⇒成熟期⇒衰退期⇒廃業」で表される。必ず衰退期が来るのは、現経営者が一定の年齢を過ぎると、もはや将来への展望を描けず、更新期に至った機械・施設の更新投資すらできない、技術力・社会的信用力・経営判断力が低下するためである。これが第1の課題である。
重要な点は、衰退期に移る前に後継世代に経営移譲できることである。それには、言うまでもないが、経営者能力の素養を身に着けた後継者をきちんと育てておくことである。農業経営では、法人格の経営でもせいぜい雇用型の家族経営が多い。養豚経営も例外ではない。しかも、世襲慣習に従って子息に経営継承させるのを建前とする。まずは、身内に後継者確保である。
次に、後継者が確保されているとして、後継者が円滑に経営を引き継ぎ、そのまま「成熟期」のステージを維持できるよう、経営者としての素養を身に着けさせていることがポイントになる。継承者には自家の経営内、そして外部の公的機関、私的な組織・個人から、積極的に学習、実地研修をして欲しい。経営者への階梯は、時間をかけて一段ずつである。ジャンプはない。子息を後継者たる人材として経営内外で育てる過程は、いわば「農業経営者へのキャリア・パス」である。もっと力を込めて言うなら「主体形成過程」である。タイムリーな継承ができるように、後継者には経営内と経営外で実利ある充実したキャリア・パスを経てもらいたい。
本報告では、TPP発効後の市場環境に対応した養豚経営の展開戦略構築に、上に述べた経営イノベーション観点と経営継承者の育成という観点で大きなヒントを与えてくれそうな経営を紹介し、その取り組みを評価する。
2 (有)大野農場(代表取締役社長 大野賢司さん)の概況
グローバリゼーションの時代にふさわしい経営戦略を立て、その経営体制を整え、「強い養豚経営」を築いて欲しい。果敢な挑戦を期待する。その行動に向けて、1つの事例を示す。先に述べた経営イノベーションの典型的な形態である。埼玉県川越市で繁殖・肥育養豚と豚肉の加工・販売、そしてレストランまでの垂直複合一貫ビジネスをする(有)大野農場である。
都心から1時間の埼玉県川越市は、かつて江戸城の北方要所であった川越城を擁する城下町として栄えた歴史ある町で、「小江戸」と愛称されている。目抜き通りには蔵造りの建造物が建ち並び、江戸情緒を醸し、城下町の商人の活況をほうふつさせる。近年は、全国から観光客が訪ねて来る。そんな川越市のもう1つの顔は、平たんな地形で山地がないため、県下市町村別で最大の農地面積2600ヘクタールを擁する農業地域で、稲作と野菜の産地である。川越産野菜は「いるま野産」というブランド名で売り出されている。川越市の特産物はさつま芋である。「かわごえ芋」と称されるさつま芋は、かつては徳川家に献上してきた歴史を有する銘品である。
(有)大野農場は、そんな川越市の北東部の水田地帯に立地する。養豚業は先代が昭和30年頃に稲作の副業として子取り経営を始めた。社長の大野賢司さん(64歳)は昭和58年に経営を移譲された。養豚専業経営に切り替え、昭和60年には養豚一貫経営に転換した。そして、平成13年に資本金300万円で有限会社法人を設立した。現在の事業部門構成と社員体制は、表の通りである。
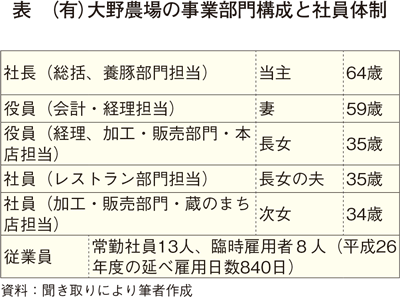 |
家族総出で役員と3部門を責任担当する家族経営法人である。3部門とは、繁殖肥育部門、加工・直販部門、直営レストラン部門であり、これによって養豚・豚肉垂直複合経営を実現している。
現在の繁殖母豚の飼養頭数は100頭、肥育豚の年間出荷頭数は黒豚900頭、白豚450頭の合計1350頭である。飼養規模は大規模とは言えない。しかし、もの静かな面持ち、隅々に思慮深さを漂わせる大野社長によると、養豚と豚肉加工、直売、レストラン部門の営業規模は、現要員体制で可能な最大規模であると言う。「各部門の責任者が目の届く範囲を適正な守備範囲と考えており、その経営方針を押し通した結果が現在の規模である」との弁である。経営形態も規模も、自らが考え抜き、確信を得て組み立ててきたと言う。今、目指していることをやっていけばTPPを乗り越えられると自信に満ちた返事である。
直近、複数年の経営収支を参照すると、売上高は増加させているが、社長(本人)を除く家族役員に役員報酬を払った後の営業利益は、若干の赤字である。飼養技術指標には問題なさそうであるが、白豚に比べて黒豚は繁殖効率、肥育効率が低く、収益確保が難しいが、このところの各種購入飼料単価の値上がりと、長引く景気の冷え込みによる消費の落ち込みが原因している。実は、本来ならば肥育頭数の全頭を黒豚にしたいところであるが、現在の冷え込んだ経済下では、背に腹替えられず、苦肉の策で白豚を肥育しているとの大野社長の説明である。
(有)大野農場のレイアウトと外観を紹介しておこう。(有)大野農場は市街地に続く住宅地帯に近接しているとはいえ、周囲は水田に囲まれている。農場敷地は、まず道路に面して自社製豚肉商品の直販店舗「ミオ・カザロ本店」がある。自社産豚肉を原料にした豚肉商品の加工場が店舗の後ろにある。その横と後方は広い間口の駐車場になっている。駐車場の奥がレストラン「小江戸黒豚鉄板懐石オオノ」である。平成25年の創業で、「豚肉を和食の主役に」という積年の社長の夢をここに実現した。レストランの裏は野菜畑である。無農薬栽培である。年中、収穫する作付け体系になっており、季節の新鮮野菜がレストランの厨房に持ち込まれる。
野菜畑のすぐ後方には水田が広がるが、レストランから約50メートル離れた右奥に飼料庫、配合作業場があり、その奥に7棟の豚舎から成る養豚場がある。3方を水田が取り囲んでいる。養豚場の不快臭や騒音が全くなく、整理も行き届いて整然としている。
理由は、第1に臭気抑制策として乳酸菌発酵飼料を調製、給与していること、第2に豚舎内外・周辺の清掃・整頓の徹底、そして第3に直売所、レストランは野菜畑と周囲の水田が消臭・消音の緩衝帯になっていることによる。なお、後述するが、(有)大野農場は埼玉県優良生産管理農場の認証を受けている。
川越市内中心部の観光客でにぎわう通りに「ミオ・カザロ 蔵のまち店」を出店している。
こちらは、1階は自家の豚肉製品を素材にした軽い調理品と飲み物などで、観光客向けのスタンド・ショップ、2階は自家産豚肉を素材とする大衆ランチ・レストランである。
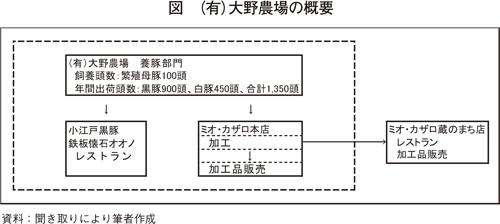 |
3 (有)大野農場の経営方針
経営方針は、第1に、消費者目線を大切にして風味、味覚、安全・安心を最重視していることにある。その観点から黒豚の飼養に到達した。さらに、試行錯誤による独自の飼料配合・給与技術で黒豚のうま味を引き出している。大野社長の、「誰にも負けないうまい豚肉を生産している」という自負心が伝わってくる。日常の飼養・繁殖・衛生面の管理と豚舎環境はデータとして記録しており、そのデータに基づいて判断し、作業を進めている。また、HACCPとトレーサビリティを実施して、安全・安心で、しかも透明性の高い経営を行っている。社長の言う「オンリーワン」、つまり「(有)大野農場にしかないもの」が作られている。この努力が、後段で紹介する「小江戸黒豚」ブランドの確立に結実した。
第2に、生産から加工・販売、飲食部門へと自社で養豚・豚肉ビジネスを完結させていることである。既存の販売チャネルで流通させていた当時は、品質差別的な豚肉に仕上げて出荷しても、品質差別販売されない無念さを身を持って体験してきた。だが、現在は、後述する「小江戸黒豚」なるブランド名で、自分で価格を付けて販売している。いわば、B to C型のビジネスであるが、経営者側が努力したことの全ての付加価値が自らの手に回収される。また、消費者の満足顔や頂いた言葉を経営者としての喜びややり甲斐として実感できる。
第3としては、大規模飼養は目指さないことである。豚舎環境の衛生・防疫、繁殖豚・肥育豚の健康状態をチェックしながら、事故なく飼育するには、隅々まで行き届いた観察、行き届いた作業を履行しなければならないという信念を貫いている。ブランドを守り通すため、地場に無理なく自家配飼料原料を調達できることも規模限界を規定している。今後も現状以上に飼養拡大する計画はないが、その代わり、加工・販売、レストラン部門を創設し、付加価値の高い経営にしている。飼養規模は大きくないが垂直複合化によって「ビジネス規模」は十分大きい。
4 (有)大野農場の事業内容
(1)養豚部門
イギリス系バークシャー種・純粋黒豚の一貫生産である。肥育月齢が白豚よりもやや長期、分娩頭数が少ない、哺育期の飼養が難しいという短所があるにもかかわらず、あえてバークシャー黒豚を飼養しているのはその味覚にある。肉質は軟らかく、脂肪の融点が低いので脂がうまくまろやかで、赤身にクセがない。そんな黒豚に川越市の特産さつま芋のくず芋、パンくず、大麦、牛乳などを主体にした自家配合飼料を給与している。この飼料によって、もともとの黒豚の上質な肉質に、さらにきめ細かく、軟らかさとうま味が引き出されて、独特のまろやかさと風味がのったものに仕上がっている。その味は誰にも真似のできない逸品と評されている。
そこで、(有)大野農場の黒豚は、川越市が昔から小江戸と称されていることにちなんで「小江戸黒豚」なるブランド名を商標登録し、(公社)小江戸川越観光協会(以下「川越観光協会」という)から川越ブランド産品の認定を得て販売している。今や、川越市民に慣れ親しまれたブランド名となっている。小売価格は一般の豚肉価格よりかなり高いが、味を知っている消費ファンは顧客になってくれている。白豚より生産コストは高いが、有利販売を実現している。
なお、自社の加工・直販部門とレストラン部門へ仕向ける黒豚頭数は週8頭のぺースで、年間にして約450頭である。従って、残る黒豚、白豚合わせて年間1千頭余りの肥育豚は「大野農場の小江戸黒豚・白豚」として馴染みの地元の卸売業者に販売している。自社内で黒豚の付加価値を確保する営業工程を取り込んでこそ、繁殖・肥育が劣勢にある黒豚を飼養する経済メリットが生まれてくるのであり、今後は、地場市場の拡大はもとより、ネット通販などによる自社販売圏域の拡大に向けての取り組みも考えている。
ブランド名の「小江戸黒豚」の根拠の1つが飼料原料を地場調達していることにあるが、飼料原料の農産残さも食品残さも安定的に収集できている。結果として、通常の肥育専用配合飼料への依存を低くしている。(有)大野農場の自家配原料の飼料化処理法や配合割合は、肥育効率と栄養成分量、嗜好性を確認しながら、可能な限り、地場調達の飼料原料を多用する観点からの試行錯誤を繰り返して確立してきた。なお、留意しなければならない給与技術は、季節と月齢による変化への適確な対応であると言う。
そして、抗生物質を一切投与しないこと、また加工部門で、増量剤や合成保存料を一切使っていないことを挙げておく。安全・安心はもちろんのこと、消費者に本物の味を味わってもらいたいという社長の思いからである。(有)大野農場は「彩の国畜産物生産ガイドライン」(HACCP)を採用し、トレーサビリティも採用して、安全・安心を貫く作業と管理を徹底していることから、埼玉県から「優良生産管理農場」の認証も受けている。
現在、繁殖・育成・肥育の工程は社長が管理責任者で、2人の常雇従業員が作業に従事している。管理と作業は管理台帳データに基づいている。事故率は低く、肥育効率も良好で、計画的に平準化した繁殖成績、肥育成績を達成している。これまで、深刻な疾病や事故に遭遇したこともない。社長は現場方針として、従業員に託せる作業と自分が判断し、責任をもって遂行しなければならない管理的業務とを明確に仕分けしていると言う。ただし、先に述べたが、日常管理に目が行き届く範囲を飼養規模限界としているのが大前提であるとも言う。
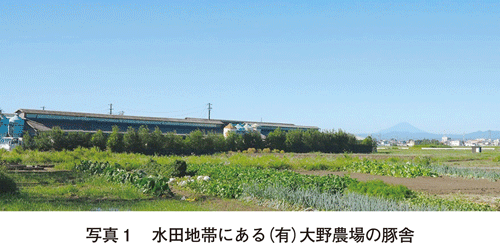 |
(2)加工・直販部門:直営ハム・ソーセージ工房、直売店・ミオ・カザロ(Mio Casalo)本店、ミオ・カザロ蔵のまち店
自分達の作った商品を自分達が納得できる価格で売りたい、企業努力に正当な報酬を受け取りたいという社長のかねての願望を実現するために起業したのがハム・ソーセージ工房と直売店のミオ・カザロ本店である。「ミオ・カザロ」とはイタリア語の「私の農家」と言う意味で、消費者に親しみを感じてもらう店になることを願って命名したとのことである。顧客は市内各地から緑の水田地帯をすり抜けて自家用車で来る。贈答シーズンには広々とした駐車場に車が溢れる。時にはツアー客のバスで立ち寄ってくれる。
(有)大野農場に加工部門を創設するに当たっては、肉加工の技術の習得のために、長女の大野恵子さんを(公社)全国食肉学校(以下「食肉学校」という)に進学させ、豚肉製品の加工・製造技術を習得させた。卒業後は、名古屋の本格ドイツ製法ハム・ソーセージ工房で修行を積んだ。固有の味、風味と舌触りの自家産小江戸黒豚を原料肉とした商品を取り揃えて開店したのは平成14年である。直営工房と売店は恵子さんが部門責任者として現場を仕切っている。
自家産黒豚から歴史あるドイツ製法とレシピに従いつつも、日本人の好みの味覚に合わせてアレンジしてハム、ベーコン、ソーセージ、生ハムなどを製造している。次々と製品開発し、現在、ハム類4種類、ソーセージ類16種類、ベーコン類5種類、他に生ハムやポークジャーキーなどを加えて20種類程度にまで増えた。(有)大野農場自慢の一商品を挙げるなら、小江戸黒豚特製生ハムである。黒豚に特有の脂の融点の低さによる難しさがあったが、それを克服して、安定した品質を維持できるようになった。生ハムの完成には紆余曲折あったが(次頁に説明)、今や当店自慢の特製生ハムで、地元ファンが多い。(有)大野農場こだわりの逸品ぞろいである。贈答用ギフト・セットや調理の用途に合わせたお取り寄せセットも販売している。
広く名前の知れ渡ったブランド名「小江戸黒豚」を売りにして、次のことを訴えている。商品の差別性を目いっぱい強調している。
(1) 自家生産豚であること
(2) 飼料の大半を地元で調達した飼料原料を給与し、「埼玉県優良生産管理農場」の認証を受けた安全・安心な飼養方法で飼養していること。
(3) 増量剤、着色料、合成保存料を一切使っていないこと。
(4) 本場の味を守った本格ドイツ製法で製造していること。
もちろん、精肉も販売している。
ミオ・カザロ・蔵のまち店は、市内観光スポットになっている蔵のまち通りの一角に店を開いている。こちらは全国からの観光客をターゲットにしている。感度の高い若い世代、全国各地からの客が立ち寄るのでアンテナショップとしての役割も担っている。今後、インターネット宅配事業も視野に入れており、店の評判や話題を故郷に持ち帰ってもらい、全国に知れ渡った店にしたいという夢を抱いている。
店をきりもりするのは次女の大野由美子さんである。1階は手土産向けのハム、ソーセージ類の販売、そして当店が開発したスナック的商品の焼きたての長いソーセージやホットドッグ・バーガー類に地ビールの“COEDO生ビール”などを販売している。2階は、自家産黒豚肉・加工品をふんだんに使ったランチ・メニューを用意したレストランである。気軽に入れる雰囲気で、自慢の小江戸黒豚の味は上々、旅行客の口コミが広がっているとのことである。
 |
 |
(3)直営レストラン部門:「小江戸黒豚鉄板懐石オオノ」
直営レストラン「小江戸黒豚鉄板懐石オオノ」は平成25年に開店した。和食レストランとして開店したのは2つの理由がある。
まず、養豚、豚肉加工・販売とレストランを同じ場所に立地させて、養豚・豚肉の複合施設地とし、そして自家産の小江戸黒豚を調理し、心のこもったもてなしで消費者に満足していただきたいという思いがある。そこまでを見届けないと養豚・豚肉一貫ビジネスが完結しないと考えていた。
第2に、豚肉が和食の食材としては殆ど使われていないのが現状であるが、(有)大野農場で仕上がった黒豚の甘い脂がのって風味よく、軟らかな食感は何とも品がよく、和食ジャンルに適合しているはずで、よって和食のジャンルに自家産の黒豚肉を中心に座らせた料理を開発し、黒豚肉を使った料理の幅を広げたかった。この思いを実現してくれる腕の立つ和食料理のシェフを見つけて開店した。
(有)大野農場の次代を担う予定の義理の息子(長女の夫)の大野
特徴は、豚肉による和食料理の専門店は極めて少ない中での黒豚肉を中心食材にした和食料理店であることである。
なお、開店当初は生ハムと熟成肉を提供する予定であったが、豚肉の熟成を手掛けてはみたものの、さしたる利点は見られず、また長期の熟成によるトリミングの必要性もあった。そのため現在では生ハムと通常の精肉類の提供としている。芳醇な香りとコクのある生ハムは、2〜3年の熟成期間を要するが社長自ら製造に当たっている。
今や、(有)大野農場の生ハムは小江戸川越黒豚の逸品の一品として市民からの定評を得ている。「決してあきらめず、家族であれこれ考えながら粘り強く試行錯誤してきたが、苦労が実った」、「これが、
都会の喧騒を忘れさせる周囲を緑に囲まれた田園で、静かに流れる時間を楽しみながら、コクのある黒豚に新鮮野菜を織り交ぜた鉄板懐石や鉄板膳の和食が堪能できる。黒豚肉の懐石料理は評判よく、市の広報誌での紹介や来客の口コミで、市内のお食事名所になっている。集客に向けて、随時、各種イベントを開催しているが、それが消費者との交流機会にもなっている。
5 後継人材育成
日本の農業経営は家族経営によって担われており、後継者は世襲制度の考え方に基づいており、子息が継承すべき考えはしっかり残っている。また、(有)大野農場のように、法人化しても家族主体の法人経営では世襲制度の経営継承を考えている。
今、日本の農業経営は後継者がいないという深刻な問題に直面している。家の相続者はいるが、農業経営を継承させるには、後継候補者たる子息に、動機とそれなりの定まった目的を内包した自意識が形成されてなければならない。それがない者に経営継承を強制することはできない。子供の頃からの興味、関心を持たせ、それがやがて意欲や自信に、そして後継者としての責任感へと変遷していくのが理想であるが、実際には、そういう育ち方をしてない場合が多い。もちろん、農業という産業が他産業に比べて色あせて映っている現実があるが、今の親たちが、経営を見せて、あるいは会話を通して、夢開く将来への可能性を自家の農業経営から見せてない、そして勇気を与えてなかったではないか。むしろ、子息達を農外への就業に導いてきた。
そうした反省に立つとき、(有)大野農場がやってきた後継人材の育成はうらやましい。(有)大野農場は、まだ、法的な経営継承はしてない。しかし、次代を担う人材はそろっている。大野家は2人の娘を育てた。実は、2人とも、子供時代には、家業の養豚経営に関心がなかったわけではないが、女性が家業の養豚経営の担い手になれるとは思ってなかったと言う。
恵子さんの経歴はドラマチックである。“家庭を持つまでのOL”と考えていた恵子さんは、短大卒業後、希望していた通りOLとして会社勤務をしていた。勤めて2年経ち、仕事にも慣れた頃、父親の大野社長から、突然、相談を受けた。「自社の豚肉を加工、製品化して販売したいのだが、ついては会社を退職して豚肉ハム・ソーセージなどの加工専門学校に行き、その技術を身に着けてきてもらえないか、その後は、自社で豚肉加工・販売部門を担当して欲しい」という全く想定外の相談であった。
大変戸惑ったが、父の発展思考と情熱に心を打たれた。結局、退職して食肉学校への入学を決心した。しかし、それでも、将来、自分が(有)大野農場の経営者の一員になる自覚は持てなかった。とりあえず、長期間、農場を離れられない父に代わって、加工・製造の技術を身に着けて帰り、それを父に伝達するのが自分の役割だと考えての決断だった。
しかし、入学後の学習・実習では、商品の種類ごとに、材料となる豚肉の品種や部位で味、風味、舌触りなどの出し方にデリケートな技がものをいうことを知った。また、食肉学校には、さまざまな目的や夢を持ち、人生設計を持って真剣に勉強する特有の雰囲気があり、同期生からも大いに刺激を受けた。眠っていた本気心が起き上がった。今後、主婦となって平凡に過ごす人生ではなく、これからの人生を、日本一の名人を目指してハム・ソーセージ作りにかけてみようという夢を抱いて家業に参画する決断をした。人生を託せるやりがいのある仕事だと自覚した。
食肉学校を卒業した後、研修生として各地の手作り店で修行を重ねたが、名古屋のドイツ製法の店のハム・ソーセージが自分が目指すハム・ソーセージであると見定めて、その店で腕を磨いた。自信をつけて(有)大野農場に帰ってきたのは平成14年、ミオ・カザロを開店した。今は父の片腕となり、加工・販売部門を任され、役割を果たせていることに充実した人生を感じていると言う。
以上が長女が経営に参画するまでのキャリアであるが、経営継承者の確保に向けての父親の行動は遅過ぎた印象ではあるが、育ってきた環境の中で、両親の経営への姿勢を知っており、目指している経営目標が伝わってきており、後継者として未来を託し、人生に夢を描いて、(有)大野農場の経営の一翼を担うことに進んで取り組める自覚を持てたのである。振り返ると、人生の転機はやや遅かったが、しかしその気になれば何時からでも再スタートできる、「遅い」はないと思うと言う。
次女も姉に見習って(有)大野農場で働き始めた。平成18年に2号店の「ミオ・カザロ蔵のまち店」を出店したのを機に、蔵のまち店の責任者として従事している。日々、メニューの開発改良、職員の調理技術、接客の指導に充実感一杯である。市内商工会でも活躍している。大きな責任を分担しているが、姉の活力みなぎった仕事ぶりを見てきているので、自分も同様に家業に関わり、責任を分担して仕事するのは当たり前と考えていると言う。
恵子さんの夫の大野丈往さんは、結婚前はサラリーマンで、販売関係の仕事に就いていたが、(有)大野農場で夫婦一緒に働くことにした。とは言っても農場の仕事は全くの素人であるから、農場を支える最重要な現場である養豚部門に社員と共に従事した。義父の社長の直接の手ほどきを得ながら、そして社長の経営姿勢から、技術と経営を体験的に学んだ。また、もの言わぬ家畜を相手に1日も休むことなく飼養する畜産経営の工業や商業との違い、その収益を生み出す難しさも体感した。農業経営の苦労を体全体に染み込ませた。その経験を経て、平成25年に開店した「小江戸黒豚鉄板懐石オオノ」の店長として責任を任された。現在は、川越市青年会議所の会員として、異業種との交流、そして人脈形成しながら、社会的研さんも積んでいる。給料取りのサラリーマン時代にはなかった責任感、緊迫感をレストランの営業成績につながる創意工夫へのエネルギーに置き換えて、充実した日々を送っている。
結局、2代の家族全員が(有)大野農場の経営に、責任を分担して従事している。その限りでは法人経営とは言っても家族経営である。そして、大野社長は、今は、何時でも経営移譲できる体制にある。後継世代が円滑に経営を継承してくれる体制になっていればこそ、30年、50年の長期の経営展望を持って経営計画を立て、資本投資ができた。夢を実現した。「持続的発展」とは、まさにこれである。
従来の農業経営は、自己の経営の長期の見通しを持てないまま、ただ“バスに乗り遅れまい”、“隣近所と同じことをやっておけば安心”の発想で経営投資してきた。やがて、高齢化と後継者不在で行き詰まった。これからの農業経営にはビジネス意識を明確に持つ担い手後継者を育成する主体形成過程を持つことが不可欠であると認識してもらいたい。それをもって、長期の将来を展望した資本投資も新技術の導入もありうる。持続的な経営発展である。家族が結集して経営にあたっている(有)大野農場がその理想モデルを示してくれている。
6 結び
TPP交渉が大筋合意し、本格的なグローバル競争時代を迎えることが明白になった今や、国内農業は「競争力強化」策を急がねばならない。関税が大幅削減されることになった養豚もしかりである。そうした背景にあって、本稿は、今後の養豚経営の1つのビジネス・モデルと見なしうる埼玉県川越市の養豚経営・(有)大野農場を紹介した。
(有)大野農場の経営の特質を挙げれば次のように集約される。
(1) 生産部門(養豚)は個体に目配りが行き届く範囲の頭数規模にする。そのかわり、生産・加工・販売・レストランの養豚・豚肉一貫ビジネスの経営形態(垂直複合化)にする。
(2) B to C型一貫経営の全工程で黒豚品種の長所を生かし、付加価値最大化を目指す。また、その方法として地場に飼料原料を調達し、地場に市場を開拓した。つまり地場に根付いた商品に育て上げ、地場の消費者を囲い込むという地産地消型のビジネスとした。
その1手法として、「小江戸黒豚」なるブランド名を川越市ブランド産品として川越観光協会の認定を得て、地元市民への周知・愛着を図ることができた。
ここに、1つのビジネス・モデルが出来上がる。膨大な資本投資で飼養規模を拡大するのではなく、何か“
(有)大野農場の“拘り技術”は少なくとも3つあった。列挙すると、
(1) 味を最優先して黒豚を飼養。しかも、地場産飼料原料を最大限に利用して、黒豚のうま味を一層引き出している
(2) 豚肉加工製品は、最もおいしいと確信するドイツ製法で製造。種類は20種類程度
(3) 豚肉の本格的な和食鉄板レストランの直営
である。大野社長は言う“ナンバーワンを言う前に、まず、オンリーワンを”と。
垂直的複合形態の養豚・豚肉一貫経営を構築した背景を大野社長は次のように説明する。生産者は生産だけでなく、市場で品質差別化して付加価値を獲得するところまで見渡さなければならない。しかし、一方でそれを正当に回収するためには、自らが川下事業に参入し、自らが決めた価格で販売すべきと言う。社長は「自信をもって消費者に勧められるわが農場の小江戸黒豚である。市民にこの味をしっかり覚えていただきたい。」と言う。
大野社長は、まだまだ自分の描く経営に到達してないが、次代を担う世代が、将来への課題を共有してくれている、まだ、経営発展の伸びシロはあると言う。それは、1)ネット通販などの販売チャネルの開拓に取り組み、肥育豚の自社内仕向け率をできる限り高めたい、2)観光都市・川越市の特性を生かして、観光型事業を取り込み、地元客、観光客との顧客交流をしたい、と言う。目線は常に消費者である、そして地域社会に接点をもっておかなければならないとも。
しかし、こうした(有)大野農場の経営戦略は担い手人材育成、技術開発・技術習得と表裏一体である。(有)大野農場は当家2世代の家族全員が名実共に経営陣として従事している。管理体制は部門責任分担制とし、養豚部門、追加事業の加工・直販部門とレストラン部門のそれぞれに、身内の者が部門責任者として配置されている。それぞれに、担当分野の技術・知識を習得させつつも、同時に経営者としての自覚、経営者としての資質を高める努力もさせる。円滑な世代交代ができてこそ「持続的な農業経営」である。それによって経営発展を指向した長期視点での経営展開が可能になる。大野社長の後継人材育成の手腕も高く評価したい。