【要約】
きたやま南山は、3種の赤身和牛肉を核として京都市内で焼肉店を経営し、消費者を会員とする「食農倶楽部」や、生産者との交流会や料理教室などのほか、医師や栄養士と連携した健康セミナーにも新たに取り組むなど、食と農のコミュニケーションを通じた赤身和牛肉の魅力の普及・浸透に尽力している。生産者、消費者、医学と連携した同社のユニークな取り組みは、国産牛肉の需要拡大の可能性を広げるものである。
1 はじめに
近年の物流は、著しい発達を遂げ、注文すれば、日本国内はもとより、海外からも適確に商品が届く。また、商品が届くまでの途中経過も、インターネットでの把握が可能であり、商品を受け取った後に何かしらの不都合が生じた場合でも、トレーサビリティにより安全性が精度の高いレベルで確保されている。その一方で、昨今の食品流通において、物流の進化から漏れ落ちてしまったものがある。それは、流通過程の各段階において取り交わされていた商品に関する情報の交換である。従来、「生産者→卸売→小売・レストラン→消費者」あるいは、逆に「消費者→レストラン・小売→卸売→生産者」へと行き交っていたさまざまな情報が、伝わりにくくなってきている。以前であれば、取引上、それぞれが相手を意識しながら、生産や販売がなされ、我々消費者はその食品を身近に感じながら、安心感を持って食することができた。しかし現在では、物流の合理化、効率化の名のもと、相互のコミュニケーションが減り、情報が散在している。例えば、食肉や牛乳・乳製品において、消費者は生産の実態を知らない場合が数多く見受けられる。消費者の大半は、牛は大草原で、ゆったりと放牧され、のんびりと飼われていると想像するが、現実はそうではない。もちろん農家は安全性に配慮しているものの、経営の合理化や効率化、また流通システムの都合などを考慮せざるを得ない状況もあり、大草原でゆったりと飼養するわけにはいかないのが実情である。
本稿では、食品流通における関係者間のコミュニケーションの欠落が危惧される中、赤身和牛肉の振興に向け、独自にユニークな取り組みを進めている㈱きたやま南山(以下「きたやま南山」という。)を率いる同社代表取締役の
2 きたやま南山の歴史と経営理念
きたやま南山は1971年、楠本氏の父が大分県中津市で創業した「レストラン南山」をルーツに持ち、現在は、京都市左京区北山通で営業している(写真2)。楠本氏は1974年、大分県をはじめ九州北部や京都などに展開していた同社に就職し、子育てのため1994年に
 |
|
写真1 きたやま南山代表取締役の楠本貞愛氏
|
 |
|
写真2 きたやま南山の本館は、ダムに沈む運命にあった
築200年の農家を1971年11月に移築したもの。 改修はされているものの、依然、何とも言えない 重厚な風格を漂わせている。 |
楠本氏は、きたやま南山の経営にあたり、「南山5つの約束」として以下の経営理念を宣言している。
(1) 私たちは、「食」と「農」、「人」と「人」の笑顔をつなぐレストランを目指す。
(2) 私たちは、生産者さんと共に「安心安全な食」をお客様に届ける。
(3) 私たちは、環境にやさしい循環型の農畜産業を応援し、豊かな食文化を支える。
(4) 私たちは、牛から分けてもらった愛と命に共感できる食育の場を目指す。
(5) 私たちは、お客様に元気をお届けするレストランとして人と夢を育てる。
この約束を守るために楠本氏は、顧客とのコミュニケーションツールとして、「食農倶楽部」という会員制の組織を運営するとともに、生産者との交流や産地ツアー、料理教室、食と健康に関するセミナーの開催など、さまざまな取り組みに挑戦している。
3 きたやま南山の活動
(1)いただきます・ありがとう協働隊
楠本氏は、地域活動の一環として、2014年度より、新たに農林水産省のフードチェーン食育活動推進事業に参画している。この事業は 「消費者に健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への理解を深めるための体験活動などの食育活動を、フードチェーンを通じて一体的に行う取組」を支援している。言い換えると、「食と農の魅力を伝え、人と地域を育てる食育事業」である。楠本氏は、この事業を通して国産農畜産物の需要を促進し、「未来の食と農の担い手である若者の仲間意識を育て、自炊力・自立力・生活技術を育てる」ことを目指している。「命あるものを食すことの尊さと、健康な心身を作るための食べ方」を普及するため、「いただきます・ありがとう協働隊」という愛称の下、畜産と農業による生産・流通・加工・調理までをトータルに学ぶ体験実習を各地で展開している。
また、楠本氏は、「いただきます・ありがとう協働隊」事業の一環で、医農食をつなげるイベントを頻繁に開催している。2014年10月24日には、畜産システム研究会(注1)との共催で、「牛と共に生きる元気で愉快な農業者が語る夢」と題したシンポジウムを開催し、土地利用型で大家畜畜産に取り組む農家ほか計4組が、特色のある肉牛生産や酪農経営の状況などについて発表した。
注1: わが国の畜産の持続的発展のため、生産と研究の関係性を重視し、地域における畜産関係 者の連帯を深め、環境、資源および市場の有限性に対処し、食の安全性を重視した生産シ ステムの構築に関する研究および情報交流を推進していくことを目的とした組織。
京都大学大学院に事務局が置かれている。
そのうちの1組に、楠本氏が最も力を入れている、次世代の若者における食育活動を実践している愛農学園農業高等学校(三重県伊賀市。以下「愛農高校」という。)による、「牛肉プロジェクト」の講演があった。同プロジェクトは、2014年に楠本氏らと連携して立ち上げた生徒主体の企画で、廃用が決まった同校の乳牛「アッスー」を、生徒自らが枝肉の解体から整形まで手掛け、さまざまな牛肉料理にして食するという取り組みであった。このプロジェクトをきっかけに、きたやま南山の支援のもと開発された「高校生が育てた牛1頭まるごといただキーマカレー」は、2014年8月、滋賀県大津市で牛肉料理のさらなる普及・浸透を目的に開催された「牛肉サミット2014」において準優勝を収めるなどの成果を収めている。シンポジウムでは、このプロジェクトに参加した農業後継者の生徒たちから、牛の飼養、枝肉解体、調理および販売などを通じて得た充実感や感動のこもったエピソードなどが発表された(写真3)。
 |
|
写真3 シンポジウムで牛肉プロジェクトの概要を発表する
愛農高校の生徒 |
(2)京都 社会的共同親プロジェクト
楠本氏の思いは、単なる食育にとどまらず、次の時代を見据え、2つのタイプの若者たちにも焦点を当てている。1つは、「裕福に育ち親に甘え気味で、目標を持てない若い世代」。もう1つは、「種々の事情から親と離れて暮さなければならなくなり、希望を失いつつある子供たち」である。楠本氏は彼らに対し、「胃袋の体験を通した」食農教育と種々のスキルを身に付ける気持ちを持たせることで、将来、日本の食を担う仕事に就いてもらいたいと考えている。特に後者の、肉親と離れて生活してる子供たちに対しては、2013年より京都府立大学の地域貢献事業(ACTR:Academic Contribution To Region事業)として、同大の公共政策学部津崎哲雄研究室と共同で、京都社会的共同親プロジェクト「みんなで拓こう子供の未来」に取り組んでいる。現在、家庭内の虐待やその他の事情で、施設や里親家庭に行かなくてならなくなった子供たちの中には、無職やホームレス、生活保護のほか、刑事施設や精神病院の利用などの経験を持ち、社会的自立が難しい状況にある者も少なくない。楠本氏は、このような若者たちに対する食育を通じた支援により、「命あるものを食すことの尊さと、健康な心身を作るための食べ方」を基盤に、次世代の食と農を担う優良な人材が育ってほしいという熱い思いを持っている。
(3)糖質オフへの取り組み
楠本氏は、健康志向に配慮した赤身和牛肉の振興を、後述する生産システムの面からだけでなく医学的な面からも図っている。カロリー摂取とその消費のバランスが崩れ、メタボリック症候群の増加が危惧される中、楠本氏は、赤身和牛肉と組み合わせた糖質オフダイエットを推奨している。
牛肉の赤身には、脂肪燃焼作用のあるLカルニチンが豊富で、糖質がほとんど含まれていない上、消化のためのエネルギー消費で代謝がアップするので、減量効果がすぐに表れる。ただし、糖質を一緒に摂取すると、脂肪は燃焼せずに取りすぎた糖質が脂肪になるので減量効果が期待できないというものである。楠本氏は、この理論をもとに2011年1月に参加者15名を募り、1週間毎日きたやま南山の焼肉を食べ続ける焼肉ダイエットの実証試験を実施した。その結果10名が減量に成功し、最高は、80歳代の女性が1週間で5キログラム減量したということであった。もちろん実証試験は、医師や栄養士の監修のもとで行われており、安全性に配慮されたものである。筆者も1日だけ参加したが、糖質の代わりに牛肉を食することで、空腹感をあまり感じることはなく、継続的に取り組めると実感した。
糖質オフダイエットは世界でも広まっているダイエット法である。近年では、感情をコントロールする基礎メカニズムにおいて、神経伝達物質の種類や濃度とそのバランスをコントロールしているのは、セロトニンなどのたんぱく質であることがわかっている。セロトニン生成の材料になるのはトリプトファンであり、トリプトファンは畜肉に多く含まれている。 このような意味からも、赤身肉からタンパク質を摂取することはダイエット上意味があると言える。また、できるだけ薬剤を使わない、あるいは薬剤を低減する糖尿病患者の新しい食事療法としても注目されており、きたやま南山の実証試験は、理論から実践への架け橋として、有用な試験であったと評価される。なお、この実証試験結果を含めて、心と体が丈夫になる食べ方や、太らない食べ方、お肉の豆知識など生活に役立つ情報は、「肉菜健美な糖質オフのすすめ」として冊子に取りまとめ、きたやま南山のHPで公開されている(http://www.nanzan-net.com/common/file/nikusaikenbi.pdf)。
4 きたやま南山で扱う3種の赤身和牛肉
このように楠本氏は、赤身和牛肉の魅力を伝えるべくさまざまな活動に取り組んでいるが、自社で取り扱う牛肉にもこだわって仕入れている。きたやま南山では、できるだけ輸入飼料に頼らず、放牧や自給飼料、エコフィードを利用する農家を指定して、いわて短角和牛(日本短角種)、近江牛(黒毛和種)と京たんくろ和牛(和牛間交雑種)の3品種の和牛肉を1頭丸ごと調達している(写真4)。
 |
|
写真4 きたやま南山の3種の赤身和牛肉(左上:近江牛、
右上:いわて短角和牛、下:京たんくろ和牛) |
(1)いわて短角和牛
いわて短角和牛は、ひきしまった赤身のうまみが特長の日本短角種である。きたやま南山は、自然交配で生まれ、母子放牧で育った、国産粗飼料多給の和牛として「いわて短角和牛」を応援している。二戸や岩泉産のものを使用しており、各地で肥育方法は異なるが、それぞれの地域で飼料自給率を高め、エコフィードにも取り組んでいるのが共通点である。東日本大震災後、楠本氏は放射能汚染などの検査も行い、安全性を確認しながら、いわて短角和牛の取り扱いを続けており、岩手県の畜産復興を力強く応援している。
(2)近江牛
近江牛は、きめの細かい柔らかさと脂の甘さが特長の黒毛和種である。きたやま南山は、国産飼料100%の肥育に挑戦している滋賀県の木下牧場から調達している。同牧場は、繁殖から肥育までの一貫経営で、繁殖牛約70頭、育成と肥育を合わせて約160頭で合計230頭を飼養し、生後から出荷まで、輸入飼料を用いずに自家産の飼料を給与することを目指している。2002年には、自給飼料による健全な家畜生産をテーマに、肉牛飼育農家有志で「近江牛粗飼料生産組合」を設立した。また、滋賀県ブランド米「近江米」の生産に牛ふん堆肥を使用し、化学肥料の低減にも貢献している。これらの取り組みが、近江牛精肉店であるサカエヤの新保吉伸氏に注目され、同氏による生産者ブランド商品の販売は、マスコミにも多く取り上げられている。この一環で展開された同氏のプロデュースによる木下牧場との共創事業は、4年前のフード・アクション・ニッポンアワード2010(注2)で、プロダクト部門優秀賞を受賞した。楠本氏もシンポジウムなどにおいて木下牧場を取り上げ、国産飼料100%の生産を推奨している。
注2: 国産農産物などの消費拡大に寄与する事業者・団体などの取り組みを一般 から広く募集 し、優れた取り組みを表彰するもの。フード・アクション・ニッポンの取り組みの1つで、 国産農産物の消費拡大に向けた活動を推進し、我々や未来の子供たちが安心しておいしく食 べていける社会の実現を目指す。
(3)京たんくろ和牛
京たんくろ和牛は、きたやま南山が命名したオリジナルブランド牛であるが、このユニークな牛について、少し詳細に紹介したい。京たんくろ和牛は、黒毛和種を父に、日本短角種を母に持つ、最近では珍しい和牛間交雑種である(写真5)。日本短角種の「たん」と黒毛和牛の「くろ」を合わせて「たんくろ」と名付けられた。京たんくろ和牛の名称には、異なる和牛どうしの交配による新しいタイプの和牛の普及を、可能な限り地元京都の地域特性を活かして生産、普及したいという思いが込められている。なお、和牛間交雑種はもちろん立派な「和牛」である。写真5のとおり黒毛であるが、顔つきは日本短角種の面影を残し、28カ月齢肥育で仕上がり体重は800キログラム程度である。
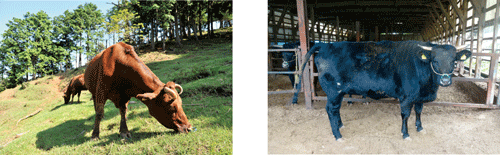 |
|
写真5 日本海牧場で放牧される日本短角種繁殖牛(写真左)と京たんくろ和牛
(日本短角種写真は、きたやま南山ホームページより) |
京たんくろ和牛について、きたやま南山の連携先で京都府京丹後市にある農事組合法人日本海牧場(以下「日本海牧場」という。)代表の山﨑高雄氏と飼養担当の前田隆氏を訪問した(写真6)。京丹後市は、京都府の最北部に位置する人口約5万9千人の町で、日本海牧場はその名前の通り、日本海を望む山地に放牧地を持つ。
 |
|
写真6 日本海牧場の牧場長の山﨑氏(写真左)と
牛飼養担当の前田氏 |
調査時点(平成26年11月3日)では、日本海牧場では、母牛(繁殖牛)として日本短角種を43頭飼養している。受胎率は年間7~8割程度であり、京たんくろ和牛を年間約30頭出荷しているということであった。日本海牧場では、当初、きたやま南山との連携を進めるに当たり、肉牛生産に精通している有限会社シェパード中央家畜診療所の松本大策獣医師の指導を受けて、「京とうふ藤野」の乾燥おからをエコフィードに利用し、食味の向上を図ったことで、京たんくろ和牛は消費者から高い評価を受けたということであった。その後、飼料用米と共に、京豆腐の「京都庵」や兵庫県たつの市の「ヒガシマル醤油」から出される副産物を飼料原材として使用し、京都大学の熊谷元准教授のアドバイスにより乳酸発酵技術なども取り入れて、独自の飼料レシピも作成するなどして、京たんくろ和牛への給与飼料におけるエコフィードの割合を4割にまで高めている。
また、山﨑氏は、京たんくろ和牛の安全・安心な牛肉としての信頼確保を目指し、2007年10月にJAS認定を受け、この認定をきっかけに楠本氏に販売を依頼することとした。これを受けて、楠本氏は日本海牧場産の和牛間交雑種の牛肉を「京たんくろ和牛」と名付けて試験販売を開始し、2009年2月23日、きたやま南山は日本海牧場とともに農商工連携事業の認証を受け、安全・安心な牛肉としての理解を得るためのブランド確立と販売拡大を目指す連携事業をスタートさせている。農商工連携事業とは、農林水産省と経済産業省が地域経済活性化のため、地域の基幹産業である農林水産業と商業工業などとの連携を強化し、相乗効果を発揮していくことを目的としており、両氏は同事業において、次の取り組みを目標に掲げている。
(1) 新商品の売上向上
(2) 京丹後地方の旅館・飲食店での地元産牛肉料理による集客
(3) 京都市と京丹後市における食育+食農観光交流の活性化
(4) 京豆腐のおからなど食品残さを活用したエコフィードの推進
(5) 飼料用米や牧草などの生産による京丹後市の農業の活性化
(6) 新規雇用の創出
昨今の消費者の健康志向の高まりを受け、霜降り肉から赤身肉への牛肉人気のシフトが見られる中、粗飼料や食品残さを活用して環境への配慮と経済性を追求した美味しい牛肉を生産し、地域限定で販売を進めることにより、大消費地京都で支持されるブランド牛として、競争力を高めたいというのが両氏共通の思いであった。
日本海牧場の京たんくろ和牛の肉質の格付けは、2等級から3等級であるが、種々の試食会で高い評価を得ており、引き合いが多くなっているという。京たんくろ和牛は、きたやま南山のほか、京丹後市の料理旅館や、舞鶴市と宮津市のレストランでも販売されている。さらに、2014年6月には、イスラム系外国人観光客の増加を踏まえ、きたやま南山は、京たんくろ和牛のハラール向けのと畜を開始し、京都ハラール評議会から「ハラール和牛」の認証を受け、10月1日より京たんくろ和牛を使った「ムスリムフレンドリーメニュー」を提供するなど、より一層の消費拡大を目指し、先進的な取り組みを進めている。
日本海牧場における京たんくろ和牛の生産は、赤身のおいしい日本短角種と、脂肪交雑度の高い黒毛和種を交配させることで、両方の特長を兼ね備えた牛肉が生産できるのではないか、という山﨑氏の発想が原点となっている。
山﨑氏が、このように京たんくろ和牛を飼養するに至るまでには物語がある。もともと山﨑氏の本業は建設業であるが、所有する山の活用法を模索していた山﨑氏の父・欣一氏が、日本の食肉消費の増加を見越して、牛好きが高じて牛飼養を趣味的に始めたのが牧場経営の発端である。開設当初は、放牧したホルスタイン種や黒毛和種が、疾病(ピロプラズマ病)にことごとくやられるなど試行錯誤が続いた。そのような中で山﨑氏は、ヒマラヤ技術協力会(現在のNPOヒマラヤ保全協会)の一員としてネパールに渡航した際に知り合った、岩手県岩泉町で肉牛生産に従事する青年を欣一氏とともに訪問した。その際、山で放牧され、のびのび育つ日本短角種を見る機会を得た欣一氏の、「日本も将来的には牛肉の消費がますます拡大し、霜降り肉よりも健康的な赤身肉の需要が伸びるだろう」という言葉を聞いた山崎氏はその時、日本短角種の導入を決意したのである。山崎氏が本格的に家業を継いだ頃、日本でBSEが発生したため、かねてから構想を温めてきた日本短角種と黒毛和種を交配した和牛間交雑種「京たんくろ和牛」に切り替えて牧場経営を続けることとした。
日本海牧場の社訓は、「一円融合」という二宮尊徳が提唱した報得思想である。これは「万物は一つの円の中で、互いに働き合い一体となることで、初めて成果が現れる」というもので、山﨑氏は高校球児でもあったこともあって、チームワークを重んじ、多角的な視線で経営している。牛肉生産とそのフードチェーンにもこの「一円融合」の哲学が注ぎ込まれている。
5 おわりに
これまで、きたやま南山の楠本氏による生産者と消費者をつなぐ取り組みを述べてきたが、その内容は極めて多彩であり、本稿だけでまとめきれるものではない。また、それを支えるネットワークは、生産者、流通関係者、消費者、医師、管理栄養士、社会学者および畜産研究者など多岐にわたるが、実はそのネットワークを維持する仕掛けとして、イベント後の懇親会があった。これは、食農や医農をつなぐイベントの終了後に、楠本氏が牛肉を囲んだ懇親会を開催し、講演者と参加者がともに赤身和牛を食べながら、語り合うというものである。このような、関係者における活発な議論が熟成し、さまざまな立場から本音が飛び交う場が増えていくことで、日本の食料生産、また食料循環とその産業は、良い形で発展していくように感じている。牛の飼養から始まり、最終的にその生産物を食するという若い世代に向けた議論は「我々が真に行うべき食料循環」を考えさせる必要な取り組みである。今後は、机上の食育ではなく、このような取り組みを行う若い人材の育成が最も重要であると考える。
今回紹介した事例は、あくまで一企業の取組みにすぎない。しかし、高齢化や担い手不足など、日本の肉牛・牛肉産業が直面する課題を解決する糸口を提示していると考える。このような「ユニークな挑戦」に、心強さを感じるとともに、今後の国産牛肉の需要拡大に期待が高まるものである。