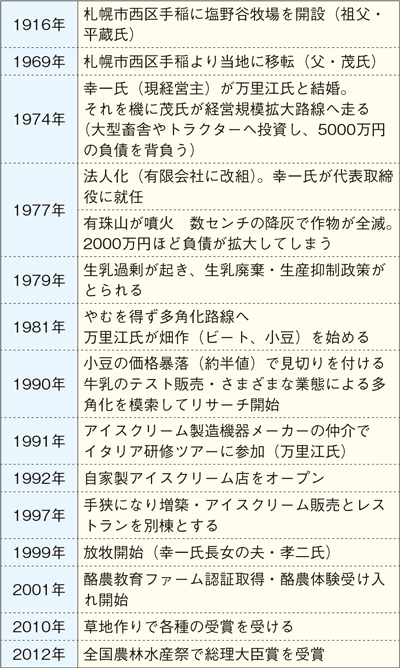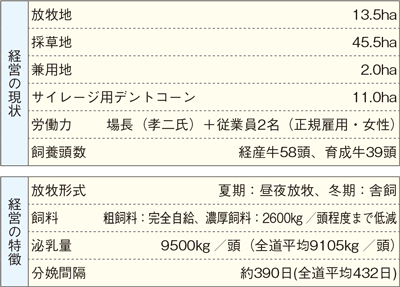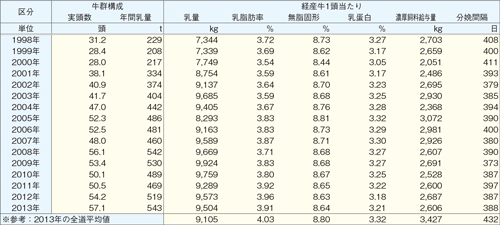【要約】“六次産業化”や“放牧・高泌乳酪農”の魁(さきがけ)として高名な“(有)レークヒル牧場”であるが、その歴史は苦労の連続であった。経営主の妻・万里江氏の“肝っ玉母さん”魂によって開かれた六次産業化と経営主の長女の夫・孝二氏が始めた放牧・高泌乳酪農は、周囲の人と生きる牛との“信頼”関係を築くことによって、各種の賞を冠されるほどとなり、我々に「汲み尽くせない学びの場」を提供してくれる。 1 はじめに JR洞爺駅から国道230号線を札幌方面に向かって車で20分ほど。前方を有珠山系の美しい山並みに囲まれた丘の上に(有)レークヒル牧場(以下「レークヒル」という。)は
“能ある鷹は爪を隠す”とは良く言ったものである。こうした静かなたたずまいこそが人々を引きつけ、何とも言われぬ感動を与え、リピーターを増やし、そして優れた“口コミ力”を発揮させているのかも知れない。 2 規模拡大に大ブレーキをかけた有珠山噴火と生乳過剰レークヒルは1977年、北海道南部の洞爺湖町に産声を上げた。塩野谷一家の個人牧場を有限会社に改組しての誕生であった。今でこそ法人化などと聞いても何も珍しくないが、40年弱も前のことである。当時としては、また当地としては、極めて先駆的だったと言って良い。この先駆性は何も今に始まったことではない。塩野谷一族の歩みを聞くにつけ、先駆性や開拓者精神などは、塩野谷一族のDNAにもともと組み込まれていたものではないか、と思えてくるのである(表1)。
塩野谷牧場は元々“洞爺”産ではない。1969年、札幌市手稲から移転してきたのである。手稲の牧場は1916年、レークヒルの現社長・塩野谷幸一氏の祖父・平蔵氏が開設したことに始まる。今では平蔵氏と言っても知る人も少なくなったが、彼こそ“牛の大家”と呼ばれ、純粋種ホルスタインの普及に尽力した人である。また、酪農の指導・普及に努めるとともにサツラク農業協同組合(本所:札幌市)の結成にも携わり、北海道酪農の礎を築いた“一大功労者”“大恩人”である。日本に導入されたばかりの新しい農業形態である酪農、この酪農発展の将来に確信を持ち、幾多の困難を乗り越え この手稲の牧場が1960年代、父・茂氏の代に大きな転機を迎える。札幌市と小樽市を結ぶ札樽高速道のインターチェンジ建設予定地とされ、立ち退きを求められたのである。いろいろと思案のあげくに出した答えは、酪農の継続と当地移転であった。「親戚筋(塩野谷家の本家)が近隣でクルミ園を営んでいたことが当地移転の切っ掛けとなった」と幸一氏は言う。1969年、発足の地手稲から舗装されたばかりの中山峠を牛40頭などとともに越え、移り住んできた。時に、幸一氏の酪農学園大学卒業の年であった。 幸一氏は1974年、後に“六次産業化”の 息子・幸一氏の結婚を機に先代の茂氏 (当時の経営主)は規模拡大路線へと舵を切る。生乳増産と規模拡大が政策的に強力に推進される中では当然すぎる選択であった。年利3.5%の資金を5000万円ほど投じて、100頭規模への畜舎拡張やトラクターの新規導入などを行った。今でこそ100頭規模などと聞いても何ら驚くに足りないが、当時は“平均30頭”そこそこの規模の時代である。魁的とも言える投資であるが、当時としては決して無謀なものではなく十分に償還可能な投資であった。しかし、順風満帆のはずであったレークヒルの行く末は、予想だにしなかった事態によって大きく その第一弾は1977年8月の有珠山噴火である。7センチメートルもの降灰に見舞われ作物は全滅。結果、負債が2000万円程度も増えてしまった。第二弾は1979年の生乳過剰問題の勃発である。100頭規模畜舎を整備し着々と増頭を進めていたレークヒルにとって、生産制限は大きな痛手である。想定した収支バランスは徐々に崩れ、借金償還圧がボディーブローのように効いてきた。“儲からない酪農”が常態化し、いよいよ1981年には借金借り換えを謳った“酪農経営負債整理資金制度”(経営が悪化した農家に対して、農協などや行政機関が中心となって経営指導を実施するとともに、借り換え資金の貸し付けなどを実施する制度)も始まった。レークヒルとてうかうかとしてはいられない。 この難局を如何に乗り越えるか。ここは家族一丸、知恵を絞り「畑作との複合経営」に転換を試みる。ビートや小豆を植え、その部門を万里江氏が担当することにした。レークヒルの命運を握るかもしれない部門を彼女に任せたことは、当時の農村部における女性の地位を考えた時、先駆的と評して良いかもしれない。また、夫婦間・家族間の深い“信頼”を強く感じるのは決して我々だけではあるまい。大量に投入した堆肥が効いたのか、特に小豆の収量は周りの畑作農家よりも良く、10アール当たり5〜6俵の収穫となり、その年は10ヘクタール栽培し1250万円の収入があったと言う。小豆からは1俵当たり2万5000円の収益が得られたため、当年の借金償還を辛うじて果たし一息つくことができた。しかし、安定した相場は長くは続かない。1990年には小豆相場が1俵当たり1万5000円弱にまで暴落。昨年までと同じ苦労をして、売上げは1250万円から650万円ほどにまで落ち込み、借金返済後、500万円ほどの赤字となった。 こうした状態に追い打ちをかけたのはガット・ウルグアイ・ラウンドの乳製品の自由化交渉の行方であった。乳製品自由化などとなればわが国の酪農、もちろんレークヒルとてひとたまりもない。“ここは引くべきか。どうするべきか”。「農業こそ生涯の仕事」と飛び込んだ彼女は大いに悩んだと言う。 3 六次化へ歩を進めさせた“都会っ子”魂・“肝っ玉母さん”魂起死回生への第一幕は万里江氏の“都会っ子”魂、“肝っ玉母さん”魂によって開かれた。魂に火を付けたのは“子供達の通学バス賃すら賄えないという酪農の苦境”“働けど働けど楽にならない酪農の苦境”と言って良い。 そして転換のヒントはレークヒル前の国道が与えてくれた。そこではバブルの影響もあってか、昭和新山や洞爺湖温泉に向かう車でごった返しで、休日には渋滞すら生じる始末。この車列とこの景観、これを活かさない手はない。「牛乳を売り、この素晴らしい風景の下で飲んでもらおう」。そう思い立った彼女は早速、子供達と協力し、レークヒルの前の路肩で“牛乳販売”で市場調査を試みた。土曜日の初日には1杯100円の牛乳が150杯も売れ、売上げは1万5000円にも達した。日曜日の2日目には何と350杯も売れ、3万5000円にもなった。「道路にはお客さんが一杯いる」、「幸い、わが家には丹精込めて育てた美味しい生乳がある。これを牛乳にして売っていこう」と、方針を加工・販売へと大きく舵を切った瞬間であった。 方向は決まった、あとは実践あるのみ。彼女は牛乳販売で貯めた資金を元手に子供達を連れて“先進事例視察・探求の旅”に出かけた。新聞でみつけた“パパラギ”(十勝・池田町。六次化の先駆者)に行くため最寄駅でタクシーをつかまえ、現地に向かった。パパラギの鈴木社長はプライベートブランド牛乳を作るには製造プラントの設置許可が必要であるが、それがなかなか下りないこと、またプラント設置には1億円を下らない資金が必要なことなどを教えてくれた。教えを請うことはできたが、今の自分には時間も資金もなく、プライベートブランド牛乳を作ることは不可能であることがわかったのである。ところが、駅前で偶然拾ったタクシーの運転手から新しい情報を耳にする。近くに“ハッピネスデーリィ”と称する酪農家経営のお店があり、牛乳は販売していないが大変繁盛しているという。すがる思いでたどりつくと、そこはアイスクリームを販売する酪農家であった。ハッピネスデーリィの嶋木社長は、アイスクリームであれば保健所の許可を取れば他に特別な許可は必要ないこと、またアイスクリーム製造機械だけならフリーザーとパステライザーの2台でよく、導入資金も500万円ほどで済むことも教えてくれたのである。その上、嶋木社長は「ここは山の行き止まりで条件が良くないが、おたくの牧場は近くに洞爺湖温泉もあり、目の前には国道も通っていて、ここよりはるかに立地条件が良い。酪農家でアイスクリームに取り組んでいる人はまだまだ少ないので是非頑張って下さい」との励ましも受けたという。“探求の旅”は作るものこそ牛乳からアイスクリームへと変わったものの、大きな成功を収めたと言って良い。レークヒルは“生乳”販売オンリーから自家生乳によるアイスクリーム製造・販売、すなわち“生乳+加工品”販売の複合的経営へと転換を遂げていくことになるのである。今でこそ六次化経営も珍しくなくなったとはいえ、当時としてはまさに魁的で、“清水の舞台”級の大転換であったことは言うまでもない。 もう一つの幸運が彼女を後押しした。店舗を建ててアイスクリーム製造・販売を行うためには総額4000万円もの資金が必要であり、農協かどこからか借りてくるしかなかった。すがる思いで農協にお願いしたが、既に大きな負債を抱えていたレークヒルでは無理な相談であった。しかし、諦めるわけにはいかない。あらゆる 4 農村景観こそ最良のスパイス、アイスクリーム部門のオープンレークヒルのアイスクリーム部門は1992年7月23日、オープンした(写真2)。アイスクリーム製造・販売所と食堂を兼ねた約30坪の店舗でのスタートであった。立地の良さも手伝ってか、評判が評判を呼び、すぐに売り切れを起こすほどであった。寝る間を惜しんで作っても、機械能力の低さも手伝ってか、到底間に合うような状況ではなかったとされる。しかし、高額な高能力機械を一度に導入するのではなく、当面は手堅く安価な同一能力の機械増設で当座を凌いだという(表2)。需要にまだまだ不透明感のある中では極めて賢明な判断と言って良い。“小さく産んで大きく育てる”が六次化の神髄と思うからである。しかし、それも1990年代半ばにはいよいよ限界に達する。1997年には約70坪の店舗1棟を増築し、アイスクリーム製造・販売スペースとレストランスペースとを分離し、アイスクリーム製造機の能力アップを図るとともに落ち着いて食事できる空間・環境も整備した。
万里江氏は“天下一品”と評されるアイスクリームの製造術やレストランの運営術をどのように学んだのであろうか。前者をジェラートの本場とされるイタリアに学び、後者を室蘭の老舗レストラン“蘭亭”に学んだ。アイスクリームとレストランの組み合わせも単なる思いつきなどではない。冬場でのアイスクリームの落ち込みを想定しての積雪寒冷地ならではの対応、併設なのである。
開店に先立つ1991年、彼女はアイスクリーム製造機器メーカー関係者が主催したイタリアアイスクリーム業界の視察・研修ツアーに参加した。そこではバックヤードへの出入りも許され、レシピすら教えてくれたという。そのレシピを日本人の好みに合うように改良し、また“牛乳本来の美味しさ”を引き出すべく大いに工夫を凝らしたという。アイスクリームの種類も、自家産・地場産を軸にスイートコーンやブルーベリー、かぼちゃ味などを加え、今や100種にも及び、定番と季節ものを組み合わせながら常時20種類が並んでいる。一方、併設するレストラン運営のため、室蘭の名門“蘭亭”で修業したところ、チーフより働きぶりが認められ、メニューのラインナップから開店準備のための食器の枚数やら日々の釣り銭の枚数など、細やかな経営ノウハウを伝授してくれたという。 販売はその後も順調に伸び、アイスクリーム向けの仕向け量は、レークヒルの生乳生産量450トンのうち1割弱、40トンほどに達し、次第に名前も売れてくるようになった。しかし、だからといってレークヒルには、アイスクリーム販売網を外に向けて大いに拡大していこうという指向は全く見られない。否むしろ、「大量販売が目的ではない。皆さんにこの地の良さを知ってもらうとともに交流の輪を広げたい。そしてこの地でずーっと農業を続けて行きたいとの思いでアイスクリーム屋さんをやっている」と彼女が言うように、一時はデパート経由でも販売していたが、今ではそのような規模拡大の展開はほとんど行っていない。「この風景の中で楽しんでもらいたい」と再三彼女が強調するように、“不動の大地”に根ざす農業が生み出す“産物”と“景観”は切っても切り離せないのである。そうした思いが2001年の酪農教育ファームの認証取得につながり、酪農体験やバター製造体験をはじめ、一般消費者はもちろん外国人団体客をも含めて年間2000人もの受け入れにつながっているのではなかろうか。 5 牛を“本来の姿”に、生乳を“本来の姿”に ―放牧酪農の開始新生レークヒルへの第二幕は、六次化への取り組みから遅れること7年後の1999年に開かれた。同年、幸一氏の長女・久子氏の夫・孝二氏が牧場部門の長となり、放牧酪農を開始したのである。もちろんそれ以前でも「原料に勝る製品なし」の精神で、良質な生乳の生産に心がけていたことは言うまでもない。放牧酪農への転換はさらに歩を進め、乳牛を“牛本来の姿”に戻し、その生乳を“本来の生乳”に戻すものと評しても良い。それは久子氏の「広大な牧草地がありながら、なぜ牛たちはその草を自分で食べられないのか?不自然だ」との何気ないつぶやきから始まった。 牛を本来の姿に戻すと言っても、ただ放牧し、好きなように牧草を食めるようにすれば良い、と言うほど単純なものではない。まず、“食む牧草”が問題である。カロリーだけではなく、微量要素なども含めて栄養価が高く、牛の嗜好に合うものでなければならない。そのためには草地改良・土壌改良は欠かせない。綿密な土壌診断と施肥設計を行い、牧草の作付計画、作業・収穫計画などを立てなければならない。13.5ヘクタールの放牧地はもちろん45.5ヘクタールの採草地とて何ら変わることはない。現在、採草地には中生オーチャード、晩生チモシー、アルファルファをおのおの10〜15ヘクタールほど作り、1・2番刈のみを収穫し乾草にする(表3)。収穫した乾草にはほ場番号を記入しておき、栄養が均等になるようにブレンドの上、給与する。次は牛の“食べたいタイミング”を巧みに見分け、十分に食べさせることである。言われてみれば当たり前のことで、我々人間とて変わらない。「反
こうしたことが実ってか、レークヒルの1頭当たり濃厚飼料給与量は2005年の3000キログラム台をピークに減少曲線を描き、2010年以降、2600〜2700キログラム弱へと減少しているのである。 牧草だけではない。放牧主体となれば“草で生乳を出すタイプ”の牛を選抜し、育成していかなければならない。すなわち“良い牛作り”である。また、受胎率の良好な牛、長く搾乳出来る牛の選抜・育成も重要な問題と言える。さらに、受胎タイミングを見分ける眼力、観察力も求められる。牧場部門3人の従業者間で牛の個体情報を共有するとともに、十分に目を行き渡らせるために、調査時点(2014年10月1日)においては、飼養経産牛はたったの58頭でしかない(+育成39頭:飼養頭数計97頭)。大規模化やメガファームなどがもてはやされる中で、“その道に反する”と評しても良いかも知れない。加えて、「責任を持って仕事をしてもらうが多少の失敗はあり得る。その責任は僕が取る。しかし同じミスを繰り返してはいけない」とする、孝二氏の従業員に信頼を寄せ仕事を任せると言う姿勢も“良い牛作り”に大きく貢献していると言えよう。牛の個性を確実に見分け、牧草を食むことを可能な限り早期に覚え込ませ、足腰の強い牛を育てるために、育成牧場などは利用せず、自家繁殖・育成を行っていることを付け加えておきたい。レークヒルでは子牛を50日ほどで離乳させ、3カ月目からは放牧に出すとされる。6カ月目から放牧に出す一般的なやり方に比べ、3カ月も早くから放牧と草を食むことに牛たちは このようなレークヒルの飼養方針は、成果として高泌乳と濃厚飼料給与量の減少に表れている(表4)。1頭当たり乳量は放牧開始時(1999年)7339キログラムであったものが2002年には9000キログラムを超え、2009年には9924キログラムを達成し、以降もほぼ9500キログラム超を実現している。
全道平均が9100キログラムほどとされる中、この成績は驚嘆に値する。しかも、細菌数は2000個未満、体細胞数は最大でも15万個未満、平均1桁台なのである。そればかりではない。一頭一頭、愛情を持ってしっかり育てられた牛は“実に元気で長持ち”なのである。平均でも3.5産、5産以上が4割以上で、中には10産を超える牛もいるということである。2〜3産が平均と言われる中で10産以上とはまさに“乳牛 6 おわりに 〜レークヒルの重奏低音―“信頼”の二文字〜 以上、レークヒルのあゆみと特長・特色について紹介してきた。“六次産業化”と“放牧・高泌乳酪農”で名を 六次化へと踏み切ったレークヒルの英断に大いなる称讃を送りたい。塩野谷家の先駆性・開拓者精神のDNAの発現とでも言えようか。さらに、それに歩調を合わせながら生乳のさらなる良質化、乳牛の飼養管理の綿密化に取り組んでいったことも特筆される。それは何と言うことはない。牛をただ“本来の姿”に、生乳を“本来の姿”に戻すだけだったのである。しかし、それは“言うに易く行うに難い”ことかも知れない。そこには牛本来の姿、牛の能力に対する限りない“信頼”、そしてその発現をじっくり静かに待つと言う姿勢が求められるからである。
ところで、今“信頼”と言う言葉を出したが、レークヒルの動きはこの二文字が軸になって展開してきたような気がしてならない。六次化も家族間の信頼、4000万円の借入の承認がなければ画餅であったし、また、その前提に一見“バブルに浮かれた”ように見える人々の“本来の心”―本物を求め、農村景観を求めている人々の心―に対する信頼がなければ踏み切れるものではない。また、いろいろな局面でレークヒルに知恵を貸し、相談に乗ってくれた人々との関係も同じであるし、従業員との間でも同じである。心からの信頼、我々が“親友”とか“ 六次化と高泌乳酪農の灯台、“汲み尽くせない学びの場”、“酪農家・農業者へのエール”としての(有)レークヒル牧場のますますの発展を祈らずにはいられない。 |
元のページに戻る