�C�O���݈����|�[�g�@
�č��ɂ����鋍������̓����ɂ���
���V���g�����݈��������@����@�p�r�A�n�Ӂ@�T��Y
�@�č��̐H���ƕ����āA�����������̃X�e�[�L��z���������������̂ł͂Ȃ�
���Ǝv����B�P�l�����苍���̏���ʂ́A���̃s�[�N���ł���76�N�ɂ�42.7kg
�i�����d�ʃx�[�X�B�ȉ������j�ŁA�ؓ���2.1�{�A�{����2.6�{�ƁA�܂��ɐH����
���҂Ƃ��ČN�Ղ��Ă����B�������A77�N�ȍ~�A��������͌��N���ւ̌��O�Ȃ�
��w�i�Ƃ��āA��20�N�Ԓ���𑱂��A�P�l������̏���ʂɂ��Ă��A93�N�ȍ~
�{���Ɏ�ʂ̍��𖾂��n���Ă���B
�@���̂悤�ȏ̒��A�������N��������ɉ̓����������Ă���B������
�������ɂ��ẮA�č��o�ς̍D������~���j�A���Ɋւ���s�����ɕt��������
�v�Ȃǂ̈ꎞ�I�܂��͖{���Ƃ͈قȂ镔���ł̒ǂ����ɏ�����Ƃ������ʂ��ے�
�ł��Ȃ��B�������A�����ɑ��錒�N�C���[�W�̉A�����𗘗p���������ς�
�H�i�̊J���ȂǁA����҂��������������ƊE�ɂ����g�݂��t�������邱
�Ƃ������ł��낤�B
�@�����̃��|�[�g�ł́A�č����ɂ����鋍���̏���p�^�[���Ȃǂ̊�{�I�ȏ��
�ɉ����āA�ŋ߂̏���̓����Ɋւ���v���Ȃǂɂ��ĕ��邱�ƂƂ���
���B
�@���̏͂ł́A�č��ł͋������N�ɂǂ̂悤�ɏ����Ă���̂��A�Ƃ�������
�{�I�ȏ����������B
�i1�j����`��
�@�����̏���`�ԂƂ��ẮA�����X�ł̗①�܂��͗Ⓚ�����A�\�[�Z�[�W�Ȃǂ�
���H�H�i�A���ؓX�i�f���j�Ȃǂ̒��H�X�܂ł̍w���A�O�H�̗��p�Ȃǂ��������
��B�����ŏЉ�鐔�l�́A96�N�̐��v�l�ł��Â����̂́A�e����`�Ԃ̑S��
�ɐ�߂�ʒu�ɂ��āA���̊T�ς��Ƃ炦���ł̎Q�l�ɂȂ���̂Ǝv����B
���̐��l�́A�H�����i�̊e�`�Ԃł̔��㍂���牵�����z�𐄌v���A���ꂼ��̐H
���ɑ������镔��������o�������̂ł���B����ɂ��A�����̏ꍇ�A�����X
�̗①�`�Ԃł̏���i�w���j���S�̖̂�W�����߂����A�ؓ�����щƂ����
�ɂ��ẮA���ꂼ��34�������51���ł��邱�Ƃ���A���̌`�Ԃ̐�߂銄����
�傫������������̓����ƌ����ėǂ����낤�B
�@�����X�̗①�ł̍w�����������啔�����O�H�ŁA�S�̂̂Q����ƂȂ��Ă���B
�ʋl�A�\�[�Z�[�W�Ȃǂ̉��H���i�̊����͂킸���Ȃ��̂ł���A����炪�S�̂�
�R���ȏ���߂�ؓ��Ƃ̈Ⴂ���ۗ����Ă���B�Ȃ��A�č��ɂ�����O�H�̐H��
�S�̂ɐ�߂銄���͑����X���ɂ���i99�N��46���j�A96�N�ȍ~�A�����ɂ��Ă�
�O�H�̊������������Ă��邱�Ƃ��\�z�����B
�\�P�@�H���̏���`�ԕʉ����̔��z�̐��v�l
 �@�����F�e��ƊE�������Sparks Companies, Inc.�iSCI�j�����v
�@�@���F�l�̌ܓ��̊W�ŁA���v�ƌX�̐ςݏグ�����v���Ȃ��ꍇ������B
�i2�j�������@
�@����҂̍D�ދ����̒������@�ɂ��ẮA2000�N�Ƀl�u���X�J��w�̌����҂�
�V�J�S�ƃT���t�����V�X�R�ōs����������蒲���̌��ʂ��Q�l�ƂȂ�B����ɂ�
��A�ł��l�C�̂��钲�����@�̓o�[�x�L���[�ȂǂɌ�����Grilling���ŁA����
�ɃI�[�u���Ȃǂ𗘗p����Broiling���������A�S�̂̂X������߂�B���������u
���f���A�����̃^�C�v�ɂ��Ă��A�X�e�[�L�J�b�g���ł��l�C�������A����
�Ń��[�X�g�r�[�t�p�A�Ђ����̏��ƂȂ��Ă���B
��Grilling��Broiling
�@�Ƃ��ɕ��˔M�ɂ���āu���Ԃ��ďĂ��v�����@�ł��邪�AGrilling�͈�ʓI�Ɍ�
�O�̃o�[�x�L���[�Ȃǂ̂悤�ɒY�Ȃǂ��g���ĖԂ̏�ŏĂ����́ABroiling��
�{�̊ۏĂ���i�u���C���[�I�[�u���j�̂悤�ɕ��˔M���o���R�C���ɂ���ďĂ�
���̂Ƌ�ʂ����B
�i3�j�G�ߕϓ�
�@�H���̏���ɂ́A���C�t�X�^�C���f�����G�ߕϓ���������B��ʓI�ɒm
���Ă���ʂ�A�t����Ăɂ͌ˊO�ł̃o�[�x�L���[������ɍs���邽�߁A��
����{���̏���A�܂��A���ӍՂ̎����ɂ͎��ʒ��̏��������X��������B
�����ɂ��ẮA90�N����2001�N�R���܂ł̎l�������Ƃ̃f�[�^�ɂ��ƁA����
�ʂ��ő�ƂȂ��R�l�����ƍŏ��ƂȂ��S�l�����ŁA�P�l���������ʂ͖�P
�|���h�i��450g�j�̍�������B
���}�P�F�P�l������H���H��̋G�ߕϓ���
�i4�j�����A���ыK�͂���э\���A�n��Ȃǂɂ�����p�^�[��
�@�����K�w�ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j������ƁA�N���V���h���i��875
���~�F�P�h����125�~�j�����̊K�w�܂ł́A�����̑����ɉ����Ďx�o�z��������
����̂́A�������K�w�ł͎x�o�z���O�O���[�v�̐����������B��ʂɁA
�������ґw�́A���琅����N��w�������A�J�����Ԃ������X���ɂ��邪�A������
���r�I���Ȃ��X���ɂ��邱�Ƃ��m���Ă���B�܂��A�t�����_��w�̌�����
�̒����ɂ��A���琅���������l�قǁA���܂��܂ȐH�ނ����݂�X��������A
�H�i�ƌ��N�ւ̊S�������Ƃ����B
���}�Q�F�����K�w�ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@���ыK�͕ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA���э\�����̐����Q
�`�S�l�܂łł́A�傫�ȈႢ�������Ȃ����A�T�l�ȏ�̏ꍇ�́A�啝�ɑ�����
�Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ȃǂł̋����̃o�����[�p�b�N
�i�X�e�[�L�p�J�b�g������ʂɂ܂Ƃ߂ăp�b�N���Ă��邨�l�ł��i�j�̑��݂���
����̂Ƃ݂���B
���}�R�F���ыK�͕ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@�n��ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA�k�����Ɛ��C�݂ł�⑽
���ق��́A�n��ɂ��Ⴂ�͂قƂ�nj����Ȃ��B
�\�Q�@�n��ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j
�@�����F�e��ƊE�������Sparks Companies, Inc.�iSCI�j�����v
�@�@���F�l�̌ܓ��̊W�ŁA���v�ƌX�̐ςݏグ�����v���Ȃ��ꍇ������B
�i2�j�������@
�@����҂̍D�ދ����̒������@�ɂ��ẮA2000�N�Ƀl�u���X�J��w�̌����҂�
�V�J�S�ƃT���t�����V�X�R�ōs����������蒲���̌��ʂ��Q�l�ƂȂ�B����ɂ�
��A�ł��l�C�̂��钲�����@�̓o�[�x�L���[�ȂǂɌ�����Grilling���ŁA����
�ɃI�[�u���Ȃǂ𗘗p����Broiling���������A�S�̂̂X������߂�B���������u
���f���A�����̃^�C�v�ɂ��Ă��A�X�e�[�L�J�b�g���ł��l�C�������A����
�Ń��[�X�g�r�[�t�p�A�Ђ����̏��ƂȂ��Ă���B
��Grilling��Broiling
�@�Ƃ��ɕ��˔M�ɂ���āu���Ԃ��ďĂ��v�����@�ł��邪�AGrilling�͈�ʓI�Ɍ�
�O�̃o�[�x�L���[�Ȃǂ̂悤�ɒY�Ȃǂ��g���ĖԂ̏�ŏĂ����́ABroiling��
�{�̊ۏĂ���i�u���C���[�I�[�u���j�̂悤�ɕ��˔M���o���R�C���ɂ���ďĂ�
���̂Ƌ�ʂ����B
�i3�j�G�ߕϓ�
�@�H���̏���ɂ́A���C�t�X�^�C���f�����G�ߕϓ���������B��ʓI�ɒm
���Ă���ʂ�A�t����Ăɂ͌ˊO�ł̃o�[�x�L���[������ɍs���邽�߁A��
����{���̏���A�܂��A���ӍՂ̎����ɂ͎��ʒ��̏��������X��������B
�����ɂ��ẮA90�N����2001�N�R���܂ł̎l�������Ƃ̃f�[�^�ɂ��ƁA����
�ʂ��ő�ƂȂ��R�l�����ƍŏ��ƂȂ��S�l�����ŁA�P�l���������ʂ͖�P
�|���h�i��450g�j�̍�������B
���}�P�F�P�l������H���H��̋G�ߕϓ���
�i4�j�����A���ыK�͂���э\���A�n��Ȃǂɂ�����p�^�[��
�@�����K�w�ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j������ƁA�N���V���h���i��875
���~�F�P�h����125�~�j�����̊K�w�܂ł́A�����̑����ɉ����Ďx�o�z��������
����̂́A�������K�w�ł͎x�o�z���O�O���[�v�̐����������B��ʂɁA
�������ґw�́A���琅����N��w�������A�J�����Ԃ������X���ɂ��邪�A������
���r�I���Ȃ��X���ɂ��邱�Ƃ��m���Ă���B�܂��A�t�����_��w�̌�����
�̒����ɂ��A���琅���������l�قǁA���܂��܂ȐH�ނ����݂�X��������A
�H�i�ƌ��N�ւ̊S�������Ƃ����B
���}�Q�F�����K�w�ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@���ыK�͕ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA���э\�����̐����Q
�`�S�l�܂łł́A�傫�ȈႢ�������Ȃ����A�T�l�ȏ�̏ꍇ�́A�啝�ɑ�����
�Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ȃǂł̋����̃o�����[�p�b�N
�i�X�e�[�L�p�J�b�g������ʂɂ܂Ƃ߂ăp�b�N���Ă��邨�l�ł��i�j�̑��݂���
����̂Ƃ݂���B
���}�R�F���ыK�͕ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@�n��ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA�k�����Ɛ��C�݂ł�⑽
���ق��́A�n��ɂ��Ⴂ�͂قƂ�nj����Ȃ��B
�\�Q�@�n��ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j
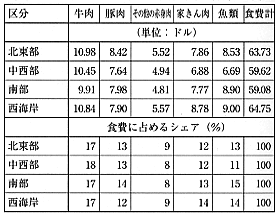 �@�����F�t�r�c�`�uMeat & Poultry Facts�v
�@�����F�t�r�c�`�uMeat & Poultry Facts�v
�i1�j��������
�@�P�l������̋������76�N���s�[�N�ɖ�20�N�Ԓ���𑱂��������̂P�Ƃ�
�����̂��A77�N�Ɍ��\���ꂽ��A�č����̍��������H�����w�j�i80�N�j�̊�b��
�Ȃ����A�ċc���@�́u�H�����Ǝ��Ɏ���a�v�Ə̂������ł���Ǝw�E��
���B�����������̏�@�̓����́A�}�������Ô�}����̂P�Ƃ��āA�H����
�̌������ɂ��S���a���̎��������炷���߂̎��݂ł��������A���ʂƂ��ċ���
�̌��N�ɑ��鈫���C���[�W������҂ɋ����Ă��t���邱�ƂƂȂ����B�܂��A��
���̎Љ�i�o���}���ɑ������A�H�����߂������҂̃j�[�Y���傫���ω�������
��������炸�A�����ƊE�̑Ή����x�ꂽ���Ƃ��A�������������ɑf������������
�Ƃ�����ƊE�Ƃ̖��Â����Ƃ������Ă���B
�@���̌�A�P�l�����苍������ʂ́A30kg�O��Œ���𑱂������A98�N��1.8���A
99�N��3.5���A2000�N�ɂ�1.6���A���ꂼ��O�N�����������Ƃ���A�����ƊE��
�͂��߂Ƃ��āA����̓������傫�Șb��ƂȂ����B
���}�S�F�P�l�����苍������ʂ̐��ځ�
�i2�j�̗v��
�@��������̗v���Ƃ��ẮA���܂��܂Ȃ��̂�����A���ꂼ�ꂪ���G�ɉe��
�������Ă���ƍl�����邪�A�����ł͂��̎�Ȃ��̂̓����ɂ��Č��Ă݂����B
�@�č��o�ς̍D�����A�~���j�A�����v
�@�܂��A��P�̗v���Ƃ��ċ�������̂��A�č��o�ς̍D�����ł���B���݂́A
��⌸���C���ł�����̂́A91�N�ȍ~�A�����Ԃɂ킽���Ĉ���I�Ɋg��𑱂���
�������߁A����ɔ����l�����̑������������v�̉ɍv���������̂Ƃ݂��
����B
�@�J���U�X�B����w�̃G�R�m�~�X�g�̌����ɂ��A�č��̋�������͏���
�e���������A�P�l������̐H���x�o���P����������A���������0.9����������
�Ǝ��Z���Ă���B���������ɐ�߂鑍�x�o�̊����́A80�N��̏��߂ɂ͖�90��
�ł��������̂��A99�N�ɂ́A�ق�98���ɂ܂ő��債�Ă���A��������̉ɂ�
��^�������̂ƍl������B�Ȃ��A���R�̂��ƂȂ���A�o�ς̌����ɂ��A����
�҂��x�o��}������A��������Ƀ}�C�i�X�̉e����^���邱�ƂƂȂ�B
�@���Ɏw�E�����̂��A�~���j�A���̊֘A�s���i�p�[�e�B�A�e��C�x���g�j��99
�N���ɁA���ɍ������ʂ̎��v�����������Ƃ������̂ł���B���������s���ł̋�
������ʂɊւ���f�[�^�͂Ȃ����̂́A�`���C�X���ȏ�̃��C���n�A�C�e�����i
���ł��邱�Ƃ≿�i�������������ƂȂǂ��`�����Ă���A��ʂɋ������v����
�v���̂P�Ƃ��ĔF������Ă���ƌ����ėǂ����낤�B
�A����҃j�[�Y�ւ̑Ή�
�@���v�ɂ́A����̕ω��ɔ�������҃j�[�Y�ւ̓K�ȑΉ������������A��
���ŏq�ׂ�悤�Ȏ��g�݂��A��������̉Ɋ�^�������̂Ƃ݂���B
�ȕ��̒Nj�
�@�č��ł́A�����̎Љ�i�o���ڊo�܂����A���������̏A�Ɨ���60�N��32������
�ŋ߂ł�60������܂łɑ������Ă���B����A�ƒ�̐H�������d��̂́A
�ˑR�Ƃ��ď����ł��邽�߁A�������Ԃ���ю�Ԃ̒Z�k���d�v�ȉۑ�ƂȂ邱��
�͎��m�̒ʂ�ł���B
�@
�@����}�[�P�e�B���O��Ђ̒����ɂ��A�[�H�̏����ɂ����鎞�Ԃ́A30�N�O
�ɂ͕��ςQ���Ԃł��������̂��A���݂ł͔����ȉ���45���`60���ƂȂ��Ă���A
�������̂�25�����T�P�`�Q��A15�����S�����Ȃ��Ȃǂƌ������Ă���B
�@���������ω��ɑΉ����ׂ��A�����ƊE�c�̂ł́A�d�q�����W�ʼn��߂邾���̒�
���ςݐH�i�i"Heat�]and�]Serve Beef Products"�j�̔̔��ɗ͂����Ă���A�S
���������Y�ҁE��������iNCBA�j�ɂ��A99�N�P������2000�N�X��23���܂�
�̊Ԃɂ����āA31�̐H�i��Ђ���50�̂��������V���i����������Ă���A�����
���ɂ��ẮA97�N12������̂R�N�Ԃ�8,427���h���i��105���~�j�Ƃقڔ{����
����B
�����ςݐH�i�̗�A���V�s�t�������p�b�P�[�W
�@�ʐ^�P�́ANCBA����Â���u2000�N�������i�ŗD�G�܁v�̏�������̎�ܐ�
�i�ŁA�g�b�v�T�[���C���X�e�[�L�̃o�[�{���\�[�X�Ђ��B�������Ԃ��W���Ƌ���
����Ă���ق��APremium�i�����ȁj�ASignature�i�����́j�Ƃ���������������
�o���錾�t��������B
�@���̏܂̑��ɁA�t�[�h�T�[�r�X����A�������[�J�[�ɂ�鋍�����i����A�v�V
�I�ŏ��ƓI�����������܂�镔��ł̂R�܂��݂����Ă���B�����̏܂́A
�u�ȕ��v�Ƃ�������҃j�[�Y�ɍ��v���鋍�����i�̊J������є̔��Ɏ����邱
�Ƃ�ړI�Ƃ��A�����̔����Ȃǂɒ��������`�F�b�N�I�t�����𗘗p����98�N��
����{����Ă�����́B���Ȃ݂ɁA�����ςݐ��i�̕��y�́A����܂ŕs���v����
�Ƃ݂Ȃ���邱�Ƃ̑��������J�^����̍��t�����l���Ƃ��������b�g��������
���Ă���B�܂��A�����������݂́A���łɂ��̕���ő傫�����[�h����Ƃ����
�ƊE�ɒ��킷����̂ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B
�@�ʐ^�Q����тR�́ANCBA�ƃ����[�����h�B�̃X�[�p�[�}�[�P�b�g���s���Ă�
��̑������̈�Ƃ��āA�p�b�P�[�W�̕\�Ɂu���Ԃ�Ă��p�v�A�u�ύ��ݗp�v��
��܂��Ȓ������@���L�����V�[��������t����ꂽ���́B����ȊO�ɂ��A���ʁA
�J�b�g�Ȃǂɂ��A�u�\�e�[�p�v�Ȃǂ̃V�[��������B�V�[���̕\�ʂ��͂����ƁA
���ʂȂǂɂ���̓I�ȃ��V�s�Ȃǂ��L�ڂ���Ă���A���ۂ̒����̎Q�l�Ƃ���
���Ƃ��ł���i�ʐ^�S�j�B���钲���ɂ��A�҂̔����ȏオ�A�����̕�e
��蒲���Z�p����ђm�������Ɠ����Ă���A�����Ɋւ���m�E�n�E�����
���Ƃ��d�v�Ȏ��v���i�����̂P�ƔF������Ă���B
���N�C���[�W�̉��P
�@70�N��̌㔼�ȍ~�A�����i���ɂ��̎��b�j�̌��N�ւ̈����C���[�W����|����
���߁ANCBA�ł́uWar on Fat�v�Ə̂������g�݂�90�N�����J�n���A�����p
����уt�[�h�T�[�r�X�p�����̕\�ʎ��b���W���̂P�C���`�i��Rmm�j�ȉ��Ɏ��
�������Ƃ�����B�����������g�݂̌��ʁA���݂ł́A�����X�Ŕ̔������
���鋍���̎��b�́A20�N�O�Ɣ�r����27�����������ƕ���Ă���B
�@�ŋ߂ł́ANCBA�́A�����Ɋ܂܂�鈟���A�S���A����ς����A�r�^�~���a�Q
�̌��N�ێ��ɂ�����d�v������Ƃ��ĕ�e�w�ɑi����L�������Ȃǂ��s���Ă���B
�i���̌���
�@��������̒���ɑ��āA�i���ʂł̋����͂����߂���g�݂��s���Ă���A
���̂P�ɋ����̓�炩���Ɋւ��钲��������B���̌����̋�����ؒf���邽
�߂ɕK�v�ȗ͂��d�ʂł���킷Warner�]Bratzler Shear Force�iWBSF�j�@�Ȃǂ�
��@��p���āA98�N����99�N�ɂ����Ď��{���ꂽ�������ʂɂ��A�O����
��90�N�Ɣ�r���āA��炩������Q�����サ�����Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@����́A��莞�Ԃ������Ď}�����p����悤�ɂȂ������ƁA�����X��X�g
�����ł̏n�����Ԃ������������ƂȂǂɂ����̂Ƃ݂��Ă��邪�A��炩����
����҂��ł��d������|�C���g�̂P�ł��邱�Ƃ���A����ɂ��ăv���X
�ɓ����v�f�ƌ��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�܂��A��炩���Ɋ֘A����Ǝv�����
�`�q�}�[�J�[�����肳��Ă���A����̓������ǂ����҂���Ă���B
�@�Ȃ��A�O�o�̃J���U�X�B����w�̌����ɂ��A�ؓ��ƉƂ�����ɂ��āA��
������ɑ���������i�e�͐����͂��ꂼ��0.04�����0.02�Ǝ��Z����Ă���A
������͔̂F�߂�����̂́A�ؓ���Ƃ�����̉��i��������������ɗ^����
�e���͂��܂�傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă���B�����������Ƃ��܂߂āA��������
���́A����̋������v�ɂ��āA���̐H���̉��i�����Ȃǂ��������̕i������
�����d�v�ȗv���ƂȂ�ƌ��Ă���B
���������i�e�͐�
�@������̉��i���P���ω������Ƃ��A���̍��̎��v���ω����銄���Ƃ��ĕ\����
��B
�B������ς����_�C�G�b�g�̗��s
�@�����鍂����ς����_�C�G�b�g�̗��s������̗v���̂P�ɋ�������B
���̃_�C�G�b�g�@�́A�Y�������A�����A�ʎ��Ȃǂ̐ێ���T�������ɁA����
�Ȃǂ̍�����ς����H�i��ʁA�ێ�Ȃǂ̐�����݂����ɐH�ׂĂ��ǂ��Ƃ�
����̂ŁA���̌��ʂ�e���ɂ��Ă͂��܂��܂ȋc�_���s���Ă�����̂́A��
�H���������A������ς��H�i�ɂȂ��݂̐[���č��l�ɂƂ��Ă͔�r�I�����
�����A�傫�ȃu�[���ƂȂ����B�Ȃ��A�����܂Ńu�[���ł��邽�߁A�ꎞ�I�Ȏ��v
���ɂ����Ȃ��Ƃ̌���������B
�C���S���̌���
�@�����̈��S���̌��������̉v���̂P�ɋ�������BNCBA��2000�N��
���{���������ɂ��A���������S�ƔF���������҂̊����́A�J�b�g�����W��
���A�Ђ������V����ƂȂ��Ă���A����܂ł̒����ōō��ƂȂ��Ă���B�Ĕ_��
�ȁiUSDA�j�ɕ��ꂽ�L�Q�o�N�e���A�ւ̉����Ȃǂɂ��H���̃��R�[����
�����̂͌������Ă��Ȃ����̂́i�t�Ƀ`�F�b�N�@�\�����サ�Ă��錋�ʂƂ��Ƃ�
��j�A�����ɗR������傫�ȐH���Ŏ������Ȃ��������ƂȂǂ���A�����̈��S��
�ɑ������҂̔F�������P���ꂽ���ʂƍl������B
�@�����ł́A����̎��v�����Ɋ֘A������ȃg�s�b�N�X�ɂ��ďЉ��B
�i1�jBSE��FMD��肪�y�ڂ��e���ւ̌��O
�@�č��ł́A���C�ȏ�]�ǁiBSE�j������u�iFMD�j�͔������Ă��Ȃ����̂́A
����������肪�}�X���f�B�A�Ɏ��グ������������߁A�����̈��S����
�̕s���������ւ̃l�K�e�B�u�ȉe���ɔ��W���邱�Ƃ����O����Ă���B������
�E�ł��A������@��ɂ����̖��Ɋւ���s�������ɓw�߂Ă��邱�Ƃ�����
�Ă��A�E�H�[���X�g���[�g�W���[�i�����i�R���W���t�j�̒����ł́ABSE�ɂ�
�Ă̔F���͂��邪�A���̂��Ƃ͎����̋�������ɉe����^���Ȃ��Ɠ������l�̊�
�����W������߂�Ƃ������ʂł������B�������A�ŋ߂ł́A�t�@�X�g�t�[�h��
�E�ŁA�����������ɂ�����ނ̓�����������Ƃ̕�����A���R�̂�
�ƂȂ���A�y�ώ����邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�i2�j�o�ς̌���
�@�č��̌i�C�́A��N���ɔ�ׂ�Ό����͊ɂ₩�ɂȂ��Ă�����̂́A��������
����Ƃł̌ٗp�팸�̓����Ȃǂɂ��A��s�����s�����ȏ�ԂƂȂ��Ă���B
�ߏ�ɂ̊ɂ₩�Ȍ����Ƃ���ɔ������Y�̑����A�A�M�������x������iFRB�j
�̗��������ʂȂǂɂ��A���N�㔼�ɂ͌o�ς�������Ƃ���G�R�m�~�X�g������
���A������ɂ���A�������͂��߂Ƃ��āA���܂��܂ȏ���ɉe����^�����{�I
�ȗv���ł���A����Ƃ��������Ă����K�v������B
�i3�j�l���\���̕ω�
�@�č��ō�N���{���ꂽ���������ł���Z���T�X2000�̌��ʂɂ��A�č��̑�
�l���͂Q��8,142���l�ƂȂ����B10�N�O�̃Z���T�X���ʂƂ̔�r�ł́A��3,270��
�l�̑������L�^���A�V���Z���T�X�Ԃ̑����Ƃ��Ă͉ߋ��ő�̐��l�ƂȂ����B�l
��ʂ̓���ł́A���l��75.1���A�q�X�p�j�b�N�n��12.5���A���l��12.3���A�A�W
�A�n��3.6���ƂȂ��Ă���B
�@���ł��L���������̂��A���l���������q�X�p�j�b�N�n�ł���A���O���[
�v�͍�������������������A2050�N�ɂ͑S�̖̂�S���̂P�߂����߂�悤�ɂ�
��Ƃ��\������Ă���B
�@����A�č��ł����{�قǂł͂Ȃ����̂́A������i�W����Ɨ\�z����Ă���B
���ł��A���̎s��֗^����e���̑傫������A���т��у}�[�P�e�B���O�̑Ώۂ�
�Ȃ��Ă����x�r�[�u�[�}�[�i1946�N����1964�N���܂�̐l�j�̍ŔN���҂����N�A
�ꍇ�ɂ���Ắu�V�j�A�v�̃J�e�S���[�ɋ敪����邱�Ƃ�����55�Ƃ����N��
�ɒB���邱�Ƃ����ڂ𗁂тĂ���B
�i4�j�얞�̑���
�@�ی��Љ���Ȏ��a�Ǘ��\�h�Z���^�[�iCDC�j��99�N�Ɏ��{���������̌��ʁA
�č��̐��l�̂U���ȏオ����߂��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����BCDC�ɂ��A
���b���̂̐ێ�͌������Ă�����̂́A�J�����[�̐ێ悪�����Ă���Ƃ����B��
���A���̌X���́A�ʂɍs��ꂽ��w�̗����Ɋւ���ӎ������̌��ʂƈ�v����B
����ɂ��A���������鎞�ɃJ�����[���l������Ɠ������l�̊�����90�N�ɂ�
39���ł��������̂��A����ȍ~�قڈ�т��Č������A2000�N�ɂ͂���܂łōŒ�
��25���ɂ܂ŗ�������ł���B
�@���{�́A�얞�̐l�̊��������炵�Ă��������Ƃ����ӌ��������Ă���A���݂�
�얞�X���̔����Ƃ��āA�Ăы�������Ƃ������Ԃ��N����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B��
���������Ƃ���A�����ƊE�ɂƂ��ẮA�h�{�ʂł̏���ҋ��炪����ɏd�v�Ƃ�
����̂ƍl������B
�@���܂��܂ȗv�������钆�ł��A�����ƊE�̏���҃j�[�Y�ւ̑Ή����A�����
�̈ꗃ��S���Ă��邱�ƁA�����č�������������ƊE�̎��g�݂��p������邱
�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B����́A����u�����̉Ƃ�����ƊE���v�Ƃ������铮���ł�
��i�������Ȃ��������̂́A�{���̍ő��p�b�J�[�ł���^�C�\���t�[�Y�ɂ��
�č��ő�̐H���p�b�J�[IBP�����͂������������̏ے��Ǝv��ꂽ�j�B�Ƃ����
�̋ƊE�́A�H���̒��ł́A����҃j�[�Y�ɓK���������ςݏ��i��K�i�����ꂽ�u
�����h���i�̒ȂǁA�}�[�P�e�B���O��@�����p�������g�݂̐��҂ł���A
�����҂ł���ƌ�����B�܂��A�{���̐����I�����i�C���e�O���[�V�����j�Ƃ���
���Y�E���ʑ̌n�́A����҃j�[�Y�Ƃ����쉺�̏�����̐��Y����֓`�����
�ŁA�����I�Ȏd�g�݂ł���ƌ�����B
�@����A�������Y�҂́A���R�ƓƗ������ւ�Ƃ��Ă���A���Y�ɂ��Ă���ʂɁA
�ɐB�A�琬�A���Ƃ��ꂼ��̒i�K�ŕʁX�̌o�c�ɂ���čs���Ă���B�o�ς�
�������ABSE��FMD���Ƃ�������������Ƀ}�C�i�X�̉e����^���鏔��肪��
�O����钆�A�{���I�ȈӖ��ł̏���g��ɂȂ������҃j�[�Y�ւ̑Ή��ɂ�
�āA���ꂼ��̐��Y����ɂǂ̂悤�Ȍ`�Ńt�B�[�h�o�b�N���āA�i���̌���Ȃ�
�ɂȂ��Ă����̂��A���̍ۂɌ{���قǂł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���Y�_���̔��_��
�Ȃlj��炩�̐����I�Ȓ������s���Ă����̂��ȂǁA�����[���B
�i�Q�l�����j
Ted C. Schroeder, et al "Beef Demand Determinants",
Jan. 2000, Kansas State University
"The fall and rise of BEEF", National Cattlemen,
Jan.�]Feb. 2001
"Meeting Consumer Needs, unleashes an era of
unparalleled change" National Cattlemen, Jan.�]Feb. 2001
USDA/ERS "Food Consumption and Spending"
Food Review, Vol.22, Issue 3
Various Articles from NCBA Home Page and
NCBA Annual Conference in Feb. 2001
University of Florida News "Who eats beef?" Sept. 14, 2000
Various Articles from USDA/ERS
"Livestock Dairy and Poultry Situation and Outlook"
CNN.com "CDC says 61�� of US adults overweight"
Dec. 15, 2000
Wall Street Journal "Skip the Tofu�]More Americans Tear
into Steaks" Mar. 8, 2001
���t�{�u�C�O�o�ϕv����13�N�S��
�ȏ�̂ق��A�R���T���^���g��Ђ̒��������Q�l�Ƃ����B
���̃y�[�W�ɖ߂�
 �@�����F�e��ƊE�������Sparks Companies, Inc.�iSCI�j�����v
�@�@���F�l�̌ܓ��̊W�ŁA���v�ƌX�̐ςݏグ�����v���Ȃ��ꍇ������B
�i2�j�������@
�@����҂̍D�ދ����̒������@�ɂ��ẮA2000�N�Ƀl�u���X�J��w�̌����҂�
�V�J�S�ƃT���t�����V�X�R�ōs����������蒲���̌��ʂ��Q�l�ƂȂ�B����ɂ�
��A�ł��l�C�̂��钲�����@�̓o�[�x�L���[�ȂǂɌ�����Grilling���ŁA����
�ɃI�[�u���Ȃǂ𗘗p����Broiling���������A�S�̂̂X������߂�B���������u
���f���A�����̃^�C�v�ɂ��Ă��A�X�e�[�L�J�b�g���ł��l�C�������A����
�Ń��[�X�g�r�[�t�p�A�Ђ����̏��ƂȂ��Ă���B
��Grilling��Broiling
�@�Ƃ��ɕ��˔M�ɂ���āu���Ԃ��ďĂ��v�����@�ł��邪�AGrilling�͈�ʓI�Ɍ�
�O�̃o�[�x�L���[�Ȃǂ̂悤�ɒY�Ȃǂ��g���ĖԂ̏�ŏĂ����́ABroiling��
�{�̊ۏĂ���i�u���C���[�I�[�u���j�̂悤�ɕ��˔M���o���R�C���ɂ���ďĂ�
���̂Ƌ�ʂ����B
�i3�j�G�ߕϓ�
�@�H���̏���ɂ́A���C�t�X�^�C���f�����G�ߕϓ���������B��ʓI�ɒm
���Ă���ʂ�A�t����Ăɂ͌ˊO�ł̃o�[�x�L���[������ɍs���邽�߁A��
����{���̏���A�܂��A���ӍՂ̎����ɂ͎��ʒ��̏��������X��������B
�����ɂ��ẮA90�N����2001�N�R���܂ł̎l�������Ƃ̃f�[�^�ɂ��ƁA����
�ʂ��ő�ƂȂ��R�l�����ƍŏ��ƂȂ��S�l�����ŁA�P�l���������ʂ͖�P
�|���h�i��450g�j�̍�������B
���}�P�F�P�l������H���H��̋G�ߕϓ���
�i4�j�����A���ыK�͂���э\���A�n��Ȃǂɂ�����p�^�[��
�@�����K�w�ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j������ƁA�N���V���h���i��875
���~�F�P�h����125�~�j�����̊K�w�܂ł́A�����̑����ɉ����Ďx�o�z��������
����̂́A�������K�w�ł͎x�o�z���O�O���[�v�̐����������B��ʂɁA
�������ґw�́A���琅����N��w�������A�J�����Ԃ������X���ɂ��邪�A������
���r�I���Ȃ��X���ɂ��邱�Ƃ��m���Ă���B�܂��A�t�����_��w�̌�����
�̒����ɂ��A���琅���������l�قǁA���܂��܂ȐH�ނ����݂�X��������A
�H�i�ƌ��N�ւ̊S�������Ƃ����B
���}�Q�F�����K�w�ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@���ыK�͕ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA���э\�����̐����Q
�`�S�l�܂łł́A�傫�ȈႢ�������Ȃ����A�T�l�ȏ�̏ꍇ�́A�啝�ɑ�����
�Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ȃǂł̋����̃o�����[�p�b�N
�i�X�e�[�L�p�J�b�g������ʂɂ܂Ƃ߂ăp�b�N���Ă��邨�l�ł��i�j�̑��݂���
����̂Ƃ݂���B
���}�R�F���ыK�͕ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@�n��ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA�k�����Ɛ��C�݂ł�⑽
���ق��́A�n��ɂ��Ⴂ�͂قƂ�nj����Ȃ��B
�\�Q�@�n��ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j
�@�����F�e��ƊE�������Sparks Companies, Inc.�iSCI�j�����v
�@�@���F�l�̌ܓ��̊W�ŁA���v�ƌX�̐ςݏグ�����v���Ȃ��ꍇ������B
�i2�j�������@
�@����҂̍D�ދ����̒������@�ɂ��ẮA2000�N�Ƀl�u���X�J��w�̌����҂�
�V�J�S�ƃT���t�����V�X�R�ōs����������蒲���̌��ʂ��Q�l�ƂȂ�B����ɂ�
��A�ł��l�C�̂��钲�����@�̓o�[�x�L���[�ȂǂɌ�����Grilling���ŁA����
�ɃI�[�u���Ȃǂ𗘗p����Broiling���������A�S�̂̂X������߂�B���������u
���f���A�����̃^�C�v�ɂ��Ă��A�X�e�[�L�J�b�g���ł��l�C�������A����
�Ń��[�X�g�r�[�t�p�A�Ђ����̏��ƂȂ��Ă���B
��Grilling��Broiling
�@�Ƃ��ɕ��˔M�ɂ���āu���Ԃ��ďĂ��v�����@�ł��邪�AGrilling�͈�ʓI�Ɍ�
�O�̃o�[�x�L���[�Ȃǂ̂悤�ɒY�Ȃǂ��g���ĖԂ̏�ŏĂ����́ABroiling��
�{�̊ۏĂ���i�u���C���[�I�[�u���j�̂悤�ɕ��˔M���o���R�C���ɂ���ďĂ�
���̂Ƌ�ʂ����B
�i3�j�G�ߕϓ�
�@�H���̏���ɂ́A���C�t�X�^�C���f�����G�ߕϓ���������B��ʓI�ɒm
���Ă���ʂ�A�t����Ăɂ͌ˊO�ł̃o�[�x�L���[������ɍs���邽�߁A��
����{���̏���A�܂��A���ӍՂ̎����ɂ͎��ʒ��̏��������X��������B
�����ɂ��ẮA90�N����2001�N�R���܂ł̎l�������Ƃ̃f�[�^�ɂ��ƁA����
�ʂ��ő�ƂȂ��R�l�����ƍŏ��ƂȂ��S�l�����ŁA�P�l���������ʂ͖�P
�|���h�i��450g�j�̍�������B
���}�P�F�P�l������H���H��̋G�ߕϓ���
�i4�j�����A���ыK�͂���э\���A�n��Ȃǂɂ�����p�^�[��
�@�����K�w�ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j������ƁA�N���V���h���i��875
���~�F�P�h����125�~�j�����̊K�w�܂ł́A�����̑����ɉ����Ďx�o�z��������
����̂́A�������K�w�ł͎x�o�z���O�O���[�v�̐����������B��ʂɁA
�������ґw�́A���琅����N��w�������A�J�����Ԃ������X���ɂ��邪�A������
���r�I���Ȃ��X���ɂ��邱�Ƃ��m���Ă���B�܂��A�t�����_��w�̌�����
�̒����ɂ��A���琅���������l�قǁA���܂��܂ȐH�ނ����݂�X��������A
�H�i�ƌ��N�ւ̊S�������Ƃ����B
���}�Q�F�����K�w�ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@���ыK�͕ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA���э\�����̐����Q
�`�S�l�܂łł́A�傫�ȈႢ�������Ȃ����A�T�l�ȏ�̏ꍇ�́A�啝�ɑ�����
�Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ȃǂł̋����̃o�����[�p�b�N
�i�X�e�[�L�p�J�b�g������ʂɂ܂Ƃ߂ăp�b�N���Ă��邨�l�ł��i�j�̑��݂���
����̂Ƃ݂���B
���}�R�F���ыK�͕ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j��
�@�n��ʂ̂P�T�����苍���x�o�z�i98�N�j�ɂ��ẮA�k�����Ɛ��C�݂ł�⑽
���ق��́A�n��ɂ��Ⴂ�͂قƂ�nj����Ȃ��B
�\�Q�@�n��ʂP�T������H���x�o�z�i98�N�j
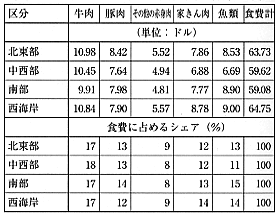 �@�����F�t�r�c�`�uMeat & Poultry Facts�v
�@�����F�t�r�c�`�uMeat & Poultry Facts�v



