III インドにおける食肉需給
一般にも知られているように、インドでは宗教の影響などにより、食肉の摂取に関してさまざまな制約がある(表5)。このため、インドではすべての加工食品に「100%ベジタブル」か「ノンベジタブル」かの表示をすることが義務付けられている(本誌海外編2006年5月号特別レポート参照)。
表5 インドにおける宗教と肉食との関係
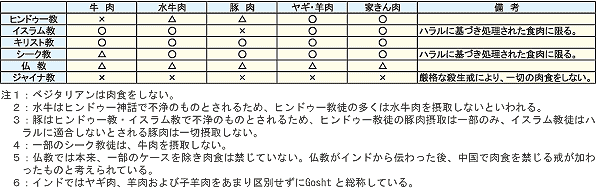
このような背景もあり、2004/05年度におけるインドの畜産総生産額1兆7,335億ルピー(約5兆円:1ルピー=2.9円)のうち、約7割弱に当たる1兆1,597億ルピー(約3兆4千億円)は「ベジタブル」に分類される乳類が占め、食肉(食肉加工品を除く)の生産額は、畜産総生産額の15.0%に当たる2,598億ルピー(約7千5百億円)となっている。また、食肉加工品を除く食肉生産額のうち、43.3%は家きん肉(1,126億ルピー=約3千3百円弱)、39.8%はマトン(1,033億ルピー=約3千億円弱:インドではヤギ肉、羊肉および子羊肉をあまり区別せず、単にGoshtと総称)が占めており、この両者で食肉生産額の8割以上に相当する。これに対し、牛肉(水牛肉などが含まれるか否かは不明)は271億ルピー(約8百億円弱)と、1.6%弱を占めるにすぎない(インド統計計画履行省中央統計局)。
1.食肉生産
(1)食肉生産量の推移
インドにおける食肉生産量は、80年代前半までは総じて低水準にあるものの、80年代後半から90年代前半にかけ、ヤギや羊など伝統的な畜種以外の食肉、つまり牛・水牛肉、豚肉および家きん肉の生産量が急増している。
この時期は、それまでの混合経済体制(二重経済体制:政府・公共団体の経済機能が拡大し、公共部門が民間部門と並んで大きな役割を果たしているような経済体制)による社会主義型経済運営の矛盾が発現し、自由経済体制に移行している時期とほぼ重なる。
図3 インドの食肉生産量の推移(枝肉ベース)
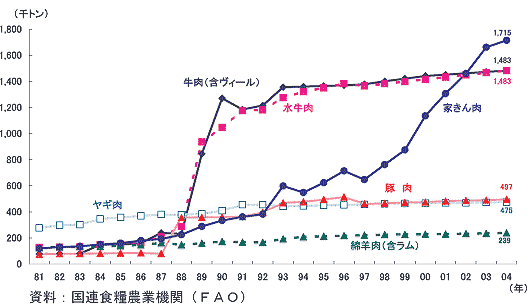
インドではかつて、穀物を食用に仕向けるのが精一杯で、家畜・家きんに給与する余裕がなかったことや所得水準の問題などもあり、もともと食肉消費は低水準で推移するにとどまっていた。そして、構造的には、食肉の消費は特定の富裕層に限られ、年間数十キログラムを消費する層と、ほとんど消費しない層とに二極化しているとされてきた。
しかし、自由経済への移行による経済発展に伴い、インドでは、いわゆる中間層が年々増加しているといわれ、国内のノンベジタリアンや外国人などによる食肉消費の伸びや食の多様化などが、食肉、特に伝統的な畜種以外の食肉生産量の伸びに拍車をかけているものと推察される。
特に家きん肉については、国内のノンベジタリアンにとって、摂取に対する宗教上の制約がほとんどなく、また、欧米品種の導入やこれを元にした改良品種を用いた大都市周辺の近代的養鶏産業の伸長や、穀物増産による飼料の供給確保などを背景としたブロイラー産業の発展に伴い、その生産量と食肉生産に占める割合は年々高まる傾向にある。
ただし、インドの食肉生産量については、国内で飼養されている家畜・家きんの頭羽数に比べ、統計上、著しく過小な数値が計上されているといわれている(表6)。
表6 インドの家畜飼養頭羽数と食肉生産量の推移
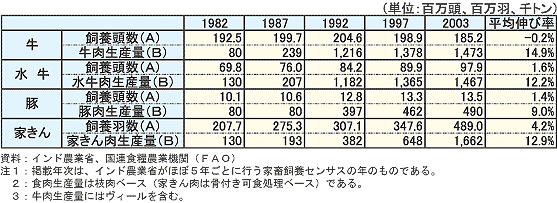
その原因としては、(1)牛や水牛をはじめ、宗教上の理由などにより、と畜や肉食に制約がある家畜があること、(2)特に90年代前半頃までのインドの食肉統計自体が、非公式に行われていると畜の数値を(推計によっても)含んでいないと思われること、(3)肉用に改良された家畜や家きんがまだ少なく、個体当たりの産肉性が低いこと、(4)ブロイラーや豚、輸出肉向けとして飼養されている水牛など一部の家畜・家きんを除き、肥育という概念がまだ乏しいことなどがあると考えられている。
表7は、公式に行われたと畜のみの数値(部分肉ベース・精肉ベースなどの別は不明)による、最近のインドの食肉生産指標を表したものである。表6の97年以降の数値と見比べても、飼養頭数に対すると畜頭羽数および公式なと畜による食肉生産量の少なさが顕著であり、個体当たりの食肉生産量は極めて低い水準にある。このうち、家きん肉以外の食肉の個体当たり食肉生産量については、インドにおける産肉性の低さが一因といわれてはいるものの、そこに示されている数値をうのみにはできない難しさがある。
表7 インドの食肉生産指標
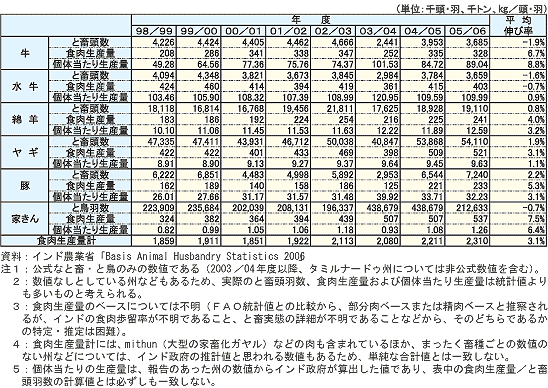
(2)畜種別食肉生産量
インド農業省によると、2005/06年度におけるインドの食肉生産量は231万トン(ベースは不明)とされている。ただし、この数値は、2003/04年度以降のタミルナードゥ州を除き、公式なと畜のみの数値であり、かつ、州などによっては数値なしとしているところも多いため、実際の食肉生産量は、統計値よりもさらに多いものと考えられる。
図4 インドの畜種別食肉生産量(2005/06年度)
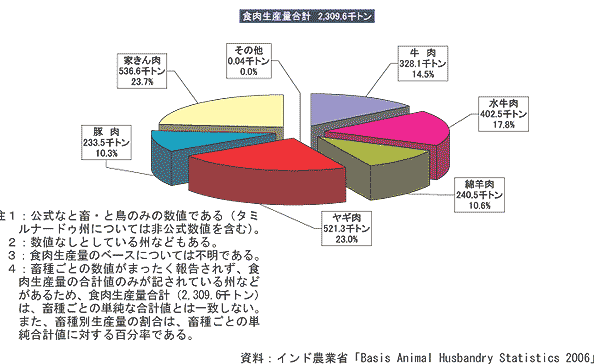
このうち、ヤギ肉と家きん肉がともに4分の1ずつを占め、次いで水牛肉が2割弱、牛肉が1割強となっている。インドでは一般に、ヤギ肉、羊肉および子羊肉をあまり区別せずにGoshtと総称することが多く、インドの伝統的な食肉であるマトンとして見た場合には、食肉生産量全体の3分の1を占める。
2.食肉消費
インドの食肉消費量に関する統計は極めて少なく、その全容を把握することは困難な部分が多い。インドでは、最近の経済成長に伴う所得水準の向上や生活の欧米化などにより、少しずつではあるが、食肉の消費量が伸びてきているといわれる。
しかし、一方では、すでに述べたように、インドにおける食肉をめぐる事項は、宗教的、思想的かつ政治的に極めてセンシティブな問題でもある。インドにおける最近の経済成長率が、数%から年によっては10%前後という高い伸び率を示しているにもかかわらず、1人当たりの年間食肉消費量は低レベルにとどまっている(表8)。
表8 日印の食肉需給の比較
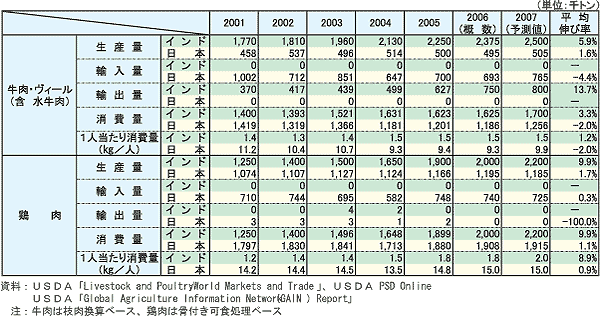
表9 主要国における1人当たりの年間食肉消費量(2005年)

米国農務省(USDA)の統計による牛肉・水牛肉および鶏肉の消費状況から考えて、Goshtや豚肉などを加えた食肉全体のインドにおける1人当たりの年間消費量は、枝肉換算ベース(鶏肉は骨付き可食ベース。以下同じ)でも、おそらく数キログラム程度であろうと推察される。前述のように、インドの食肉消費層は、どちらかというと富裕層のノンベジタリアンに偏っていると思われるが、近年の経済発展による中間層の増加や生活様式の欧米化は、今後における食肉消費の伸びに対する潜在的な可能性をうかがわせる。
しかし、インド人の8割強が宗旨とするヒンドゥー教はインド人の生活そのものであり、肉食に対する制約が簡単に免除されるものではないことなどから、今後のインドにおける食肉消費についても、ある程度の増加はするものの、その伸び率は緩やかなものにとどまるのではないかと思われる。
3.食肉の流通加工
元来、インドにおける畜産自体が自給自足型、あるいは生活のための日銭稼ぎの意味合いが強く、必ずしも組織的な生産や流通・加工を必要とするものではなかった。そのため、産業としての成立は比較的新しく、酪農・乳業など比較的組織化が進んでいる特定分野や一部の畜産関係企業などを除くと、その規模も中小から零細のものが多いといわれる。また、インドではコールドチェーンなどインフラ整備が途上段階にあり、食肉の流通については、一部を除き原則として限定的な状態にある。
また、前述したように、公式なと畜場以外でのと畜も日常的に行われているようで、現地での話によると、農村部などでは道端などでと畜・解体が行われているケースなどもあるほか、祭礼や宗教儀式で供物としてと畜されるものなども多いといわれる。
現地の関係者によると、チェンナイやベンガルール、コーチンなど南インドでは、比較的スーパーマーケットなどの量販店が発達しており、ベンガルール市内には、ショッピングモールが10カ所以上あるといわれる。こうしたスーパーマーケットなどでは、コールドチェーンによる食肉製品が店頭の冷蔵・冷凍の展示ケースに収容されており、欧米や日本などとほとんどそん色のない販売方法が採られている。
しかし、インド全体として見た場合、首都デリーも含め、一部の富裕層や外国人などを除けば、一般のインド人の食料品の購入先は、いわゆるウェットマーケットが主流である。これらウェットマーケットの食肉売り場では、売り場の裏手でヤギや鶏などがと畜され、一部には冷蔵庫や冷凍庫を所有しているところもあるようだが、その多くは、店内で常温のまま解体から精肉処理・販売までが行われ、その日のうちに売り切るという方式が採られているようである。
 |
 |
デリー市内のウェットマーケット(左)と高級スーパー内の食肉店 |
|
| 一般のインド人の主要な食料品購入先であるウェットマーケット(デリー・インドラマーケット)の食肉店(左)。価格は売り手との交渉によるが、おおよそヤギ肉が1キログラム当たり140ルピー(約406円)、鶏肉が同80ルピー(約232円)、鶏卵が1ダース当たり26ルピー(約75円)前後。 右はデリーのバサント・ロック地区の高級スーパーマーケット内にある食肉・鮮魚店。1キログラム当たりの価格は、カナダ産ベーコンが1,400ルピー(約4,060円)、マトンのモモが170ルピー(約493円)、同ボンレスモモが255ルピー(約740円)、同ミンチが180ルピー(約522円)、チキンのモモが140ルピー(約406円)、同ボンレスモモが180ルピー(約522円)、同スキンが100ルピー(約290円)など。 |
|
4.輸 出
食肉およびその加工品を含む畜産物輸出に関しては、本誌海外編2006年5月号特別レポート「巨大な可能性を秘めたインドの酪農」の「8 畜産物輸出の現状と輸出振興」に記載されているので参照されたい。
今回の調査では、2005年12月に続き農産・加工食品輸出開発機構(Agricultural and Processed Food Products
Export Development Authority:APEDA、商工省の外局)を再訪することができた。ここで新たに得られた知見などを中心に、以下に概説することとしたい。
(1)インドの食肉輸出の概況
APEDAの取扱品目である農産加工食品(林水産物を除く)の2005/06年度における輸出額は前年度比6.5%増の1,791億8千万ルピー(約5千2百億円)となった。そのうち畜産物の輸出額は、同44.6%増の356億6千万ルピー(約1千億円強)とAPEDAの全取扱品目の約2割を占め、そのシェアはここ数年増加してきている。畜産物輸出額の4分の3近く(73.7%)を水牛肉が占める。
表10 インドの畜産物輸出の推移
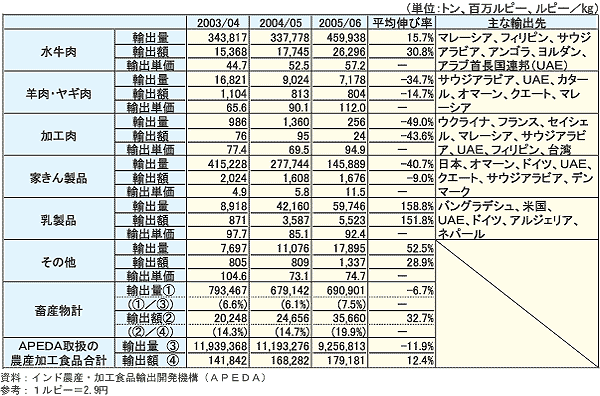
(2)食肉輸出に関する所要手続き
インドにおける輸出用食肉および食肉製品の処理場(と畜場)・加工場については、農業省、食品加工産業省、各州畜産部局(State Animal
Husbandry Development)、輸出検査評議会(Export Inspection Council)および獣医学の専門家からなるプラント登録委員会(Plant
Registration Committee)の認定を経て、APEDAに登録されていなければならない。
輸出認定に当たっては、中央政府が策定した輸出基準への適合性などが審査され、最終的に合格した場合には、APEDAから登録証明書が交付される。輸出基準については、と畜場、食肉加工場のほか、製品自体に対する事項も対象となっている。
APEDAの登録証明書の有効期限は1年間のみで、毎年更新される性格のものであるため、輸出をしようとする企業などは毎年、検査・認定を受けることが必要である。
表11 APEDA登録の食肉輸出企業
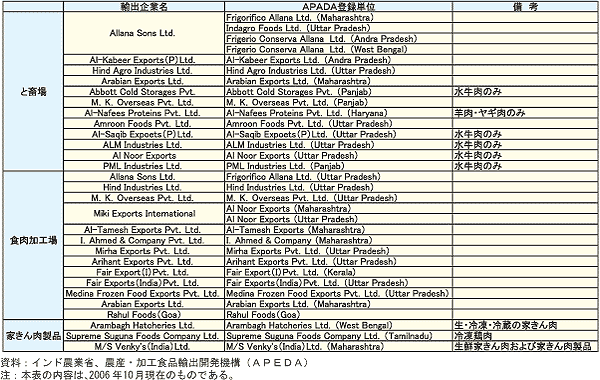
IV 食肉企業の例(MPI)
ミート・プロダクツ・オブ・インディア(Meat Products of India Ltd.:MPI)は、インド国内で牛のと畜が公式に許されている唯一の州であるケララ州最大の都市コーチンのエルナクラム地区に所在する同州政府系の食肉企業である。ブランド名は「mpi」。
宗教上の理由に加え、政治的な要素などが複雑に絡み合っていることなどもあり、インドの食肉関連産業は極めて限定的で、その従事者はイスラム教徒が多いといわれる。また、食肉関連産業に携わるのは民間企業が一般的で、州政府などが関与するところは非常に少ないとされるほか、インドのと畜場は、通常、と畜部門しかないことが多く、MPIのように、カット・加工部門があるものは例外的といわれている。
MPIは1970年、国連児童基金(UNICEF)のプログラムに基づき、デンマークの技術援助による豚のベーコン製造を目的として設立された。現在、牛肉、水牛肉、豚肉、鶏肉およびベーコン・ソーセージなどの加工品の製造を行っているほか、今後は付加価値商品として、チキンカレー、ビーフカレーなどのレトルト食品や、ランチョンミート(生の状態で食肉を缶に充てんし、密閉後に加熱して殺菌・調理を同時に行ったもの)など缶詰商品の販売も計画中であるとしている。元来、豚のベーコン製造を主目的としていたこともあって、現在も製造・加工品の約6割は豚肉由来のものであるという。
MPI幹部によると、同社では価格はあまり問題にせず、品質管理を最重視しており、これによって同社は、他の競争各社よりも25〜30%ほど高価格で売れているとのことである。同社の従業員の平均給与は1日当たり350〜400ルピー(1,015〜1,160円)、1カ月当たりでは約1万2千ルピー(約3万5千円)であり、民間企業に比べ人件費がかさんでいるという。また、同社には4名の獣医師がおり、獣医衛生および公衆衛生面をはじめ、あらゆる部門において指導を行っている。

ミート・プロダクツ・オブ・インディア(ケララ州コーチン市)
MPIは800頭規模の繁殖豚農場を所有しており、うち約450頭が母豚で、残りは後継豚と雄豚である。1カ月当たり約300頭の子豚が生産され、45日齢で契約農家に販売され、育成・肥育された後、再び同社に搬入されてと畜・加工が行われている。同社はこのほか、ウサギの繁殖舎やレンダリング施設も所有しており、例えば加工過程で除去された骨は骨粉に加工し、肥料用として販売している。
また、同社幹部からの聴き取りによると、同社の1カ月当たりの平均食肉生産量(部分肉ベース)は、牛肉・水牛肉計で5トン、豚肉20トン、鶏肉20トン程度であるという。各家畜の食肉の平均歩留まり(部分肉ベース)は、牛肉(生体重約200キログラム)および水牛肉(同約220キログラム)で約28%、ヴィール(子牛肉:同約80キログラム)で約25%、豚肉(同約100キログラム)で約55%、鶏肉(同約1.5キログラム)で約70%とされる。現在のところ輸出はしておらず、ケララ州内での販売だけでも十分であるが、将来に向けて輸出体制を整えたいとしている。
廃水はFAOのドイツ人技術者の示唆に基づき、活性汚泥法により5段階で処理され、最後は農業用水として流しており、4〜5段階の処理水では、魚の養殖ができるレベルであるという。
MPIにおける豚のと畜・加工フロー(例) (1) 搬入検査……搬入時に獣医師が生体チェック、24時間係留 (2) 生体検査……と畜直前に検査を行い、問題のないものだけをと畜 (3) スタンニング……70ボルト電気ショック (4) シャックリング(足掛け、けん垂) (5) 放 血……頚動脈切開 (6) 湯漬け……68℃、1〜3分 (7) 脱 毛 (8) と体洗浄……室温水 (9) 内臓除去……獣医師による内臓検査。望診・触診などで問題ありとされたものは、検査室で病理検査などを実施 (10) 内腔洗浄……室温水 (11) 背割り……電動のこぎり (12) 重量測定 (13) 冷蔵庫……4℃(子牛枝肉および豚枝肉は頭付き) (14) 解体・整形……No Blood,No Bone,No Fat の状態に (15) 塩 漬 (16) くん煙……アカシア材を使用 (17) ソーセージ加工……チョッパー、ミキサーはドイツ製 (18) 冷凍庫……マイナス20℃ |
V 畜産副産物の利用
1.畜産副産物利用の概況
食肉生産などの過程で産出される皮や骨、腸などの畜産副産物の生産額は、2004/05年度で340億ルピー(約986億円)に達し、牛肉(271億4千万ルピー=約787億円)や豚肉(168億2千万ルピー=約488億円)の生産額を上回っている。
特に皮については、皮革産業の原材料として、その加工従事者の雇用機会を生み出しているほか、輸出による外貨獲得の面でも大きな役を担っている。インド商工省の統計によると、2004/05年度の家畜・畜産物輸出額512億ルピー強(約1,485億円)のうち、5割強に当たる266億ルピー強(約771億円)が皮革(Leather)によって占められている。
表12 インドの畜産生産額の推移
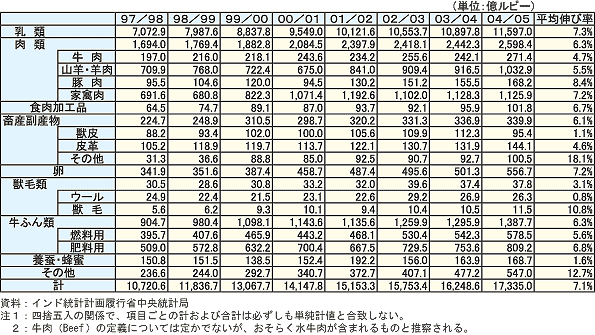
しかし、実際には、公認・非公認にかかわらず、皮や骨などを除き、と畜場の近くに血液や脂肪、くず肉などの副産物を捨てているところも少なくないといわれ、衛生面・環境面などで問題となっているほか、都市の発展・拡大により、それまで郊外や非居住区にあったと畜場などが都市部にのみ込まれることから生ずる問題なども指摘されている。
なお、ケララ州政府の関係者によると、インドにおける最大級のレンダリング業者は、国内最大の食肉生産加工業者でもあるAllana Sons Group (本社:ムンバイ)および Al Kabeer Group(本社:ハイデラバード)などである。
表13 インドにおける家畜・畜産物関連製品の輸出額の推移
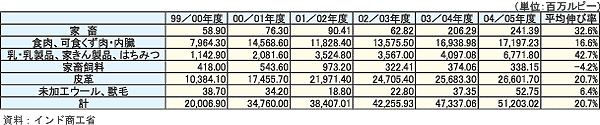
2.特定危険部位などの取り扱い
EU委員会では、各国のBSEの感染リスク(地理的BSEリスク:GBR)を以下のとおり4段階に分類している(2007年1月19日施行の5段階から3段階に簡素化されたBSEステータスのカテゴリーとは異なるので注意されたい)。
レベル1 BSE感染の可能性(BSE感染牛が1頭もしくはそれ以上存在する可能性。以下同じ)はほとんど考えられない。
2 BSE感染の可能性は小さいが、完全には排除されない。
3 BSE感染の可能性はあるが、いまだ確認されていないか、確認されても低レベルである。
4 BSE感染が高いレベルで確認されている。
現在までのところ、インドではBSEの発生は報告されていないが、インドはこのうちGBR-レベル2に分類されている。先にも述べたが、インドでは宗教と食性が密接に関係しており(表5)、特に上層階級およびそうありたいと思う階層ほど、乳・乳製品以外の動物性たんぱく質を摂取しないベジタリアンの傾向が強まるといわれている。このため、肉骨粉や骨粉、血粉などは、ゴム、茶、コショウ、バナナなどの栽培肥料としては使えるが、牧草の肥料や飼料には使うことができない。その理由は、これら畜産副産物を牧草の肥料や飼料として供した場合、その牧草や飼料を摂取した家畜から生産される乳・乳製品がノンベジタブル扱いとなり、商品価値がなくなってしまうからである。
こうした規制は、いわばインドの慣習に基づく自発的なものであり、法的な規制に基づくものではないため、食物連鎖などから見て、実質的にはインドのGBRはかなり低いと考えられるにもかかわらず、レベル2に分類される由縁となっている。
このような背景もあり、関係者からの聴き取りによると、インドでは通常、BSEフリーとの観点から、と畜場などでの特定危険部位(SRM)の除去は行われていないとされる。しかし、EU向けに輸出されるゼラチンやクラッシュボーン(粉砕骨)などは、EU規則に基づき処理され、商工省傘下の化学関連製品輸出振興委員会(Chemicals
& Allied Products Export Promotion Council:CAPEXIL)の検査を受けることとされている。
VI 畜産副産物加工企業の例(KCPL)
Kerala Chemicals and Proteins Limited(KCPL)は、日印合弁の先駆け的な存在で、ゼラチンの製造・輸出を目的として、ケララ州産業開発公社(The
Kerala State Industrial Development Corporation Ltd.:KSIDC)と日本の大手企業である新田ゼラチン株式会社(本社:大阪市浪速区)および三菱商事株式会社(本社:東京都千代田区)の出資により、1975年4月、ケララ州コーチンに設立、79年から商業生産を開始した。
1.ゼラチンの利用
動物の真皮(表皮の深層にある皮膚構造の主体)や靱帯(じんたい)、腱(けん)、骨、軟骨などに分布する結合組織中に含まれるたんぱく質であるコラーゲン(collagen=膠原(こうげん))を加熱変成して得られるものがゼラチン(gelatin)で、精製度の低い粗製品を膠(にかわ:glue)と呼んでいる。
ゼラチンの製造原料は、最初は動物の皮が主であったようだが、1814年にイギリスでオセイン(ossein:骨素=酸で無機質を溶出したもの。脱灰骨)の製造技術が確立すると、19世紀初頭には骨を原料としたゼラチン製造が工業化された。日本では、植物性の寒天や葛(くず)が古くから食品素材として用いられていたことなどもあり、工業的なゼラチン生産は20世紀に入ってからといわれている。現在、ゼラチンは食用、医療用、工業用など幅広い用途を持つ素材として重用されている。
(1) 食 用
ゼリー、プリン、ババロア、マシュマロ、グミ、焼き肉などのたれ、ヨーグルト、アイスクリーム、スープ、ハム、ソーセージ、せんべい、あられ、日本酒、ワインなど。
(2) 医療用
カプセル、錠剤、トローチ、代用血漿(けっしょう)、湿布薬、ゼラチンスポンジ(外科手術に際し局所止血に使用)など。
(3) 工業用
接着剤、画材、塗料、化粧品、フィルム、印画紙、食品模型、ビニル系ポリマー、墨、人工皮革、生コンクリート、マッチ、断熱材、サンドペーパー(砂やすり)など。
2.インドにおけるゼラチン産業
KCPL幹部によると、インドにはゼラチン工場が数カ所あり、南インドにある同社を除くと、その多くが北部から中央部に分布しているという。また、インドのゼラチン産業の製品は、大ざっぱにはその9割が輸出向け、1割が国内向けとされ、そのうち国内向けの9割以上は、医薬品などのカプセルに使われているといわれる。理屈からすれば、カプセルの服用は、動物性素材を摂取していることになるのであるが、カプセルが出来上がるまでには、何段階もの加工・製造工程を経ていることや、カプセル自体が直接に動物由来であることを連想させないこと、さらに、ベジタブル・ノンベジタブルは食品に対しての概念であることなどもあり、ベジタリアンも抵抗なくカプセルを服用している。
3.KCPLの概況
KCPLは、2つのオセイン工場と1つのゼラチン工場を有し、牛・水牛含め年間約3千5百トンのクラッシュボーン(粉砕骨)から得られる約4千4百トンのオセインを原料に、約2千2百トンのゼラチンを製造している。骨の価格は、地域や日次変動などもあるが、おおむね1トン当たり1万5千ルピー(約4万4千円)前後という。
希塩酸で脱灰したオセインは、中和のため消石灰液に浸された状態で特別なコンテナに収容されてゼラチン工場に搬入されてくる。インドではこれまでBSEの発生はなく、以前は自然死した牛・水牛の骨も業者から購入していたが、世界的なBSE発生以降は、と畜場で問題のなかった牛・水牛の骨だけを購入しているという。
図5 KCPLまでの牛・水牛の骨の流れ
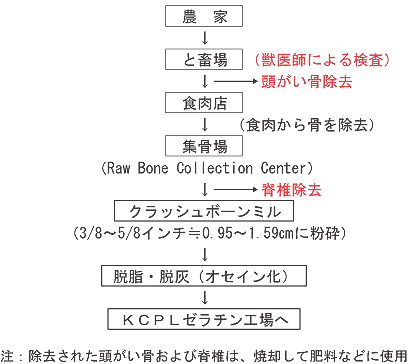
ゼラチン工場の従業員は約120人、うち約40人が管理部門、約80人が技術部門であり、3交代制の24時間操業で、機械は米国APV社製のものを使用している。
搬入されたオセインは水で洗浄された後、再脱灰のため、希塩酸でさらに前処理が行われる。前処理が終了した原料は水洗の後、温湯によって加熱し、ゼラチンの抽出が行われる。最初の抽出(1番抽出)後はゼラチン液を抜き取り、残った原料に再び温湯を張って、1番抽出のときよりも高い温度で2回目のゼラチン抽出を行う。KCPLの場合、1番抽出のときは70℃で、その後、抽出のたびに温度を上げ、95℃の7番抽出まで行っている。ゼラチンの品質は初めのものほど高く、抽出を重ねるごとに低くなる。
温湯によって抽出されたゼラチンは、コットンフィルターでろ過(primary filtration)後、イオン交換樹脂により無機イオンを除去するなど精製処理を行って純度を高める。ゼラチン抽出に際しては大量の温湯を使うため、ゼラチン液の濃度は5%程度しかないが、これを15%程度まで濃縮し、再びコットンパルプでろ過(final filtration)する。その後、30%程度の濃度になるまでさらに濃縮し、殺菌(145℃、8秒)の後、乾燥工程に送られる。
ゼラチン液は、20℃以下に冷却されるとゼリー状になるため、これをところてんのようにヌードル状に押し出し、空調された条件下でベルトコンベアの上を流しながら通風乾燥させ、適当な大きさに粉砕(first crush)する。ドライヤーの通風温度は、ベルトコンベアの流れに沿って37℃→35℃→38℃→41℃→49℃→54℃→60℃→65℃→29℃と設定されている。
1番抽出から7番抽出までのゼラチンは、それぞれ1番、2番……7番の順にラインを流れ、別々に処理されている。
乾燥後の半製品は一時的に保管され、物理・化学的な分析が行われ、それぞれユーザーの要望に応じ、粉砕、ふるい通しして抽出回次の異なるものを適宜ブレンドし、所定の形態に包装して製品とする。その後、最終的な検査を経てユーザーに出荷される。
KCPLでは、ゼラチン液のろ過に用いたコットンフィルターは、湯に解かして洗浄した後、同じくフィルターに再生して利用している。工場内のエネルギー供給には、オイルボイラーを使用しているが、最近の原油価格の高騰などから燃料費がかさみ、試験的に廃材などをたきぎとして利用し始めたという。また、最近は使える水の再利用も検討しているものの、現実には難しい面も大きいとのことであった。
工場の廃水は、希塩酸などを使っているため、中和処理などを行った後に活性汚泥法により処理している。汚泥処理については、ゼラチンかすとともに乾燥させ、必要な業者に販売しているという。また、オセイン製造の際に発生する脱灰残さであるモノリン酸は中和して消石灰を加え、第二リン酸カルシウムとした後、鶏の飼料用などとして業者に販売している。
KCPL幹部によると、同社で製造されるゼラチン製品の85%は輸出向けで、その約半分が日本へ輸出されているという。
VII ケララ州における畜産対策
ここでは、元インド食肉品質格付委員会のメンバーで、現在もケララ州技術顧問を務めるRamachandran氏から筆者らが聴き取った内容を基に、ケララ州における畜産対策の一端について概説する。
1.州境での家畜防疫措置
インドで唯一、公式に牛のと畜ができるケララ州には、年間100万頭前後の牛・水牛が州外から輸送されてくるという。そのうち約60万頭が牛、約40万頭が水牛であるといわれる。
州外から移入される牛・水牛などの家畜は、あらかじめ決められたルートで輸送され、州境に14カ所ある検問所(check points)で獣医師による検査を受け、感染症やその疑いのある家畜などは州内に入ることができない。ただし、不合格となったものをそのまま帰すことはせず、ワクチン接種など必要な措置を講じた後、24時間係留して様子を観察し、耳標装着などにより識別が可能な状態にしてから送還されている。
検問所は3交代24時間体制で、検査に合格したものは州内で開催されるキャトルフェア(1の1の(2)参照)に運ばれ、農家や家畜商、と畜場などに販売される(場合によっては契約仲買人などを通じることもある)。検問所では軽度の症状も見逃さず、州内に疾病が入らないよう厳重なチェックが行われ、相当の費用を投じているという。
2.州内畜産の産業化誘導
インドでは、畜産生産額の7割弱を占める酪農部門において、水牛が重要な位置を占めている(本誌海外編2006年5月号特別レポート参照)。現時点で最新の2003年家畜センサス(インドでは5〜6年ごとに実施)によると、ケララ州には約6万5千頭の水牛がおり、うち雄水牛が約2万4千頭、雌水牛が約4万頭となっている。
ケララ州のみならず、インドでは、生まれた雌は搾乳用として育成される一方、雄については、最低6〜8カ月間は飼料を給与する必要があり、すぐに商品として販売することができず、コスト的にも見合わないことなどから、生後間もなくと畜されてしまうことが多いといわれる。このことは、インドにおける雌水牛飼養頭数が、雄水牛の約4.5倍にも上ることからも一目瞭然であり、ケララ州で雌水牛の飼養頭数は、雄水牛の約1.7倍となっている。
ケララ州政府は、畜産の産業化育成と農家の増収対策の一環として、雄水牛を生後1カ月まで母水牛と一緒にしてほ育・育成することを奨励し、1カ月齢のものをMPIなど食肉企業が買い取って飼養し、6〜8カ月齢でと畜・商品化するよう誘導しているほか、農家の後継者育成のための対策にも知恵を絞っているという。
3.州内におけると畜場と畜産副産物処理
ケララ州内には51カ所のと畜場があるが、すべて州政府系のものである。また、州内で食肉加工品の製造が許可されているのは、前出のMPI、ケララ農業大学など3カ所のみとされる。
一方、原皮など畜産副産物を処理するレンダリング施設は、ケララ州内にはMPIとケララ農業大学に設置されている2カ所のみで、現在、コーチン市郊外に州政府が3カ所目を建設中であるという。最新の国勢調査(インドでは10年ごとに実施)である2001年時点で、ケララ州の人口密度は1平方キロメートル当たり819人と、インドの全国平均である同313人の3倍弱に上る。このため、臭気の問題など環境面で不利な条件にあるレンダリング施設の立地が難しい面もあり、畜産副産物の一部は、他州へ運ばれて処理されるものもあるという。また、ケララ州には皮革工場がないため、原皮は塩蔵された後、隣接するタミルナードゥ州へ輸送され、皮革として処理されている。
おわりに
インドはわが国とは古くからつながりのある国であり、現在でも各方面において活発な交流が行われている。国際協力銀行(JBIC)が、日本の製造業企業本社を対象に毎年実施している中期的な有望事業展開先として、インドは年を追うごとに順位を上げ、このところ2005年、2006年と2年連続で中国に次ぎ第二位となっている。また、日印包括的経済連携協定(EPA)の締結交渉も本年1月末から開始されたところである。
インドは、今でも全就業者に占める農業者の割合が約6割にも及び、国土に占める農地面積も約6割、国民の7割以上が農村部に居住し、農業が国内総生産(GDP)の2割強を占める農業大国である。中でも畜産は、農業生産額の2〜3割を占めて重要な位置付けにある。畜産生産額の7割弱は酪農部門からのものであり、食肉部門は1割強にとどまっているが、最近は生活水準の向上や洋風化などが進み、インドにおける食肉消費は増加傾向にある。
インドの食肉産業は、宗教上の理由や政治的背景、生活習慣などもあってまだ限定的であり、今後も爆発的に食肉消費が増加するとは考えにくい。しかし、インドにおいて重要な位置付けにある水牛を例にとると、搾乳をメインに飼養されている雌も、そして役用の雄も、いずれは食肉となるのであり、現に水牛肉は東南アジアや中近東、アフリカへ46万トンも輸出されている。また、最近は鶏肉の生産・消費の伸びも著しく、さまざまな角度から、インドの食肉産業の潜在能力の大きさを感じることができる。
今回の調査では、家畜の導入からその行方、さらにと畜処理から畜産副産物利用の一端までの大きな流れをつかむことはできたが、具体的に輸出されている食肉製品の種類、規格、品質、価格等については把握できなかった。世界の食料需給におけるインドのプレゼンスが高まりつつある現在、さらなる調査が望まれる。
最後に、今回の調査に関し、デリー地域における調査先の調整と同行をいただいた在インド日本国大使館の坂田一等書記官、南インドでの調査先の調整と事前の情報収集に多大なるご協力をいただいた海明インターナショナルの坂本社長、ベビー・マリン・インターナショナル社の皆様、JETROバンガロール事務所の久保木所長、そして、インド中央政府をはじめとする多くの関係者の方々にご支援をいただいたことに、この場を借りて深謝申し上げたい。
(参考資料)
1)今泉清監修:獣医公衆衛生学.東京,学窓社,1987.3
2)内澤旬子:世界屠畜紀行.大阪,解放出版社,2007.2
3)岡本幸治:インド亜大陸の変貌1990〜2000.東京,展転社,2004.1
4)小澤義博:牛海綿状脳症(BSE)の現状と問題点(その5).日本獣医学会誌第65巻第9号,東京,社団法人日本獣医学会,2003.9,pp5−12
5)今東光:毒舌仏教入門−苦楽は一つなり.東京,祥伝社,1990.8
6)社団法人畜産技術協会:平成4年度畜産技術協力推進事業報告書「インド畜産現地調査報告書」.東京,1993.5
7)社団法人日本畜産学会編:新編畜産用語事典.東京,養賢堂,2001.5
8)獣医学大辞典編集委員会編:獣医学大辞典.東京,チクサン出版,1995.2
9)瀬戸内寂聴:釈迦.東京,新潮社,2005.11
10)道免昭仁、坂西裕介:ドイツにおけるBSE発生後の食肉処理施設の状況.「畜産の情報」海外編 平成18年6月号(NO.200),東京,独立行政法人農畜産業振興機構,2006.5,pp46−61
11)長谷川敦、谷口 清:巨大な可能性を秘めたインドの酪農.「畜産の情報」海外編 平成18年5月号(NO.199),東京,独立行政法人農畜産業振興機構,2006.4,pp44−77
12)森本達雄:ヒンドゥー教―インドの聖と俗.東京,中央公論新社,2005.6
13)Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority,Department
of Commerce,Ministry of Commerce & Industry,Government of India:Export Statistics
For Agro & Food Products(India 2004−2005).New Delhi,2005
14)Department of Animal Husbandry,Dairying & Fisheries,Ministry of
Agriculture,Government of India:Basic Animal Husbandry Statistics 2006.New
Delhi
15)Department of Animal Husbandry,Dairying & Fisheries,Ministry of
Agriculture,Government of India:Number of Veterinary Institutions and Infrastructure
Data of Animal Husbandry(Year-2006).New Delhi
16)独立行政法人日本貿易振興機構:海外のビジネス情報>国・地域別情報>アジア>インド>貿易管理制度(http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/
in/trade_02/)