| �@�u���ɗD�����{�Y�v�A�u���S�����m�ۂ��ꂽ���R�Ȓ{���v�Ȃǂ��������҂���Ă���ɂ�������炸�A���q�^�{�Y�̑�\�i�ł����茧�k��R�n�𒆐S�Ƃ������{�Z�p���̋ꋫ�͐[�܂�A���ܑ��S�̊�@�̒��ɂ���B�����A�Y�n��K�˂Ă݂�ƁA���Y�҂�W�Ǝ҂̕��X�́A�k��R�n�̕��y�ɗn�����Z�p������Ɍւ�Ǝ��M�������Ă���A�ꋫ�ɋ����邱�ƂȂ��V�������g�݂Ƀ`�������W���鑧����������ꂽ�B�Z�p������̋��_�ł����茧���ɌS��̍ŋ߂̏ɂ��ă��|�[�g�������B
���{�Z�p���Ƃ�
�@���{�Z�p���͓��{�ݗ�����N���Ƃ���4��̘a���i���јa��A���јa��A���p�a��A���{�Z�p��j�̈�ŁA���јa��ƂƂ��ɕ��q�����ɗD��Ă��邱�ƂŒm���Ă���B�ݗ��̓암���i�������j�ɖ������ɊO���̃V���[�g�z�[������|�����킹�ĉ��ǂ��ꂽ���̂ŁA1957�N�ɕi��o�^����Ă���B
�@���{�n��͋��암�˂̊�茧�k�𒆐S�ɏH�c���A�X���A�k�C���Ȃǂł���B�����̒n��͂��Ă̔n�Y�n�������A�n�Y����̖q�����ӂ̗ђn�𗘗p�����ĎR�~�������̕��q�^���炪�������Ă����B��t���́u�܂����v�ƌĂ����q�n�ł̎��R��z�ŁA3�`5������Ɏq�������܂�A�ꋍ�ƂƂ��ɏH�܂ŕ��q�琬�����B���q�n�͖q��g���ɂ���ĊǗ�����Ă���A�g���ɂ�鋤�����q�ƂȂ��Ă���B�H�ɗ��ɍ~�낳��āA���f���Ƃ��Ĕ̔������B�����Ԃ͂��̌�14�`18�J���ŁA�e�����ƍ����ň�Ă�ꐶ��22�`26�J���Ŏd�グ��B
�@���{�Z�p��̓����͈����͂Ȃ��A���q�ˑ��̑e���������^�O���X�t�F�b�h�Ƃ��Ă͑����ȉ\��������Ƃ���Ă���B�������A�Ԑg���n�ŁA���јa���̂悤�ȃT�V������ɂ����A�����a���s�ꂩ��͕ߏo����Ă����B�����̗A�����R���i91�N�j�ȍ~�͗A�������Ƃ̋����i��Ƃ���A�̔��ʂł̍���������Ă���B
�W�O�N��|���{�Z�p�ċ��̎�
�@���{�Z�p���̎��{��70�N��܂ł͂قډ����ł��������A80�N�㒆�������̊����������o�����B����Γ��{�Z�p���ċ��̎��ł������B���R�������������{�`�Ԃ̗D�ʐ��ɒ��ڂ����Y�������̊J�����ċ��E�������̎�ȓ��e�������B
�@��ڂ������̂������𒆐S�ɓW�J���Ă����L�@�_�Y���̔��c�̂́u��n������v�ƎR�`���i��Ɨאځj�̒�g�������B�u��n������v�͂���ׂ��{�Y�̎p����q��̂̓��{�Z�p���Ɍ��������A�R�`���ɂ�������{�Z�p��������x�����A�ɐB�݂̂̎Y�n�ɔ��o�c����āA������ё̐����\�z���A���O�_��ɂ��ꓪ���������Ŕ������A�Ǝ��̐������H���o�āA�Đ��Y�\�Ȍ_�i�őS���ʂ�����҂Ɍv��I�ɋ�������Ƃ����V�X�e�����m�������B
�@���˂Ă���Z�p���U����}�肽���ƍl���Ă�����茧�́A�R�`���Ɓu��n������v�̒�g�����ɒ��ڂ��A�܂���ڊo�܂������W�𐋂��������n�搶���ɌĂт����āA���̕����𑼂̎�v�Y�n�ɂ��L�����B�n����ɔɐB�E�琬�E����ѐ��Y�̐�������A���蒬���Ɠ��萶�����Ƃ̒�g�W�����ԂƂ��������ł���B��ɂ��ẮA�����́u�����s�������v�ƁA��Ɂu�������܃R�[�v�����v�Ƃ̒�g�ƂȂ����B
�@��������������A���̐V�����̃|�C���g�́A(1)����̐����ȂǂƂ̒�g�A(2)�n������A(3)�n�����ѐ��Y�̐��̊m���A(4)�ꓪ�����A(5)�\������ƌ_�������i�A�Ȃǂł������B
|
�}1�@���{�Z�p��̔ɐB�����{��
|
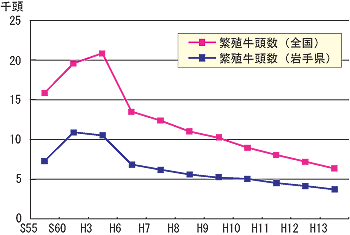 |
| �����F�ƒ{���NJW�����i�ƒ{���ǎ��ƒc�E�����{�Y��j�Ȃ� |
�@���̐V�����Ɏx�����āA��茧�̓��{�Z�p���Y�n�́A�ɐB�E�琬�����̎Y�n���������|���鑍����ѐ��Y�n�ւ̓]�����}��ꂽ�B���{�����͑����ɓ]���A85�N���Ƀs�[�N���}���A�S���ŔɐB��19,598���A��狍13,815���A�v33,413���i��茧�F�ɐB��10,910���A��狍5,287���A�v16,197���j�ƂȂ����B
�@���̎����ɕ��q�q��̗l�q���傫���ς�����B��ɂ��q�ׂ��悤�ɓ��{�Z�p���̎��{�q��͎�Ƃ��Ă��Ă̔n�Y�q��ł������B�k��R�n�͐�O������̎����ɖؒY�̑�Y�n�Ƃ��Ċ�����т����Ƃ��������B�s���A�s�s�����҂̐����G�l���M�[�����K�X��Ζ��ɂȂ�܂ł̈ꎞ���A���ؒY�͈ꐢ���r�����B�Y�R�Ƃ��Ĕ��̂��ꂽ�Ւn���Z�p���̕��q�q��Ƃ��ė��p���ꂽ�Ƃ�����������B��������쑐�n�A�a�ђn�A�M�n�ȂǂŁA�n�`���ɂ͎肪�������Ă��炸�A���R���엿�ł������B
�@���������ݗ��q��ƍL�t���і��Ώۂ�70�N��ɂ͍��c�k��R�n�J�����n�����A���̈�Ƃ��Ėq����ǁ��l�H���n���������g�܂ꂽ�B80�N�ォ��90�N��ɂ͖쑐�n�q��̑����͐l�H���n�ɑ���ւ���ꂽ�B�k�ρA�{��Ȃǂ̋@�B��Ƃ��\�Ȃ悤�ɒn�`��������x���ς���A�y�n�͖q���n�Ƃ��čk�ϑ�������A�{�삳��A�q���̎�q��������A���N�̉��w�엿�{��ƒ���I�ȑ��n�X�V���`���Â���ꂽ�B�q��͎��R�Ȃ��̂ł���A���̊Ǘ��o��͂قڂ����A�ƌ�������A���̐��Y�͂͑��������A���̑���ɖq����ǂ̕��S���̎x�����A���N�̊Ǘ��o��ȂǁA�q������Ȃ�̌o��̂����鑶�݂ƂȂ����B
|
�}2�@���{�Z�p��̔�狍���{��
|
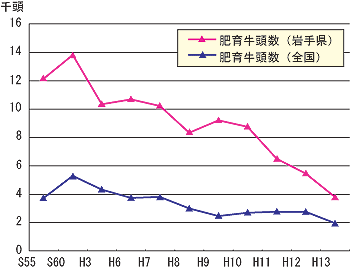 |
|
�����F�ƒ{���NJW�����i�ƒ{���ǎ��ƒc�E�����{�Y��j�Ȃ� |
�����A�����R���Ǝ��{��������
|
�}3�@�q�����i�̐��ځi�S�_��茧�{���j
|
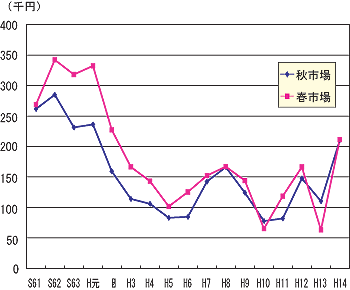 |
�@�����A�Z�p���ċ��E�������͂��̊ԂɏI���A�������R���i91�N�j�ȍ~�͗A�����Ƃ̋����i��Ƃ���A�Z�p�����{�̎Љ�I���͋ɂ߂Č��������̂ƂȂ����B
�@���{�Z�p���̉ƒ{�s��̉��i�i��茧�j�́A87�N���s�[�N�ŁA�t�s�ꂪ342,229�~�A�H�s�ꂪ284,936�~�ŁA�قڂ��̐�����89�N�܂ő������B�������A90�N�ɂ͖\�����A�Ȍ�01�N�܂ł͏t�H�Ƃ���10���~�O��̒ᐅ���Ōo�܂��A02�N��BSE���������ďt�H�Ƃ���21���~��ƂȂ����B��茧���̉ƒ{�s��ւ̏�ꓪ����91�N���s�[�N��5,695���A���̌�͈�т��Č������A02�N�ɂ�815���ɂ܂ŗ�������ł���B95�N������͍��јa��Ƃ�F1�̏o�ׂ��n�܂�A02�N�ɂ�1,286�������o�ׂ���Ă���B
�@��狍�̎}���̊i�t����2�������ق�80���A1������15���ʂň����͂Ȃ����A���i�͈����B���ώ}�����i��91�N���Z�p1,043�~�^�s�A���Y1,116�~�A����2,178�~�A01�N�͒Z�p797�~�A���Y758�~�A����1,572�~�ł������B
�@���̂悤�ȋ������i�̉��������ڂ̌����ƂȂ��āA���{�Z�p���̎��{�����͌������A2001�N�ɂ͑S���ŔɐB��6,343���A��狍3,794���A�v10,137���i��茧�F�ɐB��3,704���A��狍1,955���A�v5,659���j�ƂȂ��Ă��܂����B85�N�Δ�ł݂�ƔɐB����32���i��茧33���j�A��狍��27���i��36���j�A�S��30���i��35���j�Ƃ�������Ή�œI�����ł���B
�@���̏���茧���̎�v�Y�n�i��A�R�`���A��䑺�A���㒬�A�ʎR���A��@�����j�ɂ��āA91�N��02�N�̑Δ�Ō���ƁA�ɐB����6,088������2,584����42���A��狍��2147������1,279����60���A�S�̂�8,235������3,863����47���ƂȂ��Ă���B��v�Y�n�ł��S�̂Ɠ��l�ɓ��������̒��ɂ��邪�A�ڂ����݂�ΔɐB���̌��������͎�v�Y�n�Ƃ��̑��Y�n�̓����ɑ傫�ȈႢ�͂Ȃ����A��狍�̌����ɂ��Ă͎�v�Y�n�ɂ����闎�����݂͑��ΓI�ɏ��������Ƃ��m�F�ł���B��v�Y�n�ɂ����Ă�80�N��Ɋm�������Y�������ƒn�����ѐ��Y�̐��������@�\���A����������a�炰�Ă���Ɛ��@�����̂ł���B
�@�����n��̏ꍇ��91�N�ɂ͔ɐB��1,233���A��狍518���A�v1,751���ł��������̂��A02�N�ɂ͔ɐB��567���A��狍470���A�v1,037���ƂȂ��Ă���B�ɐB��46���A��狍91���A�S��59���Ƃ���������Ԃł���B�Y�������ɂ��Z�p�����{�̒��S�n�ł���R�`���̏ꍇ�͔ɐB����1,044������456����44���A��狍��678������612����90���A�S�̂�62���ƂȂ��Ă���B�Ƃ��낪��Ɨאڂ����v�Y�n�̐�䑺�ł́A�ɐB����1,286������267����21���A��狍��467���������̂�0���ƂȂ�A�S�̂ł�15���ŁA�����ʂ��ŏ�ԂƂȂ��Ă���B��䑺�ł͍s���A�_���A�_�Ƃ���̂ƂȂ��Ėq��g�������{�݂��Ǘ��A�^�c����ȂǒZ�p���֘A�̎Y�Ƒ̐����m�����Ă����̂����A00�N�ɂ��̌o�c���j�]���A��炩��̊��S�P�ނƂȂ��Ă��܂����̂ł���B
�Y�������̗h�邬
 |
�@�ȏ�T�ς����悤�ɁA���{�Z�p���͖k��R�n�̕��y�ɖ��������`���I�{�Y�Ƃ��đ������Ă������A80�N��ɖq�엘�p�̕��q�����̗D�ʐ��ɒ��ڂ����Y�������̊J�����y�ɂ���āA�V���Ȑ���オ�肪���o���ꂽ�B�������A���̌�̋����A�����R���̍r�g�̒��ŁA���������Y�����������ł͐��Y�̐����ێ��ł����A���܁A���ł����\�������悤�ȋꋫ�Ɋׂ��Ă���̂ł���B
�@�������������ŊJ���鏈���́A�Y�������̍X�Ȃ鋭���ƍ��x���Ƃ������ƂɂȂ�̂����A���͂��̎Y���������̂ɂ�����I�ȗh�邬������n�߂Ă���̂ł���B��䑺�̔��Z���^�[���|�Y���A�����̒Z�p�����Y����ł������Ƃ͐�ɐG�ꂽ���A��ɂ��Ă��A02�N�ɂ͒����̎q���s��͕��ƂȂ����B�����q���s��́A�Y�������̊�ՂƂȂ�ɐB�_�ƂƔ��_�Ƃ���g��������ё̐�������d�v�Ȏd�g�݂ł��������A�o�ד����̌����̂��ߊJ�݂��ێ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ł���B�������A�n���ƒ{�s�ꂪ�Ȃ��Ă͊�Ƃ��Ă̒Z�p���̈�ѐ��Y�V�X�e���͂��蓾�Ȃ��B�����ŁA�n���ƒ{�s��ɑ�����̂Ƃ��āA�����̔ɐB�_�ƂƔ��_�Ƃ̒�g�ɂ��]���w���������l�Ď��{����Ă���B������i�͐����s��̕��ω��i���K�C�h���C���Ƃ����W�c���Ύ���ł���B
�@����Ɏ�͏o�א�ł������u�������܃R�[�v�v�Ƃ̎Y�������03�N�x�Ŏ���߂ƂȂ��Ă��܂����B�����Ƃ̎Y����88�N����J�n����A�����̎�������łȂ��A�_�Ƃ͍�ʂ̏���҂̉ƒ��K�₵�A����҂͊�̔_�Ƃƕ��q�q���K�˂�Ƃ������𗬂��ςݏd�˂��Ă����B���̌o�߂̒��ŁA��ɂ�������{�Z�p���̎��{�Ǘ��͉��P�[�����A����҂̋����ɂ��Ă̈ӎ����ς���Ă������B�Z�p���̗ǂ������L������҂ɂȂ��Ȃ���������Ȃ��A���i��i���Ȃǂɂ��ĎY�n�Ɛ����̈ӌ����Ȃ��Ȃ�����Ȃ��ȂǓ�������܂݂Ȃ������Ɓu�������܃R�[�v�v�̎Y���������Ȃ蒆�~�ƂȂ�悤�ȏł͂Ȃ������B
�@�Y������̒��~�̗��R�͂����ς�u�������܃R�[�v�v�̐����H���̕ύX�ɂ������B�u�������܃R�[�v�v�́u�R�[�v�Ƃ����傤�v�Ǝ����㍇�����A����Ɏ�s���̑���4�����i�u���R�[�v�v�A�u���炫�R�[�v�v�A�u�Ƃ����R�[�v�v�A�u�R�[�v����܁v�j�Ƌ������ƒ�g�����ԂƂ���������I�������̂ł���B�u�R�[�v�l�b�g���ƘA���v�̔��{�I�ȍĕҋ����ł���B���ƍ����̓X�P�[�������b�g�̒Nj��ɂ�鐶�����Ƃ̐����c�肪�ő�̃��`�[�t�ł���A��ʁE�����E�K�i���̕����֏��i����͑啝�ɕύX����Ă������B
�@�u�������܃R�[�v�v���������~�ɂ�������Ė��Ƃ��ꂽ�_�͉��i�ƃ��b�g�ł������B���i�ɂ��Ă͏]����800�`1,000�~�^kg�����Ŏ������Ă������A���f�����i�̍����̂��߁A���̉��i�����ł͔��o�c���ێ��ł��Ȃ����߁A02�N�x�ɒ����͒l�グ��v�����A03�N�x�͋��c�̌���1,200�~�Ƃ������ƂɂȂ����B�������A�u�������܃R�[�v�v���͂��̉��i�ł̎���̌p���͖����ł���Ƃ��āA���i��������������p���̏����Ƃ��Ă����B�܂��A���b�g�ɂ��Ă��]���͔N��120�����炢�̎���ł��������A�g�勭�����ꂽ�R�[�v�l�b�g�Ƃ��Ă͂���ł̓��b�g������������A�啝�ȃ��b�g�g�傪�K�v���Ǝ咣�����Ƃ����B���b�g�g��̋K�͖͂�������Ȃ������Ƃ̂��Ƃ����A�܂��͂قڔ{���x�Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B
�@������~�͌����c�̌��ʂł���A�o���Ƃ����~�͂�ނȂ��Ɣ[�����Ă̌��_�ł������B�������A�c�O�Ȃ��Ƃ͂��̌��v���Z�X�ł́A��̒Z�p�����Y���ǂ̂悤�Ɉێ����W�����邩�ɂ��Ă͘_�c�̑ΏۂƂ͂Ȃ炸�A�܂��A���N���̒Z�p����H�x���Ă�������҂̓o��Q���͂Ȃ������_�ł���B���̎Y���������g�D�Ƒg�D�̏��i����Ƃ����g�g�݂����Ȃ������Ƃ������Ƃł��낤�B
��̓��{�Z�p�����Y�̐V�W�J
�@�u�������܃R�[�v�v�Ƃ̎�����~�͊�̒Z�p�����Y�̍�����˂��������˂Ȃ��o�����ł������B02�N�x�̏ꍇ�́u�������܃R�[�v�v120���A���̐H�����50���A��~�[�g�Z���^�[40���A��ʎs��̔�100���A�v310���Ƃ����̔����тł���A�u�������܃R�[�v�v�䗦��38�����߂Ă���B�ő�̂��������肵���������������Ƃ͒Z�p���֘A�̒n��Y�ƂɍŌ�̂Ƃǂ߂��h���悤�ȕ����ʂ�̊�@�ł������B
�@���������ˑR�̊�@�ɑ��āA��̒Z�p�����Y�҂Ƃ�����x������s����_�ƒc�̂́A�Z�p�����Y����̓P�ނƂ��������ł͂Ȃ��A�Z�p�����Y�̓��������ߒ����A��������ǂ��[�߁A�L��������Ŋ�{�헪�̍č\�z��}�����B������h���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��悤�����A�S�̂Ƃ��đO�����Ȉӗ~���Y�n�ɂ͖����Ă����B����܂Ƃ߂��헪�����u�Z�p�U����ɂ��Ă̍l�����v�̖����ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
�@�u���{�Z�p��̓��ِ����痬�ʔ̔�����傫�ȉۑ�Ƃ���邪�A������ɂ���A�Y�n�Ƃ��Ĉ�v�c�����Ď��g�߂A���܂��܂ȉۑ�����z���A���{�Z�p��̐����ȕ]���邱�Ƃ͏\���\�ƍl���Ă���A���Y�҂̊F����̋����ӎu���āA���Ƃ��Ă������̑Ή�������l���ł���v
�@��1�̉ۑ�́A�u�������܃R�[�v�v�ɑ���V���������̊J��ł������B�����ł̊�{�I�ȍl�����́A�Z�p���̗ǂ��Ɛ��Y�̈ێ��p�������̊m�ۂɂ��Ă��[���������Ă��炦������������o���Ƃ������Ƃł������B�u�������܃R�[�v�v�Ƃ̎Y�����Ƃ̋��P�́A�Z�p���̔̔���P�Ȃ鏤�i����ɏI��点���̂ł͒Z�p�����Y�͈ێ����W�������Ȃ��Ƃ������Ƃł������B
�@�K���Ȃ��Ƃ�04�N�x����́A�L�@�_�Y�����̑�z��Ђł���u��ł�����ځ[��v�Ƃ̎������̓�����邱�ƂɂȂ����B
�����S���̍������Y�����ւ̈ڍs
�@���̉ۑ�́A���̐V�������������m�ۂ��A���肳���邽�߂̕���̊m���ł���B���̓_�ɂ��đO�f�́u�Z�p�U����ɂ��Ă̍l�����v�i��j�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
�@�u���{�Z�p��̉��l���悭�������A���Y�\�ȉ��i�ł̎��������\�ł���̂́A��ł�����ځ[��A��n������ȂǁA�����ɊS�������A���A���S�E���S�Ȕ_�Y����^���ɋ��߂Ă������Ғc�̂�H���X�E���X�g�����Ȃǂł���B�i�����j
�@���S�E���S�Ȕ_�Y�������߂Ă���Ƃ���ł́A
�@(1)�G�T����`�q�g�݊����łȂ�����
�@(2)��玞�̑e�����̑���
�@(3)�ł��邾���_��≻�w�엿�Ȃǂ��g��Ȃ�����
�@�Ȃǂ��ɑ�ς�������Ă���B�i�����j
�@�܂��A�ŋ߁A�����̃g���[�T�r���e�B�@���������A��{�I�ȍl�����łǂ̂悤�Ȑ��Y���@�����Ă��邩�ɂ��āA���ɊS�������B�]���āA��{�I�Ȑ��Y�����ɂƂǂ܂炸�A���̓��{�Z�p��̐��Y�ɂ��Ă̍l�����ƁA����ɑΉ�����Ǝ��̐��Y����ł��邾���������肷��K�v������v |
�@���̂悤�ȍl�����Ɋ�Â��āA��`�q�g�݊����̂ł͂Ȃ��g�E�����R�V�inonGMO�R�[���j�̓����A�_��≻�w�엿���g��Ȃ������������Y�Ȃǂ̎��݂��J�n����Ă���B���Z�p�ɂ��ẮA���{�Z�p��ł��T�V�����߂č��јa��Ɨގ������Z�����������^�ɌX���Ă������Ƃ��������A�e���������̔��Z�p�̊m�����ڎw����Ă���B�R�X�g���⎔�{�E�͔|�Z�p�̊m���ȂǂȂ��ۑ�͎c����Ă��邪�A�����悻�������������ɐ��Y�̐����}���Ɉڍs���Ă�������ɂȂ��Ă���悤�ł������B�����ɗL�@�{�Y�ւ̃`�������W�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��悤�����A���̕����������ӎ����Ȃ���A�P�Ȃ���q�{�Y���������ł͂Ȃ����{���e�̋ᖡ�ƍ��x�����ڎw����n�߂Ă���B
�q�엘�p�̌�����
�@��ɏq�ׂ��悤�ɁA���{�Z�p���̕��q�n�́A���Ă͍ݗ��q��A�a�ђn�A�M�n�Ȃǂ���A���q�`�ԂƂ��Ă͂ނ���ъԕ��q�ƈʒu�Â�������̂ł������B�����̕��q�n�̑e�������Y���́A���Ǒ��n�قǍ����͂Ȃ��A���������ĒP�ʖʐϓ�����̋����{�����������͂Ȃ������B���������k��R�n�̕��y�Ɉˑ������ݗ��{�Y�́A�����ړ���O��Ƃ��Đ��Y�����������Ƃ���ߑ�{�Y�Ƃ͓���܂��A����́u�Y�Ƃł͂Ȃ��L�m�R���̂悤�Ȃ��̂��v�Ƃ���A�u�L�m�R���{�Y�v�Ƃ������������ׂ̓I�j���A���X�Ō���Ă����B
�@����Ɏ��c���ꂽ�悤�ȒZ�p�����Y�������ł�����Ƀ}�b�`�����`�ɔ��W���������B1980�N�㍠�ɁA�k��R�n�����J���Ɋ֘A�����q����ǁA���n�������L�͂ɐi�߂�ꂽ�w�i�ɂ͂��������v�����������̂��낤�B�������ꂽ���n�́A�тƖq��Ǝ��R���Z��������ł͂Ȃ��A�т⎩�R�ƕ������ǂ��ꂽ�A�������Y���u�Ƃ��Ă̕��q���n�ł������B�������n�͎��ӂ�ђn�Ɉ͂܂�Ă���A���n����������Ȃ������ݗ��q����c����Ă���̂ŁA�Z�p���̕��q���n�����S�ɐl�H���n�����ꂽ�Ƃ�����ł͂Ȃ����A�ݗ��q��ł̕��q�Ƃ͂��Ȃ�قȂ������̂ƂȂ��Ă���B
�@�����������q���n�̌���Ɋւ��āA�����̎��_����݂Ă������̖��_���ӎ������悤�ɂȂ��Ă���B
�@��1�͈ێ��o��̖��ł���B���ǖq��̑����͍��L�ѓ��ɂ�����ؒn�_��ƂȂ��Ă���B�����ɂ͌Â�����̓���p���͂������Ǝv����̂����A�k�㑍���J���ł͎��ƃV�X�e���Ƃ��č��L�т̏ꍇ�ɂ͒��ݎɐ�ւ���ꂵ�Ă܂����悤�ŁA���N���Ȃ葽�z�̎g�p���i�`�q��g���̏ꍇ��50�w�N�^�[���Œn��͔N��76���~�j�����Ɏx����Ȃ���Ȃ炸�A�܂��A���ݎ؏I�����ɂ͌���A���Ȃ킿�ђn�������`���Â����Ă���B�����������ݎ؊W�̎����͂��Ȃ蕉�S�ƂȂ��Ă���B
�@���̒n��́u���R�Ԓn�擙���ڎx�����x�v�̑Ώےn��ł���A�X�Βn�̓c���ɂ��Ắu�W������v�ŁA�q��ɂ��Ă͖q��g�����Ƃ́u�ʋ���v�ɂ�钼�ڎx�������Ă���B��ł́u�W������v��12�W���A63�w�N�^�[���A669���~�A�q��g�����́u�ʋ���v��5�g���A468�w�N�^�[���A2,494���~�̌�t�ł������i02�N�x�j�B���L�ї��p�̖q��ɂ��Ă͂��̌�t���Œn�オ�d���Ă���B�n���]���Ƃ��Ắu���ڎx�����x�ɏ������Ă���v�Ƃ������̂����A�q�엘�p�ɂ���č��L�ъǗ����Ȃ���Ă���̂�����A�{���Ȃ���͒n��̎擾�ł͂Ȃ��A�ނ���Ǘ��ϑ���̎x���������ׂ��P�[�X�ł͂Ȃ��̂��B�k��R�n�́A�N�ɂ���āA�ǂ̂悤�ɕۑS�Ǘ������ׂ��Ȃ̂��A���̔�p�͂ǂ̂悤�ɘd����ׂ��Ȃ̂��ɂ��Ă̗��j��k���Ă̍Č������K�v���Ǝv����B
�@��2�͑��n�Ǘ��̂�����̖��ł���B�u�ݗ��q��������Y���̍����l�H���n�v�u�g���N�^�[���̋@�B���g����ɌX�̑��n�v���ꂪ�q����ǂ̃R���Z�v�g�ł������B�������A5�`7�N���̑��n�X�V�͌����ɂ͎��s������A���N�̉��w�엿�{��͘J�͓I�ɂ��o��I�ɂ����S���傫���B���n�X�V�̓G���[�W�����i�y��N�H�j�̖����N�����₷���B���w�엿�ɂ�鐅�n���ׂ̖�������B����ɑ��n���̎��ђn�䗦���Ⴂ���߁A���l�ȐH���ێ��؉A�̋x�ݏ�m�ۓ��ɂ�鋍�̌��N�ێ��̖ʂł̖��_���w�E����Ă���B�����������ʼn��Ǒ��n���������x���R�q��ւ̉�A�Ƃ������ӎ����n���ɂ͉萶������悤�ł������B
�@��3�͒n��̎��R�i�ϕۑS�ɌW�����ł���B�k��R�n�̎��R�i�ς́A�L�t���тƒZ�p�����q�q��ɂ���č\������Ă����B�L��ȍݗ��q��ŁA�������͑���Ă�H�ׂȂ���������i�ς��`�����A�ۑS���Ă����B�t��ɂ̓J�^�N���╟�������炫�A�t���[�܂�Ɛ��m�Ԃ�c�c�W���炫�A�H�ɂ͑N�₩�ȍg�t�ŎR��������i�ς́A�L��Ȗq��ł̒Z�p�����q�ɂ���č��o���ꂽ�`���I�ȁu�����i�ρv�ł������B�Ƃ��낪�l�H���n���ɂ���āA�ђn�Ƒ��n����������A���̕��q�͉��Ǒ��n�ɏW�������悤�ɂȂ�ƁA����ɂ��Ă̖q��i�ς͎����Ă��܂��B
�@���Ǒ��n�͂���Ƃ��Ĕے�͂��Ȃ����A���q��Ղ����Ǒ��n�����ɍi�荞�ނ̂ł͂Ȃ��A�ݗ��q��̗��p�����������A�q��i�ς��ێ����Ă��������Ƃ���n���̎��g�݂��L�������B
 |
�k��R�n�̕��y�ƕ�炵��������
�@����̓W�J�Ɋւ���ȏ�3�̐헪�́A���R�Ƌ��ɂ���Z�p���Ƃ������i�R���Z�v�g���e�̍��x���A�����������Ƃɂ���Ď��R��n���Ă�Ƃ����g�g�݂̍Č��Ƃ������̂ł������B�������A���̕��X�́A�Z�p�������Ő����Ă����ł��Ȃ��A�q��i�ς�������ړI���Ƃ��������킯�ł��Ȃ��B���̕��X�͉��߂ĂȂ����������̂��A�Ȃ��q����ɂ���̂��A����ɂ͂Ȃ����ŕ�炵�����Ă����̂���Â��ɖ₢��������悤�Ɋ�����ꂽ�B���̓����͖k��R�n�̕��y�ƕ�炵��������Ƃ������ƂȂ̂��낤�B���ɂ͊��̕��y������A��炵��������B���̕��y�ƕ�炵�����������͍D���Ȃ̂��B�L��Ȗq��ł̒Z�p���̎��{�����̕�炵���̈�Ȃ̂��B����Ȑ��������������畷�����Ă���悤�������B
�@��̒n��Y�ƐU���̐헪�Ƃ��ẮA�Z�p���U�����܂ޒn�掑���̌@��N�����Ə��i�����d�_�I�Ɏ��g�܂�Ă���B�s���o���̑�O�Z�N�^�[�u��Y�ƊJ���v�ł́u���̐��v�̑S���̔����肪���āA������x�̐��������߂Ă���B�Z�p���ɂ��Ă͎Y���̔������łȂ��A�n���ł̉��H�A�n������A�����Ȃǂł̏���g��ȂǑ��ʓI�Ȏ��g�݂��L�����Ă���B
�@�������A���Ƃ����Ă����̕��y�ƕ�炵�̍����ɂ������̂̓q�G�A�L�r�A�����R�V�A�G�S�}�Ȃǂ̎G���Ƒ哤�A�����Ȃǂ̓��ނ��낤�B�G���Ȃǎ���x�ꂾ�Ƃ̕����̒��ł��A���̂��N��肽���͌X�Δ��ɏ������G���ⓤ��n�����葱���Ă����B���̉c�݂�r�₦��������ɂ������A���N��肽�������܂ł���������_�Ƃ̎d�g�݂���肽���A�Ƃ����C��������u�Y�ƊJ���v�ł́A�G���Ȃǂ̌_��͔|�Ə��i������|�����Ă���B�����̐��Y�́A�͔|���e�Ƃ��Ă͗L�@�͔|�Ȃ̂�99�N�Ɂu��L�@�_�Y�����Y�ҋ��c��v���ݗ�����A���݂ł�165���̐��Y�҂��o�^����A�G���A���A��Ȃǂ̌_��͔|�Ɏ��g��ł���B�n�����Y�́u���ƒn�_�C�R���v�͔̍|�g��Ə��i�J��������������B
�@����ɂ����̎��g�݂͑傫������X���[�t�[�h�^���Ƃ��đ����ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ̍l������ׂ̎R�`���Ƌ��͂��Ċ�茧�X���[�t�[�h�����ݗ����A�����ɒZ�p�����H�ׂ��郌�X�g�����̂���A���e�i�V���b�v���J�݂����B�����̓��̉w�ł͎G���Ȃǂ̔̔��̂ق��A���X�g�����ł͒Z�p����h���O�����g�������j���[���p�ӂ���Ă���B�n��Y�i�̉��H�����Ɏ��g��ł������������́u�H�Ɣ_���l�������̉�v��ݗ����A�n���Y�i���g������V�����̔_�ƃ��X�g�������J�݂��Ă���B
�@�܂��A�k��R�n��̕��y�ƕ�炵�����ߒ����A������ւ�Ɏv�������̋C��������Ă�B�����̎��g�݂��A���R�i�ς̕ۑS�A�`���̐H�����̌@��N�����A�G���Ȃǂ̍ݗ��_�Ƃ̑g�D����i�߂�B�����Ėq�엘�p�̓��{�Z�p���U���Ȃǂ̂悤�ɁA���̕��y�Ɗ��炵����炵���Ƃ��ĒN�ɂł�������`�Ɉ�ďグ��B����ɂ��̎��g�݂ɓs�s�̐l�X�̎Q�����Ăт����A�L������Ă����B����ȕ�������@�ɂ��炳�ꂽ���{�Z�p���̒��S�Y�n��ō����g�܂�Ă���21���I�헪�̂悤�ł������B�Z�p�����Y�҂����́A��@�̒��ʼn��߂Ċ�ɂƂ��Ă̒Z�p�����q�̑�����ĔF�����A�������畗�y����Ă���q�{�Y�ւ̐V�������g�݂��L�������悤�ł������B
|

