1.はじめに
穀物をはじめとする農産物の価格高騰が飼料費を押し上げ、わが国の畜産はかつてないほどの厳しい状況に置かれている。食品残さの飼料化は、循環型社会形成を目標にした食品リサイクル、バイオマス利活用推進といった観点から関心が寄せられるようになっていたが、ここにきて一気に脚光を浴びるようになった。本稿では、畜産経営の経営戦略に関連し、食品残さ飼料による生産コスト低減と生産物の高付加価値化について検討することにしたい。
畜産経営の維持発展のための戦略については、大きく分けて二つの方向性がある。
ひとつは、コスト低減である。安価な輸入品との競合を意識し、生産コストを低減させることを主として考える方向性である。これは、商品としては普及品、一般品に該当する。
もうひとつは、高付加価値を追究する方向性であり、コスト低減を課題としながらも商品の差別化を行って経営を伸ばして行こうとする考え方である。商品としての質を高める方向性であるため、商品としては高品質で相対的に高い価格帯の商品が想定される。
これら二つの方向性は決して二者択一というものではないが、どちらにより重点を置くかで飼料の選択も生産物の商品的性格も変わってくるものであり、それによって食品残さ飼料の利用のあり方も変わってくるといえる。
2.食品残さ利用飼料と生産費の低減
食品残さの利用によって飼料費が低減できることは大方の認めるところであり、その事例はすでに何例も紹介されているが、問題はどの程度の価格水準が現実的に求められるかである。食品残さ飼料の価格水準は、その利用を決定付ける第一要因となるため、畜産経営者からみた食品残さ飼料の価格条件を把握することが必要となる。そこで、アンケート調査結果(注)を利用して、食品残さを使った飼料の希望購入価格をみることにしたい。ここで仮定されている飼料は、食品残さを乾燥させたものであり、品質が一定で定量供給され、異物がないこと、配合飼料に10%から30%の割合で混合給与することを前提としている。
図1は、アンケート結果を利用してリサイクル飼料の単価と購入意思をもつ経営の割合をみたものである。縦軸に食品残さ飼料の単価が示されており、横軸は、ある価格水準であるときに何割の経営がその食品残さ飼料を購入する意思をもち得るかを百分率で示している。図中の点は、単価の高い方から累積購入農場率をプロットしたものであり、曲線はそれらの点に近似曲線を当てはめたものである。例えば、単価がキログラム当たり30円の水準であると購入の意思をもつ経営は20%程であることを意味している。この図をみてわかるように、単価が低くなるほど利用しようとする農場は多くなるが、とりわけ単価が25円から15円の価格帯ではグラフの曲線が横になっており、単価を少し下げただけで大きく需要量が伸びる。この図からは、さしあたり50%を超える経営が購入を考える20円の水準を価格設定の目標にすべきといえる。この20円という水準は、調査時点での配合飼料価格がキログラム当たり39.8円だったことから、配合飼料価格の半額水準ということになる。このことから、食品残さ飼料(乾燥飼料)を販売する場合は、その価格水準を配合飼料の半額に置くことが第一の目標といえる。
図1 養豚経営における食品残さ飼料の購入意思価格
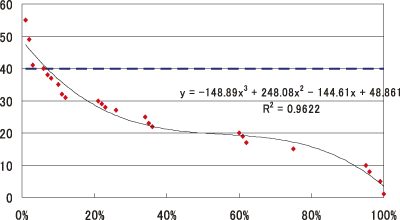
(注)全国農林統計協会連合会が2004年1月から3月にかけて実施された「養豚農場意向調査」の結果である。対象地域は、北海道、青森、山形、茨城、埼玉、東京、山梨、愛知、大阪、鹿児島の10都道府県であり、回答数は156で回答率は78%である。
次に問題となるのは、このキログラム当たり20円という価格が実現可能な水準であるかどうかである。そこで全国の先進事例を図2でみてみると、20円という水準は決して実現不能な水準ではないといえる。ここに挙げられている事例は、いずれも事業系の調理くず、食品加工くず、日切れ食品などを中心とした飼料化の事例である。
図2 食品残さ飼料の販売価格(事例)
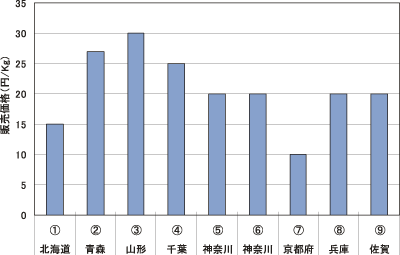
注:(3)(7)は農場渡価格、それ以外は工場出荷価格
3.畜産物における高付加価値化
次に高付加価値化を考えるために食品の価値要因について整理すると、次のようになる。
食品には三つの機能があるとされている。第1の機能は、生命の維持に必要なエネルギーや栄養の源となって身体に働きかける栄養機能であり、第2の機能は、おいしさに関わるものであり嗜好や感覚器官に働きかける感覚機能である。第3の機能は、生理機能を調整して健康維持や健康の回復に働きかける生体調整機能であり、最近は「機能性」として注目を集めるようになった。
消費者の食に対する欲求・要求を踏まえ、上記の機能に着目して畜産物の高付加価値化を差別化としてみると、その展開は図3のように考えることができる。
図3 食肉における商品差別化の展開
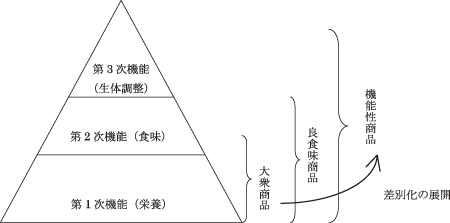
第1の機能を満たすことは当然として第2の感覚機能を「並」レベルで満たすものを一般商品、大衆商品とみることができる。いわゆる差別化はそこから先で行われる。食味を追求した差別化は第2の機能を高次に満足させるものであり、健康に良いなど有効成分を多く含むといった差別化は、第3の機能についての差別化である。
つまり、食品の機能を踏まえると、付加価値の中身を、第2の機能に関わる食味と第3の機能である健康によい生体調整機能で考えることができ、食味がよく機能性成分が豊富であれば、結果的に高い価格を期待できるということになる。
4.生産物の差別化と利用される食品残さ
生産物の差別化と飼料として用いられる食品残さについての関係を整理したものが図4である。横軸は食品残さの取引価格であり、左から逆有償で引取料(処理料)の高いものから安いものへ、そして無償(原点)さらに有償で価格の低いものから高いものへと並ぶ。縦軸は生産物の販売価格の水準を示しており、標準的な価格を原点としてそれより下がより安価なものとなり、原点から上はより高価なものということになる。
図4 利用する食品残さと生産物価値の関係図
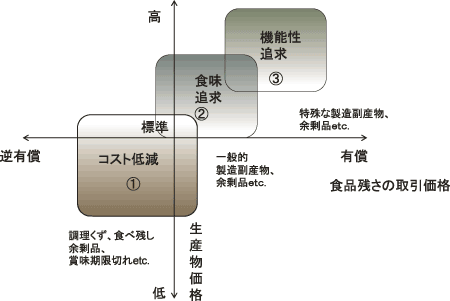
食品残さの利用と生産物の差別化についての組み合わせをカテゴリー分類すると次のようになる。
(1)は、逆有償となる食品残さを中心に利用して低コスト生産を目指すものである。利用する食品残さは調理くず、食べ残し、そして余剰品、消費期限切れ商品などの一部が相当する。生産物は標準的あるいは普及品、大衆商品といった商品となる傾向が強い。逆有償、無償の食品残さを利用して低コスト生産を実現し、標準的価格あるいは低価格の状況下でも一定の所得確保ができるようにできることを狙いとする。
(2)は、有価で食品製造副産物などを調達して飼料利用することがメインとなるカテゴリーである。利用する食品残さとしては、ふすまや油かす、パンくず、粉乳、麺類などである。これらは、配合飼料の部分代替によってコスト低減を追究するという側面もあるが、生産物の品質を高めるという性格が強く出てくる。良食味の畜産物を価格的に有利販売することを狙いとする付加価値追求型のカテゴリーといえる。
(3)は、付加価値追究の発展型といえ、生産物の高付加価値化のために比較的価格の高い食品残さを購入するやり方である。食品残さを有価で調達する場合でも価格が高い食品残さを購入するパターンは、それらを原料として使うことによって相応の高付加価値が期待できるケースである。具体的には、健康食品・飲料の副産物や余剰品など有効成分が含まれる食品残さの利用によって生産物の機能性と評価を高めようとする形である。
5.事例にみる食品残さ利用と経営戦略
上述の整理を踏まえて若干の事例をみることにしたい。飼料製造業の事例として、調理くずや食べ残し、日切れ品など逆有償のものを中心として飼料製造する大規模のA社と中規模のB社を取り上げる。また、養豚経営の事例として、逆有償の残さ利用を中心とするK養豚と副産物や規格外品等の有価の残さ利用を中心とするH養豚の事例をとりあげる。
1)京都A社:カテゴリー(1)の飼料化事業者(大規模)
京都府にあるA社は京都市内の廃棄物関連企業9社が共同出資して平成14年に設立した会社であり、産業廃棄物(動植物性残さ、有機汚泥)と一般廃棄物(調理くず、日切れ品、余剰品など)の飼料化、肥料化を行っている。
食品残さの処理方法は、バッチ方式の油温減圧乾燥システム(いわゆる天ぷら方式)であり、この装備を2ライン装備している。ひとつは有機汚泥、動植物性残さを肥料化するラインであり、もうひとつは動植物性残さ、厨芥(ちゅうかい)を飼料化するラインである。能力としては、肥料化のラインが1日8時間で19.1立方メートル、飼料化のラインが1日24時間で126トンである。
肥料化と飼料化のラインが併存することによって、収集された食品残さのなかでも飼料化に向かないものや栄養的に偏りが生じるような部分については、肥料化ラインで処理をして飼料の品質の均一化、安定化を図っている。
食品残さの収集先、収集量は表1の通りである。平均して1日当たり70トンの食品残さを原料として受け入れている。
表1 食品残さの収集先と収集量

収集業務は、出資企業8社が近畿圏一円から効率的に回収を行っており、運搬費用は、京都市内の小口ルートがキログラム当たり20円、近畿圏内で中距離の多量排出事業者は10円程度であり、処理費用は20円から30円である。
飼料の生産量は、日量12〜15トン、月間390〜420トンである。製品は、茶褐色の粉末状であり、水分は4〜8%、粗タンパク20〜23%、粗脂肪7〜9%である。この製品は、飼料メーカー3社の4工場と養豚経営2農場に出荷されており、飼料メーカーでは養鶏用の飼料として3〜5%の割合で配合飼料に混合され、養豚経営においては5〜10%の割合で配合飼料に混合して利用されている。
この企業の飼料化は、一般廃棄物が多く種々雑多な原料を扱うことになる。このような原料を大量に飼料化する上では油温減圧乾燥システムは最適技術のひとつであるといえる。また、広範にさまざまな食品残さを収集することから成分値は一定値に収れんする傾向がある上に経験の蓄積によって培われたノウハウによって製品の成分値は安定化する。製品の品質の変動をある程度の範囲内に抑え、逆有償の食品残さを利用することによって低価格の飼料供給を実現している。
 クッカー(円筒部):油分と混合された原料の食品残さが送り込まれ、減圧・加熱して水分を除去する。天ぷらの原理を応用した技術であり、加熱温度は80〜90℃、最高110℃まで上がり、原料受入から当行程終了まで2時間〜2時間半である。 油切ホッパー(手前):自然分離による油分を1次分離する。この後の行程で、圧搾によりさらに油分を分離する(2次分離)。 |
2)千葉県B社:カテゴリー(1)の飼料化事業者(中規模)
B社は、醤油かす、コンビニなどの日配品(おにぎり、サンドイッチ等)、米飯、ゆで卵、麺、菓子、調理残さ等を収集し、減圧乾燥させて飼料化を行っている。
産業廃棄物中間処理施設としての許可は1日当たり68トン、一般廃棄物処理施設として同28トンである。受入れは、月曜日から土曜日までの6日間、月に25日稼働で1日当たり60トンの処理量となっている。
減圧乾燥機はバッチ式で4機あり、2機ずつ原料の粘性の違いを考慮して稼動させている。野菜は別途破砕した後、乾燥させて添加する形をとっている。1バッチ6〜7時間で原料や加工品の出し入れを含めると8時間ほどになる。これを1日2.5バッチ行う。食品残さの受け入れは月間1,200トンくらいであるが、飼料化されるのはその中の1,000トン弱であり、乾燥処理後は300トンくらいの製品量となる。醤油かすは300〜350トンの受け入れであり、量的には2〜3%の減量でほぼ全量が製品化される。
製品は、5〜6戸の養豚経営へ供給しているが、その販売価格は工場の置場価格でキログラム当たり25円である。このところの原油高騰で同30円に上げることを考えている。また、製品の一部は東南アジアの関連農場に輸出している。
ここでの特徴は、大規模ではないが養豚経営と飼料についてのコミュニケーションをとることによって、互いの希望と技術的可否を調整して製品化に反映させて取引を継続していくという「顔が見える」関係を構築している点である。大規模に飼料化を行って配合飼料原料として飼料メーカーに販売する戦略とは異なり、できる範囲内でユーザーの要望を取り入れながら、成分分析や飼養試験などを重ねて自社製品の特徴と良さを理解してもらうことに努め、安定的な取引関係を形成した例といえる。
3)C養豚:カテゴリー(1)(2)の中間的存在の養豚経営
C養豚は、大阪府の関西空港にほど近い母豚95頭の一貫経営である。近くに食品コンビナートと呼ばれる食品工業の集中した地域があり、そこからパン生地、うどん、米飯、ちくわ、茶粕などを収集し、粉砕、乾燥してから大豆たんぱくなどを加え、乳酸菌を添加して発酵させたリキッド給餌を行っている。
当農場で生産される豚肉は、肉色がよく、適度に脂肪交雑が入り、味が良いことから評判を呼んでいる。品質を高めている技術的ポイントは、食品残さの利用によって飼料費が極めて低く抑えられていることから、肥育期間を通常より1カ月長く飼養していることと、小麦系の残さを多給することによってきめの細かい脂肪交雑を可能にしている点である。
かつては、軟脂などで肉の品質に問題があり「安かろう悪かろう」の残飯養豚の肉そのものであったが、養豚経営の存続のためには安価な食品残さを利用して質の良い豚肉を生産することが必要であるとの認識に至り、他の養豚経営者とともに肉質向上の研究会活動を積みかさね、品質を向上させることに成功した。
品質を高めることに成功した豚肉は、ブランド化され、大阪府内のスーパーなど6か所で販売されるようになった。販売事業は、後継者が販売会社の経営者となって展開され、朝市やインターネットによる直売も行っていた。手ごろな価格でおいしい豚肉という評判が次第に広まり、徐々にブランド肉としての地位を築いていったのである。ブランド肉としての認知度が広まり、人気が出て引きが強くなり、安定的な流通が見込めるようになったことから、平成20年から後継者は販売事業をやめ、父親と一緒に生産に従事することになった。つまり、ブランドとして基盤が固まったことから、販売事業に向けていた経営資源を生産拡大に向ける戦略をとることにしたのである。肉の流通業者に市場価格の数十円高で安定的に購入してもらえる体制を確立したことから、むしろ供給量を増加させることを選択したのであった(図5参照)。
図5 K養豚の経営展開
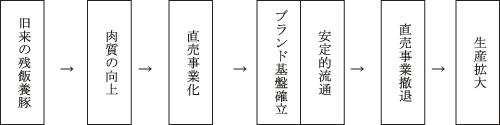
この経営は、利用する食品残さが逆有償で取り引きされるような食品加工の余剰品等が中心となっていることから、頭数規模はあまり大きくなく中小規模であるが、肉質を高める研究を積み重ね、手ごろな価格で美味しい肉という地元での評価を高めてブランド化に成功した好事例といえる。
4)D養豚:カテゴリー(2)の養豚経営
D養豚は横浜市内の住宅地に位置する養豚経営であり、母豚340頭の一貫経営を行っている。労働力は、自家労働力が経営主夫妻、長男、長女の4人、雇用労働力が3.5人である。年間の出荷頭数は5,900頭、肉豚販売額は約2億円を超える。
昭和24年に肥育素豚を導入して養豚を開始したのであるが、それは当時一般的であった残飯養豚であった。横浜市の中華街から毎日トラックで残飯を収集して給餌して肥育を行っていた。昭和40年代には繁殖も行うようになり一貫経営化した。
昭和50年代に入ると配合飼料の価格が低下し、配合飼料の利用が全国的に広がったのであるが、当経営においても配合飼料の利用が開始され依存度を高めて行ったのであった。配合飼料の利用によって早朝の残飯収集作業から解放され、伝染病のリスクも残飯利用に比べて低いことが認識された。ちょうどこのころ、現経営者が父親から経営を引き継ぐ時期でもあり、世代交代とともに配合飼料依存の養豚へと姿を変えた。
昭和60年に繁殖豚を100頭規模から200頭規模へと拡大し、平成6年には増築で離乳子豚舎を導入し、さらに平成8年にはウインドウレス離乳子豚舎、育成子舎を新築した。
このように規模を拡大して企業的な経営になってきたものの財政状態は厳しかった。そこで再び食品残さを利用して飼料費を低下させることを考えるようになった。
現在、学校やホテル、デパートなどからの事業系の廃棄物である食品残さを乾燥させた飼料を購入し、菓子粉、パスタなどの有価購入食品残さと合わせて表2のように利用している。
表2 D養豚の食品残さ利用
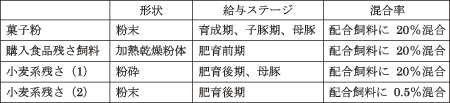
子豚、育成の段階では、菓子粉を中心として粉ミルク(乳児用の在庫処理品)を利用している。混合率は2割から3割くらいである。肥育豚になると、前期は食品残さの乾燥飼料を主として利用し、後期になるとパンくずなど小麦系の食品残さが主となる。混合率はどちらも2割程度である。つまり、肥育前期にはコスト低減効果の高い食品残さの乾燥飼料をメインで用い、仕上げの時期となる肥育後期にはパンくずなど肉質を向上させる効果のある小麦系の残さがメインとなる。
以上の食品残さの購入単価は平均すると配合飼料価格の半額程度であることから、2割の混合率とすると配合飼料の単価よりも1割購入単価が抑えられていることになる。
肉豚の販売単価は表3に示されている。これは平成20年1月の横浜食肉市場出荷分の上場価格である。出荷銘柄によって価格差があり、契約による価格設定が異なるため、部分的に市場価格より低い価格となるケースも存在するが、総じて市場の平均価格よりも高い水準で販売されているとみてよい。
表3 肉豚販売価格(円/キログラム)
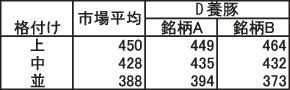
このように、D養豚は食品残さの利用によって飼料費を低減させる一方で、肉質の高品質化を追究して、ブランド販売に成功し、相対的に高価格の販売単価を獲得しているといえる。
6.食品残さ利用と畜産経営の経営戦略
食品残さの飼料利用は、かつての「安かろう悪かろう」の残飯養豚とは異なり、新たな姿で展開している。食品残さを利用してコスト低減を実現する一方で、付加価値を追求する技術が確立されつつある。パンくず等の麦類の残さを多給することによって肉質を高め、さらには飼料費が抑えられていることから肥育の仕上げ期間を長くしてサシを入れるノウハウが知られるようになり、ブランド化も行われるようになった。現時点では、付加価値の追求は食味が主たる差別化のポイントとなっているが、これからさらに差別化が進むと健康によい、美容によいなどといった機能性が追求されるようになると考えられる。現に、茶葉や茶殻、健康食品・飲料の残さを用いた差別化も出始めている。例えば、神奈川のE養豚では、商品化されない茶葉を有価で購入して飼料に添加している。茶葉の利用は、健康によいイメージを形成するだけでなく、臭みをとり、肉色をよくする効果があると考えられ、さらには肉質の保持にも有効であることが期待されている。
付加価値を追求する差別化は今後も進化していくと考えられるが、単なるイメージづくりにとどまらず、なぜその食品残さが有効なのかを科学的に解明し、技術として確立した上で、販売時にその理由を説明できるようにしなければならない。
同時に、食品残さの飼料化は付加価値追求ばかりではなく、飼料費低減というメリットの追求も忘れてはならない。そのために飼料費の低減というメリットを社会的に享受できる仕組みづくりを構築していく必要がある。例えば、事例でみたA社のように、高級品ではなく普及品の生産向け飼料をターゲットにして、飼料メーカーに対し、一定程度に成分変動を抑えた安価な飼料原料の供給を行うことは、配合飼料価格の上昇抑制、低減に広く寄与するものである。事業系の調理くずなどを大量に飼料化するケースでは、このような役割が社会的に望まれる。一方、同様の事例でもB社のような中小規模では、飼料メーカーへの供給というよりも、畜産経営とフェイス・トゥー・フェイスの関係をつくり、互いに調整し合いながら特定の顧客に応じた飼料生産を通じてコスト低減さらには付加価値の追求へとつながっていくことが望まれる。
今後は、利用する食品残さの内容および量と飼料化技術の組み合わせによって、市場でのポジショニングが分化してくるものと思われる。現段階は、食品残さ飼料の利用が広まる創成・普及期であるといえるが、付加価値追求の差別化の進展とともに分化の段階に入りつつあるといえる。