しかし、今回紹介する農業生産法人有限会社北海道ホープランド(以下、「北海道ホープランド」という。)ではそうではない。年中放牧と聞いたとき、われわれはにわかに信じられなかったが、確かにマイナス20℃を下回る冬場にも豚たちは一日中、元気に圃場を走り回り、餌を摂り、睡っているのである。
 |
|
厳寒の中、冬毛に覆われた放牧中の元気な豚たち |
《進取の気鋭みなぎる北海道ホープランド》
北海道ホープランドは帯広から車で小一時間、幕別町にある。幕別町は十勝大規模畑作地帯の中心地の一つで、小麦・ジャガイモ・ビート・豆類を主作物とする。
北海道ホープランドの代表、妹尾(せのお)英美氏は妹尾農場の4代目として、帯広農業高校を卒業した1963年の春に就農した(表1)。就農10年目の1973年に父を失い、若干29歳で経営主となった。父を失う前の1968年、国際農友会農業実習生としてアメリカに渡り、オレゴン州・アリゾナ州で1年間の経験を積み、また、1972年には神奈川県の相模原生協と馬鈴薯・豆類の産直を始めている。そして1977年には産直仲間とともに「神奈川県農畜産物供給センター」を立ち上げるなど、極めて積極的に活動を展開してきた。それらの一つの集大成が1981年の北海道ホープランドの設立であり、1988年の北海道中小企業同友会への加入だったと言えるかも知れない。
現在の耕地面積は130ヘクタール(うち放牧地40ヘクタール)。放牧地を除く90ヘクタールに小麦27ヘクタール、ジャガイモ20ヘクタール、ブロッコリー13ヘクタール、アスパラガス7.5ヘクタール、かぼちゃ7.5ヘクタール、豆類5ヘクタール、スイートコーン6ヘクタール、大根3ヘクタールを作付けしている。また、100坪または150坪のハウス13棟にいちごを栽培している(表2)。
|
表1 北海道ホープランドの沿革
|
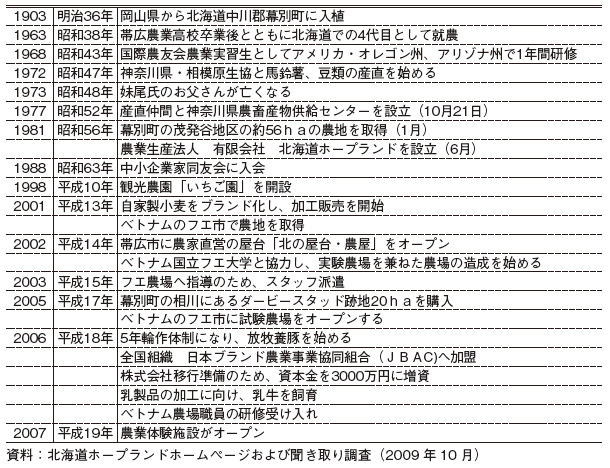 |
|
表2 北海道ホープランドの経営概要
|
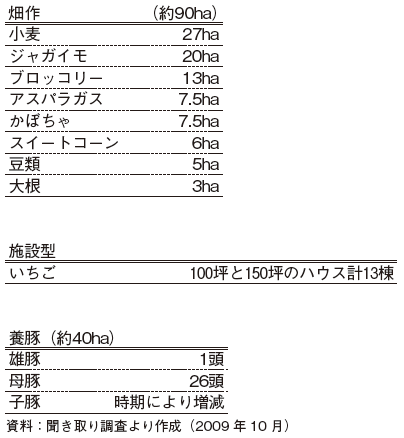 |
 |
|
いちご栽培で消費者との交流広げる
|
「販路は自ら切り開く」と言う方針の極めつけは小麦の独自販売である。それは価格支持制度から民間流通と麦作経営安定資金制度となって2年目の2001年に始まった。事の始まりは三重県からの働きかけ。三重県に本社を持つベビースターラーメンメーカー「おやつカンパニー」が創立50周年を記念して国産小麦でベビースターラーメンを製造しようと、国産小麦の入手方法などについて三重県に相談。しかし三重県では小麦はほとんど作られていない。そこで、小麦大産地の北海道のさる機関に相談したところ、回り回って妹尾氏のところに話しが来たのである。もちろん農協を通さなければ60キログラム当たり6,500円程度の麦作経営安定資金は支払われない。妹尾氏は、みすみす損を覚悟でその話しに乗ったのである。すこぶる芯が通っているとしか言いようがない。
こうした“進取の気鋭”が、“大冒険”とも言える厳寒の地・幕別町での放牧養豚の導入へと連なる推進力になっていったのではなかろうか。
 |
|
緑提灯5つ星の農屋(みのりや)
|
《第5の作物−放牧養豚》
北海道ホープランドでの放牧養豚は2006年9月に始まった。そのきっかけは2005年、15年程前に倒産し、そのまま放置されていた元軽種馬農場の農地15ヘクタールを手に入れることができたことである。今どき、幕別町で15ヘクタールものまとまった土地を手に入れるのは容易なことではない。おまけに、そこには40ヘクタールの十勝川河川敷の利用権や多くの厩舎、倉庫なども付いていた。もちろん15年もの放置の影響は大きく、ハリガネ虫駆除などの耕地改良や軽種馬用牧柵の撤去に多大な労力・費用を要した。特にハリガネ虫の被害は甚大で、草地を耕起し、そこにジャガイモを植えたところ全滅したと言う。
生後6カ月の雄豚1頭と雌豚10頭を農協から購入し、放牧養豚はスタートした。それは循環型有畜農業を目指していた妹尾氏の長年の夢が現実となった瞬間であった。とは言え、それが順風満帆にいったかと言えば、決してそうではない。まず問題は、放牧養豚はおろか、舎飼養豚の知識・技術すら、農協や役場の職員はもちろん、農業改良普及所の普及員すらもが持ち合わせていなかったのである。一般畑作地帯であり、やむを得ないことと言ってしまえばそれまでだが、柵の作り方や餌の種類・配合の仕方、防疫対策、去勢の方法などで手探りの状態が続いた。もちろん、冬場の対処の仕方などについては“暗中模索”状態。そうした中で一つの救いだったのは、大学で養豚を学んだベトナムからの研修生が当時、北海道ホープランドにいたことであり、豚の誘導の仕方や小屋の作り方など、彼から様々な助力を得たと言う。また、「物を大事にする姿勢や道具・資材がなくても何とか工夫する知恵」も彼から学んだと、妹尾氏は言う。
さて、放牧養豚である。放牧地は十勝川河川敷と収穫後の畑。放牧に使う畑には、次年度の餌となるように収穫後、牧草の種をまき、河川敷も含めて2〜3ヘクタールに区分けする。1区画20〜40頭ずつ放ち、牧草を食べつくす頃を見計らいながら転牧する(概ね一カ月に一度の転牧)。ブロッコリー・カボチャ・スイートコーンなどの跡地に放すと収穫残さを綺麗に食べてくれると言う。確かに、60頭が放たれた3ヘクタールのスイートコーン跡地には、豚達はスイートコーンの茎の間を歩き回り、かすかな残さや地中の虫などを探し食し、土や水と戯れていた。残さ以外に与えているのは放牧地の牧草や規格外で出荷出来ない農産物やでんぷんかす。そして、農協選果場から出る長いもの規格外。マイナス20℃を下回る冬場の一時期だけは、それに耐える体力作りと栄養の偏り防止のため少々の濃厚飼料を与えている。飼料自給率は70%を超し、購入しているのは冬場に与える濃厚飼料だけである。「ゆくゆくは濃厚飼料も自給したい」と妹尾氏は言う。通例であれば、せいぜい肥料にしかならない規格外品や作物残さ屑などが、立派な飼料となり、豚肉となるわけであるから、効率の良いこと、この上ない。また、自給飼料であれば、国際市場での穀物価格の乱高下に左右され、頭を悩ますこともない。
 |
|
妹尾氏が呼ぶとコーン畑から現れる放牧豚たち
|
これこそ、資源循環的な「循環型有畜農業」の一つの典型だし、また経営経済的に見ても「一石二鳥」あるいは「三鳥」取りの極めて優れた経営形態と評することも出来よう。
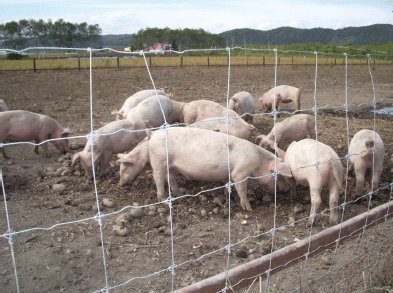 |
|
規格外ジャガイモを食す
|
《なぜ、放牧養豚か》
さて、なぜ、妹尾氏は厳寒の地で放牧養豚に取り組んだのであろうか。そこには20年ほど前、ヨーロッパに農機具展を見学に行った時に味わった豚肉の美味しさが深く関係している。それは日本で食べる豚肉とは大きく違い、実に美味しいものであった。聞けば放牧養豚のもので、体重は150〜200キログラムにも及ぶと言う。舎飼養豚もので100キログラム程度を基準とする日本では、当然にも「規格外品」として扱われ、販売価格はすこぶる安くなる。しかし、その美味しさは妹尾氏の脳裏から離れず、何とか日程を調整し放牧養豚農家を訪問するという挙に出させることになる。そこで聞いた放牧養豚・有畜農業の話しも、これまで大規模畑作専業経営をいちずに目指してきただけに強烈な印象を残した。ヨーロッパ紀行は、妹尾氏に「いずれ放牧養豚・循環型有畜経営を」の決意を抱かせたのである。
わざわざ「規格外品」の豚を作ろうというのであるから、一般の市場への出荷を目指すわけにはいかない。北海道ホープランドの豚は、世間では6カ月飼養・100キログラム程度が「常識」なのに、12カ月以上飼養され、その体重は150キログラムを超し、枝肉重でも優に110キログラムを超える。規格外も規格外、「立派な規格外品」である。
豚肉は「蝦夷豚(えぞぶた)」のブランド名で、全てレストランなどの実需者や消費者への直売されている。最大の取引先東京の大手DIY商品量販店系列のレストランチェーン。そこでシェフをしていた人が、北海道ホープランドの放牧豚に関心を抱き自店で使用してくれたのがきっかけだったと言う。シェフはその味の良さに惚れ込み、次々に系列店などに紹介してくれ、今では販路の70%が関東方面となっている。地元では「北の屋台村」の直営店「農屋」で使用しているのはもちろん、帯広のレストランELEZO
MARCHE JAPON(エレゾ・マルシェ・ジャポン)にも販売している。ELEZO MARCHE JAPONでは今、ハム・ソーセージ工場を建設中であり、完成の暁には原料に北海道ホープランドの放牧豚を使いたい意向とされ、既に今以上の取引、ゆくゆくは年間1千頭もの要望が寄せられていると言う。その他、現在帯広に一店の直売所を持ち、さらに2010年には釧路に一店、関東に一店の直売所の開設が予定されている。
販売価格は一頭当たり8万円。通例100キログラム程度の舎飼豚の取引価格が3万円程度とされるから、その2.6強で取引きされているのである。確かに、生体重が1.5〜2倍あり、飼養期間も2倍程度かかることからすれば、トントンかむしろ「割安」とも言えるが、何せ残さ利用の養豚である。一頭ずつ見れば十分に採算のとれる価格と言って良い。
言うまでもなく放牧豚の魅力はその味の良さにある。しっかりした健康的で、歯ごたえのある肉質で、中でもその脂身は、「脂身が美味しくなければダメ」と妹尾氏が断言するように、甘みもあり絶品である。帯広畜産大学地域共同研究センターが行った官能試験でも「肉質が柔らかい」「臭みが少ない」などの高評価を得ている。また、さる有名料理人が「妹尾氏の豚の脂身で揚げた天ぷらは実に美味しい」と評するのも、けだし当然と言わなければならない。脂身の美味しさ、妹尾氏がヨーロッパで感じた美味しさは、それだったのかも知れない。
現在飼養しているのはランドレース種と大ヨークシャー種の交配種にデュロック種を交配した3元交配豚であるが、ゆくゆくは大ヨークシャー種に代え中ヨークシャー種を導入し、ランドレース種と中ヨークシャー種の交配種にデュロック種を交配したものにしていきたいとされる。もちろん、味にこだわってのことであることは言うまでもない。
とは言え、現在、販売が順風満帆かと言えば決してそうではない。2008年には年間販売頭数400頭を目標に奮闘したもののそれに達せず、また2009年には200頭としたものの、調査時の10月初旬時点でそれに達していなかった。販路拡大、それが今日の北海道ホープランド放牧養豚が抱える緊急にして最大の課題なのである。そこには現在の取引方法、「一頭丸ごと取引」が深く関連していると言える。決して安売りに走らず、また、部分肉取引を導入したとしても全ての部位を確実に売り切る態勢を構築する。それが、今後の北海道ホープランド放牧養豚に課せられた大きな課題である。
《アニマル・ウェルフェアの先駆》
さて、これだけさまざまな仕事を北海道ホープランドでは、7名の妹尾氏家族、1名の常勤、そして18名ほどのアルバイト及びボラバイト(ボランティアとアルバイトの中間のようなもの)の計26名と若干名の実習生で行っている。常勤とアルバイトは基本的に通年雇用で、仕事のない冬場には政府の雇用対策事業を利用していると言う。実習生は基本的に、将来農業で自立することを目指している人で現在6名。これまで、農地や農機具などを貸与するなどの支援をし、2名を独立させてきた。アルバイト・ボラバイトは全国から受け入れており、2棟所有する宿泊・研修施設に空きがある限り受け入れている。ところで、雇用のことをお聞きし、感服したのはその姿勢である。妹尾氏は共に働いてきた従業員とは、彼が望めば「生涯を通じて一緒に仕事をし、過ごしていく」方針だと言う。事実、元農家で、長年北海道ホープランドで働いてきた、とうに60歳を超えた人を未だ「常勤」として雇い続けているのである。そうした優しい心情が、家族や従業員のストレス解消と癒し効果を求めてのポニーや犬の飼養へと結びついていったのかも知れない。
そうした優しさは、放牧養豚のあり方にも遺憾なく反映されている。例をあげればきりがないが、何点かあげておこう。
その一つは、通例淘汰してしまう病豚に獣医を呼び、治癒を願い、必要な治療を施していることである。二つは、個体管理用に一般に行われている耳の切断を行っていないことであり、そのせいか豚達の耳は目を覆い隠すほどの長さとなっていた。三つは、生後数日のうちに行う尻尾の切断を行っていないことである。尻尾の切断は、ストレス蓄積時、別の豚の尻尾に噛みつき、そこから細菌が入る危険性があるため、その予防のため行われるものである。「ストレスを与えない飼い方をすれば良い」と妹尾氏は何気なく言うが、決して容易なことではない。
その他、去勢のやり方、交配でも“豚に気をつかったやり方”になっていると言って良い。去勢は、感染症に十分注意しつつ、子豚に過剰なストレスを与えないように慎重に、生後1週間以内に行っている。また、交配は自然交配で、人間のやることと言えば発情を素早く見つけ、交配の条件を作ることぐらいしかない。時には3〜4日と短い発情期間を見落とし、子豚の産出が少なくなったこともあったが、その方針を変えるつもりはないとされる。また、当初導入した雄豚の体重が300キログラムを超し、交配時に雌豚がつぶされそうになることもあり、新しい雄豚を導入しなければならないとは考えているが、しかし、「今いる雄豚がかわいそう」とついつい結論を出さず仕舞いになってしまうのも、その優しさの現れとしてあげて良いかも知れない。
ここまで書いてくれば、読者諸賢の脳裏には「アニマル・ウェルフェア」との言葉が容易に浮かぶに違いない。そう、「妹尾型」放牧養豚にはアニマル・ウェルフェアの精神が満ち満ちているのである。
思えば、アニマル・ウェルフェアと言われてから久しい。もちろん、その発祥地がヨーロッパであることは言うまでもない。アニマル・ウェルフェア思想はヨーロッパで徐々に広がりを見せ、ついに1997年、「動物の保護及び福祉に関する議定書」がヨーロッパ共同体設立条約に加えられた。そして2000年、WTO農業交渉の場にEU委員会が「動物福祉と農業貿易」を提案するに及んで、アニマル・ウェルフェア思想は一気に国際化していったのである。その後、国連食糧農業機関(FAO)が「畜産動物の人道的取扱い、輸送並びに屠殺に関する指針」を打ち出し、コーデックス委員会が「有機畜産ガイドライン」を採択し、更に、国際獣疫事務局(OIE)が「2001〜2005年戦略計画」で動物福祉の最優先と加盟国のその分野でのリーダーシップ発揮を決し、ここにアニマル・ウェルフェアは“世界の常識”と化したと言って良い。
こうした動きを受け、わが国でもアニマル・ウェルフェアに対する関心は高まり、アニマル・ウェルフェア思想に則った畜産経営や、「家畜にも人にも優しい信州コンフォート畜産支援事業」に基づく長野県松本家畜保健衛生所の信州コンフォート畜産認定基準値の制定(2007年2月)のような事例も出てきている。しかし、われわれの見る限り、彼我の隔たりは未だにすこぶる大きいと言わざるを得ない。世界の潮流が大きくアニマル・ウェルフェアに向かっている時、わが国だけぐずぐずしている訳にはいかない。わが国畜産の世界からの“孤児化”は高まる危険性も高いからである。
 |
|
妹尾氏と愛馬
|
《“点”から“面”へ−「十勝放牧養豚研究会」の旗揚げ》
2009年2月14日、妹尾氏を会長とする「十勝放牧豚研究会」が産声をあげた。放牧養豚農家(予定者も含む)及び豚肉加工・販売業者8名を正会員とし、放牧豚の応援者18名を支援サポーター会員とする、実に小さな組織である。小さいながらも、すこぶる大きな第一歩が印されたと言って良い。飼養方法や販路開拓などに関する情報交換や切磋琢磨による技術力の向上などが期待されるし、また、消費者や実需者へのアピール力、販売力も特段に上昇する可能性があると思われるからである。さらに、生産者・農家へのアピール力になること、うけあいである。思えば、ホエー豚やチーズ工房の先駆的取り組みの例をあげるまでもなく、十勝地域は進取の気鋭に富む数多くの生産者・農家が活躍しているところである。“点”から“線”へ、そして“面”へと放牧養豚は広がり、放牧養豚“王国”へと発展していく可能性を十分秘めていると言えるのではないだろうか。今や「食の安全性・安心性」担保が叫ばれ、「地産地消」など、“顔の見える関係”の再構築が叫ばれる時代である。放牧養豚は、まさにそうした時代の要請に適合的な形態であり、また、飼料の自給率の特段の上昇ひとつとっても「食料と環境の世紀」と言われる今日に求められている形態と言えるのではないだろうか。また、“顔の見える関係”は決して人間同士に限ったことではない。作目の顔もその中に含まれており、であるが故に農作業体験やグリーンツーリズムなどに、人々はすこぶる強い関心を示すのである。野菜や米(稲)、一般畑作物などはもちろん、作目の中には当然家畜も含まれているのであり、家畜がストレスの少ない環境の中でのびのびと家畜が飼養されていることが必須の要件と言えよう放牧養豚、広くは放牧酪農など家畜生理に適合的な飼養形態は、まさに時代の要請に合致したものなのである。
放牧養豚の発展を心から期待したい。
 |