

東京大学大学院経済学研究科 助教授 矢坂 雅充
近年、メガファームと称される大規模酪農経営の潜在的な成長力を評価し、日 本酪農のけん引車としての役割を期待する声が高まっている。 生乳生産が伸び悩み、家族経営主体の酪農経営の生産力にかげりが出始めてい るからである。家畜排せつ物法に基づくふん尿処理への規制強化、牛乳消費の減 退、原則として年中無休の労働条件のもとで、従来どおりの経営を続けていくこ とへの不安が募っている。 そこで法人経営の大規模酪農経営にスポットライトが当てられるようになった。 メガファームという大げさな呼称には、大規模酪農経営モデルとして知られるア メリカの企業酪農のように、酪農産業を革新していく先導的な経営として発展し 続けて欲しいという期待が込められている。 もっともメガファームについて明確な定義があるわけではない。酪農総合研究 所は日本型メガファームの革新性を、高度な経営管理、主体的にリスクを負う企 業者、経営多角化などの展開による規模の経済性を超えた生産性の向上に求め、 それを実現しうる分岐点を年間産乳量3,000トン、経産牛頭数でおよそ300頭と いう経営規模に置く。むろん飼養頭数規模の拡大が一義的に経営の革新をもたら すわけではない。そもそも日本型メガファームの対象となる酪農経営の数はまだ 少なく、各経営の個性・多様性も無視できない。 そこで以下では、メガファームと呼ばれる経営の多様性に留意しながら、北海 道と関東のメガファームを比較し、それぞれの特質を整理して見ることにしよう。 なお、訪問したメガファームは、以下のとおりである。北海道では鹿追町「笹 川三愛農場」、新得町「北広牧場」、関東では茨城県大宮町「みずほ農場」、群 馬県昭和村「吉野牧場」である。いずれもメガファームの代表的な経営と目され ており、大規模酪農経営を目指す経営のモデルとして大きな影響を与えている。 多様なメガファームの姿を網羅的にとらえることはできないとしても、これらの 事例からメガファームの特質を理解することができよう。
みずほ農場 |
||
 |
 |
|
吉野牧場 |
||
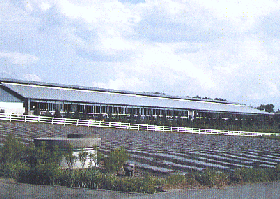 |
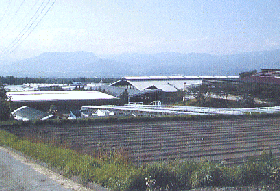 |
|
笹川三愛農場 |
||
 |
 |
|
北広牧場 |
||
 |
 |
|
表1 経営の概要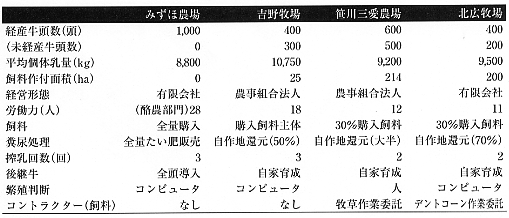
メガファームの登場は酪農における多頭飼養管理技術の確立に支えられている。 稲作兼業経営の安定的な存続にとって、中型機械化体系に基づく標準的な技術が 極めて重要な役割を果たしてきた。酪農においても大規模経営における飼養効率 を飛躍的に引き上げるような技術体系が整いつつある。こうした多頭飼養技術の 成果は、メガファームにおける経産牛1頭当たり乳量の高さに端的に現れている。 上記4法人の個体乳量もほぼ9,000〜10,000キロリットルとなっており、吉野牧 場では群管理のもとで2万キロリットルもの高泌乳牛が現れたという。飼養頭数 の増大とともに個体乳量は減少する傾向がみられてきたが、メガファームではむ しろ極めて高水準の個体乳量が維持されている。 多頭飼養技術の一つは、多様な飼養技術のシステム化にある。フリーストール およびミルキングパーラーによる飼養管理、TMRによる効率的な飼料給与などの 手法が導入され、飼養効率の向上や省力化が図られる。さらにコンピュータによ って飼養管理情報を集約的に処理して、多様な飼養管理作業が一体的に管理され る。経営規模拡大の下で可能となる多額の投資によって、給じ・搾乳・繁殖・淘 汰に関する個々の作業管理がほぼ網羅的に機械化・自動化され、多頭飼養技術シ ステムとして定着してきたといえよう。 いま1つは、徹底したアウトソーシングであろう。雇用労働力の活用も家族経 営から見れば、アウトソーシングの1つということができる。雇用労働者はマニ ュアルどおりに、個人的な判断を差し入れずに正確に作業を進めることが期待さ れる。むろん通常の意味でのアウトソーシングも幅広く取り入れられる。作業手 順や経理システムなどのデザインは、それぞれの専門コンサルタントのアドバイ スに応じて設計されるのが一般的である。後継牛供給の北海道への依存、飼料作 業のコントラクターへの委託なども欠かせない外部化戦略とされる。労働力や土 地などの経営内資源を効率的に活用するために、酪農経営における専門性・分業 体制を明確にしているのである。 もっともこうしたメガファームには多頭飼養における経営合理性を追求する共 通の特質がみてとれる一方で、北海道と府県、あるいは協業経営と個人経営とい えるような大きな差異が存在する。そこで、次にそれぞれについて事例に基づい て、おおよその性格を素描してみよう。
北海道には年間産乳量3,000トン以上の酪農経営が13戸(平成11年)あり、大 半の経営が機械利用組合などを母体とする協業形態での法人経営である。数戸の 家族酪農経営がいわば合併して、大規模酪農経営を築いてきた。それは大規模酪 農経営のタイプとして新しいわけではないが、平成2年以降、十勝地方を中心と して各地で法人化を契機として多頭飼養を実現する経営が目立つようになった。 笹川三愛農場は3年、北広牧場は8年に設立されている。こうした法人経営の設 立ブームを背景として、北海道では家族酪農経営の限界を克服しうる経営として メガファームへの期待が募っている。 設立の経緯と基本的性格 協業経営形態のメガファームの多くは、普及センターや農協と連携を取りなが ら、家族経営の合併を図ってきた。トラクター利用組合などに参画していた近隣 の酪農経営が統合して、それぞれが持ち寄る農地や労働力を活用した多頭飼養経 営へと踏み出す際、既存の機械設備の評価、新しく導入する施設・技術の選択、 融資や補助事業の導入、構成員(家族)間の意見調整ルールの策定が必要となる。 農協等は法人経営の準備段階から、その具体的な運営方法やビジョンの形成に大 きな役割を果たしてきた。言い換えれば、農協はこれらのメガファーム経営に有 形、無形の支援に対応したリスクを負っている。北海道のメガファームが農協の ベンチャービジネスといわれるゆえんである。 法人経営に踏み出した構成員の動機も、協業型メガファームの性格に深く関わ っている。前述の2法人のいずれにおいても、機会・設備が老朽化して更新しな ければならず、しかも経営規模拡大とともに農作業が過重となっていたことが、 法人化の契機となっている。家族酪農経営として維持していくことが、資本と労 働力の両面で限界に達していた。そこで法人経営のメリットは新規大型投資の実 現にとどまらず、酪農経営における「ゆとり」の実現におかれている。笹川三愛 農場では6組の夫婦などのペアによって構成されており、毎日1組が非番となる 5勤1休体制を実現した。北広牧場でも作業の繁閑によって調整しているものの、 年間60日の休暇を確保している。家族経営における過重労働を解消し、ヘルパー 利用よりも自由度の高い経営内部でのローテーションによって定期的に休暇を取 ることが、就農継続に欠かせない条件となっている。労働条件の改善は各家族の 生計と就労の維持を支える最優先課題として位置づけられている。 意思決定 法人経営を発足する以前からの共同作業の経緯を踏まえ、経営内の意思決定は 平等の立場からの協議が基本となっている。理念的には家族間の融合、いわば拡 大家族が目指されていると言って良い。従って法人の代表は基本的には構成員の 持ち回りとされ、時間をかけて相互理解の下で経営方針が立てられることになる。 もっとも繁殖・ほ育、搾乳、飼料生産などの個々の作業責任は、ローテーショ ンではなく、メンバーの資質や意向を踏まえて固定的に分担されている。専門的 な分業体制によって、家族協業組織の効率的な事業運営が目指されている。 一般的に協業経営に対して意思決定の遅さ、経営内での権限の不明確さが欠点 として指摘される。逆に言えば、家族的なあうんの呼吸とでも言いうるような意 識の一致や経営全体を思慮する寛容さが維持されていれば、家族酪農経営の限界 を克服した安定的で強靱な経営が実現するに違いない。2年以降、次々と設立さ れてきた協業型メガファームの活力を支えているのは、皆で家族経営の壁を超え ていこうという熱意であるといえよう。 経営戦略 家族経営の集合体として発足する協業型メガファームでは、持ち寄った労働力、 農地、さらに新規導入も含めた施設・機械などとの不整合の調整が課題となる。 構成家族数の多寡をはじめとする法人発足時における資本の差が、より効率的な 資本活用のための経営戦略の差、ひいてはこのタイプのメガファームの多様性と なって現れているといえよう。 まず構成員の家族労働力のゆとりある就農を基礎として飼養規模の目標が設定 され、不足する労働力が雇用される。構成家族数が多い笹川三愛農場では、アル バイトを含めて雇用には否定的である。4戸の協業経営である北広牧場では、口 コミ等で応募してきた3人が従業員として雇われている。北広牧場の経営規模で 年間60日程度の休日を確保するためにはおよそ10人の従事者が必要だからである。 いま一つ、農地と機械の調整が避けられない。高品質の飼料生産を実現するた めには、短期間で収穫調製作業を終わらせることができる大型機械を装備しなけ ればならない。そこで、飼料生産のコントラクター利用あるいはコントラクター への業務受託が常とう手段として採用される。笹川三愛農場では補助事業で導入 した機械を使用してデントコーンは自家栽培しているが、牧草はすべてコントラ クターに委託している。大型機械を保有するコントラクターの作業効率がより高 いからである。北広牧場でも近隣農業法人との飼料共同栽培生産やデントコーン の委託栽培を行っている。一方、大型機械を導入した法人経営は、機械の利用効 率を上げるためにコントラクター業務を取り入れている事例が多くみられる。コ ントラクターを通じた機械投資の効率化、さらには労働力の調整が図られること になる。言い換えれば、こうした調整が地域農業への支援やメガファーム間の提 携活動として注目されることになる。 いうまでもなく労働力、農地、機械のバランスを取るための調整方法は多岐に わたる。ほかにもほ育育成、ふん尿処理などでも、アウトソーシングや提携とい った手法で、最適な資本バランス、とりわけ構成員家族労働力のゆとりある就農 の実現を重視した経営戦略が編みこまれているといえよう。
府県で増えつつあるメガファームは北海道の協業型メガファームとは性格をか なり異にしている。それは個別企業型メガファームとでもいいうる中小企業であ る。愛知県知多半島の酪農経営に代表される都市近郊の粕酪農型多頭飼養経営の 生産性の高さは、かなり以前から注目されてきた。それが近年、メガファームと してクローズアップされるようになってきたのは、肉牛肥育経営の多角化の一環 として大規模な酪農生産が登場したからであろう。その代表格である栃木県のJ ETファームは、2年以降、F1の肥育とともに乳牛の多頭化を図り、搾乳牛1,300 頭を上回る日本最大の酪農経営となっている。本稿で紹介するみずほ農場も酪農 部門を導入したのは昨年であるが、すでに搾乳牛はおよそ1,000頭に達し、急速 に多頭化を進めている。 こうした肉牛肥育経営からの参入に加えて、それと共通の経営戦略をもつ搾乳 主体の大規模な個別酪農経営の存在が目立つようになってきた。吉野牧場にみら れるような家族酪農経営の企業的展開も、個別企業型メガファームとして注目さ れるようになっている。 設立の経緯と基本的性格 何よりも生乳生産の安定性が酪農経営の規模拡大をけん引している。 1つは、乳価の安定性である。不足払い制度や生産者団体・乳業間の取引価格 安定志向の下で、生産者乳価は安定的に推移している。数年先の経営計画に基づ く収支予想が大きく外れることはない。 2つは、収益の安定性である。飲用向け比率の高い府県の乳価は北海道に比べ て高く、送乳経費などの付帯経費も割安である。乳代の相対的な高さが早期の負 債返済、収益計上の見通しをもたらし、連続的な投資を可能にしている。しかも 毎月一定の生乳販売収入が見込めるので、資金繰りは肉牛経営よりもはるかに容 易である。 3つは、飼養管理の安定性である。すでに見たように多頭飼養の技術的な基盤 が整い、マニュアルに即して乳牛の栄養・繁殖管理を徹底すれば、高水準の個体 乳量を確保しうるようになった。肉牛の場合は28カ月にもおよぶ肥育期間の後に 飼養管理の成果が判明するのにたいして、乳牛のそれは日々明らかになることも、 乳牛飼養管理の安定性を増している。 酪農生産の安定性にたいする高い評価が、酪農経営における確実な規模拡大投 資を促し、さらに肉牛経営のリスクをヘッジする事業として酪農への参入を積極 化させている。 意思決定 個別経営の規模拡大、多角化の結果として登場した個別企業型メガファームで は、最終的な経営の意思決定権は言うまでもなく経営者に帰属する。基本的には トップダウンで意思決定が下される。 むしろ注目すべきは、日常的な経営判断における従業員の参画が積極的に図ら れていることであろう。みずほ農場では経営計画、マニュアル作成などの経営判 断に対する議論が、オーナーである会長を交えた5名の役員会で討議決定される。 また生産現場の代表である社長は、その意欲が評価されて、当時入社2年目の26 歳の従業員が抜擢されている。「従業員全員が同じ方向を向いて生き生きと働く」 ことが、マニュアルどおりの確実な作業を保証しており、そのために従業員との 意思疎通や深い信頼関係の構築が重視されているといえよう。 経営戦略 個別企業型メガファームの最大の特徴は、その経営戦略の合理性、ち密さにあ る。いくつかの代表的な点を例示することにしよう。 1つは、綿密な投資管理である。経営規模が拡大するにつれて、省力的な設備 導入やふん尿・汚水処理などの環境対策のための投資需要が累増する。それは多 頭飼養に伴って酪農生産技術体系が変化してしまい、家族酪農経営の設備投資水 準では従前の生産効率をも維持できなくなるからである。ミルキングパーラー、 フリーストール(フリーバーン)の導入は言うまでもない。飼養管理、経営管理 におけるコンピュータによる自動管理システム、ふん尿のたい肥化設備、汚水の 洗浄処理設備など、規模拡大によって新たに必要となる機械設備が多く存在する。 資本装備率は格段に引き上げられる。 そこで、メガファームでは徹底した投資の節約が図られる。従業員による施設 の設営・修繕や人工授精や削蹄の実施は、その一例であろう。みずほ農場では牛 舎の建設・修繕ばかりでなく、初乳搾乳設備の製作にも従業員が当たってきた。 人工授精を専門的に担当する従業員も養成されている。いわば可能な限り、施設 ・サービスの内生化が図られている。また、補助事業の活用も投資の節減の一手 法である。吉野牧場では公社営の再編整備事業を初めとして各種の補助事業を取 り込みながら、投資額を節減してきた。補助事業の導入に際して、補助要綱や工 事規格などの弾力的な採択を要請して投資額を最低限に抑え、自己負担を節減す ることの意義が両事例で指摘された。メガファームを軌道に乗せるための初期投 資額は際限なく膨張する傾向にあり、投資拡大にブレーキをかけ、少しでも自己 負担を抑制する姿勢が欠かせないのである。 2つは、規模の経済性を活かした飼料調達である。恒常的に大量の飼料を購入 するメガファームでは、飼料メーカーとの取引交渉を相対的に有利に進めること ができる。具体的には相当額の大口メリットが獲得され、両事例では通常の飼料 価格より40〜50%程度も低い価格水準での飼料調達が可能になっているという。 肥育部門を抱え、さらに同企業グループに属する他の農場との飼料共同購入を行 っているみずほ農場では、飼料メーカーからの信用供与も獲得しており、大口需 要者としての交渉力をフルに活用している。 3つは、搾乳と和牛・F1素牛生産など、生産管理が容易な部門への集約化であ る。吉野牧場は後継牛の自家育成を基本としており、400頭の搾乳牛に対して250 頭の育成牛を飼養しているが、多くの場合、出産時の事故が少ないF1や和牛の子 牛生産が選択される。みずほ農場のように肉牛肥育部門を兼ね備えている場合、 酪農は肥育素牛の供給源として位置付けられることになる。従ってメガファーム は多くの初妊牛を恒常的に北海道で購入しなければならない。またすでにふれた ように、飼料は粗飼料を含めてほぼ全面的に購入に依存している。天候に作業が 左右され、品質の安定性も確保し得ない自給飼料生産は、ふん尿処理や酪農生産 のイメージを維持する目的のためといった程度に過ぎない。北海道と海外に初妊 牛と飼料生産をアウトソーシングすることで、搾乳部門の効率を引き上げている ともいえよう。 4つは、たい肥マーケティングの充実である。膨大な量のふん尿を処理するた めには、完熟たい肥にして販売するしかない。たい肥は当初より販売目的のため に製造されることになる。みずほ農場ではグループ関連企業が20年前からたい肥 の販路を築いてきた。80℃以上の温度で発酵した高品質のたい肥を低価格で販売 することで、県内全域の畑作農家などに固定的なたい肥販売先を確保している。 たい肥部門は人件費を賄う程度の収入しか得られないというが、年間1,800万円 のたい肥売上げは、たい肥の品質管理とマーケティングの成果であるといってよ い。 5つは、マニュアルとインセンティブを重視した労務管理である。すでに見て きたように、作業は徹底したマニュアルに基づいて行われている。酪農について の知識が全くなくても、同じ水準での作業が遂行されるようなマニュアルや作業 点検システムが作成される。例えば、コンピュータがデータに基づいて発情と判 断した牛には、仮に十分な発情状態が見受けられなくても、とにかく人工授精が 行われる。従業員の主体的な判断を排除して、客観的な判断のもとで作業を進め ることが、多頭飼養の飼養管理には欠かせなくなっている。 それだけに労働者の労働意欲をいかに維持するかが重要な課題となる。従業員 の経営への参画意欲を充足するだけではなく、賃金体系にも多くの工夫が見られ る。みずほ農場では年功序列による賃金体系を排し、年齢や性差による区別なく、 30歳代半ば当たりまで比較的フラットな賃金体系が採用されている。就業年数が 上がるとともに相対的に賃金水準は低下し、退職を促すことが可能になる一方で、 若年者や女性にとっては比較的高い賃金水準が保証され、労働意欲を刺激するこ とが期待される。また吉野牧場では繁殖部門での受胎率向上など、部門ごとに評 価指標を設けて経営実勢手当を採用したことで、経営効率が大幅に向上したとい う。作業マニュアルの徹底は労働のインセンティブ・システムと不可分の関係に あるといってよい。 6つは、経営管理技術の重視である。マニュアルに基づく生産システムが構築 されると、経営者の関心は生産管理から経営管理に移行する。計数データの的確 な処理と判断によって、将来の収支および負債返済見通しを立て、それに基づい て次期以降の投資計画を練ることが経営者の基本的役割として位置付けられる。 みずほ農場の社長、吉野牧場の後継者はいずれも主として経営管理を担当してい る。 以上見てきた経営戦略の特徴は、養豚・肉牛肥育経営、さらには熟練を要しな い製造分野の中小企業のそれと類似しており、必ずしも経営革新とはいえないか もしれない。しかし、個別企業型メガファームの中小企業的な特質は、異業種か らの参入という事情も手伝って、家族経営の枠内で発展してきた酪農に大きな波 紋を投げかけているというべきであろう。
最後に、長期的な展望からメガファームを眺めて見ることにしよう。協業型メ ガファームはもはや再び家族酪農経営に再分割されることはない。構成員家族の ゆとりある就農と高収入はメガファームでしか得られないからである。家族間の 利害対立や意見の衝突が、構成メンバー全員の生涯設計を危うくするという認識 の下で、協調的な経営体制が持続する可能性は高い。 もっとも構成員の世代交代や従業員を含めた経営継承が、協業体制の維持を左 右する課題となって立ち現れることになろう。協業経営組織は実質的に経営者と 従業員に分化し、いずれ個別企業型経営へと収れんするのだろうか。それは協業 経営のいわば宿命的な課題でもある。 このほかにもいくつか気になる点がある。1つは、農協や行政のメガファーム 支援についてである。これまで農協や普及センターは協業型メガファーム設立に 際して、集中的に積極的な支援を行ってきた。農協はメガファーム設立の経験を 普及する役割を担ってきたといえよう。しかし、メガファームの経営が軌道に乗 るにつれて、大規模酪農経営としての論理が農協や行政の思惑あるいは期待と衝 突する可能性が高い。生乳共販体制への批判、飼料調達における大口メリットの 要請あるいはアウトサイダー化、地域の家族酪農経営とのコントラクター契約の 選別強化などを通して、地域酪農との共生・協調というスローガンは形骸化して いくかもしれない。 いま1つは、株式会社によるメガファーム経営についてである。北海道のメガ ファームの多くが協業型となっているのは、家族酪農経営のわずかな資産を前提 にすると、家族経営の合併による規模拡大しか選択の余地がないからである。し かし、乳業などの株式会社がメガファームに資本参加しうるようになれば、様相 は一変するかもしれない。生乳生産が低迷する中で、安定した集乳地盤としてメ ガファームに白羽の矢が立てられる可能性は皆無とはいえないだろう。 一方、急成長を遂げつつある個別企業型メガファームが、近い将来、府県各地 に数多く登場すると想定するのは難しいと考えられる。このメガファームの成否 は、既に見てきたように、まさに中小企業経営者としての資質にかかっている。 肉牛肥育経営が事業の多角化として酪農部門に参入する余地は高いとしても、家 族酪農経営の経営者にとって生産者としての認識を削ぎ落とし、事業経営者とし て酪農を営むことは容易なことではないに違いない。 さらに個別企業型メガファームの立地条件も限られている。さきに見た乳価、 飼料価格、ふん尿処理の条件を踏まえると、牛乳の消費地に近く、輸入飼料を安 く入手することができる大型飼料輸入港の周辺で、かつたい肥需要が旺盛な畑作 地域に立地することが望ましい。このタイプのメガファームは特定の地域に集中 すると考えるべきであろう。 個別企業型メガファームの長期的な展望として、さらに3点付け加えておこう。 その1は、経営の効率性を支えているアウトソーシングの不安定性についてで ある。例えば、後継牛(初妊牛)の調達条件は北海道の乳牛飼養頭数の動向に左 右されるであろうし、海外からの輸入飼料購入は国際穀物市況や為替レートの大 きな変動がもたらす不安定性から自由ではいられない。 その2は、土地利用型畜産としての酪農の社会的評価との矛盾である。企業型 メガファームは土地との結びつきは弱い。これまでのところ自然と共生した酪農 のイメージが維持されており、このイメージとメガファームでの女性の就業希望 が多いこととは無関係ではないだろう。乳牛や酪農が保持している牧歌的なイメ ージが喪失されれば、養豚経営と同様に外国人労働者の就業の場となるに違いな い。これらのメガファームは酪農産地の土地依存型酪農が築いてきたイメージと は対極にあり、既に揺らぎつつある酪農の自然的なイメージを一掃してしまう恐 れもある。 その3は、アメリカの影響を強く受けた農業近代化理念についてである。農業 生産の近代化は機械設備による生産性の向上、自然環境のコントロールによる生 産の安定化であり、それを農業経営存続の最も有効な方策として評価する傾向が 根強くある。酪農もこうした理念に支えられて急速な規模拡大を実現してきたと いえよう。今日、地域経済や景観の維持、農地の保全などの農業の多面的機能を 再確認しようとしている中で、メガファームをどのように位置付けていくかが問 われている。生乳生産不足の下で、酪農の多面的機能は単なるスローガンとして 処理されることになるのだろうか。メガファームを射程に入れた酪農の社会的価 値、外部経済効果を考えていく必要がありそうである。 参考文献 天間 征「メガファーム」『畜産の研究』55-3、13年3月 永木正和「法人経営体は生乳生産力低下の救世主になり得るか」 『デーリィマン』50-3、12年3月 北海道農業協同組合中央会・ホクレン農業協同組合連合会 『ほっかいどう酪農共同経営の現場から』13年3月 酪農総合研究所「高度な農地整備に関わる調査検討業務 メガファームの実態と今後の課題」13年1月