◎専門調査レポート

こだわるフードサービスへの転進
・・・有限会社筑波ハム・・・
日本大学 商学部 教授 梅沢 昌太郎
1 豚飼いをやめてハム・ソーセージ加工に
 食肉加工とフードサービス
有限会社筑波ハムは、茨城県つくば市でハム・ソーセージ、そしてチーズの加
工と販売を行っている企業である。
また、加工品の売り場に併設して「自然味工房」というレストランを経営して
いる。レストランでは、自社で加工したハム・ソーセージを材料にした料理を提
供している。
年間の売上高は平成13年度で、約3億3,000万円。ハム・ソーセージなどの加工
部門が2億3,000万円、レストラン部門が1億円となっている。
人員の規模は、レストラン部門に8名、加工部門がチーズ工程に3名、食肉加工
部門に8名、そして包装工程に2名が常時雇用されている。販売は社長を含めて4
名が担当している。
レストランは、6人席が1、4人席が10、2人席が2で、最大で約50人が着席でき
る規模である。
お客の入りは昼食時に多く1日当たり平均して約60人だが、少ない日だと20人
程度に落ち込むということである。
食肉加工とフードサービス
有限会社筑波ハムは、茨城県つくば市でハム・ソーセージ、そしてチーズの加
工と販売を行っている企業である。
また、加工品の売り場に併設して「自然味工房」というレストランを経営して
いる。レストランでは、自社で加工したハム・ソーセージを材料にした料理を提
供している。
年間の売上高は平成13年度で、約3億3,000万円。ハム・ソーセージなどの加工
部門が2億3,000万円、レストラン部門が1億円となっている。
人員の規模は、レストラン部門に8名、加工部門がチーズ工程に3名、食肉加工
部門に8名、そして包装工程に2名が常時雇用されている。販売は社長を含めて4
名が担当している。
レストランは、6人席が1、4人席が10、2人席が2で、最大で約50人が着席でき
る規模である。
お客の入りは昼食時に多く1日当たり平均して約60人だが、少ない日だと20人
程度に落ち込むということである。
 |
【レストラン「自然味工房」の入口】
|
研究熱心が転身の動機
実を言うと、私は5年ほど前に、財団法人食生活情報サービスセンターの仕事
で代表者の中野正吾氏にインタビューしたことがあった。その時は「こだわり」
の食の調査がテーマであったが、話の中で茨城県を代表する養豚農家でありなが
ら、それを切り捨てて食肉加工業に転身した話に感動を覚えた。
その時はあまり時間がなかったが、今回改めて調査する機会を得、その事業の
原料調達から加工と販売までをトレースすることとなった。
筑波ハムの創業は、昭和55年と比較的新しい。筑波ハム 代表取締役 会長 中
野正吾氏はこの筑波に生まれ、育った。分家ではあるが中野家4代目で、120年続
く農家の家系である。
農業を継いだとき、食糧難から脱却し食料事情が好転している時代の流れを感
じ、畜産を志したと聞いている。
自分に合っている畜産業は養豚であることを見出し、1頭飼いの規模から始め
て、この地域最大規模の養豚家となった。最盛期には1万2,000頭の豚を肥育する
規模まで成長したが、始めた頃は豚の病気が多く、それが経営の足を引っ張る原
因となっていた。病気を無くす手段を研究するために、県の試験場をいろいろと
訪問した。
当時、千葉県にあった農林省畜産試験場を偶然に知ることとなり、訪問するう
ちにハムの加工技術を習得した。
畜産試験場での手作りのハムの評判が
良かったが、そこが筑波に移転してしまい、作ることが出来なくなってしまった。
そこで1頭という小規模で、中野氏の自宅で加工を始めることになった。
 |
【品揃え豊富な筑波ハムの製品】
|
抵抗の大きかった加工部門進出
自宅で加工したハムが評判を呼び、本格的な加工を考えた。豚価の安値が続き、
養豚業の将来に不安を抱いていたこともあって、食肉加工へ進出の一歩を踏み出
したのである。しかし、食肉加工領域への進出には、大きな抵抗があった。
まず、保健所の壁が厚かった。保健所に相談したところ、そこで食べさせるだ
けなら良いが、持ち帰りは駄目だと言われた。保健所の本音は、食肉加工を農家
にはやらせたくなかったところにあると、中野氏は語る。
ならば本格的に許可を得て販売までしようと、保健所の要求を全て満たす、文
句のつけようの無い加工場を作り、その許可を得ることができた。
資金調達も、大きな問題であった。当時は養豚業を営んでいたので、1万2,000
頭の養豚事業の維持に資金需要は手一杯で、加工事業に回す余裕はなかった。制
度資金に頼る外に手だてはなかったが、当時の農林中金は加工事業への融資につ
いては「加工は商工業の分野」という見方から商工中金の領域であるとして、近
代化資金の融資に難色を示した。
これに対し中野氏は、「農家が付加価値を付けたものを作り、独自の価格を付
けては駄目だという論理はない」と反発した。
いろいろな曲折を経て、農林中金から1,250万円の資金を借りることができ、
資金問題は軌道に乗った。
また、加工事業に対する抵抗は、農業側からもあった。養豚場を潰しては不名
誉になるという考えが、試験場の人たちに強かったのがその原因である。「加工
場はダメ。大手企業が力を持っている。農家がやっても…」と言われ、「天秤棒
を折った(事業に失敗した)」先輩の話などを聞かされたこともあったが、それ
に対して、「時代が違う」と、逆にその人々を説得した。
「おいしければ買ってくれる」という思いは強く、最後には失敗しても、
「(養豚の負債は)夜逃げすれば良い。親が死ぬまでは我慢すれば…。」と覚悟
を決めた。結局、「そこまで考えているのなら」と、試験場の場長から指導の許
可を得ることができたという。
原料へのこだわり
5年前にインタビューしたとき、「養豚場のにおいが、精肉に移る」と言われ、
その言葉が強く印象に残っていて、今回の調査の動機ともなっている。
かつて豚コレラ防止のために豚舎に消毒薬クレゾールを散布したところ、「肉
から消毒薬の臭いがする」とクレームが来たことがあった。
えさも当然肉質に影響するので、配慮が必要になる。「人間が食べれるような
えさ」で飼育することが重要になる。
生肉用と加工用の肉は一緒であると、中野氏は力説する。生肉として本当にお
いしくないものは、加工用に仕向けてもおいしくないということである。
肉質では、保水性が問題になる。パーツで購入した部分肉は、パサパサになっ
てクレームがつく。
原料が悪いと、ソーセージなどはまとまらず、結着材を使うことになる。しか
し、そうなると味の悪い製品となってしまい、意に反する結果となる。
肉質を保つために、個体差が出ないように、農場は1つに限定する必要があり、
また、同じ品種系統での育成が求められている。
飼育環境の整備がきちんと出来ていないとダメということで、経済連の紹介を
得て、近隣の岩間町にある林牧場に、原料となる豚肉を委託していた。しかし、
この養豚場は後継者難で廃業してしまった。林農場の豚肉は、何処にでもあるよ
うな肉ではなかった。保水性が高く、肉の繊維が違い、肉の香りが違ったという。
今は茨城経済連から仕入れている。後に触れるが、茨城経済連とは特別の肥育
契約を結んでいて、経済連(茨城くみあい畜産株式会社)の養豚場は、筑波ハム
向けに特別に肥育した豚を出荷している。
肥育日数も、通常のSPF豚の5カ月出荷よりも長い。5カ月の飼育では、肉の細
胞が弱くなり、おいしい肉とはならない。筑波ハム仕向の豚は、7カ月をメドに
じっくり肥育されている。
中野氏は美味しい豚肉は、見た目が悪いのだと言う。今、消費者が買っている
のは、「ピカピカ光ったみずみずしい」豚肉であり、本当はおいしくない肉だと
言う。
原料となる豚肉はと畜されて、翌日には筑波ハムに入荷される。
品質の点から現在はローズ・ポークの系統で統一しているが、それでも肉質に
ばらつきが出るという。
納入されるものすべてが「締まりのある豚」とは限らず、中には「締まりのな
い豚」も入ってくるが、後者については使っていない。
ハム・ソーセージの味は、漬け込む期間によっても異なる。7日間のつけ込み
には7日間の味がして、15日間のつけ込みには15日間の味がするそうである。
レストランと加工体験コーナー
レストランは、昭和62年に開業した。体験コーナーの延長線として、試食の
場所として、位置付けられてきた。
レストラン部門は、最初は「製品販売の足し」と考えていた。しかし、食べて
もらわないと売れないことに気がつき、レストラン部門への本格的な取り組みの
姿勢が取られることになった。
ところが、レストラン部門は「儲けが少ない」部門となっている。確かに、常
時8名の人を雇っていて1億円の売上高では経営は苦しいと考えられる。社会保険
などを含めた福利厚生費を考えると、理論上は8,000万円以上の人件費が固定費
としてかかってくる。また、料理素材コストは4割近くなると考えられ、4,000万
円がコストとなる。事業のコンセプトから、品質を落とすことは出来ないため割
高な原料コストになる。
上記のように単純に考えても、原料費と人件費だけで、赤字になってしまうこ
とになる。「このままでは儲からない、足を引っ張るだけ。何か新しいものを。」
ということで、2階を結婚式場にし、ブライダル事業にも進出した。しかし、こ
ちらも人件費が高くなり、この事業もあまり儲かっていないのが現状である。
中野氏自身も言われているように、かなり厳しい経営ではあるが、ハム・ソー
セージは自家加工なので、コストをさらに低くすることは可能である。また、雇
用者をパートタイマーにするなどの合理化の余地はある。
しかし、販売促進的な意味があるので、「儲からない」部門であってもサービ
ス部門の存在は重要である。
ハム・ソーセージの加工体験コースでは顧客に一番難しいところを教えている。
乾燥、スモークそしてボイルなどの勘どころを教え、特に、スモークの工程では、
製品の量と天気の関係を教えている。そして、ハム・ソーセージをどうやって食
べたらおいしいかを、レストランで実地に体験してもらっている。本当のハム・
ソーセージを知ってもらう意味で、レストラン部門の貢献度は大きい。
1年間で観光バス300台の訪問があり、大手の観光バス会社の買い物ツアーの立
ち寄り指定店となっている。当然のことながら東京からの客が多い。
しかし、重要なことは、筑波という地域の顧客が多いことである。学園都市と
してのこの街は、また公務員の街でもある。昔の味を懐しんで転勤した先からの
注文も多く、宅配便での販売の主要の顧客となっている。また、転勤の際に筑波
ハムのことを継承事項としている人も多く、その人々が顧客拡大の核となってい
る。
もっとも、地元タクシーの運転手さんによると、評判は高いが価格も高いので、
常時家族連れで使えるような店ではないという。顧客が限定されていて、そのこ
とが「夜に弱い」原因とも言えそうである。
 |
【落着いた雰囲気のレストラン。
中央のダルマストーブが興味を引く】
|
|
|
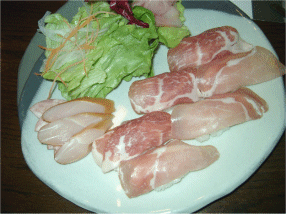 |
【おすすめの1つ、生ハム寿司】
|
直販による販売チャネル
加工事業を始めた3年間は、日光の有名ホテルである金谷ホテルのみに販売し
ていた。このホテルの探し求めていた味と一致して、試作の段階からの深い関係
があった。このホテルとの取引のウエイトが、一時は15%にまでなった時もあっ
た。なお、金谷ホテルには量は少なくなったものの現在も販売している。
現在の主な販売チャネルは、自社の店舗とデパート、そして宅配の3つから成
り立っている。
販売部門の売上高2億3,000万円のうち、3,000万円はデパートを通しての売り
上げである。デパートとの取引では、最初は剣もほろろだった。欠品ペナルティ
が高く、返品あり、そして支払いサイトが2カ月と、あまり有利な条件ではなか
った。
デパートでの販売は、実際には店頭に「見本」を置き、その注文伝票を元に宅
配で配送している。手数料が30%と高く、粗利益40%の大半を占めていて、手元
に利益が「残らない」と言う。
しかし、デパートに出店しているという信用度が大事であり、あくまでもPRの
ためと言う。
西武デパートとの取引が一番長く、「一村一品」キャンペーンに参加している。
また、高島屋の「全国味百選」にも出品している。
「養豚の安定のために加工事業をはじめたので、その姿勢が見えないなら取引
をやめ、金谷ホテルのみにする」と、中野氏は言う。創業の精神をあくまでも貫
く、心意気と根性と言える。
売れるようになるまでに、2年かかった。発色剤が少なく、酸化防止剤を使っ
ていないので、宣伝中に変色してしまう。1時間で色が変わるので、ホテルでは
使うことができないなどのハンディがあり、販売に苦労したとの話であった。一
般の人は発色剤を嫌うが、殺菌剤としての効果があるため、少量使用している。
顧客の客単価は、1,500円程度。場合によっては、800円のこともある。50歳か
ら60歳の女性が買ってくれると、製品が良く売れるようになるという。
原料は1頭丸ごとなので、いろいろな製品を製造している。骨付きハムの人気
が高い。次に人気の高いウインナー・ソーセージの価格でさえ、100グラム360円
である。大手のものは100円程度であるから、かなり高い価格になる。しかし、
採算を考えると、それでもまだ厳しいとのことであった。
だが、価格が高くても売れるという自信があることも事実である。「高くても
良い」という顧客が増えているということを、中野氏自身実感として感じている。
生産、加工、台所までの一貫システム
「生産、加工そして台所まで一貫すべき」と言うのが、中野氏の信条である。
しかし、その全ての面倒は中野氏一人では見切れなくなった。「養豚、豚飼いは
誰でも出来る」と考え、養豚は人に任せることにした。しかし、万博の3年ほど
前で、景気が良かったため、養豚農家で働いてくれる人がいなかった。そこで林
牧場に生産を任せることにしたのであった。
筑波ハムはチーズも作っている。「自分で使うものは自分で作る」ということ
で、レストランで使うことを目的としているが、店頭でも販売されている。
普通のチーズの5倍の手間と時間をかけている。熟成に2年の時間をかけて、
「匂いが強い」独特のチーズが出来上がる。「ナチュラル吉野」というブランド
でチェダー・チーズ、マロン・チーズ(特産の栗をチーズに加えた、お菓子風の
チーズ)そしてドリンク・ヨーグルトを製造している。
この「吉野」というのは、チーズ製造の技術者である吉野氏の名前に由来して
いる。
注目されることは、研究集団との共同である。つくば市という研究学園都市の
機能を活用して、農林水産省の(旧)畜産試験場加工部の「先生」の助言を得て
いるのである。「自社に研究室が無いので、問題があったら持っていく」、そう
すればすぐに原因を調べてもらえるのである。
レストランでも「最初はコックを入れることは考えていなかった」。
今のシェフは客として来店した際、「せっかくの店の雰囲気と料理のコンセプ
トが一致せず、もったいないですね。」と忠告してくれた人である。中野氏が当
レストランで働くことをもちかけた。シェフ以外にも料理学校卒業生2名が、調
理に従事している。レストラン部門の役割が大事になったのである。
一連の事業を「道楽で始めたのだが、道楽でなくなった。」と、中野氏は述懐
している。苦しい時期を経て、比較的安定した今、事業の使命を改めて感じてい
るようであった。
「オーナーの喜びが、従業員の喜びとなる会社にしたい。客はその空気を感じ
る。嫌々でのサービスはだめ。儲からなくても良い。長続きすればよい。」と、
中野氏は語る。
筑波ハムには、定年制はない。「本当にやる気のある者が残り、気の合うもの
が集まれればよい。」と、会社のあり方を語る。
「規模拡大は考えていない。今の規模がちょうど良い。しかし、もう少し利益
を出せる企業にしたい。」と言う。
もっとも、ただ利益だけには走らないとも明言している。「気がついたら客が
いなかった」という事態は、避けたいと。
品質を保つために、原料の調達構造にはこだわっている。「経済連がだめにな
っても、自分で農家を育てる」と、理想を語る。かつて林牧場を選択したのも、
その一環と言うことである。
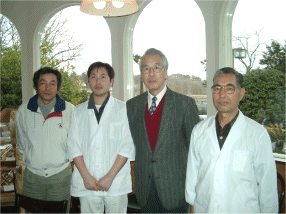 |
【右側から(有)筑波ハム 代表取
締役会長中野氏、筆者、工場長岩
浪氏、茨城くみあい畜産(株)推
進部副部長大串氏】
|
2 筑波ハムの原料供給者としての経済連
系統豚の造成
茨城県系統豚供給センター
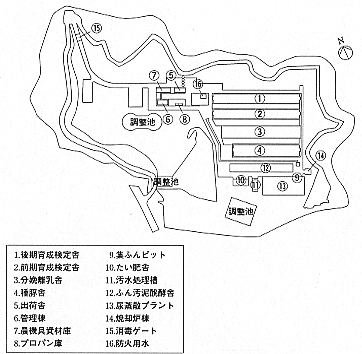 筑波ハムに原料豚を供給しているのは、茨城県農業協同組合連合会(茨城経済
連)が運営する茨城県系統豚供給センターである。厳密に言うと、施設の設置は
茨城県が実施し、その運営を茨城経済連が行う仕組みになっているが、実際はそ
の系列企業である茨城くみあい畜産株式会社が同センターの管理を委託されその
役割を担っている。このセンターは平成7年に完成し、同センターの職員(場長
1名、職員3名)は出向という形で派遣されている。
今回、同社推進部副部長の大串勝輝氏が案内してくれた。大串氏は獣医師であ
り、以前この茨城県系統豚供給センターの場長を努め、立ち上げの主役であった。
その役割を大串氏は、
「本県では優良基礎豚によって造成された系統豚(ローズL−2、ローズW−1)
と国の系統造成豚(サクラ201)を利用して銘柄豚肉ローズポークを始めとす
る高品質豚肉の生産を推進している。このような背景の中で、畜産の活性化によ
る地域振興と系統豚の需要の増加に応えるため、系統豚の種の維持、ならびに特
定病原菌に感染していない清浄(SPF)で高能力な種豚を安定的に供給するため」
と述べている(「養豚の友」1995年11月号)。
養豚での重要課題は病気であり、それも貿易のグローバル化に起因する発生が
多く、テロではないが「世界同時多発」の傾向がみられる。
PRRS(豚繁殖・呼吸器障害症候群)やAD(オーエスキー病)がその代表といえ
るが、「繁殖成績が上がっているにもかかわらず、肥育成績が落ちる。」のはそ
れら病気が原因であり、それらを解決できればまだ養豚事業の将来は明るいと力
説する。
厳しい品質要求
茨城県にはローズポーク指定農場が39カ所あり、3万3,000頭から3万4,000頭の
系統豚が飼育されている。
その豚を茨城県経済連が集荷して販売しているが、筑波ハム向けは1,000頭か
ら1,200頭となる。
筑波ハムの中野会長の要求は厳しく、イタリアにおけるハム用豚なみの14カ月
飼育とはいわないまでも、生後7カ月以上の肥育期間をかけてほしいと要望され
ている。
ローズポークは2000年2月20日幕張メッセで開催された「2002食肉産業展」で
の全国の銘柄ポーク好感度コンテストで、鹿児島県の黒豚などを押さえて、No.1
に選ばれた程の豚肉であるが、中野氏からは、まだまだ満足はいただいていない。
また大串氏は少しでも品質の格差をなくすために、1販売先には1農場からの供
給が理想と語る。
大串氏によると筑波ハムはテーブル・ミートと同じ品質を要求しており、旨味
重視で品質的には問題ないとしている。
また大串氏は、1販売先には1農場からの出荷にしたいと語る。
現在筑波ハムへは、前述の林農場が廃業したため、一時的に同社の水海道農場
から出荷している。しかし、年間1,000頭規模の生産能力しかなく、筑波ハムは
月100頭の供給を求めており、ギャップが生じている。この要望に応えるために、
新しい農場を建設した。新農場は14年2月から分晩が開始され、秋からはここか
ら供給されることになる。
筑波ハムに原料豚を供給しているのは、茨城県農業協同組合連合会(茨城経済
連)が運営する茨城県系統豚供給センターである。厳密に言うと、施設の設置は
茨城県が実施し、その運営を茨城経済連が行う仕組みになっているが、実際はそ
の系列企業である茨城くみあい畜産株式会社が同センターの管理を委託されその
役割を担っている。このセンターは平成7年に完成し、同センターの職員(場長
1名、職員3名)は出向という形で派遣されている。
今回、同社推進部副部長の大串勝輝氏が案内してくれた。大串氏は獣医師であ
り、以前この茨城県系統豚供給センターの場長を努め、立ち上げの主役であった。
その役割を大串氏は、
「本県では優良基礎豚によって造成された系統豚(ローズL−2、ローズW−1)
と国の系統造成豚(サクラ201)を利用して銘柄豚肉ローズポークを始めとす
る高品質豚肉の生産を推進している。このような背景の中で、畜産の活性化によ
る地域振興と系統豚の需要の増加に応えるため、系統豚の種の維持、ならびに特
定病原菌に感染していない清浄(SPF)で高能力な種豚を安定的に供給するため」
と述べている(「養豚の友」1995年11月号)。
養豚での重要課題は病気であり、それも貿易のグローバル化に起因する発生が
多く、テロではないが「世界同時多発」の傾向がみられる。
PRRS(豚繁殖・呼吸器障害症候群)やAD(オーエスキー病)がその代表といえ
るが、「繁殖成績が上がっているにもかかわらず、肥育成績が落ちる。」のはそ
れら病気が原因であり、それらを解決できればまだ養豚事業の将来は明るいと力
説する。
厳しい品質要求
茨城県にはローズポーク指定農場が39カ所あり、3万3,000頭から3万4,000頭の
系統豚が飼育されている。
その豚を茨城県経済連が集荷して販売しているが、筑波ハム向けは1,000頭か
ら1,200頭となる。
筑波ハムの中野会長の要求は厳しく、イタリアにおけるハム用豚なみの14カ月
飼育とはいわないまでも、生後7カ月以上の肥育期間をかけてほしいと要望され
ている。
ローズポークは2000年2月20日幕張メッセで開催された「2002食肉産業展」で
の全国の銘柄ポーク好感度コンテストで、鹿児島県の黒豚などを押さえて、No.1
に選ばれた程の豚肉であるが、中野氏からは、まだまだ満足はいただいていない。
また大串氏は少しでも品質の格差をなくすために、1販売先には1農場からの供
給が理想と語る。
大串氏によると筑波ハムはテーブル・ミートと同じ品質を要求しており、旨味
重視で品質的には問題ないとしている。
また大串氏は、1販売先には1農場からの出荷にしたいと語る。
現在筑波ハムへは、前述の林農場が廃業したため、一時的に同社の水海道農場
から出荷している。しかし、年間1,000頭規模の生産能力しかなく、筑波ハムは
月100頭の供給を求めており、ギャップが生じている。この要望に応えるために、
新しい農場を建設した。新農場は14年2月から分晩が開始され、秋からはここか
ら供給されることになる。
 |
【経済連の水海道農場。
14年秋からは新しい農場からの
出荷を予定している。】
|
肉の味覚の違いは、えさの内容にある。筑波ハム向けには大麦を30%入れたえ
さを与えた、特別飼育の豚を販売している。
系統豚はローズポークのブランドで出荷されているが、系統内での出荷頭数で
のシェアは3分の1程度である。シェアを拡大することが必要であり、その意味か
らも筑波ハムは核となる重要な顧客といえる。
もっとも、中野氏は自社の製品にローズ・ポークの名称を使わないことにして
いる。他の人と同じローズポークを使っている、と言われるのが心外というのが
その理由である。
3 多様化する食肉の高付加価値化の試み
筑波ハムは養豚という生産プロセスを、他者に任せることで事業の転身を図っ
た。しかし、生産者の精神が健在なことは、原料豚への要求の高さから分かる。
生産からの転身は、養豚とフードサービス事業をどう両立させるかというマネジ
メント上の問題が大きかったと見ることができる。
筑波ハムの多角化の特色は、垂直と水平の両面に見られる。
垂直的な多角化は、販売とフードサービスという消費者直結のチャネルを開発
したことである。
ハム・ソーセージと生ハムそしてチーズなどの製品の開発は、水平的多角化と
言える。
さらに、体験学習とサービスを行っている。これは促進活動の一環と位置づけ
られる。併せて、「本当のハム・ソーセージとは何か」を、消費者に知ってもら
う、社会的使命も果たしているとも考えることができる。
昨今の一連の農業をめぐる不祥事は、食肉への信頼感を揺るがすものとなって
いる。筑波ハムのさまざまな試みは、食の生産と消費の距離を短くし、相互のコ
ミニュケーションを潤沢にするものと位置付けることができる。その事業活動を
通して、農業者の魂に、消費者は触れることができる。
このような試みは、茨城県経済連も積極的に行っている。経済連本部の傍に建
設された「ポケットファームどきどき」は、その具体的な姿であると言える。こ
の原型は、三重県の「モクモクファーム」にある。
ここでは農産物の直販、レストラン、パン工房、手作り体験コーナーがあり、
また遊園施設、動物との交流そして散策の道など、多様で多面的な生活のニーズ
に応える施設を目指している。
その場で焼き上げられているパンに人気があった。また、ここでも手づくりハ
ム・ソーセージが販売されている。買ってみて試食したが、メーカー品では味わ
えない、本来の味を楽しむことができた。
また、ここの直販コーナーを活用して、ベンチャー農業を立ち上げた農村女性
もいる。農村活性化にも貢献しているといえる。
このような試みも生産と消費の距離を縮め、相互の信頼を深めるものとなって
る。
これらの新しいチャレンジを、温かく見つめ育てていくことが、日本の畜産そ
して農業を希望のあるビジネスに育てると考えている。
 |
【ポケットファームどきどき】
|
元のページに戻る


食肉加工とフードサービス 有限会社筑波ハムは、茨城県つくば市でハム・ソーセージ、そしてチーズの加 工と販売を行っている企業である。 また、加工品の売り場に併設して「自然味工房」というレストランを経営して いる。レストランでは、自社で加工したハム・ソーセージを材料にした料理を提 供している。 年間の売上高は平成13年度で、約3億3,000万円。ハム・ソーセージなどの加工 部門が2億3,000万円、レストラン部門が1億円となっている。 人員の規模は、レストラン部門に8名、加工部門がチーズ工程に3名、食肉加工 部門に8名、そして包装工程に2名が常時雇用されている。販売は社長を含めて4 名が担当している。 レストランは、6人席が1、4人席が10、2人席が2で、最大で約50人が着席でき る規模である。 お客の入りは昼食時に多く1日当たり平均して約60人だが、少ない日だと20人 程度に落ち込むということである。



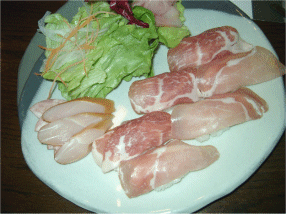
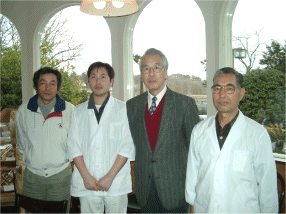
筑波ハムに原料豚を供給しているのは、茨城県農業協同組合連合会(茨城経済 連)が運営する茨城県系統豚供給センターである。厳密に言うと、施設の設置は 茨城県が実施し、その運営を茨城経済連が行う仕組みになっているが、実際はそ の系列企業である茨城くみあい畜産株式会社が同センターの管理を委託されその 役割を担っている。このセンターは平成7年に完成し、同センターの職員(場長 1名、職員3名)は出向という形で派遣されている。 今回、同社推進部副部長の大串勝輝氏が案内してくれた。大串氏は獣医師であ り、以前この茨城県系統豚供給センターの場長を努め、立ち上げの主役であった。 その役割を大串氏は、 「本県では優良基礎豚によって造成された系統豚(ローズL−2、ローズW−1) と国の系統造成豚(サクラ201)を利用して銘柄豚肉ローズポークを始めとす る高品質豚肉の生産を推進している。このような背景の中で、畜産の活性化によ る地域振興と系統豚の需要の増加に応えるため、系統豚の種の維持、ならびに特 定病原菌に感染していない清浄(SPF)で高能力な種豚を安定的に供給するため」 と述べている(「養豚の友」1995年11月号)。 養豚での重要課題は病気であり、それも貿易のグローバル化に起因する発生が 多く、テロではないが「世界同時多発」の傾向がみられる。 PRRS(豚繁殖・呼吸器障害症候群)やAD(オーエスキー病)がその代表といえ るが、「繁殖成績が上がっているにもかかわらず、肥育成績が落ちる。」のはそ れら病気が原因であり、それらを解決できればまだ養豚事業の将来は明るいと力 説する。 厳しい品質要求 茨城県にはローズポーク指定農場が39カ所あり、3万3,000頭から3万4,000頭の 系統豚が飼育されている。 その豚を茨城県経済連が集荷して販売しているが、筑波ハム向けは1,000頭か ら1,200頭となる。 筑波ハムの中野会長の要求は厳しく、イタリアにおけるハム用豚なみの14カ月 飼育とはいわないまでも、生後7カ月以上の肥育期間をかけてほしいと要望され ている。 ローズポークは2000年2月20日幕張メッセで開催された「2002食肉産業展」で の全国の銘柄ポーク好感度コンテストで、鹿児島県の黒豚などを押さえて、No.1 に選ばれた程の豚肉であるが、中野氏からは、まだまだ満足はいただいていない。 また大串氏は少しでも品質の格差をなくすために、1販売先には1農場からの供 給が理想と語る。 大串氏によると筑波ハムはテーブル・ミートと同じ品質を要求しており、旨味 重視で品質的には問題ないとしている。 また大串氏は、1販売先には1農場からの出荷にしたいと語る。 現在筑波ハムへは、前述の林農場が廃業したため、一時的に同社の水海道農場 から出荷している。しかし、年間1,000頭規模の生産能力しかなく、筑波ハムは 月100頭の供給を求めており、ギャップが生じている。この要望に応えるために、 新しい農場を建設した。新農場は14年2月から分晩が開始され、秋からはここか ら供給されることになる。

