緒 言
本研究の目的は牛乳乳製品摂取が子供の成長にどのような重要な役割を有しているかを、体組成やそれに関与する液性因子を測定することにより、より明確に確認しようとするものである。発育の活発な年齢では、カルシウムやたんぱく質などの重要な栄養素が、摂取しやすく消化吸収も良好な形で含まれていることが望ましい。牛乳乳製品はこの面から重要かつ有効な食品と考えられる。
それと同時に近年の健康上の最も大きなテーマの一つは生活習慣病への対応・予防であり、各種の栄養素、食品の意義や重要性が論じられている。しかしながら必ずしもエビデンスに基づいた議論のなされていない場合も見受けられる。生活習慣病の危険因子を検討することにより、牛乳乳製品がそれとどのように関連しているのかを明らかにすることも必要であろう。
この検討により牛乳乳製品の小児期・思春期における重要な意義を確認し、不適切な危惧を払拭することが出来ると期待される。
対象・方法
対象者は小学校4年であり、本人および家族に対しあらかじめ検査の方法や意義について文書で説明をした。調査地域は静岡県西部の農山村地区である。学校長および町村行政担当者との共同事業として行われた。対象者数は3年間の合計で小学4年生男子614名、女子563名であった。
対象者については身体計測を行い、身長、体重の計測値から過体重度(肥満度)を以下の式で算出した。
過体重度(%)= 100×(実測体重−標準体重)/標準体重
過体重度が+20%以上の児を肥満と判定した。+20%以上〜+30%未満を軽度肥満、+30%以上を中等度・高度肥満と分類した。なお本研究は成人病予防活動として希望者を対象としているため、過体重児の割合が高くなった。
採血を行い脂質(総コレステロール、HDLコレステロール)、レプチンの血清中濃度を測定した。総コレステロールは200mg/dl未満を正常範囲とし、200mg/dl以上〜220mg/dl未満を境界値、220mg/dl以上を高値と判定した。実際の生活習慣、特に牛乳摂取などを含む食事について書面にてアンケート調査を実施した。
肥満について軽度肥満には集団指導、中等度・重度に対しては個別指導を実施した。
結 果
男子614名のうち過体重度+20%未満の非過体重児は503名(81.9%)であった。20%以上〜30%未満の軽度肥満の小児は53名(8.6%)、30%以上の児は56名(9.1%)であった。女子ではそれぞれ493名(87.6%)、39名(6.9%)、30名(5.3%)であった(表1)。
|
表1.過体重度の分布
|
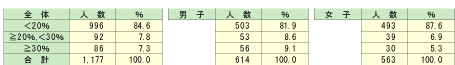 |
総コレステロールが200mg/dl未満の正常範囲の者(男/女)は499名(81.3%)/440名(78.2%)であった。境界値を呈した児は79名(12.9%)/80名(14.2%)であった。220mg/dl以上の高値を示した者は36名(5.9%)/43名(7.6%)であった(表2)。
|
表2.血清総コレステロール値の分布
|
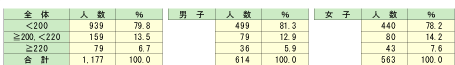 |
レプチン値は過体重度と有意の相関を示した。同一の過体重度でも女子のレプチンがより高値であった(図1)。
|
図1.過体重度とleptinの相関
|
|
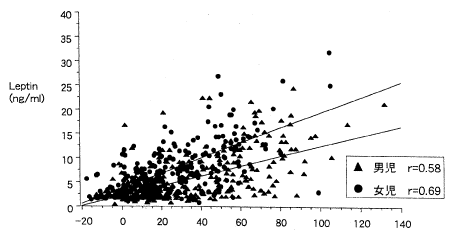 |
|
| 過体重度(%) | |
朝食はほとんどの児が摂取していた。朝食を一人で摂る者の比率は男62名(5.3%)、女77名(6.2%)であった。食事中・食後の飲料として牛乳を飲んでいる者は総計229名(22.8%)であったが男子の152名(29.2%)に比べ女子では100名(15.9%)とその半分であった(表3)。運動後に牛乳を飲む者は男53名(10.2%)、女38名(7.9%)、総計91名(9.1%)であった(表4)。その他の食事中・食後の飲料としては日本茶・中国茶が585名(58.3%)と最も多かった。運動後では男子がスポーツ飲料の比率が高い(173名、33.4%)のに比べ、女子では日本茶・中国茶が222名(46.0%)と最も多かった。
|
表3.食事中や食後に良く飲む飲み物
|
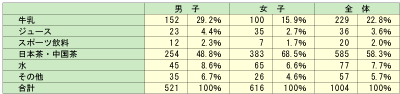 |
|
表4.運動後に良く飲む飲み物
|
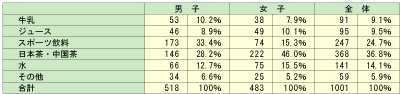 |
間食は大部分(88.4%)の者が摂っていたが、夕食前(79.2%)に摂る者が多かった。ヨーグルト・牛乳類の摂取は男子の187/521(35.8%)、女子では119/484(24.6%)と男子でより高率であった(表5)。
|
表5.おやつはどんなものが多いですか(複数回答)
|
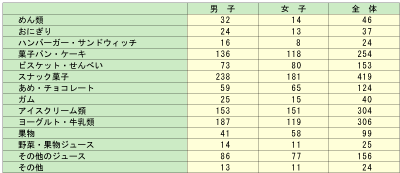 |
3年間の経過観察のなされた376名について過体重度の変動では、検診時に正常体重であった264名の過体重度の増加度(平均値±SD)は0.07±7.99であった。肥満の事後指導の出席状況では出席群(78名)では−0.76±12.76と肥満は改善傾向を示した。反対に指導を欠席した34名では4.33±10.28と3年後も過体重度は増加しており、事後指導の出席状況と肥満の進行が関連していることが明らかとなった(表6)。
|
表6.事後指導の出欠と3年後の過体重度(%)の増加
|
|
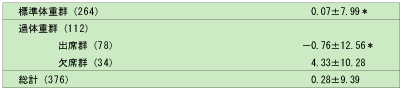 |
|
| (*欠席群に比較してp<0.05で有意差) |
|
考 察
本研究は3年間で計1,000名を越える対象者について行われ、現在も継続されている。この研究では牛乳と成長や脂肪、骨・カルシウムなどの体組成との関連を検討することを目的としている。本年度はこれまで3年間の結果をまとめ成果を確認し、今後の方向性を決定することができた。
本研究の対象は文書により研究内容を説明し、それぞれの調査項目について理解を得て行われた。文書により同意を確認した。この様な調査・研究の重要性は十分に認識されているが、近年では対象者の権利や意志を十分に尊重することが必須のこととなっている。我々は行政および教育担当者との協力のもとに行った。都市地域でないことは十分な医療・健康施設があるとは言えず、この点からも本研究は貢献していると考えられた。
これらの背景があるため対象者は農山村の児童である。これらの結果は必ずしも都市部の対象者と同一とは言えない可能性も否定できない。しかしながら以前に存在した人口密集地域とそれ以外の地域の差異が小さくなっていることが指摘されている。肥満の頻度、食事内容など、地域差が余り多くないと指摘する報告もある。今回の結果は農山村を対象とはしていても、より広くわが国小児の現状を反映していると考えられる。
体重に関しては上記の方法で説明後に同意を十分に確認した上で行った。したがって肥満小児の比率がやや高くなっている。現在の本邦の過体重度+20%以上の小児の割り合いはおよそ10%前後の報告が多い。今回の肥満小児の比率は男子18%、女子12%と一般的な比率を上回っている。肥満対象者数は男子で109名、女子69名と研究には十分な対象者数が得られた。
脂質の中ではまず総コレステロールを検討した。総コレステロール値の標準範囲については成人のみならず小児においても議論のあるところである。これまでは200mg/dlを標準の上限とし、これ以上を異常値とすることが多かった。成人の基準として220mg/dlないし240mg/dlがあげられている。小児では220mg/dl以上を介入の対象とするのが適切と考えられるが、200〜220mg/dlの範囲は予防医学的意義から重要と考え、これを境界値として取り扱うこととした。
この基準で検討すると200mg/dl以上の児の比率は男子18%、女子22%とやや高値であった。220 mg/dl以上のものは計79名であり、介入が必要であると思われた。これらは必ずしも肥満と関連していない例も少なくなく、遺伝的素因の関与も考えられる。高コレステロール血症に対する指導は素因などの個人的要因に基づいてなされるのが望ましく、一律な食事指導は必ずしも適切でない場合もある。一般には人的ないし施設的要素から集団的指導が行われることが多い。今回我々は顕著な例では個別指導を行った。後述するごとく指導は効果的であると考えられ、それをいかに有効な形態で実施するかも極めて大きな影響を与えると思われる。
血清レプチンは発見されてから未だ10年程度であり、その病態生理的意義や役割については研究がなされている。その濃度は体重の変動と関連し、今回の検討でも過体重度との明確な相関が認められた。レプチン濃度は思春期以後では男女差が明確になるが、小児期には男女差は顕著ではない。今回の検討対象は小学4年生であり早熟傾向であれば思春期の初期である場合もあるが、多くは思春期に至っていないと考えられる。肥満の正確な定義は単なる体重の増加ではなく、体脂肪の増加であることより、脂肪量(率)を反映するレプチンが肥満ないし体組成の指標として有用である可能性が考えられた。今後は各種の体組成の指標との関連をより詳細に検討すべきであろう。
食事内容・形態についても興味ある結果が得られた。朝食を摂取しない児の存在が問題となっているが、今回の検討では数%程度であった。他の研究ではより高い値も報告されることもあるが、生活環境の特質かも知れない。
食事中・食後に乳製品を摂取しているものは男子では約30%と比較的高い値であったが、女子では15%程度でありかなり低値であった。運動後の飲み物についても男子に比べ女子では低い値であった。この傾向は間食の面からも認められ、男子が35%前後であるのに女子ではおよそ25%であり、やはり男子に比べ低値であった。近年わが国では、思春期以後の若年女性における体重減少、骨密度の低下などが問題とされ、今後の進行が懸念されまた予防も重要な課題となろう。今回の対象者は小学生であり、計測や検査上でこの様な変化は確認されていないが、すでに女子において乳製品の摂取が男子と比較してかなり低値であったことは、今後の低体重や骨塩量低下の促進因子となると考えられる。本研究の事後指導は主として肥満・高脂血症などを中心としてなされている
が、今後は栄養素の摂取不足やバランスの乱れなどについても啓蒙する必要性が示唆された。
事後指導をどのような形で行うべきかは、このような研究の成否において重要な項目となる。
今回体重面に関し事後指導の対象になった者のうち、それに出席したか否かで3年後の体重に有意の差異が認められた。指導に出席/欠席の差により3年後の体重(過体重度の変動)は−0.76/4.33とその差は統計学的にも有意であった。経過の良好なもの、ないしは意欲のあるものが指導に参加している可能性は否定できないが、少なくとも欠席は危険因子と考えられ、指導が何らかの役割を果たしている可能性は十分に考えられよう。また小児肥満は治療抵抗性ないし難治である場合も少なからず経験されるが、どのような理由にしろ肥満が進行しないでわずかではあるが軽快していることが示されていることは、一般的な肥満の指導・治療にあたって念頭に置くべき結果であろう。
結 論
1)静岡県西部地区の小学4年生に対し3年間にわたり体格測定および血液検査(脂質、レプチン)を行い指導を実施した。
2)対象者は1,000名を上回ったが行政や教育機関と協力することにより事業を順調に進行させることができた。
3)肥満についいては計178名について解析が可能であった。レプチン値は過体重小児の体組成解析における指標の一つとなる可 能性が考えられた。
4)高コレステロール血症は境界例を含め238名であった。これらには遺伝的素因を有していると考えられるものもあり、それに応じた 指導・介入が必要と考えられた。
5)乳製品の摂取量は女子においてすでにこの年令においても男子に比べ明らかに低値であった。このことは思春期以後の若年女 性の低体重や骨塩量の低下の増悪因子となると思われ、適切な栄養学的指導・啓もうの必要性が示唆される。
6)事後指導がそれ以後の肥満の進行防止に有効である可能性が示された。
1)藤澤泰子、大関武彦:内科医のための思春期外来。思春期の身体的特徴。モダンフィジシャン22: 953, 2002.
2)大関武彦、中川祐一、中西俊樹、稲葉泰子:小児の肥満の特徴とその管理。日本臨床 59: 597, 2001.
3)大関武彦、中西俊樹、中川祐一ほか:小児医療から成育医療へ.小児肥満とその管理.小児科診療61:1119, 1998.
4)大関武彦:摂食異常症の早期発見と治療.日本小児科学会雑誌102:951, 1998.
5)大関武彦、花木啓一、浦島裕史、白木和夫。成長・発達からみた思春期の特徴−ムからだの視点から。小児内科 29: 515, 1997.
6)Nakanishi T: Sexual dimorphism in relationship of serum leptin and relative weight for the standard in normal−weight, but not in overweight, children as well as adolescents. Eur J Clin Nutr. 55:989, 2001.
7)Ohzeki T, Hanaki K, Motozumi H, et al.: Skinfold thickness at ulnar, triceps, subscapular, and suprailiac regions in 1,656 Japanese children aged 3−11 years. Ann Nutr Metab 36: 251, 1992.
8)Ohzeki T, Hanaki K, Ishitani N, et al.: Usefulness of a stature−based standard of skinfold thickness, especially for short children. Am J Hum Biol 7: 237, 1995.
9)大関武彦、衣笠昭彦:小児の肥満。日本肥満学会 肥満症診療のてびき編集委員会編、肥満・肥満症の指導マニュアル。東京:医歯薬出版 p160, 2001.
10)Ohzeki T, Hanaki K, Motozumi H, et al: Prevalence of obesity, leanness and anorexia nervosa in Japanese boys and girls aged 12−14 years. Ann Nutr Metab 34: 208, 1990.
11)Ohzeki T, Ohtahara H., Hanaki K., Motozumi H., Shiraki K.: Eating attitudes test in boys and girls aged 6 through 18 years: Decrease in concerns with eating in boys and the increase in girls with their ages. Psychopathology 26 : 117, 1993.
12)平野浩一、大関武彦:さまざまな摂食障害のかたち。久保木富房編、たべられない やめられない/摂食障害、日本評論社、p195, 2002.
13)大関武彦:拒食と過食はなぜおこるか。小児科領域からのアプローチ〜成長・成熟に伴う体組成およびその認識の変動。思春期学 17: 29, 1999.
14)竹内浩視、大関武彦:静岡件における思春期糖尿病児の管理ム病院小児科16施設における検討。思春期学 18: 87, 2000