1.はじめに
平成13年のわが国におけるBSE(牛海綿状脳症)患畜牛発生の影響は、食の安全性に対する生産者・流通業者の対応、ならびに消費者の消費行動を大きく変えてきた。牛肉に関しては、わが国では、行政主導でいち早く全頭検査に取り組むなど、国産牛肉に対する消費者の安心感を回復させている。すなわち、生産者がJAや家畜商を通じて生きた牛をと畜場へ持ち込み、と畜・枝肉に解体されるまでの過程で、BSE患畜牛の発見・隔離と、全頭の危険部位の除去が、徹底して行われているのである。
さらに、平成15年6月11日に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサビリティ法)が公布され、平成15年12月1日に、牛の管理者は、全ての牛に(10桁の個体識別番号がついた)耳標の装着と出生の届出が義務づけられ、平成16年12月1日に、精肉などの販売業者と、牛肉料理(焼き肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキ)が主となる料理専門店は、個体識別番号の表示などが義務づけられている。これによって、流通業者から消費者への流通の最終過程にまで、国産牛に限られるが、牛の個体識別番号が伝わることになる。それ故、消費者が(独)家畜改良センターのホームページの中の「牛の個体識別情報の検索」のコンテンツにある「個体識別番号」に10桁の数字を入力して検索すれば、該当する牛の品種・飼養場所・移動の状況などを瞬時に知ることができるのである。
以上のように、国産牛に限られるが、消費者は、自分が食べる牛肉の「生産者の顔」が見えることになる。すなわち、このシステムが、国産牛肉の安全・安心を構築することにつながるのである。さらに、消費者は、自分が実際に食べて美味しいと感じた牛肉の生産者を、特定することが出来る。このことは、努力して美味しい牛肉を生産している農家に、多くのファンができる可能性を秘めている。
牛肉の場合、野菜や果物と異なり、と畜というプロセスが入るため、生産者と消費者が直接に取引することは難しい。しかし、本稿で取りあげる、かわむら牧場では、個人経営レベルで、牛肉を地元の学校給食に提供したり、自らの店舗や宅配で販売している。この分野では先行事例といえるだろう。そこで、本稿では、本牧場が牛肉を学校給食に提供するに至った経緯、その背景を明らかにし、そこから得られる教訓を導出したいと考えている。
 |
| かわむら牧場肥育舎 肥育牛の常時飼養頭数は約130頭 |
2.かわむら牧場の経営展開
常に、発展期
かわむら牧場については、放牧を取り入れた肉専用種繁殖肥育一貫経営ということで、多くの研究がなされている。『畜産の情報』でも1998年8月号の専門調査レポートで、鳥取大学農学部の小林一教授が「復活した里山放牧 −国立公園・島根県 三瓶 山−」(以下「小林レポート」)の中で、本牧場を取りあげて、詳細に整序している。しかし、かわむら牧場は常に進化を続け、通常の経営のライフサイクルである、発展期−成熟期−衰退期のうち、常に発展期にあるので、小林レポートを基に、それ以降、動態的に発展している部分に重点を置いて、記述していくことにする。発展には矛盾が生じるが、矛盾を克服すればさらに経営を発展に導くというダイナミクスが存在する。いわばより高次の発展へとつながっていくのである(伊丹敬之・加護野忠男『ゼミナール経営学入門』日本経済新聞社、2003年参照)。このように、本牧場は、矛盾の克服を続けながら発展を続ける、たいへん魅力ある畜産経営である。
現在の経営概況
本牧場は、島根県大田市三瓶町志学に立地している。小林レポートでは、経営主の孝信氏(56歳)と妻の千里氏の2人だけの家族経営であったが、37歳の研修生を1人、平成11年6月から常雇に近い形で雇用している。また、平成14年春に長女が就農している。ただし、長男が平成15年11月に就農するのを契機に、長女は他産業へ転出する。仕事の役割分担では、経営主の孝信氏と研修生が農作業一般を担当し、夫人が事務会計や営業を担当している。長女は家事を担当し、パソコンによる簿記記帳を行ったり、夕方の作業補助を分担している。長男の就農は、本牧場にとって大きな戦力になることが予測される。
本牧場の飼料作の経営面積は、表1に示すように7haである。そのうち、借地が6ha、自作地が1haである。7haの飼料作のうち4haは、冬作がイタリアンライグラスとライ麦の混播で、夏作がスーダンまたはグリーンミレットである。3haは、永年牧草である。何れもロールベールにして採草している。ロールベーラーなどの機械装置は、平成6年に導入している。なお、平成15年度中に、新しい機械装置の導入を約550万円の事業費で計画している。飼料作の借地料は、6haのうち3haのみ支払っており、10a当たり5,000円とのことであった。ロールベールの生産量は、年間で350〜400個、1個当たりの重量が低水分ロールベールサイレージで150kgであるので、52.5tから60tになる。以上のように、本牧場では、積極的に個別完結型で飼料作に取り組んでいることが分かる。
また、冬期のみ7haの永年草地を知人から借りており、運動場かわりに妊娠鑑定済みの繁殖牛15〜16頭を放牧している。これについては、後述する。さらに、水稲を0.7
ha作付けしている。
さて、2000年世界農林業センサスによれば、大田市の総農家数は2,743戸、販売農家数は1,901戸であった。この販売農家数1,901戸の中で経営耕地面積の規模が5.0ha以上の戸数は、わずか17戸にとどまっている。さらに、かわむら牧場が属する旧佐比売村の総農家数は401戸、販売農家数は333戸であった。この販売農家数333戸の中で経営耕地面積規模が5.0ha以上の戸数は、わずか4戸にとどまっている。従って、かわむら牧場は経営耕地面積規模において、大田市では大規模層17戸の中に含まれ、旧佐比売村では大規模層4戸の中に含まれていることが分かる。
大田市全体の経営耕地面積は1,709haであるのに対して、耕作放棄地面積は296haに達している。経営耕地面積に対する耕作放棄地面積の割合は17.3%にもなる。同様に、旧佐比売村全体の経営耕地面積は296haであるのに対して、耕作放棄地面積は50haに達している。経営耕地面積に対する耕作放棄地面積の割合は16.9%にもなる。これは、島根県全体の割合9.1%と比較しても高いことが分かる。従って、かわむら牧場が農地を有効利用することによって、いかに地域の農地資源の維持存続に貢献しているかが理解できるのである。
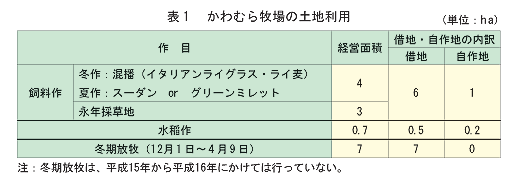 |
現在の牛群
本牧場の黒毛和種繁殖牛は、表2に示すように、100頭規模に達している。肥育牛(8カ月齢〜30カ月齢)は常時飼養頭数が約130頭である。年間に100頭の繁殖牛から約80頭の子牛が生まれると仮定すると、雌子牛の10頭(繁殖牛100頭の1割)が後継牛として残されて、70頭が肥育に供されている。
70頭 × 肥育期間(22カ月) ÷ 12カ月≒130頭
上式のように、自家で生産された肥育素牛だけで、現状の肥育牛が賄われているのである。それ故、現在のところ、肥育素牛に関して外部からの導入はない。平成6年から、自家生産の肥育素牛だけで回転するようになっている。ただし、繁殖牛の耐用年数が10年以上であるので、10頭の後継牛を残すと、飼養頭数が徐々に増加しているとのことであった。
さらに、経営革新の一つとして、島根県の種雄牛を、平成14年6月から導入している。これは、繁殖牛100頭の人工授精の労働が非常に厳しいことによる。また、放牧をしているため、イージーブリード(黄体ホルモン製剤)を用いて発情の同期化を図っている。
さて、繁殖牛は、常時100頭規模に達しているが、放牧を考慮して、舎飼の常時飼養頭数(冬期放牧を含める)に換算すると、下式の通り44頭ということになる。
(100頭×130日÷365日)+(13頭×235日÷365日)≒44頭
上式において、冬期舎飼の日数が130日、放牧の日数が235日であり、放牧期における繁殖牛の平均舎飼頭数を13頭として計算している。この13頭は、繁殖牛常時飼養頭数100頭から表2の放牧頭数87頭を控除した数値である。
もう一度表1に戻るが、飼料作面積は7haであった。これを舎飼換算の繁殖牛常時飼養頭数44頭で除すと、1頭当たり15.9aの飼料作面積になる。ちなみに、(社)中央畜産会『先進的畜産経営の動向[平成14年実績]』における繁殖牛20頭以上規模の繁殖専門経営の繁殖牛(成雌牛)1頭当たり耕・草地のべ面積は、14.7aであり、かわむら牧場も先進的大規模繁殖経営の飼料作のレベルにあることが分かる。
粗飼料・配合飼料の調達
第1次オイルショックで輸入飼料が高騰した際に、近隣の酪農家を中心に任意組合のAST飼料合理化センター(ASTは、赤名・三瓶・頓原の地名のアルファベットの頭文字)が作られた。かわむら牧場は、本センター発足当初からの組合員で、そこから単味飼料を購入し自家配合している。肥育牛の飼料の研究会にも参加するなど、単味飼料の素材を一つ一つ吟味しながら、牛群のステージに合致した配合飼料を作っているのである。
なお、本センターの職員は、現在、製造担当が2人、庶務担当が1名の3名で、本センター利用の組合員戸数は25戸とのことであった。
また、かわむら牧場では、自給のロールベール以外に、流通粗飼料として、購入乾草と稲わらを用いている。購入乾草は、舎飼の繁殖牛、育成牛に給与している。その量は年間で約40tである。稲わらは、約8割を肥育牛の前期・後期に給与している。稲わらに関しては、自家の稲作0.7ha、後述のたい肥と稲わらの交換1ha以外に、大田市内や 邑智町( の稲作農家から6.3ha分の稲わらを購入している。なお、稲作農家が稲わらを道路沿いに積んだ状態にしており、それを川村氏がトラックで取りに行くのである。稲わらの収量は10a当たり約500kgであるので、自家の稲作分から3.5t、たい肥と稲わら交換分から5t、購入分が31.5tの稲わらを調達していることになり、合計で約40tにもなるのである。ちなみに、本牧場が支払う稲わらの代金は、購入部分の31.5t分だけであるが、稲わら1kg当たり17円を支払っているので、約54万円の現金支出で収まっている。40tの稲わらの集草にはかなりの労働を伴っているが、もし、全量輸入稲わらで代替して、農家庭先価格で1kg当たり46.5円(「飼料月報」((社)日本飼料協会)の平成13年の全国データ)とすれば、約186万円の現金支出にもなるのである。
以上のように、本牧場は、多くの労働を投下し、現金での支出を少なくしながら、出所の明確な飼料を用いていることが分かる。
家畜排せつ物の処理
牛舎は、1〜2週間に1回、新しいオガクズやカンナクズを追加している。直下型の換気扇で牛床を乾燥させている。そして、半月に1回、牛舎から家畜排せつ物と副資材の混合物をたい肥舎へ搬出している。現在、たい肥舎は170m2であるが、400m2に拡張し、完熟たい肥の製造を目指している。たい肥処理の方法は、ショベルローダーを用いた堆積発酵処理方式である。
たい肥の農地への還元は、(1)稲作農家の1haの稲わらとたい肥の交換、(2)近隣の野菜農家の圃場1〜2haへの投入、(3)7haの飼料作物の圃場への投入という形態で行っている。何れも、たい肥の運搬は、かわむら牧場が行っている。(1)と(2)は長期契約になっている。(1)では2〜3t/10a、(2)では3t/10a、(3)では5〜6t/10aのたい肥が投下されている。
副資材のオガクズやカンナクズは、かわむら牧場から10 km離れた邑智町の製材所から調達している。オガクズは8t/月、カンナクズは4t/月を用いている。カンナクズは無料だが、オガクズは有料で、年間15万円のコストがかかっている。
平成16年11月1日から、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(家畜排せつ物法)の「施設の構造設備に関する基準」と「管理施設内における家畜排せつ物の管理」が適用されることになるが、本牧場はいち早く当該対策に取り組み、後顧の憂いを無くしている。
入会 ( 放牧場の活用
放牧は、表2に示すように、4月10日〜11月30日まで行っている。東の原(41 ha)の入会放牧場に27頭を放牧、西の原(30 ha)の入会放牧場に30頭を放牧、西の原第2牧区(30
ha)の入会放牧場に30頭を放牧し、合計で87頭に上る。西の原では、かわむら牧場以外に1戸の農家も放牧している。その頭数は1〜2頭程度である。西の原第2牧区では、本牧場以外に3戸の農家も放牧している。その頭数は14〜15頭程度である。これら4戸は何れも大田市内の農家である。
何れの入会放牧場にも牧番は置いていない。西の原第2牧区において、他の3戸の農家が定期的に自分の牛を見に行っている程度である。
なお、夫人の千里氏によれば、三つの入会放牧場における放牧のポリシーは下記の通りである(平成14年度地域先導技術総合研究のシンポジウムでの報告「放牧と自家配合飼料を基礎にした肉牛の生産から販売まで」から引用)。
 |
| 牧野全体の見わたすことができる西の原牧区(11月中旬) |
【東の原】多様な地形と林地も含めて多様な植生をもっており、長い年月放牧を継続してきたため草地が安定していて、牛が最も生活し易い牧野。このため、春〜初冬まで長期間の放牧が可能で、放牧期間中にお産が予定されている牛やお産後の親子の放牧を行っています。
【西の原】平成8年に放牧が再開した牧野。道路から近く、牧野全体を見わたすことができ、牛の観察が容易な立地条件にあるため、育成牛や放牧経験の浅い牛など要観察の牛を放牧しています。
【西の原第2牧区】平成9年に放牧が再開した牧野。樹木を伐採し整地したため、草原部分が少なく、ニセアカシアや野イバラが繁茂している。このため、放牧経験の豊かな牛を放牧し、草地の拡大を図っています。妊娠鑑定済みで放牧経験のある牛を放牧し、ほとんど見回りに行くことはありません。
以上のように、本牧場の放牧の特徴は、妊娠鑑定済みの繁殖牛・親子を中心に放牧し、手をかけず自然に任せている点である。そして、経営革新の一つとして、平成14年から放牧場で分娩させていることが挙げられる。牛舎で分娩させない理由は、過去2年連続で一冬に10頭の子牛が大腸菌症による下痢で死亡したためと、入会放牧場の大腸菌が牛舎より少ないことによる。放牧場での自然分娩のため、1〜3月はお産させないような季節分娩を行っている。分娩後2カ月で集牧し、3カ月で離乳している。このような画期的な放牧が可能になった理由として、(1)放牧の経験の蓄積があったこと、それ故、(2)繁殖牛が放牧に慣れていること、(3)放牧ゆえ、繁殖牛が過肥にならず、子牛が巨大化しないため、分娩が容易なことが挙げられる。平成15年になって、11月中旬までの子牛の死亡は2頭のみで、その死亡理由も逆子で大腸菌症による下痢ではなかった。
三瓶の入会放牧場
三瓶の入会放牧場には、大田市三瓶牧野委員会があり、事務所が大田市農林課に置かれ、JA石見銀山の組合長が会長を務めている。入会放牧場の利用料金は、放牧日数100日以下が1,000円/頭、100日以上が2,000円/頭である。この利用料金が牧柵・飲料水の維持管理費に充当されるのである。維持管理は利用者が行うことになっている。
|
|
電牧による放牧により作られた西の原牧区の火入れのための防火帯
|
かわむら牧場が利用している東の原は大田市の公有地と民有地であるが、西の原は大田市の公有地で、林地部分は国有地である。西の原第2牧区は大田市の公有地と民有地からなる。平成7年度の公社営畜産基地建設事業で西の原の入会放牧場が完成し、平成8年から放牧が開始され、平成8年度の公社営畜産基地建設事業で西の原第2牧区の入会放牧場が完成し、平成9年から放牧が開始された。なお、かわむら牧場が利用する三つの入会放牧場以外に、東上山(23
ha)、小屋原(40 ha)、大水原(1ha)の三つの入会放牧場がある。
さて、火入れは、西の原の一部でなされている。火入れには、防火帯を作るための輪地切りなど多くの労力を要し、一時期廃止していた。しかし、昭和63年に西の原で火災があり、平成元年から防火と草原維持のため、平成元年より毎年3月に火入れを行ってきた。しかし、防火帯(輪地切り)を作るためには、多大の労力を要した。「緑と水の連絡会議」(代表高橋泰子氏、現在NPO法人「水と緑の連絡会議」理事長)の発案で、放牧場の火入れをする境(輪地切りの部分)に電牧を張り、そこに草が短くなるまで牛を放牧し、それを防火帯とするなど工夫して、人力の投入を軽減している。
冬期放牧
前述のように、15〜16頭の妊娠鑑定済みの繁殖牛は、知人から借りた7haの永年草地に、12月1日〜4月9日まで放牧している(ただし、平成15年〜16年にかけては行っていない。表1参照)。この永年草地は、かわむら牧場から7キロ離れたところに立地し、24頭用の連動スタンチョンが設置してある。冬場ゆえ、緑のものとしては笹しか無く、運動場の機能しか果たしていないので、毎日飼料は運んでいる。このように、飼料の運搬作業が伴うものの永年草地を借りている理由は、牛舎が足りないことによる。ちなみに、笹と水と林があれば、たとえ氷点下になっても、充分越冬できるとのことであった。
牛舎を増設せず、冬期放牧というような画期的な挑戦を行うところが、かわむら牧場の真骨頂であり、そこに弾力的な発想を窺うことができるのである。
学校給食の利用
かわむら牧場の肥育牛の流通は、JA石見銀山→全農島根→(株)島根県食肉公社になっており、枝肉取引がなされている。
さて、本牧場の経産牛の流通は、平成13年にわが国でBSE問題が発生する以前は、その部分肉を京都の食肉小売店に販売していた。そして、部分肉は、フルセットで1頭25万円で販売され、この外に処理料4万円程度と輸送量1万円(販売店持ち)のコストがかかっていたのである。しかし、BSE問題の発生以後、当該取引は中止になった。
そのような状況下で、学校給食で経産牛が食材として取り扱われる運びになったのである。後述のように放牧利用でしかも自家で生産された経産牛であったので、安心・安全と認められたのである。
さらに、本牧場の経営革新の一つとして、学校給食への食材供給を契機に、経産牛の販売に乗り出したのである。食肉販売の許可を取得し、平成13年は島根県食肉公社でJA石見銀山畜産課の方にスライスしてもらって、製品を自家の冷凍庫に保存して販売していた。しかし、平成14年から注文に応じてスライスしてもらえなくなったので、同年9月に500万円の投資で、スライスできる施設を建築した。そして、併せて食肉加工・小売りの許可を取得している。初めは夫人がスライスしていたが、作業が大変なので、現在は、1カ月に1回くらいの頻度で、職人に来てスライスしてもらっている。
経産牛の現在の流通は、島根県食肉公社で部分肉にカットされ、冷蔵庫に保存される。この部分肉の所有は、かわむら牧場にある。そして、学校給食などの注文があれば、食肉公社内にある施設でスライスされ、JA石見銀山を通じて販売される。ロース、ヒレ、肩ロース等の部分肉は、本牧場で引き取り、氷温冷蔵庫で保存してステーキや焼肉、しゃぶしゃぶ、すきやき用にスライスして200g〜500gのパック詰めにして販売するのである。和牛の経産牛は、肉にコクがあり、完熟しているため、肉質が落ちないという長所がある。現在は、1〜2カ月の平均在庫で消費者に販売されている。
かわむら牧場の小売は、来店による購買と宅配からなる。来店の購買者は、三瓶地区内の個人、大田市内の個人やレストランなどの外食が中心である。宅配便は、県外者が多く利用している。その注文の多くは、電話やファックスで受けている。ただし、季節的な繁閑があり、お中元・お歳暮の時期と、焼き肉の需要が多い春夏期に注文が集中し、正月から春までは注文が比較的少ないとのことであった。更に定期的に注文するリピーターも多いとのことであった。
なお、平成14年度にと畜された経産牛肥育頭数は10頭である。1頭当たりの精肉の量を平均270kgとすると(枝肉は平均350kg)、約2,700kgの精肉が生産されたことになる。それに対して学校給食の需要量が約1,800kg、店舗や宅配などの小売販売が約900kgであった。かわむら牧場では、経産牛の肥育は30年の歴史があり、技術が蓄積されており、6〜8カ月の肥育期間で出荷されている。
 |
|
 |
| かわむら牧場の敷地内に建られた加工施設内に設置されたスライサー |
|
宅配の注文に応じて氷温冷蔵庫から取り出してスライスする。 |
3.大田市教育委員会の挑戦
学校給食の現状
大田市の学校給食は、平成15年4月現在、単独校方式の4施設で353食、センター方式の2施設(東部・西部)で3,039食が提供されている。平成14年度の給食日数は201日であった。
学校給食は、元々、各校舎に併設されていた。すなわち、すべて単独校方式であった。幼児・児童が給食を作る過程や匂いに触れる機会は重要なことである。しかし、昭和52年に大田市立第二中学校が統合した際、東部給食センターが設立された。国もセンター方式を推進していた。次に西部給食センターもできたが、大田市が広域であるので、搬送の時間の問題も考慮すると、両センターでカバーできない地域ができる。カバーできないところは、単独校方式が継続しているのである。
大田市学校給食会の設立は、表3のとおり昭和38年である。給食物資の調達、調査研究などの事業を行っている。献立委員会と物資委員会は月初に来月の献立を検討し、中旬に物資について検討する。会計は、物資会計・業務会計・退職積立会計の三つ。物資会計は年間の物資購入などにかかる予算額で平成15年度は約1億6,300万円。業務が約680万円である。
平成13年9月9日にわが国で最初のBSE患畜牛が発見された。それを受けて、大田市の学校給食では、10月から牛肉の使用を見合わせることになった。
放牧牛の学校給食への導入
しかし、表4のように、平成13年9月26日に、「緑と水の連絡会議」代表の高橋泰子氏から放牧牛の学校給食利用について、教育委員会に提案があった。また、同年の10月1日にかわむら牧場へ視察依頼をし、10月10日に視察を行い、調理場長・栄養士・教育委員会が協議を行った。その結果、放牧牛の安全性が確認できたのである。
教育委員会の松村総務課長は、BSEが国内で発生する以前に、中学生の職場体験活動において、川村氏に話題提供をしてもらったことがあった。それが、川村氏を知る契機でもある。また、その頃、三瓶の放牧牛がテレビで放映されて、その印象が課長に強く残っていた。BSE発生後、かわむら牧場の現場に行き、放牧牛がまさしく三瓶の自然に育まれていることを実感する。
そこで、世の中がBSEの騒乱の最中にもかかわらず、放牧牛の学校給食への導入を進めることになる。正しく、教育委員会にとっては、大英断といえる。10月31日にJA石見銀山の畜産課長とどの部位を納入するか協議を行い、平成14年の1月16日の東部給食センターを皮切りに、1月17日には西部給食センターおよび単独校の4校が、放牧牛を給食に提供するようになったのである。
栄養士をされている先生の話によれば、「BSEの問題が大きかったときに牛を使うのは、不安があったが、かわむら牧場へ視察に行き、実際に畜産の現場に触れ、話をすることで不安感を払拭することができた。また、川村さんが自己の経営に自信を持っておられるのが、何よりも頼もしかった。」とのことであった。
なお、表5のように、平成14年1月16日の連絡ノートに、先生や生徒達の放牧牛肉に対する感想が綴られている。
|
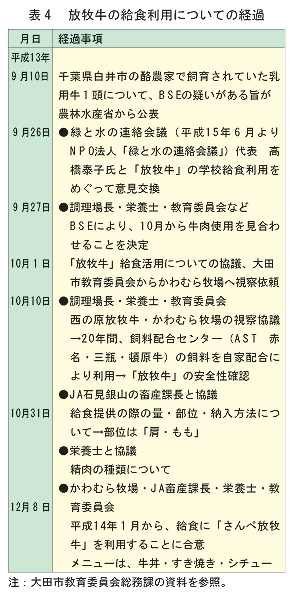 |
 大田市内の小学校の給食風景 大田市内の小学校の給食風景 |
|
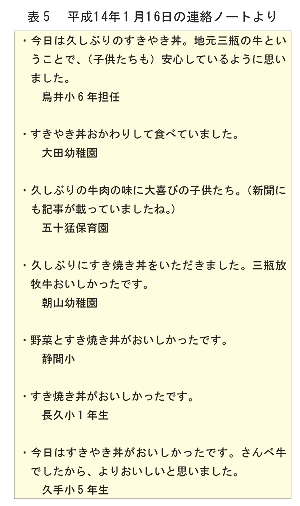
|
| |
|
放牧牛の牛肉の流通
放牧牛の牛肉の流通は、学校給食会から、JA石見銀山の畜産課に発注して、JAから放牧牛の牛肉を購入する。購入量は、1カ月前におよその量をJAに連絡し、購入の1週間前くらいに実際の量を連絡することになっている。
学校給食会の購入単価は、最初に契約した時から変動はない。すなわち、もものスライス2,500円/kg、小間切れ2,000円/kg、合挽ミンチ1,700円/kgである。そして、かわむら牧場の販売単価は、もものスライス2,000円/kg、小間切れ1,600円/kg、合挽ミンチ1,250〜1,260円/kgである。両者の差額が、JA石見銀山の運賃、加工料、手数料などということになる。ちなみに、表6からも分かるように、学校給食会が購入している単価は、もものスライスでみると国産の乳用種牛肉の特売価格に相当する。このように、学校給食会では、非常に安価に、良質の放牧牛の牛肉を調達できていることになるのである。
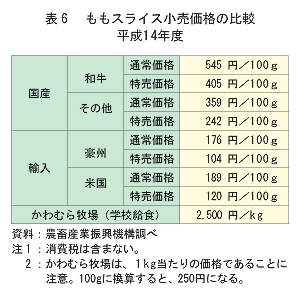 |
4.おわりに
技術革新・経営革新を続けている、かわむら牧場は、常に発展期にあるといえる。三瓶山の自然条件を熟知し、その自然条件を徹底的に活かしているところに、経営のオリジナリティと魅力があるといえる。また、かわむら牧場の日々の営みが三瓶山の素晴らしい景観の創造・保持にも大きく貢献しているのである。自然の草を食べながら、健康に生きている放牧牛は、安全性の面から全く申し分無しである。ビタミンの豊富な自然の草を食べているが故に肉の色が濃く、市場での評価は低くなるが、味は濃厚で、食味に優れている。表5に示したように、学校給食において、先生や生徒から好評を博しているところである。
かわむら牧場が学校給食へ展開した一つの要因として、以上のように、地域の自然の恵みを活かした健康な牛の飼養を追求しているところにある。確かに、肉牛は産業動物であるが、本牧場の場合、短期的な視点ではなく、長期的な視点に立脚して持続的な経営を構築しているのである。
もう一つの要因として、川村氏をはじめ家族全体の開かれた気風を挙げることができる。このことが、人的なネットワークの構築に大きく貢献している。大田市教育委員会の松村総務課長との出会いが何といっても大きい。
放牧牛の学校給食への導入という画期的なプロジェクトの推進には、当然のことながら多くの乗り越えるべき壁が存在したことと推察される。しかし、教育委員会を中心に、かわむら牧場、JA石見銀山が一丸となって、当該プロジェクトの推進に当たったことは、後に続く肉牛経営にとって、大きな教訓になる。
そして、学校給食で美味しい放牧牛を食した生徒達は、将来大きくなったときに、かわむら牧場の牛肉のファンになり、重要な購買層になることが予想される。このように、学校給食への放牧牛の提供は、かわむら牧場にとって短期的な経済行為にとどまらず、長期的な投資にもなっているのである。正しく、「奇貨おくべし」である。
さて、江津家畜保健衛生所では、かわむら牧場における入会放牧場での自然分娩の和子牛が、舎飼いで分娩された和子牛と比較して、より健康に育成するかどうか、定期的な血液検査によって実証的な研究が進められている。このような実践的な研究によって、牧野での自然分娩の和子牛がより健康に育つことが証明できれば、自然分娩の和子牛やそれを素牛として肥育された肥育牛の市場評価が高まることが期待できる。さらに、色やサシだけに偏った牛肉の評価だけでなく、牛肉の歯ごたえ(texture)の善し悪しを客観的データによって評価できるようなシステム構築が目指されている。
なお、常石英作氏の「放牧繁殖雌牛の肉は体脂肪燃焼作用を持つカルニチンを豊富に含有」『畜産の情報』(2004年4月号)、および『日本農業新聞』(2004年3月31日)の中で、疲労回復に貢献するカルニチンの含量が、放牧繁殖雌牛に多く含まれていることが記載されている。今後、このような健康面からの栄養学的研究の蓄積が期待されるところである。
今回の現地調査に際して、川村孝信様とご家族の方々、大田市教育委員会・総務課課長・松村淳真様、調理場長補佐・森山祥朗様はじめ栄養士の先生方、大田市経済部・農林課課長補佐・伊藤静稔様、JA石見銀山・畜産課長・武田章様、課長補佐・厚朴邦広様はじめスタッフの方々、江津家畜保健衛生所・家畜衛生課長・若槻義弘様、主幹・村尾克之様にたいへんお世話になりました。深甚なる謝意を表します。
|

