はじめに
平成18年6月6日、平成17年度食料・農業・農村白書が閣議決定の上、国会に提出、公表された。
今回の白書は、経済のグローバル化の一層の進展や人口減少局面への移行など経済社会の転換期を迎える中で、新たな「食料・農業・農村基本計画」(17年3月)に基づく農政改革の初年度の主要施策の取り組み状況と課題を整理し、農政改革について、国民の関心と理解を深めることをねらいとして取りまとめている。
ここでは、17年度白書の中から、特に畜産をめぐる情勢を中心に説明していく。
食の安全確保に向けた取り組みと課題
国内外でのBSEの発生、食中毒などの食品安全の問題や、高病原性鳥インフルエンザの発生、食品の偽装表示などを契機とした、国民の食の安全に対する関心が高まっている。消費者や食品関係事業経験者などの中では、日常生活を取り巻く自然災害や交通事故などに比べて、食の安全に対する不安感が相対的に大きいとみている者が4割を占めるという調査結果もある。
安全な食料を安定供給し、国民の健康を守るためには、「食品の安全」確保のための施策から、家畜・水産動物の衛生対策や植物防疫対策、栄養や食事習慣に関する施策等までを含む「食の安全」を確保するための施策を幅広く講じていくことが重要である(図1)。
これら食品安全の施策とともに、トレーサビリティ・システムの導入や食品表示の適正化、事業者の法令順守など消費者の信頼確保の取り組みを推進することによって、食に対する消費者の安心につながっていくこととなる。
BSE、高病原性鳥インフルエンザ問題に対する取り組み
国内のBSE対策については、リスク評価機関である食品安全委員会の答申を踏まえ、17年8月、リスク管理機関である厚生労働省と農林水産省は、と畜場におけるBSE検査対象月齢の見直し(生後20カ月齢以下の牛の除外)や飼料規制の実効性確保の強化などの措置を講じた(表1)。また、政府は、消費者や生産者の不安解消を図るため、自治体による自主的なBSE検査に対し、経過措置として、引き続き補助を行う措置を当分の間、講じることとしている。
米国産牛肉問題については、食品安全委員会の答申を踏まえ、輸出プログラムの順守などを条件に、17年12月、輸入停止から2年ぶりに輸入を再開した。
図1 農林水産省の「食の安全と消費者の信頼確保」に関する施策
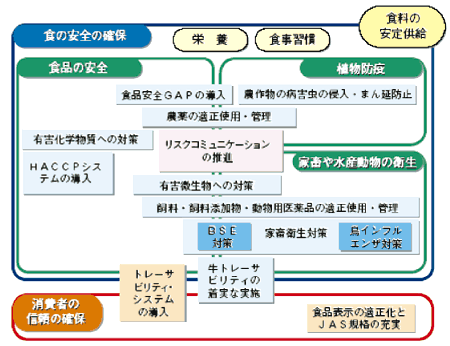
表1 BSE発生以降の国内対策・米国産牛肉対応などに関する経緯
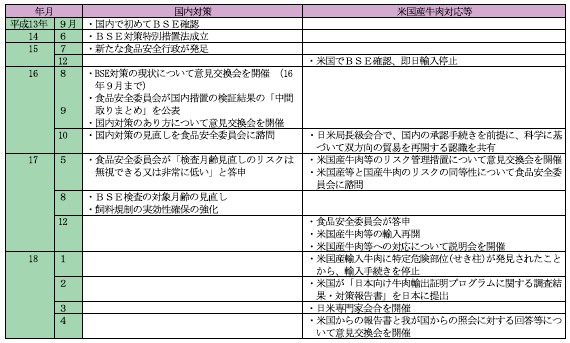
しかしながら、18年1月にわが国に到着した米国産牛肉に特定危険部位(せき柱)の混入が確認されたことから、直ちに米国産牛肉の輸入手続きを全面停止し、現在、米国に原因究明と再発防止を要求している。
今後、意見交換会で出された意見や米国の再調査結果などを考慮して、日米間の協議を行うこととしており、引き続き、関係者が十分に連携し、国民の安全・安心の確保を大前提に適切に対応していく必要がある。
高病原性鳥インフルエンザについては、国内において、17年6月以降、弱毒型のウィルスが茨城県や埼玉県で確認され、家畜疾病のまん延防止措置として18年4月までに約580万羽の家きんが殺処分された。
また、感染経路を明らかにするため、専門家で構成される「高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チーム」により、発生農場などの疫学調査や、分離されたウィルスの遺伝子解析などが行われた。同年10月の中間とりまとめでは、発生原因や伝播経路の解明にまでは至っていないが、その解明に向けた疫学調査などが続けられている。
さらに、H5N1型(強毒型)が、ベトナム、タイ、中国など東アジアでの発生にとどまらず、欧州やアフリカなどにも広がっており、世界的な拡大が懸念されている(図2)。
図2 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う家きん肉などの輸入停止状況
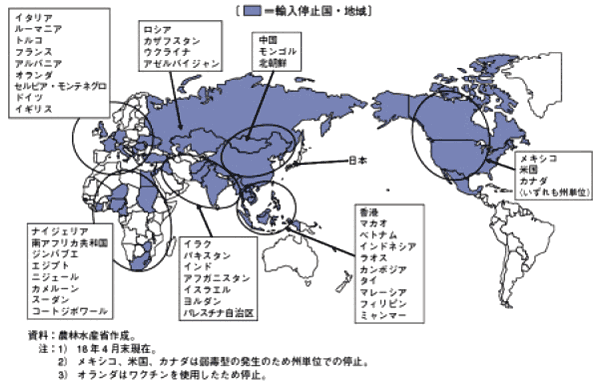
このようななかで、わが国としては、国内で引き続き発生予防や早期発見のための適切なモニタリングの実施、発生後のまん延防止措置の徹底とアジア各国における防疫活動の支援、家畜衛生分野の専門家派遣や人材育成などの国際連携の強化が重要である。
最近の畜産物の需要動向
最近の食肉の需要量は、国内外でのBSEや高病原性鳥インフルエンザの発生などの影響もあり、畜種ごとに大きな変動がみられるものの、畜種間の代替需要もあって、食肉全体では、16年は5年前と比べて1.5%減にとどまり、ほぼ横ばいとなっている。畜種別にみると、牛肉の需要量は、13年9月にわが国で初めてBSEが発生して以降、大幅に減少した。その後、カナダ(15年5月)、米国(同年12月)でのBSEの発生に伴う輸入停止措置により輸入量が減少し、16年の需要量は、5年前に比べて23.4%減少している。一方、豚肉の需要量は、牛肉の代替需要などから増加傾向で推移し、5年前に比べて14.4%増加している。鶏肉については、15年12月以降、アジアや北米での高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、家きん肉などの輸入が停止され、さらに、16年1月には79年ぶりにわが国で高病原性鳥インフルエンザが発生したことなどから、需要量は5年前に比べて2.5%減少している。
一方、家計の購入量をみると、食肉の需要量の傾向と同様、畜種別に変動がみられるが、牛肉や鶏肉がBSEや高病原性鳥インフルエンザの発生以前の購入量まで回復していないことなどから、食肉全体では5年前に比べて7.6%減少している(図3)。このことから、消費者の中には、家畜疾病の発生などに敏感に反応し、発生した疾病に関する畜種の食肉消費を家庭で避ける動きがあることがうかがわれる。
図3 畜産物の家計購入量の推移
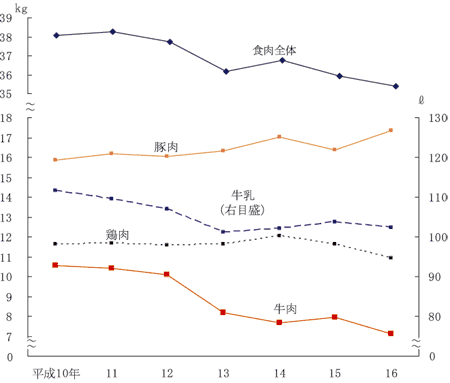
牛乳の消費については、他の飲料との競合などから、近年、減少傾向で推移しているが、食生活の乱れなどに対応した食育の推進の重要性が高まっている状況も踏まえて、カルシウムなど牛乳に含まれる栄養素に関する知識の普及などに向けた取り組みが行われている。
飼料自給率の動向と向上に向けた取り組み
畜産経営の動向をみると、総飼養頭羽数、飼養戸数ともに減少傾向で推移しているが、1戸当たりの飼養頭羽数は増加傾向にあり、着実に規模拡大が進展している。
このように畜産は、水田作などの土地利用型農業と比べ、構造改革は進んでいるものの、今後の国際化の進展などに対し、競争力の高い生産構造の確立と一層の経営体質の強化が重要であり、生乳や肉用子牛の再生産の確保、肉用牛肥育経営などの安定を図る必要がある。このため、経営安定対策について、これまでの目的と効果を踏まえ、対象経営を明確化し、経営の安定性を向上させることを基本として、19年度からの移行に向けた見直しが検討されている。
また、自給飼料基盤に立脚した安全・安心な畜産物の供給体制の確立も重要であるが、近年の飼料作付面積の動向をみると、経営規模の拡大に伴い、1戸当たりでみれば、拡大傾向にあるが、全体でみると、16年は91万4千ヘクタールで5年前と比べ5%減となっている。
飼料需要量は、家畜飼養頭羽数の減少などを反映して、減少傾向で推移しており、14年度は、13年9月にわが国初のBSEが発生したことに伴い、乳用牛・肉用牛の出荷が一時的に停滞したことなどによりわずかに増加したが、その後再び減少し、16年度には2,514万TDNトンとなっている(図4)。また、飼料需要量のうち国産飼料が占める割合である飼料自給率は、近年、横ばい傾向で推移しており、16年度は25.1%となっている。
図4 飼料需要量及び飼料自給率の推移
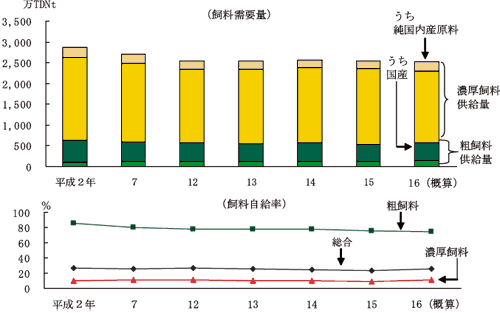
このうち、粗飼料自給率は16年度は74.5%であり、輸入粗飼料が25.5%を占めている。この要因には、畜産経営の規模拡大の進展により、飼養規模に見合った飼料生産基盤の確保が不十分であることや労働力不足などが影響しているとみられる。また、近年の乳価の安定的な推移や米国産牛肉の代替需要による国産牛肉の価格の上昇などを背景に、飼養規模の拡大による粗収益の増大が自給飼料生産などによる経営コストの引下げよりも経営上有利となっていることなどから、利便性がよく、労力負担の軽減にもつながる輸入粗飼料が利用される傾向があるものと考えられる。
飼料自給率の向上は、食料自給率の向上のみならず、国土の有効活用、資源循環型畜産の確立などを図る上で重要であることから、食料・農業・農村基本計画(17年3月)において、27年度の飼料自給率を35%とする目標が掲げられている。
飼料自給率の向上に当たっては、耕畜連携による稲発酵粗飼料などの生産拡大、国産稲わらの飼料利用の推進や耕作放棄地、林地、河川敷などの有効活用に加えて、草地の計画的な更新や整備・改良、優良多収品種の育成・普及などが重要である。また、労働力不足に対応するため、コントラクターの利用や放牧の推進など、飼料生産の外部化・省力化への取り組みや、濃厚飼料の自給率向上を図るため、エコフィード(食品残さの飼料化)の推進も重要となっている。
これらの課題を踏まえ、農林水産省は、17年5月に「飼料自給率向上特別プロジェクト」を発足させた。このプロジェクトの中で、飼料自給率向上に向けた行動計画の策定・点検などを行う「飼料自給率向上戦略会議」を設置し、粗飼料自給率100%を目指した自給飼料の増産や濃厚飼料の自給率向上などに向けたエコフィードの推進という目的ごとの行動会議の開催など、飼料自給率向上に向けた行動計画の機動的な実行を図ることとしている。
今後、飼料増産の取り組みを点から面に拡大していくための飼料増産重点地区の拡大やエコフィードの一層の普及・定着に向けて、消費者をはじめ関係者の意識改革を図るための取り組みなどが重要となっている。
循環型社会の形成を図る上で重要な家畜排せつ物の利活用の促進
全国で1年間に発生する家畜排せつ物は、家畜飼養頭羽数の減少などにより減少傾向にあるが、16年には約9千万トンが発生しているとみられる。
家畜排せつ物は、これまでもたい肥などとして、農業経営において有効利用されてきたが、一部では野積み・素掘りなどの不適切な処理が行われ、悪臭のほか、河川、地下水などへの流出・浸透を通じた家畜排せつ物由来の硝酸性窒素などによる水質汚染などが問題となっている。このため、11年に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が制定され、5年の経過期間を経て16年11月から全面施行された。経過期間を中心に畜産経営における家畜排せつ物処理施設の整備が促進された結果、11年時点で発生量の10%程度あった不適切な処理への仕向量は、16年時点では大幅に減少し、たい肥化等や浄化・炭化等の処理へ仕向けられている。
家畜排せつ物の処理については、たい肥化などにより農地に還元することが基本であるが、都道府県別の耕地面積当たりの家畜排せつ物の発生量を窒素ベースでみると、南九州など一部の畜産地帯では、その数値が高くなっており、地域の耕地面積からみて、還元可能な量を上回る過剰な家畜排せつ物が発生している(図5)。このため、家畜排せつ物の地域内の農地への還元のみならず、たい肥等の需要拡大、広域的な流通体制の整備などを図ることが課題となっている。今後のたい肥の利用に関する農業者を対象とした調査によると、9割が「利用したい」と回答しており、潜在的な需要は大きいとみられる。このため、たい肥の形態、品質、成分など、利用者のニーズにこたえられるたい肥生産を推進することが重要である。
図5 耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量(平成16年、窒素ベース)
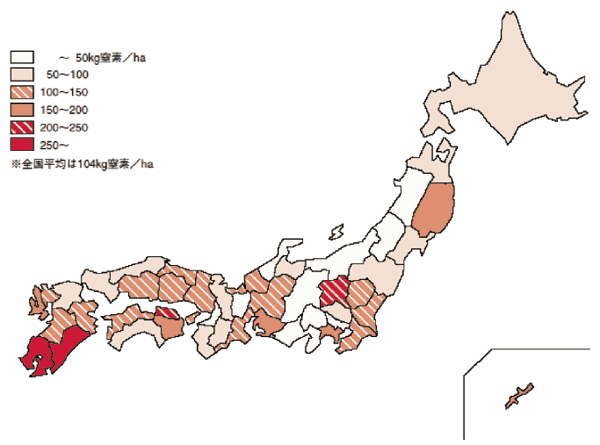
また、近年では、たい肥化による農地への還元以外にも、メタン発酵や炭化・燃焼などによるエネルギー利用、家畜排せつ物の減量化などへの取り組みもみられる。今後、これら技術の開発・普及への取り組みを進めることは、バイオマスとしての利活用を含め、循環型社会の形成を図る上で、大きな意義を有している。
平成17年度白書の構成
以上、畜産をめぐる情勢を中心に17年度白書について紹介したが、白書全体の構成は、以下のとおりとなっている。
なお、その他分野の詳細について、白書本体をご参照いただきたい。
-トピックス-
食料・農業・農村基本計画に基づく主要施策の取り組み状況、WTO農業交渉の取り組み、知的財産の活用等と革新的技術の開発・普及、農産物輸出の促進、原油高騰への対応とバイオマス等の利活用、少子高齢化・人口減少局面での食料・農業・農村の動向といった、この1年間の特徴的な出来事を紹介。
第Ⅰ章 望ましい食生活の実現と食料安定供給システムの確立
食の安全確保に向けた取り組み、米国産牛肉への対応、消費者と生産者の顔の見える関係づくりなどの取り組みについて記述。
また、国民運動としての食育の推進、「日本型食生活」の重要性や食料産業の動向、食料自給率目標や向上への取り組みと課題について記述。
さらに、WTO農業交渉など農産物貿易交渉について記述。
第Ⅱ章 地域農業の構造改革と国産の強みを活かした生産の展開
気象災害の状況、農家経済・農業労働力の動向について記述。
また、認定農業者、集落営農などや農地の動向、「品目横断的経営安定対策」の紹介、担い手の育成確保の取り組みと課題、農協の課題と改革の取り組みについて記述。
さらに、国産の強みを活かした農業生産の現状と課題について、地域ブランド化、技術の革新・開発・普及、農産物輸出の促進などについて記述するとともに、環境保全を重視した農業生産の推進などについて記述。
第Ⅲ章 農村の地域資源の保全・活用と活力ある農村の創造
農村集落の最近の構造変化と社会活動や農業生産活動への影響及び課題について記述。
また、農地や農業用水などの地域資源の維持管理の重要性、農地・水・環境保全向上対策(仮称)の意義と内容、バイオマスの利活用に向けた取り組みについて記述。
さらに、都市農業の役割、グリーン・ツーリズムなど、都市と農村の共生・対流の取り組みによる魅力ある農村地域の形成促進について記述。