1.低温殺菌牛乳生産は消費者の提案から始まった
食品の偽装表示・不適切表示などが相次ぎ、消費者の「食の安全・安心」に対する関心が一層の高まりをみせている中、商品の付加価値として「安全・安心」を消費者に訴求する商品が数多く店頭に並んでいる。その際、生産履歴を明らかにするなど消費者に「生産者の顔が見える」ことをアピールする場合が多いが、こうした中、生産者と消費者の交流を重視し、「生産者にも消費者の顔が見える」双方向性の取り組みを続ける酪農の専門農業協同組合がある。本稿では、消費者からの要望に向き合いながら、消費者と生産者が一体となった牛乳生産を展開する群馬県太田市の東毛酪農業協同組合の取り組みを紹介する。東毛酪農業協同組合(以下「東毛酪農」)は昭和27(1952)年に設立され、大消費地である東京への市乳原料乳の供給を手がけ、昭和35(1960)年から東京向けなどに市乳販売を開始した。昭和49(1974)年に原料乳を納入していた太田市農協が牛乳工場を閉鎖したのを機に、翌年牛乳工場を新設した。平成17/18年度(10〜9月期)の牛乳工場の製品販売量は7,218キロリットル(生乳ベース:製品200ミリリットル換算×36,091千個)、製品販売高は12億9,095万円となっている。主力の飲用牛乳の販売量は、一般市乳が4割強、学校給食向けが3割弱、低温殺菌牛乳が2割強となっている。特に学校給食向けは、群馬県内のみならず、ごみ減量運動のために瓶容器での納入を条件とする東京都内2市(国立市、小平市)にも納入している。平成19年11月現在、傘下の酪農家戸数は37戸である。
東毛酪農の牛乳販売の特徴として、首都圏の共同購入グループへの直接配送、東京都内の牛乳専売店を通じた瓶牛乳の宅配および学校給食など、「誰の手に渡っているか」が明らかな販売先が全数量のうち5割を占めることが挙げられる。これは、看板商品である低温殺菌牛乳の生産に取り組むきっかけが「消費者の提案と真摯(しんし)に向き合うこと」から始まったことと大きなかかわりがあると思われる。
最初に東毛酪農に対して低温殺菌牛乳の生産を持ちかけた消費者は、「ドイツから帰国して以来、家の子どもたちが牛乳を飲まなくなった。何とか搾ったままの生乳の良さを生かした安全な低温殺菌牛乳を生産してもらえないか」と提案をした。そのころ、すでに東毛酪農では利根川の河川敷における野草の飼料利用を実施しており、それを知ったこの消費者が「自然の野草を利用する組合なら、安全な低温殺菌牛乳の生産に取り組んでくれるかもしれない」と考えたことから、東毛酪農に話が持ち込まれた。昭和57(1982)年7月のことであった。この消費者を代表とするグループからは、子どもたちに母乳に近い(加熱せずに飲める)牛乳を飲ませたいとして、(1)原料乳は安全な飼料を食べている健康な乳牛からの生乳とすること、(2)搾りたての生乳にできるだけ手を加えず、牛乳本来の風味・質などを保つため、低温殺菌のノンホモゲナイズとすること、(3)リサイクルを考え、瓶容器とすること―という3つの要望が提示された。しかし、組合内からは当時の原料乳の生菌数から考えて「低温殺菌で事故でも起きたら一大事」という懸念が示され、生産者からも「原料乳の生菌数を減らし、さらに自給飼料を増やすには今まで以上の重労働が強いられる」との声が挙がったという。組合内で検討が重ねられる中、当時の根岸孝組合長による「これからの酪農の進むべき道を消費者と組んで探っていこう」という説得が功を奏し、低温殺菌牛乳の生産に踏み切ることとなった。そして、消費者、酪農家および東毛酪農の三者の代表で組織する「みんなの牛乳勉強会」で要望・提案を収集しながら、それらについて酪農家で組織する「低温殺菌牛乳指定指導委員会」で検討を重ねることで、両者の距離を縮める努力が継続され、現在の低温殺菌牛乳をはじめとするさまざまな製品が生まれたのである。消費者の要望に最大限にこたえた低温殺菌牛乳とこれに対する取り組みは、各方面から高い評価を得ている。
2.低温殺菌牛乳の生産は、生産者の努力から始まる
低温殺菌牛乳は、一般に62〜65℃で生乳を加熱する低温保持式殺菌法(LTLT)により生産された牛乳を指し、この方法によりパスツールがワインの殺菌方法を確立したことにちなみ、「パスチャライズド牛乳」(以下「パス乳」)ともいわれる。東毛酪農のLTLTは、クリームライン形成へのこだわり(第4章参照)から、63℃で30分間加熱処理する方法であるが、63℃の加熱で大腸菌群を陰性にするためには、原料乳中の生菌数を減少させる努力が不可欠となる。東毛酪農では、「安全な牛乳」は生菌数の少ない「クリーンな原料乳」を集めることから始まると考えている。そこで東毛酪農では、パス乳の原料乳中の基準細菌数を1ミリリットル当たり2万以下とし、さらに同1万以下を努力目標とする独自の設定を行っている。同組合の看板商品の1つであるパス乳の生産に適した原料乳を生産するため、酪農家と丁寧に向き合い、乳質の向上を目指す体制を築き上げる過程では多くの試行錯誤があった。そこで取り組まれたのが、乳質向上巡回指導、指定農家制度およびプレミアム(報奨金制度)の導入である。パス乳の生産に取りかかった昭和57(1982)年当時は、酪農家ごとに日々乳質にむらがあることが問題となった。酪農家には、飼養管理においてそれぞれ長年培った経験があり、同時にそれに則した習慣があるため、組合側からの一方的な指導では改善に限界があるとの考えから、乳質検査結果のフィードバック(回数、速報性)に重点を置くこととした。毎日のサンプリングに加え、月6回の乳質検査(集乳時)を実施し、生菌数、大腸菌数、乳脂肪、乳たんぱく、乳糖、体細胞数のチェックおよび官能検査などを項目とした。酪農家は、飼養管理方法を詳細に指導されるよりも、数値を目前に示された方が、改善の必要性を認識することができ、これが指導員にアドバイスを求めるきっかけになるとのことであった。巡回指導には、東毛酪農の事業部および牛乳工場の職員、組合役員が3人で1班を組んで当たり、県の家畜保健衛生所の職員が加わることもある。かつては頻繁に実施していたが、指導が浸透してきたため、最近は年1回となっている。指導に当たっては「5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、習慣づけ)」と銘打たれた衛生管理の目標が達成されているか目視によって確認するほか、生産履歴を正確に記録しているか確認することなどが中心とされている。必要な場合には注意を促すが、基本的には酪農家側の自発性が尊重されている。各酪農家が集乳所に自ら生乳を運んでいた頃は、そこが情報交換の場として機能していたが、タンクローリーによる集乳になった今では指導員とのやり取りが重要な情報交換の役割を果たしている。
巡回指導が乳質向上に効果を発揮するためには、乳質検査に対する酪農家の積極的な対応が前提とされるため、酪農家の意欲を刺激する対策が必要となる。このため、東毛酪農ではプレミアムを導入している。これは、乳質検査のチェック項目ごとに組合が独自に採点基準(表1)を定め、点数化する仕組みが採用されており、農家に支払われる乳価は群馬県一律の乳価にプレミアムを上乗せした金額となる。以前は、乳質の基準点数と、乳牛の運動場を整備していることなど条件を満たしている「指定農家」(パス乳など特定商品の原料となる生乳を生産する酪農家)のみにプレミアムが付与されていたが、現在は指定農家以外の酪農家でも、乳質の基準点数さえ満たせばプレミアムが付与される。プレミアムについては、平等の観点から批判がなされたこともあった。しかし、乳量によるものの、成績上位の酪農家に「プレミアムだけで生活できる」額を供出することにより、批判よりも「やる気がでる」との積極的な意見が多勢を占めるようになったとのことである。成績優秀者には、プレミアムだけで年間250万円程度が支払われた実績もあるという。衛生的な飼養管理の徹底、ひいては乳質を向上させることは、酪農家にとって収入の増加に直結するわけだが、この点において「家族経営の場合、一番関心が高く熱心に取り組むのは家計を預かる女性」とのことで、巡回指導や勉強会には夫婦同伴での参加を呼びかけることにしているという。
表1 乳質採点基準
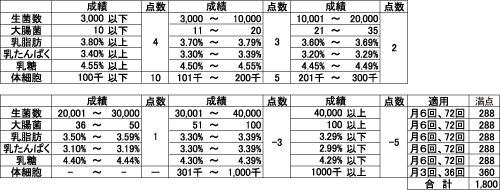
資料:東毛酪農業協同組合
注1:点数ごとの単価は、月ごとに変動する。
注2:体細胞数については、県が月3回実施している乳質検査値を使用
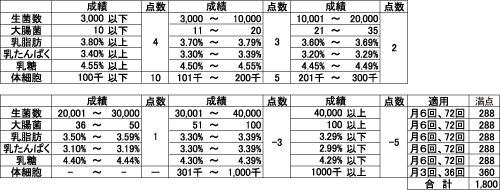
資料:東毛酪農業協同組合
注1:点数ごとの単価は、月ごとに変動する。
注2:体細胞数については、県が月3回実施している乳質検査値を使用
巡回指導やプレミアムによるインセンティブ効果もあって、生菌検査で1ミリリットル当たり10万未満となった東毛酪農の生乳の比率は、群馬県の平均をおおむね上回って推移している(表2)。プレミアムの点数基準もこれに対応し、導入以来3回ほど改定している。
表2 乳質の推移
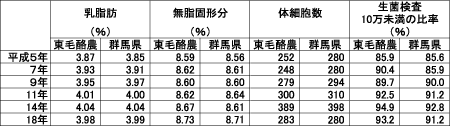
資料:東毛酪農業協同組合
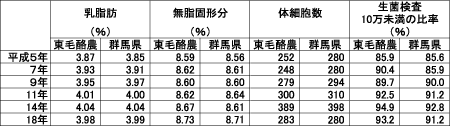
資料:東毛酪農業協同組合
なお、指定農家の条件であった「牛の運動場を整備している」という項目は、乳牛の生理に則すれば3時間ごとに少しずつ給餌することが最適との考えを実践するに当たり、乳牛を運動場に放牧する時間を十分に確保することが難しくなったため、撤廃されている。現在は、点数基準を満たすことに加え、非遺伝子組み換え(non-GMO)飼料を給与することが条件として追加されている。証明書付きnon-GMO飼料は、一般の配合飼料と比較し高価なため、奨励金を交付し、その生乳はnon-GMO飼料給与の乳牛由来の牛乳として販売される「東毛酪農協牛乳」の原料として使用される。現在、37戸中15戸が指定農家とされている。
3.自給飼料増産で「安全な牛乳」を追求する
消費者から「安全な低温殺菌牛乳」の生産を依頼された際、要望の一つに「乳牛に安全なえさを給与して欲しい」というものがあった。その点を「粗飼料自給率の向上」で追及することとし、以前から取り組んでいた利根川沿いの野草を利用した粗飼料生産の拡充に努め、東毛酪農の特色あるえさ作りの取り組みの一つとして発展した。東毛酪農が最初に野草利用に着眼したのは、昭和48(1973)年の第一次オイルショック後のことである。多頭化が進み、粗飼料を家族労働による自家生産で賄うには限界が生じていたところに、オイルショックによる輸入粗飼料の高騰が起こった。そこで、太田市の南側を流れる利根川の河川敷にそよぐ野草を利用する案が挙がった。利根川の堤防管理は、建設省(当時)と契約した堤防清掃業者が請け負い、野草を刈り取り焼却し処分していた。当初は、同省が東毛酪農による河川敷の組織的利用について難色を示したため、清掃業者が刈り取った野草を組合が梱包し、運び出すことから始まった。昭和53(1978)年には、河川愛護団体として優遇されることとなり、同省と堤防敷・河川敷合計約518ヘクタールについての利用契約が締結された。一般的に河川敷を農業利用する場合は、これを管理する国土交通省に対し占有料を支払う必要があるが、東毛酪農は自生する野草を刈り取るだけなので、特にその義務は生じていないとのことである。
昭和61(1986)年には大型牧草梱包機(ロールべーラー)を導入し、利用契約が締結された518ヘクタールのうち刈り取り対象となる敷地面積が大幅に拡大した。当時は、1ロール当たり500〜700キログラムのものを年間1万個程度生産することができた。利根川中流の河川敷であり、その下流で利根大堰を介して東京都および埼玉県への上水供給を行っていることから、水質保持のため施肥することが禁じられており、当然、農薬も散布していない。野草利用においては刈り取りを行うのみで、それらの作業には主に組合職員が従事している。現在、150ヘクタールで刈り取りを実施しており、梱包した野草は、1ロール当たり5,000〜6,000円で組合員向けに販売される。
ロールべーラーを導入した際には、組合員から「本当に必要なのか」と一部に批判の声が挙がったという。しかし、粗飼料の自家生産を行う酪農家のために東毛酪農が梱包の内容確認を始めたところ、酪農家の女性から大きな好評を得た。それまで、主に飼料作りに取り組んでいたのは酪農家の女性であり、機械導入以前、1梱包当たり20キログラム程度のものを運搬するのは一苦労であり、梱包作業を東毛酪農に委託することにより、重労働から解放されたためである。機械導入以前から、粗飼料の自家生産のみならず、家畜排せつ物処理の必要性もあって、各酪農家に飼料畑の確保を促してきたが、牧草作りの労働負担が重く、簡易サイロによる調製がうまくいかないこともあり、家畜疾病が増加することもあったという。このため、酪農家は輸入粗飼料に頼りがちであったが、東毛酪農の梱包受託が始まってからは、各酪農家にとって粗飼料生産の省力化が実現され、自給飼料を無農薬で栽培することができるまでになった。傘下の酪農家では、主に夏はスーダングラス、冬はイタリアンライグラスを作付けしているところが多く、下草除去のために農薬を使うデントコーンは、奨励していないという。この地域は、民家との混住化が進んでおり、増頭による経営の拡大が難しい中、それでも無農薬の自給粗飼料増産にこだわる理由は、「乳牛に安全な粗飼料を給与して欲しい」という消費者の要求にこたえるためである。現在では、5〜7戸の酪農家が共同でロールべーラーを導入したり、ロールベールを運搬するための手作りのリアフォークを製作したりするなどして、それぞれ省力化に努めている。
また、東毛酪農では飼料の低コスト化の一環として、群馬県内で生産された細身で商品にならない大麦を地元農協から1キログラム当たり25円で購入し、国産飼料の使用比率を高めているが、大麦の生産量自体が少ないため、国産大麦の確保は難しい状況である。
4.「目で見る温度」クリームラインにこだわる低温殺菌
飼養管理を徹底した乳牛から生産された生乳は、毎朝東毛酪農のタンクローリーにより集乳されるが、各農家のバルククーラーから吸い上げる際には、乳質を損なわないよう集乳ポンプの回転速度を落とし、丁寧に工場まで運搬する。東毛酪農がこうしたことに細心の注意を払うのは、牛乳の生産過程のすべてにおいて貫かれている「酪農家が搾った生乳そのままの味を知って欲しい。だから、なるべく手を加えずに牛乳を作りたい」という、消費者との話し合いの中で共に築き上げてきた理念がある。 |
 |
| 岡本雄司氏。経産牛52頭(うち搾乳中のもの42頭)、育成牛15頭程度を飼養。1日当たりの平均生乳生産量は約1,200キログラムで、1頭当たりの年間平均生乳生産量は8,000キログラム強。東毛酪農では、1頭当たりの年間泌乳量は乳牛に負担をかけない8,000キログラム程度を目指し、それ以上の生乳生産量を求めるよりも乳質の向上に重点を置いている。岡本氏も、優良牛乳の出荷者として東毛酪農から表彰を受けている。今後は生産資材や燃料価格の高騰など増加が懸念されるが、「プレミアムのおかげで何とかやっていける」とのこと。後ろは、手作りのリアフォーク。 | |
 |
(左)岡本氏の飼料畑。6ヘクタールの飼料畑の大部分は耕作をやめた耕種農家からの借地で、イタリアンライグラスおよびスーダングラスをロールベールで年間合計400個(ロールベーラーによる梱包は東毛酪農に1個当たり2,500円で委託)生産している。1日1個を乳牛に給与し、粗飼料の3分の1を賄う。不足分は東毛酪農から購入。配合飼料価格が高騰しているので、粗飼料はできる限り自給で賄いたいとしている。写真左奥はたい肥舎。 |
集荷された生乳は、パス乳向け、オーガニック向け(non-GMO飼料給与)、一般の超高温瞬間処理法(UHT)による牛乳向けなど目的別にタンクに分けて貯蔵される。そのため、指定農家の生乳の集荷は一般の農家とは別に行われる。看板商品でもあるパス乳の原料乳は7℃で保存され、350リットルのバッチパスチャライザー(1バッチ当たり5分で溜まるようにしている)7個を通過させて加熱殺菌する。前処理に20分間をかけ、63℃に達してから30分間加熱する。小型のタンクを通過させるやり方は一見非効率なようだが、大型のタンクにした場合、最後にタンクから出てくる生乳は40分以上加熱されてしまうことになるため、小型タンクを採用しているとのことであった。63℃・30分間の加熱処理にこだわるのは、東毛酪農が健康な乳牛由来の生乳を丁寧に工場まで運び、厳密な温度管理の下で殺菌し、高温高圧で脂肪球を破壊(ホモゲナイズ)していないというあかしとして、パス乳にクリームライン(牛乳中の脂肪球が上部に浮かんでできる層)が形成されることを重視しているからである。東毛酪農によると、クリームラインが形成されるためには、ホモゲナイズ処理をしないことと、63℃以上の熱を加えないことが必要とされる。東毛酪農ではこのクリームラインを「目で見る(殺菌)温度」と表現していた。クリームラインの形成は、日によって多少の差が出てしまうこともあるそうだが、熱心な購入者からは、「今日の出来はよくない」と指摘を受けることもあるという。瓶牛乳の生産には、昭和62(1987)年から取り組んでいるが、瓶入りはクリームラインの形成の出来が一目で判断できるため、生産者側も、日々気を抜くことはできないとしている。
なお、平成14(2002)年12月20日付け厚生労働省令第164号により、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(乳等省令)の一部が改正され、低温殺菌牛乳の加熱殺菌処理の条件が、(1)熱処理が保持式の場合は、保持温度までの昇熱時間が20分以上である場合に限り、保持温度を63〜65℃とし、30分間保持すること、(2)熱処理が連続式などの場合は、保持温度までの昇温時間が20分未満である場合には、保持温度を65〜68℃として30分間保持しなければならない―とされた。しかし、前述の通り、東毛酪農のパス乳はクリームラインの形成を重視し、63℃以上の過熱を避けなければならないため、(1)の方法による必要があった。先に20分の前処理を行うとした必要性は、あくまでクリームライン形成のこだわりによるものである。

パス乳のクリームライン

低温保持式殺菌法によるバッチパスチャライザー
瓶牛乳は、200ミリリットル入りと720ミリリットル入りが生産されているが、これもまた、環境問題の観点から容器回収が可能なこと、内容物が見えるため安全であることなどから消費者が要求し、実現したものである。東毛酪農によると、新設したばかりの紙パック専用工場に瓶ラインを増設するに当たり、「小規模酪農組合」が多額の投資を行うために理事会のみならず組合員全体会議まで開催し、組合員全員の了解を得たとされ、消費者が「販売量の拡大に協力する」という合意の上、増設が決定されたとしている。
また、瓶の再使用の基本として、顧客には回収前に洗浄をすることや、ごみを瓶の中に入れないことなどの協力を依頼する。瓶の回収率は宅配向けのものを中心に9割程度であり、約60回使用されるが、駅の売店やスーパーなどでは、今のところ回収する仕組みができあがっていないとのことであった。以前、大手量販店において、持参された空き瓶に対し返金するシステムを構築したことがあった。これは、買い物金額から減額する方法であったが、レジスターに減額機能を付与することができず、客がレシートを持って別のサービスカウンターに回らなければならなかったため、定着させることができなかったという。
現在、工場の1日当たり処理量は最大28トンで、そのうち11トンが宅配・直販用に仕向けられており、首都圏を中心としたポスト(共同購入グループ)向けの直接宅配商品「みんなの牛乳」、首都圏の牛乳専売店向けの宅配用商品「牛乳屋の低温殺菌牛乳」として販売されている。
図3 東毛酪農 主な商品のミルクフロー
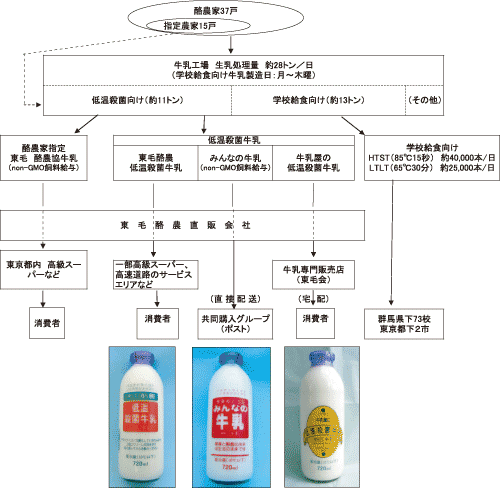
*東毛酪農からの聞き取りにより作成
注:学校給食用牛乳の製造がないときは、余剰生乳は他者の乳業工場などに搬送する。
(写真提供:東毛酪農業協同組合)
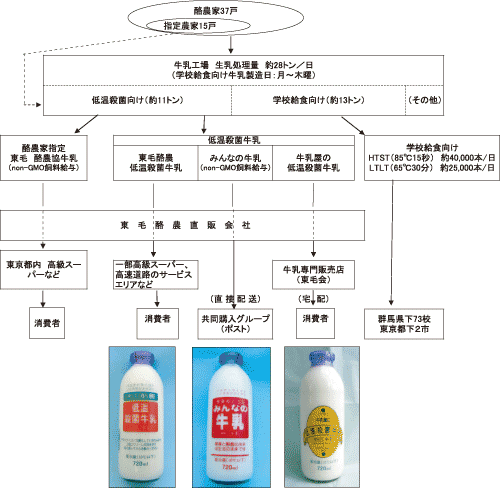
*東毛酪農からの聞き取りにより作成
注:学校給食用牛乳の製造がないときは、余剰生乳は他者の乳業工場などに搬送する。
(写真提供:東毛酪農業協同組合)
5.大手メーカーにできないこととは何か
〜消費者と生産者の一体感が販路を拡大する〜
首都圏の牛乳専売店向けの瓶牛乳「牛乳屋の低温殺菌牛乳」は、東毛会を通じて消費者の手元に届く。東毛会は、東京都内で宅配などを行う牛乳販売店が構成する組織で、現在は130店ほどが東毛酪農の瓶入りパス乳を販売している。東毛酪農にとっては、スーパーなど量販店で販売を展開するよりも瓶回収の点で効率がよく、牛乳販売店にとっては量販店にないオリジナル商品を扱えるという点で双方にメリットがある。東毛会と組んだ瓶牛乳の販売を始めるに当たっては、瓶牛乳の生産を要望した消費者グループが、自らボランティアとして東京都内の住宅を回りセールスを展開したという。共同購入、または牛乳専売店からの購入により東毛酪農の商品を手にする消費者には、熱心な支持者が多いといわれる。東毛酪農によると低温殺菌やクリームラインなどにこだわった牛乳の風味が評価されていることのみならず、「河川敷の無農薬のえさを給与している」という点も食品に関心が高い消費者の興味を引いているようだ。東毛酪農の幹部も「興味を持って飲み始めた方は、(他の商品に)浮気をしない」と自信をのぞかせる。実際、利根川の河川敷のカラシナを除去するために、当時の建設省から除草剤を散布する計画が持ち上がったときには、無農薬の野草を守るために「みんなの牛乳勉強会」の消費者メンバーが手刈りで対応したというエピソードもある。それ以降、勉強会メンバーに限らず、年1回、生産者や消費者の有志による河川敷のカラシナ除去やゴミ拾いが続けられており、百人以上が集まる。昨年は19回目を数え、例年、参加した消費者から乳牛の乳房をふくためのタオルが生産者へ贈呈されている。「生産者の衛生管理に一役買いたい」という消費者の気持ちが込められている。
東毛酪農の大久保克美組合長は、「大手メーカーと競ってコストダウンをするには限界がある。開発力、資金力でもかなわない。同じことをやっていては生き残れない」と言う。その点を、組合は消費者の要望にまじめにこたえる商品を提供することで克服してきた。消費者と生産者の交流を重ねることでなし得た一体感は、消費者による支援と酪農家の向上心を継続させることに成功している。東毛酪農では、今後、販路を拡大し、消費者の支援を拡大していきたいと考えている。現在、首都圏のポストと呼ばれる共同購入グループは、20年前にパス乳生産を要求した消費者グループを中心に高齢化が進んでおり、ポスト数が頭打ちになっている。それに対応するため取り組んだインターネット販売は、少量販売を望む人が多く、運賃の方が高くつくケースもあるため、なかなか主力の買い手にはならないとのことである。そこで、東毛酪農では、首都圏向けが主流であるパス乳の一部を地域限定商品として、地元でも普及に努めたいと考えている。東毛酪農は、「生産履歴だけではなく、誰がどのように搾ったのかまでを開示し、多くの消費者に東毛酪農のパス乳に興味を持って欲しい」としている。「大手と同じ土俵で競争をしない」という方向性は、手間を惜しまずに消費者に向き合う商品作りをすることによって具現化され、牛乳消費の低迷が問題となる現状下における小規模農協の活路の一つを提示している。東毛酪農は、パス乳の生産についてこう語っている。「われわれは、差別化商品を製造しているのではない。本来の牛乳作りをしているのである。」
最後に、今回の調査において多大なご協力をいただいた東毛酪農の大久保克美組合長および關戸董司専務理事、東毛酪農直販株式会社の木村弘常務取締役・営業部長ほか関係者の方々に深く感謝申し上げる。