1.転換を求められている日本酪農
これまで日本酪農の急速な発展は、海外からの輸入穀物に支えられてきた。関税がほとんどかからない輸入飼料の価格と先進国の中で最も高い乳価との差益が酪農経営を成り立たせてきた。比較的飼料基盤に恵まれた北海道でも同様である。しかし、乳価の漸減と飼料穀物の高騰は酪農経営に打撃を与えている。緊急対応として乳価の値上げ、酪農経営の再生産を保証する補給金の増額や配合飼料価格を安定させるための基金への財政支援が求められるが、長期的には自給飼料を活用した酪農への転換が必要とされ、特に放牧は有効な手段として期待される。
2.消費者の酪農イメージと生産現場とのギャップ
大方の消費者は、酪農=放牧と思っている。そのため、北海道を訪れた消費者グループは放牧が行われていない生産現場を見て落胆を隠せない。これは乳業メーカーや農業団体の牛乳の宣伝方法として牧歌的な放牧風景が使われてきたからである。実際、乳牛は牧草地で採草した粗飼料を牛体の維持のために利用し、もっぱら配合飼料の給与によって個体乳量は増加するものとされ、逆に余計な運動を要する放牧は産乳量を減らすものとして敬遠されてきた。また、酪農関連組織も「お金にならない飼養方法」として消極的な対応がとられてきた。しかし、食の安全に対する消費者の関心が高まる中、牛乳の生産工程の情報開示が求められる時代になり、放牧が見直されてきた。
| 図 日本とNZの酪農生産システムの比較 |
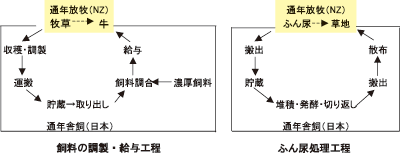 |
3.低コスト手段としての酪農
世界の生乳の生産コストを概観すると、日本の4に対して、アメリカ、EUは2、ニュージーランド(NZ)、オーストラリアは1である。オセアニア両国の低コストは放牧によって可能になっている。図は日本とNZの酪農の生産システムをみたものである。日本では牧草収穫は機械で行われ、収穫物はサイレージや乾草に調製されサイロや倉庫に貯蔵される。それらは再び取り出され給与される。一方、NZでは牛舎はなく通年放牧であるため牛が直接牧草を食べる。これはふん尿処理についても同様である。日本では排せつされたふん尿を人間が機械を使って搬出し、貯蔵し、取り出して散布する。しかし、NZでは牛が草地に直接排せつする。これら日本の酪農生産システムは迂(う)回生産・処理工程と称され、たくさんの労働力と機械、エネルギーが必要となり生乳のコストを高くしている。一方、放牧は牛の動く機能を積極的に使うことで生産コストを低くしている。
4.集約放牧による低コスト方策
昔の放牧を経験した生産者は、放牧は牛舎の出し入れに労力がかかることや粗放な土地利用のため個体乳量が落ちるものと考えてきた。これらの問題点を克服したのがNZやオーストラリアで行われている集約放牧で、電気牧柵や牧道を使って牛の動きをコントロールし、さらに放牧地を電気牧柵で区切り小牧区を作り、毎日利用する牧区を変える輪換放牧によって草地の利用率を最大限に高めている。そこでは短い草(15〜20センチメートル)を何回も繰り返し利用する。短草は栄養価が高く、消化率も高くなる。また、草丈の短いクローバーなどの高栄養牧草が繁茂してくる。このように電気牧柵、牧道と短草と高栄養牧草品種の活用によって濃厚飼料を大幅に減らす酪農システムが集約放牧である。
5.酪農の未来を担う放牧
牛は本来、人間が食さない草を牛乳に変えることのできる素晴らしい家畜であるが、穀物を牛に給与することは間接的に飢餓の原因となる。日本は寒冷地や山地をたくさん抱え、草資源が豊富な国なので国土資源を活用した自給飼料型の酪農に転換すべきであろう。また、牛は動物なので、牛舎に拘束すること自体ストレスを増し、病気の原因となる。現在、EUでは家畜福祉の基準が制定され、いずれは日本にも入ってくるであろう。放牧を柱とした家畜福祉は有機酪農の必要条件となっている。有機酪農はEUやオーストラリアでは盛んになっており、オーガニック牛乳、乳製品がスーパーの棚に並んでいる。これからの貿易交渉の如何によっては、国際的な価格競争、品質競争がますます激化するであろう。そのため、生産コストを下げ牛乳の品質を高める放牧は将来の日本酪農の発展にとっては欠かせない生産システムになるものと思われる。
〈引用文献〉
荒木和秋著『世界を制覇するニュージーランド酪農』
(デーリィマン社、2003)P143 |

