本稿では、近年のわが国と主要国の1人当たり家計消費支出や消費者物価指数の推移などを比較することにより、国民生活の重要な側面を表す消費支出において、世界の中でわが国が極めて特異的な動きをしていることを概説する。
日本と主要国の1人当たり家計最終消費支出
−日本のみ、1人当たり家計最終消費支出が減少−
わが国とNAFTA(米国、カナダ、メキシコ)、EU主要国(英国、フランス、ドイツ)、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)、食料の重要な供給国アルゼンチンおよび資源大国豪州の1995年〜2005年における1人当たり家計最終消費支出(各国通貨ベース)を比較した。いずれの国も年々同消費支出が増加しているのに対して、日本だけが1997年をピークに減少傾向という特異的な動きをしていることが分かる。
なお、計算は次により行った。
1人当たり家計最終消費支出
=各国の家計最終消費支出(Household final consumption expenditure)年間総額÷各年の人口
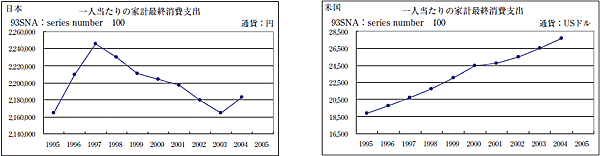 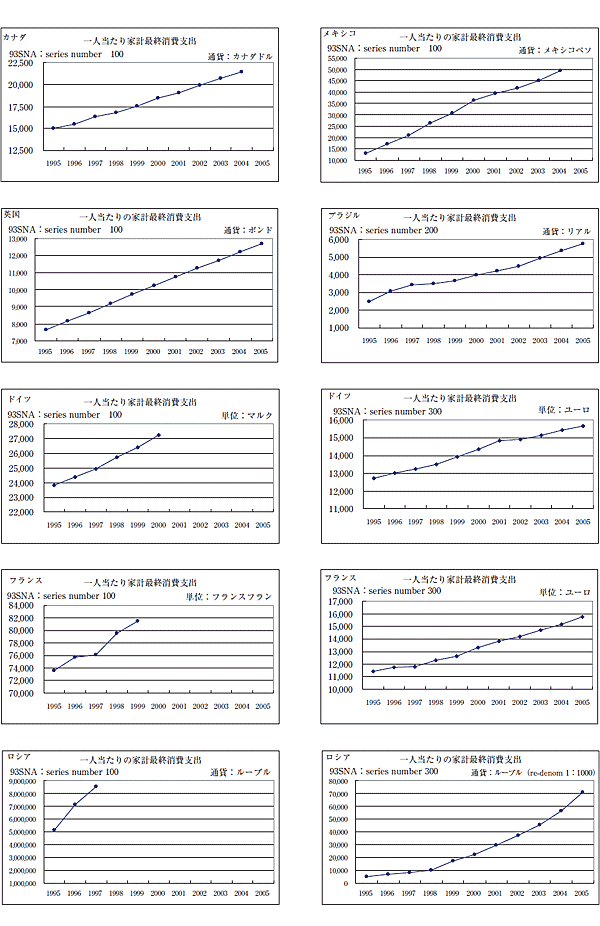 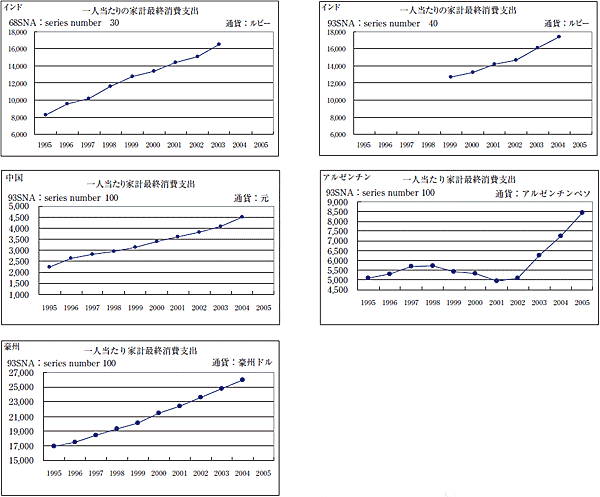 |
| 資料:United Nations Division―Household final consumption expenditure,current prices(code30236) 総務省「世界の統計2006」2−3 主要国の人口の推移(1995―2005) 注:各グラフに記されたSNA(System of National Accounts)series numberは100、200、300など(インドのみ30、40)があるが、数字が多いほど新しいデータを用いたものであり、それ以上の意味はない。 |
主要国の消費者物価指数(CPI)の比較
−日本は世界でもまれな消費者物価の安定国−
わが国が1人当たりの家計消費支出において特異的な下落傾向を示していることについて、その背景、要因を考えてみる。わが国のほか、前述のNAFTA、EU主要国、BRICsなど12ヵ国に産油国代表のサウジアラビアを加えた14ヵ国の、2000年〜2007年(2008年は予測)におけるCPI(2000年=100)を比較すると、次のような特徴が浮かび上がる。
(1)日本の消費者物価の安定度が際立っている。
(2)各国のCPIは上昇を続けているが、日本の消費者物価は横ばいないし低下傾向にあった。(2005年を底に、2年連続でCPIはごくわずか上昇。CPI上昇率は06年+0.5%、07年(見込)+0.3%)
(3)通貨危機などの影響と、その後の世界の資源、食料需要の強さに支えられて好景気の国々はインフレ傾向で物価上昇率が非常に高い。特に、ロシア、アルゼンチン、ブラジルの上昇率が群を抜いて高い。
(4)中国は2007年には、豚肉、鶏卵の価格高騰が主因で十数年ぶりの高いCPI上昇を記録したが、政府による物価統制が効いており、他のBRICs諸国、新興経済国に比較すると消費者物価は安定している。
(5)EU諸国(フランス、ドイツ、英国)は比較的消費者物価が安定しているものの、継続的な上昇傾向 に変わりはない。
(6)サウジアラビアは日本に次いで消費者物価が安定しているが、2001年を底に上昇傾向がみられる。
消費者物価指数(CPI)の推移2000年=100
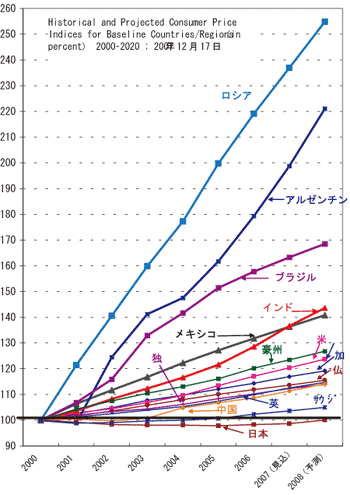
資料:International Financial Statistics, International Monetary Fund and ERS Baseline Regional Aggregations
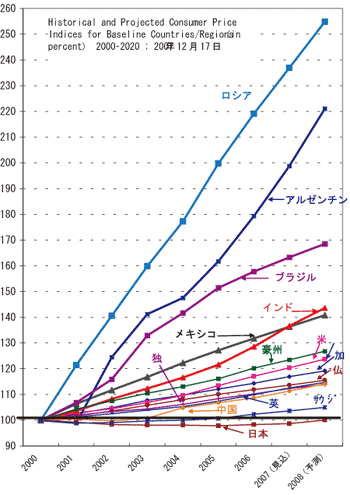
資料:International Financial Statistics, International Monetary Fund and ERS Baseline Regional Aggregations
上図の拡大
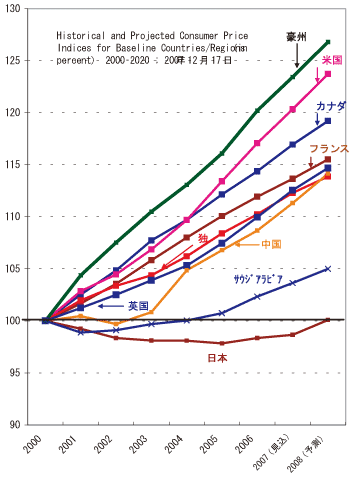
資料:International Financial Statistics, International Monetary Fund and ERS Baseline Regional Aggregations
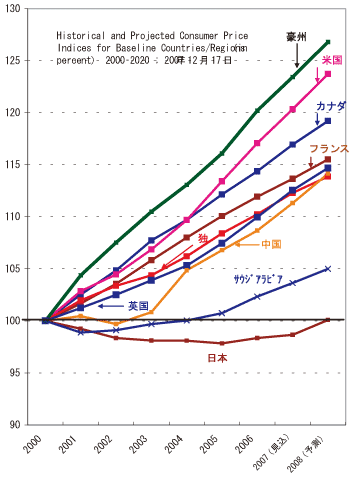
資料:International Financial Statistics, International Monetary Fund and ERS Baseline Regional Aggregations
日本の勤労者世帯は実収入、可処分所得、消費支出とも減少・横ばい
わが国の勤労者世帯の家計(1世帯1ヵ月平均。2人以上の非農林漁家世帯をモデル)は、実数ベース(CPIで調整し実質化していない生のデータ。以下同じ)で実収入、可処分所得、消費支出のいずれもが1997年をピークに2003年まで減少の一途をたどり、2004年にわずかに回復したものの2005年には実収入、可処分所得とも2003年の水準を更に下回った。また、2006年の消費支出320,026円は1990年以降最低の水準であった。このようなわが国の勤労者世帯の家計の状況は、バブル崩壊後のわが国の賃金制度の見直しや人件費抑制策と無縁ではあり得ない。「日本は世界でまれな消費者物価の安定国」であるが、そのようにならざるを得ない経済状況があり、家計においては実収入や可処分所得が10年にわたって減少・横ばいの中で、一般的な勤労者世帯は貯蓄に回すべき分を切り崩しながら家計を守る工夫をしてきたというのが現実であろう。
なお、上表〔勤労者世帯の家計状況の推移(1976〜2006年)〕の黒字率(=(可処分所得−消費支出)÷可処分所得)を「貯蓄率」とみれば、バブル崩壊以降もそれほど貯蓄率は低下しておらず、横ばいとなっている。これに対し「平成17年版国民生活白書」では、貯蓄残高ゼロ世帯が急増している(2003年で21.8%)ことと併せて、内閣府「国民経済計算」(SNA)ベースの家計貯蓄率は低落傾向にあると指摘している。それによると、1990年代初頭に12〜13%であった家計貯蓄率は、2001年〜2003年には5〜6%台と半分以下の水準にまで落ち込んだ。
同白書では、この総務省「家計調査」と内閣府「国民経済計算」(SNA)における「貯蓄率」の違いについて、家計調査の貯蓄率が(1)勤労者世帯のみを対象にしている点、(2)持ち家の帰属家賃を所得および消費に含めていない点、(3)固定資本減耗を考慮しない粗貯蓄となっている点などから生じているとしている。
勤労者世帯の家計(1世帯・1ヵ月平均)・日本
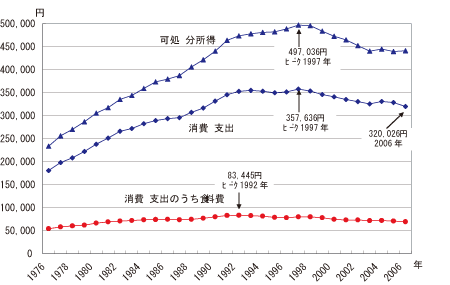
資料:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊、総務省統計局「家計調査年報」
注:2人以上の非農林漁家世帯。可処分所得とは、課税前の家計収入から直接税、社会保険料などを差し引いた残り。
勤労者世帯の可処分所得と平均消費性向(日本)
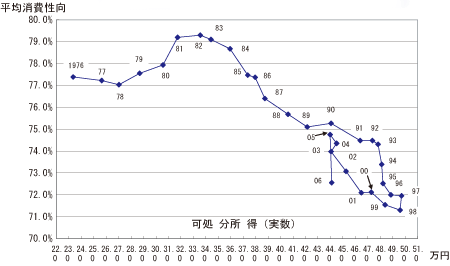
資料:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊、総務省統計局「家計調査年報」
注:2人以上の非農林漁家世帯。消費性向とは、可処分所得に対する消費支出の割合
勤労者世帯の家計状況の推移(1976〜2006年)
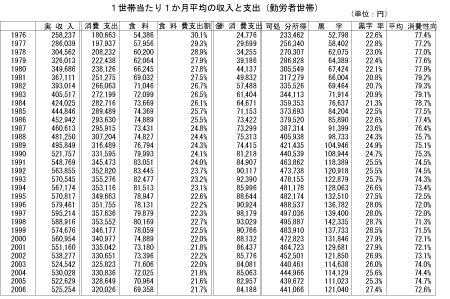
資料:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊、総務省統計局「家計調査年報」
注:本表のデータは勤労者世帯で、2人以上の非農林漁家世帯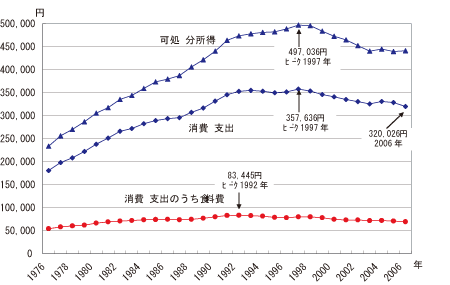
資料:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊、総務省統計局「家計調査年報」
注:2人以上の非農林漁家世帯。可処分所得とは、課税前の家計収入から直接税、社会保険料などを差し引いた残り。
勤労者世帯の可処分所得と平均消費性向(日本)
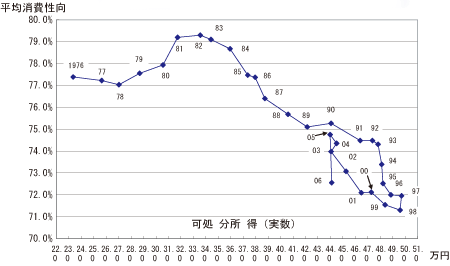
資料:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊、総務省統計局「家計調査年報」
注:2人以上の非農林漁家世帯。消費性向とは、可処分所得に対する消費支出の割合
勤労者世帯の家計状況の推移(1976〜2006年)
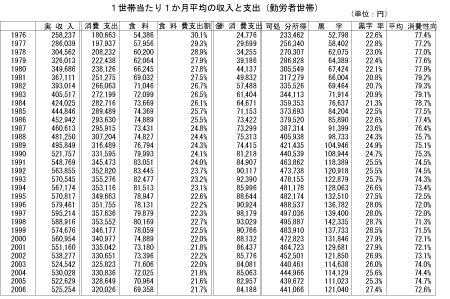
資料:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊、総務省統計局「家計調査年報」
・可処分所得とは、課税前の家計収入から非消費支出(直接税と社会保険料など消費を目的としない義務的支出)を差し引いた残りの所得
・消費支出とは、消費を目的とする財・サービスへの現金支出。具体的には食料、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服・履き物、保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽などの費目
・消費性向とは、可処分所得に対する消費支出の割合
・黒字とは、可処分所得から消費支出を差し引いた額。黒字率とは可処分所得に対する黒字の割合
食料価格を構成する主な要素
−生産・加工・流通、すべての段階で急激なコスト上昇圧力−
米国などのバイオエネルギー政策とそれに伴う原料需要の増加、中国などBRICs諸国に代表される需要の高まり、気候条件の変化など諸要素が食料の需給や価格に影響を及ぼすメカニズムについては、内外の多くの専門家により報告されている。次のフロー図「世界の農業・食料事情」を参照されたい。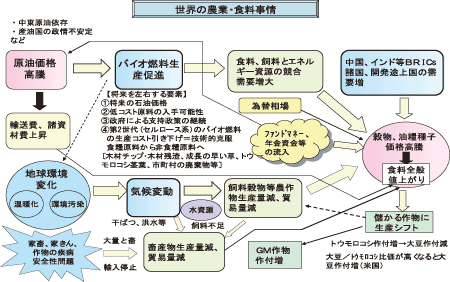
食料品について、国産原料または輸入原料を使った製品が小売店や外食の店頭に並ぶまでの一般的な生産・加工・流通の流れは下図〔食料品が店頭に並ぶまで〕のとおりである。この流れの中で、食料品価格の主な構成要素は次のようなものが想定される。
(1)輸入原料の場合:
食料品価格=原材料の原産地価格+運賃(海上または航空)+保険料+輸入諸掛り+国内流通経費(運賃+倉庫保管料+諸経費+マージン)+加工費(加工賃(人件費)+燃料・光熱水料+包装資材費+保管料など諸経費+マージン)+〔小売段階のコスト+マージン〕
(2)国内原料の場合:
食料品価格=原材料の国内産地価格(生産・収穫に要する労働費+飼料費+肥料費+燃料・光熱水料働費などほ場・牧場管理に係る諸経費+マージン)+国内流通経費(運賃+倉庫保管料+諸経費+マージン)+加工費(加工賃(人件費)+燃料・光熱水料+包装資材費+保管料など諸経費+マージン)+〔小売段階のコスト+マージン〕
輸入に依存している穀物、油糧種子、乳製品、砂糖などの原産地価格の値上がり、原油価格上昇に起因する輸送費の値上がり、生産資材・包装資材などあらゆる資材価格や燃料・光熱水料の値上がりは、生産・加工・流通のすべてのセクターに急激なコスト上昇圧力をかけ、販売価格の値上げを余儀なくさせている。国産であっても、多くを輸入飼料穀物に依存している畜産業は、飼料費の大幅な値上がりや各種生産資材価格の上昇とそれらの高値安定が、国の施策であるセーフティーネットの枠組みを超え、こうしたコスト上昇分が生産者価格に反映されなければ農家の経営の存続に関わるという非常に切迫した状況に置かれている。
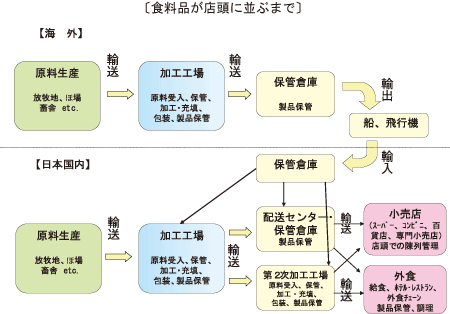
おわりに
2008年に入り、2月から食品関連メーカーなどによる値上げが相次いでいる。これまでの述べてきたような家計状況、デフレ傾向の中、小売価格を上げれば消費者の購入量が減る(売上減)懸念もあり、値上げは生産、加工、流通各セクターにとって存続がかかった決断であろう。消費者を含め原料、諸資材コストの上昇分を各セクターが分担し合うことは、わが国だけではなく各国共通の課題である。
こうしたコスト上昇分は、一部のセクターのみがバッファー(緩衝剤)となって担うことは難しいと考えられ、生産、加工、流通、小売、消費者のそれぞれの段階で分担し合う必要があるのではないか。
さらに、非遺伝子組み換え大豆のみを選別輸入したり、今般の中国製ギョーザ問題をめぐる中国製冷凍食品撤去の動きに見られるように、食品の安全・衛生面でのわずかなリスクをも回避して原料や製品を選別すればするほど、「安全・安心のための選別コスト」ともいうべき新たなコストが加わる。消費者であるわれわれは、「安全・安心」を求める一方でなく、そのコストを負担する責任があることを自覚しなければならない。
本稿は、食料をめぐりわが国が現在置かれている状況を理解するための材料を提供したにすぎず、さらなる分析が必要と考えている。読者諸氏のご批判を賜わりたい。