1 はじめに
−なぜ、畜産飼料を増産し、利益を上げることが可能なのか−
鹿児島県志布志市にある野菜生産法人が、「契約野菜(実需者との契約による野菜栽培)」に特化した輪作体系(ケール、バレイショ、甘藷(かんしょ)など)の中にトウモロコシを取り入れ、積極的に作付面積を拡大し、畜産飼料づくりで「利益」を上げている。
トウモロコシの作付面積は、作付けを始めた平成16年はわずか4ヘクタールであったが、平成19年の延べ作付面積は、この4年間で20倍の伸びとなる80ヘクタールに拡大し、20年は、さらに10ヘクタール上回る90ヘクタールが見込まれている(図1)。
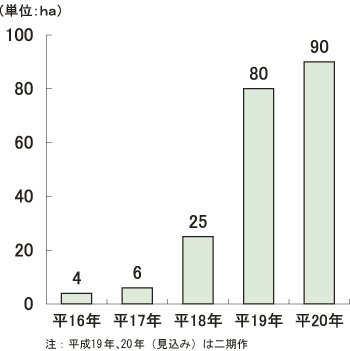
畜産業に不案内であったこの野菜生産法人による「畜産飼料を生産する」という発想は、「もうけなくても損はしない」というこれまで大手食品企業との間で培われた「契約野菜」の経験に根差しており、その経営は、パソコンを活用したデータベースに基づくサイバー農業(パソコンによるシミュレーションに基づいて包括的に管理された一連の生産体系)により管理されている。
また、この経営のユニークな点は、農地管理にある。当法人が所有する農地は、2ヘクタールに過ぎないが、耕作放棄地などを借り受けることで農地を拡大し、19年に借り受けた農地は、所有する農地の36倍に当たる71ヘクタールとなる(写真1)。

写真1 畑に生まれ変わる農地
穀物価格の高騰などから、自給飼料の安定的な確保が急がれる一方、全国の耕作放棄地は年々拡大し(平成17年:38.6万ヘクタール)、今や琵琶湖(6.7万ヘクタール)の5.7倍、東京都(21.9万ヘクタール)の1.8倍に匹敵する広さまでに及んでいる。
こうした中にあって、なぜ、畜産業からではなく異業種である野菜生産法人が、借り受けにより耕作放棄地などの農地を拡大させ、畜産飼料を増産し、「利益が上がる農業」を可能にしているのか。
本稿では、この野菜生産法人である有限会社坂上(さかうえ)芝園が取り組んでいる土地に根差した経営を掘り下げて整理することは、効率的な飼料生産を考える上で、また、多様な形での新たな担い手を考える上で有益であると考え、その手法について紹介する(図2)。
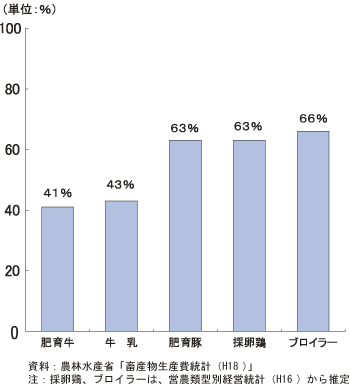
2 概要
鹿児島県志布志市(人口約3万5千人:平成20年8月1日現在)は、平成18年に曽於郡松山町、志布志町、有明町が合併して発足した。鹿児島県の東部・大隅半島の付け根に位置し、宮崎県南部と接しており、南東部には志布志湾を望む。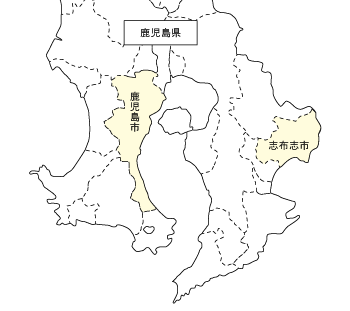
曽於地域は、豊富な粗飼料基盤に支えられた全国有数の肉用牛生産地であり、平成19年の飼養戸数は3,770戸、肉用牛飼養頭数は66,400頭であり、曽於地域の肉用牛飼養頭数は、鹿児島県全体の約2割を占める。また、鹿児島県内の黒豚の一大産地でもあり、豚の飼養戸数は202戸、飼養頭数は318,800頭、このうち黒豚飼養頭数は、子取り用雌豚が9,794頭である(図3)(図4)。
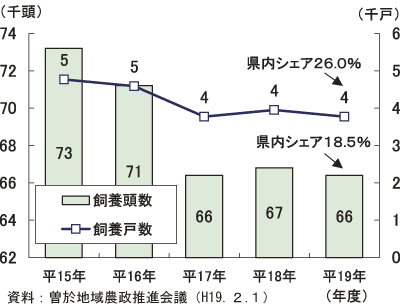
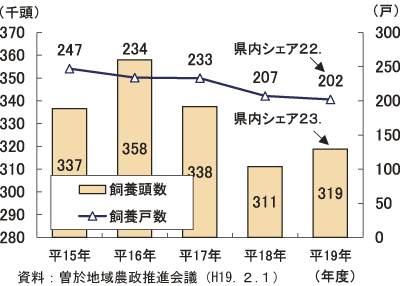
同地域の畜産農家の年齢別構成を見ると、全国の傾向と同様に高齢化が進み、肉用牛繁殖農家では65歳以上が全体の66%以上を占めており、そのうち9割近くで後継者がいない状況である(図5)。
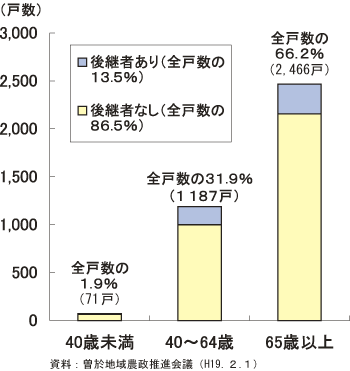
1.青刈りトウモロコシサイレージの生産、販売に至るまでの経緯
1)社名のとおり、もともとは芝の栽培農家
−設立経緯−
坂上芝園は、社名のとおり、もともとは芝の栽培と販売を昭和62年に開始した。平成7年に資金繰りや営業業務を強化するため有限会社化、耕作放棄地などを借り受けて耕作農地を拡大し、露地野菜などを栽培・販売している。
有限会社化後の実質的な経営は、創業者である父親の坂上平代表取締役から息子の坂上隆専務取締役(昭和43年生、平成4年に就農)に引き継がれている。
芝の栽培と販売は、創業時からの顧客との関係に限り続けていたが、本年からは行われていない。このため、社名の変更が検討されたそうだが、創業からの愛着もあり、あえて変更していないとしている。
2)大根の大損失から、単価は安いがすべて「契約野菜」に切り替え
−露地野菜栽培を「契約野菜」に特化−
法人化した平成7年に、高値を期待して青果市場向けの青首大根生産に取り組んだが、期待に反し価格低迷が続き、「家1軒分」に相当する大損失を負った(坂上専務)。この「市場取引」での失敗を契機に同じ轍は踏むまいと、市場価格にゆだねた経営から離れ、露地野菜栽培すべてについて、安くても売り先が決まっている「契約野菜」に特化することを経営の柱に据えている(坂上専務)。坂上専務によると、経営に対する考え方は、これを契機として野菜を栽培するということではなく、「実需者が必要とするサービスという“製品”を売る」という考え方に切り替えたとしている。
「契約野菜」による栽培は、8年のコンビニ向け加工用大根栽培に始まり、11年に無農薬の青汁原料用ケールを栽培、翌年に大手製菓企業向けのポテトチップス用バレイショを栽培した。また、13年からは焼酎用甘藷(かんしょ)の栽培などを展開している(表1)。
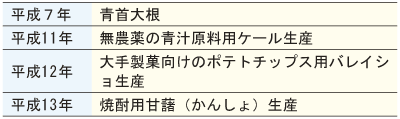
3)ソルゴーのすき込みからヒント
−青刈りトウモロコシサイレージの生産を開始−
青刈りトウモロコシサイレージの取り組みのきっかけは、当時の主要な栽培品目であった大根の線虫防除に多額の農薬費を要しており、その節減のために、ソルゴーを植えつけ、緑肥としてすき込んでいたが、すき込むくらいなら畜産飼料として利用したいとの話を聞いたことによる(坂上専務)。
これが現在の飼料生産ビジネスにつながり、平成15年にトウモロコシ・ソルゴー混播で12ヘクタールを作付け、16年に畜産飼料としてトウモロコシを4ヘクタール作付けた後、17年から事業として本格的に、輪作体系の中に取り入れてトウモロコシ栽培を開始した。
2.経営の概要
1)自身が所有する耕作農地はわずか2ヘクタール
−栽培品目、作付面積など−
平成19年における作付けは、(1)ケール(作付面積25ヘクタール)、(2)バレイショ(同14ヘクタール)、(3)焼酎用甘藷(かんしょ)(同8ヘクタール)、(4)飼料用トウモロコシ(二期作で同80ヘクタール(一期作、二期作とも40ヘクタール))の4品目である。輪作体系により「契約野菜」やトウモロコシが計画的に作付けされており、延べの作付面積は127ヘクタールとなる(図6)。
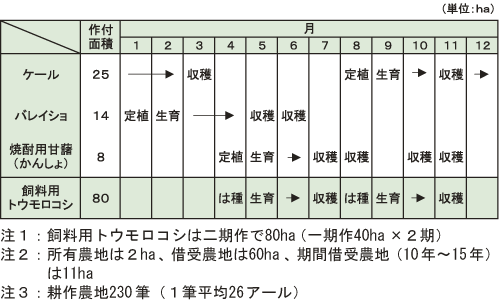
このうち、自身が所有する農地は2ヘクタールに過ぎないが、借受農地は60ヘクタール、期間借受農地(裏作期間のみの借り入れ、10年〜15年)は11ヘクタールあり、耕作農地は230筆(1筆平均26アール)に及んでいる。また、20年における借入農地はさらに5ヘクタール増え65ヘクタール(250筆)が計画されている。
2)この4年間で20倍の伸び、平成20年はさらに10ヘクタールの拡大
−トウモロコシの作付面積−
トウモロコシの作付けは、平成16年の4へクタールに始まり、本格的に事業を展開した17年は6ヘクタール、18年は25ヘクタール、19年は80ヘクタール(1期作40ヘクタール、2期作40ヘクタール)に拡大し、作付面積は、この4年間で20倍である。
また、20年におけるトウモロコシの作付面積は、さらに10ヘクタール増えて90ヘクタール(販売量1,200トン(1期作40ヘクタール、2期作50ヘクタール))が予定されている。
これにより、畜産飼料としての青刈りトウモロコシサイレージの生産量は、この4年間で13.5倍となる(図7)。
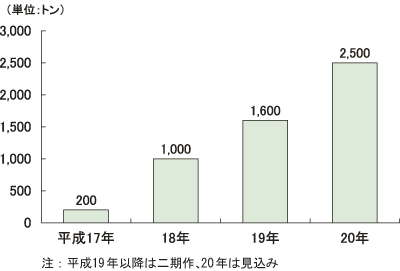
3)離島などからも引き合い
−飼料の販売農家戸数−
青刈りトウモロコシサイレージの販売先である畜産農家の経営規模は大小さまざまで、販売農家戸数は、直販および農協を経由し年々増加傾向にあるとのことである。平成19年の販売農家戸数は、継続的な取引先として、県内20戸程度(肉用牛15戸、酪農家5戸)あり、これ以外にも自給飼料が切れた畜産農家とのスポット的な取引も行われている(坂上専務)。
スポット的な取引は、青刈りトウモロコシサイレージが、バンカーサイロで製造したものをさらにラッピング(再梱包)している特性が生かされ、地域内だけでなく九州全域に及び、最近では、離島などを含め10数カ所から引き合いがきているとのことである。
平成20年の販売農家戸数は、県内の継続的な取引先として20戸(肉用牛農家5戸、酪農家15戸)増加する予定で、昨年の2倍となる40戸(肉用牛農家20戸、酪農家20戸)が見込まれている。
4)自己資金3千万を一時的に投入
−資本金、売上高、従業員数など−
坂上芝園の資本金は315万円、平成19年の従業員数は17名である。
平成19年の売上高は2億5千万円であり、このうち、青刈りトウモロコシサイレージは2,200万円を占め、経営的に全売上高に占める割合を年々高めたいとの意向があるとしている。
平成20年における青刈りトウモロコシサイレージの売上げは、販売目標数量を前年度実績に1,000トン上積みし2,000トンに拡大していることから5千万円が見込まれている(図8)。
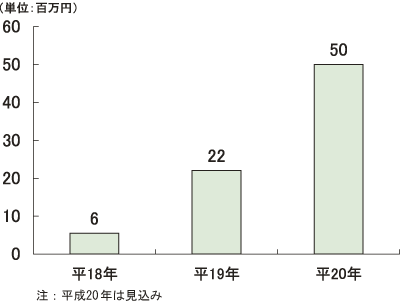
経営理念から金融機関からの借り入れを行わないこともあり(坂上専務)、平成16年には自己資金から約3千万円を負担し、は種・収穫機械などを購入している。
国からの補助事業としては、平成18年に「強い農業づくり交付金」から、ケールの苗床として硬質プラスチックハウスを建設しており、平成19年には、農業機材購入のため、「飼料生産対策事業」の交付を受け、自己負担分のうち約4千万円については、農林漁業金融公庫から初めての借り入れとなる無利子融資を受けた。また、県からの補助事業として、平成18年に「革新的農業技術実践支援事業」により、約1,800立方メートルの大容量可変型バンカーサイロを建設している。
3 データベースに基づくサイバー農業を実践
−「契約野菜」の経験が発想の原点−
これまで大手食品企業との間で積み上げられた「契約野菜」の経験を青刈りトウモロコシサイレージの生産に取り入れることで、気象変動、需給変動、価格変動など農業経営の上で避けて通れない危険を見事に分散(リスクヘッジ)し、利益を上げる仕組みを築いている。具体的には、(1)自然災害を被ったとしても、契約数量を下回ることがないよう生産量を確保しなければならないという経験から、リスクを見越した上での確実な生産体制のプランニング
(2)食品に対する安全性へのこだわり、納品基準のハードルの高さから学んだ「いかに農薬、化学肥料を減らすか」というリクエストへの対応
(3)化学肥料に代わるたい肥利用の重要性
などとされる。
当法人の事務所は、簡単な10畳ほどのプレハブ建てであるが、その内部に入ると、一同で打合せが出来るよう大画面スクリーンに何台ものパソコンが接続されていることに驚かされる。生産管理はデータベース化され、その経営が、パソコンを活用した「サイバー農業」で管理されていることを確認することができる。農業一般では馴染みが薄いが、「IT化」することにより、誰でもが「確実」に、また、「容易」に作業が実行されるようマニュアル化されている。
パソコンを活用したサイバー農業なくしては、230筆もの耕作農地を管理することに、支障をきたすことが容易に想像出来よう。
ここでは、従来の農業慣例によらない特徴的な経営手法などについて紹介する。
1.畜産飼料の生産は「契約野菜」の発想から
−販路を確定−
青刈りトウモロコシサイレージ生産の発想は、安くても売り先が決まっている「契約野菜」の経験から「儲けなくても損はしない」という考え方にある(坂上専務)。
トウモロコシの作付数量は、この経験から書面での契約を取らないものの、畜産農家からヒアリングした購入予定数量に、自然災害などによる減少量(台風に直撃された場合などでは、生産量の5割以上に被害が発生するという)を勘案した上で決められている。
過剰生産分の扱いについては、「契約野菜」の場合、農地にすき込むことになるが、青刈りトウモロコシサイレージの場合、発酵飼料のため、長期の保存が可能である。
2.生かされている畑作生産者ならではの技術、土づくりへの「こだわり」
−野菜栽培と組み合わせることでさらなる低コスト化が実現、肥料価格の急騰も追い風−
トウモロコシの栽培を輪作体系の中に取り入れたことは、さらなる低コスト化の実現に生かされている。具体的には、
(1)連作障害が回避されることや収穫後のトウモロコシの茎、根などをすき込んでいることから、農薬費、化学肥料費の軽減につながっている。また、青刈りトウモロコシサイレージを販売している畜産農家からたい肥を譲り受けており、肥料価格の急騰(図9)する中にあって、このたい肥利用の促進が、低コスト化につながっている。平成19年には、年間4千トンのたい肥が農地に還元されている(図10)。
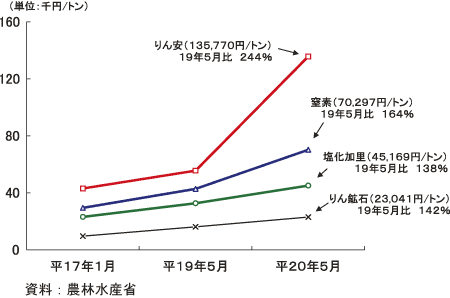
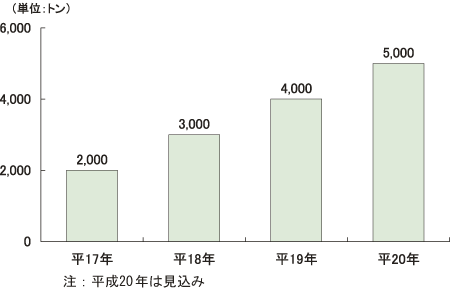
土づくりへの労力を惜しまない畑作生産者ならではの「こだわり」から、作付け前には、畜産農家では見られない土壌検査を必ず実施しており、その養分バランスを踏まえた上で、たい肥などの投入量を決定している。土壌検査には、多額の費用が発生しているが、長い目で見れば、これも低コスト化に寄与しているとしている。
低コストの実現に向けたい肥資源を有効活用することで、現在求められている資源循環型農業が自然と取り込まれている。
(2)輪作体系の中にトウモロコシの栽培を取り入れたことで、野菜栽培のない夏場の農地や農業機材を遊ばせることなく、これらを有効活用させることができ、生産効率が引き上げられコストの低下につながっている。
(3)農地が有効に活用されていることから、年間労働が均等化され、労働コストの低下につながっている。また、雇用が安定化されたことで優秀な労働力が確保されるという二次的なメリットも生み出している。
3.畜産農家のニーズをダイレクトに把握
−詳細な市場調査を広範囲にわたり実施−
販売先を拡大することについては、平成16年実施した簡易な市場調査に負っていたため、17年から青刈りトウモロコシサイレージの生産・販売事業を本格的に開始するに当たり、畜産農家のニーズをダイレクトに把握する必要から、詳細な市場調査を実施した。
この市場調査は数名で行われ、半年間にわたる大掛かりなもので、域内の畜産農家100戸(肉用牛農家、酪農家)を戸別訪問し、対面調査により行った。調査項目は、青刈りトウモロコシサイレージの希望価格、梱包形態(流通形態)、粗飼料の委託生産、耕作農地の貸し付け意向、サイロの形態、また、農機具の稼働率を上げる必要もあって、畜産経営の省力化に必要とするサービスなどにも重点を置いた内容で、この結果はその後の販促活動にフィードバックしている。
また、今年の6月〜7月にかけて、飼料高による畜産農家の対応を把握する必要から、緊急に市場調査(県内および近県の畜産農家300戸)を実施している。この結果は、さらなる販路を拡大するために生かされ、現行の青刈りトウモロコシサイレージの販売価格(税抜きキログラム当たり25円)を期間限定ながら引き下げたて販促活動(広告(500部)の配布)を実施している。
まさに、工業製品を販売するごとき手法で市場を開拓しているのである。
4.サイレージを再梱包、使い勝手を追及した梱包形態
−主力商品の開発−
1)青刈りトウモロコシサイレージ生産の流れ
青刈りトウモロコシサイレージ生産の流れは、
(1)当法人の耕作農地で作付け、収穫した青刈りトウモロコシを自身のバンカーサイロで調整し、細断型ロールベーラでラッピングによる再梱包後、販売する方法。
(2)当法人の耕作農地で作付け、収穫した青刈りトウモロコシを細断型ロールベーラでラッピング後、販売する方法。
(3)畜産農家からの依頼により、当法人の耕作農地で作付け、収穫した青刈りトウモロコシを畜産農家のサイロに詰め込むことで、販売する方法。
に大きく分けられる(図11)。
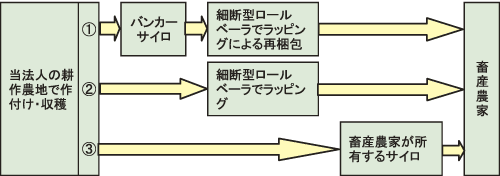
また、平成19年からは、「富山の薬売り」のように青刈りトウモロコシサイレージを作り置きすることにより販売する新たな提供方法を展開している。
これは、畜産農家の所有する耕作農地で、当法人が作付け、収穫した青刈りトウモロコシを、畜産農家が所有するバンカーサイロに詰め込むことで販売する方法である(図12)。
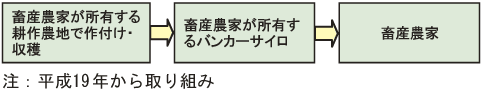
当法人のバンカーサイロを開封後、ラッピングマシーンにより再梱包したロールサイレージ(ロールベール)は、「サイロール」という商標名で登録(登録確定日:平成19年11月9日)され、その品質は、鹿児島県畜産試験場で分析したところ、日本標準飼料成分表の数値とそん色ない品質が確認されたとしている(写真2)。

写真2 登録商品「サイロール」
平成20年1月以降の配合飼料価格(農林水産省、全畜種加重平均工場渡税込価格)は、平成18年当初に比べて1トン当たり約1万5千円値上がりし、約5万8千円の水準である。4月はさらに値上がりし約6万3千円となる中にあって、「サイロール」の販売単価は、配合飼料価格とは単純に比較できないものの、1トン当たり税抜き2万5千円(1キログラム当たり25円)であり、その価格非常に安い。販売価格は、量産によるスケールメリットを価格に転換しているため、販売数量の拡大に伴い、当初に設定した価格を引き下げている(図13)。
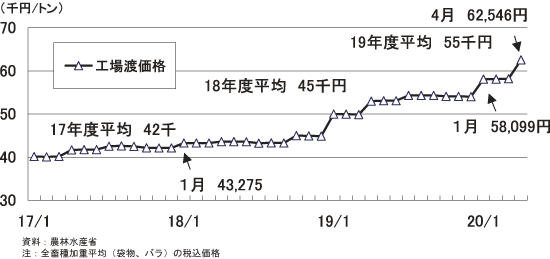
2)畜産農家による評価
畜産農家にとっての購入メリットは、価格面でサイレージ生産の初期投資に係る費用などを考えても低価格であり、輸入穀物飼料のような価格変動を受けにくいこと、また、量的な面で安定して確保することが可能であることから、価格、数量の両面で畜産経営の見通しを立てやすいという安心感が安定的な購入につながり、それまで飼料生産に振り向けていた自らの時間が家畜の世話に当てられることから好評である。
購入している肉用牛農家によると、
(1)部分的に濃厚飼料の代替品として置き
換えることにより、生産コストの低減につながること
(2)ビタミンなどが特に不足する冬場の飼料として適当であること
(3)イタリアンライグラスやストロー系の飼料はもっているが、夏に栽培するトウモロコシの飼料は持ち合わせていないこと
(4)バンカーサイロを建設することなどの新規投資が不要のため、経費の節減につながること−が挙げられている。
また、酪農家が所有する農地で、トウモロコシのは種から酪農家のバンカーサイロでの生産までを委託している酪農家によると、現在の乳量にこだわりがあるため、青刈りトウモロコシサイレージを使うことで飼料の給与割合を変更する考えはないことから、コスト低減のメリットは感じないとしつつも、
(1)人手不足であるため草づくりに時間を費やせず、委託することで乳牛の世話に専念できること
(2)委託より、農地が耕作放棄地とはならずに済んでいること
(3)事業者が導入している大型の農業機材は、サイレージ生産に特化しており、従来のコントラクターよりも利便性に勝ること
(4)完全混合飼料(TMR
)のベース飼料として供給できること−が挙げられている。
3)農家のニーズを反映した梱包形態
青刈りトウモロコシサイレージの梱包形態は、畜産農家の市場調査で得られたニーズをもとにして、大口向けの梱包形態であるラッピングしたロールサイレージ(ロールベール:1ロール当たり約400キログラム(直径90センチメートル))から、高齢あるいは小規模の畜産農家が扱い易い25〜30キログラムに小型化した容器(サンテナ)まで取り揃えられている。
5.畜産農家には「まね」できない農業機材への大型投資
−適期、迅速に収穫が可能、日本に数台の自走式大型フォーレージハーベスタを導入−
事業の拡大に伴い機械化、それも大型化することでさらなる省力化を進めている。平成17年にはキャリアーを、また、平成18年には細断型ロールベーラ、自走式大型フォーレージハーベスタ(500馬力)を導入した。高性能であるが高価なため日本に数台しかないこのフォーレージハーベスタは、一日当たり6ヘクタールの集中収穫が可能(一度に6列のトウモロコシを収穫)であることから、「適期に」収穫できるばかりでなく、この地域に頻発する台風襲来前に「迅速に」威力が発揮でき、台風などでトウモロコシが倒れた場合でも収穫することが可能である(写真3)。

写真3 適期に迅速に収穫可能な大型農業機材
大型農業機材は大変高価と考えがちであるが、輪作体系を農業機材の稼働率を向上させるように組み立てたり、飼料生産を畜産農家から受託することなどにより有効活用が図られ、十分に購入コストの負担はまかなえるとしている。また、個々の畜産農家がこれらの高価な農業機材へ投資したとしても引き合わないことから、「適期に」、「迅速に」威力を発揮する農業機材を所有していることは十分な売り要因になっているとしている。
バンカーサイロについては、17年に港湾用ブロックを利用した簡易な200立方メートル規模の建設に始まり、18年には1,600立方メートル規模を建設した。19年には、トウモロコシの作付面積を前年の25ヘクタールから80ヘクタールに増加させる計画であったことから、平成18年に国の補助事業である「革新的農業技術実践支援事業」を利用することで、約1,800立方メートルの大容量可変型バンカーサイロを建設している(図14)。
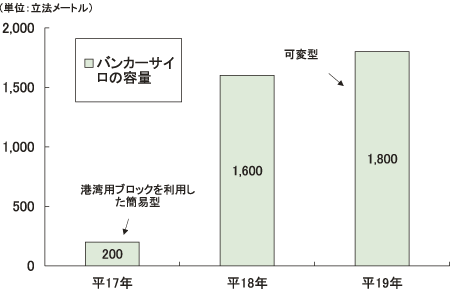
6.雇用を保証し、人づくりを重視
−経営哲学、人は財産−
坂上専務自身、大学卒業後にフリーターを経験したことから、雇用の保証や人づくりの大切さを重視している。従業員は技術系の熟練者を雇用する一方、新たに採用したスタッフについては、その都度、能力向上のため目的に応じて中小企業大学校などでの研修を実施、正社員として通年雇用することにより地域の活性化にも貢献している。また、飼料供給事業を開始するに当たっては、畜産先進地域である北海道などで飼料生産技術やコントラクター経営管理を学ぶための調査や視察に力を入れて取り組んでおり、プロの生産者集団を目指しているとしている。
従業員数は、飼料販売事業を本格的に開始した平成17年は10名であったが、事業の拡大とともに平成19年は17名となる(図15)。
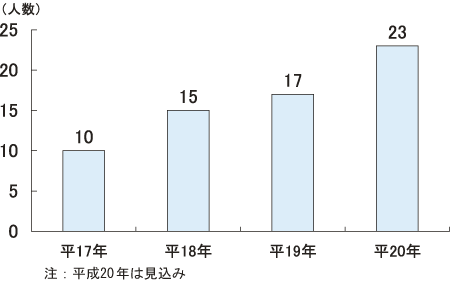
国際食品・飲料展(フーデック ス)などの展示会にも率先して参加しており、世の中の動きについて販売ブースを通して感じ取るとともに、情報の発信も怠らない(坂上専務)。
4 さらなる耕作農地の拡大を優先
−今後の事業展開−
今後の経営は、さらなる耕作農地の拡大、集積化を第一に考えているとしている。また、事業の拡大に伴い経営をリスクヘッジする必要から、従来の4品目(ケール、加工用バレイショ、焼酎用甘藷(かんしょ)、飼料用トウモロコシ)に加え、平成20年は、ニンジン、タマネギなどの新規野菜の栽培に取り組むことを検討している。さらに、青刈りトウモロコシサイレージをTMR原料として供給することや焼酎かす、でん粉かすなど地元の農産副産物や飼料イネWCS(ホール・クロップ・サイレージ)などを活用してTMR調整を行うことにより、現在、取引している畜産農家への提供も視野に入れているとしている。
5 おわりに
−人、知恵を借りる−
穀物価格の高騰は、畜産経営を直撃し食品価格を押し上げている。これまで海外の安価な穀物飼料に依存してきたわが国畜産業は、海外のトウモロコシ価格などの著しい値上がりにより大きな曲がり角を迎えている。国内の飼料生産については、平成27年度までに達成すべき飼料自給率について、粗飼料自給の完全達成および飼料用米の利用などにより、同15年度の24%から35%までに引き上げるという目標(食料・農業・農村基本計画(平成17年3月25日))が示されている(図16)。
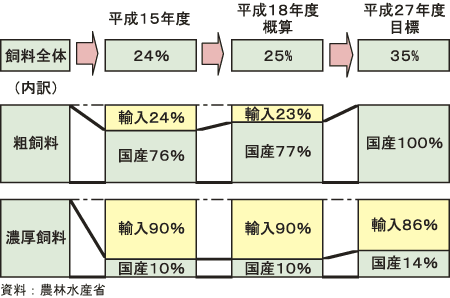
その一方で、耕作放棄地は全国的に年々拡大し、わが国の耕作面積の2.5倍に匹敵する農畜産物が輸入されていることを考え合わせると、耕作する農地が限られているがゆえに、その無駄のない取り組みが急がれる(図17)。
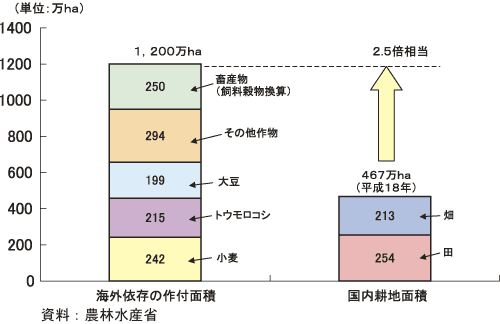
高齢化や担い手不足などから、飼料づくりにまで手が回らない畜産の生産現場では、新たな担い手と多様な形で深く結び付かざるを得ない流れの中にあり、この流れは、これからも勢いを増すことはあっても、後戻りすることはないようである。
このような流れの中で、「利益が上がる」経営力を推進力とし、所有農地の36倍に当たる農地を借り受け、耕作放棄地などを農地として有効に活用する「新しい風」が吹き始めている。
この風は、一時的な「そよ風」ではなく、従来の農業慣例にとらわれない柔軟な発想を持ち合わせることで、「垣根」を越えたコラボレーション(連携)を巧みに活用し、それが生み出すシナジー(相乗効果)により、畜産の生産現場を単に活性化することにとどまらず、農業全体を魅力あるこれからの成長産業へと導いている。
自給飼料の生産は、地域ごとの「土地」に根差していることから、生産現場ごとの「知恵」が「カギ」となるようである。本稿が、ほかでは見ることのできないこの創意工夫に満ちた新たな試みを紹介することで、飼料の増産に結び付くヒントを提供できれば幸いである。
以上