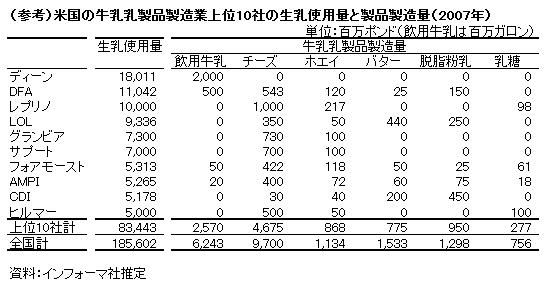1 はじめに
米国で生産される乳製品はその大半が国内で消費されている。また、米国政府は主要乳製品の輸入に対して高い国境措置を維持しており、主要な乳製品に対する価格支持措置も制度化されている。このように、米国の乳業は基本的には国内向けの供給を主体とすることを前提とした産業・政策構造になっており、長く、国際市場への供給は政府による海外食料支援や補助金付き輸出に限定されていた。しかし、近年、国内需要が伸び悩む中で、国際的な需要の拡大と主要輸出国の生産の不安定さを背景に、米国から海外への乳製品輸出は急速に増加する傾向にある。一方、これらの乳製品を製造する乳業各社は、技術の進展を背景に工場の大規模化を進めており、主要な生産地域や生産主体の構造もこれまでとは大きく変化してきている。今回は、米国における乳製品の消費と乳業の構造変化の長期的動向について報告する。
2 米国の酪農・乳業の全体構造
(1)生乳生産と牛乳乳製品消費の概要
米国における2007年の生乳生産量は8,421万トンで、日本の生乳生産量(802万トン:平成19年度)の10倍強に当たる。米国では、この10年間で生乳生産量が18.9%増加しており、この間の年平均増加率は約1.6%に上るが、特に2005年以降は前年比2%を超える高い伸びが続いている。日本の生産量がこの10年間で7.0%減少しているのとは対照的である。
一方、同年における米国の牛乳乳製品の消費量は生乳換算で8,534万トンと推定されており、日本の年間消費量(1,224万トン)の約7倍に相当する。生乳生産と同様に消費も拡大傾向が続いており、10年前に比べて21.4%増加(年平均増加率1.8%)している。図1は米国における牛乳乳製品の消費量を生乳相当量に換算し、主要品目別に区分して表したものである。1970年以降、飲用牛乳の消費はほぼ横ばいで推移しており、牛乳乳製品の消費量全体に占める割合は1970年の44.6%から2007年には全体の23.3%にまで低下している。一方、チーズの消費量は1970年から2007年までの間に4倍近くに増加しており、この間、全体に占める割合も1970年の19.1%から2007年には42.8%に拡大している。このほかの乳製品について見ると、2007年にはバターの割合が全体の7.1%、脱脂粉乳の割合が同4.4%、アイスクリームの割合が同5.1%を占めている(表1)。
図1 牛乳乳製品の消費量の推移(生乳換算)
|
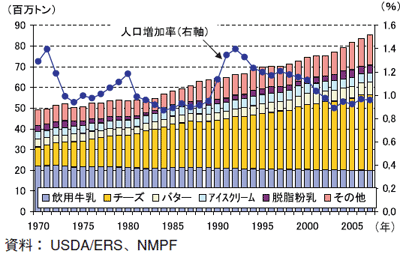 |
表1 牛乳乳製品の品目別消費量の割合(生乳換算)
|
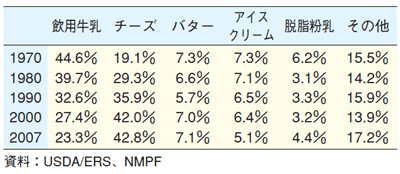 |
牛乳乳製品の消費が拡大しているのは、米国の人口が増加を続けていることによるところが大きい。2007年7月における米国内の居住人口は3億162万人で日本の2倍強であり、10年前に比べて10.6%増加している。米国の年間人口増加率は、直近でこそ1.0%をわずかに下回っているが、この10年間の平均は1.0%、1970年にさかのぼっても平均1.1%と長期的には安定している。米国は先進国の中では比較的出生率が高く、かつ、世界各国から移民を受け入れていることから、今後も人口増加により国内の需要拡大が下支えされる構造は続く可能性が高い。
(2)乳脂肪分と無脂固形分の需給バランス
図2は2007年に米国で生産された生乳の最終製品別仕向割合を、乳脂肪分と無脂固形分に分けて比較したものである。乳脂肪分の仕向先として最も大きいのはチーズ向けで全体の40.2%を占めており、次いでバター向けが18.2%、飲用牛乳向けが15.3%、クリーム(サワークリームを含む)向けが10.6%、アイスクリーム類向けが8.1%の順となっている。国内で生産される乳脂肪のうち、飲用に仕向けられる割合が15%余りしかない一方で、クリーム製品向けの割合が10%を超えている点が特徴的である。これに対し、無脂固形分の仕向先として最も大きいのは飲用牛乳向けで30.1%を占め、ホエイ向けの14.4%、チーズ向けの13.7%、脱脂粉乳等向けの8.2%がこれに続いている。また、乳糖や乳タンパクなど、その他の乳製品や非乳製品の加工に仕向けられる割合が全体の22.8%と非常に高いのも特徴である。
図2 生乳の最終製品別仕向割合(2007年)
|
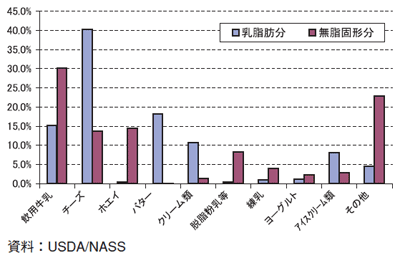 |
このように、乳脂肪分と無脂固形分の仕向先に大きな乖離がある中で、それぞれの乳成分の需要量は季節によってどのように変動するのであろうか。図3は無脂固形分と乳脂肪分の1日当たり消費量について、1998年から2007年の10年間における各月の平均値を年間平均値と比較して指数化したものである。乳脂肪分の月別消費量は年の前半が比較的低水準で推移した後、サンクスギビングやクリスマスなど年末の需要期に向けて大きく増加する傾向があり、需要期の11月と不需要期の1月とでは、平均消費量に約14%の格差がある。一方、無脂固形分の需要は学校が期末休みに入る7月と年末年始の12月から1月にかけて低下する傾向こそあるものの、乳脂肪分に比べると年間を通じて比較的安定しており、需要期と不需要期の平均消費量の差も約6%にとどまっている。
図3 牛乳乳製品の月別消費指数(98〜07平均)
|
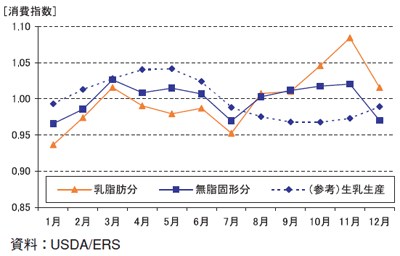 |
一方、米国の生乳生産量が最も増加するのは4月から5月にかけてであり、生乳の需要が増大に向かう9月から10月にかけては生産が落ち込む。生乳の生産と牛乳乳製品の需要との間に季節的なズレが生じる点は、日本と同様である。
(3)生乳と乳製品の生産地域
米国の生乳生産地域は、伝統的に飲用牛乳向けの出荷割合が高く小規模経営が多い東海岸北部(ニューヨーク州、ペンシルベニア州など)、自給飼料基盤に恵まれチーズ向けの出荷割合が高い五大湖沿岸地域(ウィスコンシン州、ミネソタ州など)、大規模経営が大半で脱脂粉乳やバター向けの生乳出荷割合が比較的高い西部地域(カリフォルニア州など)に大別される。それぞれの地域により、酪農家の経営形態は大きく異なり、生乳の生産コスト構造も全く異なっているが、概して、東海岸北部地域の酪農経営は飼料費も施設費も高く、高乳価を前提とした生産が行われている。これに対し、五大湖沿岸地域は購入飼料費が安い反面、施設・機械などの減価償却費が高くなる傾向にある。西部地域は大規模経営が多く、乳量当たりの固定経費が小さいことから生産費は最も低いが、購入飼料と借入資本に依存していることから、乳価の下落や飼料価格の高騰時の経営リスクは最も大きい。
表2はこれらの主要生乳生産地域における2007年の生乳の用途別出荷割合を示したものである。飲用向けの割合が最も高いのは東海岸北部地域で、同地域の出荷乳量の46%が飲用向けに仕向けられる。また、同地域ではクリームやヨーグルトなどの液状乳製品に仕向けられる割合も21%と他地域に比べて高い。これに対して、五大湖周辺地域ではチーズ・ホエイの製造に向けられる生乳の割合が圧倒的に高く、出荷乳量の76%を占めている。一方、同じく乳製品向けが主体となっている西海岸のカリフォルニアでは、チーズ・ホエイ向けの乳量は47%と五大湖周辺ほど高くなく、脱脂粉乳・バター向けの割合が30%と他地域に比べて高いのが特徴である。
表2 地域別の用途別生乳仕向け割合の比較
|
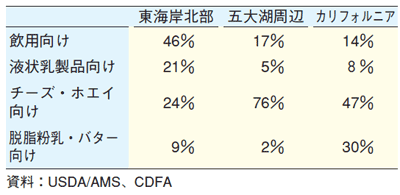 |
この結果、主要な乳製品の生産地域は、米国内で大きく異なっている。近年、乳業工場の統廃合が進んでいるため、USDAは乳製品の生産数量について、東海岸、中央部、西部の地域に分けた数字しか公表していないが、これにより大まかな産地ごとの傾向がわかる(表3)。これによると、チーズの生産は中央部と西部がともに4割強を占めており、中央部のウィスコンシン州や西部のカリフォルニア州では近年消費が増加傾向にあるイタリアンチーズの生産割合が高いことがわかる。また、バターの生産については西部が約5割、中央部が約4割となっているのに対し、輸出向けの生産の割合が高い脱脂粉乳については生産の7割が西部に集中している。なお、中央部では、脱脂粉乳の生産がほとんどないにもかかわらずバターの生産量は多くなっているが、これは、低脂肪牛乳やイタリアンチーズの製造の際に生じたクリームを他の地域から移入してバターの原料に使用しているためであり、地場産の生乳を使用したバターの生産割合は低いことに注意が必要である。
表3 主要乳製品の地域別生産割合(2007年)
|
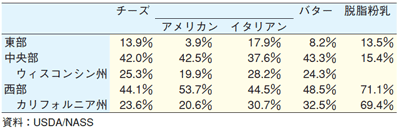 |
3 主要な牛乳乳製品の需給の特徴
(1)飲用牛乳
(ア) 消費の動向
前述のとおり、米国の飲用牛乳の消費は近年ほぼ横ばいで推移しているが、これは、一人当たり消費量が長期にわたって低落を続けていることを意味している(図4)。1960年代に年間115キログラム前後だった飲用牛乳の一人当たり消費量は、2006年にはその約2/3に当たる74.6キログラムにまで減少している。このうち、特に減少が著しいのは普通牛乳(注1)の消費量であり、2006年にはピーク時の1/4以下の24.9キログラムにまで落ち込んでいる。これは、日本の一人当たり消費量28.0キログラム(平成19年度)を下回っており、消費の長期低落傾向に歯止めがかかっていない。一方、米国の飲用牛乳消費の主体となっている2%低脂肪牛乳の消費量は、1960年代から増加を始めて1990年前後に年間35キログラムを超えた後、減少傾向に転じて2006年には27.0キログラムまで減少している。また、1%低脂肪牛乳および無脂肪牛乳の消費は、近年比較的安定しており、2006年にはそれぞれ10.0キログラム、12.6キログラムとなっている。これらの低脂肪牛乳は普通牛乳に比べて消費の減少が比較的小さく、飲用牛乳の消費全体に占める割合は年々上昇している。なお、量的には少ないがフレーバー牛乳(ストロベリー牛乳やチョコレート牛乳など)の消費は着実に増加しており、2006年には6.8キログラムが消費されている。また、有機牛乳や有機低脂肪牛乳の消費も、近年大きく増加している。
図4 一人当たり飲用乳量の推移
|
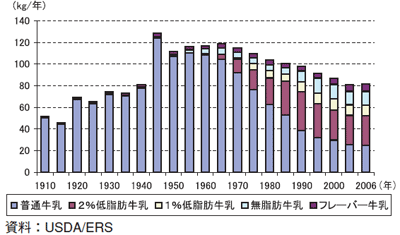 |
(注1)米国には日本で主体となっている「成分無調整」牛乳はほとんど存在しない。普通牛乳は、脂肪分が年間を通して3.25%に調整され、ビタミンAやDが添加されているものが中心である。
(イ) 消費の季節性
日本の飲用牛乳生産は、学校が夏休みに入る7月から8月にかけて大きく落ち込むことが知られているが、米国ではどのような特徴が見られるだろうか。図5は米国における飲用牛乳の1日当たり平均販売量を指数化し、日本の消費動向と比較したものである。米国では、米国の学校が期末休みに入る6月から7月にかけて飲用牛乳の消費が最も低下し、秋から冬にかけて上昇する傾向が見られるが、その月格差は10%前後でさほど大きくない。これに対し、日本の飲用牛乳類(加工乳、乳飲料などを含む)の生産は夏休み明けの9月に最大となり、秋から冬にかけて低水準となる傾向が見られる。学校給食における消費の動向が全体に影響を与える点では両国は共通しているが、日本の飲用牛乳の消費が基本的に夏場に増加するのに対し、米国の消費はむしろ秋から冬にかけて増加する傾向にある点が特徴である。また、日本における消費の月格差が米国の2倍近いことも注目される。日本の牛乳消費の傾向を品目別に見ると、業務用牛乳の消費の季節動向がむしろ米国の消費動向に近いことは興味深い。
米国の飲用牛乳の消費動向をさらに細かく分析すると、普通牛乳や2%低脂肪牛乳の消費は年間を通じて比較的安定しているのに対し、1%低脂肪牛乳とフレーバー牛乳の消費は6月から7月にかけて大きく落ち込んでいることがわかる(図6)。これは、米国の学校給食(スクールランチ)で販売されている商品の大半が1%低脂肪牛乳やフレーバー牛乳であり、普通牛乳はほとんど扱われていないことが原因である(注2)。日本では、学校給食の影響により消費動向が大きく変動するのは普通牛乳であり、加工乳・成分調整牛乳や乳飲料の消費に学校給食の影響がほとんど見られないこととは対照的である。
図5 飲用乳の月別生産・消費指数の日米比較
|
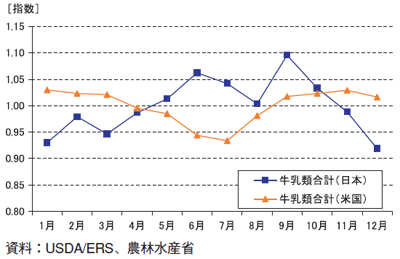 |
図6 飲用乳の種類別月別販売指数(2000〜08年平均) |
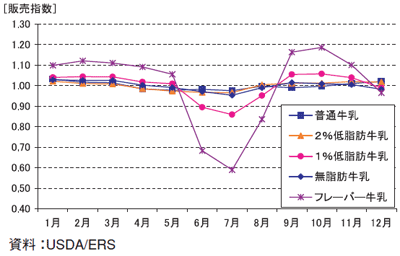 |
(注2)筆者の住む地域の公立小学校でスクールランチの際に生徒が購入できる飲料は、1%低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、ストロベリー牛乳(脂肪分1%)、チョコレート牛乳(脂肪分1%)、豆乳、水の6種類である。公立中学校では、豆乳の代わりにアップルジュースが購入できるが、飲用牛乳の商品構成は小学校と同様である。
(ウ) 飲用牛乳の価格変動と消費への影響
図7は米国の普通牛乳の小売価格と飲用向け乳価(クラスⅠ乳価)の動向を示したグラフである。米国の飲用向け乳価は政府が毎月公表する最低乳価をベースに酪農協と乳業が交渉して決定するが、この最低乳価が前月前半の基幹乳製品(チーズ、ホエイ、脱脂粉乳、バター)の価格を基に算定される仕組みになっているため、飲用向け乳価は乳製品の価格に連動して1カ月単位で大きく変動する。乳製品価格の高騰を受けて昨年7月に100ポンド当たり23.67ドル(キログラム当たり51.7円:1ドル=99円)まで上昇していたクラスⅠ乳価は、その後の国際的な乳製品価格下落の影響を受けて、本年3月には同12.32ドル(同26.9円)まで急落している。
米国の飲用牛乳の小売価格は、この飲用向け乳価の変動に並行して変動している。筆者の印象では、スーパーの「希望小売価格」の変更はあまり頻繁には行われていないが、飲用向け乳価の高騰時には牛乳の「割引販売価格」が上昇し、割引販売の頻度も減っていたように思われる。
小売価格の変動が大きい一方で、乳業と小売によるマージン(小売価格とクラスⅠ乳価の差額)は非常に安定しており、かつ、長期的にはわずかに右肩上がりで推移していることも注目される。原料乳の価格変動が直ちに小売価格に反映される要因としては、飲用牛乳最大手のディーンフーズの市場シェアが全体の4割以上を占めること、全体の2割前後が大手スーパーの直営工場で生産されていること、取引乳価の報告が義務化されているため価格の透明性が極めて高いことなどが考えられる。
図7 飲用乳の小売価格とその構成の推移
|
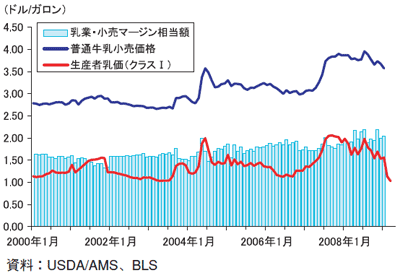 |
このように小売価格が大きく変動する中で、米国では飲用牛乳の消費に価格変動の影響が出ていないのだろうか。図8は普通牛乳と2%低脂肪牛乳の1日当たり平均販売量を左軸に、普通牛乳の小売価格を右軸に示したグラフである。前述のとおり、米国の普通牛乳の消費量は長期低落傾向を続けており、現在では2%低脂肪牛乳が牛乳消費の主流にとって換わっている。2000年以降、普通牛乳の小売価格は、2004年春と2007年夏を境に二度の大きな値上げを経験しているが、図で見る限り、価格上昇が消費に与えた影響はほとんど見られない。これは、酪農家や乳業メーカーが拠出した自主基金により、業界がファストフードにおけるプラスチック容器充填牛乳の提供を支援するなどの努力が功を奏したこともあるが、「牛乳は価格硬直性が高く、販売価格の変動は消費にあまり影響を与えない」という定説が間違いでなかったということでもあるのだろう。米国では、経済環境の悪化を受けて、高価な外食の回数を減らして割安なファストフードや家庭内での食事を増やす動きが見られ始めているが、飲用牛乳に限って言えば、このような状況は消費の維持・拡大にとって追い風になる可能性もある。
図8 牛乳の1日当たり消費量と小売価格 |
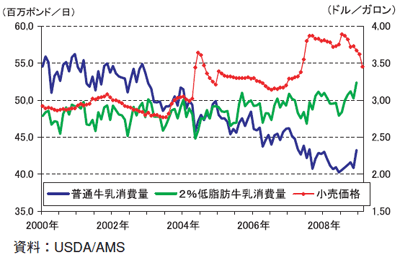 |
(2)チーズ
(ア) 消費の動向
米国の年間一人当たりチーズ消費量は日本の約7倍の14.7キログラム(2006年。以下同じ)に上る。このうち、チェダーチーズなどのアメリカンチーズの消費が5.9キログラム、モッツァレラチーズなどのイタリアンチーズの消費が6.2キログラム、クリームチーズなどその他のチーズが2.6キログラムを占める。また、全体の8割以上の12.1キログラムがナチュラルチーズとして直接消費されるが、プロセスチーズや一部植物性脂肪を加えたチーズ加工品として消費されるものも3.5キログラムある。この他、カッテージチーズが年間1.2キログラム消費されている。
図9は米国における一人当たりチーズ消費量の推移である。1980年代半ば以降、アメリカンチーズの消費が伸び悩んでいるのに対し、イタリアンチーズを含むその他のチーズの消費は増加を続け、1988年にその消費量が逆転している。特に、イタリアンチーズのうち、ピザなどに使用されるモッツァレラチーズの消費は、外食産業向けの需要拡大に牽引されて増加を続けており、2006年には10年前に比べて1.0キログラム増の4.8キログラムに達している。
図9 一人当たりチーズ消費量の推移
|
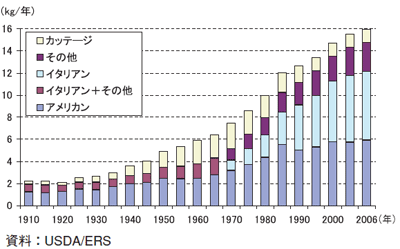 |
(イ) 消費と生産の季節性
米国では、飲用牛乳と同様にチーズでも消費の季節性が見られる。図10はアメリカンチーズとそれ以外のチーズについて、1日当たり平均消費量を指数化して月別の動きを比較したものである。アメリカンチーズの消費が1年を通じて比較的安定しているのに対し、それ以外のチーズは消費の月別変動が比較的大きく、年末にかけて増大する傾向が見られる。また、学校が長期休みに入る7月にはアメリカンチーズもそれ以外のチーズも消費が落ち込む。これらの傾向は、アメリカンチーズに比べてモッツァレラチーズなどのその他のチーズは外食や加工向けに使用される割合が高いこと、また、学校給食で供給されるハンバーガーやピザに使用されるチーズの量が全体の消費量の中で無視できない水準にあることを反映している。
図10 チーズの月別消費指数(98〜07平均)
|
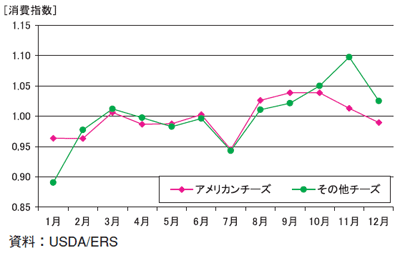 |
一方、チーズの生産の季節的な変動は、生乳の生産の動きにほぼ並行しており、消費の季節変動との連動はあまり見られない。これは、チーズは飲用牛乳に比べると、生乳の季節的な需給変動に与える影響が小さいことを示している(図11)。
図11 チーズの月別生産指数(98〜07平均)
|
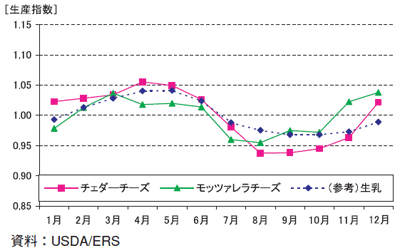 |
(ウ) チーズ向け原料乳価と製品価格の変動
図12は米国のチェダーチーズの小売価格と卸売価格を左軸に、チーズ向け乳価(クラスⅢ乳価)を右軸に示したグラフである。チーズ向け最低乳価は、当該月のチェダーチーズ、ホエイおよびバターの卸売価格を基に政府が算定して事後的に公表される(注3)が、ホエイとバターの価格が最低乳価の算定に与える影響は極めて小さい。このため、チーズ向け乳価はチェダーチーズの卸売価格とほぼ並行して変動する。2000年以降、一時的な高騰時を除いてポンド当たり1.1〜1.6ドル(キログラム当たり2.4〜3.5ドル)の範囲で推移してきたチェダーチーズの卸売価格は、国際的な乳製品需給のひっ迫により2007年の春からほぼ1年半にわたって2ドルに迫る高水準を維持してきた。しかし、オセアニアの供給増と世界的な不況による需要の減退により、2008年後半には急速に価格を下げている。ちなみに、米国政府(商品金融公社:CCC)によるチェダーチーズの価格支持買上げ価格は、2001年1月以降ポンド当たり1.13ドルに設定されているが、2003年7月以降は買上げの実績はない(2009年3月5日現在)。
図12 チェダーチーズの小売価格とその構成の推移
|
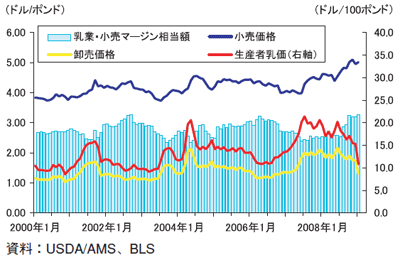 |
一方、チェダーチーズの小売価格は、原料乳価や卸売価格の変動とは必ずしもリンクしておらず、特に直近では卸売価格の下落にも関わらず上昇傾向が続いている。これは、小売向けの出荷割合が高い飲用牛乳とは異なり、チーズの半分以上が外食産業や二次加工向けに使用されていることが影響しているものと考えられる。チーズ向け乳価が高騰する中で、2008年に入ってこれまでチーズ消費の増大を牽引してきたモッツァレラチーズの生産量は減少に転じている。これは、価格の上昇を嫌った外食産業が一部の原料を比較的安価な代替品に変更したためとされており、チーズの消費は全体的には増加傾向にあるものの、飲用牛乳に比べて価格変動の影響を受けやすいことを示している。
なお、チーズ向け乳価の算定に当たって使用されるチェダーチーズの製造コストは、燃料価格の高騰などを受けて昨年10月に2割ほど引き上げられており、現在はポンド当たり0.2003ドル(キログラム当たり0.4416ドル)に設定されている。
(注3)米国の連邦生乳マーケティングオーダー(FMMO)制度では、飲用牛乳向けやヨーグルト向けの最低乳価が取引月の前月末に公表されるのに対し、チーズや脱脂粉乳・バター向けの最低乳価は取引月の翌月初めに公表される。
(3)バター・クリーム
(ア) 消費の動向
米国のバターの消費量は年間一人当たり2.1キログラムで、日本の約3倍である。一方、クリーム類の消費量は5.8キログラムであり、こちらは日本の約7倍前後と推定される。クリーム類のうち、約6割(3.7キログラム)は通常のクリームだが、約4割(2.1キログラム)はサワークリーム類が占めている。また、通常のクリームのうち、日本の生クリームに相当するヘビークリームは全体の3割程度でしかなく、残りの約7割が料理用やコーヒー用に使用されるライトクリームやハーフアンドハーフ(脂肪分12.5%前後の超低脂肪タイプクリーム)である。
図13は米国における一人当たりのバターとクリーム類の消費量の推移である。バターの消費量が近年ほぼ横ばいで推移しているのに対し、クリームの消費量は1980年代以降急速に拡大を続けており、乳脂肪を主体とする製品全体の消費の伸びを牽引している。クリームの消費量が増加し始めた1980年代後半は、普通牛乳やアメリカンチーズなどの全乳を原料とする商品の消費が伸び悩む一方で、低脂肪牛乳やモッツァレラチーズなどの脱脂乳を原料とする製品の消費が増加し始めた時期と一致している。このことは、米国の生乳の処理・加工の形態が、この時期を境に、全乳を主体とする構造から、脱脂乳とクリームを別の原料として取り扱う構造に変化してきたことを示唆している。
図13 一人当たりバター・クリーム消費量の推移
|
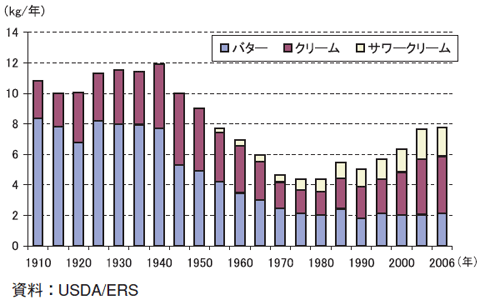 |
(イ) 消費と生産の季節性
米国におけるバターの消費量は、他の乳製品に比べて特に季節による変動が大きい。サンクスギビングを抱える11月には、1日当たり消費量が年平均を3割以上上回るなど年末に需要が増加し、1月から7月までは消費が低迷する。これに対し、バターの生産量は12月から5月までが平均を上回り、需要期を前にした夏場から秋にかけては生産が減少する。このように、米国においても日本と同様に、バターの生産と消費との間に時期的なズレが生じている(図14)。
図14 バターの生産と消費の季節性(98〜07平均)
|
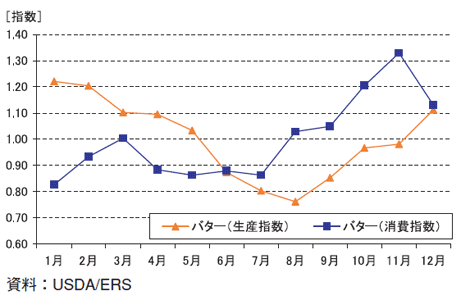 |
バターと普通牛乳が乳脂肪の消費の中心となっている日本とは異なり、前述のとおり、米国ではチーズが乳脂肪消費の約4割を占めており、また、飲用牛乳の消費は低脂肪牛乳が主体となっているため、乳脂肪需要の季節変動はあまり大きくない。にもかかわらず、バターの需給に季節的なズレが生じているのは、バターの生産がアイスクリーム消費の季節変動の影響を受けるためである。図15はバターとアイスクリームとの月別生産量を指数化してグラフに示したものである。バターの生産が夏場に大きく減少するのに対し、アイスクリームの生産量は春から夏にかけて大きく増加していることがわかる。米国においては、アイスクリームやクリームなどの液状乳製品向けの最低乳価が脱脂粉乳・バター向けよりも100ポンド当たり70セント高く設定される。このため、日本と同様に乳脂肪分の供給先としてのバターの優先度は最も低く、他の製品の需要の季節変動の「しわ寄せ」を受けやすい構造にある。これが、バターの生産が季節により大きく増減する最大の要因である。
図15 バターとアイスクリームの月別生産動向
|
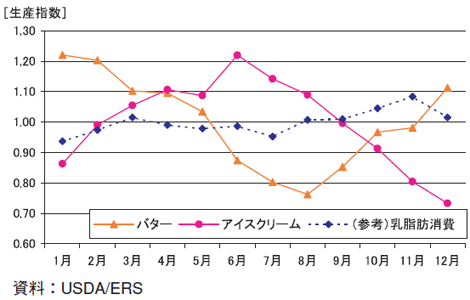 |
(ウ) バター向け原料乳価と製品価格の変動
米国のバター・脱脂粉乳向け乳価(クラスⅣ乳価)は、当該月のバターと脱脂粉乳の卸売価格を基に算定されるが、おおむね、バターの価格が4割強、脱脂粉乳の価格が6割弱反映される仕組みになっている。図16は米国のバターの小売価格と卸売価格を左軸に、クラスⅣ乳価を右軸に示したものだが、原料乳価とバターの卸売価格とのリンクは、チェダーチーズの場合ほど明確ではない。これは、前述のとおり、原料乳価に反映される脱脂粉乳価格の比率が6割を占めるためである。
図16 バターの小売価格とその構成の推移
|
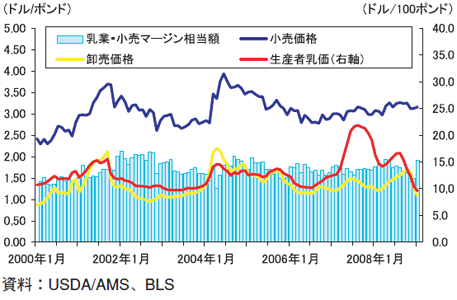 |
バターの卸売価格は、政府支持価格が2002年11月にポンド当たり1.05ドルに引き上げられて以降、長くこれを上回る水準を維持してきた。このため、政府によるバターの価格支持買上げは2003年6月を最後に行われなかった。しかし、バターの卸売価格は他の乳製品と同様、国際価格の下落に伴って2008年後半から急速に下落を始めており、2009年1月7日から脱脂粉乳に続いてCCCによる価格支持買上げが行われている。ちなみに、クラスⅣ乳価の算定に当たって政府がバターの加工経費として使用している算定額はポンド当たり0.1715ドルである。
バターについて卸売価格と小売価格の関係を見ると、飲用牛乳ほどではないものの、チーズよりは卸売価格の変動が小売価格に反映される傾向が強い。これは、バターを生産・販売する乳業者の数がチーズに比べると圧倒的に少なく、小売店における特定ブランドの価格支配力が強いことが影響しているものと考えられる。
(4)脱脂粉乳・ホエイ類
(ア) 消費の動向
米国における脱脂粉乳の年間一人当たり消費量は、2006年には1.0キログラムと日本の1.5キログラムを下回っている。一方、栄養補助食品やサプリメントなど、多くの加工食品の原料として使用されているホエイ類の消費量が一人当たり1.2キログラムあり、乳原料の需要の多様化が進んでいるとも言える。しかし、他の乳製品に比べると、粉乳類の消費量は多いとは言えない。図17は米国における粉乳類の長期的な消費動向を、また、図18は1980年以降の消費動向を表したものである。粉乳類の消費は1960年代までに急速に増加した後、脱脂粉乳とホエイの置換が進む中でほぼ横ばいで推移している。また、1990年以降について見れば、脱脂粉乳とホエイの構成比についても安定している。一般的に、粉乳類の消費は先進国よりも途上国で高く、経済の成長に伴って消費が伸び悩む傾向があるが、米国もその例外ではないということだろう。なお、粉乳類は、他の乳製品に比べると年による消費量の変動が大きくなっているが、これは、他の乳製品よりも生産量に占める輸出量の割合が高いことが影響しているものと考えられる。
図17 一人当たり粉乳類消費量の推移
|
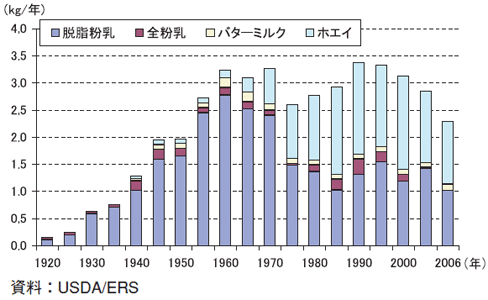 |
図18 一人当たり粉乳類消費量の推移(1980〜)
|
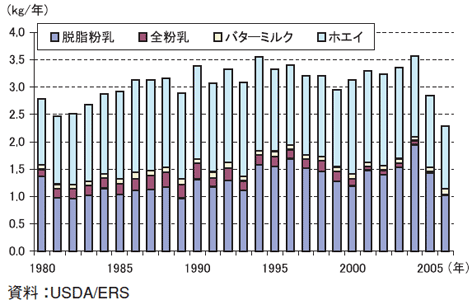 |
(イ) 消費と生産の季節性
米国における脱脂粉乳の消費量は、夏場に比較的高くなり、秋から冬にかけて低迷する傾向があるが、バターに比べるとその季節変動はあまり大きくない。これに対し、脱脂粉乳の生産量は生乳の生産が増加する4月から5月にピークとなり、生乳生産が減少する9月から10月に底となる。生産の季節変動傾向こそ生乳と同様だが、脱脂粉乳の生産の季節変動幅は生乳に比べて非常に大きく、年間平均値から上下に20%以上の変動幅がある(図19)。これは、多くの場合、生乳の供給に際しては飲用向けやチーズ向けが優先されるため、脱脂粉乳・バター向けの原料乳供給量の季節変動が大きくなることによる。
図19 脱脂粉乳の生産と消費の季節性
|
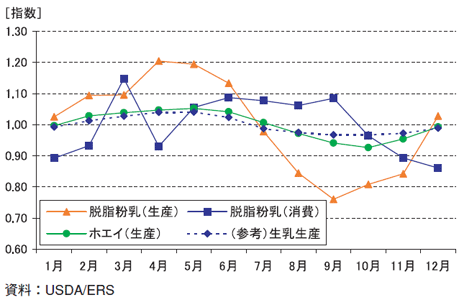 |
一方、ホエイの生産量はチーズの生産量とほぼ並行した季節変動のパターンを取り、春先の5月に最大となって秋の10月に最小となる。また、年間を通じた生産量の変動幅は、チーズと同様に平均値を挟んで上下に5〜6%前後の範囲に収まっており、脱脂粉乳に比べると季節変動は非常に小さい。このため、単純に工場の稼働率だけを考えるならば、脱脂粉乳よりはホエイを製造するほうが有利と言える。
なお、ホエイの製品性状はその製造過程により大きく異なるが、一般的には、全乳を原料とするチーズ(アメリカンチーズやスイスチーズ)の製造時に生産されるもののほうが、低脂肪牛乳を原料とするイタリアンチーズの生産時に製造されるものよりもユーザーの評価が高い。
(ウ) 脱脂粉乳・ホエイの製品価格の動向
図20は米国における粉乳類の価格動向を比較したものである。脱脂粉乳の政府支持価格は、2000年初めにはポンド当たり1.10ドルだったが、その後数度にわたって引き下げられ、2002年11月以降は同0.80ドルに設定されている。一方、CCCによる脱脂粉乳の価格支持買上げは、1999年の初めから2004年11月まで続いた後、2006年3月から7月まで再び実施されており、この間の卸売価格は、支持価格をわずかに上回る水準で硬直的に推移してきた。その後、2006年後半から2008年の前半にかけては、国際価格の急騰を受けて米国内の脱脂粉乳価格も高騰したが、2008年後半に入ると、主要輸出国の生産増加と国際不況による消費の伸び悩みにより脱脂粉乳の価格は急落し、2008年10月7日から再び同0.80ドルでの価格支持買上げが行われている。
図20 脱脂粉乳およびホエイ類の卸売価格の推移
|
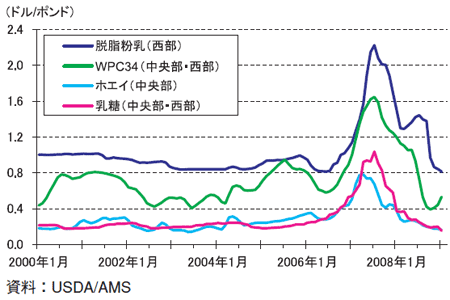 |
一方、ホエイ製品のうち、タンパク質(主にアルブミン・グロブリン)の割合が通常のホエイの約3倍に高められた34%タンパク濃縮ホエイ(WPC34)の価格は、2000年以降ポンド当たり0.5ドル〜1.0ドルの範囲内で変動してきたが、2007年初めから2008年前半にかけて脱脂粉乳の価格上昇に並行して同1.0ドルを超える高値で推移し、その後急速に下落している。また、通常のホエイからタンパク質や灰分などを除去して製造される乳糖についても、同0.18〜0.24ドルで推移していた価格が2006年春に上昇を始め、2007年7月に同1.0353ドルを記録した後、2008年以降は下落を続けて2009年1月には同0.15ドル台に低下している。ホエイの価格もおおむね乳糖と同様の動きを示しており、2009年1月の価格は同0.1638ドルとなっている。
ちなみに、クラスⅣ乳価の算定の際に政府が適用している脱脂粉乳の加工経費はポンド当たり0.1678ドルであり、同様にクラスⅢ乳価の算定の際のホエイの加工経費は同0.1991ドルである。2008年10月以降、ホエイの卸売価格はこの加工経費を下回っており、理論的にはホエイの生産・販売は原価割れの状態が続いていることになる(注4)。
(注4)実際には、2008年の後半から燃油価格の低下などが進んでいることから、乳製品の製造コストも低下しているものと考えられる。
4 進展する乳業の構造変化
(1)乳業工場数の減少と大規模化
米国の酪農家戸数は、過去30年間にわたって年平均5.5%のペースで減少を続け、2008年には7万3千戸にまで減少している。直近の10年間を見ても酪農家戸数は平均で前年比5.2%減少しており、全国の生乳生産量の増加に伴って、1戸当たり出荷乳量の増加は続いている。一方、日本における2008年の酪農家戸数は2万4千戸で、過去30年平均の減少率は5.3%となって いる。規模拡大を伴いながら酪農家戸数が長期にわたって減少を続ける構造は日米共通である(注5)。
(注5)日本の直近10年の平均酪農家減少率は4.2%であり、短期的には米国よりも減少が緩やかである。
また、米国においては、酪農家だけでなく乳業者についても生産構造の変化が続いており、工場数の減少と生産規模の拡大が現在も進展している。以下では、飲用牛乳と主要乳製品に分けて、米国の乳業工場の構造変化の状況を追ってみたい。
(ア) 飲用牛乳の生産構造の変化
図21は米国の飲用牛乳工場数と1工場当たり年間出荷量の変化を示したものである。米国の飲用牛乳工場数は、戦前の1940年には9,950カ所あったが、酪農家の生乳販売形態がそれまでの自家分離・クリーム限定販売から酪農協を通じた全乳販売へと移行する過程で急減し、1970年には2,216カ所と30年前の4分の1に減少した。その後も、飲用牛乳工場の減少と大規模化の動きは続き、1990年に605カ所あった飲用牛乳工場数は、2007年には327カ所まで減少している。
図21 飲用牛乳工場数と1工場当たり出荷量
|
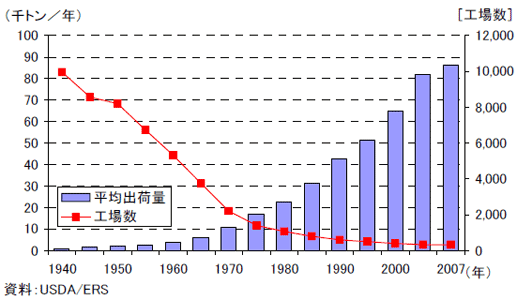 |
この過程で、工場1カ所当たりの飲用牛乳生産量は拡大を続け、2007年には平均で年間8万6千トン(1日当たり236トン)にまで増加している。これは、1990年の4万3千トンの約2倍、1970年の1万1千トンの約8倍に相当する。ちなみに、2007年における日本の飲用牛乳工場数は534カ所であり、1カ所当たりの年間平均生産量は約1万トンと米国の1970年の水準にとどまっている。
(イ) 主要乳製品の生産構造の変化
図22は米国における主要乳製品の製造工場数と1工場当たり年間出荷量を示したものである。
図22-1 チーズ製造工場数と年間平均出荷量
|
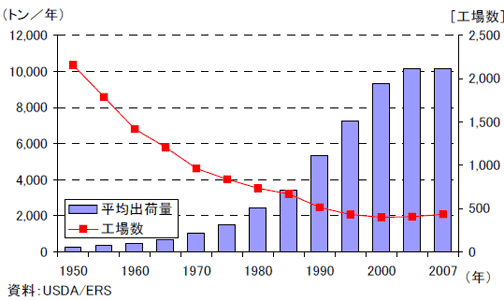 |
図22-2 バター製造工場数と年間平均出荷量
|
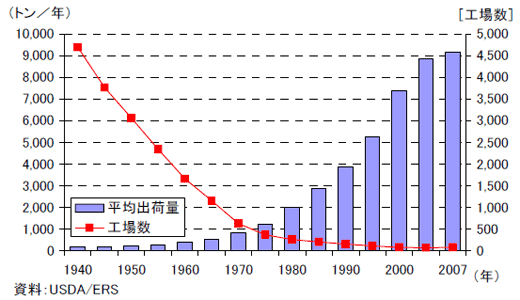 |
図22-3 脱脂粉乳製造工場数と年間平均出荷量
|
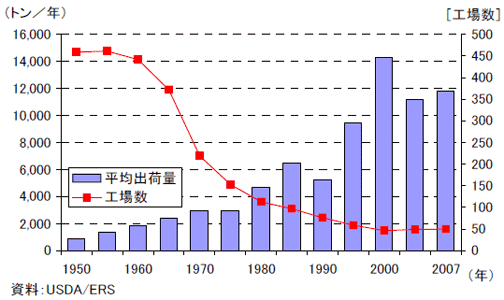 |
チーズの製造工場数は1950年の2,158カ所から1998年には398カ所にまで減少したが、その後は増加に転じており、2007年は434カ所まで回復している。一方、1工場当たりの年間出荷量は、1950年の250トンから順調に増加して2000年には9,317トンに達したが、2000年以降はその伸びが鈍化し、2007年の1工場当たり生産量は1万138トンにとどまっている。これは、テキサス州など新興酪農地域で近代的な大規模工場の新設が続くと同時に、東海岸などでは小規模のチーズ工場が増加しているためであり、チーズの生産構造は二極化が進展しつつある。
バターの1工場当たり生産量の長期的傾向はチーズによく似ているが、工場の減少速度はチーズよりも急である。1950年にチーズを上回る3,060カ所を数えたバターの工場数は、1997年に100カ所を下回り、2003年には69カ所まで減少した。2007年のバター工場数は76カ所とやや増加しているが、これは、有機バターなどのニッチ製品を製造する小規模工場の新設によるものと考えられる。一方、1工場当たりの年間出荷量は、1950年の206トンから2007年には9,149トンまで増加しており、全体としてはチーズとほぼ同様の規模拡大傾向となっている。これは、バターの総生産量が長期的にはさほど増加していない中で、工場数がチーズよりも急速に減少した結果である。
脱脂粉乳の製造工場数は1950年の時点で既に459カ所しかなく、1984年には100カ所を下回るなど、チーズやバターに比べると早い段階から工場の集約化が進展した。1997年に50カ所を下回ってからは工場数の変動はほとんどなく、年によりわずかな増減を繰り返しながら、近年は45〜50カ所の範囲内で推移している。一方、1工場当たりの年間出荷量は順調に増加を続け、2002年には1万6,087トンに達した。直近では生産規模がやや低下しているが、これは、低脂肪牛乳やイタリアンチーズなどの消費の変動などにより脱脂粉乳の生産量が減少したためであり、工場の製造能力そのものが低下しているわけではないことに注意が必要である。
(2)牛乳乳製品の種類別に異なる大手乳業
米国には、飲用牛乳と主要乳製品のすべてを自ら製造・販売する「総合乳業」はほとんどなく、乳製品の種類ごとに大手乳業メーカーが異なっている。例えば、飲用牛乳で最大の製造シェアを持つ米国最大の乳業のディーン・フーズ社は、チーズやバターの生産を行っていない。逆に、小売向けのバターで広く知られている農協組織のランド・オレイクス(LOL)は、飲用牛乳は自らの工場では製造せず、委託商品の販売を主体にしている。
一般に、米国で生産される牛乳乳製品のうち、飲用牛乳やヨーグルトは民間企業の製造シェアが高く、脱脂粉乳やバターは農協のシェアが高い。図23は主要乳製品の生産全体に占める酪農協のシェアの変動を示したものである。酪農協が自ら製造する乳製品はバターと粉乳類が中心で、そのシェアが増加傾向にあるのに対し、飲用牛乳における酪農協の製造シェアは極めて低く、かつ、その割合は低下傾向にあることがわかる。以下では、主要な牛乳乳製品について、品目別に業界の状況を説明する。
図23 牛乳乳製品の出荷量に占める酪農協のシェア
|
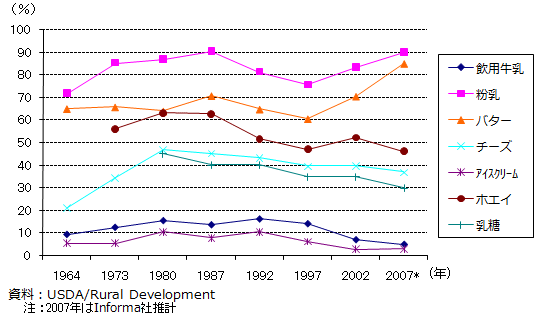 |
(ア) 民間企業が主導する飲用牛乳市場
米国で飲用牛乳の製造を手がけている主体は、酪農協、小売企業、商系乳業の3つに大別される。
飲用牛乳市場における酪農協のシェアは1930年代までは高かったとされるが、戦後、加熱処理技術の進化に伴う工場への先端技術投資や製品管理技術などの問題に対応できなかったことから市場からの撤退が相次ぎ、1964年の時点で市場シェアは9.4%にまで低下した。その後、1980年代から90年代前半にかけては他社からの工場買収などによりやや上昇したものの、1992年の16.2%をピークに再び減少に転じており、2007年における市場シェアは5%前後にまで低下している。なお、米国最大の酪農協であるデイリー・ファーマーズ・オブ・アメリカ(DFA)は子会社(株式会社)で飲用牛乳を製造しているが、LOLやカリフォルニア・デイリー(CDI)など他の有力酪農協は大手飲用牛乳企業に生産を委託し、飲用牛乳の生産からは完全に手を引いている。
スーパーやコンビニなどの小売企業は、多くの州で飲用牛乳の小売価格規制が行われていた1960年代から1970年代にかけて、飲用乳工場への直接投資を進めた。これは、生産・販売の川上統合による供給の安定化と、労働費などの流通コストの削減などの面でメリットがあったためとされる。しかし、1980年代に入って州による規制の撤廃が続く中、工場近代化のための投資が必要となった大手スーパーは工場の売却を進め、1980年代には小売系乳業の市場シェアは15%程度に減少した。なお、USDAによると、2001年にはこの割合が約20%に回復しているとされ、小売業界第2位のクローガー社や、同第4位のセーフウェイ社は引き続き自社の飲用乳工場を保有している。
飲用牛乳の大半は、株式会社が所有する飲用乳工場で製造されており、この構造は古くから変わっていない。しかし、企業の買収や統合が頻繁に行われたため、1970年代の有力企業は既に業界には残っておらず、1980年代に有力だったボーデン社もブランド名だけを残して飲用乳業界から撤退している。1990年代後半には、1920年代から飲用牛乳の販売を行ってきたディーン・フーズ社と、1993年に冷蔵業界から飲用乳業界に進出を始めたスイザ・フーズ社の大手2社により、中堅の飲用乳工場の買収・統合が積極的に進められた。その後、2001年12月にはスイザ・フーズ社がディーン・フーズ社を買収し、乳業界での歴史の長いディーン・フーズ社を社名として引きついだ巨大飲用乳企業が誕生している。
(イ) 商系乳業と酪農協がシェアを分け合うチーズ市場
チーズの製造には小売企業の関与はほとんどなく、酪農協と商系乳業が製造の主体となっている。
チーズ市場に占める酪農協の出荷量の割合は、1964年の21.1%から1980年には47.0%にまで上昇し、その後徐々に低下して2007年には37%となっている。酪農協が生産するチーズはアメリカンチーズが主体であり、イタリアンチーズやスイスチーズなどこれ以外のチーズの市場シェアは低い。2002年には、アメリカンチーズの66.0%が酪農協により生産されたのに対し、イタリアンチーズとスイスチーズの市場シェアは、それぞれ22.1%、15.6%にとどまっている。しかし、2003年には一部の酪農協がアメリカンチーズ工場を集約化するとともにイタリアンチーズ工場を新設するなど、酪農協の中にも需要の変化に対応しようとする動きが見られる。チーズの出荷量が多い酪農協としては、全国に組合員を抱えるDFAやLOLのほか、ウィスコンシン州周辺の酪農家を中心に組織されたフォレスト・ファームや、ミネソタ州周辺の酪農家を組合員とするアソシエイテッド・ミルク・プロデューサー(AMPI)などが挙げられる。
一方、チーズの製造に占める商系乳業のシェアは近年増加傾向にあり、特に、モッツァレラチーズを中心とするイタリアンチーズでその製造シェアが高い。商系乳業は、近年、カリフォルニア州、アイダホ州、ニューメキシコ州、テキサス州などの西部地域で相次いで工場を新設しているが、これらの工場は、一回の生乳処理単位が大きく、短時間でのチーズ生産が可能で、その製造コストも安い。チーズの出荷量が多い商系乳業には、外食向けを中心に世界最大のモッツァレラチーズ生産量を誇るレプリノ・フーズ社、小売向けブランドを展開する企業向けにアメリカンチーズを供給するグランビア・フーズ社、97年に米国に進出したカナダ最大の乳業メーカーで、イタリアンチーズやスイスチーズを製造するサプート社、アメリカンチーズの生産が中心で、近年、テキサス州に新工場を建設するなど急速に生産を拡大しているヒルマー・チーズ社などがある。
(ウ) バターと脱脂粉乳の生産は酪農協が中心
バターや脱脂粉乳の生産は、酪農協が主体となって行われている。バターの生産に占める酪農協のシェアは、1987年の70.8%から1997年には60.6%に低下したものの、再び上昇に転じて2007年には85%前後に達している。また、脱脂粉乳を主体とする粉乳類の生産についても、1987年の90.6%から1997年に75.7%に低下した後、2007年には再び90%前後に回復している。
バターの生産量が最も多い酪農協は、米国で強いブランド力を誇るLOLであり、工場はカリフォルニア州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州、オハイオ州の4カ所に分散している。また、カリフォルニア州に4工場を保有するCDIや、北西部のワシントン州とアイダホ州に工場を持つ地域型酪農協のデイリーゴールド(ノースウエスト・デイリー・アソシエーション)の生産も多い。このほか、前述のフォアモーストファームやAMPIをはじめとする地域型の酪農協でも一定量の生産が行われているが、広域酪農協のDFAは自社工場での生産はさほど多くない。企業系乳業では、ウィスコンシン州、ユタ州、ネブラスカ州に工場を保有するグラスランド・デイリー社の生産が多い。
一方、脱脂粉乳はカリフォルニア州に5工場を保有するCDIの生産が最も多く、広域酪農協のLOLやDFAがこれに次いでいる。地域型酪農協ではデイリーゴールドの生産が多く、フォアモースト、AMPI、ミシガン・ミルク・プロデューサーズなどでも脱脂粉乳の生産が行われている。CDI、LOL、DFAなどの9酪農協は、脱脂粉乳や全粉乳の共同販売会社であるデイリーアメリカ社を通じて脱脂粉乳の販売を行っており、特に輸出向けでは同社が窓口となった販売が大半を占める。デイリーアメリカ社はニュージーランド(NZ)の独占的乳業であるフォンテラ社と委託販売契約を結んでいることから、米国の脱脂粉乳の需給や価格は、他の製品以上に国際市場の影響を大きく受ける構造にある。
(3)乳業者の寡占化の進展
米国では食品小売業者の寡占化が進展しており、食料品の総売上高に占めるウォルマートなど大手7社の割合は、1994年の25%から2007年には54%に上昇している。大手の市場シェアが拡大する傾向は、外食向けの食材供給業者においても同様であり、2006年の上位5社シェアは31%と1994年の17%を上回っている。
食肉業界では寡占化がより進んでいる。肥育牛の処理頭数に占める上位4社の割合は、1980年の35.7%から1990年には71.6%に上昇し、1990年代後半からは80%前後の高い割合で安定している。また、肉豚の処理頭数に占める上位4社の割合は1990年の40.3%から2006年には62.8%に、鶏肉の生産に占める上位3社の割合も1990年の35.5%から2007年には50.9%に上昇している。
前述のとおり、米国の牛乳乳製品製造工場数は減少を続け、1工場当たりの出荷量も増加するなど大規模化が進展している。関係業界の寡占化が進展する中で、乳業分野における大手乳業の市場シェアはどのように変化してきたのであろうか。以下では、米国商務省センサス局の統計を基に、牛乳乳製品における市場占有度の推移を品目別に比較してみたい。
(ア) 飲用牛乳
図24は飲用牛乳の年間出荷額における市場占有度の推移を示したものである。全体に占める上位50社の割合は1958年の45%から徐々に上昇し、2002年には83.7%に達している。これは、小規模飲用乳業が市場から撤退していく中で、残された乳業の規模拡大が着実に進んできたことを示している。一方、上位4社の割合は1958年の23.0%から1997年の21.3%までほとんど変化せずに推移し、2002年に大きく上昇して42.6%に達している。これは、1990年代中盤から後半にかけて、スイザ・フーズとディーン・フーズの大手乳業2社が30件を超える中堅企業の買収を行った後で2001年末に合併したことによる。現在、米国の飲用牛乳市場で圧倒的な市場への影響力を持つのは、この合併により誕生したディーン・フーズ社である。
図24 飲用牛乳製造業における市場占有度の推移
|
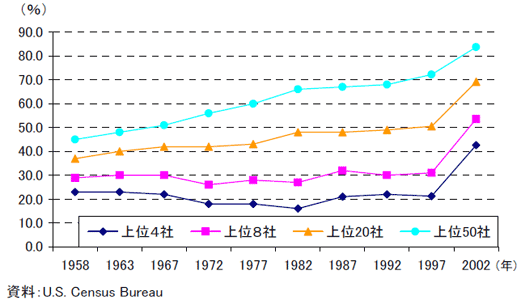 |
ちなみに、飲用牛乳市場に占める農協系乳業の割合は極めて低いが、農協系乳業の内数で見れば、2002年には上位4農協が出荷する飲用牛乳の割合が全体の73%を占めている。
(イ) チーズ
図25はチーズの市場占有度の推移である。上位50社の市場シェアが1963年の69.0%から2002年には88.0%まで上昇しているのに対し、上位4社のシェアは逆に1963年の44.0%から2002年には34.6%に低下している。また、5〜8位の4社のシェアは同期間に7.0%から15.5%に、9〜20位の12社のシェアは8.0%から22.7%に上昇している。特に、1992年以降は9〜20位の中堅乳業のシェア拡大が著しい。
図25 チーズ製造業における市場占有度の推移
|
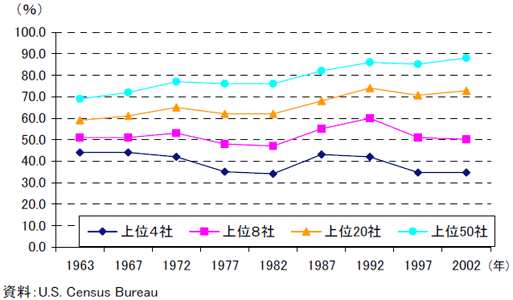 |
チーズの生産で大手4社のシェアが上がらない一方、中堅乳業のシェアが上昇しているのは、企業ごとに生産の主体となるチーズの種類が異なっているためである。すなわち、古くからの大手乳業が消費の伸び悩むアメリカンチーズを主体に手がけてきたのに対し、イタリアンチーズやスイスチーズを製造している中堅企業で生産拡大や新規参入が進んでいることが、この数値に反映されているものと考えられる。近年、西部地域を中心に大規模なチーズ工場の新設が相次いでいるが、これが市場シェアの動向にどのように影響してくるのか、今後の動きが注目される。
なお、ナチュラルチーズの生産に占める農協系乳業の割合は2002年の時点で約4割(39.8%)となっているが、その74%は上位4酪農協により生産されている。視点を変えれば、上位4酪農協が全国の約3割のナチュラルチーズを生産しているということであり、アメリカンチーズを中心に、大手酪農協の市場への影響力は依然として大きい。
(ウ) バター・粉乳類
図26はバターの年間出荷額における市場占有度の推移を示したものである。飲用牛乳やチーズと異なり、バターについては1970年前後に乳業の集中化が急激に進展し、1977年には上位4社の占有度が49.0%に達した。その後、1987年にこの割合は40.0%まで低下したが、近年再び上昇に転じており、2002年の市場占有度は57.5%に達している。米国農務省地域振興局(USDA/RD)の調査によると、同年のバター生産に占める農協系乳業の割合は70.6%で、大手4社がその8割を占めるとされていることから、この4社がすべて農協系乳業であることがわかる(注6)。なお、米国のバターの生産はカリフォルニア州が最も多いが、全体の45%前後を占める小売向けのバターは消費地に近い州で再加工されることが多い。このため、原料バターの工場間転送やライバルの乳業メーカーへの製造委託が頻繁に行われていることも、米国のバター市場の大きな特徴となっている。
図26 バター製造業における市場占有度の推移
|
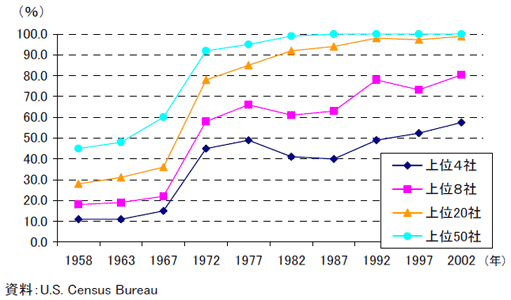 |
(注6)2005年に商系のグラスランド・デイリー社がウエストポイント・デイリー社を買収してバターの生産量を拡大しており、現在では上位4社がすべ
て農協系という状況は変わっている。
図27は粉乳・練乳の市場占有度の推移である。他の品目と異なり、上位50社の占有度は1963年の時点で既に90.0%に達し、その構造がほとんど変化していないのが特徴である。上位4社の占有度は1963年の40.0%から1980年前後に一時的に低下したものの、長期的に見ればおおむね40%前後で推移しており、2002年には47.4%に上昇している。また、上位8社で市場の50〜60%、同12社で70〜80%を占める構造も変化していない。脱脂粉乳に限定したUSDA/RDの調査によると、2002年の農協系乳業大手4社の市場占有率は1997年調査に比べて23ポイント上昇して64%となり、農協系乳業における内部占有率も63%から74%に上昇している。なお、前述のとおり、主要な農協系乳業はデイリーアメリカ社を通じて脱脂粉乳の販売を行っているが、2002年の同社の脱脂粉乳取扱シェアは75%に上っており、市場への影響力が非常に大きいことも脱脂粉乳の特徴である。
図27 粉乳・練乳製造業における市場占有度の推移
|
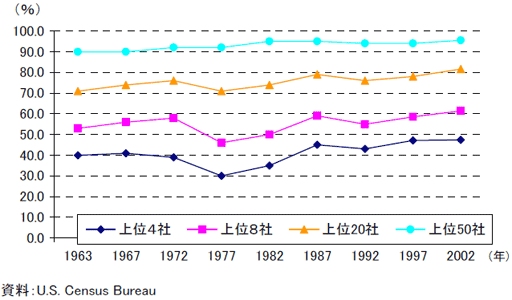 |
5 拡大する輸出量と輸出振興措置
米国はガット・ウルグァイラウンド(UR)合意により乳製品の輸入が自由化されるまで、1933年輸入調整法第22条に基づいて主要乳製品の輸入を一定数量以下に制限していた。現在はこの輸入制限が撤廃されており、バター、脱脂粉乳、チーズなどについては国別に設定された一定量の関税割当枠の下で低税率での輸入が認められている。しかし、枠外で輸入される乳製品には高水準の二次税率が課されており、一部の品目を除いて、乳製品の輸入急増を防止する構造は維持されている(表4)。
表4 米国の主要乳製品の関税率(2009年)
|
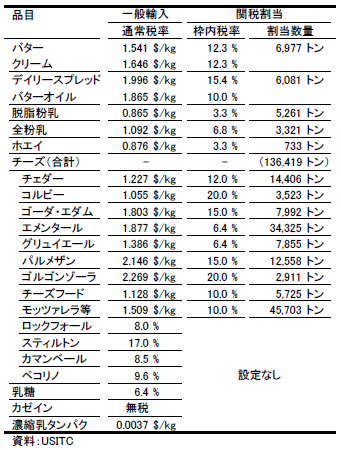 |
一方、乳製品の輸出に目を転じると、UR合意以前は、政府(CCC:商品金融公社)が価格低落時に買い上げた国内在庫の直接輸出と、DEIP(乳製品輸出奨励事業)を通じた輸出補助金付きの民間輸出がその中心であった。1990年代の後半から2000年代前半にかけては、UR合意により政府による輸出補助措置に上限が設定されたこともあって、純粋な商業的輸出は乳糖やホエイなど一部の品目に限られており、この上限数量を超えた輸出の拡大はほとんど進まなかった。しかし、2003年以降、新興経済国における需要の拡大や生産者団体の自主基金による輸出支援措置もあって、乳製品の輸出量は拡大が続いている。以下では、米国の乳製品貿易の概要と品目別の貿易の状況について説明する。
(1)米国の乳製品貿易の概要
(ア) 乳製品貿易の国際収支は黒字に転換
前述のとおり、米国では価格の低落時には政府による主要乳製品の買上げ措置が実施されており、多くの乳業者が国内供給を優先する市場構造にある。このため、乳製品の国際需給がひっ迫しない限り、一部を除いて米国産乳製品の価格競争力は弱く、結果的に乳製品貿易については輸入超過の状況が長く続いてきた。図28は1989年以降の米国の乳製品貿易額の推移を示したものである。多額の補助金付き輸出が行われた1993年を除いて赤字が続いていた米国の乳製品貿易収支は、国際的な需給ひっ迫に伴う輸出価格の上昇と輸出数量の増加により、2007年に14年ぶりに輸出超過に転じ、2008年には黒字額を7.1億ドル(702億9千万円)に拡大させている。
図28 乳製品の輸出入金額の推移
|
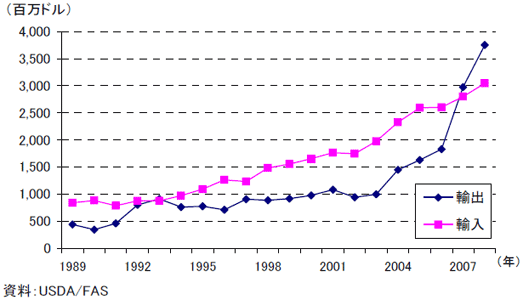 |
(イ) 変化が続く乳製品の輸出先
米国の乳製品輸出金額は、WTO協定により補助金付き輸出が制限される中で、2003年まで年間9〜10億ドルの範囲内でほとんど増減してこなかった。しかし、2004年以降、脱脂粉乳とチーズの輸出が拡大を始め、2006年後半から2008年にかけては国際価格の高騰も手伝って乳製品の輸出金額は急増した。2008年の乳製品輸出金額は前年を大きく上回る37.6億ドル(3,722億4千万円)に達したが、このうち、脱脂粉乳が37%、チーズが15%、ホエイ類が14%を占め、バターの7%、調製品の7%、乳糖の5%がこれに次いでいる。ホエイ類と乳糖の構成割合が前年に比べて大きく下落したのは、前年の国際価格の暴騰により需要が代替商品に移行したためである。輸出数量ベースでの構成割合は、ホエイ類が25%、脱脂粉乳が24%、乳糖が14%を占めており、単価の安いホエイ類や乳糖の割合が高い(図29)。ホエイ類や乳糖は国内生産に占める輸出の割合が高く、国内の価格支持の対象となっていないことから、国際価格の影響を大きく受ける商品と言える。
図29 乳製品輸出量の推移
|
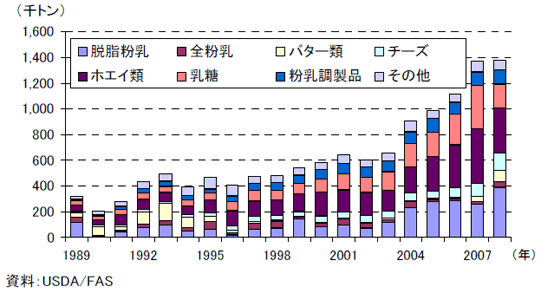 |
図30は米国の乳製品輸出金額と輸出先の変化を示したものである。1990年に最大の輸出先であった旧ソ連に属する国は2008年の主要輸出先10カ国には含まれていない。一方、メキシコとカナダはNAFTAの発効以前から全体の18%を占めていたが、2000年までにその割合は3分の1を超え、2008年には全体の34.9%に達している。また、2000年には日本、台湾、韓国、香港など東アジアの先進国が主要な輸出先であったが、2008年にはフィリピン、インドネシア、マレーシアなどのASEAN諸国や中国への輸出割合が増加しており、さらに、エジプトやサウジアラビアなど中東向けの輸出も急拡大している。上位10カ国の輸出先が全体に占める割合は低下傾向にあり、米国の乳製品の輸出先は品目に応じた多様化が進展しつつある。
図30 米国の乳製品輸出額の拡大と輸出先の変化 |
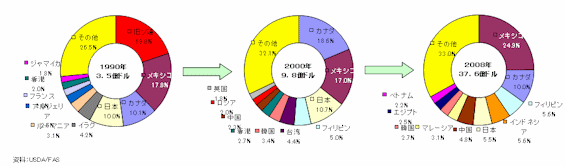 |
※クリックすると拡大します。 |
(ウ) 輸入元により大きく異なる輸入乳製品
米国の輸入金額は、WTO協定に基づく関税割当数量の拡大に伴って1995年から2000年まで着実に増加してきたが、割当枠の拡大が停止した2001年以降も、引き続き増加を続けている。これは、低税率輸入が可能な一部のチーズ、ホエイ類、粉乳調製品などで輸入数量が増加を続けてきたためである(図31)。輸入の品目別構成を見ると、2008年の輸入金額30億5千万ドル(3,019億5千万円)のうち、チーズが38%、カゼインが25%を占め、粉乳調製品が10%でこれに次いでいる。チーズやカゼインが全体に占める割合は、1990年には総輸入額の9割前後を占めていたが、1990年代の後半から調製品やホエイ類の輸入の増加により徐々に低下傾向にある。
図31 乳製品輸入量の推移
|
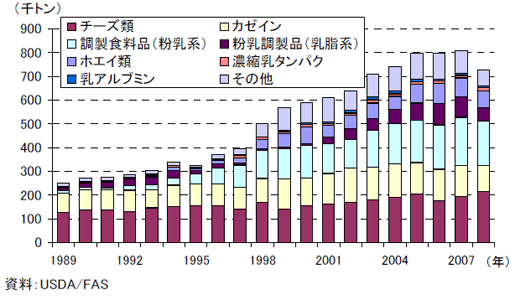 |
図32は米国の乳製品輸入金額の拡大と輸入先の変化を示したものである。最大の輸入先であるNZからの輸入割合がカゼインとホエイ類の輸入増加により2割前後でほぼ安定していること、カナダからの輸入割合がNAFTAの発効による粉乳調製品の輸入増加に伴って2000年までに拡大していること、欧州からの輸入割合がカマンベールやブリーなどの低税率チーズの輸入拡大に支えられて比較的安定していることなどが特徴である。輸出先が1990年以降大きく変化しているのに比べると、輸入先については国別の全体構造に大きな変化は見られない。しかし、輸入先により重要な輸入品目が大きく異なっていることは注目される。
図32 米国の乳製品輸入額の拡大と輸入先の変化 |
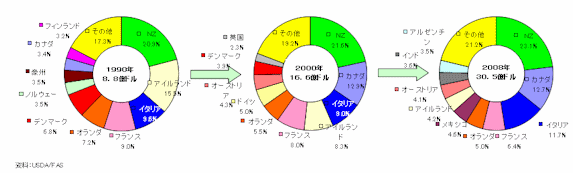 |
※クリックすると拡大します。 |
(2)主要品目の貿易面での特徴
米国の乳製品貿易において重要な位置を占めるのは、輸入品目ではチーズとカゼインであり、輸出品目では脱脂粉乳、ホエイ、乳糖である。また、バターやチーズは輸入が輸出を上回る状況が続いていたが、近年、輸出が大幅に増加している。以下では、これらの主要乳製品について、品目ごとに貿易の状況を説明する。
(ア) 大きく変動する乳製品の貿易割合
図33は主要乳製品の生産量に占める輸出量の割合を比較したものである。米国の乳製品のうち、古くから輸出市場への依存度が高いのは乳糖であり、国内生産の40%前後がコンスタントに輸出に向けられ、近年ではその割合が50%を上回っている。また、ホエイについても輸出依存度が高く、UR合意の実施に伴って輸出割合が20%から30%前後に上昇した後、直近ではその割合が50%を超えている。さらに、タンパク濃縮ホエイの輸出割合もホエイと並行して近年上昇傾向にある。これに対し、政府による価格支持の対象となっている基幹的乳製品(脱脂粉乳、バター、チーズ)の輸出割合は総じて低く、特に1995年以降は補助金付き輸出に上限量が設定されたこともあって、バターとチーズの輸出割合は非常に低い水準が続いてきた。しかし、2004年以降、それまで1割前後だった脱脂粉乳の輸出割合が急激に上昇して国内生産の半分程度が輸出されるようになるなど、バターやチーズも含めて、基幹的乳製品の輸出は急速に増加している。これは、生産者団体の自主基金を原資とする輸出支援措置の実施、国際的な乳製品の需給ひっ迫、さらには主要通貨に対するドル安などによるところが大きいが、脱脂粉乳に限って言えば、2002年に米国内における脱脂粉乳の支持価格が引き下げられたことも要因の一つと言える。
図33 乳製品の生産量に占める輸出量の割合
|
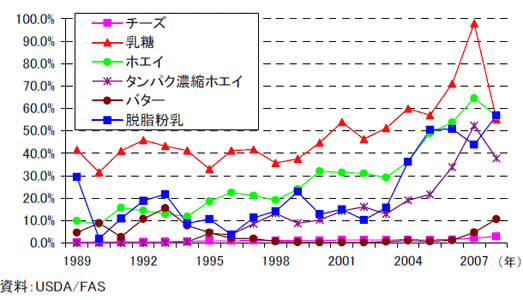 |
一方、生産量に占める輸入量の割合はすべての主要乳製品で非常に低くなっており、最も輸入依存度の高いホエイ類(注7)でもその割合は国内生産の15%前後にとどまっている(図34)。米国の乳製品輸入のうち金額ベースで最大の割合を占めるチーズについては、輸入量が増加しているにもかかわらず、国内市場の拡大もあって輸入依存度は5%前後で安定している。また、バターについてはUR合意の実施に伴って輸入量が国内生産量の8%前後に上昇したが、近年は国内生産の増加により依存度が低下傾向にある。しかし、米国の乳製品輸入のうちチーズに次いで輸入金額の多いカゼインについては、米国内での生産が限られており(注8)、2000年代前半に輸入の急増が問題となった濃縮乳タンパク(MPC)と同様に、米国内で流通する商品の大半が輸入品となっている。これらの製品は、脱脂粉乳との代替性が高い反面、乳製品価格支持制度の対象とはなっていないため、乳業に生産のインセンティブが働きにくいことが、生産が少ない理由と考えられる。
図34 乳製品の生産量に占める輸入量の割合
|
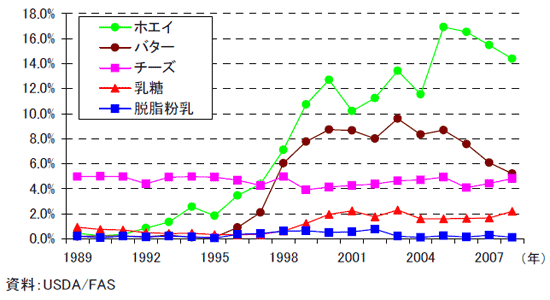 |
(注7)米国の輸入統計では、ホエイとタンパク濃縮ホエイが区分されていない。
(注8) 製造工場数の減少に伴い、USDAは1970年を最後に生産数量の公表を停止しているが、毎年数千トンのカゼインが輸出されていることから、国内生産が全くないわけではない。
(注8) 製造工場数の減少に伴い、USDAは1970年を最後に生産数量の公表を停止しているが、毎年数千トンのカゼインが輸出されていることから、国内生産が全くないわけではない。
(イ) 品目別に見た主要貿易相手先
米国の主要輸出品目の輸出先は、脱脂粉乳、ホエイおよびタンパク濃縮ホエイ、乳糖などの品目により傾向が異なるが、このような原料型の乳製品に限れば、概してタンパク質の含有割合の高い品目ほど輸出に占める新興経済国の割合が高い。脱脂粉乳についてはかつてはメキシコがほぼ唯一の主要な輸出市場であったが、2004年以降、フィリピンやインドネシアをはじめとするASEAN諸国への輸出が急増し、その重要性が増している(図35)。これに対し、ホエイおよびタンパク濃縮ホエイはメキシコに次いで日本やカナダへの輸出も多く、近年では中国向けの輸出も多い(図36、図37)。また、乳糖についてはかつては日本向けが輸出先の大半を占めていたが、現在では韓国、中国、メキシコ向けの輸出も多くなっている(図38)。このほか、チーズについてはメキシコ向けの輸出が急増しているものの、カナダ、日本、韓国向けの割合も依然として高いこと、また、粉乳調製品の輸出はメキシコやカナダ向けが中心となっていることも特徴である。
図35 脱脂粉乳の輸出先別輸出金額の推移
|
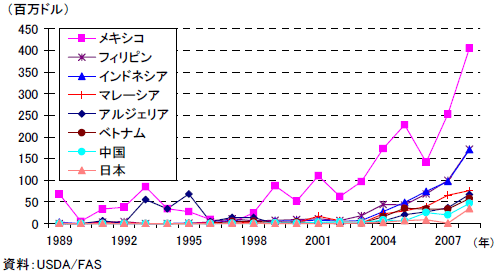 |
図36 ホエイの輸出先別輸出金額の推移
|
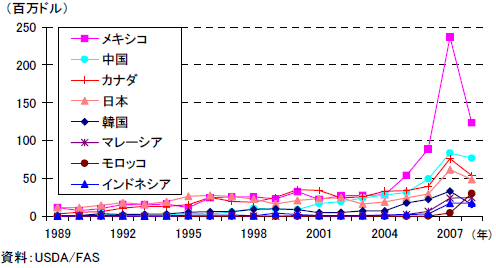 |
図37 タンパク濃縮ホエイの輸出先別輸出金額の推移
|
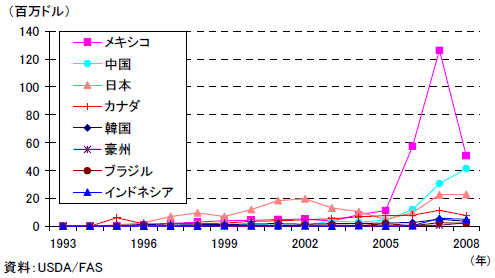 |
図38 乳糖の輸出先別輸出金額の推移
|
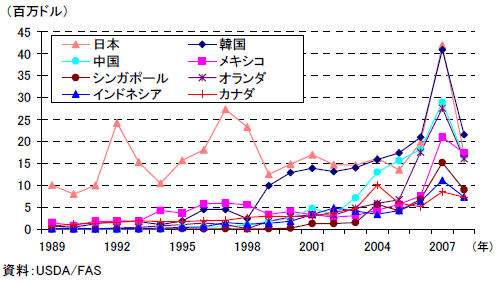 |
一方、米国の乳製品の輸入元も品目により大きく異なっている。チーズの輸入元はその大半が欧州であり、特にイタリアやフランスからの輸入が順調に増加を続ける一方で、NZからの輸入額は減少している(図39)。これとは逆に、カゼインの輸入についてはNZからの輸入が増加を続ける一方で、欧州のアイルランドからの輸入額は減少傾向にある。また、近年はインドやアルゼンチンなど、新たな輸入元からのカゼインの輸入も増加している(図40)。
図39 チーズの輸入先別輸入金額の推移 |
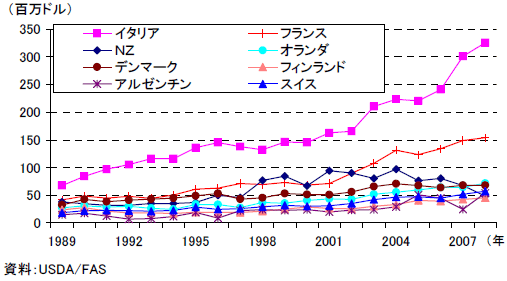 |
図40 カゼインの輸入先別輸入金額の推移 |
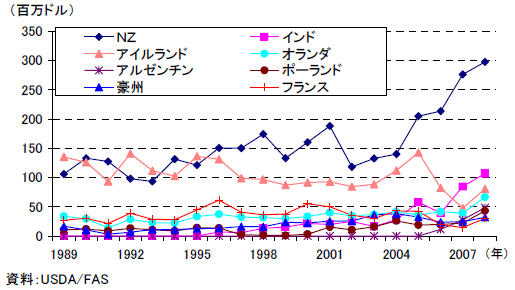 |
(3)輸出補助措置の変遷とその影響
(ア) 輸出補助措置の歴史
米国における乳製品の補助金付き輸出の歴史は、生乳の供給過剰により生産者乳価が下落した1920年代後半に、乳価回復を目的に行われたのが始まりである。戦後、1949年に生乳価格支持制度が開始され、CCCが脱脂粉乳、バター、チーズなどの基幹乳製品の買上げを通じて生乳価格の維持を図るようになると、米国の乳製品需給が緩和するたびに、CCCは大量の乳製品の在庫を抱えるようになった(注9)。当初、これらの在庫は国内外の食料援助などに向けられるものが中心であったが、1970年代から1980年代にかけて保管在庫が増加する中で、CCCは自ら脱脂粉乳やバターを国際市場に販売するようになった。しかし、国際的な乳製品の供給過剰や欧州の補助金付き輸出の影響により乳製品の国際価格は低迷しており、価格競争力が弱い米国産乳製品を抱えたCCCは赤字覚悟の輸出を余儀なくされていた。
このような中、米国議会では、欧州の補助金付き輸出などの不公正な貿易慣行に対抗するために自らも乳製品の民間輸出に補助金を交付すべきとの主張が高まり、1985年食料安全保障法でDEIPが制度化されるに至った。制度開始当初はDEIPの実績が上がらなかったが、これはCCCが補助金付き輸出の契約を行った民間企業に在庫乳製品を現物支給する仕組みで制度を運用していたためであり、1990年代に入って現金による直接補助の仕組みが導入されるとDEIPを通じた乳製品輸出は大幅に増加した。この結果、1980年代前半に国内生乳生産量の10%相当量を超えていたCCCによる乳製品の買上げ数量は、1990年代半ばには国内生産の2〜3%にまで減少した(注10)。
その後、1993年12月に最終合意に至ったUR交渉の結果を受けて、農畜産物の補助金付き輸出数量と補助金額に上限が設定されることになり、米国は乳製品も含めて1995年から2000年にかけてその段階的な削減を約束した。合意の実施初期段階では、米国の乳製品需給は比較的安定しており、輸出補助金も約束の上限数量を下回っていたが、実施期間の後半になると生乳生産が増加したこともあって乳製品価格が低下し、脱脂粉乳を中心に価格支持買上げが行われるようになった。このような状況にあって、米国は輸出補助金に認められた例外措置(注11)を活用し、1999年度から2000年度にかけてチーズと脱脂粉乳でWTOの譲許数量を上回る補助金付き輸出を行った。なお、2000年度以降、米国の補助金付き輸出数量の年間上限は、チーズが3,030トン、バターが21,097トン、脱脂粉乳が68,201トン、全粉乳などそのほかの乳製品が34トンに制限されているが、2004年1月のチーズと脱脂粉乳を最後に、米国政府はDEIPによる輸出補助金の交付を実施していない。
米国の生乳需給は、2000年代前半の生産の伸びが比較的低水準にとどまったことで安定を取り戻したが、これに貢献したのが、米国の主要酪農協を会員とする全米生乳生産者協議会(NMPF)が2003年7月に設立した酪農協共同基金(Cooperative Working Together:CWT)による自主財源事業である。CWT事業は、生乳100ポンド当たり10セントの生産者任意拠出金(注12)を原資に、生乳の需給引き締めを目的とする事業を行うものであり、現在は、基金の設立と同時に開始された生乳供給削減のための搾乳牛とう汰促進事業と、2004年から開始された戦略的乳製品への輸出補助金交付事業が実施されている。このうち、輸出補助金の交付事業は、今後の成長が見込まれる重要市場向けの特定の乳製品に限定して輸出補助金を交付するもので、個別の輸出契約ごとに乳業者(酪農協)がCWTに事業承認を申請し、承認が下りた契約の輸出先と輸出数量がHPに掲載される透明性の高い運営がなされている。事業が開始された2004年当初は輸出補助対象の多くが中東向けのチーズであったが、2008年にはバターとバターオイルが補助の大半を占めており、このうち、バターについては年間輸出量の3割強(25,300トン)が補助の対象となっている。また、補助金付き乳製品が輸出された国の数も35カ国に増加している。CWTは政府の財源を使用しておらず、WTO協定上の問題を生じる可能性が低いため、チーズやバターの補助金付き輸出数量がUR合意に基づく約束水準を超えている年がある点も重要である。2008年後半から、新興経済国における乳製品の需要が景気の減速の影響で伸び悩む中で、CWT事業が対象とする品目や輸出先がどのように変わっていくかは、今後の米国の乳製品需給の動向を判断していく上で重要な指標になるものと考えられる。
(注9)支持価格は、家畜の改良や飼養技術の改善による生乳の生産性向上にかかわらず、1914年を基準とするパリティ指数(生産資材などの総合物価指数)の変動に応じて定められていた。このため、支持価格は実際のコストよりも高く設定されがちであり、供給過剰を招きやすい構造にあった。なお、支持価格とパリティ指数との連動は1981年10月に廃止された。
(注10) CCCは価格支持を目的とした買上げだけではなく、国内外の被災者や貧困層向け支援を目的とした乳製品の買上げも行っている。
(注11)WTO農業協定第9条には、削減約束の実施期間(2000年まで)に限り、前年度までに使用されなかった「輸出補助金枠」を翌年度以降に持ち越すことを認める規定がある。
(注12) 事業が開始された2003年当初の拠出金単価は生乳100ポンド当たり5セントであった。
(注10) CCCは価格支持を目的とした買上げだけではなく、国内外の被災者や貧困層向け支援を目的とした乳製品の買上げも行っている。
(注11)WTO農業協定第9条には、削減約束の実施期間(2000年まで)に限り、前年度までに使用されなかった「輸出補助金枠」を翌年度以降に持ち越すことを認める規定がある。
(注12) 事業が開始された2003年当初の拠出金単価は生乳100ポンド当たり5セントであった。
(イ) 主要品目別の輸出補助数量の推移
このように、米国における乳製品の輸出補助措置は、CCCによる在庫の放出からDEIPによる民間貿易補助を経て、現在はCWTによる生産者自主支援へと形を変えてきているが、この間、これらの輸出補助措置は米国の乳製品輸出にどの程度の影響を与えてきたのであろうか。図41〜43は、主要乳製品における輸出補助措置ごとの輸出実績を、全体の輸出数量と比較したものである。なお、一部の年で補助金付き輸出量が全体の輸出量を上回っているのは、CCCの放出とDEIPの実績の数値が財政年度(前年10月〜当年9月)ベースになっており、暦年ベースの総輸出量の数値との間に時間的なズレが生じているためである。
図 41 チーズの補助金付き輸出量と総輸出量 |
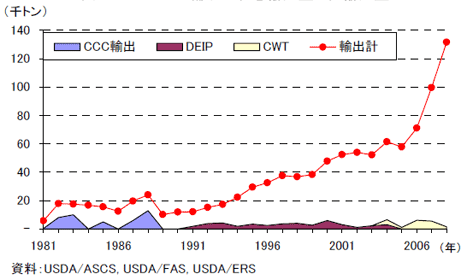 |
図42 バターの補助金付き輸出量と総輸出量
|
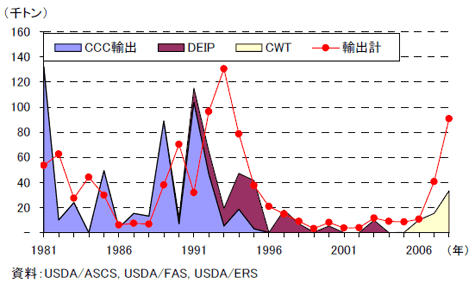 |
図43 粉乳の補助金付き輸出量と総輸出量
|
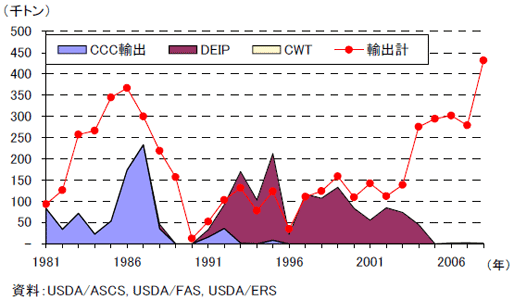 |
チーズの輸出量は1995年を境に大きく増加し、2008年には13万トンを超える水準に達している。1980年代から1990年代前半にかけては、チーズの年間輸出量は1万トン台で推移していたが、その増減は補助金付き輸出の増減と並行しており、純粋な民間輸出数量は1万トンを下回っていた。その後、1990年代の後半から輸出量は大きく増加したが、DEIPやCWTによる補助金付き輸出の数量は年間3千トン前後で推移しており、その割合は大きく低下している。
一方、バターの輸出量は輸出補助金への依存度が極めて高く、純粋な商業輸出は限定的である。特に、輸出量が急増した1992年から1994年にかけては、CCCの在庫放出やDEIPによる民間輸出支援に加えて、3年間合計で約26万トンのバターが海外食料援助のために輸出されており、輸出の大半が何らかの政府施策に基づくものであった。国際需給がひっ迫した2007年から2008年にはバターおよびバターオイルの輸出が急増しているが、前述のとおり、その3割以上はCWTによる支援を受けたものである。
脱脂粉乳・全粉乳の輸出はチーズとバターのちょうど中間のパターンをとっており興味深い。1980年代の脱脂粉乳輸出は、CCCの在庫放出とこれを上回る海外食料援助向けの輸出が主体であり、民間輸出はほとんどなかった。1990年代に入ると食料援助向けの輸出は減少し、DEIPによる脱脂粉乳と全粉乳の輸出が主体となったが、補助金付き輸出が全体の輸出を支える構造には変化がなかった。しかし、2000年代に入って脱脂粉乳の支持価格が引き下げられたころから補助金なし輸出が増加し始め、東南アジアを中心とする新興経済国の急速な需要拡大にも支えられて、2005年以降は年間30万トン前後の商業輸出が行われるようになっている。2007年10月以降、米国では価格の急落を受けて脱脂粉乳の政府買上げが行われているが、今後、CCCが保有在庫をどのような方法で放出していくのか、その動向が注目される。
6 終わりに
継続する国内人口の増加と、チーズを中心とした一人当たり乳製品需要の堅実な拡大に支えられ、米国の乳業はこれまで順調に生産を拡大してきた。また、近年は新興国における乳製品需要の高まりを背景に、輸出を大幅に増加させることで西部地域における大幅な生乳生産の増加を吸収してきた。その一方で、米国の乳業界は、大規模化・寡占化が進む国内の小売業界の動きに対抗して工場の統廃合と大規模化を進めるとともに、飲用乳、チーズ・ホエイ、脱脂粉乳・バターの3つのカテゴリー別に専業化を進めてきた。
現在、世界的な景気の悪化に伴う需要の減退が各国の酪農・乳業界を襲う中で、輸出依存度を高めていた米国の基幹的乳製品の価格は、国際価格と連動して急落している。米国政府は昨年末から順次、脱脂粉乳とバターの価格支持買入れを開始しているが、乳製品価格に連動して決まる酪農家の用途別乳価は大幅に下落しており、需要増大に伴う飼料価格の高騰と、金融危機による流動資金融資条件の悪化も加わって、購入飼料と借入資本への依存度の高い米国西部の大規模酪農経営は極めて苦しい経営環境に置かれている。
米国の乳業は、制度により製品価格の下落に応じた原料乳価の低下が担保され、かつ、最終的には連邦政府による無制限の乳製品の買上げも保証されていることから、原価が高い乳製品在庫の償却の問題こそ抱えているものの、経営的には比較的「余裕」があるように見える。本来、生乳需給の安定を通じて酪農家の経営安定を図ることを目的としていた国内施策が、国際市場が大混乱に陥る中ではほとんど用をなさず、結果的に酪農協をはじめとする大手乳業の経営安定につながっていることは何とも皮肉である。
現在は大きな混乱下にあるとはいえ、長期的に見れば、新興国における消費の拡大に牽引されて世界の乳製品需要が拡大を続ける可能性は高い。その一方で、需給に見合った生乳の安定供給の難しさは酪農・乳業界の永遠の課題であり、国際市場における流通量の不安定さもあいまって、乳製品の国際価格はこれまで以上に乱高下を繰り返すものと想定される。大規模化と省力化によって製品生産コストを削減しつつ、国内外のユーザーに対する価格交渉力を高めるための取り組みを進めてきた米国の乳業には、国内の生乳生産基盤の安定的な発展と、拡大が見込まれる輸出市場への進出の両方を存立させるための新たな戦略的行動が求められている。