【要約】
2000年の中国産稲わらにより発生した口蹄疫、ほぼ同時期からの飼料価格の上昇を契機とし行ってきた食品循環資源の活用を通じて、飼料費削減には直接には繋がらなかったものの、食品循環資源が加熱・発酵済であること、そのままでも食品として流通できる安全性の利点を生かして、国産飼料の安定供給およびブランドを構築するとともに、家畜ふん尿のたい肥化などによる地域稲作農家との連携、耕作放棄地・遊休農地における子牛の放牧による耕地の有効利用など、畜産経営のみならず耕種部門を含めた地域農業全体の活性化を図っている取り組みについて報告する。
1.はじめに
近年における各種生産資材の高騰がわが国農林水産業に及ぼした影響は極めて大きく、生産基盤の脆弱化が従前以上のテンポで進行している。各種生産資材を輸入に依存することから、国際的な需給変動のほか、投機マネーや為替相場の影響を強く受けるためである。生産資材の量的・価格的安定供給は、農林水産業振興において必要不可欠であり、とりわけ酪農・畜産部門においては生産コストの中心をなすことから、調達コスト低減が求められている。
表1及び2は2000年度以降の肉牛(去勢若齢肥育)及び生乳生産費の推移を示している。注目すべきは、2009年度にやや回復する傾向が看取されるものの、2007年度から2008年度にかけて農業所得が急激に減少し、肉牛については依然として赤字となっている事態である。生産物価格問題について論究するまでもなく、飼料費上昇が要因の一つとなっていることは明らかである1。すなわち、飼料価格が比較的低位であった2000年度における飼料費は、去勢若齢肥育牛1頭あたり188,725円、生乳100キログラムあたり3,015円であったが、2008年度には335,141円(+77.6%)、3,883円(+28.9%)にまで上昇し、2009年はトウモロコシ価格の下落により低下したものの、近年では再び上昇しており、飼料費は再び上昇している。近年において、食品循環資源をはじめとする低・未利用資源の飼料利用が拡大する所以はここにある。
1 紙数の都合から、もと畜費(肉牛)、乳牛償却費(生乳)については割愛した。近年における上昇は、循環的な価格変動と中小零細繁殖農家の離農が主たる要因となっている。詳細は、栗原幸一「肉用牛繁殖経営の課題」社団法人全国肉用牛振興基金協会『びーふキャトル』第15号、p2−p5、2009年を参照されたい。
表1 肉牛(去勢若齢肥育)生産費の推移 |
単位:1頭当たり円 |
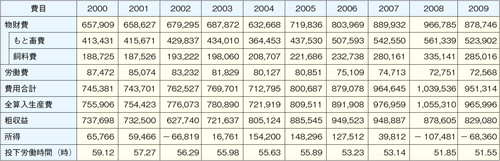 |
表2 生乳生産費の推移 |
単位:100kg当たり円 |
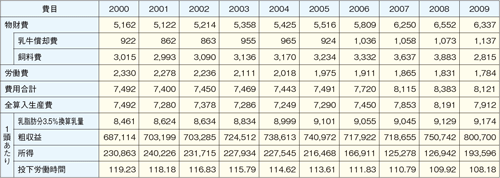 |
資料:農林水産省統計部『農業経営統計調査報告 畜産物生産費』 |
ところで、食品廃棄物処理問題からも食品循環資源の飼料利用が近年において注目されている2。2001年に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」では、食品循環資源の飼料化が再生利用の一つに位置づけられ、さらに2007年に公表された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」では、「飼料化は、食品循環資源の有する成分や熱量(カロリー)を最も有効に活用できる手段であり、飼料自給率の向上にも寄与するため、優先的に選択することが重要である(太字は筆者による)」と明示されるなど、政策的に食品循環資源を安価な飼料として活用することが推進されているのである。
2 2001年に公表された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」では、「食生活の多様化・高度化に伴い、生産・流通段階においては消費者の過度の鮮度志向等の要因により大量に食品が廃棄されるとともに、消費段階においては大量の食べ残しが発生し、多くの食品が浪費されている。(中略)一方で、土地利用の高度化、住民の環境への意識の高まり等を背景として廃棄物の処理施設の確保はこれまでにもまして困難なものとなってきており、最終処分場の残余容量のひっ迫等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化している」と、問題提起されている。
食品循環資源の飼料利用は、わが国に酪農・畜産が導入された当時より行われ、「カス酪」という言葉に代表されるように、副業的な酪農・畜産が中心であった1960年代前半まで一般的であった。したがって、近年における食品循環資源を飼料として利用する取り組みは、輸入飼料に強く依存した「加工型」酪農・畜産に内在する諸矛盾を、温故知新により克服しようとする取り組みと位置づけられよう。
事例とする奥田ゴールドファームグループは、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の施行以前より、食品循環資源の飼料利用に取り組むことで飼料費削減にはつながっていないものの、家畜ふん尿や稲わらなどのバイオマスの循環利用を通じて地域農業との連携強化と飼料の安定供給を図っている。環太平洋戦略的経済連携協定への参加が議論され、国内農業への甚大なる影響が懸念されることから、酪農・畜産を含めた地域農業を、経済的・環境的に持続可能なシステムへいかに再構築するかが喫緊の課題となっている。本稿では、食品循環資源をはじめとしたバイオマスの利活用という視点から奥田ゴールドファームグループの取り組みを捉え直すことで、この課題への接近を試みたい。
 |
「奥田の伊賀牛」 |
2.奥田ゴールドファームグループの概要
奥田ゴールドファームグループの中核となる奥田ゴールドファーム株式会社(以下「ファーム」とする)は、三重県伊賀市南部の中山間地帯に和牛肥育農場、名張市内に和牛繁殖農場を有する和牛繁殖・肥育経営である。両親より経営を継承した奥田哲也氏(有限会社奥田精肉店社長)によって2007年に設立され、現在は弟の奥田能己氏が社長を務めている。肥育頭数は500頭程度で、このほかに繁殖雌牛30頭と種牛1頭を有する、伊賀南部地域でもっとも飼養規模の大きい和牛繁殖・肥育経営となっている。従業員は能己氏を含めて6名で、能己氏と弟以外の4名は農外からの転職者であるが、現在はすべての従業員が肥育農場で個体管理まで担当している。このほかアルバイト1名(有限会社奥田精肉店の元従業員)と社長夫人が繁殖農場で給餌などを担当している。また、障がい者の雇用も計画されており、担当可能な作業の見極めが行われているところである。
 |
(有)奥田精肉店 社長 奥田哲也氏 |
奥田ゴールドファームグループの経済圏は名張市に属しており、別法人ではあるが、名張市内に精肉卸・販売及びレストラン事業を行う有限会社奥田精肉店(以下、「精肉店」とする)がある。同社ではファームから出荷される牛肉の全量を取り扱っている。従業員は哲也氏を含めて17名で、うち6名が卸部門に従事し、配送及び翌日配送分の仕込みを担当する。残りの11名が主に店舗での精肉販売事業及びレストラン事業に従事する。従業員のほかにパート・アルバイトが50名ほど雇用され、主にレストラン事業に従事している。年商は5億円程度で、うち90%が店舗での精肉販売事業とレストラン事業によるものとなっている。
3.経営継承と存続の危機−200円不足で不渡りの危機−
奥田ゴールドファームグループの特徴は、①繁殖・肥育事業と卸・販売事業がそれぞれ法人化されていること、②生産直売ではあるが法人・経営者とも異なること、③地域バイオマスの積極的な活用を図っていること、の3点に集約され、その目的は事業継続性の担保にある。具体的には、市中銀行からの融資を受けられる水準にまで経営の透明性を高め、意志決定を数値に基づき行うことと、顧客の信用を獲得すること=「奥田の伊賀牛」というブランド構築を図ることである。現在の事業概要を概観すれば、その目的に到達しつつあることは容易に推察されよう。ただし、そこに至る過程は順風満帆であったわけではない。むしろ両親から経営を継承した奥田哲也氏が直面した逆境がそうさせたといっても過言ではない。
(1)母親の顔で繋がっていた顧客
東京のステーキ・レストランでの修行を終えて経営を継承したのが1991年であった。1日当たり20万円の売り上げがあったが、店の看板であった母親が経営から退くと半減したのである。口座残高200円不足で不渡りの危機に直面した。母親の顔で顧客が来店していたことの脆弱さが露呈した結果であった。
経営者個人の「顔」ではなく、企業としての「ブランド」、すなわち「奥田の伊賀牛」により顧客を獲得し、それを担保するための農場部門における血統、飼料を含めた飼養管理体制の確立、販売部門における牛や肉について説明できる従業員の育成が経営を継承したばかりの若い哲也氏が取り組まなければならない課題となった。「肥育から販売までのすべての経営を継承したことで、ブランド構築において必要とされる条件に気がつくことができた」と哲也氏は振り返る。
幸いにして、後者については哲也氏の修行が功を奏することとなった。都市部富裕層を対象とするステーキ・レストランでの接客経験に基づき、自らが部位や肉質の特徴などについて積極的に顧客へ説明することを通じて、従業員の知識向上や接客姿勢の改善を図ってきたのである。ただし、2006年頃より哲也氏は第一線を退き、社長としての経営管理を主たる業務としている。哲也氏の「顔」ではなく、「奥田の伊賀牛」による顧客獲得・固定化に徹するためである。
(2)口蹄疫と飼料価格の上昇
ブランド構築においてもう一つの柱となる飼養管理体制、とりわけ飼料への着手は2000年に発生した口蹄疫と、ほぼ同時期からの飼料価格上昇を契機とする。前者については、中国産稲わらを中心とする輸入飼料が感染拡大の原因であったことから国内産への切り替えを、後者については食品循環資源の利用拡大を試みることとなったのである3。
食品循環資源の利用は、飼料費削減という点で注目されることが多いが、事例においては、飼料費削減ではなく、飼料の安定供給、ブランド構築において重要な意味を持つ。詳細については後述するが、国内産稲わらのほか、豆腐粕、酒粕やみりん粕など、そのまま食用として流通するだけでなく、国内産原料に由来する食品循環資源、すなわちMade in Japanの飼料を給与していることの安全性が「奥田の伊賀牛」というブランド構築に大きく寄与しているのである。
3 国際獣疫事務局(OIE)東京事務所によれば、「韓国と日本でのほぼ同時期の口蹄疫の発生は、中国から輸入された飼料が関与していることは否定できない」「口蹄疫の発生源がわら、乾草類のような動物用飼料であることが否定できない」としている。詳細は、OIE東京事務所プレスリリース「東アジアの口蹄疫に関するOIE緊急会議」2000年6月23日を参照されたい。
(3)グループ会社の設立
哲也氏が経営を継承した後、両親は農場及び精肉店の経営からは引退したが、給与などの軽作業には従事していた。しかしながら高齢となり身体的に作業負担が大きくなってきたことや、兄弟6人の今後の生活問題などから、それまでの経営のあり方を問い直す必要に迫られた。すなわち、生産直売システムを維持しながら、兄弟が安心して就農・就職できる経営環境を整えなければならなくなったのである。
既に哲也氏が経営を継承した段階で、農場部門と販売部門の経営は一応分離されてはいたが、経験や感覚に頼るのではなく数値に基づき経営判断を行うには十分ではなかった。換言すれば、利益管理が大雑把であるため、経営上の問題点が判明しにくい状態にあったのである。
こうしたことから、2000年中頃より農場の株式会社化が検討され、2007年に完全に別法人となる奥田ゴールドファーム株式会社が設立された。その後、弟の能己氏が経営を継承することで目的が果たされている。
4. バイオマスの活用
図2は、奥田ゴールドファームグループの取引関係を示したものである。以下では、食品循環資源、ふん尿・稲わらのバイオマスに注目して、その取り組み内容と意義について整理していきたい。
図2 奥田ゴールドファームグループ取引関係 |
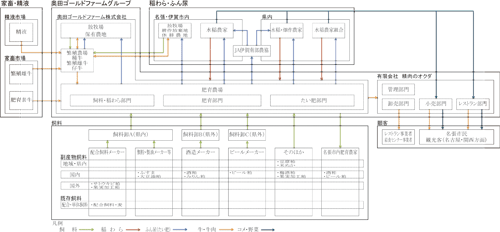 |
(1)多様な食品循環資源の飼料利用−経営問題への対応と次世代のための事業環境整備−
ファームの特徴の一つとして、多様な食品循環資源を自家配合して給与していることを指摘できよう。図表に示されるように、11種類にのぼる食品循環資源が利用されているが、ふすまや大豆粕など肉牛肥育において一般的な食品循環資源と、地域内から調達されるおからと米ぬかは経営継承以前から利用されてきたが、そのほかの多くの食品循環資源の利用は、2000年以降における飼料価格上昇を契機としている4。そこで以下では、利用経緯・目的と課題などについて整理していきたい。
<地域・県内>
豆腐粕は、繊維質及びタンパク質の代替飼料資源として給与されており、市内に立地する豆腐店より毎日ファームへ生状態で持ち込まれている。無償ではあるが、季節変動が大きく1日当たり60キログラム〜100キログラムまで変動するほか、水分含有率も変動するなど乾物計算が難しい食品循環資源となっている。また、腐敗性が高く、そのまま給与すると下痢をすることから、配合割合を少なくするとともに、搬入された当日中にサトウキビ粕(バガス)と攪拌して嫌気発酵させている。
米ぬかは、ビタミンEの代替飼料資源として給与されており、近隣の水稲農家から直接調達されている。脱脂されていないため粘度が高く、反芻能力が低下することから、配合割合は低く抑えられている。また、酸化が速く大量在庫が不可能な食品循環資源であることから、定期的に従業員が水稲農家へ引き取りに出向いている。しかしながら、必要量確保のために数戸の水稲農家から調達していることもあり、調達価格は一律ではなく、季節によって変動するという問題がある5。この問題は、後述するふん尿・稲わらの交換等を通じた地域農業との関係強化への展開とも関係している。
4 肉牛用配合飼料の農家庭先価格は下落傾向にあったが、2000年12月の36,004円/トンをボトムに上昇へ転じており、2004年9月には46,104円/トン(+10,100円、+28.1%)に至っている。その後は下落傾向に転じ、この価格水準を超えるのは2007年1月になってからである。数値は、農林水産省『ポケット農林水産統計』に基づく。
5 名張市の面積の50%以上が林地であるという地理的特性から、冬季は狩猟が比較的活発に行われている。猟師が罠のエサとして米ぬかを調達することから、価格の季節変動が大きい。
<国内>
酒粕とみりん粕は、マイロの成分に近いことからその代替飼料資源として給与されている。特に、みりん粕は糖度が高いことから、採食性向上も期待して給与されている。いずれも加熱・発酵済みであることから、保存性が高く、胃の負担も軽減されるほか、消化率の問題から加熱処理が必要とされる飼料用米やマイロを給与するよりも手間が省けるという利点がある。ただし、豆腐粕と同様に、水分含有量が変動するため乾物計算が難しい食品循環資源である。みりん粕については、みりん需要の関係から、供給量の季節変動が大きく、料理用調味液の普及から需要そのものが減少していることもあり、みりん需要と比較して安定している料理酒の粕を混合して対応している。
これら食品循環資源は、2000年頃より本格的に利用されるが、経営継承以前から取引関係のあった米穀・飼料卸との関係から、それ以前より過剰在庫を引き受けるかたちでスポット的に利用されてきた。本格的な利用に至った直接的な契機は飼料価格の上昇にあったが、酒粕やみりん粕の漬け物原料としての需要が減少し、在庫過剰が常態化したことにあった。
庭先価格は配合飼料の半額程度であるが、乾物重量に換算すれば配合飼料に対してそれほど優位な価格とはなっていないと考えられる。代替可能な飼料用米と比較しても同様である。それでもこれら食品循環資源が利用されるのは、加熱・発酵済みであることの利点に加えて、そのままでも食品として流通する食品循環資源であるという点にある。「奥田の伊賀牛」というブランド構築において条件となっていた、安全性を担保するためである。これは酒粕、みりん粕だけでなく、前述の豆腐粕や米ぬか、さらには後述する梅酒粕などの利用にも共通する。
 |
採食性が良くなる梅酒粕、まだ香りが残っており美味しそう |
梅酒粕は、酒粕やみりん粕と同様の発酵済みであることの利点のほか、アルコールを含むことから採食性向上と、破砕種によるルーメン活性化を目的に給与されている6。梅酒粕を給与することにより関西方面への販路拡大が可能となるとの勧誘を受けて主に酒造メーカーが会員の協会に加盟したことを契機に、2003年頃より本格的な利用をはじめ、加盟酒造メーカーから直接調達している。
このほかの国内産食品循環資源ではビール粕が利用されている。京都や神戸に立地する工場から飼料卸を経由して、脱水処理された水分含有率60%程度のビール粕を14本(500キログラムのフレコン)単位で2週間に1度の割合で調達している。庭先価格はキログラム当たり20円程度であるが、これが許容できる上限であり、これ以上になれば費用面で折り合いがつかない価格となっている。また、長期的な景気低迷にともなうビール需要低迷と、酒税法改正以降の麦芽を使用しない第3のビール需要の増大により、ビール粕そのものの供給量も減少する傾向にあるため、従前と同水準での量的・価格的安定供給を期待することが困難な状況にある。この予兆はすでにビール粕の調達経路構築の際に発現している。すなわち、ビールメーカーからの直接調達を試みた際に、既存需要者から供給量の減少を懸念して反発を受けたのである。したがって、ビール粕を利用しながらも、これに代替する飼料資源の確保がこれからの課題となってこよう。
6 梅酒粕の飼料特性および飼料化の経緯については、小野誠「梅酒つけ梅の有効利活用を図って作出されたブランド牛 大阪ウメビーフ」社団法人全国肉用牛振興基金協会『びーふキャトル』第5号、p23−p26、2006年を参照されたい。
<国外>
国外から調達される食品循環資源は、サトウキビ粕(バガス)と果実加工粕で、繊維質と採食性向上を目的として給与されている。取り扱いロットや輸入に関わる事務手続き問題から独自に調達することが極めて難しいことから、飼料卸を経由して調達している。
いずれも国内の産地から直接調達が可能な食品循環資源であり、それらを大量に排出している沖縄県から独自に調達して利用を試みたが、水分含有率の高さから物流コスト負担が大きく、経営として許容できない水準(庭先価格キログラム当たり50円)であったばかりか、カビの発生もあって利用を中止せざるを得ない状況となっている。ただし、果実加工粕を排出する缶詰工場は通年稼働しているため量的な季節変動も少なく、また需要を満たすだけの供給量もあることから、国内産飼料資源をブランド構築の柱に据える奥田ゴールドファームグループにおいては、現地での乾燥技術確立による調達コスト削減とカビ防止が次なる課題となっている。
以上のように、食品循環資源利用拡大の契機は、2000年以降における飼料価格上昇への対応にあったが、同時に飼料の安全性を訴求することによるブランド構築の柱ともなっていったのである。だが、目的は自己の経営問題への対応だけではなく、以下の2つで確認される次世代のための事業環境整備にもある。
1つは飼料問題で畜産に携われない次世代を生み出さないことである。すなわち、輸入飼料に強く依存した畜産が安定的に継続できない状況なのに対して、食品循環資源をはじめとする低・未利用資源を徹底的に活用した畜産の確立を図ることである。すでに近隣の若手肥育経営者に対して、配合設計の教授だけでなく、一部の食品循環資源について供給を行っている。また、ファーム従業員の独立も視野に入れた従業員教育が行われているのである。
2つは脆弱化する繁殖経営への間接的な支援である。肥育素牛市場における標準的な体重は10カ月齢で300キログラムとされているが、実際にはそれ以下の肥育素牛も出荷され、市況や体重によっては買い手がつかない場合もある。これを積極的に購入することで繁殖経営を支援しようというのである。すなわち、300キログラム前後を前提として設計された配合飼料では、当然ながら20カ月の肥育期間において十分な増体は期待できないが、酒粕類(酒粕、みりん粕、梅酒粕)、サトウキビ粕、果実加工粕など、ファームで給与される食品循環資源の多くが採食性向上を目的としている。採食性の高い自家配合飼料を給与することで、最終的には標準的な肥育素牛と遜色ない水準で出荷することが可能となっているのである。ファームでは200キログラム程度の肥育素牛でも導入できるという。一般的な配合飼料を給餌した場合と比較して1日当たり3キログラムほど飼料消費量が増加するため、標準的な肥育素牛より安価に仕入れたとしても、その差額がそのままファームの事業収益とはならないが採食性の高い食品循環資源利用との相乗効果によって採算性向上にも貢献している。
(2)家畜ふん尿の土壌還元と稲わら利用−経営外部における変動要因排除と耕種部門との共生−
家畜ふん尿処理の問題は、経営内部に還元する土地、飼料生産基盤をほとんど有していない、あるいは有していても飼養規模と比較して狭隘なわが国の酪農・畜産経営に共通する問題である。これは同時に、粗飼料調達問題にも関係していることは周知のとおりである。
水分調整後で1日当たり2トンの家畜ふん尿由来たい肥が発生するファームもこの例外ではない。このため、土壌還元先として、また粗飼料である稲わら調達先(無償譲渡)として水稲農家との関係強化を図っている。ファームに設置したたい肥盤で完熟たい肥化され、稲わら調達先である水稲農家へ無償譲渡されている。受け入れ先である水稲農家における労力問題から、譲渡に際してはファームの従業員も運搬・散布作業に従事している。ただし、水稲農家へのたい肥譲渡は稲刈り後の晩秋から初冬に集中するため、たい肥保管問題から水稲農家以外の供給先が必要となる。ファームでは、県外の畑作農家へ春野菜収穫後に供給するほか、系統への販売委託などによって在庫の解消を図っている。
輸入稲わらから国産稲わらへの転換の契機が2000年に発生した口蹄疫にあったこと前述のとおりである。このとき、流通する国内産稲わらではなく、水稲農家からの直接調達としたのは、ブランド構築のために、ファームが直接関与することで稲わらの安全性をより高い水準で担保するほか、経営外部における変動要因を極力排除することにあった。口蹄疫の影響で稲わら輸入が停止された際に、多くの和牛肥育経営がその代替粗飼料として乾牧草を給与した結果、脂肪への色素沈着による枝肉価格下落の影響を受けたが、全量を水稲農家から直接調達していたファームはこの問題を回避することができたのである。
水稲農家から稲わらを直接調達するため、ファームでは2000年代前半に、トラクター、ロールべーラー、ユニック車(4トンロング)を500万円かけて購入している。初年度は600ロールを哲也氏と能己氏の2人で収集したが、現在では従業員がそれに従事することで1600ロール(水田15ヘクタール分)まで増加している。この結果、4年前から全量がこの経路で調達された稲わらとなっているのである。調達先は主にファームから40キロメートルほど離れた水稲農家組合となっている。これは、耕地面積及び一筆当たり面積が大きく、作業効率が高いためであるが、他方で輸送に関しての人的・費用的・時間的負担が大きくなる課題を有している。名張市内の水稲農家からの調達も検討されているが、面積が狭く作業効率の低さから、本格的な調達には至っていない。
 |
ファーム指導担当のJA伊賀南部、井上大輔氏(右) |
たい肥との交換であることから稲わらは無償で譲渡されている。また保管場所もファーム内の建屋であることから必要経費は低位に抑えられ、キログラム当たり25−30円で調達している計算となる。これはほぼ中国産稲わらと同様の水準で、国内産流通稲わらと比較すれば10円以上安価に調達していることになる。ただし、稲わらとたい肥の交換(以下、「稲堆交換」という)に基づく無償譲渡であることから、たい肥化及び運搬・散布までの費用を含める必要があり、この価格以上の負担となっているのは確実である。しかしながら、稲堆交換以外の経路でたい肥販売をしても採算性確保が極めて困難である現状を勘案すれば、家畜ふん尿処理と稲わら調達において稲堆交換が全体としての費用負担がもっとも低位となるだけでなく、確実にたい肥が土壌還元される方法となっている。
稲堆交換は水稲農家においても経済的に優位となっている。すなわち、運搬・散布において労力が必要となるが、ファームからの人的支援を受けることでその負担が軽減されるばかりでなく、無償で完熟たい肥を調達することができるが、各種肥料価格が高騰する現状では、その節減効果も高くなっているのである。また、稲堆交換から発展して水稲農家のコメが精肉店で販売されるに至っている。つまり、近隣に存在する耕畜相互が自己の存立基盤になっており、共生関係にあると言っても過言ではない。
 |
近隣の水稲農家から稲堆交換で調達した稲わら |
5.繁殖部門への展開−耕作放棄・遊休農地の活用−
繁殖雌牛の導入は、2005年に繁殖農家が手放した経産牛を肥育牛として導入したことを契機とする。繁殖能力が高く、また現在繁殖農場となっている旧農場があるばかりでなく、能己氏が人工授精師の資格を有していたこともあって、実験的に繁殖雌牛として導入したのである。現在では30頭の繁殖雌牛を導入しているが、完全な一貫経営のためではない。年間に300頭程度の肥育素牛を導入しているが、同一産地の肥育素牛であっても肥育成績に個体差があることへの疑問について、和牛生産のすべてのプロセスを管理することから解明しようと試みているのである。
また、種牛が1頭飼養されているが、これも種牛を目的として導入されてはいない。導入した繁殖雌牛が妊娠していた子の血統が良く、その父牛が死亡したことから、優良な種牛になる可能性に期待して飼養しているのである。種牛として登録されており、これまで3頭出荷しているが、統計的な裏付けがとれる段階ではないため、あくまで従業員教育を兼ねた実験的な段階にとどまっている。
 |
奥田ゴールドファーム(株)社長 奥田能己氏 |
このように繁殖部門は、主に従業員教育を兼ねた牛への理解のために展開されているが、耕作放棄・遊休農地対策としても機能している。現在、年間20頭の子牛が産出されているが、その放牧・採草地として耕作放棄地・遊休農地(4反×3カ所)を無償で借り入れているのである。荒れた耕作放棄・遊休農地を農地として再整備し、そこへたい肥を投入して放牧・採草地として利用することで、子牛育成費を節減しているのである。同時に、家畜ふん尿の土壌還元先確保としての意味があることも重要といえよう。
ここで面白いことが起きている。耕作放棄・遊休農地の所有者が、放牧・採草地として再生した農地をみて、農業をもう一度やりたいと言うのである。その場合、所有者へ返却して一からやり直しとなるのだが、能己氏は「地域で農業をする人が増え、耕作放棄・遊休農地が減るのならそれが一番良いこと。耕作放棄・遊休農地を放牧・採草地として再整備するのは、その意味の方が強い」という。逆説的ではあるが、次の放牧・採草地の候補に困らないほど耕作放棄・遊休農地がこの地域には多いということでもある。
6.おわりに
奥田ファームグループでは、農場の株式会社化によって、新規学卒者や転職者に対して、就労先としての選択肢を提供してきたほか、バイオマスの利活用により次世代のための事業環境整備を図ってきた。これらに加えて、児童・学生(中高生)に対して、総合学習の時間などで畜産に対する理解の醸成を図っている。事業者としての社会貢献の側面もあるが、農家子息でなければ農業ができないという認識の払底、換言すれば新しい担い手の発掘も目的としている。つまり、その取り組みは、自己の経営問題への対応を超えて、地域農業の再生にまで向けられているのである。
奥田ファームグループの取り組みは、自己の畜産経営のみならず、耕種部門を含めた地域農業全体を、経済的・環境的に持続可能なシステムへ再構築しようとするものと位置づけられ、これからの地域農業のあり方を示唆している。その取り組みの根底には、地域農業・経済の存在が自己の存立基盤であり、単独では展望を見いだせないとの問題意識があるが、それ故に、地域農業・経済に対する危機意識も強く、課題は山積しているという。
 |
市役所でのバイオマス推進協議会へ向けた打ち合わせ |
この詳細については紙数の都合から別の機会に譲らざるを得ないが、本稿のおわりにあたり、二人の若手経営者が指摘する地域農業・経済全体としての課題を紹介しておきたい。すなわち、肥育農家、水稲農家、果樹農家、農協、商工業、行政などが問題解決のために個々に取り組むことの限界を認識し、関係する各主体の組織横断的な対応に基づく解決策の有機的な結合・実施にあるという。若干の説明を加えるならば、個別的課題についての解決策は、これまで蓄積された情報・経験や支援施策などですでに準備されていることから、各主体、とりわけ個人及び一事業者において隘路となる費用対効果や人的資源等に起因する制約を、地域内の多様な主体が直面する課題と解決策を組み合わせることで克服することが課題となるのである。
そして、二人が独自に克服を試みてきたなかでの失敗と挫折に裏付けられたこの課題に対して、行政が着手するという明るい胎動にも触れておかなければならない。
2010年1月に名張市はバイオマスタウン構想を公表し、バイオマスを活用した経済的・環境的に持続可能な地域経済の再構築を推進しているが、その推進協議会には農林業関係者だけでなく、商工業関係者、市民、行政が参画しているのである。構想実現にむけての調整が図られるこの推進協議会と、その下にテーマごとに組織され、具体的な課題析出と解決策が検討される部会が、組織横断的な対応のための問題意識・情報共有と話し合いの場となっているのである。二人の若手経営者の地域農業・経済に対する強い危機意識と問題意識が共有され、経済的・環境的に持続可能な地域経済の再構築にむけた第一歩が踏み出されることを期待せずにはいられないのである。
謝辞:有限会社奥田精肉店社長・奥田哲也氏、奥田ゴールドファーム株式会社社長・奥田能己氏、伊賀南部農業協同組合肉牛部会長・山崎祥生氏、伊賀南部農業協同組合・井上大輔氏、名張市産業部監事・柳嶋正範氏、名張市産業部産業政策室・荻田匡嗣氏には、大変お世話になった。心から御礼申し上げたい。