【要約】
肉用種の流通において、そのスタートに位置する繁殖経営の収入は子牛の販売に依存している。そのため、子牛価格の変動は繁殖経営者始め流通に携わる者には大きな意味を持つものである。そこで本稿では、ここ20数年間の子牛価格(黒毛和種)の推移を追っていくことで、価格に影響を及ぼしてきた要因を分析した結果、自由化以降の子牛価格は、子牛の生産・流通における需給関係のみではなく(内部要因)、輸入量や飼料価格などの外部要因の影響を大きく受けていると考えられる。
1.はじめに
子牛価格は、飼養頭数と連動しタイムラグを伴う7年程度の周期で変動するビーフ・サイクル(キャトル・サイクル)で、かつては説明されてきた。しかし、平成3年度の牛肉輸入自由化により輸入牛肉が国産牛肉の価格形成に影響を及ぼしてきたこと等が要因で、この周期変動は無くなったとも言われている。
そこで、本稿では肉専用種の太宗を占める黒毛和種に着目し、その価格形成に影響を及ぼす要素を洗い出し、自由化以降の価格の推移を検証しながら、肉用子牛の価格形成要因について分析をすることとする1 。
図1 ビーフ・サイクル |
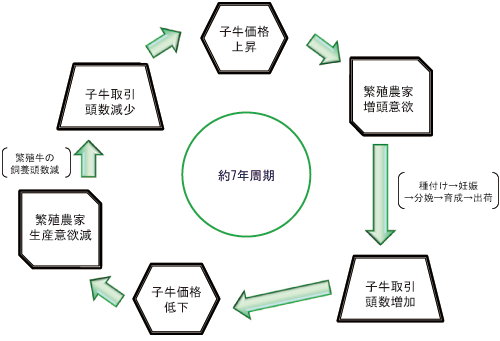 |
1 本稿での分析対象は黒毛和種であり、以降特に断りの無い場合は肉用子牛は黒毛和種を指す。
2.枝肉価格の影響を受ける子牛価格
肉専用種の流通経路は図2のとおりで、繁殖経営、肥育経営という2経営体と子牛市場、卸売市場の2市場を経由する。経営体には、子牛生産を主目的とする繁殖経営、もと畜を購入して肥育することを主目的とする肥育経営、子牛生産と肥育を同一経営体内で行う一貫経営があるが、日本において一貫経営の割合は少ない。また、子牛市場の取引形態は市場取引と相対取引がある。乳用種や交雑種では相対取引の割合が多いが、肉専用種では市場取引が主といわれており、実際独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の調査でも黒毛和種では9割の肥育経営者がもと畜を家畜市場から導入しているという結果であった。よって、肉専用種の流通経路は図2の市場取引経由の形が一般的であり、肉用子牛の価格を考える場合はここがポイントとなる。
図2から分かるように、家畜市場の供給者は繁殖経営者であり、需要者は肥育経営者である。しかし、肥育経営者は食肉卸売市場等では供給者という側面も持つ。つまり、卸売市場での枝肉価格が肥育経営者を通じて子牛価格にも影響を与えるという構造となっている。
図2 肉用牛の流通経路 |
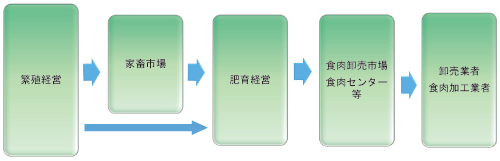 |
|
肉専用種の食肉卸売市場での取引割合は約45%で、その他は食肉センター等を通じた相対取引(市場価格を参考)となっている。
|
3.自由化以降の子牛価格の推移と変動要因
図3は、平成3年度の牛肉自由化以降の黒毛和種(去勢)の子牛価格と取引頭数の推移である。ここでは、価格の傾向から期間を4期に分類し、その要因を分析する。なお、価格、取引頭数とも季節変動があり、傾向を見るに当たってはこれを考慮する必要があることから、図では季節調整前と季節調整後(図3中の、橙、桃、青色の線)の推移を表し、季節調整にはセンサス局法X-12-ARIMA2を用いた。
2 センサス局法とは、米国商務省センサス局が開発した季節調整法であり、現在日本銀行を含むほとんどの官公庁で採用されている季節調整法である。X-12-ARIMAバージョンは現在米国センサス局HPで公表されている。
|
図3 子牛価格と取引頭数(黒毛和種、雄)及びと畜頭数(めす和牛)の推移 |
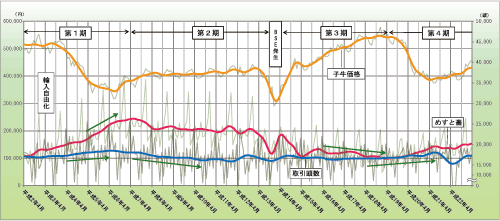 |
|
資料:独立行政法人 農畜産業振興機構 肉用子牛の取引頭数と価格、月別肉用子牛取引状況表 (黒毛和種) 農林水産省 「畜産物流通統計」 |
(1)牛肉自由化から平成6年度まで
図4 子牛価格変化の要因(自由化〜平成6年度) |
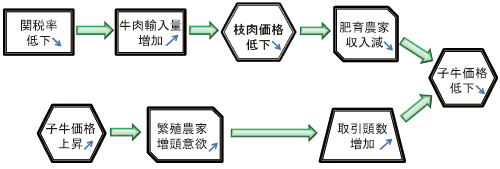 |
表1 牛肉の関税率の推移 |
 |
平成3年度からの牛肉自由化の影響を受けて、平成3年度に平均51.1万円であった黒毛和種雄の子牛価格は平成6年度には平均で36.4万円まで急激に下落する。この背景には、図4のような流れがある。自由化により平成3年度に70%だった関税率は、平成5年度には50%となった(その後ウルグアイラウンド農業交渉を経て、平成7年度から段階的に下がり、平成12年度には現行の38.5%となっている。(表1参照))。それに伴い、平成3年度32.1万トンだった牛肉輸入量は増加し、平成6年度には57.9万トンとなった。牛肉自由化の影響は輸入牛肉と品質面で競合する乳用種だけでなく肉専用種にも表れ、格付けの低い牛肉の卸売価格から低下していく。図5は平成2年度以降の牛肉輸入量と枝肉価格の推移である。自由化(平成3年度)前後の年度(平成2年度→平成4年度)で枝肉価格を比較すると、A-3は16.9%、A-4が9.2%低下しているのに対し、A-5は1.5%しか下がっておらず、この時点でA-5には大きな影響は出ていないものの、A-3には明らかな影響が見られる。しかし、平成6年度では、同じく平成2年度比でA-3が21.5%、A-4が14.6%、A-5が3.9%低下している。ここから、自由化の影響はA-5よりもA-4、さらにA-3の枝肉価格に早くかつ大きく影響が現れたことが分かる。(なお、A-3、A-4の枝肉価格は平成7年度を下限としてその後上昇していくが、A-5価格は平成8年度まで低下する。)枝肉価格低下の影響は、肥育農家の収入減少に繋がり、自由化以降子牛価格も低下することとなった。また、子牛の取引頭数(黒毛和種雄)は、平成3年度から平成6年度にかけて増加した(平成3年度の取引頭数20万7005頭。平成6年度の取引頭数22万124頭。)この時期に出荷された子牛は、子牛価格の高かった平成2年度、3年度に種付けされたものであるが、輸入量増加の影響に加え取引頭数の増加が子牛価格の低下を更に大きくしたとも考えられる。なお、平成6年度第1四半期と第2四半期に、黒毛和種において初めて肉用子牛生産者補給金が交付されている。
図5 牛肉輸入量と枝肉価格(去勢和牛)の推移 |
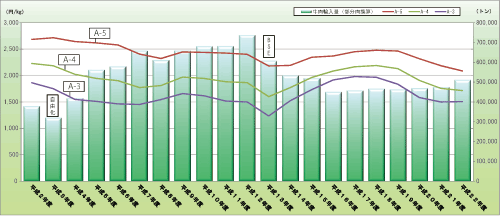 |
資料:財務省「貿易統計」、農林水産省「畜産物流通統計」より算出 |
(2)平成7年度から平成13年度まで
一時は30万円台前半まで下げた子牛価格であるが、平成7年度以降持ち直し、平成13年9月の日本でのBSE発生の前まで40万円前後で推移する。この背景としては、子牛価格が下がったことにより、繁殖農家は経営を縮小、または離農という形をとり取引頭数が減少したことがある。子牛価格の低下が始まる平成3年10月のめす和牛と畜頭数が1万9791頭に対して平成7年10月は2万5428頭とおおよそ30%増加している。めす和牛のと畜頭数には、繁殖めす牛以外の肥育牛も入っているが、農林水産省「畜産統計(肉用牛調査)」によると子取り用めす牛飼養頭数は平成5年度をピークに以降減少していることから、この時期のと畜頭数の増加の主要因は繁殖めす牛のと畜と考えて良いと思われる。と畜頭数の増加、つまり繁殖経営の縮小により、国内の子牛生産頭数が減少(取引頭数の減少)となり、自由化以前までには及ばないものの、子牛価格は持ち直すこととなった。
しかし、ビーフ・サイクルを考慮すると、価格にはピークと谷が現れるはずであり、平成6年度に谷を示した子牛価格は平成9年度〜10年度付近にピークが現れると推定されるが、この期間の価格は大きな変動なく推移している。その要因としては輸入量の増加による枝肉価格の低下及び飼料価格の上昇による肥育経営の収益性悪化という、子牛の取引価格の形成にマイナスの事象があったことによる。牛肉の輸入量は、腸管出血性大腸菌О-157による食中毒などの影響で消費が減退した平成8年度を除き、増加傾向にあり平成12年度は65.8万トンでピークに達した(図5)。また、配合飼料価格も米国産とうもろこしの大幅減産や円安等の影響で平成7年10月以降、平成8年度まで高水準で推移した。つまり、この時期に価格のピークが現れなかったのは、取引頭数の減少による価格上昇期に肥育農家の収益性の悪化が価格上昇にブレーキをかけた形になったと推察する。このような状況の中、平成13年9月日本でBSEの発生が確認され、枝肉価格、子牛価格ともに暴落することとなった。
図6 子牛価格変化の要因(平成7年度〜平成13年度) |
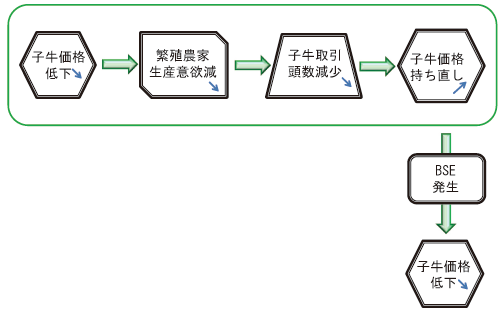 |
(3)平成14年度から平成18年度まで
平成14年度はBSEの影響からの回復がみられ、枝肉価格・子牛価格ともに平成14年度半ばにはBSE前の水準に戻っている(平成14年10月黒毛和種雄42.5万円。BSE前1年平均比102%)。実際この時期の肉専用種に対する肉用牛肥育経営安定対策事業(通称「マルキン」)の発動は、平成14年度第2四半期で終わっている。平成14年から平成19年は“いざなみ景気”の時期にあたり、かつてのバブル景気には及ばないものの、景気の回復がみられた時期である。さらに、平成15年12月に米国でのBSE発生を受け、米国産牛肉の輸入が禁止されるとともに、国産牛肉への志向が高まった影響で、枝肉価格が上昇、それに伴い子牛価格も上昇し、平成18年12月の子牛価格は57.9万円とピークに達した。
図7 子牛価格上昇の要因(平成14年度〜平成18年度) |
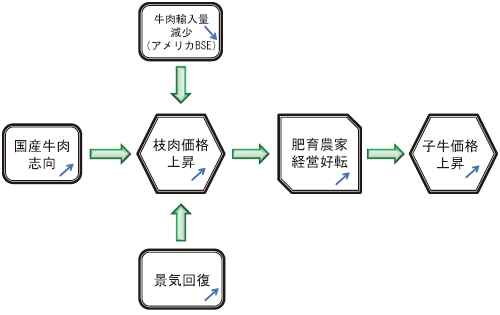 |
|
|
(4)平成19年度から平成22年度まで
子牛価格が上昇傾向で推移する中、平成17年3月に出された「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」にも見られるように、国の国産牛増頭政策に基づいて各種の支援事業が行われたことも加わり、繁殖経営は拡大傾向へ移行し、その結果取引頭数は徐々に増加していく(平成19年4月取引頭数1万6356頭。平成21年4月取引頭数1万7336頭。)。他方、景気の後退による枝肉価格の下落(平成22年4月枝肉価格 「A-3」1,586円/kg 19年4月比82.6%、「A-4」1,841円/kg 同比85.3%、「A-5」2,260円 同比92.4
%)、さらに平成18年10月からとうもろこしの国際相場が高騰したことによりこれまで5万円/kg前後で推移していた配合飼料価格が平成20年12月には7万3500円/kgまで高騰した。それにより肥育農家の経営は収入と支出の両方面でマイナスの影響を受けた。子牛価格は、取引頭数増加による価格の低下以外にも肥育農家の経営の悪化という二重の低下要因を受け、平成21年6月には37.5万円と平成13年の国内のBSE発生時以降の最低値を記録した。その後、子牛価格の低迷が要因と考えられる、めす牛のと畜頭数の微増が見られ、子牛価格は若干の回復を見せてきた。平成22年度は、4月に宮崎県における口蹄疫の発生により取引頭数、価格ともに一時的に低下したが、口蹄疫の終息とともに価格は回復傾向を見せ始めた。
図8 子牛価格変化の要因(平成19年度〜平成22年度) |
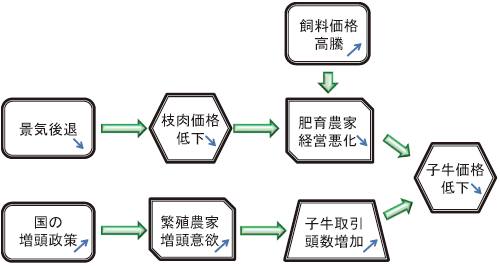 |
〜繁殖経営の構造変化が進展〜
繁殖経営の縮小は、5頭未満飼養の小規模経営の離農や兼業農家の畜産業廃業という要因が大きかった。図9は子取り用めす牛飼養頭数と飼養戸数の推移を表している。飼養頭数は、平成5年をピークに年々減少し、平成18年には最低となったが、価格上昇により繁殖農家の増頭意欲が増し、国の増頭政策も加わったことから、増加している。
一方で、農家戸数は、平成元年以降減少の一途をたどっている。つまり、最近の頭数増は既存農家の規模拡大が大きく、現に平成22年の頭数規模別飼養戸数の割合をみると、日本の繁殖経営において大きな割合を占めてきた5頭未満の農家は大きく減少し、それ以上の規模の農家の割合が増えている。また、全体に占める割合は2.5%と少ないものの、50頭規模以上もかつてと比べるとその割合は大きくなってきている(図10)。これは、従来の経営が兼業・副業的な経営から変化してきていることを示している。
図9 子取り用めす牛飼養頭数及び戸数(H1〜H22) |
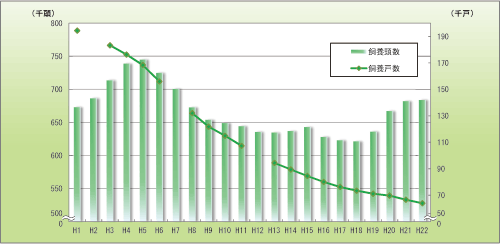 |
資料:農林水産省「畜産統計 肉用牛調査(平成1〜平成22年)」 ※H2,7,12年についてはセンサス年のため基本統計なし。 |
図10 子取り用めす牛飼養頭数規模別飼養戸数(全国) |
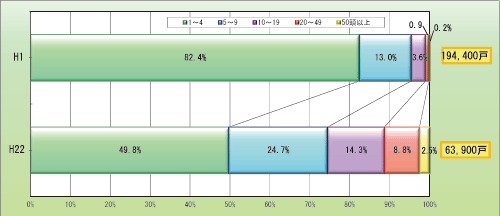 |
資料:農林水産省「畜産統計 肉用牛調査(平成1年、平成22年)」 |
4.肥育経営の収益性からみた子牛価格
これまで述べてきたとおり、子牛価格には肥育経営の動向が大きく影響してくることから、ここでは肥育経営側から見た子牛価格を分析していくこととする。
(1)肉用牛肥育経営の収益
肉用牛肥育経営は、繁殖経営からもと畜を導入し、約20か月肥育した後に肥育牛として食肉卸売市場等で販売する。去勢若齢肥育牛1頭当たりの粗収益は84万246円で、そのうち肥育牛の売却による収入が82万9297円と98.7%を占めている。堆肥等の副産物の販売による収入は、1万949円と限定的である(平成22年度農林水産省「農業経営統計調査(畜産物生産費)」以下、「生産費調査」という。)。したがって、収益は枝肉価格の動向に大きく左右されていることから、一般的に肥育農家は、肥育牛1頭当たりの収益を増加させるために、(1)枝肉価格の動向を見て、需要期に多く出荷できるよう生産を調整する、(2)枝肉格付等級の高い肥育牛を生産し、枝肉単価を高める、(3)枝肉重量の大きい肥育牛を生産し、1頭当たりの販売価格を高める、などの努力を行っている。(2)肉用牛肥育経営の費用
生産費調査によると平成22年度の去勢若齢肥育牛1頭当たりの費用は85万6542円(支払利子・地代を除く。)であり、うち物財費が78万2412円と91.3%を占める。なお、所得は4万1596円で、もと畜費が減少したこと等により3年ぶりに黒字になった。図11 肉用牛肥育経営の所得の推移(肥育牛1頭当たり) |
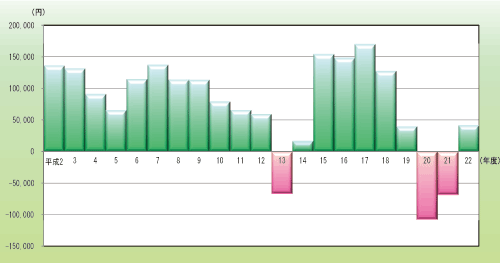 |
|
資料:農林水産省「農業経営統計調査 畜産物生産費」 |
費用の内訳では、もと畜費が全体の51%を占めており、飼料費の32%と合わせて全体の8割を超えている。費用の額はもと畜費の動向に左右されるが、近年、飼料費の増加により、もと畜費の割合が減少し、飼料費の割合が大きくなってきている。
図12 肉用牛肥育経営の費用の内訳 |
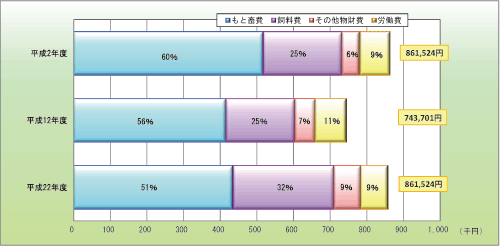 |
|
資料:農林水産省「農業経営統計調査 畜産生産費」 |
生産コストの低減を図る上で、もと畜費及び飼料費の削減は効果的である。しかし、血統を重視したもと畜や育種価の高いもと畜を導入することは、肥育牛の販売価格を上げるための一つの方法であり、もと畜費を一概に削減できるものではない。また、飼料費については、無駄のない飼料給与、疾病、事故等の抑制による飼料効率の向上などが取り組まれている一方で、収益を求めるには肉質と枝肉重量を確保しなければならず、飼料給与量を単に削減することは困難な面もある。
このような中、肥育経営では、牛個体ごとにもと畜の血統、育種価等と販売時の枝肉の成績及び販売価格とを比較し、より利幅が大きくなるもと畜の条件を検討したり、飼い直し等の必要がなく肥育しやすいもと畜を生産している繁殖経営から導入する等の努力がされている。
(3)もと畜購入可能額と子牛価格の比較
肥育経営1万1700戸(平成22年農林水産省「畜産統計」)のうち、一貫経営である2,400戸以外の経営では、外部からのもと畜の導入は不可欠である。一般に肥育経営では、肥育牛を販売した収益を肥育途中にある牛の飼料、労働費等に割り当て、その残額をもって次のもと畜を導入することになる。そこで、毎月の枝肉価格(和牛去勢・卸売市場平均)から毎月のもと畜費以外の飼料費・労働費等の費用(生産費調査)を差し引いた額を、現金ベースでの当月のもと畜購入可能額として算出し、これと実際の子牛価格(黒毛和牛・雄)とを比較した。なお、ここでは現金ベースで比較することを主眼と置くため、季節変動は考慮しない。また、マルキン及び配合飼料価格安定制度の補てん金は含まない。
自由化以降、もと畜購入可能額と実際の子牛価格を比較すると、BSE発生の影響時期を除き、4つの時期に分けることができる。
第1期平成6年12月までの期間は、牛肉自由化により枝肉価格が低下していったため、もと畜購入可能額も下降傾向にあった。しかし、子牛価格も同様に低下傾向で推移していたことから、子牛価格はもと畜購入可能額を下回って推移しており、肥育経営にとっては、収益性の低下をもと畜費に転嫁できた時期と言えるだろう。もと畜購入可能額と実際の子牛価格との差は、肥育経営の利潤のほか、販売手数料、肥育期間中の事故によるコスト増分等に相当すると考えられる。
第2期
平成7年1月から平成13年のBSE発生までの時期は、もと畜購入可能額と実際の子牛価格とが拮抗して推移している。平成6年から7年にかけては、枝肉価格は引き続き低迷しており収益は少ないものの、この時期に販売した肥育牛は子牛価格が低い時期に導入したものが多く、枝肉価格が下げ止まったことにより、販売された肥育牛1頭当たりの所得は回復している。このため、もと畜の導入意欲が高まったとみられ、子牛価格も回復し始めている。肥育経営にとっては、収益が限られるものの将来の枝肉価格を考慮し、一定価格のもと畜を導入していたとみられる。
第3期
BSEによる枝肉価格の低迷が落ち着いた後、平成20年3月までは、景気回復、と畜頭数の減少、米国産牛肉の輸入停止などにより、枝肉価格が上昇し、堅調に推移している時期である。そのため、肥育経営では、収益の増加に従い、もと畜購入可能額も上昇した。子牛価格も枝肉価格と同様に上昇傾向を示したが、もと畜購入可能額を上回ってはいない。
第4期
平成20年4月以降は、景気低迷により枝肉価格が下降したことに加え、世界的な穀物価格の上昇により飼料費が上昇している。生産費調査によると飼料費は、平成18年度の23万2738円から平成20年度には33万5141円と大幅に上昇しており、10万円以上の生産コストの増加となった。平成20年3月から7月にかけて、もと畜購入可能額、子牛価格ともに大きく下降し、両者はそれ以降再び拮抗して推移している。
以上のもと畜購入可能額に関する動向を踏まえると、各時期の区切り目は、生産費調査による肥育牛1頭当たりの所得が大きく変動する時期と前後している。第1期と第2期の境は、平成5年まで減少傾向にあった所得が、平成6年から7年にかけて回復した時期に当たる。また、第2期と第3期の境に当たる平成13年、第3期と第4期の境に当たる平成20年には共に所得が大きく落ち込んでいる。このことから、肥育経営の所得水準の変化が、もと畜購入の判断の目安等に変化が生じるきっかけになっているといえよう。
また、BSE発生による影響の大きい時期を除くと、もと畜購入可能額が40万円以上で推移している時期には、上昇期であれ下降期であれ、子牛価格を上回る傾向にある。一方で、40万円前後まで下がると、子牛価格と拮抗しており、現金ベースでの利益を確保した経営が出来ていないとみられる。しかし、肥育経営としては、そのような厳しい経営状況の中でも、将来の販売価格を考慮し、40万円前後を経験的に子牛価格の底値、即ち、経営の継続が可能であろうと考える限界の水準と捉えて行動していると推察できる。
図13 肉用牛肥育経営におけるもと畜導入可能額の推移 |
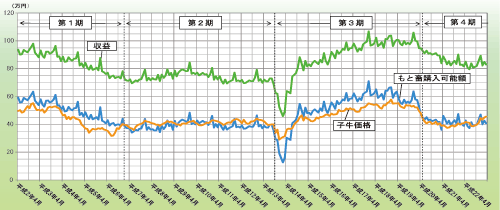 |
|
資料:独立行政法人農畜産業振興機構 肉用子牛の取引頭数と価格 農林水産省「農業経営統計調査 畜産物生産費」「畜産物流通統計」より算出 |
5.子牛価格の形成要因
これまで見てきたように、子牛の価格は、諸々の要素によって変動し、形成されていることが分かった。これらの要素は、肉用子牛の生産・流通の中にある内部要因とそれ以外の外部要因に分類できる(図14)。牛肉自由化以降、子牛価格は、内部要因のみならず外部要因の影響を大きく受けるようになってきた。自由化以降の子牛価格の低下は、輸入量の増加という外部要因が、平成19年度以降の低下は、平成18年度の飼料価格の高騰という外部要因が、子牛価格に下降圧力を与えた結果と考えられる。
また、BSE発生前の子牛価格は、牛肉輸入量の増加という外部要因が影響を与えたと考えられることは、既に述べたとおりである。逆に、BSE発生後は、輸入量の減少、景気回復等の外部要因が子牛価格の上昇を後押しし、最高時には60万円に迫る価格となったと推測する。このように、自由化後の肉用子牛価格を形成する要因は外部要因の大きさがそれまでの価格の変動でみられたビーフ・サイクルを打ち消していると考えられる。
平成22年度以降、子牛価格は上昇傾向にある。外部要因として、飼料価格や景気変動が子牛価格に影響を与える要因として存在する。さらに、新たな外部要因として原発事故の影響も挙げられ、今後これらがどう影響を与えていくか、注目していきたい。
図14 子牛価格に影響を与える内部要因と外部要因の関係 |
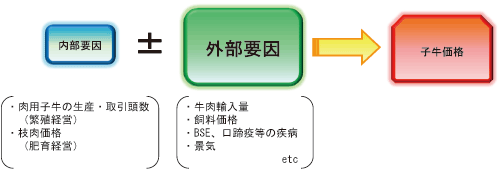 |