【要約】
オホーツク海に近い中標津町の冬は厳しく、時には零下30度にも達する。そうした中で、養老牛山本牧場は通年24時間の完全放牧酪農を行っている。初年度こそ若干の問題が起きたものの、次年度からは完全放牧に伴う問題はほとんど起きていない。更に、飼料は濃厚飼料の給与ゼロ、ほぼ100パーセントの自給粗飼料(牧草)に挑戦している。1頭あたりの年間乳量は4,500キログラムほどに減少したものの、生産される牛乳には言いようのないうま味が込められており「1ミリリットル1円」の牛乳として飛ぶように売れ、またアイスクリームやチーズなど新たな商品の開発や地域振興などへと繋がっている。
1.はじめに
ホルスタイン種の飼養で濃厚飼料の給与ゼロ。購入飼料は、搾乳時に放牧牛を呼び寄せるためにやむを得ず与えるわずかなビートパルプのみで、餌はもっぱら自給牧草 ― こうした酪農経営が北海道の東端、中標津町にあると聞き、一種の驚きを感じつつ現地へ向かった。ホルスタイン種は濃厚飼料給餌を前提に改良された乳牛と聞いており、濃厚飼料の給与ゼロ、ほぼ100パーセント自給牧草のみで経営が現存しているとは、正直思ってもいなかったからである。その牧場は道東の交通拠点の一つ、中標津空港から車で小一時間ほどのところにあり、広大な根釧原野に抱かれるようにして存在している。そこで山本照二氏(50歳)が奥さん共々切り盛りしている。牧場の名は、近隣の秘湯、養老牛温泉から“養老牛”の三文字を拝借し、「養老牛山本牧場」と命名したという。養老牛温泉は知る人ぞ知る、長きに渡って静かに愛されてきた、まさに秘湯の名に相応しい温泉である。「養老牛山本牧場」の命名の中に、そうした思い、つまり一過性の人気に留まらず、長期に渡って人々から愛される牧場、そして牛乳・乳製品でありたいという思いがある。そして、山本氏が追い求める酪農が徐々に定着し、大きく育っていって欲しいという期待が、そこには込められているのではないだろうか。
 |
自宅・工房の周囲には45ヘクタールの放牧地が広がる |
2.まず、365日24時間の「完全放牧」に挑戦
養老牛山本牧場は今から11年前、2002年12月に誕生した。有限会社別海町酪農研修牧場で2年間、その後、酪農経営で1年間の研修を受けたのちの就農であった。別海町酪農研修牧場から農地の斡旋を受け、同年春、一家揃って移住し準備を整え、49頭の牛と45ヘクタールの農地でスタートした。山本氏は東京都で生まれ、大学時代を北海道で過ごし、卒業後、東京で流通業に12年間従事した。しかし、モノを仕入れ、ただ販売するだけの流通業に、“心躍る”ような喜びをほとんど感じることは出来なかった。心躍り、そして“根源的な喜び”を感じ取ることができる仕事をしたい。山本氏は様々に考え、そして悩んだ結果たどり着いたのが“より根源的なモノを生み出す”一次産業であり、その代表格である農業であった。
農業をやろう。心は決まった。さて、何処でやるか。一家揃ってキャンプなどで何度も訪れ、大好きになった道東に限る。早速、中標津町の役場に電話で相談した。帰ってきた答えは「それなら、酪農をやりなさい!」であったという。
これで方向が決まり、研修を受けることとなった。「体力がもつかな」との心配があったものの、そこは“夢”と“希望”、そして夫婦揃って力を合わせることで乗り切った。しかし、研修中に大きな疑問を抱いた。現行の酪農は、 “牛たちがのんびりと牧草を食み”、その傍らで人々も“木陰に寝そべるかのように牧歌的でスローな時”を満喫しているという、かつて想像し夢見ていたものとは大きく異なり、その対極に位置するものであった。効率化を重視し、“産地や作り方などが明確ではない餌を大量に与え、出来るだけ多くの生乳を搾る”酪農であった。そして“スロー”どころか牛にも人間にもストレスがたまり、疲弊していくように思えた。
これではない、と悩み、あれこれと模索した末に出した結論が、当時徐々に広がりを見せていた“放牧酪農”の道であった。しかも、春から秋にかけての暖かい時期だけ放牧するのではなく、厳寒の冬場も含めて365日24時間放牧するという“完全”放牧酪農である。
放牧は12月、時には零下30度にも達するという厳寒の冬場から始まった。よそから山本牧場にやってきた牛たちにとって、それは極めて大きな環境変化だったに違いない。4頭が廃用になり10頭が凍傷から乳房炎にかかったものの、残り35頭はこの環境を乗り越えた。牛たちは想像以上に強く、環境に極めて順応的で、次年度からはほとんど心配する必要はなくなったと言う。牛たちはどうやって冬場を過ごし、乗り切るのか。興味を持ったNHKが先般、それを探ろうと一昼夜カメラを回し続けた。その映像によると、牛たちも賢いもので雪のフカフカなところに寄り合い、風よけの穴を掘るようにして寝ていたという。3年程前、通年放牧の養豚経営「北海道ホープランド」をレポートしたが(「畜産の情報」2010年2月号)、そこでも豚たちは零下30度にも達する十勝平野で元気に越冬していた。牛も豚もわれわれが思う以上に強靱で適応力に富んでいる。また、山本牧場の牛のその後の状態を見る限り、そうした方が牛の生理にかなっているのではないかとさえ思えるのである。
 |
牧草のみ365日24時間放牧で育つ “日本一ワイルドな牛” |
 |
冬用牧草をたっぷり蓄えたバンカーサイロ |
3.就農前からの悲願であった「濃厚飼料ゼロ」へ
研修中の2001年、BSEが国内においても発生し、山本氏に大きな衝撃を与えた。いわゆる“肉骨粉問題”として世間を騒がせた餌=飼料問題である。中でも輸入濃厚飼料の問題は大きく心を揺さぶった。それを使っている限り世間の疑いや不安は晴れず、またBSEの潜在的危険性も100パーセント払拭できない。「安全・安心」を確かなものにするためにも、輸入濃厚飼料の給餌をゼロにし、更に輸入だけではなく濃厚飼料そのものをゼロにするという目標を決めた。こうして、道東では初と言える極めて珍しい、濃厚飼料ゼロの酪農への挑戦が就農と同時に始まったのである。
ところで、今でこそ濃厚飼料の給与はゼロであるが、当初からゼロだったわけではない。完全放牧は実現しつつも、当初は一日1頭当たり8キログラムの濃厚飼料を与え、年間1頭当たり9,200キログラムも搾り、また、搾乳頭数は最盛期には65頭にまで達した。山本氏の脳裏には当初から濃厚飼料の給与をゼロにするという目標があったものの、入植時の多額の借金を返済するために“多頭化”せざるを得ず、なにより濃厚飼料に適応した改良が行われている牛たちにとって、いきなりの濃厚飼料給与ゼロは負担が大きい。“高泌乳化”もまた必然であった。しかし、山本氏は当初の目標に向かって進み続け、濃厚飼料の給餌量を毎年ほぼ1キログラムずつ減らしていき、今から5年前、濃厚飼料給与ゼロがついに達成された。
当然のことではあるが、濃厚飼料が減った分だけ、牛たちは良く牧草を食べるようになる。しかし、草地は45ヘクタールしかない。草地面積に見合うように乳牛も徐々に減らしていき、ついに40頭程度(訪問時には40頭)となった。草地約1ヘクタールに対し乳牛1頭の規模である。EUのアニマル・ウェルフェアの基準が「1ヘクタール1頭」であったことを思い起こし、その偶然の一致に驚かされた。
餌がほぼ100パーセント自給牧草だけとなると、乳牛の健康は牧草のあり方に依存することとなる。乳牛を健康的に育て、安全安心な生乳を生産するために、山本氏は安全安心な牧草作りに腐心しているのである。牧草は無化学農薬、無化学肥料で生産しており、購入しているのは鶏糞を使った有機質肥料のみである。可能な限り“有機物循環が自牧場内で完結する”有機農業を理想とし、それに向けて前進しているのである。バンカーサイロに貯蔵するのは1番草だけであり、その収穫時期は7月下旬から8月上旬と遅い。2番草まで収穫した時に比べてトータルの収量は20パーセント程落ち、収穫時期を遅らせたことで栄養価も下がってしまうが、草地に種を落とさせることで再生力を維持することが可能となる。すなわち、草地更新を必要としない”質の高い永年草地”作りを目指しているのである。
濃厚飼料給与ゼロに伴って、乳量は夏場で7,000キログラム、冬場で2,500キログラム程となり、平均して年間4,500キログラム程に減少した。しかし、乳牛の分娩回数は平均4.5産と周りの酪農経営家に比べて多産になった。2産ほどで廃用となる牛に比べて長生きになり、長い“牛生”を送る“スローライフ牛”とも言える。“日本一ワイルドな牛”と山本氏は評するが、それはすこぶる自然の理にかなった健康な牛、本来の牛であり、また見方によっては幸せな牛と言えるのかも知れない。“人も牛もスローライフ”といったところであろう。
4.ミルクプラントの設置と「1ミリリットル1円牛乳」
山本牧場の牛たちはワイルドに育ち、評価の高い生乳の生産を続けている。“濃厚”飼料給与がゼロだけあって、その生乳は決して“濃厚”ではない。北海道よつ葉牛乳は乳脂肪分が年間3.6パーセント以上、あるコンビニエンスストアチェーンでは4.0パーセント以上を謳っていることからすれば、冬場で4.5パーセント、秋口で3.5パーセントでは決して高くはなく、むしろ、低いと言わざるを得ない。しかし、味は数値ではないようだ。「味の輪郭がはっきりしている」、「生命力がみなぎっている」と山本氏が評すように、一口飲むと数値では計ることのできない、なんとも言えない“うま味”や“濃厚さ”がそこには秘められているのである。
こうした一品を直接消費者に届けたいと誰しもが思うことであろう。しかし、現行の生乳の取引制度の中でそれを実現するためには、ミルクプラントを設置し、自ら処理し、販売するしかない。そこで、彼は意を決して2009年に資金の一部を借り入れ、ミルクプラント“工房森羅”を建設した。現在、一日処理量約200リットルで週5日程度稼働している。朝5時からプラントを動かし、全工程90〜120分余りの時間をかけ、低温長時間殺菌法のノンホモタイプの牛乳を生産している。消費者向けには180ミリリットルの小瓶(一回600本生産)と900ミリリットルの大瓶(一回100本生産)、大口需要者には大容量パック(5あるいは10リットル詰)を生産し、「WILD MILK 養老牛放牧牛乳」の名で町内の空港や観光地売店、農協店舗など12カ所をはじめ、道内外の量販店などで販売している。また、個人や都府県のレストランなどへは電話、インターネットなどを通じて販売している。
 |
牛乳製造後、分解掃除中のミルクプラント |
 |
人気で完売となっているモッツァレラチーズ |
5.“よそ者”だからできた「中標津マルシェ」
山本氏は地元出身でもなければ農家出身でもない。地域にとっても農業にとっても言わば“よそ者”である。しかし、今日では異業種交流、産官学連携などと言われ、農商工連携、農業の六次産業化が提唱されている。それは「“よそ者”の力を取り込もう」あるいは「“よそ者”こそが新たな息吹をもたらす」ということではなかろうか。“よそ者”である山本氏は、一日も早く地域に溶け込もうと積極的に地域活動に加わっていった。そして、その中で地域には多様な力量を持つ人々がいること、しかしそれが残念ながらバラバラなことに気がついた。これを何とか一つに組み合わせたいという思いから、多くの人々と語り合い、協力、協働の輪を広げ、ついに2010年、「中標津マルシェ」としてそれを結実させたのである。1999年の入植から数えて11年、長い助走期間と言っても良い。町内のホテルを会場に、様々な方々の出店、参加の下、同年“第一回中標津マルシェ”が開催された。来店見込み200人に対して実際の来場者は700人余となったため、商品が不足したものもあったと言う。「中標津マルシェ」は今でも続いており、大いに好評を博している。
注目すべきは、続いているということだけではない。それが起爆剤となり、新たな人々の連携、輪が生まれている。その一つに「中標津素材感覚」がある。同会は22軒の農家や職人(料理人)などが集い結成されたもので、地元の素材を大切にしながら「良い感性で良いものを作る」をコンセプトに、各々の持つ力量や素材を持ち寄ろうというものである。そこには「WILD MILK」はもちろん、それまで埋もれていた実に美味しいジャガイモや10年ものの行者ニンニク、鹿肉、平飼い卵、肉厚シイタケなどが持ち寄られたという。また、共通ブランドでの販売も目指し、既に東京のデパートなどの催事に「中標津素材感覚」の名で共同出店している。もちろん山本氏も出店し、牛乳やチーズ、ソフトクリーム、ジェラートなどを販売している。
こうした連携や協働の深まりは、山本牧場の幅、製品ラインナップの拡大に大きな力を与えている。中標津町内のケーキ店「フランダース」とのコラボレーションによるスイーツ・カタラーナ、近隣の別海町にある「中山ミルク工房」とのコラボレーションによるゴーダチーズやモッツァレラチーズ、東京のジェラート専門店「シンチェリータ」ではジェラートが製造販売されている。“餅は餅屋”と言うが、それぞれの持つ力量や特技などを結合し、新たな物を作り、地域としての販路を広げる。決して大上段に異業種交流、農商工連携、六次産業化などと叫んでいないとしても、まさにその典型がそこには展開されているのである。
 |
放牧地を前に思いを語る山本氏 |
6.「養老牛山本牧場」は“夢”を映し、灯す一つの灯台
山本氏の理想は、搾乳牛10頭程の規模で借金のない独立自営の酪農家になることだと言う。そこでは、乳牛の生理にマッチした“人も牛もスローライフ”を体現した“経営内で有機物が循環する”有機農業をベースにした農業が営まれているはずである。
多頭化や高泌乳化に慣れてしまったわれわれは、“搾乳牛10頭でそれは無理だよ”と即断しがちであるが、1頭当たり年間4,500キログラム程の乳量で搾乳牛10頭、「1ミリリットル1円」とすれば、収益がおよそ4000万円となる。机上の計算では十分に成り立ち得るものであり、実際、昔は搾乳牛10頭はおろか数頭程でも成り立っていたのである。
今、搾乳牛10頭で経営を成り立たせるためには「1ミリリットル1円」の超高乳価の条件は欠かせない。それをいかに実現するか。まず、確かな生乳を生産すること、そして様々な人の力も借りながら、いわゆる農商工連携、六次産業化の方向を目指すこと、それを決して急がず、一歩一歩着実に推し進めていくことの重要性を、山本牧場は教えてくれているように思えてならない。
確かに、山本氏の理想は今日ではなかなか実現できない理想なのかもしれない。しかし、酪農の「あるべき姿」を求めてなのか、あるいはアニマル・ウェルフェアを意識してなのか、購入飼料から自給飼料へ、スタンチョンからフリーストールへ、舎飼から放牧へ、高泌乳型からマイペース型へなど、乳牛との関係を見直す動きが徐々にではあるが高まってきている。それは、1,000頭を超えるようなメガファームが多数存在し、酪農主産地とされる北海道とて例外ではない。
また、今次の国際飼料穀物市場の逼迫や価格高騰が酪農経営を直撃し、自給飼料やエコフィードの重要性がしきりに叫ばれている。本誌2013年2月号でも「自給飼料生産の振興に向けて」のテーマの下、耕作放棄地活用や飼料用米(籾米サイレージ)、エコフィードなどが取り上げられた。
今、酪農・畜産のあり方は大きな転換期に差し掛かっているのではないだろうか。こうした時こそ、人々は“夢”を描き“希望”を抱きたがるものである。養老牛山本牧場は一つの“夢”を映し出し、将来の方向性を考える際の大きな“灯台”の役割を担っていると言える。養老牛山本牧場のますますの発展を祈って止まない。
表1 養老牛山本牧場の経営概況 |
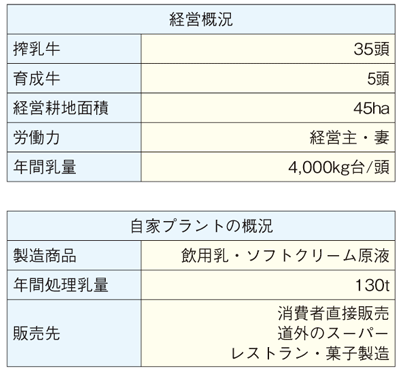 |
資料:聞き取り内容を基に作成 |
表2 山本牧場の特徴 |
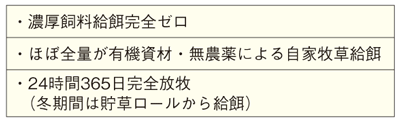 |
資料:聞き取り内容を基に作成 |