�y�v��z
�@�킪���̓��p�����o�c�́A�����������i�̍�����}�����i�̒���Ȃǂɂ�茵�����o�c���������Ă���B���̂��߁A�o�c������I�Ɏ���������ɂ́A�n��̎����o�c�܂������g�݂ɂ��A�e���v�̌����Y��̍팸��}���ď������m�ۂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@�����ŁA�{�e�ł́A�Ƒ��o�c��100�����x�̋K�͊g�����������5����ɂ��Ē������s���A�o�c������A���W�����Ă������g�ݓ��e�ƁA���̓����͂����B
�@���̌��ʁA�e���v�̌���̂��߂ɂ́A���{�Ǘ��Z�p�̓O��ɂ��u�����h���ɂӂ��킵���i���������̐��Y�A����A���Y��̍팸�ɂ́A���Ɣz���̎������^������Ԃ̒Z�k�Ȃǂ��A���ꂼ��L���Ȏ��g�݂Ƃ��ċ�������B
1�D�͂��߂�
�@�킪���̓��p�����o�c�́A�����������i�̍�����}�����i�̒���Ȃnj������o�c���������Ă���B
�@���̂悤�Ȓ��A�o�c������I�Ɏ��������Ă������߂ɂ́A�K�͊g��ɂ��������݂̂Ȃ炸�A�n��̓����Ȃǂ��ꂼ��̌o�c���u���ꂽ���܂������l�Ȏ��g�݂ɂ��A�������m�ۂ��Ă������Ƃ��d�v�ł���B
�@���p���̎��{�K�͕ʂ̎��{������ƁA�N�X���{�K�͂̊g�傪�i��ł��邪�A200�������̎��{�K�͂̊K�w���A�ˑR�Ƃ��đ����{�����̔����߂����߁A���K�͊K�w�ł͉Ƒ��o�c���������߂錻��ɂ���B
�@�܂��A�_�ѐ��Y�Ȃ�����22�N7���Ɍ��\�����u���_�y�ѓ��p�����Y�̋ߑ㉻��}�邽�߂̊�{�w�j�v�̒��ŁA�ߑ�I�ȓ��p���o�c�̊�{�I�w�W�Ƃ��Ď�����Ă���Ƒ��o�c�̋K�͂�150���ł���B����́A�Ƒ��o�c�Ŏ����\�ȖڕW�l�ł���Ƃ�����B
�@���ݑ������߂鏬�K�͂̉Ƒ��o�c������A�K�͊g���ڎw���ۂɂ́A���łɋK�͊g������������o�c���s���Ă������g�݂��Q�l�ɂ��邱�Ƃ��L���Ȏ�i�̈�ɂȂ�ƍl������B
�@�����ŁA�{�e�ł́A�Ƒ��̖������S�Ȃǂɂ��100�����x�̋K�͊g��������������o�c���A�ǂ̂悤�Ȏ��g�݂��s���A�o�c�̈���Ɣ��W�ɂȂ��Ă��邩�A���̎���͂��A�Љ��B
2�D���p�����o�c�̓���
�@�e��������̎�g���e���Љ��O�ɁA���o�c�̊T�v�ɂ��Đ������Ă����B�@��ʓI�ɔ��o�c�́A�ꋍ�����{���Ďq���Y����ɐB�o�c������Ƌ��i�q���j�����A���p���Ƃ��Ă̏o�דK���܂Ŕ�炵����A�H���s���H���Z���^�[��ʂ��ďo�ׁE�̔�����B���јa��ł́A10�J����O��̂��Ƌ������A��20�J����炵����A30�J����O��ŏo�ׂ���̂���ʓI�ł���B�Ȃ��A��炾���łȂ��A�q���̐��Y����琬�E���܂ōs����ьo�c������B
�@�_�ѐ��Y�Ȃ̒{�Y���v�ɂ��ƁA���јa��Ȃǂ̓��p��̔�狍�̎��{�����́A����22�N��84�������s�[�N�Ɍ����X���ɂ���A25�N��79�����ƂȂ��Ă���B��狍�̎��{�ː��́A21�N�ɂ�1��1700�˂ł��������A25�N��1���˂ƂȂ�A�����X���Ő��ڂ��Ă���B
�@1�˓����莔�{�����́A���K�͑w�𒆐S�Ɏ��{�ː��������������ʁA����21�N��69.2������25�N��79.0���ɑ������Ă���i�}1�j�B
�}1�@���{�����A���{�ː��A1�˓����莔�{�����̐��� |
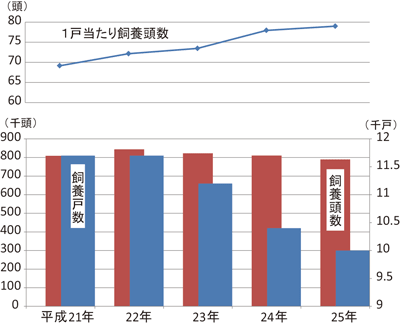 |
�����F�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y���v�v |
�@�܂��A����10�N�Ԃ̎��{�ː��̕ϓ������{�K�͕ʂɌ���ƁA����15�N�ɂ͑S�̂�75�p�[�Z���g�ȏ���߂Ă���50�������̏��K�͑w���A25�N��67�p�[�Z���g��8�|�C���g�������Ă���B�t�ɁA50���ȏ�̋K�͂́A����10�N�Ԃ�9�|�C���g�������Ă���i�}2�j�B
�}2�@��狍���{�K�͕ʂ̎��{�ː�
|
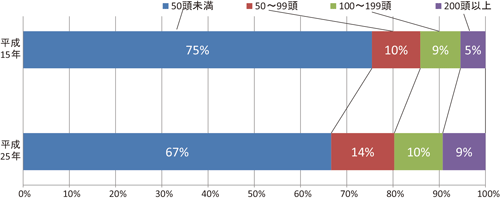 |
�����F�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y���v�v |
3�D�u�����h���Ȃǂɂ��e���v�̌���
�i1�j���o�c�ɂ�����e���v�̊T�v
�@�_�ѐ��Y�Ȃ̒{�Y�����Y��v�ɂ��ƁA�e���v�̉ߋ�5�N�ԁi����19�`23�N�x�j�̕��ς͑S�̂�85��9145�~�ƂȂ��Ă���A���o�c�����јa��1�����瓾�����Y�������́A��84��7248�~�ƁA�e���v�S�̂�98.6�p�[�Z���g�Ƒ唼���߂�B����A�͔�Ȃǂ̕��Y�������́A��1��1897�~�ƁA���ɏ����������ƂȂ��Ă���i�}3�j�B�}3�@���{�K�͕ʂ�1��������e���v�i����19�`23�N�x���ρj |
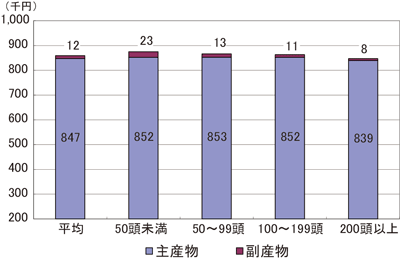 |
�����F�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y�����Y��v�v���@�\�쐬 |
�@�܂��A���{�K�͕ʂɂ��Ă��A�S�Ă̎��{�K�͂ɂ����Ă����ނ˔N�X�����X���Ő��ڂ��Ă��邱�Ƃ�������i�}4�j�B
�}4�@���{�K�͕ʂ�1��������e���v�̐��� |
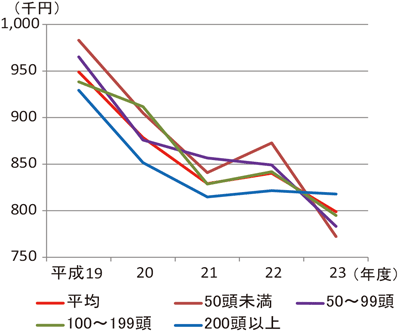 |
�����F�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y�����Y��v�v���@�\�쐬 |
�@��ʓI�ɁA���o�c�ɂ����Ď��v�����コ���邽�߂ɂ́A�i1�j�}�����i�̓��������āA���v���ɑ����o�ׂł���悤�o����������A�i2�j�}���]���̍�����狍�Y���A�}���P�������߂�A�i3�j�}���d�ʂ̑傫����狍�Y���A1��������̔̔����i�����߂�A�Ȃǂ̕��@���l������B
�@�����ŁA�����ł́A�N�X�e���v�������X���ɂ��钆�ŁA���o�c���e���v�傳���邽�߂ɍs���Ă�����g�݂��Љ��B
�i2�j��a�� �̕��y�ƕi������̓w��
�@�@�`�ޗnj��E
������ ���̎��g�݁`
�i1�j�T�v�@�ޗnj��ޗǎs�i��
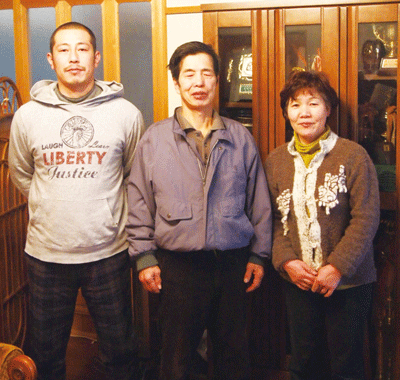 |
��a���̐��Y�Ɏ�g�ޒ�������Ɓi�������Ύ��j |
�\1�@�������̌o�c�̕ϑJ
|
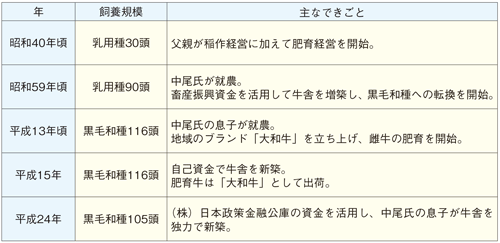 |
�����F�������ɂ��@�\�쐬 |
�@��a���́A�ޗnj����̓��p�����Y�U���̂��߁A����13�N�ɓޗnj��ƍ��c�@�l�ޗnj��H�����Ђ����S�ƂȂ�A�����u�����h�Ƃ��ė����グ���B�������͗����グ�����A�L�u�Ƌ��Ɍ������Y�҂ւ̐�����Q���̌Ăт������s�������A�^�����Ȃ��Ȃ������Ȃ������B���ǁA�������܂�6�˂��w�萶�Y�҂Ƃ��đ�a���̐��Y���n�߂��B
�@���̌�A��������̌p���I�ȌĂт������a���̔F�m�x����ɔ�������̑���������A���݂ł́A��a���̎w�萶�Y�҂�20�˂܂ő��������B�o�ד����ɂ��Ă��A15�N��342���ł��������A���X�ɑ������A23�N�ɂ�989���Ɩ�3�{�ɂȂ����B
�@��a���́A�ޗnj����𒆐S�Ƃ����w��̔��X30�X�܂�ʂ��Ĕ̔������n�斧���^�̋����u�����h�ł���A�̔����D���Ȃ��Ƃ���A����l��������Y�����߂��Ă���B
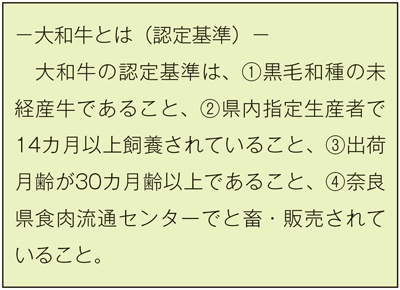 |
�@�������́A�ǎ��ȑ�a�����炷�邽�߂ɁA���ɋ��̃X�g���X�y����S�|���Ă���B���������狍���ώ@���邱�ƂŁA�����̗ǂ���2�������[�Ŏ��{���A��Ƃ肠��X�y�[�X�i9�u�^���j���m�ۂ��Ă���B�܂��A���ɂ̐V�z�ɔ����A��������o�ׂ܂ŋ��[���ړ������Ȃ��Ǘ��̐��Ƃ����B���̌��ʁA�������͒���3�N�Ԃ�1�������̋����o���Ă��Ȃ��B
�@�o�א��тɂ��ẮA24�N12���ɊJ�Â��ꂽ��24���a���}�������ɂ����āA�ŗD�G�܂���܂���ȂǁA��a���̐��Y�҂̒��ł�������琬�т��c���Ă���B
 |
�������̎��j���꒷���߂�u�݂������q��v���瓱���������Ƌ� |
�i3�j���{�Ǘ��Z�p���A�n��u�����h�ɍv��
�@�@�`�V�����E
�R�ꎡ�F ���̎��g�݁`
�i1�j�T�v�@�V�������̘a�����̎�Y�n�ł��鑺��s�Ōo�c���c�ގR�ꎁ�́A�v�Ȃŋ��͂��Ȃ��獕�јa��80�����炵�Ă���B���a40�N�㏉���ɎR�ꎁ�̕��e���A�͔�Â����ړI�Ɉ��o�c�̖T��ŔɐB���������̂����������ɁA45�N����������J�n�����B����13�N�ɂ͒n��u�����h�́u���㋍�v�̐��Y��{�i�I�ɊJ�n���A���݂͗D�ꂽ���Z�p����A���㋍�̒��S�I�Ȑ��Y�҂Ƃ��Ċ��Ă���B
 |
�u�ɂ������a����疼�l�v�̎R�ꎁ�Ƌ��� |
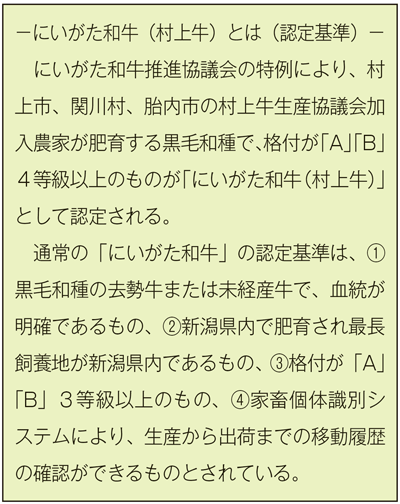 |
�@���㋍�Ƃ��ďo�ׂ��邽�߂ɂ́A�}���̕i������萅���i�i�t4�����ȏ�j�Ɉێ�����K�v������B���̂��߂ɁA�R�ꎁ�́A�q�����i�̑���ɍ��E���ꂸ�A��ɗǎ��Ȃ��Ƌ������ɂ߂ē������Ă���B�܂��A�R�ꎁ�����{�Ǘ��ōł��d�v�����Ă���̂��A���̃X�g���X�y���ł���A70���K�͂̋��ɂ�45�����x�����e���邱�Ƃŏ\���Ȏ��{�X�y�[�X���m�ۂ��A���̊ώ@��ӂ邱�ƂȂ��A���N��Ԃ̔c���ɓw�߂Ă���B���ɂ��A��璆���ɂ�����r�^�~��A�R���g���[���̓O��Ȃǂɂ���āA����BMS�i�����b���G��j���������Ă���B
�@�܂��A�ߋ��ɂ́A���v�Вc�@�l�V�����{�Y����̃R���T���e�[�V�������A1�������菊���̌v�Z���@�ȂǍׂ��Ȍo�c�Ǘ���@���w�Ԃ��ƂŁA�X�Ȃ�o�c�̌������ɓw�߂Ă���B
�@�����̎��g�݂ɂ��A����18�N�ł͖�74�p�[�Z���g���x�ł������㕨���i����������ʂ�4������5��������߂銄���j���A23�N�ł͖�88�p�[�Z���g�ƁA5�N�Ԃ�14�|�C���g���サ���B�܂��A1��������e���v�ɂ��Ă��A23�N�ł́A�S�����ςƔ�ׂ�20���~�ȏ㍂���B
�@����ɎR�ꎁ�́A����22�N�ɁA�ɂ������a�����i���c��́u�ɂ������a����疼�l�v�i�ȉ��A���l�j�̔F����Ă���B����́A�o�ׂ���}���̏㕨�����������ł��鐶�Y�ҁA�܂��́A�����Ȃǂ̓��܌o���҂ł��邱�Ƃ������Ƃ����F�萧�x�ŁA�R�ꎁ���܂�8�����F����Ă���B�R�ꎁ�́A�ɂ������a�����i���c����{�����u�ɂ������a����疼�l�}���c�[�}���w�����Ɓv�ɂ��A���l�Ƃ��āA�����̐��Y�҂ɔ��Z�p�̎w�����s���A���o�c��������ۑ�Ɉꏏ�ɂȂ��Ď��g��ł����B
�@���̂悤�ɁA�R�ꎁ�́A�n��u�����h���̐��Y��ʂ��āA����̎��{�Z�p�����コ���A���v�̑���������������ƂƂ��ɁA���g�̌o�c�����łȂ��A�n��S�̂̎��{�Ǘ��Z�p�̍��ʕ������ɂ����g��ł���B
�i4�j���ߍׂ₩�Ȏ��{�Ǘ��őe���v��
�@�@�`�R�`���E
�܌��� ���̎��g�݁`
�i1�j�T�v�@�R�`���̎�v�ȓ��p���Y�n�A���ԑ�s�Ōo�c���c�ސ܌����́A�e�q3��ō��јa��220�����炵�Ă���B
�@�܌��Ƃł́A�܌����ƕ��e�A���q�����S�ƂȂ��ċ��ɂ��ƂɒS���҂��ĊǗ����Ă���B�܂��A����̕��e�̍�Ƃ�܌����̍ȂƑ��q�̍Ȃ��T�|�[�g����Ȃǂ̖������S���s���Ă���B
�@���݁A���Y�������́A�S�ĎR�`�s�}���s��ɏo�ׂ��Ă���A���̂قƂ�ǂ����́u�R�`���v��u���ԑv�ȂǂƂ��Ĕ̔�����Ă���B
 |
3��ɂ킽���Ĕ��o�c���c�ސ܌������ |
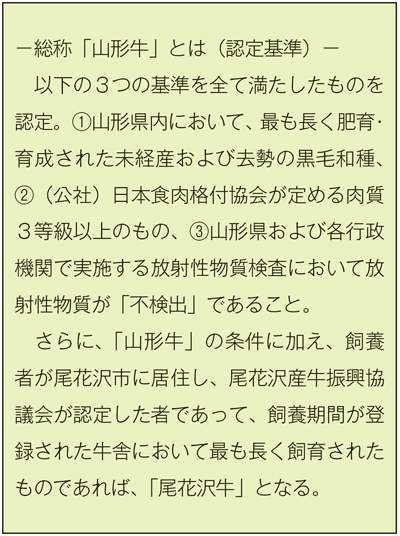 |
�@���Ƌ��́A�܌��������̏d���A���q�������d���őI��E�������Ă��邽�߁A���ꂼ��ʂ̋��ɂŔ�炵�Ă���B����͗����̓��ӕ��삪�قȂ邱�ƂɋN�����邪�A���݂�������̊Ǘ����j�Ɏ��M�������Ă���A��琬�т����������Ă���B�܂��A�琬���j�̈قȂ��狍�����{���邱�ƂŁA�o�c�̃��X�N���U�ɂ��Ȃ��Ă���B
�@���{�Ǘ��ʂł́A�~���̏�Ԃ��m�F���A1��1��͌p�������Ă���B���̍ہA�A�����j�A�ȂǏL�C�����̔����ŁA���̌��N��Ԃ��m�F���Ă���B���̂悤�ɁA���ɋɗ̓X�g���X��^���Ȃ��悤�����Ǘ���O�ꂷ�邱�ƂŁA�i���̍����������Y���\�ɂ��Ă���B
�@�o�א��тɂ��ẮA�㕨������9���ƍ������ɂ���A1��������e���v���A����23�N�ł͑S�����ςƔ�ׂ�30���~�ȏ㍂���B����́A�܌������o�ׂ���R�`�s�}���s��̕��ςƔ�ׂĂ��������Ƃ���A�����̌o�c�͋ɂ߂č������т��c���Ă��邱�Ƃ�����������B
�@�܌����͂��̑��ɂ��A������d�v�ȍ��Y�ƍl���A���痘�p�g������ё͔�U�z�g���𗧂��グ�A�ߗׂ̍k��o�c�i����A�X�C�J�A�T�N�����{�Ȃǁj�֑͔�U�z���s���ƂƂ��ɁA�e�o�c���ۗL���鐅�c���������������ȂǁA�ϋɓI�ȍk�{�A�g���s���Ă���B
 |
�܌��������{�����狍 |
�i5�j�܂Ƃ�
�@�ȏ��3���ɋ��ʂ���_�́A�u�����h���̐��Y�����������Ƃ��āA����ɂӂ��킵�����Y���邽�߁A�O�ꂵ�����{�Ǘ����s�������ʁA�����e���v���ێ����Ă��邱�Ƃł���B���ɁA3���Ƃ��ɁA���ɗ^����X�g���X���ɗ͌y������悤�ɓw�߂Ă���B4�D���Y�R�X�g�̍팸�ɂ����v���̌���
�i1�j��狍�̐��Y�R�X�g�̊T�v
�@�_�ѐ��Y�Ȃ̒{�Y�����Y��v�ɂ��ƁA���Ƌ��̓�������o�ׂ܂ł̔�狍1��������̐��Y�R�X�g�̑S�����ς�93��8569�~�i����19�`23�N�x�̕��ϒl�j�ŁA���̓���́A���ƒ{�49��9900�~�i���Y�R�X�g�S�̂�53.3���j�A�����29��3158�~�i��31.2���j�A�J���7��3263�~�i��7.8���j�A�~����Ȃǂ��̑��̌o�7��2248�~�i��7.7���j�ƂȂ��Ă���B
�@���{�K�͕ʂɔ�r����ƁA1�`10�������̏��K�͌o�c��200���ȏ�̑�K�͌o�c�̊Ԃɂ�17��5000�~�قǂ̍�������B���ɁA���{�K�͂��傫���Ȃ�ɂ��1��������̘J����͌����X���ɂ��邱�Ƃ��킩��i�}5�j�B���̈���ŁA���{�K�͂̑召�ɂ�����炸�A���ƒ{��͐��Y�R�X�g�S�̂�50�p�[�Z���g�O��A�������30�p�[�Z���g�O����߂Ă���A�K�͂̈Ⴂ�ɂ��傫�ȍ��ق͌����Ȃ��B���ƒ{��Ǝ�������Y�R�X�g�̑啔�����߂�Ƃ����\���́A���o�c�ɂ���������ƂȂ��Ă���B
�}5�@���{�K�͕ʂ̔�狍�̐��Y�R�X�g�̍\���i����19�`23�N�x���ρj
|
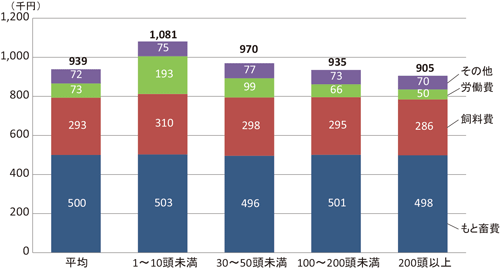 |
�����F�_�ѐ��Y�ȁu�_�ѐ��Y���v�i�_�ƌo�c���v�����j�v���@�\�쐬 |
�@�����ŁA�ȉ��̎���ł́A���{�Ǘ��ɑ��邱���������Ȃ���A�����I�ɐ��Y�R�X�g���팸���Ď��v���̌���ɂȂ��Ă�����g�݂ɂ��ďЉ��B
�i2�j�����Ԃ̒Z�k�ƌ����I�ȋ��^�Ŏ�������팸
�@�@�`�������E
�}�V���� ���̎��g�݁`
�i1�j�T�v�@�������ő��q��2�l�ŋ��͂��Ȃ��獕�јa��100�����炷��}�V���́A���e�̃u���C���[�o�c�̎�`�������������Ƃ��Ē{�Y�ɂ������悤�ɂȂ�A���̌�A���p�����o�c���J�n�����B�J�n�����͊��јa������{���Ă������A�����̗A�����R������ɔ����A�q�����i�������ɂȂ��Ă������јa������A���{�i������јa��ւƐؑւ����B1��������̎}���d�ʂ̑��ʁi���́j���d�������o�c���s���Ȃ���A���{�K�͂�100���܂ő��₵�Ă����i�\2�j�B
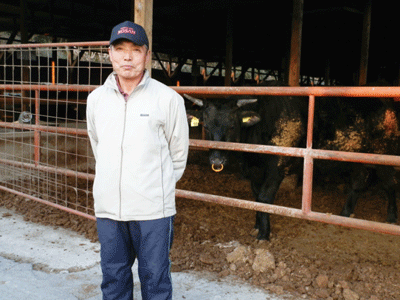 |
�����Ԃ̒Z�k�Ƒ��̂Ɏ�g�ގ}�V�� |
�\2�@�}�V���̌o�c�̕ϑJ |
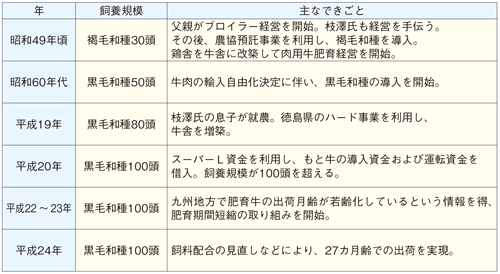 |
�����F�������ɂ��@�\�쐬 |
�@�}�V�����A���v������̂��߂ɒ��ڂ����̂��A�����Ԃ̒Z�k�ł���B�����́A�Вc�@�l�������{�Y����i���@���v�Вc�@�l�������{�Y����j������22�N�ɊJ�Â����Z�~�i�[�ŁA�����Ԃ̒Z�k�ɂȂ��鎔�{�Ǘ��Z�p���w�сA�����̋��^���@�Ȃǂ��H�v���邱�Ƃ�27�`28�J������x�ŏo�ׂ��\�ɂȂ�ƍl�����B����ɁA��������l�X�ȏ������W���钆�ŁA��B�n���̎s��ŏo������X���ɂ���ƕ����A��������������ɋ�̓I�Ȏ��g�݂��J�n�����B
�@�܂��A���Ƌ��I��ɂ����Ă͑��̌n�̋��������Ă���B����ɁA����܂Łu�O���E����v�̎����̔z�����j���[���A�u�O���E�����E����v��3��ނɕύX���A�e���i�K�ŕK�v�ȉh�{�f�������I�ɋ��^�ł���悤�ɂ����B���̎����v�ɓ������ẮA�Z�������̋��^���������߂邽�߁A�z�������̑��A�g�E�����R�V�ȂǒP���̔Z��������lj��ōw�����A���Ɣz�����s���Ă���B�܂��A���ɂ�4�����{�ł��鋍�[��2���������A�X�g���X�̌y���ɂ��w�߂Ă���B
�@�����������g�݂ɂ��A�Z���ԂŔZ�������𑽋��ł���悤�ɂȂ�A��32�J���̏o�����5�J���Z�k���A��27�J����ŏo�ׂ��邱�Ƃɐ��������B���̌��ʁA�w��������̖�9.8�p�[�Z���g�̍팸�i���j��B�����A�}�V�����o�c���s����ŏd�v������1�������藘�v���̌���ɂȂ����Ă���B
�@�܂��A�����Ԃ�Z�k���Ă���ɂ�������炸�A�o���̎}���d�ʂ͑S�����ς�478.5�L���O��������100�L���O�������x�����Ă���A���������̍���������������B
 |
�{�ɂ����z�������� |
���F����23�N�x�_�ƌo�c���v�����k��������狍���Y��i���{�K��100�`200�������j�l�Ƃ̔�r
�@�@�ɂ��B
 |
�}�V�������{�����狍 |
�i3�j�����̎��Ɣz���ƃX���[�����̓����ɂ�鐶�Y�R�X�g�̍팸
�@�@�@�`���ꌧ�E���{�D�O ���A�]���r�O ���̎��g�݁`
�i1�j�T�v�@���ꌧ�ŕv�ȂƉ��ō��јa���140�����{���鋴�{���́A���a57�N�ɓ��p��120���Ŕ��o�c���J�n�����B���݂́A���{�����S�̓I�Ȍo�c�Ǘ��𒆐S�ɍs���A��Ȏ��{�Ǘ��͉��ɔC���Ă���B���{���̍Ȃ͂��Ƌ�������3�J���Ԃ̈琬��S�����Ă���A3�l�ō�ƂS���Ă���B
�@�����n��ŗ��e�ƕv�Ȃō��јa���165�����{����]�����́A���a48�N�ɓ��p��50���Ŕ��o�c���J�n�����B���݁A�]�����Ɨ��e�����X�̎��{�Ǘ���S�����A�]�����̍Ȃ͈���̉���ȂǔɖZ���Ɍ���A�]�����̍�Ƃ��T�|�[�g���Ă���B
�@�����́A����3�N�ɋ����̗A�����R���̉e���œ��p��̎}�����i�������������Ƃ���A�t�ɏ㏸�X���ɂ��������G��ɓ]�������B���̌�A���G��̎q�����i���㏸�������Ƃ���A���{���͕���17�N�A�]������20�N�ɍ��јa��֓]�����Č��݂Ɏ���B
�@���̂悤�ɁA�����͎q�����i�Ǝ}�����i�̑���̓����ɉ����āA�̎Z�̎���i���I�����A�����ɐ������Ă����B�i��I����A���p�킩����G��A���јa��ƁA�i�K�I�Ɏ}���]���̍����i��֓]�����Ă���B���ɍ��јa��́A���i���������ʂň��肵�Ă���X���ɂ��邽�߁A�����ƕi��I��͌o�c����ւ̃J�M�Ƃ����悤�B
 |
������팸�Ɏ��g�ލ]�����i�ʐ^�E�j |
 |
�]�����̋��ɓ��� |
�@���������v������̂��߂Ɏ��g��ł���̂��A������̍팸�ł���B�����Ƃ������̎��Ɣz�����s���Ă���A�����̗ǂ����ێ����������}������z����������X�������Ă���B�܂��A���{���ɂƂ��Ď��Ɣz���́A���g�̎����d����������������₷���Ƃ����B�P�������̍w���̍ۂɂ́A���̊z���������A�������ȗ�������鎔����Ђ����ʂɍw������悤�ɂ��Ă���B
�@���Ƌ��ɂ��ẮA�����͎��ڐA�iET�j�Y�q�̃X���[�����i3�`4�J����̎q���j�����A�琬������܂ōs���Ă���B�X���[���������̒����́A�琬���ɗǎ��ȑe�����𑽋����邱�ƂŁA���[�����i���݁j�𑁊��Ɍ`�������A�����̔Z�������̏����E�z���������コ���邱�Ƃ��ł���_�ł���B����́A��ʓI��10�J����̂��Ƌ��̓����Ɣ�ׂāA���������̎�Ԃ��Ȃ����߁A���ʂȂ����ֈڍs�ł��A�����Ԃ̒Z�k�ɂȂ���B���̌��ʁA�����̐��U���^�ʂ�Ⴍ�}���邱�Ƃ��ł���B
�@�����̎��g�݂ɂ��A���{����33.8�p�[�Z���g�A�]������29.3�p�[�Z���g�̎�����팸����B�������B�܂��A�o����́A���{������28�J����A�]��������29�J����ł��邪�A����Ȃ�����Ԃ̒Z�k�ɂ��A������̍팸��ڎw���Ă���B
���F����23�N�x�_�ƌo�c���v�����i��������狍���Y��i���{�K��100�`200�������j�j�Ƃ̔�r
�@�@�ɂ��B
 |
���{�������������X���[���� |
 |
���{�������{�����狍 |
�i4�j�܂Ƃ�
�@�Љ��2����̎��g�݂ŋ��ʂ���̂́A���Y�R�X�g�̖�30�p�[�Z���g���߂鎔����̍팸�ł���B3���Ƃ��ɁA�����̔z�������ł͂Ȃ��A�����ȒP���������w�����Ď��Ɣz�����s�����ƂŎ�������팸���Ă���B�@�܂��A�����̎��Ɣz���́A���Y�R�X�g�̍팸�ȊO�ɂ��A�}�����т⎔�����i�Ȃǂ̏ɍ��킹�ď_��ɔz���������ł��邽�߁A�e�X�����z�Ƃ���}���d�ʂ�����̋������Y���\�ƂȂ�B���Ȃ킿�A���Y�R�X�g�̍팸�����ł͂Ȃ��A���v�̑����ɂ��Ȃ��邱�Ƃ��ł���B
5�D������
�@���o�c����芪�������������A����Љ�����Y�҂́A���ꂼ�ꂪ���o�c���O���\���Ɏ����ł���悤�Ȏ��g�݂��s���Ă����B�@�����ŁA����ɋ��ʂ�������ɂ��čl�@����B1�ڂ̓����́A�u���̃X�g���X�y���̂��߂Ɏ��{�X�y�[�X�ɂ�Ƃ�����������Ǘ����s���v�Ƃ����_�ł���B����ɂ���āA�����m�̐ڐG�ɂ�邯���Ȃǂ̎��̂�\�h���邱�Ƃ��ł��A�X�g���X�y���ɂ���āA�����ቺ��}���邱�Ƃ��ł���B���̓_�́A���Ƀu�����h���Ȃǂɂ���đe���v�̌����ڎw���o�c�ɂƂ��āA�傫�ȃ����b�g�ƂȂ�B����ŁA�ʏ���L���X�y�[�X���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A���ɑ��݂ȂǂɌ����Ēlj��̐ݔ��������K�v�ƂȂ�B����ɑ��A����ł͒{�Y����̃R���T���^���g�����v������Ǘ��̎�@���w�сA�o�c�����P������A�����q�E���S�ێ����Ȃǂ����p���đΉ����Ă����B
�@2�ڂ̓����́A�u�����̌���Ђ��Ă͑e���v�̌���̂��߂Ɏ����̎��Ɣz�����s���Ă���v�Ƃ����_�ł���B����́A�������i�⋍�̏�ԂȂǂɉ����āA�����̎�ނ⋋�^�ʂ����邱�ƂŁA�e�o�c���ڎw�������̋������Y���\�ƂȂ�A������̍팸�ɂȂ���Ƃ������ʂ�����ꂽ�B�������A�e�o�c�Ƃ��ǎ��ȋ����̐��Y�Ǝ�����̍팸�𗼗������邽�߁A���X�A�����̑g�ݍ����⋋�^���@���H�v���Ă���A���ꂪ���g�ݐ����̃J�M�ƂȂ낤�B
�@3�ڂ̓����́A�ނ�̎��g�݂���o�c�̂����ŋA��������̂łȂ��A�ߗׂ̔��o�c�ւ̋Z�p�`�B��A�����̋����w���A�͔�ƈ���̐ϋɓI�Ȍ����Ȃǂ�ʂ��āA�n��Ƃ̊ւ�荇���̒��Ŏ��H����Ă���_�ł���B���ʓI�ɁA�n��_�Ƃ̊������ɍv�����邾���łȂ��A�X�P�[�������b�g����������������̍팸���B�����Ă���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���K�͂̉Ƒ��o�c�ɂ����Ă��A�������̎��g�݂̐ςݏd�˂ɂ���āA100�����x�̋K�͂̌o�c����Ɣ��W�ɂȂ��Ă������Ƃ��ł���ƍl������B
�@�Ō�ɁA����Ƃ��ďЉ���Ă����������e���Y�҂̊F�l���͂��߁A���Z�������A�����ɂ����͂����������W�c�̂̊F�l�ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B