【要約】
わが国が目指す攻めの農林水産業を実現するためには、何より生産効率性の向上が必要不可欠である。
複数の家族経営がネットワークを形成して効率的な肉豚生産のための雑種生産システムを確立している宮城県の(有)東北畜研と宮崎県の(有)観音池ポークの実態分析と個票データを用いた計量分析の両面から、生産効率性の向上のための要因分析を行った結果などについて報告を行う。
1 問題の所在と課題の設定
(1)問題の所在
これまで、日本の養豚経営では家族経営がグループ化することで、効率的な肉豚生産のための雑種生産システム(以下、「雑種生産システム」という。(※1))を確立してきた。このことを前提として、家族経営においても成長や安定性を実現している実態に関して、詳しい分析が行われてこなかった。2008年度、2013年度の配合飼料価格の高騰時に、1人当たり農業所得や専従者給与を柔軟に対応させることで、財務内容を改善させていた実態、あるいは直売所による食肉加工品などの販売などの事業多角化によって地域に根差している実態に関しても同様である。
(2)研究の課題
本報告では、家族経営がグループ化することによって雑種生産システムを前提とした生産効率に関する計量、実態の両面から分析を行うことを課題とする。
具体的には、第1に、2005年以降の豚肉の需給構造の変化と養豚経営の動態について統計的な接近を行う。
第2に、家族経営における生産活動の効率性格差とその規定要因について、生産規模と生産の各段階における生産活動の指標に着目して、計量分析から明らかにする。
第3に、第2の計量分析の結果を踏まえて、家族経営の雑種生産システムの確立をネットワーク(※2)の形成によって実現している事例の生産効率に関する分析を行う。
2 豚肉の需給構造と養豚経営の動態
(1)消費の停滞
2005年以降の肉類の需給構造の変化は以下の通りである。
農林水産省『食料需給表』によると、2005年から2012年にかけて、肉類の国内消費仕向量は、約560万トンから約600万トンへ約40万トン増加した。1人当たり消費量も、43キログラムから45キログラムへと増加した。中でも、鶏肉は国内消費仕向量が約190万トンから約220万トンへ、1人当たり消費量も14.7キログラムから16.9キログラムへと2.2キログラム増加している。牛肉も国内消費仕向量は約115万トンから約122万トンへ、1人当たり消費量も8.8キログラムから約9.4キログラムへ増加した。
その一方で、豚肉では、国内消費仕向量は約249万トンから約244万トンへと減少し、1人当たり消費量も19.1キログラムから18.8キログラムへと減少した。鶏肉の国内消費量の大幅な増加と牛肉の国内消費量の微増によって、肉類全体の国内消費量が増加したが、豚肉に関しては国内消費量が減少する傾向を示し、消費の低迷によって豚肉価格が下落しやすい状況にあったといえる。
(2)配合飼料価格の高騰
穀物価格の高騰に起因して配合飼料価格が高騰し畜産経営に影響を与えてきたことが、これまでもさまざまな論者によって明らかにされている(※3)。
配合飼料価格は、2008年度に約6万5000円/トン台へと高騰した後、2009年度、2010年度と約5万円/トン台で推移していたが、2011年度から再び上昇傾向を示し、2013年7月には2008年度を上回る水準の6万8025円/トンにまで高騰している。
(3)輸入審査の厳格化と豚肉価格の安定
輸入審査の厳格化により在庫量が減少したこともあって、2013年度の豚肉価格は6月前後以降も安定的に推移した。
2012年以前は、6月前後に高価格となった後、翌年1月前後まで下落し続け、その価格差が100円/キログラム以上に達する年度も存在した。2013年度は6月前後以降の価格の下落も発生せず、約500円/キログラムという安定的な水準で推移していた。このため、2013年度では、配合飼料価格が2008年度を超える水準にあっても、収益を確保し、財務内容を改善している家族経営、法人経営が“層”として存在していると推察される。
(4)飼養頭数の動向
国内飼養頭数は、2003年、2008年、2013年の各年において、約960万頭で推移している(表1)。最大の特徴は会社への飼養頭数の集中であり、その飼養頭数シェアが、2013年、70%以上にまで達している。表出は省略するが、この期間、飼養頭数を増加させてきた地域は九州地域、とりわけ宮崎県と東北地域である。
(5)生産費の変動
飼養戸数の大幅な減少と飼養頭数規模の急速な拡大が生じていたにもかかわらず、養豚経営の生産費自体、この20年間、大きく変動していない。農林水産省『畜産物生産費統計』によれば、1頭当たりの肥育豚生産費の費用合計は1993年に3万338円であったものが、2012年度では3万2179円となっており、生産費が微かに増大している。この期間、農林水産省『畜産物生産費統計』のサンプルにあっても平均飼養頭数規模は428頭から813頭まで増加しているにもかかわらずである。
表1 豚飼養頭数の推移(子取り用めす豚飼養頭数規模別) |
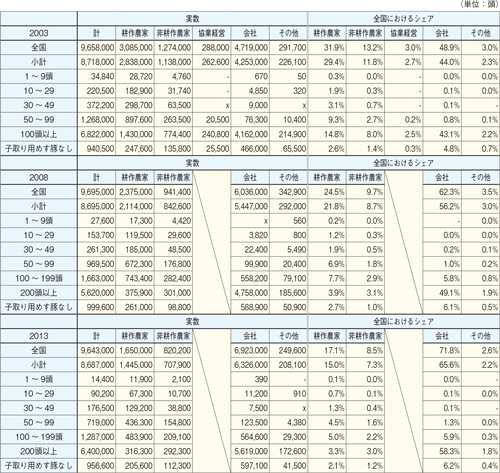 |
資料:農林水産省「畜産統計」 注:協業経営の区分による統計は2008年以降とられていない. |
3 効率性分析
(1)生産効率性の計測
本節の課題は養豚経営の個票データを用いて、養豚経営の生産性・規模の経済について数量的に明らかにすることである。その際には単純な投入-産出だけでなく、生産の各段階での生産能力の影響が最終的な生産性にどのような影響を与えているのか分析することを回帰分析と分散分解から明らかにすることを主眼とした。分析には、(公社)中央畜産会『先進事例の実績指標』をデータとして用いた。
ここでの分析に当たっては、サンプルデータの投入-産出からその生産可能性集合を推定する包絡分析(DEA)(※4)による効率性計測をおこなった。
図1~3は、計測した規模の経済の存在を想定しないCRS(Constant Return to Scale)効率性、規模間で産出能力に違いがあることを想定するVRS(Variable Return to Scale)効率性、VRS効率性とCRS効率性の比によって表される特定の投入-産出方式における生産フロンティア上での生産効率性が最も生産効率の高い投入-産出方式と比較してどの程度の効率性をもつのかを表す規模効率性について、生産規模の指標としての売上高との関係をみるために特定の関数形を想定しないノンパラメトリック回帰によって回帰分析したものである。
養豚生産の効率性には大きいというほどではないにしろ、経営間で生産効率性には差があること、規模の経済が無いと考えるのであれば、大規模経営ほど高い効率の経営を行っていること(図1)、規模間の投入-産出方法の違いによる生産性の差を考慮するならば、大規模経営では生産効率性が高い一方で小規模経営でも効率性は高くなること(図2)、売上高5000万円から1億5000万円の領域では売上高の大きい経営ほど規模効率性が高い訳ではなく、規模の経済が存在するとは言えないこと(図3)などが明らかとなった。
分散分解の数式
分散分解は次式の分散の法則に基づいて、計量分析の結果を分解するものである。分散の法則に基づけば、
のとき、
となる。
重回帰による推計結果は、
を推定するものであるが、計量分析の前提として、cov(ε、 xi)=0となるため、
となる。
図1 CRS効率性と売上高 |
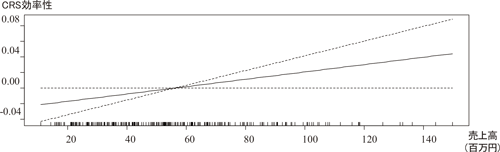 |
注1:点線は95%信頼区間を意味する。 注2:信頼区間とは、ランダムな分布に対して特定の信頼レベルを設定することによって決まる、 データのうちの特定割合のサンプルが含まれると想定される区間のことである。 |
図2 VRS効率性と売上高 |
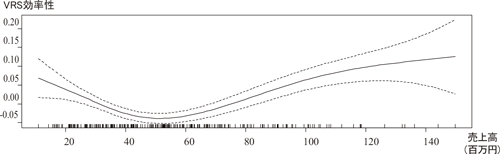 |
註:点線は95%信頼区間を意味する。 |
図3 規模効率性と売上高 |
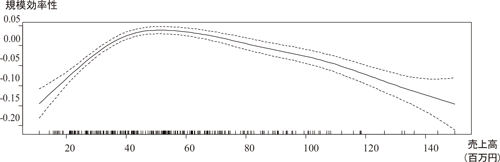 |
註:点線は95%信頼区間を意味する。 |
(2)生産効率性の規定要因と分散分解
次にDEAによって得たCRS効率性の値についてどのような生産活動に関連する指標によって規定されているのか、重回帰分析によって推定したものが表2である。数字は重回帰分析による係数、括弧内は標準誤差をあらわす。分析に際しては、単純に被説明変数に説明変数を回帰したModel1、年度ごとの生産効率性の変動をコントロールした年次固定効果を含むModel2、都道府県間の立地条件などによるものを含む生産効率格差についてもコントロールした都道府県固定効果を含むModel3の3本の計測を行っている。3本とも平均産子数や回転数の増大、生育段階での死亡率の低下(販売離乳比・離乳哺乳比)、相対肉豚価格は効率性に正の効果を、1頭当たり飼料費の増加は効率性に負の効果を示すなど概ね予想された計測結果となっている。
Model3による計測結果とデータにおける各変数の分散を用いて、どのような変数の違いが現状の家族経営における生産効率の分散をもたらしているのかを求めるために分散分解を行った。
表2 生産効率の規定要因 |
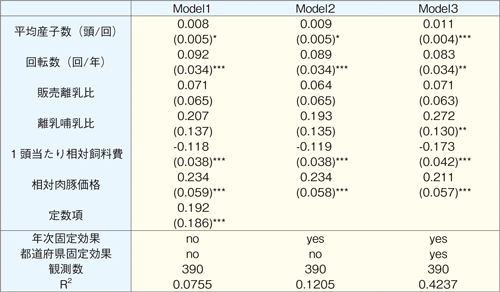 |
注1:Model1は都道府県、年次による効率性の差が無いと想定したモデル。 Model2は年次によって効率性の差があると想定したモデル。 Model3は都道府県、年次によって効率性に差があると想定したモデル。 注2:***、**、*はそれぞれ、有意水準1%、5%、10%を意味する。 ( )内の数値は、標準誤差であり、係数の有位性を検定するために用いた。 注3:平均産子数は、平均産子数は1回の出産でどれだけの肥育豚を出産できるかであり、 これが多ければ少ない母豚で多くの肥育豚を得ることが可能となり、肥育豚当たりの 母豚飼養の費用を減らすことができる。 注4:回転数は、1年間に平均で母豚が何度出産できたかであり、どれだけ母豚への種付けを 成功させることができたのかに左右されるが、これも、家畜資本としての母豚の有効活用 に繋がる。 注5:販売離乳比は年間で販売された肥育豚頭数を離乳頭数で除したものである。 本来であれば離乳した豚の何割を販売することができたのかということが肥育段階での 生産技術の指標となるべきであるが、ここでは代理指標として販売離乳比を用いている。 注6:1頭当たり相対飼料費は、各経営の1頭当たりの飼料費を各年次の全経営の 平均値で除したものである。 注7:相対肉豚価格は、各経営の1頭当たりの肉豚販売価格を各年次の全経営の 平均値で除したものである。 注8:離乳哺乳比は出生した子豚が離乳前に死亡する確率の代理指標であり、年間の 離乳頭数を哺乳開始頭数で除することによって得たものである。これは子豚 育成段階での技術指標として用いている。 注9:定数項は、全ての説明変数が0であるときの被説明変数の期待値のことである。 注10:年次固定効果は、全サンプル共通で影響を与える年次ごとの被説明変数への 影響を現す項を計測に含んでいるかを表す。 注11:都道府県固定効果は、自らの所属する都道府県内のサンプル共通で影響を与える 都道府県固有の被説明変数への影響を現す項を計測に含んでいるかを表す。 注12:観測数は、データサンプルの数を表す。 注13:R2は、決定係数であり、データの全変動のうち、モデルによって説明された部分の 大きさを表す。 |
生産効率の分散への寄与度としては都道府県固定効果によるものが最も大きかったが、計量分析に用いた指標としては、1頭当たり相対飼料費の分散への寄与度が最も大きかった。経営間の飼料要求率及び飼料購買価格の格差によって経営間の効率性格差は大きく説明されるということになる。次に大きいのは相対肉豚価格の分散であり、寄与度は4.9%である。ここからいえることは、少なくともサンプル内では、繁殖や衛生といった面での生産技術の差よりも、飼料の管理、上物率の向上や豚肉の付加価値向上、飼料の安価な購入や肉豚を販売するための交渉力の向上といった面の方が、現状の効率性の分散を説明できる、ということである。
ただし、これ以上の生産性の向上については、サンプル内では販売離乳比、離乳哺乳比ともに1前後までしか改善は望めない指標であるものの、現在のサンプルデータ上の平均値で販売離乳比は0.916、離乳哺乳比は0.910であり、これ以上改善の余地は少ない。この点に関しては、回転数においても同様である。サンプル内の平均値は2.227回であるが、豚の分娩間隔が最低でも140日程度必要なことを考慮すると、2.6回程度までしか改善は見込めない。効率性改善に回転数の向上は重要ではあるものの、生物としての限界に近い。もっとも、上への伸びしろは小さくとも、感染症などによる値の悪化は大きく生じ得るので、生産性の低下としての影響としては大きいと考えられる。現状の効率性の分散への影響は小さいにしても、繁殖・衛生面の値を保持する重要性は大きい。この点は次項で実態分析を行う(有)観音池ポーク(以下、「観音池ポーク」という。)において顕著に現れていた。
以上の効率性への寄与度の分析結果を踏まえて、次項以降では、各家族経営が、いかに飼料購買価格、肉豚の販売価格の交渉力を高め、また、産子数、分娩回転率、離乳率、離乳・哺育率、飼料要求率などの効率性も高めてきたのかの実態分析を行っていく。
その際には、宮城県の(有)東北畜研(以下、「東北畜研」という。)、宮崎県の観音池ポークの事例を取り上げた。東北畜研では、次項で整理するように、観音池ポークに比べ、繁殖めす豚、飼料の給餌内容などの統一やより多くの家族経営をネットワーク化することによって雑種生産システムを確立している。
表3 分散分解結果 |
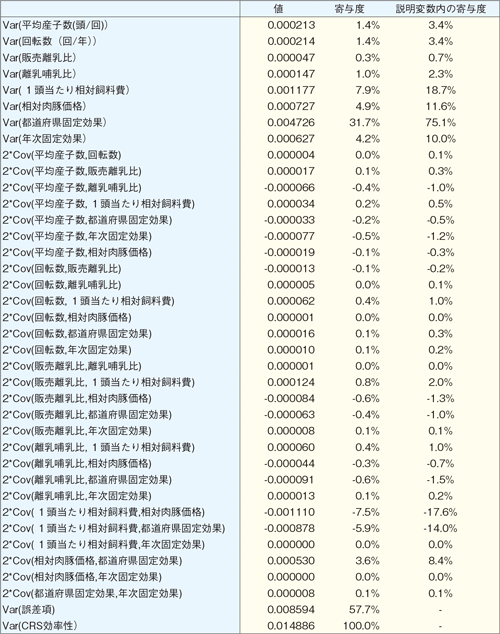 |
4 実態分析-宮城県 家族経営の成長とその要因
(1)(有)東北畜研の概要と事業内容
東北畜研は現在、山形県1戸、岩手県1戸、宮城県7戸、サブ会員2戸の計11の養豚経営によって構成されている組織である。1975年に宮城県米山、大河原、岩出山、岩手県胆沢の各地域の養豚経営が中心になって作られた任意団体、東北肉畜研究会が前身である(※5)。東北肉畜研究会の事業内容は、当初、肥育豚の共同出荷であったが、その後、生産資材および単味飼料などの共同購入にも事業を拡大させた。
1978年、任意団体であった東北肉畜研究会を解散し、(有)東北畜研を設立した。東北畜研は1979年から自家配合研究会および全国養豚経営者会議などから養豚関連の最新技術や情報を収集して経営を安定させた。東北畜研は1983年にグローバルピッグファーム(株)(Global Pig Farms。以下「GPF」という。)(※6)の設立に参加し、1992年有限会社に変え、現在、GPFのファームサービスの1組織としての役割を担っている。
東北畜研が行う事業は大きく飼料購入、種豚調達、肥育豚の共同出荷、経営改善のための取り組みの4つに分けられる(※7)。
飼料はGPF本部からの設計書をもとに複数の飼料工場と委託契約を結んで調達している。なお、この契約結果はGPF内で公開され、東北畜研以外のファームサービスも飼料契約に際してこれを用いて価格交渉することができる。複数の飼料工場と契約を結ぶ理由は、輸送費の節減および他のリスク低減のためである。飼料の調達に係る経費は東北畜研内でプールして飼料単価に算入されており、肥育豚の出荷も同様である。
前項で明らかにしたように、効率性の差を生じさせる最大の要因は飼料購買価格、肉豚の販売価格であるが、これらに関しては、11戸の養豚経営による共同購入・共同出荷によって価格交渉力が発揮されている。
また、東北畜研は種豚調達においてGPFと養豚経営との調整者の役割を担当し、種豚はGPF指定種豚場から調達している。指定種豚場は東北畜研メンバーが運営しているので、種豚の供給源と供給先が東北畜研内に存在する。つまり、東北畜研内で雑種生産システムがある程度確立しているのである。
加えて、東北畜研は毎月の定例会や婦人会を開催することで養豚経営間の交流を図り、情報交換の場を設けている。その他、仙台銀行や日本政策金融公庫との間に、長年にわたる取引に基づく信頼関係が形成されており、資金調達が比較的容易となっている。
(2)L経営の経営概要と経営成績
東北畜研の養豚経営の中でL経営を取り上げ、経営概要と経営成績を確認する。
表4は2005年に設立されたL経営の経営概要を示したものである。L経営は1農場一貫経営方式として、All-in All-outと自家繁殖めす豚更新を導入している。土地は全体730aを所有しており、そのうち、450aの林地を農場敷地に転用して養豚経営を展開している。繁殖めす豚は805頭であり、これに合わせて繁殖部門に6棟、離乳部門2棟、肥育部門11棟、環境施設の設備を備えている。なお、繁殖めす豚805頭の養豚経営を維持するため、家族構成員5人のほか、10人を雇用しており、繁殖部門に4人、離乳部門に2人、肥育部門に4人を配置している。
表4 L経営の経営概要 |
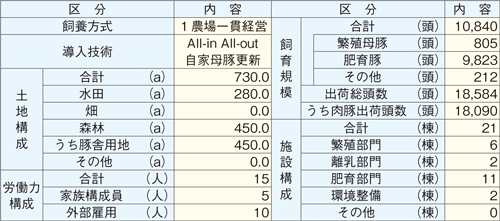 |
資料:聞き取り調査の結果による。 |
L経営の経営成績については、生産性と収益性を中心に、東北畜研とGPF全体の平均値と比較する。まず、生産性の指標においてL経営では、分娩回転率、繁殖めす豚1頭当たりの年間産子頭数・出荷頭数が東北畜研とGPFの平均値を上回っているが、繁殖めす豚1頭当たりの離乳頭数は東北畜研の平均値を下回るが、GPFの平均値よりも高い(表5)。
L経営の繁殖めす豚1頭当たり生存頭数と離乳頭数の差は3.01で、東北畜研とGPFの平均より非常に高い。これを繁殖めす豚805頭の規模と合わせて考えると、L経営では1年間約2400頭の哺乳子豚斃死が発生しているといえる。
なお、このような哺乳子豚での生産性の低位は飼料要求率と1日増体重量の下落につながる。実際、L経営の飼料要求率と1日増体重量はそれぞれ3.43と715.75グラムで、東北畜研とGPFの平均値と比べると良好な成績とはいえない。
L経営をより生産性の高い経営に成長させていくために、健康な子豚づくりに取り組む必要があり、自家繁殖めす豚更新を導入しているので、厳選な基準による雄豚の導入と候補繁殖めす豚の選別を行うべきであると判断される。
東北畜研では、生産性の高い養豚経営での技術導入が、他の養豚経営での技術導入のリスク低減をもたらす可能性があるため、L経営の生産性の改善の余地が残されている(※8)。
次に、L経営の収益性について分析を行う。L経営の月間繁殖めす豚1頭当たり総収入は6万7216円で、東北畜研の平均7万66円より低いが、GPFの平均6万4409円よりは高い。
一方、L経営の月間繁殖めす豚1頭当たり総経費は6万5500円であり、これは東北畜研平均より3600円低く、GPF平均より1794円高い。これを合わせて月間繁殖めす豚1頭当たり収支差額を見ると、L経営は1716円で、東北畜研の966円とGPFの883円より高いことがわかる。なお、通常の形で継続的であり、繰り返しながら発生する損益項目である経常損益を月間繁殖めす1頭豚当たりで計算した月間繁殖めす豚1頭当たり経常損益は、それぞれL経営が2336円、東北畜研が2103円、GPFが1352円を示しており、東北畜研とGPFの差が非常に大きいことがわかる。東北畜研が独自で行っている飼料価格交渉の成果がここに反映していると考えられる。
表5 生産性と収益性 |
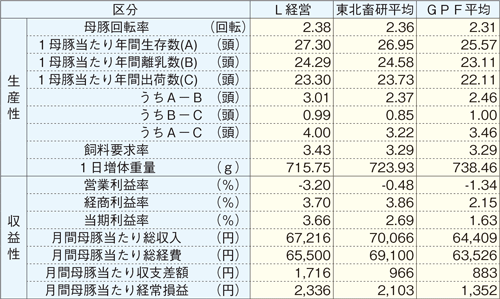 |
資料:東北畜研の資料による 註:2011年3月から2012年2月までのデータである。 |
5 実態分析-宮崎県 (有)観音池ポークの生産効率と収益性
(1)(有)観音池ポークの概要と事業内容
宮崎県都城市にある観音池ポークは、肉豚の生産、販売を行う(農)荻原養豚団地、養豚の飼養管理技術の研修などを行う「N5200会」を構成している3戸の家族経営が中心となり、銘柄豚肉の生産、契約販売を行う出荷組織としてその前身が設立された。
その後、養豚団地外から2戸の家族経営を受け入れ(ただし、1経営は2011年に離農)、2014年1月現在、4戸の家族経営によって構成されている。
各家族経営の繁殖めす豚の飼養頭数規模は約100頭で、1経営のみ120頭となっている。グループ全体での出荷頭数は約8000頭であり、販売金額は約3億円である。
また、観音池ポークは、食肉加工品の製造・販売などを行う直売所1店を設立しており、2012年に現在の組織に改編している(旧とんとん百姓村)。
すなわち、観音池ポークにおいても東北畜研ほどではないにしろ、4家族経営による共同出荷によって価格交渉力が実現されている実態が推察されてくる。
(2)(有)観音池ポークの生産効率と収益性
観音池ポークの中心である馬場氏の経営の生産効率性に関しては次の通りである。繁殖めす豚1頭当たり年間出荷頭数は、16頭~21頭台と大きな変動が確認される。
特に、2010年、宮崎県で発生した口蹄疫の際には、馬場氏の経営では移動制限区域に指定されたため、出荷日齢に達した肥育豚の出荷が遅れ、豚舎内の肥育豚の移動に混乱が生じた。この結果、PRRSが日齢の異なる肥育豚でも発症することとなり、事故率が高くなり、翌2011年には総出荷頭数、繁殖めす豚1頭当たりの出荷頭数の大幅な低下をもたらした。また、馬場氏の経営では、離乳頭数や分娩回転率においても変動が確認され、産子数、離乳・哺育率、離乳率、分娩回転率の効率性にも問題が発現していた。
ただし、配合飼料価格が高騰した2008年、2013年に注目すると、総出荷頭数は2008年1670頭、2013年1821頭と、他の年に比べると低くなっているが、販売単価や上物率を他の年よりも高めていた。2008年、繁殖めす豚1頭当たりの飼料費は前年よりも約4万円高くなり、繁殖めす豚1頭当たりの売上総利益はマイナスの値を示していたが、経常所得は確保されていた。また、先に言及した通り口蹄疫が発生した翌2011年には技術水準が大幅に低下し、繁殖めす豚1頭当たりの売上総利益は1万6278円のマイナス、経常損失も5万768円となっていたが、経常所得は確保されていた。
一方、年間の専従者給与を確認すると、その値も大きく変動している。2005年は1人当たり約400万円であったが、配合飼料価格が高騰してくる2007年、2008年では専従者給与は減少していた。
また、2009年、2010年には、再び配合飼料価格が下落する中で専従者給与も再び増加していた。すなわち、配合飼料価格の高騰による家族経営への影響を1人当たり農業所得や専従者給与を変化させることで対応してきた実態、つまり、家族経営の強靱性を発現させていた実態が明らかとなってくる(※9)。
以後、2012年、2013年は技術水準も上昇傾向にあり、特に2013年は販売単価も高くなったことからも、収益性や財務内容を改善させている様子が推察されてくる。
6 おわりに
2003年以降の10年間、国内飼養頭数が約960万頭で推移してきた一方、会社の200頭以上の階層への飼養頭数の集中が進展してきた。すなわち、国内の構造再編が進展してきた。もちろん、これまで、さまざまな論者が指摘してきた通り、今日の構造再編を進捗させてきたのは、会社の200頭の以上の階層の中でも、特に、その飼養頭数規模が統計を大幅に上回る大規模法人経営によるものと推察される。
このため、統計を大幅に上回る大規模法人経営の実態に関しては、さまざまな論者によって分析がなされてきた(※10)。ただし、家族経営が雑種生産システムをネットワークを形成することで確立してきた事例が生産効率性をどの程度上昇させているかの分析に関しては、これまで実態・計量分析の両面から分析されてくることはほとんどなかった。
そこで、本報告では家族経営が雑種生産システムをネットワークを形成することで確立してきた事例の生産効率性に関しての計量・実態分析の両面から明らかにすることを課題とした。
計量分析に関しては(公社)中央畜産会『先進事例の実態報告』から、実態分析に関しては雑種生産システムをネットワークを形成することで確立している家族経営の2事例を取り上げ、その生産効率性とその向上のための要因分析を行うことを課題とした。
計量分析では、養豚経営の生産性・規模の経済に対して数量的に明らかにすることを課題とした。その際、包絡分析(DEA)を用いて、養豚経営における生産フロンティアの推定と、それぞれの経営の生産効率性を求めた。その上で、単純な投入-産出だけでなく、生産の各段階での生産能力の影響が最終的な生産性にどのような影響を与えているのか分析することを主眼とした。その際、(公社)中央畜産会『先進事例の実績指標』をデータとして用いた。
DEAによる効率性計測の結果から、養豚生産の効率性には大きいというほどではないにしろ、経営間で生産効率性には差があること、規模間で規模の経済が無いと考慮するのであれば、大規模経営ほど高い効率の経営を行っていること、規模間の投入-産出方法の違いによる生産性の差を考慮したVRS効率性においても、大規模経営では生産効率性が高い一方で、小規模経営でも効率性は高くなること、売上高5000万円から1億5000万円の領域では規模の経済は観測されないこと、などが明らかとなった。
ここでは、これらの点を踏まえ、生産段階のどの段階での技術水準がCRS生産効率性に寄与しているのかを明らかにするため、重回帰によって生産効率性の規定要因の寄与度をそれぞれ分析し、さらにその分散を分解することで、どの要因の変動が現在の養豚経営の効率性の決定に大きく寄与しているのかを明らかにした。そこでは産子数と売上高、回転数と売上高、販売離乳比と売上高、離乳哺乳比と売上高、相対飼料費と売上高、相対肉豚価格と売上高が、主に効率性への寄与する変数として説明された。
実態分析としては、輸入審査の厳格化などにより在庫量が減少したこともあって、2013年度は、配合飼料価格が2008年度の水準を超える中でも、豚肉価格が安定的に推移することによって収益を確保し財務内容を改善している家族経営、法人経営の“層”としての存在が推察されてくる。
ただし、宮城県の東北畜研では、哺育・離乳率、離乳率、飼料要求率で効率性の改善の余地が残されている。また、宮崎県の観音池ポークでは、共同購入による価格交渉力、産子数、哺育・離乳率、離乳率、分娩回転率の効率性の改善の余地が確認された。
本稿は、畜産関係学術研究委託調査報告書の要約です。報告書の全文は、当機構のホームページに掲載しています。
(※1)雑種生産システムの研究成果の整理に関しては、宮田剛志(2010)『養豚の経済分析』農林統計出版,pp.17-22。
(※2)本報告では、門間敏幸編(2009)『日本の新しい農業経営の展望-ネットワーク型農業経営組織の評価-』農林統計協会,pp.1-6、で整理されている取引費用理論や組織間関係論からネットワーク型農業組織と位置づけている。もちろん、企業形態論から分析を加えた場合、新山陽子(1997)『畜産の企業形態と経営管理』日本経済評論社,pp.129-133や申錬鐵・柳村俊介(2013)「日本の養豚経営における生産者出資型インテグレーションの形成と課題-グローバルピッグファーム㈱を事例として-」北海道大学・農学部『農経論叢』Vol.68の「農業生産者の側からのインテグレーション」や「生産者出資型インテグレーション」と位置付けることも可能となってくる。
(※3)中島亨(2013)「輸出国の価格が最終製品価格に波及するプロセスー飼料原料価格の畜産経営への影響」『農業と経済』2014年4月臨時増刊号,p.34。
(※4)包絡分析(DEA)、確率的フロンティアなどの生産フロンティアの計測については、Coeli Coelli, T., Rao, P., O'Donnell, C., and Battese, G. E., (2005)An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis,springer. Cooper, W. W., Seiford, L. M., and Tone, K.,(2006)Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver software2nd edition, Springer. 末吉俊幸[2001]『DEA―経営効率分析法―』,朝倉書店. などを参照。
(※5)東北畜研の前史の詳細に関しては、申錬鐡・柳村俊介(2014)「養豚経営者運動と生産者出資型インテグレーション」『農業経営研究』第52巻第3号,pp.59-64を参照。
(※6)GPFの事業概要や財務内容に関しては、杉本隆重・高橋弘・赤地勝美(2011)「グローバルピッグファームの技術・情報のナレッジマネジメント」日本農業経営学会編『知識創造型農業経営組織のナレッジマネジメント』農林統計出版、pp.170-176,を参照。
(※7)東北畜研の事業内容に関しても、申錬鐡・柳村俊介(2014)、を参照。
(※8)申錬鐡・柳村俊介(2014)、を参照。
(※9)新山陽子(1997)『畜産の企業形態と経営管理』日本経済評論社,pp.60-66。
(※10)宮田剛志(2010)、等を参照。