【要約】
わが国の牛肉の自給率は年々低下し、一時期30パーセント台前半まで低下した。平成12年以降、BSE発生などの影響もあり若干盛り返したとはいえ、40パーセント台前半の水準に止まっている。特に和牛以外での落ち込みは大きく、交雑種・乳用種の生産は大幅に減少してきた。
本稿で紹介する「内藤あんがす牧場」は、「赤身肉」の美味しさに拘り、一貫経営への取り組みや飼料の切り替えなど“安全・安心の担保”に腐心しながら、今では稀となったアンガス種を一貫して守り抜いている経営である。経営主のこうした姿勢が生活協同組合の支持を受け、同組合との「固定価格」「1頭買い」といった取引を切り開いてきた。本事例は、強固な基盤に立脚する「農商工連携」の取り組みと言える。
はじめに
昭和45年の90パーセントから平成23年の40パーセントへ − これは、わが国の牛肉の自給率(重量ベース)の推移である。40年余で50パーセントの下落であるから、今何かと話題に登るカロリーベース自給率の低下(60%から39%へ21%の低下)を大幅に上回る。わが国で初のBSE感染牛が発見され、牛肉消費が大幅に落ち込む前年の平成12年は34パーセントと更に低かったことを考えると、40パーセントはむしろ“実力”以上の数値なのかもしれない。しかし、その数値にも赤信号が灯ってきた。なぜなら、消費が徐々に回復する一方、輸入牛肉の月齢制限が20カ齢以下から30カ齢以下へと緩和され、アメリカからの輸入量が増加していると報じられているからである。ここまで落ちてしまった国産牛肉の生産をいかに守っていくか、わが国は大きな転換点に立たされているのではないだろうか。図1 種類別飼養頭数と食料自給率(牛肉)の推移 |
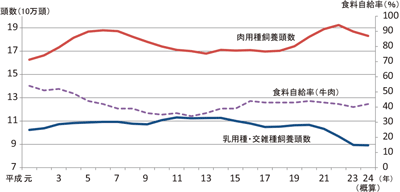 |
資料:農林水産省「畜産統計」、「食料需給表」 注:平成24年の食料需給表は概算値である。 |
 |
写真1 収穫祭では、自然の中でアンガス牛の焼き肉や 近隣でとれた野菜を活かした料理が振る舞われた |
“手軽な値段で美味しい牛肉を”−アンガス種への拘り
内藤あんがす牧場の牧場主・内藤順介氏(56歳)は、昭和55年に東京農大を卒業後、1年間、道営肉牛牧場(えりも町)で実習した。当時、彼の実家は林業を営んでおり、本格的にアンガス種の肥育を開始する平成元年までにはまだ間があった。何故、肉牛牧場での実習だったのか − 内藤氏は、木材の輸入自由化と輸入増加の中で、林業の将来が決して明るくないことを見越し、それに代わる、広大な林地を利用できる何か、例えば放牧型の肉用牛生産の可能性などを追い求めていたのかもしれない(父の代には林業も大きく陰り、椎茸などのキノコ栽培も手がけ、昭和48年にはアンガス種を下草刈り用として導入していた)。道営肉牛牧場では、広大な草地資源に立脚した、外国種を主とした肉用牛飼養を学び、その後は、カナダ・アルバータ州で本格的に放牧型の肉用牛飼養の実習経験を1年間積んだ後、平成元年に肉用牛の一貫経営に乗り出す。何故アンガス種か。1つは既に林地の下草刈り用にアンガス種を飼養していたこと、2つは、当時、農林水産省や北海道庁もアンガス種やヘレフォード種などの放牧中心の飼養管理が可能な赤身肉の品種を積極的に振興していたことが挙げられる。しかし、そればかりではない。「多くの人に“美味しい牛肉”を手軽な値段で食べてもらいたい」という内藤氏の思いが、アンガス種に向かわせた大きな動因だったのではないだろうか。当時の北海道内では、牛肉は“霜降り=高価”というイメージが強かったからか、肉類消費は豚肉や鶏肉、羊肉が中心で、牛肉消費は非常に少なかった。しかし、道営肉牛牧場とカナダでの経験は、これまでの牛肉に対するイメージを大きく変えるものであった。“霜降り=高価”な和牛ではなく、“赤味”ではあるが美味しく、手軽な値段の牛肉があったのである。 |
写真2 内藤夫妻。背後には広大な放牧地が広がる |
表1 内藤あんがす牧場の経営概況と特徴 |
 |
資料:内藤氏あんがす牧場での聞き取りにより作成 |
図2 北海道における肉専用種の品種別繁殖牛飼養頭数の推移 |
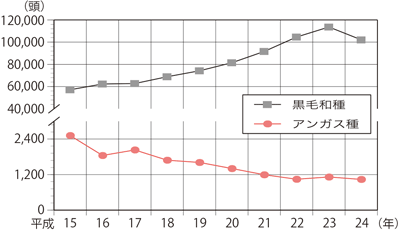 |
資料:北海道「畜産振興調べ」各年次 注:平成24年のアンガス種の値はヘレフォードなど他の外国種を含む |
図3 牛肉需給の推移と関税率 |
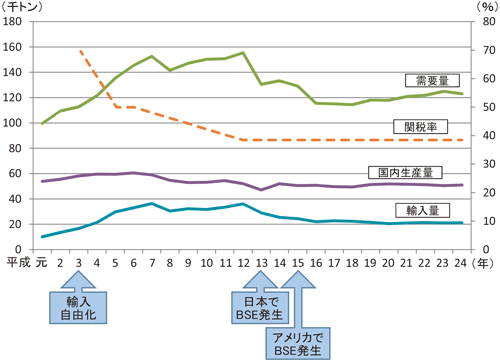 |
資料:農林水産省「食肉流通統計」、財務省「貿易統計」各年次。 (独)農畜産業振興機構「畜産物需給の推移」より引用 |
BSEを契機に配合飼料を減らし、もと牛の国産・自給へ
平成13年にわが国初のBSE感染牛が発見された。輸入肉骨粉がその原因とされ、また、アメリカなど諸外国での発生の可能性も否定できない状況となっていた。輸入肉骨粉は飼料の問題、諸外国での発生の可能性はアンガス種の繁殖もと牛の問題に直結する。BSE問題は出自不明な飼料や繁殖もと牛を避け、“出自の明らかな”ものに切り替えて行く必要性を明らかにしたと言える。
当時、内藤牧場では、単味飼料を自家配合して使用していた。もちろんその単味飼料は輸入された物であり、生産現場まで出向いて生産状況を確認することは不可能に近い。安全・安心の担保のためには、輸入単味飼料を用いた自家配合を出来る限り減らすしかないと考え、自給飼料(デントコーン)プラス若干の配合飼料など、様々な給餌方法を精力的に試した。放牧に適しているアンガス種の特性からすれば粗飼料のみでも良さそうであるが、そうすると脂肪が外側に付きやすく、歩留まりが悪くなり市場評価が下がってしまう。これ以上価格が下がっては、経営的に成り立たない。そんな中で行き着いたのが「放牧+自家製デントコーンサイレージ+配合飼料」の給餌方法であった。春から冬までは昼夜放牧を行い、肥育期間に入ってからは舎飼いで、自家製デントコーンサイレージと配合飼料を給与する。もちろん配合飼料は可能な限り出自の明らかなものを使うことは言うまでもない。こうすれば「アンガス種の特性を最大限発揮させ、柔らかく美味しい牛肉が生産できる」と内藤氏は言う。しかし、出自の明らかな配合飼料と言っても100パーセントの保障はない。いかにして配合飼料から脱却するか、その模索が後述するエコ・フィードの取組みへと繋がるのである。
さて、もう一方の問題は、繁殖もと牛である。繁殖もと牛の多くは当初、アンガス種を中心に、時にはマリーグレー種も含め、オーストラリアなどからの輸入に頼っていた。輸入元を限定するなど、安全・安心を担保するために様々な措置を講じていたものの、自分の目で直に確かめることはなかなかできなかった。トレーサビリティを完全に確保し、安全・安心を担保するには、繁殖もと牛を国産あるいは自給に切り替える必要があると考え、平成13年をもって輸入もと牛の導入を中止した。
こうした内藤あんがす牧場の地道な取り組みが、新たな牛肉生産者を探していたパルシステム生活協同組合連合会(以下、パルシステム)の目にとまり、産直取引の道が開かれて行くことになる。
 |
写真3 春から秋は親子で放牧地で過ごす |
パルシステムと「コア・フード」牛肉
パルシステムは、首都圏1都9県の10地域生協が加盟する生協連合会である。「無店舗型」を特徴とし、平成24年度末で138万世帯の会員を擁し、1930億円の供給高を誇る。注文はカタログに基づいて行われ、注文に沿って週1回の戸別配送が行われる。古くは複数戸からなる班への配送であったが、次第に戸別配送が増え、今では戸別配送が9割以上を占めている。店舗型に比べて無店舗型(カタログ型)の方が、物品に対する「思い」や「拘り」などを伝えやすいせいもあってか、産直産地の生産者のみならず、様々な生産者などとの交流も活発に行われていると言う。
特にパルシステムでは安全・安心の担保に大きな力を注いでおり、厳しい基準を設けつつ、国産品を中軸とした品揃えを行っている。中でも肉類での産直比率は高く、牛肉で90パーセント、豚肉で94パーセントに達し、鶏肉に至っては100パーセント産直取引となっている。これらの食肉の産直取引では「可能な限りの資源循環によって自給できる畜産の構築」が目指されており、パルシステムではそれを「日本型畜産」と呼んでいる。それは、ただ単に資源循環に配慮し国産自給飼料を活用すれば事足りる、と言うものではない。アニマル・ウェルフェアにも充分に配慮し、家畜にとって快適な飼育環境が提供されていること、そして食と農をつなぎ、消費者とともに生産者も幸せになれるような畜産が目指されることを要するのである。
また、パルシステムの取扱食品(青果物や畜産物)は、それらがいかなる基準に基づいて生産されたかによって、3つのランクに区分けされている(図4)。ボトムが「慣行栽培」、次が「エコ・チャレンジ」、そしてトップが「コア・フード」である。慣行栽培と言っても、何でも良いというわけではなく、「生産者が明確で農薬使用状況や土づくり資材が確認できるもの」とされている。「エコ・チャレンジ」はパルシステム独自の『農薬削減プログラム』を実践している産地、そして「コア・フード」は有機JASもしくはそれに準じた基準の下に生産されたもの、といった条件が付けられている。
図4 パルシステムのコア・フードの位置づけ |
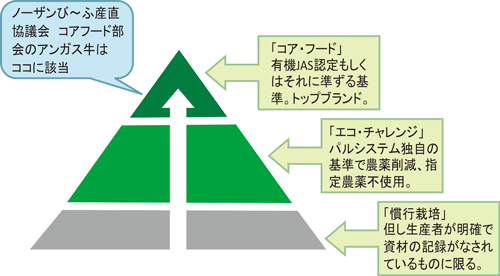 |
資料:パルシステム資料による |
放牧や国産飼料、抗生物質不使用、赤身など、いずれもパルシステムの理念を表すものと言って良い。中でも特筆されるのは“1頭丸ごとの買い支え”である。例え産直牛肉であっても、通常は「ロース」や「もも」「バラ」などの部分肉取引が中心で、“1頭丸ごと”は珍しい。なぜなら売れる部位、売れない部位があるからである。しかし、生産者は部位毎に生産することはできない。とすれば、わが国の畜産業を守り発展させるためには、“1頭丸ごと”の取引を行う必要性が出てくるわけである。
ところで、パルシステムのコア・フード牛肉への歩みは実に古く、今から30年程前の昭和59年にその源流が始まった。同年、パルシステムの前身生協の一つが、北海道の農協と赤身のヘレフォード牛肉の産直取引を始めたのである。産直取引はその後も続いていたが、昭和60年頃から“日米牛肉・オレンジ交渉”が始まったことから、牛肉の輸入が自由化されれば、アメリカ産牛肉が大量に輸入され、特に赤身の牛肉生産は大きな打撃を受けると考えられた。いかにして国内の、特に赤身牛肉の持続可能な生産を守っていくか、パルシステムにとっても大きな課題だったのである。
パルシステムでは当時、北海道内で広がりを見せていた、人間の食料と競合しない草資源を利用した、しかも抗生物質などの薬剤に頼らないアンガス種やヘレフォード種の生産に着目し、産直取引を更に広めることになった。その際、それまでホクレンや単協、生産者と個別に結んでいた産直契約を一本化し、流通過程の合理化を図るため、平成5年に「COOPノーザンび〜ふ産直協議会」を結成し、事務も一本化した。ホクレンが事務局を担い、えりも肉牛牧場や阿寒町営牧場、JA足寄町など8団体が当初の構成員であった。
当初、ヘレフォード種のほか、日本短角種やアンガス種を取り扱っていたが、農林水産省の政策変化もあって繁殖牛の供給が減少し、まずヘレフォード種の供給が困難になった。また、当初から1頭買いであったことから、パルシステムは部位別の需給調整に苦心し、更に、粗飼料中心の肥育であったため、消費者の求めるような食感や色味が出にくく、飼料選定などに大いに苦労した。
こうした試行錯誤の中でコア・フード牛肉の供給、消費の姿、骨格が固まり、平成12年に産直取引が開始されることとなった。当初、日本短角種とアンガス種の2種でスタートした。
「コア・フード」牛肉−その生産態勢と購入・消費のあり方
コア・フード牛肉は、生産側は「COOPノーザンび〜ふ産直協議会」の「コア・フード牛肉部会」に属する5戸の生産者によって、消費側は事前予約した組合員によって支えられている。コア・フード牛肉には日本短角種も含まれていたが、その後、生産が途絶え、今ではアンガス種のみとなっている。出荷頭数や価格などは「コア・フード牛肉部会」を中心に調整・決定される。気候など諸条件や思わぬ疾病などにより、時として肥育度合などが悪い場合も無いとは言えないことから、それら諸条件を出し合い、5戸で予定通りの出荷頭数を確保している。
取引単価は年間固定価格である。それは、市況や各種補助金の状況、飼料などの調達費用などを勘案して決められており、乳用種去勢牛より高く、和牛より低い水準となっている(図5)。最近では交雑種の価格が下落基調であったため、それに取引価格が接近してきており、飼料や各種資材などの価格上昇があるものの、パルシステムとの取引価格が相対的優位になりつつあると言える。また、生産者の生産意欲を高める意味も込めて、取引価格設定に当たっての枝肉歩留まり率を71.5パーセントと固定し、それを上回れば加算され、下回れば減算される仕組みをとっている。肉付きが良く歩留まりの良い肉牛を育てよう、という生産者のインセンティブも、大いに湧こうというものである。
図5 枝肉卸売価格(東京市場)の推移と パルシステム契約価格 |
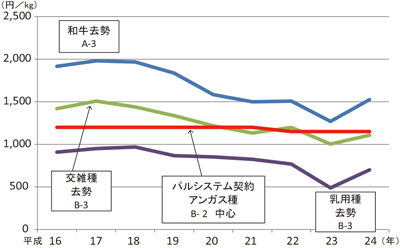 |
資料:農林水産省「食肉流通統計」 (独)農畜産業振興機構「畜産物需給の推移」より引用 |
図6 「コア・フード牛」登録セット数の推移 |
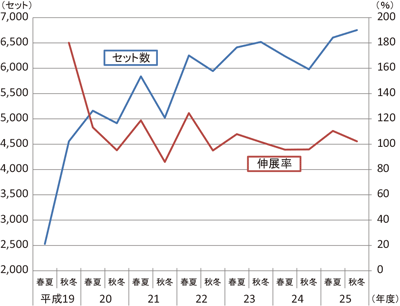 |
資料:パルシステム資料より作成 |
全ての飼料の出自を明らかに−配合飼料からエコ・フィードへ
平成16年、内藤あんがす牧場は、コア・フード牛肉の生産者としてパルシステムから大いなるエールを送られ、早速に応諾した。赤身肉や、安全・安心の追求など、内藤氏が長年追い求めてきたものとパルシステムの考えが合致したからである。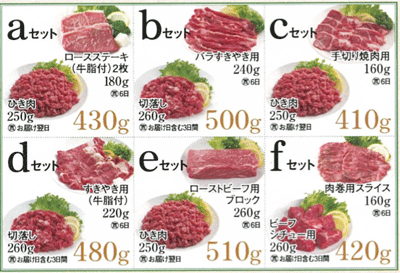 |
写真4 消費者にはこのようなセットで届けられる |
 |
写真5 エコ・フィードの一例。おから、ケール粕など |
内藤あんがす牧場では概ね、飼料業者を通じて様々なエコ・フィードを購入し利用している。食品の生産状況などによって、入手できるエコ・フィードの種類と量は変化するが、その都度内藤氏は牛の様子を良く観察し、種類や量を計算しながら給与している。平成25年度に利用しているエコフィードは、ビール粕とおからは継続入手できているものの、ケール粕は在庫限りで、昨年まで利用していたボイルジャガイモは入手できず、代わりに生のくずジャガイモを利用している(表2)。
表2 エコフィードの使用状況 |
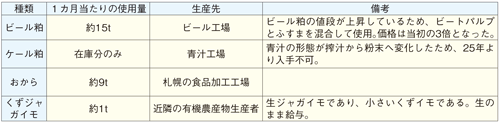 |
資料:内藤あんがす牧場での聞き取りにより作成 |
エコ・フィードの利用には他の難点もある。それは、水分含有量が多いため、冬期に凍結する恐れがあることである。水分含有量が55パーセントを超えると、内藤あんがす牧場が立地する安平町では凍結してしまい、給与するのが難しくなってしまう。しかし、内藤氏の理念、そしてパルシステムの理念の達成のために、エコ・フィードを利用するための努力を続けているのである。
ところで、内藤あんがす牧場では、概ね27カ齢の肥育牛を1カ月当たり3〜6頭、年間60〜70頭出荷している。頭数の上下幅は、月齢別の牛の在庫状況や飼料の確保状況など生産者側の事情によるものであり、決してパルシステムからの要請ではない。先に触れたように、生産者側の変動は産直協議会において調整されているのである。
また、経営的な面に関しては、「パルシステムとの取引価格は安定しており、価格も比較的優位である」としながらも、それだけでは十分な採算が取れているとは言えず、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(マルキン事業)の補助金などを含めて、ようやく赤字にならない程度である。牛肉輸入自由化後の肉牛用経営の厳しさの一端を伺い知ることができよう。
おわりに
このような厳しい経営環境であるとは言え、内藤あんがす牧場とパルシステムの取り組みに意味が無いと言うことでは決してない。むしろ、大いなる意味 ― 日本の畜産、広くは日本の農業を守るための珠玉の意味がそこには込められていると言える。“農”は今日、“農”だけでは成り立たない。もう一方の“消費”がどうしても必要不可欠なのである。しかも“農”はどんな“農”でも良く、“消費”はどんな“消費”でも良いと言うものではあるまい。お互いに共鳴し、響き合うような関係の構築が重要なのではないだろうか(図7)。アンガス種の特性を活かした、牧草主体の「安全・安心」に配慮した生産体制や、どんなことがあっても食べ支え続ける態勢の構築などに見い出されるように、そこには大いに共鳴しあえる諸要素がちりばめられているのである。もしかしたら、これこそが本当に追い求めなければならない“農商工連携”と言われる姿、“6次産業化”の姿なのかもしれない。
国際穀物相場上昇の煽りを受け、リーズナブルなエコ・フィードの入手が次第に困難となる中で、ここは「農・農連携」「農・食品産業(工業・外食・販売業) 連携」など多様な連携の網の目を張り巡らせ、規格外品や食品残さの入手などの道を拓いていくことも、今後必要とされよう。内藤あんがす牧場のますますの発展を願って止まない。
図7 パルシステムによるコア・フード牛肉買い支えの構造 |
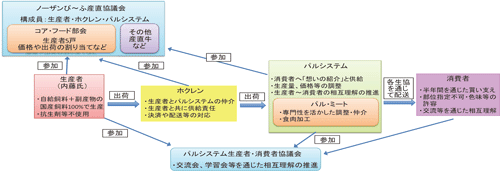 |
資料:パルシステムでの聞き取り・資料により作成 |