【要約】
我が国では、人口の都市部への集中により、地方では限界集落が増加している。このような場所で何ができるのか。このまま、限界集落がさらに荒廃していくのをなおざりにしていくのか、難しい課題である。このような中、休耕田や耕作放棄地などの地域資源を活用した飼料費低減の取り組みが少しずつ拡大しているが、高齢化などにより耕作放棄地が急速に拡大するなど、地域資源の活用が進んでいない地域も多い。そのような状況のなか、岡山県高梁市では、耕作放棄地の解消策として、「
1.はじめに
日本の土地は非常に狭い、と言われる。確かに世界地図で見れば、他国に比較して小さな国である。日本の土地面積は3779万ヘクタールと、世界の土地面積の0.28パーセントであり、世界の国の中では、第60位の面積である。その狭い日本国土の73パーセントは山地であり、66.4パーセントが森林である。この土地は果たして使えないのか。計算すると、山として使用が難しいと思われている土地は、約2759万ヘクタールということになる。土地は国の財産である。この土地は国益を生むはずである。山地や放棄された農地であふれる中山間地域、そこから人が流出した限界集落を、日本人の知恵を結集して、そして新しい技術を用いて、できる限り活用していくことが今後重要となるのではないだろうか。
本稿で取り上げる岡山県高梁市では、耕作放棄地における日本短角種を用いた放牧に取り組んでいる。
高梁市は、岡山県の中西部に位置しており、広島市と県境を接する。平成25年時点の人口は約3万4000人で、面積は約5.4万ヘクタール、うち耕作放棄地が897ヘクタール、基幹産業は農業である(産出額約90億円)。高梁市には、人口の50パーセントが65歳以上という集落(限界集落)が223ヵ所あり、岡山県内では最多ということである。本稿では、「地備栄倶楽部」という組織をつくり、限界集落に住む高齢者が、楽しみながら、日本短角種を用いて放牧を行っている高梁市の取り組みを事例に、放牧による地域資源の活用について報告する。
2. 「地備栄倶楽部」における耕作放棄地放牧の取り組み
平成20年11月、高梁市内で最初に日本短角種の放牧が始まった場所は、高梁市玉川町増原であった。放牧地は増原地域の2つの集落にまたがり、当時の集落人口は29名、65歳以上が59パーセントという小規模高齢化集落、いわゆる限界集落であった(写真1)。「地備栄倶楽部」事務局の徳田匡彦氏によると、増原地域における放牧の取り組みは、まず任意団体である「高梁短角牛生産組合」を平成20年7月に立ち上げ、農業協同組合に4頭の日本短角種子牛の購入を依頼し、それらの牛を生産組合に貸し付けてもらうことで始まった。当時は、高梁市の職員十数名も作業に参加していたが、現在は関わりが少なくなってきているという。放牧候補地の借り上げは、生産組合の組合員でもある農業委員の栗本和克氏が中心となって進めたもののなかなか進まず、土地の確保は困難であったことから、借り上げではなく、管理を請け負うという形で2年半の期限を設けて始められることになった。こうして3ヘクタールの農地が放牧用地として集積された。当初導入する牛の品種に関しては、黒毛和種や褐毛和種もよいが、放牧適性が高いこと、基盤は役牛として働きものの南部牛であり、かつ寒さにも強いこと、乳量が多く子育て上手なこと、成長速度が速いことなどから、日本短角種を導入することとなった。もちろん生産される牛肉は、霜降り肉になりにくいことは承知していた。また、放牧開始に当たっては、資金が必要であるが、その点に関しては生産組合を設立した際に、農家・サラリーマンなどからなる賛同者である組合員60名から組合費として117万円の資金が集まった。当時、高梁短角牛生産組合設立の条件は、実証放牧を2年半実施し1度解散すること、また、解散時に組合費はできるだけ返金したいが保証はできないこと、であった。
 |
写真1 放牧開始前の農地の様子(平成20年11月) |
写真2 高梁短角牛生産組合の休耕田放牧地の変遷(徳田匡彦氏提供) |
 |
放牧開始直後(平成20年11月上旬) 放牧開始2週間後(平成20年11月下旬) |
 |
平成22年11月中旬(写真1と同じ場所から撮影) 平成25年5月 |
表1 高梁型放牧年間管理費 (成牛9頭、子牛4頭規模) |
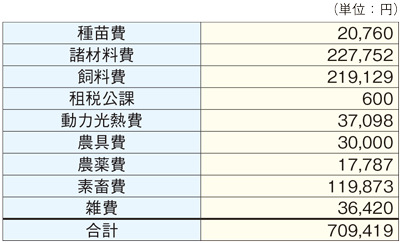 |
資料:「地備栄倶楽部」聞き取りにより作成。 |
増原牧野は、現在も栗本和克氏(元高梁市農業委員、増原農地保全組合代表)を中心に管理され、繁殖牛10頭前後での経営が中心となっている。黒毛和種の受精卵を移植した雌牛も過去には4頭いたが、現在は日本短角種に専念している(写真3)。放牧牛は非常に人になれており、非常におとなしく、餌付け用のジャガイモをおいしそうに食べていた。今後、山を含めて、放牧地をさらに3ヘクタール増やす予定ということだった。
写真3 現在の増原牧野の様子(左下段の写真は栗本氏) |
 |
楢井牧野は、市街地の東部に位置しており楢井農地保全組合の棚田放牧地である。牛2頭と育成牛2頭の合計4頭の日本短角種を、農産加工“ならい”を経営される代表の川上功氏が棚田の休耕田を活用して飼養している(写真4)。放牧地を借地し、広げていくことは続けたいが、地権者の説得が難しいと感じている、とのことである。地権者に放牧地の雑草がきれいになっている状態を見せることで、土地借用のための説得ができるのである。
写真4 現在の楢井牧野の様子(左上段は川上氏) |
 |
牧野にある設備
|
3.終わりに
今回取り上げた「地備栄倶楽部」の取り組みは、調査に協力いただいた栗本氏および川上氏にしても、本当に気軽に、楽しそうに牛を管理されていたことが印象的であった。牛に会うことを、日々の楽しみにされている。牛も非常に穏やかで、ゆったりと放牧されていた。しかしながら、放牧地の確保については、筆者らも耕作放棄地放牧の実証試験時に経験したが、かなりの苦労があったとのことである。高梁市の方で放牧地の候補地をいくつか挙げて地権者へ説明に行ったが、ほとんど断られた。先に紹介した玉川町増原地域でも同様に、数十名の地権者から断られていた。そこで、当時農業委員で、増原の地域住民であった栗本氏が再度説得したところ、地権者より承諾を得られた。その内容は、前述のとおり、借り上げではなく「土地管理の請け負い」ということであった。川上氏も言われていたように、放牧牛飼養に対する地域の理解を得ることは難しい。今では地域住民や地権者も少しずつ理解を深め、協力的になってきたということだ。最後は地域における人の信頼関係ということだろう。放牧牛のいる草地畜産の原風景は、人を和ませる。国内の未利用な山や森林、中山間地は日本の財産であり、ここには黙っていても生産される植物と環境がある。この植物に価値をつけるために、牛を用いて、癒しの景観だけでなく、牛肉といった価値の高いたんぱく源を生産することは、今後の日本の重要な課題となるのではないだろうか。「地備栄倶楽部」では、そこで育てた日本短角種を適宜食せるようになっており(写真5)、まさに国内の"未利用地 ― 植物資源 ― 耕作放棄地の活用 ― 農地保全・景観保全 ― 牛 ― 牛肉生産 ― 地備栄牛の食味"、という関係が成り立ち、それを実感できる場なのである。
 |
写真5 地備栄牛のステーキ |
放牧ということでは、面白い偶然があった。著者も放牧による牛肉生産を目指す研究を推進している。高梁市は、「山地酪農」を提唱した植物学者の猶原恭爾博士の出身地である。ご実家は、過去に薬局を営まれていたようである。現在は営まれていないが、家族の方が今も住まれており、家屋が残っていた。猶原博士は日本の急峻な山地でも、野シバを活用し、大雨などでも放牧地の土砂流亡を防ぎ、表土も保全し、放牧地のよい環境を保ち、飼料としても優れた安定した草地を作り、その草地を経営の軸として営む放牧酪農を「山地酪農」として推奨した。猶原博士は、その手法を確立するため、自ら牛を飼い酪農家としての実践を10年間も行った。猶原博士は、研究が現場の酪農家にいかに実践できるかが重要であるという認識から現場主義を貫いた[1]。その活動は全国に広がり、岩手県田野畑村、秋田県千畑村、高知県高知市、南国市、島根県太田市などでは数名から数十名のメンバーで山地酪農研究会が結成され、グループとしての活動も行われた。戦後十数年を経て高度経済成長期に入った頃、一般の酪農家は拡大路線、すなわち工業型酪農の普及が進んだが、猶原博士はその拡大路線に異議を唱え、永続性のある山地酪農を千年続く酪農形態として提唱し続けた[1]。現在こそ、この猶原博士の「山地酪農」の概念を日本の未活用な土地、特に山地に活用し、山地を活用して国益を生む、すなわち日本人のための基盤的なたんぱく源となる牛乳や牛肉を生産する時かもしれない。使用されていない山地を活用し放牧地を作れば、TPP政策に日本がさらされても、自給飼料型の畜産として畜産業は生き残れるかもしれない。
スウェーデンでは、未来研究として環境保護庁から「2021年のスウェーデン」が発表された。このプロジェクトリーダーであるアニタ・リンネル氏は、未来の実現可能なシナリオとして“持続可能な社会構築の戦略”を提言した[2]。この戦略の基軸は、食料を自給し、スウェーデンの60万ヘクタールの農地を“エネルギー源としての作物”のために確保することであった。肥沃な土と牧草地を保全しながら、窒素やアンモニアの流出を減らし、リンは効率的に循環させる戦略である。畜産についての戦略も打ち出された。それは養鶏や養豚に見られる従来型の集約的な畜産を基盤とした“タスク・マインダー”という概念、もうひとつは、草食動物や国土、特に森林などを活用したエコロジカルな畜産を基盤とした“パス・ファインダー”という概念による戦略であった。“パス・ファインダー”では、牛や羊は草地で放牧され、景観と牧草地、生物多様性が維持されることになる。現実に持続社会を形成するには、白か黒かという二者択一の政策ではなく、基盤的食料生産のための“集約的畜産”と、草食家畜による多面的機能と国土保全を基盤とした土地活用型の“循環型畜産”の両方の政策をうまく融合させる必要であるということである。今回ご協力頂いた「地備栄倶楽部」の皆さんの、肩から力の抜けた取り組みを少しずつ広げていくことで、日本の休耕地だけでなく、牛を使い、楽しく山地や森林を活用することができるのかもしれない。スウェーデンのように“パス・ファインダー”として、これまでの集約的な畜産システムとは異なるしくみを日本でも創造していく必要がある。地備栄牛の放牧管理は軽作業であり、高齢者でも趣味的に行うことができる。経営的にも近い将来、自立した経営ができるようになるだろう、とのことだった。このような山地や休耕地を活用した放牧の取り組みが、今後静かに、しかし着実に広がることを期待したい。
謝辞
本報告における耕作放棄地放牧の調査に当たっては、地備栄倶楽部事務局の徳田匡彦氏の御協力を得て行った。ここに感謝の意を表します。
参考文献
[1]中洞 正・雨田章子 (2013)中洞式山地酪農. 畜産の研究 67(1):117-126.
[2]アニタ・リンネル、「環境教育の「場と物語」 スウェーデン2021年物語」、BIO-City
(古田尚也構成・訳)、118、 pp. 2-19 (2000)