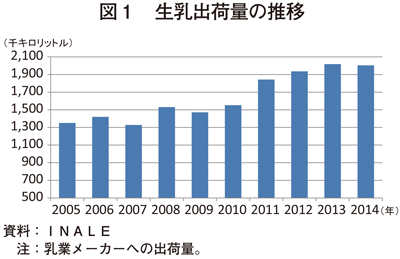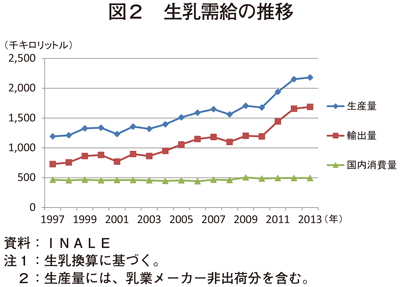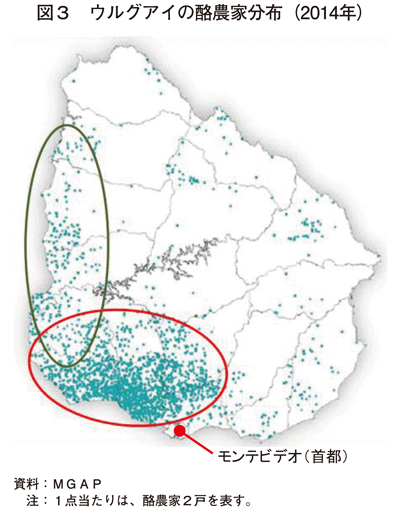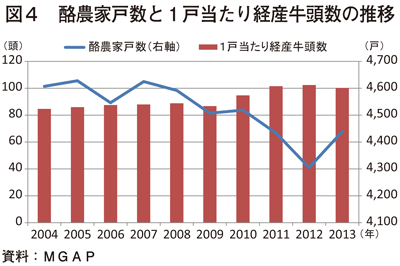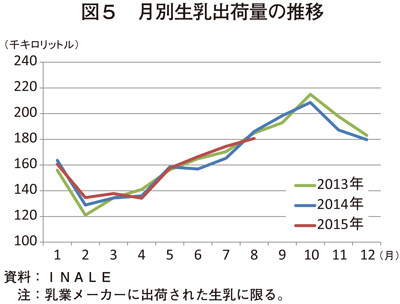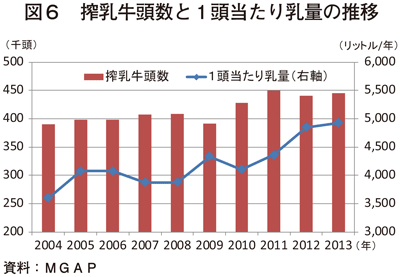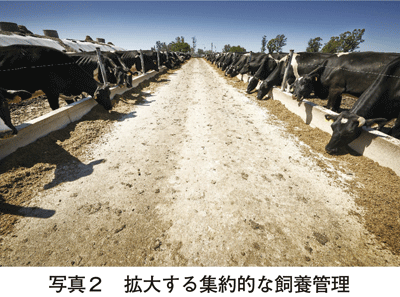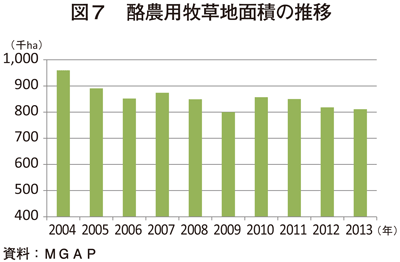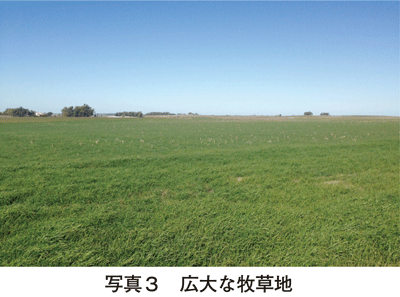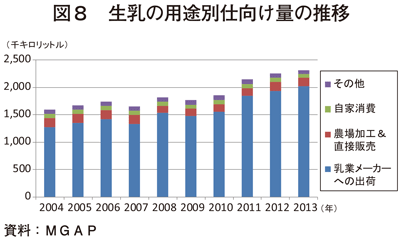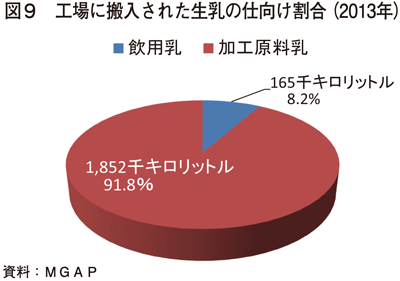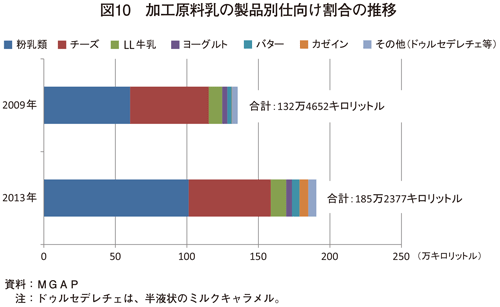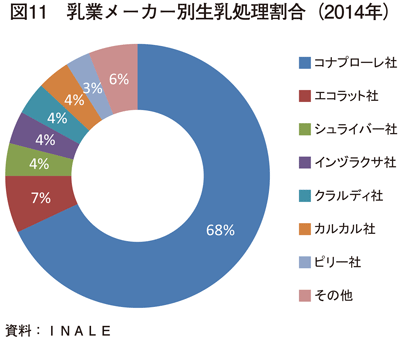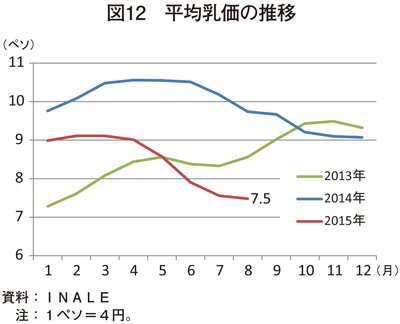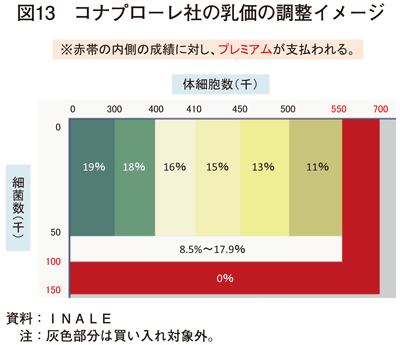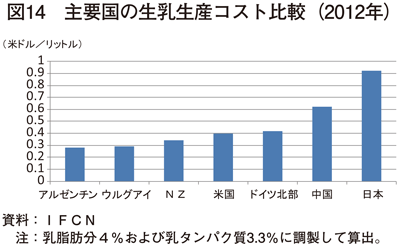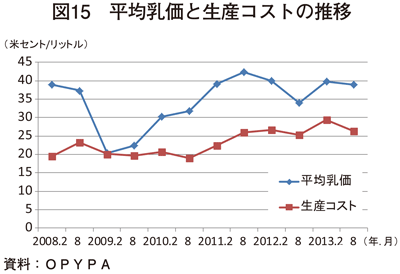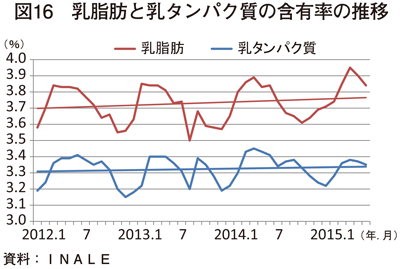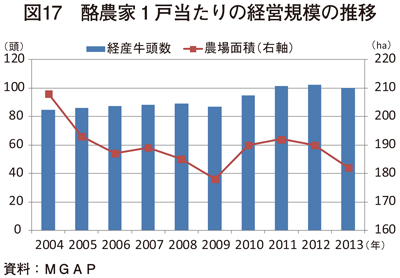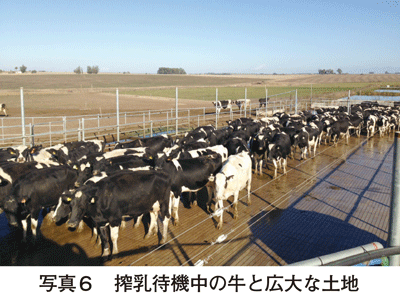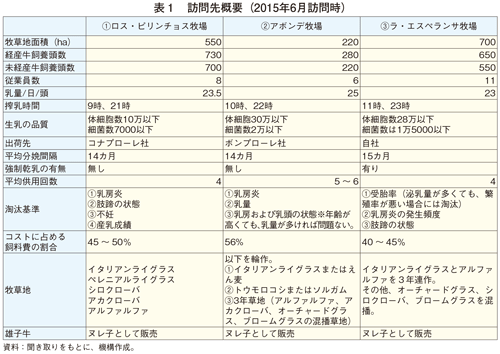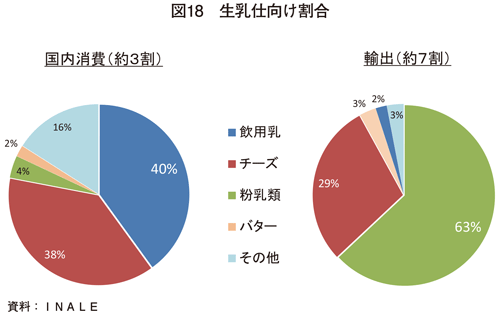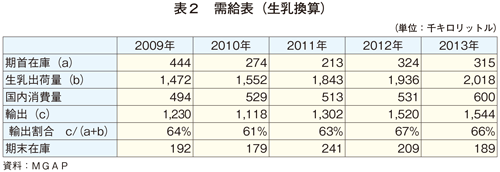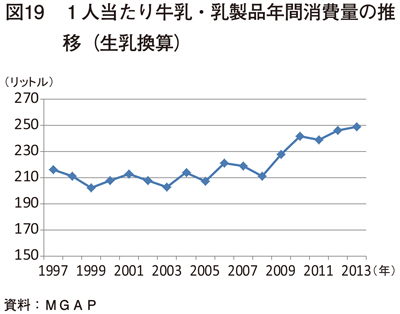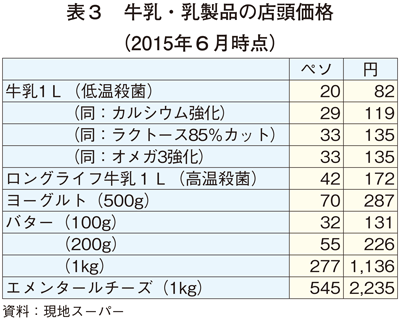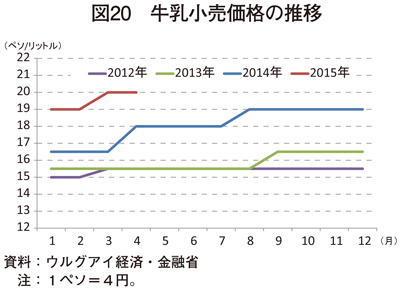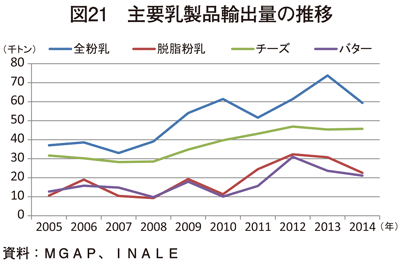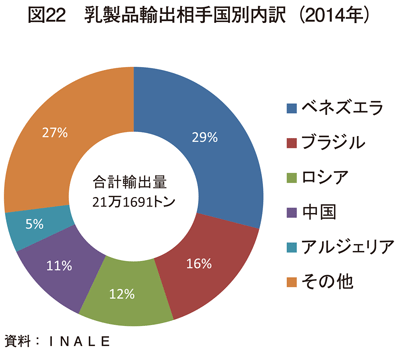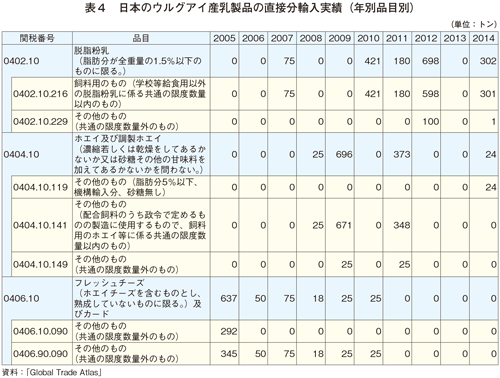【要約】伝統的に乳製品の輸出余力は、ごく一部の国・地域(EU、米国、オセアニア)に限られており、これらの国・地域の気候変動や政策を含めた生産環境の変動により、乳製品の国際需給は大きな影響を受けることとなっている。このような状況の下、南米のウルグアイは、草地主体の低コストでの生乳生産を行える国として注目されており、乳製品輸出国の一角に加わっている。ウルグアイの酪農は、近年、従来の粗放的な形態から、濃厚飼料を補助しながら高泌乳量を実現する経営に転換しつつあり、輸出余力が大きいことから、今後、国際市場への供給潜在力が高まるものとみられる。 1 はじめに ~ウルグアイとは~ウルグアイ東方共和国(以下「ウルグアイ」という)は、日本の半分程度の国土面積(17万6000平方キロメートル)を有しているが、人口は約350万人と日本の30分の1程度である。アルゼンチンとの国境を流れるラプラタ川に沿ったひよくな平原(パンパ)とブラジル南部の台地に挟まれ、最も標高の高い場所でも海抜513メートルと国土全体がなだらかな丘陵地帯であり、農牧畜に適した土地が国土の8割程度を占めている。 年間平均気温は16℃程度、冬期の6月~9月でも平均気温が10℃を下回ることは少なく、夏期の12月~3月でも平均23℃程度と、1年を通じて比較的しのぎ易い。また、降水量は、首都モンテビデオで年間平均1000ミリ程度であり、雨季は6月~10月、乾季は12月~2月となっている。 国際通貨基金(IMF)によると、同国の国内総生産(GDP)の伸び率は、直近10年間(2005年~2014年)で年率12.2%と経済成長を続けている。1人当たりGDPは、2014年に1万6642米ドル(203万円、同年の日本の一人当たりGDPは3万6332ドル)とアルゼンチンやチリを上回り、南米で最も高い水準となっている。 こうした成長を支えているのが、基幹産業である農畜産業であり、中でも、牧畜業の重要性が高い。2000年以降、世界的な食料需要の高まりを受け、牛肉をはじめさまざまな食料分野で同国の存在感や注目度が高まっている(※同国の農林水産品の中で最大の輸出品目は牛肉であり、以下、大豆、パルプ、乳製品と続いている)。 また、南米の中では、最も民主化度が高く、政治の清潔度も高いとされており、南米の優等生と評されるチリと同様に経済の安定度が高い。 こうしたことから、現バスケス政権の下では、ブラジルとアルゼンチンに挟まれた地理的条件を活用した、シンガポールのような「南米物流のハブ」としての位置づけを目指し、フリーポートやフリーエアポート(注1)の整備のほか、外国資本による投資の自由化を進めている。 (注1)フリーポート、フリーエアポートとは、一般に、中継貿易や加工貿易の発達を促すため、外国貨物に関税を賦課せず自由に出入りさせることを認めた港と空港を指す(ブリタニカ国際大百科事典より)。なお、ウルグアイにはフリーポートが3カ所、フリーエアポートが1カ所存在する。 本稿では、直近10年間で主要乳製品輸出量を倍増させるなど、世界の乳製品市場で徐々に存在感を増しつつあるウルグアイの酪農情勢について、2015年6月の現地調査に基づき報告する。 なお、本稿中の為替レートは、1ウルグアイペソ=4円(9月末日TTS相場:4.1円)、1米ドル=121円(同:121.0円)を使用した。 2 生乳生産の動向(1)生乳生産体系 ウルグアイ国立乳業機構(INALE)によると、2014年の生乳出荷量は200万4000キロリットル(前年比0.7%減)であり、過去最高となった前年よりわずかに減少した(図1)。生乳生産量は、2009年の干ばつにより一時的に落ち込んだが、その後は、輸出主導で順調に増加してきた(図2)。 ウルグアイ農牧水産省(MGAP)によると、同国の酪農は、大消費地に近い南西部を中心に行われている(図3)。また、国内の全ての牛について、MGAPが所管するトレーサビリティー制度が整備され、これによる管理がなされている。
2013年現在の酪農家戸数は4439戸と、近年、減少傾向で推移しているが、1戸当たりの経産牛飼養頭数は、増加基調で推移しており、大規模化が徐々に進展している(図4)。なお、日本と同様、乳業メーカーが直接生乳生産を行うことはほとんどない。 乳牛の品種は、ホルスタイン種が主体であり、ジャージー種やブラウンスイス種などはごく少数とされている。これは、乳量を増やした方が、農家の手取りが増えるためである。 生乳生産の季節変動は、牧草の生育サイクルや、分娩計画(※秋から春にかけて分娩が行われるように種付けを行う)により、春(10月)が最も多く、最も生産が落ち込む夏(2月)との間には2倍近い開きがある(図5)。
こうした中、増産体制に向け、乳牛の飼養管理に変化が生じてきている。従来は、長年、ひよくな土壌を生かしつつ、乳牛や草地の改良を通じて生産性を高める粗放的な放牧(改良依存型)による飼養が中心であった(写真1)。しかし、近年の国際的な乳製品需要の高まりを受け、トウモロコシやソルガムのサイレージに加え、トウモロコシや大豆かすなどの濃厚飼料を補助的に給与することで1頭当たり乳量を高める集約的な生産方式が徐々に拡大している(図6、写真2)。このような変化は、隣国のアルゼンチンでも起こっている。
また、ウルグアイは、乳牛の生体輸出も多いため、これも1頭当たり乳量増加に力点が移る要因となっている。 こうした集約的な飼養管理が拡大する背景には、大豆など収益性に勝る作物を生産する農地の拡大も挙げられる。これにより、相対的に酪農用牧草地面積は減少傾向にあり、2013年の酪農用牧草地面積は、81万1000ヘクタールで国土面積の4.6%であった(図7)。こうしたことから、同国乳業最大手コナプローレ社(CONAPROLE)の抽出調査によると、経産牛の放牧強度は、2002年の1ヘクタール当たり0.84頭から徐々に増加しており、2014年は同1.08頭となっている。具体的な飼養管理については、「3 酪農家の事例」(P.93~)を参照されたい。
(2)生乳仕向け 生乳生産量の約9割が乳業メーカーに出荷され、残りの1割程度が生産者による農場加工用や自家消費用などとされている(図8)。 乳業メーカーに出荷された生乳のうち、飲用に仕向けられる割合は1割弱で、大半は加工原料向けとなる(図9)。
加工原料乳の製品別仕向け割合(生乳換算)を見ると、2013年は粉乳国際価格の高まりを受け、粉乳向けの仕向け割合が過去最高となった(図10)。これを2009年と比較すると、加工原料乳量は約4割増加しており、このうち粉乳類向けが特に著しく増加する中で、チーズ向けは微増にとどまっている。この背景には、輸出仕向け割合が高い粉乳は、ベネズエラや中国の需要の高まりを受けて生産が拡大している一方、国内向けが中心のチーズは、国内市場が成熟していることからさほど伸びていないことがわかる。
(3)乳業メーカー 国内に約40社が存在するが、最大手で酪農協同組合系のコナプローレ社が約7割と圧倒的な生乳処理シェアを有している(図11)。企業形態別に見ると、酪農協系はコナプローレ社と同6位のカルカル社の2社で、残りは商系となっている。なお、各社とも乳業工場の処理能力には余力を有していることから、メーカー間の生乳の受け入れ量の調整は行っていない。
ウルグアイは、農畜産業分野への外資参入規制はなく、国内資本と同等に扱われることから、乳業セクターへも投資が盛んに行われている。乳業メーカーのうち、業界第3位のシュライバー社は米国資本(2015年に撤退を発表)、同4位のインヅラクサ社はフランスのラクタリス社が出資しており、また同9位のボンプローレ社もフランス系資本となっている。政府の開放政策に加え、民間格付会社から同国の経済が持続可能な統治により健全な経済状況と評されていることが海外からの直接投資を呼び込んでいる。 (4)生乳生産者価格(乳価) 乳価は、毎月、乳業メーカー主導で決定されており、各社が参考にするのが業界第1位のコナプローレ社の乳価である。なお、用途別乳価は存在しておらず、成分乳価で統一されている。 酪農家の手取り乳価は、各メーカーの基本乳価に、(1)体細胞数(2)細菌数(3)乳タンパク質含有率(4)乳脂率によって調整(減額・加算)が行われる。平均乳価の推移は、以下の通りであり、2014年下半期以降、国際的な乳製品価格の下落に連動するかたちで、下げ基調が続いている(図12)。
乳価の調整について、コナプローレ社の例を見ると、体細胞数が55万未満ではプレミアムが支払われ、70万以上は買い入れ対象外とされている(図13)。細菌数については、10万未満にはプレミアムが支払われ、15万以上は買い入れ対象外とされている。プレミアム割合は、体細胞数が30万以下かつ細菌数が5万以下の場合に最大の19%が加算される。 なお、抗生物質が残留した生乳が生乳ローリーに混入した場合、当該酪農家は同一生乳ローリー内の全ての生乳を補償する義務が生じる。
(5)生乳生産コスト 国際農場比較ネットワーク(IFCN)によると、ウルグアイの生乳生産コストは、アルゼンチンと並び最も低い水準にある(図14)。
ウルグアイ農牧水産省農牧計画政策局(OPYPA)によると、生乳1キログラム当たりの生産コストは、人件費の上昇や飼料穀物の給与増により、徐々に増えている(図15)。しかし、放牧の割合が高く、地代も割安であることから、他の主要乳製品輸出国と比べ、依然としてコスト面での優位性を有している。
(6)生乳成分 INALEによると、生乳成分のうち、乳脂肪および乳タンパク質の含有率は以下の通りである(図16)。濃厚飼料の給与割合が高まっていることなどから、乳固形分は近年漸増している。
3 酪農家の事例MGAPによると、2013年の酪農家の平均的な経営規模は、1戸当たりの農場面積が182ヘクタールで経産牛頭数が100.2頭となっている(図17)。
(1)ロス・ピリンチョス牧場 同牧場は酪農を始めてから50年間、コナプローレ社に生乳を出荷している。 雌子牛は、生後すぐに母牛から離し、初乳(3日間)、人工乳、代用乳で60日間飼育した後、タンパク質含有率18%の濃厚飼料で120日間飼育する。7カ月齢から放牧+補助飼料を給与して14~15カ月齢(体重300キログラム程度)まで育成し、人工授精による初回種付けを行っている。強制乾乳は行っていない。 発情の管理は、ヒート・マウント・ディテクター(発情期になると他の牛の乗駕を受け入れるようになる特徴を利用したシール)を装着し、観察している。分娩間近になると、24時間管理できる牧区に移され、目が行き届く体制が整えられる。なお、分娩が2月~5月になるよう、季節繁殖を行っている。 搾乳は、1日2回(9時、21時)行っており、730頭の搾乳に要する時間は3.5~4時間である。搾乳の前には、牛の導入路に相当するパドック内で濃厚飼料を給与している。1頭当たり乳量には季節性があり、1月~2月(夏季)が最も少なく(17~18リットル/日)、9月~10月(春季)が最も多い(25~26リットル/日)。 基本的な飼料給与割合は、放牧:サイレージ:濃厚飼料=2:1:1だが、調査時(2015年6月)のような干ばつの際には、1:2:2と濃厚飼料の割合を高めている。生産コストに占める飼料費の割合は、通常45~50%であるが、干ばつで濃厚飼料を多給する場合には、この割合が増加し、収益性が悪化することとなる。 サイレージは、自場で生産したソルガムを利用しているが、大豆かすなどの濃厚飼料は外部から購入している。 今後は、現在の経営規模を維持しながら、サイレージや濃厚飼料の給与量を増やして生乳生産量を増やしていきたいとしている。
(2)アボンデ牧場 同牧場は、1972年に現牧場主の父親が、ブドウ栽培から転換したことで始まった。当初の面積は100ヘクタールだったが、現在、220ヘクタールまで規模を拡大している。年間の生乳生産量は230万リットルであり、コナプローレ社より5%程度乳価が高い、ボンプローレ社に全量を出荷している。 3月~5月に40%程度が分娩し、夏季の11月~2月には分娩しないよう、季節繁殖を行っている。発情監視は、ヒート・マウント・ディテクターを用いている。未経産牛は、13~18ヵ月で2回人工授精を行い、これで受胎しない場合には、牧場内で飼養している種雄牛との自然交配を行う。経産牛の場合、初産後100~150日の泌乳量が少ない場合は、未経産牛と同様、自然交配を行うが、この間の泌乳量が多い牛には、人工授精を続ける。 同牧場では、泌乳量ごとにグループ分けして飼養管理を行っており、搾乳前に濃厚飼料を配合した飼料を給与してから搾乳を行っている。主な給与飼料は、トウモロコシサイレージとソルガムサイレージの混合物であり、泌乳量の多いグループ(1頭当たりの泌乳量32リットル/日以上)は、夜間は閉鎖パドックに収容し、日中は放牧を行うというサイクルで管理している(写真8)。
搾乳は、1日2回行っており、年間を通じて搾乳時間は10時と22時としている。2回目の搾乳時間が遅いのは、電気代が高い夕方から夜間にかけての時間帯を避けているためとの説明があった。 雌子牛には、60日までは乳(代用乳を含む)を与え、60日を過ぎるとタンパク質含有量18%の飼料に切り替えてサイレージも給与する。育成期間中は放牧せず、タンパク質含有量が多い飼料を給与している。成牛の飼料は、放牧とサイレージを基本としており、サイレージの割合が40~50%に達する。サイレージは、自場で生産したソルガムとトウモロコシで調製しており、生産は安定している(写真9)。 現在、生産コストに占める飼料費の割合は56%程度だが、干ばつなどの影響による生乳生産量の変動を避けるため、濃厚飼料の給与割合を高めたいとしている。 なお、同牧場の近隣には、他の就業機会も多いことから、賃金が比較的高めに設定されており、これも収益性を圧迫する要因となっている。
(3)ラ・エスペランサ牧場 同牧場は、日本でいう六次産業化モデル(チーズ製造・販売)を展開しているナトゥラリア社の酪農場である。40年前に設立され、当初はコナプローレ社に生乳を出荷していた。共同経営者の発案で20年ほど前より自社でのチーズ生産を開始し、現在は全量を自社プラントで処理・加工をしている。生産しているチーズは、主にエメンタールおよびグリュイエールである(写真10)。一般的なチーズ(チェダー、ゴーダ)も製造可能であるが、大規模メーカーが製造しない、いわゆる手間を要するタイプに注力している。 中でもエメンタールは、製造に技術を要するが、近隣にチーズの専門学校があるため、技術者の確保が比較的容易であり、ウルグアイでも有数の高品質チーズを製造している。
同牧場も他と同様にホルスタイン種が主体だが、乳固形分を増やすため、ジャージー種との交雑種も成雌牛の5~10%程度飼養している。 年間の生乳生産量は、450万リットルであり、チーズ生産量は350トンである。同牧場では、1年1産を目標としているが、初回受精後の発情非回帰率が40%台と低く、複数回の人工授精が必要となることから、目標の達成が困難となっている。人工授精は主に米国産の凍結精液を使用しており、実施率は80%である。泌乳能力の低い牛群(約20%)には自然交配を行っている。発情監視は、ヒート・マウント・ディテクターを使用していたが、3~4ヵ月前に、首に電子タグを装着し、牛の行動の変化を基にコンピュータで管理する方式を導入した。しかし、以前の方法に比べて受胎率が低下しているのが悩みの種となっている。 搾乳時間は、電気代のピーク時間帯や夏季の暑熱対策を考慮して設定している。0時~7時の電気代は、ピーク時間帯(18時~22時)よりも約54%安くなる。 飼料は、基本的には、(1)トウモロコシサイレージと乾草(2)濃厚飼料(3)放牧の組み合わせであり、泌乳能力グループごとに配合を変えている。泌乳量の多い牛群に対しては、タンパク質含有率が高い飼料を、1日1頭当たり乾物重量で22キログラムを与えている(写真11)。
同牧場では、小麦、大麦、トウモロコシおよび大豆を生産しているが、濃厚飼料のうち7割は外部から購入している。なお、自場で生産した大豆は、搾油業者に販売した後、ペレット化した大豆かすを買い戻している。 生産コストに占める飼料費の割合は、給餌作業員の労賃も含めると50%程度だが、これを除けば40~45%程度となる。 今後は、戦略的なパートナーを探し、投資を呼び込みながら、規模を拡大する方針である。 今回調査した3牧場の概要を取りまとめたものを表1に示した。
4 消費および輸出の動向INALEによると、生乳の仕向け割合は、国内:輸出=3:7で、輸出志向型の消費構造となっている(図18)。同国の乳製品については、1960年代までは国内消費に全てが向けられていたが、70年代以降、生乳生産量の増加を受け、過剰分を輸出する構造が確立された。近年、国内需要は増加傾向にはあるものの、輸出が主導する構造となっている(表2)。
(1)国内消費 ウルグアイは、世界でも有数の乳製品消費国である。近年、同国の1人当たり牛乳・乳製品消費量(生乳換算)は、人口が緩やかに増加していることや機能性飲料など製品の多様化が進んでいることから増加傾向で推移しており、2013年現在、249リットルとなっている(図19)。
2008年3月から経済・金融省は、牛乳の小売価格についてコストなどを考慮して決定しており、現在、一般的な牛乳の価格は、1リットル当たり20ペソ(82円)となっている(表3、図20)。政府が牛乳以外に小売価格に関与するのはガソリンのみであり、最も重要な生活必需品として位置づけられるものを、価格変動を最低限にとどめるべく管理している。なお、生産者乳価は、卸売価格の約7割程度とされている。
ウルグアイは、世界的にも1人当たり牛乳・乳製品消費量ではトップクラスを誇る。一般的な牛乳は、商品の大半がビニールパックで売られており、昨今は、健康意識の高まりなどを受けて脂肪分や糖質をカットした機能性牛乳・乳製品の取り扱いも増えてきている。チーズについては、量り売りのスペースも設けられており、多様な種類が取り扱われている(写真13)。 日本ではあまり見られない乳製品として、「ドゥルセデェレチェ」(写真14)という半液状のミルクキャラメルを日常的に多量に消費しており、「マテ茶」と並んでウルグアイ人の食生活に定着している。
(2)輸出 乳製品輸出量は、過去10年、各品目とも増加傾向で推移してきたが、2014年には、チーズを除き、前年からいずれも減少に転じた(図21)。中でも、最大輸出品目である全粉乳は、最大輸出相手国のベネズエラが原油価格の下落で経済が低迷したことに加え、ブラジルの景気減速や中国の粉乳需要が一服したことを受け、前年比19.5%減となった。
現在ウルグアイは、70カ国以上に乳製品の輸出を行っている。輸出量の内訳を見ると、(1)ベネズエラ29%、(2)ブラジル16%、(3)ロシア12%、(4)中国11%、(5)アルジェリア5%となっている(図22)。ベネズエラ、ブラジルの2カ国だけで45%を占めている。なお、ウルグアイはロシアによる農畜産物禁輸措置の対象国ではないため、禁輸措置発動当初はロシア向け輸出を伸ばしたが、その後の原油価格下落に伴うロシア経済の低迷により購買力が低下したことを受け、同国向け輸出はさほど伸びていない。
コラム1 ベネズエラへの食料輸出促進協定
ウルグアイの最大輸出先で、世界有数の産油国であるベネズエラは、2014年下半期以降、国際的な原油価格の下落を受け、経済収支が悪化している。これに加え、同国は、国有化や政府介入で非生産的な経済構造となっており、食料品や日用品の物資不足とインフレが同時進行した結果、深刻な状況に陥っている。 なお、ウルグアイには、酪農・乳業に対する補助金はなく、政府は輸出先の開拓を支援することで間接的に業界を支援する政策が取られている。市場アクセスに関しては、関税同盟であるメルコスール(注2)の加盟国となっており、域内貿易を有利に進めることができる。メルコスール以外の独自の自由貿易協定は、メキシコとの間で締結されているだけであり、各種貿易交渉については、メルコスールの一員として行っている。なお、現在、メルコスールは、EUとの間で自由貿易協定を交渉中だが、進展状況は遅れているとされている。また、数年前、ウルグアイは、単独で米国とのFTA締結を目指したが、他のメルコスール加盟国の反対により頓挫している。 (注2)メルコスール(南米南部共同市場)の正加盟国は、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ボリビアの6カ国。2.9億人程度の人口を抱える市場であり、南米のGDPの76%はメルコスールで占められている。 コラム2 メルコスール、乳製品の関税を引き上げ
メルコスールの最高意思決定機関であるメルコスール協議会(CMC)は7月16日、11品目の乳製品(粉乳類、加糖れん乳、ホエイパウダー類、モッツァレラチーズ、チーズのうち水分含量が46%未満のもの)の域外からの関税率を28%とする暫定措置の適用を2023年12月31日まで延長した。 (3)日本の輸入実績 これまでの日本のウルグアイ産乳製品の輸入実績を見ると、過去に直接輸入した乳製品の大半は飼料用であった(表4)。一方、食用については、主に粉乳類をシンガポールに輸出し、ここで砂糖やフレーバーを加えるなどの簡単な加工を行ってから、日本へ再輸出されてきたとされる。こうした中、今年6月に当機構が行ったホエイおよび調製ホエイの売買同時入札(SBS方式)では、ウルグアイ産200トンが落札されたように、実需者が求める品質規格に見合う製品の製造が可能となってきたことから、今後、同国産の輸入が拡大する可能性がある。
5 ウルグアイ酪農・乳業の優位性と課題これまで見てきたように、ウルグアイの酪農、乳業については、既に国内市場に拡大の余地が小さく拡大のためには新規市場の開拓や既存市場でのアクセス拡大によらざるを得ない状況となっている。そこで、現在の同国の酪農・乳業の優位性と課題について、整理すると以下の通りとなる。 (1)優位性 ア 生乳生産コスト ウルグアイの生乳生産コストは、主要乳製品輸出国の中で最も安い水準にある。同程度とされるアルゼンチンが政策や経済不振を背景に輸出が低迷する中で、ウルグアイが有するポテンシャルに期待して欧米の資本が参入している。これは、同国が、外国企業にビジネスを行い易い環境を整えていることも大きい。一例として、外国企業がウルグアイでの企業活動で上げた利益を国外に移転することに対する規制がないほか、外国企業の資本に対する国内資本比率の規制もない。また、外国企業にも、付加価値税や所得税に対する減免措置もあるなど税体系が一本化されている。 イ 泌乳能力の向上の余地 牧草肥育を軸としながらも、濃厚飼料などを補助的に給与することを通じて、生乳生産は飛躍的に伸びる可能性がある。濃厚飼料の調達については、近隣にブラジルやアルゼンチンなど主要穀物生産国が位置しており、コスト面でのメリットを有している。 また、乳牛の遺伝的能力を高く保つため、カナダ、米国、オランダなどからホルスタインの凍結精液を輸入している。さらに国内でも、種雄牛の後代検定や牛群検定を行っている。 ウ 自然志向 牧草主体の飼養で、ホルモン剤を投与せず、治療目的以外の抗生物質も排除しており、貿易上の障害が起こり難いほか、近年高まっている消費者の安全志向にも応えることができる。 また、輸出乳製品は、粉乳類とチーズ(両製品で乳製品輸出の9割強)であるが、特に粉乳は、生産国による品質上の格差が生じにくいコモディティー商品であるため、生乳生産コストの安さが競争力を生みやすい。 (2)課題 ア 2国間協定の締結などによる輸出市場の拡大 前述の通り、同国では、メルコスール域内における関税優遇措置以外は、特段輸出拡大につながる協定の締結に至っていない。このため、輸出先が限定的で多角化が図れていない現状がある。現地調査では、域外の協定が締結されていないことから、輸出市場の拡大が妨げられているという意見も聞かれたほか、メルコスールとしての交渉は、加盟国間での合意に時間がかかるため機動性に欠けるとの声も聞かれた。 INALEやウルグアイ貿易・投資機構(ウルグアイ21)は、輸出志向型のを進展させてきた同国の酪農・乳業について、近年の国際的乳製品需給情勢を鑑みると、主要輸出国としてその地位を確実なものとする絶好の機会と捉えており、2国間協定の推進など政府の貿易政策のかじ取りの変化が期待されている。 イ 乳業の加工技術の向上 現在の為替相場はペソ安ドル高基調で推移しており、輸出には好条件であるものの、各社製品の生産技術が欧米水準には達していない面があり、製品の輸出価格で見ると優位性が薄まっている。また、製品の規格変更への対応でも遅れている面が観察された。 ウ 安易な投資と撤退の可能性 海外からの直接投資がしやすい半面、撤退もしやすいことで、過去には生乳の余剰問題も発生した。このため、安定的な雇用の創出・生乳生産のためにも、撤退の条件を新設する必要が有るとの声がある。 エ 人材確保 近年、他業種との競合や若者の都市部への流出などにより酪農従事者の確保が難しくなってきており、同国の酪農生産の底上げには、専門的な人材の育成の重要性が増してきている。酪農従事者のうち、家族労働:雇用=6:4とされ、現在は収益性が良好であることから、労働力を何とか確保できているが、今後、問題が深刻化する可能性をはらんでいる。 オ 高い電力コスト ウルグアイでは、水力発電および燃料輸入への依存を軽減するため、風力発電などの再生可能エネルギー開発が推進されているものの、現状は発電コストが高く、電気料金がかなり割高になっている。同国の電気料金は、南米平均の2倍程度で、欧州平均よりも高いとされている。 6 まとめ ~今後の見通し~乳製品の輸出余力を持つ国は、従来から北半球を中心とした少数の国・地域に限定されている。国内市場が小さく輸出にけん引されるという、ウルグアイと同様の生産構造を有するニュージーランド(NZ)の酪農は、昨年半ばからの中国の輸入需要の急落、EUの生乳クォータの廃止による増産の可能性、ロシアの禁輸措置により行き場を失ったEU産乳製品との競争などにより、危機に瀕しているとされている。 一方、ウルグアイについては、メルコスールの域内での優位性を維持したまま、輸出先の拡大にも力を入れ始めている。ただし、同国の酪農は、1頭当たり泌乳量向上を指向するあまり、従来の放牧管理を主体とした低コストで自然志向の酪農から、濃厚飼料を補助的に給与する集約的な飼養管理に移行することで、従来の優位性を失いかねない方向に舵を切っているようにもみえる。 生乳生産コストが低いにもかかわらず、乳製品の価格競争力は、NZなど大規模化が進んでいる国に対して十分とは言いきれず、乳業各社の設備の更新や外国資本の導入を通じた積極的な発展が望まれている。乳業最大手で圧倒的なシェアを有するコナプローレ社は、引き続き業界のけん引役となることには疑いがないが、乳製品の需要者は、多様な規格を求めているのに対し、巨人なるがゆえに小回りが利かない面も見て取れる。 しかしながら、同国は、小国ながら投資環境が良く、対外開放的経済を目指すなど南米では異色の存在である。日本との関係でいえば、本年の日ウルグアイ投資協定署名を契機に、官民が共同して、対日経済関係の拡大・深化を積極的に進めたい方針である。 近々、ウルグアイの大統領が来日するとされているが、このような機会にウルグアイ産乳製品に対する認識が高まれば、調達先国の多角化の一環として同国産乳製品の潜在力は高まることになるだろう。 謝辞 今回、駐日ウルグアイ大使館ブスゥ特命全権大使他館員の皆様、在ウルグアイ日本国大使館田中特命全権大使他館員の皆様、ウルグアイ外務省、投資・輸出促進機構(XXⅠ)、農牧水産省、国立乳業機構(INALE)、農業技術研究開発機構(INIA)、コナプローレ社、ナトゥラリア社、各牧場の皆様をはじめ、多くの方々に快く調査に応じていただき、紙面をお借りして深く感謝の意を表します。 |
元のページに戻る