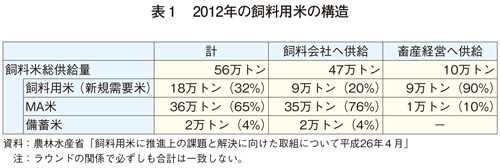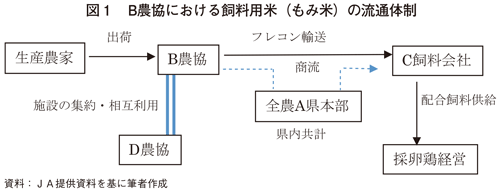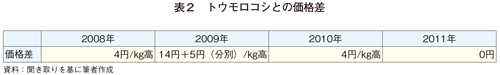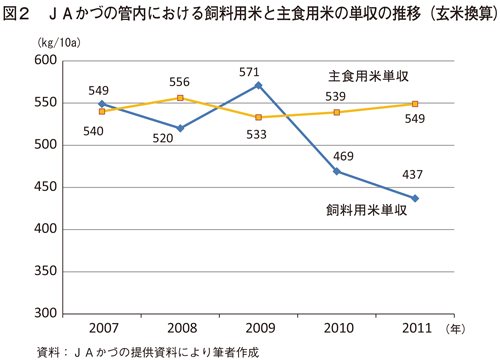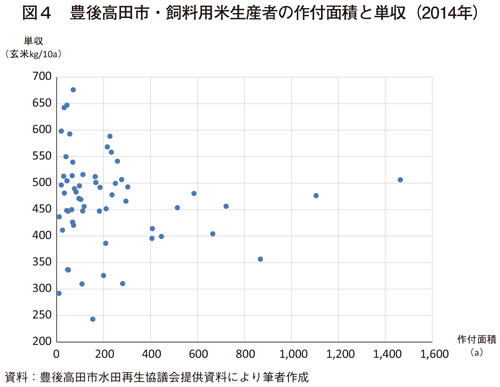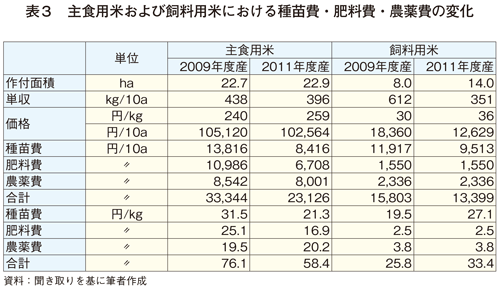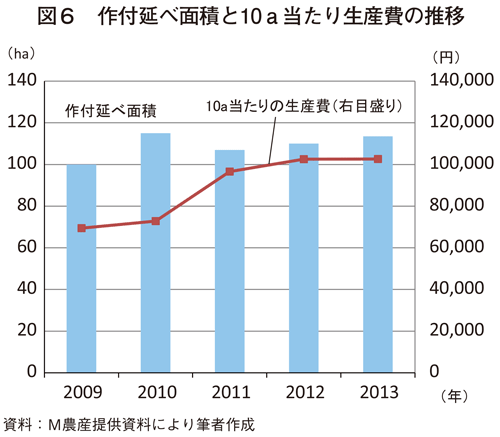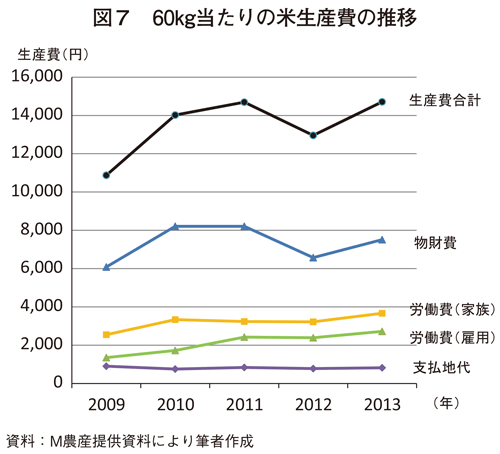【要約】米の生産調整としての飼料用米生産は単収低下を引き起こしていたが、米価の低落と数量支払いの導入によって状況は大きく変化しつつある。飼料用米生産への取り組みは農業生産者の事情によって異なるが、作付面積を積極的に拡大し、単収増加を目指す動きが強まっている。畜産経営の需要も増大傾向にある。安定的な財政支援が続けば今後も順調に拡大していくことが見込まれる。 1 本調査研究の課題現在、飼料用米は2つの面から要請されている重要な政策課題となっている。1つは供給サイドであり、もう1つは需要サイドである。 前者は米の生産調整とリンクした問題領域を形成している。増加する水田の生産調整面積に麦、大豆での転作での対応が限界に達しており、米による「転作」が進められることになった。加工用米、米粉用米、飼料用米がそれに当たる。稲WCS(稲発酵粗飼料)もこれに含めることができる。特に飼料用米は高額の助成金が支払われており、大きな政策変更がない限り、これからの生産調整の鍵を握ることになる。そこからは飼料用米が実際の農業経営にどのようなかたちで定着し、畜産経営への安定的な供給が実現されると考えてよいのかという課題が生じる。また、飼料用米生産を増加させるため収穫高とリンクした助成金の支払いへ移行したことの影響の検討も課題となる。これに応えるためには、飼料用米生産の効率性・経済性向上の可能性の規範的な検討だけでなく、飼料用米生産がそれぞれの農業経営にとってどのように位置づけられているのかを、生産者の視点から分析を行う必要がある。 後者は世界的な飼料価格の高騰によって飼料用米、稲WCSなどの国産飼料への注目が高まっていることが背景にある。具体的には畜産経営の側からみた飼料用米の評価が問題となる。また、飼料価格高騰の下での畜産経営の飼料用米へのシフトは重要な動きであり、その最新の状況をトレースする必要がある。また、飼料用米の供給と需要をつなぐ流通面でも大きな問題が存在しており、両者を合わせたトータルとしての飼料用米を捉えるという視角も重要である。 以上のような問題意識の下、飼料用米生産に取り組んでいる農業生産者の方々、飼料用米へのシフトを図っている畜産経営、関係機関・団体からヒアリング調査を行った。 2 飼料用米の生産振興と流通の課題飼料原料となる米は、新規需要米である飼料用米、輸入米であるミニマムアクセス米(以下「MA米」という)、備蓄米の3種類からなる。これまでMA米や備蓄米が配合飼料の原料として活用されてきたことが飼料用米の市場開拓の礎となり、飼料用米を固定的に使用するユーザー(畜産経営)が全国各地に登場してきたのである。その結果、配合飼料全体における飼料用米の比率はわずかではあるが、配合飼料原料として定着しつつある。2012年の流通量56万トンのうち飼料用米は18万トン(32%)にすぎず、備蓄米は2万トン(4%)、MA米が36万トンと65%を占める。飼料会社への供給に限定すれば、総量47万トンのうちMA米は35万トン(76%)である(表1)。飼料用米は供給先の確定を助成金の要件としており、当初は耕種農家と畜産農家の間での流通が基本であったため、現在も飼料用米18万トンのうち半分の9万トンは、飼料会社を通さない耕種農家と畜産農家の間の直接流通となっている。 西日本のA県B農協は、2008年に約7ヘクタールの主食用品種による飼料用米生産を開始し、2014年には350ヘクタール超にまで面積を拡大している。生産者数も当初の9名から現在は300名を超えている。飼料用米の多くはもみ米のままC飼料会社へ出荷され、C飼料会社で製造された配合飼料はA県内の採卵鶏経営へ供給されている(図1)。それ以外にも、自施設において玄米粉砕加工を行い、県内の畜産経営に自家配合原料として供給している。この飼料用米を使用して生産される畜産物は、ブランド化されて販売されている。
B農協の流通面で注目されるのは次の5点である。 (1) 米出荷によりフレコンバック(注1)での出荷が可能となり、紙袋出荷時に必要な解袋作業の必要がない。 (2) 主食用米による取り組みのため農家レベルでの追加的な費用が発生せず、作付面積の増大につながっている。 (3) 飼料用米を適正に保管するために他の農協と連携して保管施設の利用調整や新設を行っている。 (4) 県内共計(注2)の利用による輸送体制の整備。 (5)県内の需要者を確保しての配合飼料の製造・供給のため集出荷団体、飼料会社、畜産経営の3者間の調整が容易である。 以上は飼料用米供給費用の低減につながっている。 (注1) フレコンバック(フレキシブルコンテナバッグ)とは、穀物や飼料、石灰、土砂などの梱包、輸送、保管に適した袋状の包材のこと。丈夫で柔らかな科学繊維が素材に用いられており、使用しない時には小さく折り畳むことができる。 (注2) 県内共計(共同計算)とは、県内の農業者が生産・出荷した飼料用米の販売に関わる諸費用をプールし、農業者が一律の手取りを得る仕組みである。 3 配合飼料価格の高騰と大規模養豚法人経営の収益性配合飼料価格の高騰は飼料用米への追い風となっている。2006〜2008年度の配合飼料価格の上昇により、2009年度から群馬県のA社では肥育豚の後期2カ月間に飼料用米を10%加えた飼料の給餌を開始した(委託農場であるB農場の全2000頭に給餌)。さらに2013年度からは、C牧場の90%、D牧場の50%の肥育豚の後期2カ月間に飼料用米を10%加えた飼料を給餌している。その結果、A社全体で年間約3万頭の出荷頭数のうち飼料用米を給餌した肥育豚は1万頭を占めるまでに達した。この飼料用米を給餌した肥育豚は全農ミートフーズ株式会社を経て生活協同組合コープネット事業連合を通じて消費者に販売されている。飼料用米を給餌した肥育豚(精肉)は、2009年は20円/キログラム高、2013年は5円/キログラム高となっている。 A社では当初、群馬県産の飼料用米を使用する計画だったが、飼料用米生産より米粉用米生産への取り組みが活発であったため群馬県産の飼料用米の確保は困難で、全農が千葉県、茨城県、栃木県などの近隣4県より飼料用米を購入し、東日本くみあい飼料株式会社で委託配合が行われ、飼料用米を含む配合飼料がA社にて供給されることになった。飼料会社が介在することで広域流通が実現したケースである。注目されるのは飼料用米とトウモロコシとの価格差が縮小してきている点である。トウモロコシの価格と比べて2008年の飼料用米は4円/キログラム高、2009年の飼料用米は14円+5円(分別)/キログラム高(注3)、2010年の飼料用米は4円/キログラム高、2011年には飼料用米とトウモロコシの価格差はなくなっている(表2)。豚肉の差額関税制度が維持され、国内の豚肉価格が安定的に推移すれば、飼料用米を配合した飼料の需要は拡大する可能性はあるということのようだ。 (注3) 「分別」とは、農場と食肉処理場で一般豚と飼料用米を給餌した豚が混在している場合、それを分別管理するのに必要なコストである。
4 秋田県JAかづの管内における飼料用米生産の動向JAかづのは、ポークランドグループ、パルシステムと協力しながら、現在のように政策の重点課題となるはるか以前から飼料用米の生産に積極的に取り組んできた。 2007年から2011年にかけて飼料用米を生産する経営体数、出荷量、作付面積などは順調に増加してきているが、2010年、2011年の単収は469キログラム/10アール、437キログラム/10アールと低迷し、同時期における主食用米の539キログラム/10アール、549キログラム/10アールを大幅に下回る水準となっている(玄米換算、図2)。
この最大の要因は、主食用米と明らかに内容や回数の異なる肥料や農薬の投入であり、主食用米生産と比べた投入水準の低下である。飼料用米に対して数量払いが導入されたのは、このような背景があると考えられる。 ただし、2014年産米価格の低下を受けて飼料用米生産の増加という動きが予想される。そのためJAでは飼料用米専用品種と主食用米品種の作付ほ場を分ける区分管理方式に加えて、主食用米品種での飼料用米出荷を認める一括管理方式を導入 した。 一見すると飼料用米へのシフトが進みそうにみえるが、農家調査結果では必ずしもそうはなっていない。ここでは飼料用米生産に積極的なケースを簡単に紹介する。 定年退職後に規模拡大をしたN氏は主食用米4ヘクタール、飼料用米3.5ヘクタールを栽培する。飼料用米にもJAの基準以上に生産投入を行い、4500円/10アールを投じて5000円/10アールの助成金のリターンという結果となっている。これをN氏の機会費用の低さとみてよいかどうか。 I農園は43ヘクタールの水稲単作の大規模経営である。ここは米価の下落を受けて主食米を30ヘクタールから23ヘクタールに減らす一方、飼料用米を12ヘクタールから20ヘクタールに大きく増やし、10万5000円/10アールの助成金の獲得を目指している。JAへの販売が9割を占める文字通りの米生産経営ゆえの判断だろうか。 5 大分県北部振興局管内における飼料用米生産の動向大分県の飼料用米作付面積は735ヘクタールだが、このうち494ヘクタールが北部振興局管内にあり、飼料用米の主力産地である(2013年実績)。管内の豊後高田市では2014年の数量払いの導入によって地域全体の単収は2013年の485キログラム/10アール(もみ米)、玄米換算すると380キログラム台/10アールから2014年の454キログラム/10アール(玄米)へと増加している(図3)。
そこで2013年と2014年の両年とも飼料用米を生産している59名の単収を比較すると、59名中40名は収量が上昇しているが、19名は低下している。これは割合にすると3分の1となり、決して無視できる水準ではない。 2014年産について作付面積と飼料用米の単収との関係をみると、作付面積が小さい生産者は単収のばらつきが大きいのに対し、作付面積が大きい生産者の単収はおおむね400キログラム台に収まっている(図4)。今後の飼料用米生産者としてどのような経営規模を想定するのか、また、大規模経営への農地集積の進展の度合いによって、期待される単収水準に違いが生じ、飼料用米生産の全体量に影響が出てくるかもしれない。
飼料用米生産に影響を与えているのは米価の動向である。管内で建設業から農業に参入した作付面積が60ヘクタールを超える大規模水田経営A法人は2015年に飼料用米生産へのシフトを決定した。2014年の主食用米は9000円/60キログラムとなり、450キログラムの収穫があったとしても6万7000円/10アールの売り上げにしかならず、飼料用米のそれを下回ってしまった(図5)。A法人ではこれまでとは反対に、条件の良いほ場に飼料用米を作付ける計画である(主食用米22ヘクタールに対して飼料用米は8ヘクタール)。ただし、A法人は酒米生産(3ヘクタール)も重視しており、米価の低落が主食用米から飼料用米への転換を単純にもたらしているわけではない。この点はJAかづのの生産者と異なる。
6 大規模法人経営における主食用米と飼料用米の収益性に関する分析最近までA法人の飼料用米の単収は低下していた。これはJAかづのの調査でも明らかなように生産投入の減少によるものである。それを種苗費、肥料費、農薬費などに着目して検討しておこう。検討するのは2009年と2011年のデータである(表3)。
元肥に関しては、主食用米が60キログラム/10アール、飼料用米が10〜20キログラム/10アールと大きな差があり、夏の追肥も主食用米では2回行われているが、飼料用米では全く行われていないという違いがある。農薬に関しても同様で、育苗における苗箱の消毒も主食用米が2種類の薬剤が用いられるのに対し、飼料用米は1種類だけである。夏の防除作業も主食用米は2回行われているが、飼料用米では全く行われていないという状況であった。それが飼料用米の単収の低下をもたらすことになったのである。 ただし、米価の低落を受けて、2015年からは飼料用米に力を入れるような経営計画が立てられている。 7 大規模農業経営のコスト削減・阻害要因三重県の大規模水田経営M農産(水稲45ヘクタール、小麦25ヘクタール、大豆15ヘクタール、飼料稲21ヘクタールと飼料用米・飼料麦)の規模拡大過程におけるコスト削減の実態と削減の阻害要因を検討した結果、飼料用米生産を含む稲作のコストダウンのための課題は雇用労働力の生産性をいかにして引き上げるかにあることが判明した。 図6は、2009年から2013年における全部門(水稲、小麦、大豆など)の作付延べ面積と10アール当たり生産費の推移を示したものである。作付面積が拡大するにしたがい生産費は増加傾向にある。内訳は示していないが、光熱動力費、農機具費、生産管理費、家族労働費、雇用労働費では増加率が高いという特徴がある。生産や経営の複雑化・高度化により、生産費の低減は実際にはみられないのである。
次にM農産の水稲部門における60キログラム当たり生産費を期ごとに比較し、規模拡大過程における米生産費の推移を検討した(図7)。
水稲作付面積が2011年の40ヘクタールから2012年の45ヘクタールに拡大した際に生産費が低減しているが、それ以降、コストは下がっていないのが実情である。また、単位当たり雇用労働費が急激に増加しており、単位当たり物財費が変動するなかで、わずかではあるが建物費や農機具費の減価償却費が増加傾向にある点を指摘することができる。 結局、規模拡大過程において雇用労働費が増加し、それが米生産費の削減を阻害しているのである。この隘路は人材育成の難しさにある。M農産では雇用労働者の出入りが激しく、人材育成も含め雇用にかかる費用が大きい割に雇用労働力が有効に活かされていない。こうした問題は雇用を導入した大規模水田経営に共通する課題とすることができる。 8 おわりに最後に課題を4点示すことにしたい。 第1に、飼料用米の振興は、水田農業の維持問題に加えて、畜産業の経営安定化問題も視野に入れた取り組みである。しかし、現在の生産量は配合飼料の1%に満たず大きな経営安定効果は期待できない。しかし、この点は今後の飼料用米の潜在的な需要の大きさを意味している。 実際、輸入飼料の高騰によって飼料用米にシフトする動きを現地実態調査でも確認している。価格変動リスクにさらされるよりも、少々割高でも質・量ともに安定的な飼料調達ルートとしての地位を飼料用米は獲得できる可能性がある。 第2に、現在の飼料用米の流通体制は少量流通を前提としたものであり、今後の流通量の増加への対応を図る必要がある。例えば、集出荷側では主食用米を使用した場合の紙袋出荷のフレコン出荷あるいはバラ出荷への転換が課題となる。また、供給先である飼料会社側では受け入れ日量のボトルネックの解消が課題となる。これらの課題は、現在の流通量において大きな問題とはなっていないが、今後の生産増加の進展に遅れることなく、対応策を講じる必要がある。 これは広域流通体制の構築にとっての課題である。 一方、専用品種を使用して飼料用米の生産に取り組む上で、コンタミ問題(注4)への対応を徹底することが必須であり、個々の生産者および集出荷団体の両段階での取り組みが必要となる。また、生産増加が産地の拡散を伴うことから、輸送先となる飼料工場の立地に偏りがあることと、輸送コストと飼料用米の価格水準が経済輸送範囲を狭めていることから、供給地と需要者のマッチングが重要となる。そのため、より効率的な流通を維持すためには、供給者(集出荷団体)と需要者(飼料会社)間で、出荷日量と受け入れ日量のすり合わせなどの取り組みが望まれる。 第3に、現実には飼料用米に取り組む産地においてはさまざまな工夫において流通の効率化が図られている。ただし、現在の流通量に対して有効な流通体制であり、今後の生産増加に対してその効率性は担保されていない。この点で、関係機関間の協力関係の形成と連携した活動が重要となる。同時に、このことが意味するのは、全国共計への参加が一種の逆選択となり、割高な流通体制となりえることである。この点での対応は都道府県単位での取り組みでは困難であり、より広域での調整・対応を必要とする。 第4に、生産者が安定的に飼料用米生産を行うための経営環境を整備する必要がある。主食用米価格の値下がりを受けて、非良食味米地帯では飼料用米生産に本格的に乗り出す動きがみられるのに対し、良食味米地帯では調査時点ではまだ専用品種での栽培にまで踏み切るまでには至っておらず、地域によって大きな差がみられた。また、経営規模によっても飼料用米生産に対する対応に違いがみられた。こうした地域差、経営規模による差を視野に入れた助成金の仕組みが求められるところである。 (注4) コンタミとは、飼料用米が主食用米に混入すること。 |
元のページに戻る