1.はじめに
食の安全・安心に対する消費者の関心の高まりや、食料自給率の向上を加速させようとする国の諸施策の充実、さらには昨年の飼料価格の高騰にみられるような世界穀物市場の不安定性などを背景に、近年のわが国畜産においては飼料自給率の向上が喫緊の課題となっている。一方、米価をはじめとする農産物価格の下落や農業従事者の高齢化、後継者不足などを背景に全国各地で耕作放棄地が急増しており、耕種部門においても水田フル活用などと称されるように、その解消を目標の一つに掲げながら自給飼料生産の振興に積極的に取り組む地域が増えている。
本稿では、このような追い風の吹く自給飼料生産が、単なる一過性の取り組みに終わることなく、わが国農業全体の中にきちんと普及・定着し、今後さらなる拡大を図っていくための条件を検討する。考察の対象は、後述するように、ここ数年の間に稲発酵粗飼料(ホールクロップサイレージ:子実と葉茎部分を一緒にサイレージにしたもの。以下、「稲WCS」と略称)の生産を急増させている宮城県農業公社(以下、「公社」という)の取り組みである。
WCS用稲は、飼料作物全体の作付面積から見るとわずか7%(注1)足らずとマイナーな作物であるが、コメ需給が今後も緩和基調のまま推移していくと想定されるならば、各種助成金の継続的支援を前提に、主要水田地帯の平坦部において急速な拡大が見込まれる作物でもある。また、稲WCSの生産に取り組む優良事例については、本誌においてもこれまで、コンタラクター機能を発揮する農事組合法人の「仲介・調整機能」の重要性を指摘した福田[1]や、耕種農家と畜産農家の「信頼」に基づく連携の重要性を指摘した甲斐[2]などの蓄積がある。しかし、都道府県農業公社がコントラクターとして稲WCS生産に取り組む場合には、後述するように、「仲介・調整機能」や耕種農家と畜産農家からの「信頼」とは別の優位性も併せ持っている。これらが、公社による稲WCSの取り組みを対象とした理由である。
(注1)平成19年度の飼料作物作付面積は、全国計で897.2千ヘクタール、
うち牧草773.3千ヘクタール、とうもろこし86.1千ヘクタール、稲WCS6.3千ヘクタール、
その他31.5千ヘクタール(農林水産省生産局調べ)である。
参考文献
[1] 福田晋「コントラクターが担う稲発酵粗飼料生産システムと今後の課題
−千葉県干潟町農事組合法人「八万石」−」
『畜産の情報』2003年10月号6〜12頁 〔http://lin.alic.go.jp/alic/month/dome/2003/oct/senmon.htm〕
[2] 甲斐諭「耕畜連携による国土に根差した地域資源循環型畜産経営の確立
−宮崎県国富町の飼料イネとたい肥の需給システムを事例として−」
『畜産の情報』2006年11月号4〜15頁 〔http://lin.alic.go.jp/alic/month/dome/2006/nov/senmon1.htm〕
2. 宮城県におけるWCS用稲生産の推移
周知のように、わが国におけるWCS用稲の作付け面積は平成7年度にわずか23ヘクタールに過ぎなかったが、平成12年度からは水田農業経営確立対策などの実施により502ヘクタールへと拡大し、その後国による飼料増産行動計画に基づく取り組み強化などにより、平成19年度には6,339ヘクタールにまで達している。表1は、東北におけるWCS用稲生産の推移を示したものである。はじめに、平成15年度以降、東北地域では全国の作付け面積の約2割前後を担っているのが見て取れよう。次に、県別の動向に着目すると、生産調整との絡みから当然のことではあるが、WCS用稲は稲作依存度の高い秋田県、宮城県での作付けが多い(図1)。しかし、平成18年度から19年度にかけて、宮城県では前年比100%近い作付け増を記録し、東北におけるWCS用稲生産の首座を獲得した。
|
表1 東北地域のWCS用稲作付け面積の推移
|
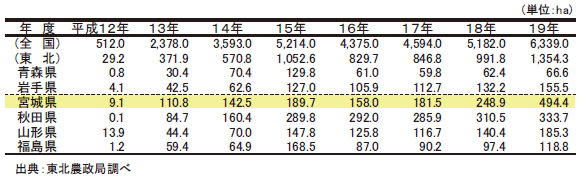 |
|
図1 東北地域におけるWCS用稲作付状況(H19)
|
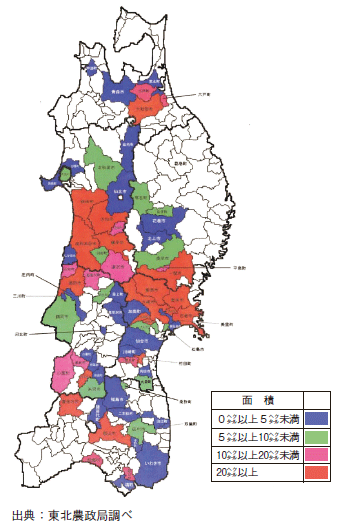 |
その急増の主因が稲作の生産調整の強化にあり、転作作物の中でも湿害に苦しむ麦作との代替が進んだことは言うまでもない。ただし、それと同時に、平成19年度と20年度に公社の作業受委託面積が急増し、公社の取り組みが宮城県の稲WCS生産全体の底上げ機能を担っている点に注目する必要がある(図2参照)。
次節以降では、なぜ公社の作業受委託面積が急速に増大しているのか、その要因について考察していくことにする。
|
図2 宮城県のWCS用稲栽培面積と農業公社作業受託面積の推移
|
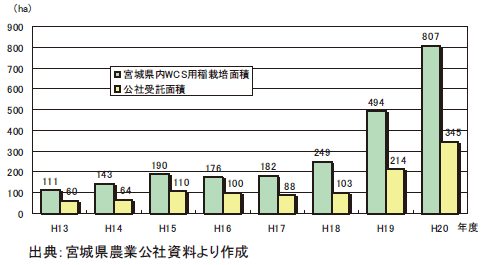 |
3.公社の稲WCS生産・斡旋システムの概要
公社は、農業経営の拡大と安定を図り、宮城県農業の健全な発展に寄与していくことを目的として、昭和55年5月に旧宮城県農地管理公社を宮城県農業公社と改称し、旧宮城県畜産開発公社の業務を包含する形で設立された公益法人である。平成20年6月時点で農地総務部と事業推進部の二部体制で構成され、役職員74名(常勤役員など3名、正職員46名、有期契約職員12名、再任用職員5名、臨時職員8名)で、以下の5つの事業などを行っている。
なお、公社は現在、各種事業収入の減少や農地保有合理化事業における長期保有地問題、未収金など多くの課題を抱えているが、これまで蓄積してきた専門知識やノウハウ、機械力、機動力を発揮し、次のような畜産振興施策に関する事業や受託事業に重点を置いた中期経営改善計画に取り組んでいる。
1)農地保有の合理化
・ 農地保有合理化事業
・農業構造改善に資する事業
2)畜産経営基盤・環境の整備
・ 資源リサイクル畜産環境整備事業
・畜産基盤再編総合整備事業
・ 畜産施設設計監理等業務(一級建築士事務所)
3)農業基盤の整備
・ 草地造成整備、圃場整備(区画整理、暗渠排水、客土など)
・農用地開発、土地改良総合整備事業等
・ 各種調査、測量、設計資料作成、施工管理等業務
|
図3 事業実施推進体制
|
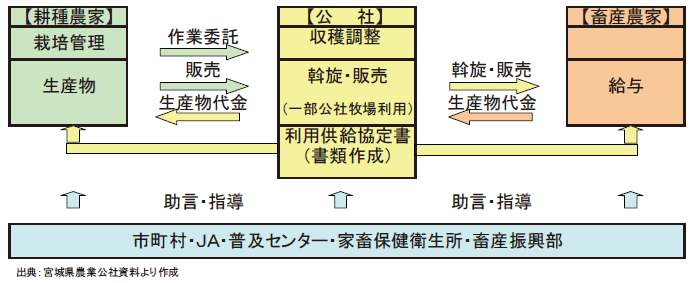 |
4)牧場の管理・運営
・ 白石牧場の運営(優良肉用子牛の生産、育成、配布)
・ 県営岩出山牧場の管理(預託育成、和牛産肉能力検定)
・ 牡鹿牧場の運営(粗飼料多給型低コスト肥育実証)
5)その他
・営農支援業務(WCS用稲収穫作業など)
・公共施設管理等業務
・特定鉱害復旧事業
さて、公社による稲WCS生産・斡旋事業の実施体制を簡潔にまとめたのが図3である。関係機関および関係団体の助言や指導を仰ぎながら、耕種農家の栽培した稲の収穫調整作業を受託するとともに耕種農家から収穫物を全量買い上げ、その一部を自社牧場で利用するものの、基本的に生産された稲WCSを需要に合せて県内外の畜産農家に斡旋・販売する仕組みである。
図4は、同事業の生産・斡旋システムを、畜産農家にほ場渡しする場合と畜産農家の庭先渡しする場合に区分し、各作業行程で発生する費用や取引価格などを整理したものである。それによると、稲を栽培・管理する耕種農家には、10アール当たり50〜63千円の助成金(産地づくり交付金+耕畜連携水田活用対策)が支給されるほか、公社から収穫されたWCS用稲の代金(1ロール≒320キログラム、3千円)が支払われる。県平均で10アール当たり8ロール弱の稲WCSが生産されることから、耕種農家の収入は10アール当たり75〜85千円程度となり、収穫前までに掛かった稲栽培・管理経費と公社に支払う収穫調整の作業料金を差し引いても、相応の収益が確保できそうである。畜産農家にとっても、稲WCS給与確立助成金として10アール当たり10千円(定額)が支給されるので、1ロール3〜4.5千円の売渡価格は充分に採算の合う水準と思われる。
|
図4 公社による稲発酵粗飼料生産・斡旋システムの概要
|
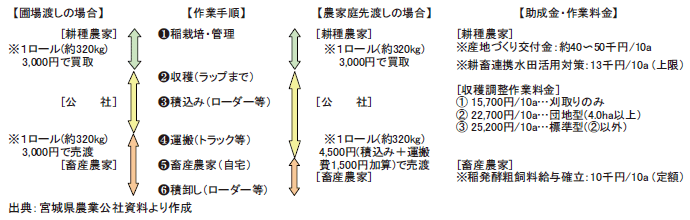 |
一方、肝心の収穫調整作業の料金は、「刈取りのみ」の場合と4ヘクタール以上まとまったほ場の「団地型」、それ以外の「標準型」の3タイプに別れており、基本となる標準型の作業料金の内訳は表2に示すとおりである。
|
表2 収穫調整作業料金の内
|
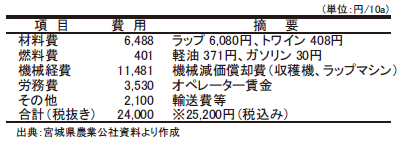 |
そして、このような公社による稲WCS生産・斡旋システムの利用実績と利用割合の推移を整理したのが表3である。利用実績としての受委託面積は、先に述べたとおり、平成18年度まで増減を繰り返しながら100ヘクタール前後で推移してきたが、平成19年度に飛躍的に急増し、その傾向は平成20年度においても継続中である。これに対して、作業委託農家割合と稲WCS販売先割合の推移には大きな変化が見られる。具体的には、かつて畜産農家が主体であった作業委託先農家は今日では耕種農家が過半を占めるようになり、また稲WCSの販売先もかつて半数を占めていた乳用牛向けから今日ではその大半が肉用牛向けに様変わりしている(注2)。これは、一つには昭和一桁世代のリタイア急増にみられるように、「信頼」できる委託先として公社を利用する高齢の稲作農家が増えているためである。いま一つは、酪農経営が年々規模拡大を図り、粗飼料生産にも自ら積極的に取り組んでいるのに対して、肉用牛経営、特に繁殖経営の大半が依然として小規模層にとどまり、効率的な粗飼料生産を実現できないでいるためである。
|
表3 作業委託先および稲WCS販売先の推移
|
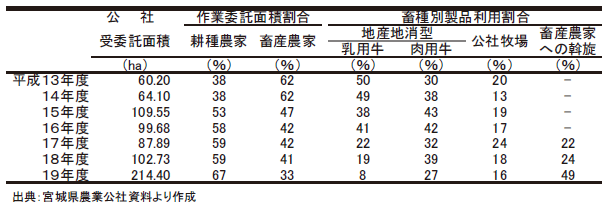 |
以上、公社の稲WCS生産・斡旋システムの概要を簡単に見てきたが、同システムを利用する耕種農家と畜産農家、および作業実施主体の公社のそれぞれに経済性が担保されていなければ、作業受委託面積の増大が実現しないことは言うまでもあるまい。その意味で、現行の補助体系の下で稲WCS普及の経済的条件は満たされていると考えられよう。次節では、同システムの成果が飛躍的に拡大している背景を考察する。
(注2)公社牧場および斡旋先畜産農家の大口需要先は肉用牛が主体の牧場である。
4.稲WCSの普及・拡大要因と公社事業の特徴
公社による稲WCS生産・斡旋事業が飛躍的な拡大を実現できた条件として、以下の5点を指摘できよう。(1)公社による利便性の高いサービスの提供
甲斐[2]が指摘するように、耕種農家と畜産農家の連携による稲WCSの利用拡大には、何にもましてお互いの「信頼」関係の構築がもっとも大切である。特に、個別農家間や生産組織などによる取り組みの初期段階において、供給側の耕種農家と需要側の畜産農家との間で製品の品質格差に対する認識の相違が表面化して係争が発生し、取引が継続されないことはよく耳にすることである。この点に関して公社の取り組みは、図3にみられるように、耕種農家と畜産農家が互いに直接顔を合わせる必要はなく、それぞれが地元の関係機関や関係団体の助言指導に従って、実績ある公益法人としての公社と契約を結べばよい仕組みとなっている。これは特に高齢の耕種農家にとっては魅力的と思われる。何故ならば、彼らにとっては収穫直前まで従前どおりに稲の栽培管理をきちんと行ってさえいればよく、稲WCSの出来不出来とは無関係に期待する生産物代金を手にすることが出来るからである。また、契約に必要な書類をすべて公社が作成してくれるというサービスも、耕種農家と畜産農家の双方にとって、極めて魅力的な誘因として作用しているように思われる。事務手続きなどにかかる煩わしさや心理的負担からの解放は、想像以上に事業への参加ハードルを引き下げてくれるからである。
(2)公社保有の専用機と機動力の優位
とは言え、公益法人への「信頼性」と契約上の利便性だけでは稲WCSの生産・斡旋事業は普及も拡大もするまい。やはりそこで第一義的に大切なことは、品質の高い稲WCSの安定供給である。そのためには作業適期と言われる出穂後30日前後の黄熟期(水分約65%)における収穫調整が肝要となる。そして、そのためには適期作業を可能とする一定数の専用機の保有と機動力の確保が不可欠である。この点においても公社の優位性は揺るぎない。表4は公社保有の専用機一覧であるが、1台約1,000万円弱の収穫機を8台と1台約250万円の自走式ラップマシンを10台も抱え、大型トレーラーを駆使して県内各地を縦横無尽に走り廻ることのできるコントラクターは公社をおいて他にない。 |
 |
|
専用機による収穫作業
|
ロールを拾い込みラッピング
|
|
4 公社の専用機保有状況
|
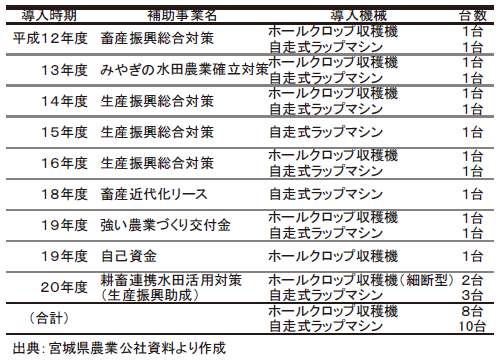 |
 |
|
開封したばかりの稲WCS。子実が完熟する前に茎葉同時に収穫しサイレージ化する。
|
(3) 効率的かつ広域的需給調整が可能とする 同一組織内部でのマッチング
このように県内全域を事業エリアとする広域性は、その一方で稲WCSの効率的かつ広域的需給調整を可能とする。表5は、平成19年度の公社の生産・斡旋状況を地域別に整理したものである。表中の地産地消とは作業受託をした地域での畜産農家への販売を意味するが、畜産農家の偏在によりバランスの取れた地産地消を実現している地域は見当たらない。それどころかコメどころ宮城県では、稲WCSは供給過剰となり易いため、どうしても県外への斡旋・販売が不可欠とならざるを得ない。このような構造的問題を抱えながら、県内外での地域間需給調整を可能としているのが、公社による自社牧場への引取であり、県外大口需要者への販路の開拓である。仲介・斡旋に取り組む生産組織やコントラクターは全国各地に少なくないが、自社牧場を抱え需給調整機能を発揮できる組織はほとんど見られない。|
表5 公社の稲発酵粗飼料生産・斡旋状況(平成19年度)
|
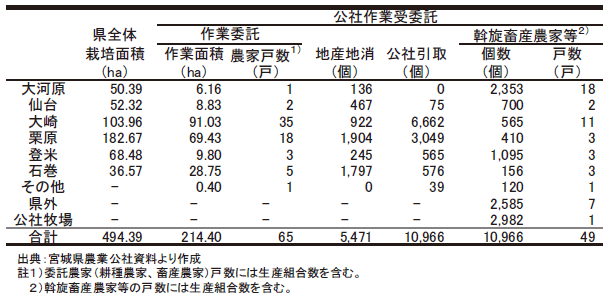 |
(4) 迅速なクレーム対応と品質リスクを内部化する自社牧場の存在
自社牧場の存在は、数量的な需給調整の『場』というだけではなく、品質面で需要者のニーズに合わなかった製品を交換する需給調整の『場』としても重要である。特に顧客からのクレームに迅速に対処し得る点は、関係性マーケティングの観点から見ても取引の継続を促す大切な要因である。このような品質重視の姿勢は、最近導入し始めたトレーサビリティー(下図参照)にも表れている。
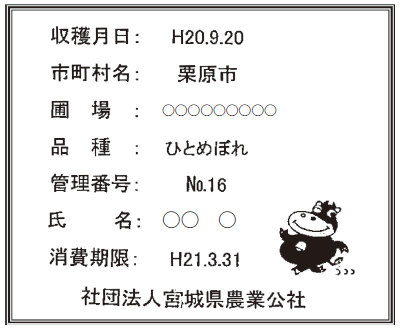 |
|
生産履歴をロールに添付し製品管理を実施
|
(5) 自社牧場での給与実証試験など研究開発機能の存在
さらに、公社の白石牧場と牡鹿牧場は、肉用牛に対する稲WCSの給与実証試験の『場』としても重要な役割を果たしている。稲WCSは未だ給与技術が確立されていないと同時に、現在もなお高収量を実現する専用品種の開発が行われており、このため絶えず生産現場での新品種の栽培実証試験や製品の給与実証試験が必要である。しかし、そのような応用研究は、個別の耕種農家や畜産農家にとってはリスクが大きく、また基礎研究を担う公設試験研究機関でも充分対処できないのが実際である。その意味で公社の実証試験は、これからの稲WCSの普及を促進していく上で、公共性を有した極めて貴重な取り組みと評価できよう。 |
|
稲WCSを肉用牛に給与、おいしそうに食べている
(白石牧場) |
5. おわりに
全国各地で行われている稲WCS生産の主体をみると、耕種農家や畜産農家の個別相対的取り組みや任意組織やコンタラクターなどによる組織的取り組みもあり多様であるが、生産(供給)側と利用(需要)側のマッチングや価格設定、クレーム処理などにかかる取引費用が高く、それらが生産拡大を阻害しているとの調査・研究報告も多い。本稿で取り上げた公社による稲WCS生産・斡旋システムは、都道府県農業公社としての組織的性格をフルに活用して、それらの諸課題を解消する仕組みであった。また、専用新品種の栽培試験や給与実証試験といった普及技術の確立に向けた応用研究への取り組みも、都道府県農業公社ならではの事業と言えよう。換言するならば、これらは稲WCSの普及・拡大に向けた様々なリスクを公社が内部化し、耕種農家と畜産農家が抱えるリスクを軽減する取り組みである。
なお、本稿では平坦部水田地帯での取り組みを考察したが、公社の保有する専用機の性能や機動力を併せ考えるならば、区画の整理されていない小規模な水田を多く抱える山間地でも稲WCSの生産は可能である。ただし、山間地での取り組みは効率性が低くなることから普及・拡大は限定的と考えられよう。むしろ山間地では水田放牧などに取り組み、粗飼料自給率を向上させる展開が適切ではないかと思われる。
最後に、地方公共団体は現在、財政難を理由に都道府県ならびに市町村農業公社の再編を検討しているが、このような公共性の高い事業活動が地域資源の維持管理には不可欠で、それが飼料自給率の向上、ひいては食料自給率の向上に貢献していることを忘れてはならない。
 |
|
筆者と公社職員(白石牧場)
|